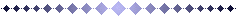ノートスの奇跡
第1章 アルマ
ジャイアントビーのカミソリのような爪がウォンの脇腹をえぐった。
「おごっ!」
ウォンの口から言葉にならない叫びが漏れる。
《しまった! 針ばかりに気を取られて……》
こいつの毒針だけは食うわけにはいかないが、だからといって爪ならば良いというわけでもない。
ウォンの動きが鈍くなったことに気づいたのだろう。ジャイアントビーは腹を丸めると子供の腕ほどもある毒針でウォンを狙い澄ました。これはかなりまずい状況だ。
ビーが襲いかかってきた瞬間、ウォンは手にした剣を横に払った。それはビーの体には当たったが、硬い甲にはかすり傷しか付かない。いや彼の剣だからこそかすり傷がついたのだ。普通の剣ではそれこそ全く刃が立たない。だがそれでもともかくビーの狙いを逸らすだけの効果はあった。
「この野郎!」
ウォンはそう吠えながら再びビーに剣を振り下ろす。だがビーはそれを軽々と躱すと、再び上空へと逃げてしまった。
「逃げるな! ゴルァ!」
そう叫んではみたものの、今の攻撃を凌げたのはかなりの幸運だった。こんなことがあと何度も続くわけがない。こいつらは固くて剣が効きにくい上すばしっこくて、ともかく始末が悪いのだ。
《やべえ! このままじゃジリ貧だぜ》
脇腹からは豪快に血が噴き出している。このままでは何分もしないうちに行動不能になってしまうだろう。
そういうウォンの都合とはお構いなしに、ジャイアントビーは最後のとどめとばかりに襲いかかってきた。その時だ。
「イオ! ウォンを!」
かん高い叫び声と共にずどんという音がして、ビーが弾け飛んだ。
「スー! お前何を……」
一瞬ウォンは目を疑った。今攻撃したのは確かにスーチだ。彼女は僧侶なのだからそんなことをするはずがない。だがウォンが彼女の方を見ると、彼女は手を前にかざした状態で放心している。
「何考えてるんだよ! 俺を直せよ!」
僧侶であっても気弾のような攻撃魔法は使える。だが実際のところその程度の魔法ではこの外骨格生物には何のダメージも与えられない。ジャイアントビーは一瞬とまどったような様子を見せたが、すぐまた立ち直った。
《ほら見ろ!》
ただその一発は結構痛かったようで、ビーは向きを変えると凄まじい羽音を立てながら彼女に向かって飛んでいった。
「きゃあああ!」
スーチが慌てて逃げ出す。確かにこれでウォンは危機を脱することができた。だが今度は彼女が危ない! しかもここで僧侶がやられてしまったら全体的には更に悪い状況になる。
「バカ! 当たり前だろ」
ウォンは最後の力を振り絞ってジャイアントビーを追った。彼女だけは救っておかなければ……その時背後から別な声がした。
「ウォン! これ使え!」
その声は魔法使いのイオだ。ウォンが振り返ると同時にイオはポーションの瓶を放り投げてきた。ウォンはそれを慌てて受け取りながら、スーチがあんなことをした理由を理解した。
スーチはイオがフェアリーダストのポーションを持っていたことをちゃんと覚えていたのだ。これなら即効性がある。
ウォンは走りながらポーションの蓋を開けると傷口に振りかける。ほとんど瞬時に血は止まり、傷口が塞がっていく。同時に体に力が舞い戻ってくるのが分かる。
「いやあああん!」
前方ではスーチがジャイアントビーに追いつめられて、その毒針を何とか払いのけたところだ。だがはっきり言って彼女の接近戦は誉められたものでない。今のもメイスを振り回したらたまたま当たっただけだ。この次は確実に串刺しにされてしまうだろう。
だがその時にはウォンが十分間に合っていた。
「馬鹿野郎! 俺様はこっちだぜぇ!」
ウォンはジャイアントビーの急所である羽の付け根に愛用の魔剣を叩き込んだ。ぱっと黄色の毛が散って、透明の羽が一枚舞い上がる。それと同時にジャイアントビーはバランスを崩して地面に落ちた。
「こうなりゃこっちのもんだぜ!」
「ウォン! 油断しないで」
「わかってら!」
飛べなくなったからといってこいつが即無力になるわけではない。ジャイアントビーの体は大変に固く、体節の間を正確に狙って攻撃しないと刃が立たない。だが地面を這いずっていてくれるのであれば、着実にポイントを稼ぐことは可能だ。
数分後ビーの体液でぐしょぐしょになりながらも、ウォンはとどめをさしていた。
「ふう、ひでえ……」
「大丈夫だった?」
スーチが心配そうに声をかける。
「大丈夫って、お前、無茶するんじゃねえよ! 自分が囮になるなんてよ!」
「だって、あの場合呪文じゃ間に合わないでしょ?」
「まあ、そうだけどな」
確かに彼女の言う通りだった。あの時僧侶としての彼女には二つの選択肢があった。
普通ならば僧侶の専門である治療行為をするのが当然だ。だが先ほどの場合は治癒する速度よりダメージを受ける速度の方が確実に速そうだった。あそこでウォンが倒されてしまったら後はもうどうしようもなくってしまう。
そのためスーチはジャイアントビーを攻撃して自分の方に引きつけ、その間にイオが持っていたポーションで治療できるようにしたのだ。
その時後ろからがさがさ音がして黒いローブを着た男が現れた。
「スーちゃん。ナイス!」
「イオ君! ありがと」
「どういたしまして。でも危ない賭だったな。こいつが間に合わなかったらゲームオーバーって感じだったぜ」
「大丈夫。間に合うって思ってたから」
「運がよかっただけだって。こんな奴あてにしてたら命のストックがいくつあったって……」
それを聞いてウォンが突っかかった。
「イオ! てめえこそ、今まで何してやがったんだ?」
「何って、休息」
「人がボロボロになって戦ってる間にか?」
「ああ? だってそれがお前の役目だろ? ひ弱な俺に殴り合いをやらせる気か?」
「せめて支援ぐらいできなかったのかよ?」
「最初ので精神力切れちゃってね。回復させとかないとな」
そういいながらイオはビーの体液にまみれたウォンを眺めた。
「それにしてもお前、汚ねえなあ」
「誰のせいだと思ってんだよ! お前が全部固めておけば良かったんだろうが! なのに何だ? 中から全部出てくる前にぶっ放しやがって!」
そう言ってウォンはイオを睨んだ。確かにこの作戦では奴らを巣からみんなおびき出してイオのブリザードの魔法で凍らせるはずだったのだ。ジャイアントビーは先ほどの戦いでも証明されたように物理的な攻撃にはやたら強いのだが、低温系の魔法には驚くほど弱いのだ。
「だってなあ。びっくりするだろ。あんだけ出てこられたら」
「だからって、もう少し待てなかったか? 素人か? お前は!」
「ああ? 蜂の爪ごときで刻まれてる奴がなんだって? 俺が薬をやらなかったらどうなってたよ?」
二人はにらみ合った。それを見てスーチが仲裁に入る。
「ねえ、二人とも、うまく行ったんだからもういいじゃない。それに元はといえばあたしが急かしたのが悪いんだし……」
それを聞いてイオが答える。
「まあ確かに夜まで待ってればこんな作戦にしなくても済んだんだろうけど……いったい何急いでたんだ?」
するとスーチは言った。
「何って夕方にほら……ああ! こんな時間。あたしもう出るわね。毛を乾かさなきゃいけないし……」
そう言うとスーチは口の中で何かぶつぶつつぶやくと、すっと消え去った。
二人は一瞬ぽかんとして彼女の消え去った後の空間を眺めていた。それからウォンが言う。
「スーは何急いでるんだ?」
「さあ。ギィと約束があるんじゃないか?」
「ふうん」
二人はしばらく黙り込んだ。それからイオが言う。
「それにしても、今回はマジやばいかと思ったけど、スーはうまくやったな」
「ああ? 俺から見ればまだまだだね」
ウォンが答えるとイオがからかうような口調で言った。
「ほう? 俺としちゃ命預けるんならもうお前よりスーの方がいいけどなあ」
それを聞いてウォンはイオをにらみつけた。
「そりゃスーちゃんはもこもこしてて抱き心地良さそうだしねえ。命だけでなく体預けるのにも丁度いいんじゃねえの? 人としてどうかとは思うけどな」
今度むっとしたのはイオの方だ。
「お前いい加減しつこいんだよ! 大体それとスーとは関係ないだろ!」
「そして目覚めると心が寒い丘にいたってか?」
その途端にウォンの足下から炎の柱が立った。
「だぁ! 危ねえ!」
「あのなあ、同じセリフをしつこく何度も何度も何度も何度も……最近気づいたんだけどさ、お前もしかして頭悪いんじゃないか? 治療してやろうか?」
「上等じゃねえか! この野郎! 俺だってなあ、てめえのそのすました喋り方が嫌いなんだよ。二度と口きけなくしてやるぜ!」
二人は弾かれたように立ち上がると、ぱっと互いに飛び下がった。
ここはまばら林の中だ。所々に灌木の茂みがあるが、木々の間はおおむね広く、下草もほとんどない。もう陽は完全に落ちているが、代わりに梢の間から明るい月が地面を照らしている。明るさも十分だ。
ウォンは愛用の魔剣を鞘から抜くとイオに向かって構えた。いつものようにその柄はぴたりと吸い付くようにウォンの掌に収まっている。
ウォンはじりじりとイオに迫った。もちろん魔導師のイオは逆に間合いを取ろうとして回り込んでいく。しばらくはそういった動きが続いた。
だがついにイオの行く手に灌木の茂みが現れた。これ以上は回り込めない。
《今だ!》
ウォンは一気にイオとの間を詰めようとした。だが彼はそのとき背後でがさがさっという音がしたのを聞き逃さなかった。
「へん! バカ野郎!」
そう叫ぶとウォンは弾かれたように横っ飛びした。それと同時に背後から真っ赤な光球が飛んできて、ウォンの今いた場所で炸裂した。
《後ろに転移しやがったか? いつも通りにせこい野郎だ!》
ウォンは反転すると、剣を構えてすさまじい速度でイオに迫った。だがそれも十分に予期していたようで、イオは持っていた杖をさっと振り下ろすとまたあの光球がウォンに襲いかかる。
「ちっ!」
ウォンがそれを避けている間に、イオは別な茂みの中に姿を消した。
《追うか? それとも先回りするか?》
ウォンは一瞬躊躇したがすぐに両方の考えを捨てた。イオ相手に単純に迫ったのではどんな罠が用意されているか分かったものではない。
その代わりにウォンはイオが姿を隠した茂みにまっすぐ突入した。
「うあららあああ!」
ウォンは手にした魔剣で茂みを両断する。茂みの上半分が一挙に吹き飛び、ついでに茂みの横の木までが両断されて大きな音を立てて倒れていく。
「うあっ!」
確かに向こうにイオがいる。ウォンは跳躍すると反転しながら一気に茂みを飛び越した。
「なに?」
「くたばりやがれ!」
叫びと共にウォンは魔剣をイオめがけて振り下ろす。剣は見事にイオを捉え、両断した……かに見えた。だが何の手応えもない。
《しまった!》
ウォンの全神経が危険を告げる。彼は何も考えずに全力で飛び下がる。
それとイオの幻が爆発するのはほぼ同時だった。ウォンは爆風でもんどり打って飛ばされてかなりのダメージを受けた。だが生きている。もう一瞬回避が遅れていたら粉々になっていたに違いない。
だがそんなことを喜んでいる暇はなかった。彼が生き残ったと見るや、イオは再び光球を連打してきたのだ。
「汚ねえぞ! この野郎!」
「いいからさっさと死ね!」
「ほざけ!」
ウォンはイオの言葉に焦りを聞き取っていた。今イオが使ったイリュージョンやエクスプロードの魔法はかなり精神力を消耗する物だ。イオは先のジャイアントビー戦で精神力を使い果たしている。あれからさっきまでの回復分ではこれが精一杯のはずだ。イオは今の一撃に賭けていたに違いない。
《だったらこっちも行くまでだぜ!》
ウォンは光球を無視してイオの本体に突進した。そんなものが当たったからといってまだ即死するわけではない。この戦いは最後に立っていた者が勝ちなのだ。
「うっ!」
ウォンの意図を察してイオの腰が引ける。こうなると魔導師には分が悪い。接近してしまえば魔導師は剣士の敵ではないのだ。
「うおらああああ!」
避けられないと見たイオは持っていた杖でウォンの剣を払いのけた。だが魔導師の杖はそういう使い方には向いていない。イオは剣の直撃は避けることができたが、杖は瞬時にまっぷたつになってしまった。
「おのれ!」
「ふははは! これでもう小細工はできまい?」
ウォンはイオの鼻先に剣を突きつけた。だがイオの表情には恐怖の代わりに驚きの色が見えた。
「お、おい! ちょっと、後ろ!」
イオはそう言いながらウォンの後ろを指さす。
「バーカ! そんな手にかかるか! 死ねや!」
確かにこれはイオが今まで何度かやってくれた小細工だったのだが、この日に限ってはそうではなかった。
ウォンが剣を振りかぶったまさにその時、まばゆい閃光と共にウォンの剣に雷が落ちて、剣を粉々に打ち砕いてしまったのだ。同時にウォンはすさまじい力で地面に叩きつけられた。イオもあおりを食って吹っ飛んだ。
「な、なんだよ?」
ウォンの問いに答えたのは冷たい女の声だった。
「何だとは何よ?」
ウォンは驚いて振り返る。そこにあったのは宙に浮かぶ半裸の女性の姿だった。肌の上には様々な色形の奇妙な文様がうごめいている。普通の者であればまずそのことに驚いてしまうだろうが、ウォンの驚きは別なところにあった。
「ああ! ラーンさん? いったい何で?」
だがラーンと呼ばれた女性はウォンと後ろでぼけっとしているイオをにらみつけた。
「ウォン! イオ! あんた達、一体何してるのよ! こんな所で?」
「え? だって、今日はもう終わりだし……」
「終わり? 朝言わなかったっけ? 新人が来るって」
「だって新人が来るのは明日じゃ……」
「だから朝に、明日から来る新人を夕方に紹介するから残っとけって言ったでしょ?」
「へ?」
ウォンは混乱してイオの顔を見た。
「そうだったっけ?」
「そ、そういえばそんな気が……」
二人の背筋に冷たい物が流れた。
「思いだした? あたしは確かに言ったわよね?」
ラーンの声はますます冷たくなっていく。
その頃にはウォンの記憶にもラーンが朝言っていたことが蘇ってきた。だからスーチはあんなに急いでいたのだ……
「で聞くけど、何してるわけ? そんなところで?」
ウォンとイオは顔を見合わせた。それから同時に答える。
「ええ? このふざけた男に天誅を……」
「まあ、このとぼけた男の脳の治療を……」
二人はにらみ合うとまた同時に叫んだ。
「あんだと?」
「まだ言うか?」
それを聞いてラーンがついに爆発した。
「いい加減にしろっての! 何度決闘してたら気が済むのよ! さっさと出ておいで! 10分以内に来ないとひどいよ!」
「ちょっと待って下さいよ、そんな早く後始末が……」
そういうイオの願いをラーンはにべもなく却下した。
「がたがたうるさいわね! 死にゃしないわよ! それとももう一発雷が欲しい?」
これ以上逆らっても無駄のようだった。だがウォンは一つ気がかりなことがあった。
「あの、一つだけ質問。いいですか?」
「何よ」
「僕の剣、砕けちゃったんですが……」
ウォンは柄だけになってしまった剣を見せた。
「そうみたいね」
「これ手に入れるの大変だったんですが……」
「知ってるわ。で?」
ラーンの声はもう氷点下273度というところだ。
「……やっぱりいいです」
「そう。じゃあミーティングルームで。あと……9分35秒」
そういうとラーンの姿は消え去った。
二人はしばし呆気にとられたようにラーンが消えた後の空間を見つめていた。それからはっと我に返ると、ぶつぶつと呪文を唱え始める。ウォンの場合はこんな具合だった。
『我が名はウォン・リンドゥーなり。ここに真の名を以て異界の扉を開かん!』
それと同時にウォンの頭の中に声が響く。無性的で機械のような声だ。
『我は汝の望みをかなえよう。汝の望みとは?』
『退出』
『了解した!』
それと共にウォンの目の前が急に真っ暗になった。同時に体がふっと浮くような感じがして、次いであらゆる感覚が消え失せる。
もちろんいつものことなのでウォンは全く慌てない。その無感覚の状態はほんのしばらく続いただけで、すぐにまた体の感覚が戻ってくる。だが今度彼がいたのは林の中ではなく、小さな個室の中の細長いケースの中だった。彼はそこに裸で寝ていたのだ。
ウォンは体を起こすと、首の後ろをまさぐった。首筋から背中にかけて白いシールが張り付けられ、そこから伸びた導線がケース本体とつながっている。
ウォンはそれに手をかけるとシールをべりべりとはがした。
「痛てて、こういうことするなっていつもはうるさいくせに。俺達はどうなってもいいのかよ」
ウォンはケースから出るとのびをした。本体の方は数時間ほどぴくりとも動いていないはずだ。筋肉をゆっくりとほぐしていかないと、急につってしまったりすることもある。また汗もかいていてシャワーも浴びたい。だが今回そんな暇はない。
彼は個室の隅にあったロッカーを開くと、服を着直して、すぐさま個室を飛び出した。
イオもほぼ同時に出てきていた。ウォンはイオに言った。
「時間はあと何分だ?」
「さあ、ともかく走った方がいいな」
二人が息を切らしながらミーティングルームに駆け込むと、そこにはNSEゲームセンター“異界の門”のスタッフが勢揃いしていた。
部屋の真ん中には迷彩服を着てサングラスをかけた男が腕組みして座っている。彼が支配人のミースだ。その横にさっき出てきたラーンがいる。彼女の格好はさっきの幻影で見たままだが、ここではもう普通の光景なので誰も気にしない。
その反対側には20歳前後に見える若い娘と白衣を着た初老の男が並んでいた。彼らは親子ではなく夫婦で、ゼナとエイドリアンという。この4名が異界の門の創業四人衆と呼ばれている。
といってもここは零細企業なので上司と言うよりは兄貴分といった間柄に近い。だからそこまで畏まる必要はないのだが、それだけに怒らせたらさっきのウォンのように別な意味でひどい目に合わされるので気が抜けない。
蛇足ながら彼らは一番若いゼナでも50歳を越えている。とにかく見かけで判断してはいけない連中なのだ。
その反対側には何人かの他の従業員と共に、スーチとギメルが並んで座っている。ウォン達には見慣れた光景だがそうでなければこれもまた驚きの種だろう。
スーチはゲーム中で見た姿とは全く異なっていて、真っ白なふわふわした髪の毛をしており、同じような毛でできたショールとスカートを身につけているように見える。だがそれは服なのではなく百パーセント自前の毛なのだ。
気配を感じてスーチが振り返った。その顔だちを見れば彼女がどう見てもヒト族ではないことは明らかだ。だが彼女の吸い込まれるような美しい瞳は種族の垣根を越えて見た者に深い印象を与えずにはおかないだろう。
そしてその横には青みがかった肌色をした、小山のように大きな男が座っている。彼も同時に振り向いた。彼もその怪物じみた顔を見るまでもなくヒト族でないことは明白だ。
ウォンとイオは息を切らせながらその横に滑り込んだ。
「一応時間通りに来たわね」
息が上がってぜいぜい言っている二人を見てラーンが言った。
「じゃあ紹介するわ。彼女が明日からアシスタントをしてもらうアルマ・マートル」
それと同時にラーンの後ろから赤毛の娘が出てきて黙って礼をした。彼女は正真正銘のヒト族のようだ。
それを見た途端ウォンの胸がきゅっといった。
《しまった! 結構好みじゃん!》
最初の印象というのは出会いにとっては非常に重要だ。だがちょっと今の登場はよろしくないのではなかろうか?
だがまだ終わったわけではない。ウォンは彼女に何かサインを送れそうな機会を探した。しかし彼女はスーチとギメルの方が気になるようで横目でそちらばかり見ている。どうやらラーンはいつもの調子でおいしい所は後回しにしているのだろう。
ラーンはウォンとイオを紹介しそうな素振りを見せてから急に尋ねた。
「あら? 彼女たちの方が気になる?」
ラーンにいきなりそう言われてアルマはちょっと飛び上がった。
「え? あ?」
《うへ! かわいい声出すじゃん!》
ウォンはそのとまどった声を聞いてまた心躍らせていた。
「そうね。あんなのより気になるわよね。じゃあ先にしましょう。彼女がスーチ・アイン。アシスタントだからまず彼女と一緒に仕事することになるわ」
ラーンがそう言うと慌ててスーチが立ち上がって手を差し伸べながら、高く澄んだ声で挨拶した。
「初めまして。スーチです」
「ア、アルマ……です」
おっかなびっくりでスーチと握手しているアルマを見ながらラーンが言った。
「スーチはユディ族っていうんだけど、見たのは初めて?」
「え? はい……」
「後でゆっくり話しなさいな。いろいろおもしろい話が聞けるわよ。で、横にいるのがカリス族のギメル・アインね。彼はメインのエンジニアをしてくれてるわ。ここのシステムの事実上の責任者ね」
それと共にギメルが立ち上がった。身長は2メートルを優に超えている。
「ギメルです。よろしく」
アルマはほとんど声が出せないようだった。無理もない。その体格と面構えの上に腹の底から響くようなドスの利いた声なのだから。実は大変心優しい男なのだが。
それからラーンはウォンとイオの方を向いた。
「で最後に今来た二人だけど、右にいるのがイオ。左がさっき言ったウォンね。二人ともヒト族。でも明らかに人類の面汚しね」
それを聞いてアルマはくすっと笑った。
「ちょっと! いくら何でもそう言う言い方は……」
イオがラーンに文句をつける。だがラーンは涼しい顔だ。
「だってあんた達が来る間どうやって間を持たせれば良かったのよ? 時間通り来てれば問題はなかったのにねえ」
「い、いったい何言ったんですか?」
「大したことは言ってないわよ。休暇の有効な過ごし方についてとか……」
それを聞いて二人は真っ赤になった。
「な何てこと言うんですか! これはやっぱり個人のプライバシーという……」
「プライバシー? みんな知ってることなのに? 彼女はもうここの仲間なのよ」
それを聞いてウォンとイオは互いに指さしながら叫んだ。
「こいつが人を悪の道に引きずり込んだんだ!」
「俺は後半はちゃんと旅行しようと思ってたんだ!」
それを聞いてラーンがにやっと笑って言った。
「どうして週末の過ごし方を話してただけでそんなに慌てるのよ?」
ウォンとイオはラーンに嵌められたことに気づいて、口をあんぐりあけたまま顔を見合わせた。その様子を見てアルマはついに声を出して笑い始めた。
ウォンとイオはいったい何とフォローするべきか分からず、ただ彼女を見つめるしかなかった。しばらくしてアルマは見つめられていることに気づいた。彼女は顔を上げると苦しそうに一言言った。
「す、すまぬ」
「?」
「?」
ウォンとイオは一瞬混乱した。すまぬ? 今のは彼女が言ったのか?
だがラーンも他のメンバーもそのことに関しては全く気にしていないようだ。アルマの笑いの発作が収まると、ラーンは二人に向かって言った。
「ええ、それはそうとあんた達、彼女のことは知らないの?」
二人は顔を見合わせた。それを見てラーンはくくっと笑った。
「まあそんなことだと思ったわ、それで自己紹介は?」
何のことだかよく分からなかったが、まずイオが自己紹介を始めた。
「あ、はい。僕はイオ・クロウリーです。インストラクターをやっています」
次いでウォンが言った。
「あ、ええ、ウォン・リンドゥーです。同じくインストラクターです」
そう言いながらウォンはアルマを眺めた。背の高さはかなりある方だ。髪の毛はやや癖のある赤毛だが、手入れは良い。それに結構スタイルもいいし、微笑んでいるところが何とも可愛い……これはもしかしたらチャンスかも知れない。ウォンがそんなことを考えていると、アルマが答えた。
「お初にお目にかかり申す。妾はアルマ・マートルじゃ。明日よりここにて働かせてもらうことになり申した。よしなにお頼み申す」
「……」
「……」
二人はしばらくぽかんと彼女を見つめた。この娘、いったいどういうキャラクターなのだ? さっきラーンが彼女を知らないかとか言っていたが、もしかして芸人か何かなのだろうか? 少なくともアイドルではなさそうだが……
そんな思いから最初に我に返ったのはイオだった。
「えっと、出身はどちらですか」
「ルフティ・ベイじゃ」
ルフティ・ベイとはこの街のことである。ここは相当変な場所ではあるが、こんな喋り方が流行っているという話は聞かない……彼女は二人のそういった疑問を察したようだった。
「すまぬな。妙な喋り方で。今様な喋り方はおいおい学ぶ故、しばらくは我慢してたもれ」
今様な喋り方? おいおい学ぶ? それを聞いて二人は何となく理由が分かった気がした。それを確かめるためにイオが尋ねた。
「ってことは、もしかして君、スリーパー?」
「そうじゃ」
これで疑問は氷解した。彼女がコールドスリーパーであれば、ズレた物の言い方をしてもおかしくない。だが彼女の喋り方はズレているというより、ほとんど古語なのだが……
「でもその言葉だとずいぶん前だよね?」
イオがそう尋ねるとアルマはなぜか悲しそうにため息をついた。
「然りじゃ。妾が眠ったのが4625年であるから、1500年ぐらいになるかな」
「1500年!」
イオは目を丸くした。普通そうだ。こんなに長くコールドスリープしたという話は聞いたことがない。いったい何でまたそんなに長く?
だがウォンの方はそういう風には考えていなかった。彼は彼女が“スリーパー”と分かった瞬間、かっと頭に血が上って見境がなくなっていたのだ。ウォンはこうなると脊髄反射レベルで行動するという悪い癖があった。ウォンは思わず彼女に言い放っていた。
「ふーん。そりゃまた裕福なお家だったんだね」
もちろんこれが誉め言葉のはずがなかった。彼女は訝しそうにウォンを見た。当然ながら彼女にはそんな皮肉を言われる筋合いはない。
「それはいったいどういう意味じゃ?」
アルマはそう言って真っ向からウォンを見返した。そう返されてウォンはさらにかちんと来た。
「聞いての通りさ。そんなお嬢様がどうしてこんな所で働こうってかな?」
普通いきなり初対面でここまであからさまな敵意を見せられると驚く方が先に来そうなものだが、彼女はこの程度で呑まれてしまうような性格ではなかったようだ。
「おのれ、何か妾に恨みでもあるかや?」
アルマは怯むどころか刺すような目つきでウォンを睨む。それを見てウォンはますます腹を立てた。
「は! スリーパーなんて、遊び半分で生きてるような奴だろうが! そんな奴らにちゃんとした仕事なんかができるのか? どうせ退屈しのぎなんだろう?」
―――ここは少し説明がいるかもしれない。この当時コールドスリープは短期的なものであれば日常的に使われていた。例えば大怪我をして移送しなければならないような場合など、凍らせてしまった方が出血もなく生体への損傷が少なくて済むので、救急カーゴなどでは冷凍化設備が標準装備となっていたりする。
だが長期間のコールドスリープとなるとほとんど存在価値がない代物だった。宇宙飛行の際はワープ航法があるので飛ぶ側も待つ側も寝ている必要などない。また医学も十分に発展しているので未来でないと直らない病気なども存在しない。
そのため長期間のコールドスリープは、現在が嫌になったんで未来へさよならとか、年下の恋人より若くなりたいなどといった、そう言った原則どうでもいい使い道しか残っていなかったのだ。従ってそれを利用する者も限られているし、費用もバカ高い。数十年間利用するだけで結構な金額がかかるのだ。要するに長期コールドスリープとは金持ちの道楽だったのだ。
もちろんウォンが怒ったのは、この時代に生まれた者はこの時代を生き抜くことにより人生の意味を見つけだすべきだ、とかいった高尚な理由のためではなかった。かつて入れ込んだ女にそんな感じで逃げられたという悲しい過去のせいだったのだが……それはともかく、周囲の者はそろそろ止めなければまずいと感じ始めていた。
だがそれは一歩遅かった。
アルマは唐突にウォンに詰め寄ると、いきなり強烈な平手打ちを食らわせたのだ。いや平手打ちと言うよりは掌打と言った方がいい。ウォンはもんどり打って椅子から転げ落ちた。
次の瞬間アルマはウォンに馬乗りになって胸ぐらをねじり上げていた。
「この下郎が! おのれごときにそこまで愚弄される謂われはないわ!」
そういって彼女はウォンの鼻っ柱に拳を叩き込んだ。
あっという間の早業だった。
ウォンは何もできなかった。自分の陥った状況が良く理解できていなかったのだ。その時やっと周囲の者が間に合った。
「やめなさい!」
そう言ってアルマを後ろから抱きすくめたのはゼナだった。
「でもこの男!」
アルマはゼナの制止を振り切ってウォンにもう一発食らわそうとした。だがゼナはその腕をしっかりと掴んで再び言った。
「やめなさい」
二回目のゼナの命令には有無を言わせぬ響きがあった。アルマは渋々立ち上がった。
それから数秒間ウォンは床に倒れたままだった。それからいきなり弾かれたように立ち上がるとわめいた。
「このアマ、ぶっ殺してやる!」
ウォンはそのままアルマに飛びかかろうとした。だが今度はギメルにいきなり首根っこを掴まれて宙に持ち上げられた。
「ウォンさん、落ち着いて下さいよ」
「は、離せよ! ギィ!」
ギメルは当然見かけだけではない。その気になればこの程度のことは朝飯前だ。
ウォンを吊り上げたギメルはミースの方を見ながら言った。
「どうします?」
「もう少しそうしとけ」
ウォンは何とかして逃れようと暴れた。だがその時ウォンの前にミースが立ちはだかった。
「いい加減にしろよ」
ミースはここの支配人をしているだけあって、こういったときには迫力がある。ウォンは一瞬で正気に戻った。それを見てからミースは低い声で言う。
「お前、今月は給料10パーセントカットな」
「え! そ、そんな! 殴られたのは俺ですよ」
「殴られて当然だ! バカ者が! 考えても見ろ。普通1500年もスリープするか? 何か訳ありだとは思わなかったのか?」
「え? あ!」
言われてみれば確かにその通りだ。途端にウォンは滅茶苦茶に理不尽な振る舞いをしていたことにやっと気がついた。
《やべ! またやっちまった……》
いつもそうだ。なぜか知らないが彼はここぞというところでこういうヘマをしでかしてしまうのだ。それを悟るとウォンはへなへなとぺしゃんこになった。
それを見てミースはギメルに合図をした。ギメルはうなずくとウォンを下ろして元の椅子に座らせた。ウォンはいっさい逆らわずに、まるで空気の抜けた人形のようだった。
ウォンの落ち込みようは見ていて哀れになるほどだったが、そういうことは良くあることだったので、呆けているウォンを無視してミースは話し始めた。
「お前らどうも知らないみたいなんで説明しとこう。彼女はいわゆる犯罪被害者で、信じられないような目に会ってるんだ。この間ニュースでもやってたんだがな」
それを聞いてウォンとイオは、先ほどラーンが彼女を見たことがあるかと聞いた意味がやっと分かった。
「これがひどい話なんだな。お前ら、マリア・ヨゼファ号事件を覚えてるか?」
ミースはイオに向かって尋ねた。
「え? 確か聞いたことがありますね。昔のハイジャック事件でしたっけ?」
「そう。トリスタン行きの宇宙船が乗っ取られて、乗員4500名が全員死亡って奴なんだがな……」
それからミースの語った内容はこうだ。
―――元々アルマは30年そこそこのスリープ予定だった。理由は彼女の兄が系外惑星探査に行くためだという。この場合だと通常空間を高速に航行することもあって、固有時間がずれる場合も発生するのだ。アルマは他に身寄りがなかったので、ちょっと贅沢をして兄の帰りを待つことにしたという。
彼女にとって不運だったのは、ちょうどその時起こったのがこの事件だったということだった。彼女は運悪くその犯人の身分詐称にうまいこと利用されてしまったのである。
この時代当然のことながら戸籍の管理はかなり厳しく、偽の身元をでっち上げるというのはかなり難しい問題だった。なぜなら戸籍のデータベースをクラックすること自体が難しい上、データはあちこちにミラーリングされているため、いい加減に改変するとすぐつじつまが合わなってしまうのだ。
しかし既に存在している二人の身元を入れ替えるのであればまだ操作しやすかった。ただしそうは言っても二人でいろいろ示し合わせて、指先の皮膚と“チップ”ぐらいは交換移植していないとお話にならないレベルである。異なった二人が同じ人間であると主張したらやはり即座に問題が発覚してしまうのは当然であろう。
だがもし片方が大変おとなしくてくれていて、通常の活動を全然しなかったとしたらどうだろう? その場合は更に話は簡単になってくるわけだ。コールドスリープ中の人間は大抵のことには文句を言わない。こういう操作には打ってつけだったわけだ。
具体的には犯人の一人がコールドスリープに入る手続きをする。同時にアルマを覚醒させる手続きもする。しかし当然ここでアルマを本当に目覚めさせるわけではなく、ここで二人のデータだけを交換してしまうのだ。
こうして犯人は戸籍上は“アルマ・マートル”になって、あの事件を引き起こした。アルマの本体の方はその犯人ということになってずっと眠っていたわけだ。
更に犯人は当然ながらコールドスリープ料金を払うつもりはなかった。そのため管理データを改竄して、彼女は表向き存在さえしていなかったのだ。前にも言ったとおり、コールドスリープとはかなり道楽要素が強い。そのためデータの管理もかなり甘かったのだ。
その結果彼女が“発見”されたのは本当に偶然で、暇を持て余した管理人が数万個もあるスリープボックスを実際に一つずつ数えてみたら、管理データの個数と食い違ったことによる。しかも彼が自分の数えた個数が正しいとしつこく主張したためで、そうでなければ彼女があと何年寝ていたか、誰にも分からない―――
それを聞いてイオが驚いた。
「ってことは、記録上は彼女が犯人になってるんですか?」
その質問にミースが答えた。
「その通り。こういう前例がないんで、今彼女の名誉回復でもめているところだ」
「でもその偽物は良く船に乗れましたね。系外に行く時にはチップ確認の他に、普通バイオ照合もしますよね」
「だからやられてたんだよ」
「え?」
「見つかったときはひどい有様だったそうだ。片腕はチップごとちょんぎられて、網膜認証用に目玉まで抜かれてたそうだ」
それを聞いてイオとウォンは返す言葉もなかった。だがその時小声でラーンが割り込んだ。
「ちょっと! ミース。彼女がいるのよ」
ミースはしまったという顔でアルマを見た。だが彼女はミースに微笑みかけた。
「良いのじゃ。もう。それに新しい目や腕の方が調子も良いしな」
だがその笑みにはかなり無理が感じられる。
「すまん。まあ、そういうことなのだ」
ミースはばつが悪そうにアルマに微笑み返した。イオとウォンは恐る恐る彼女の顔を見る。
「もう慣れてしもうた。今更騒いでもせんなかろう?」
こういう状況で返せる言葉などあるわけがない。もっと彼女と親密だったら、ぎゅっと抱きしめてやるぐらいだが……もちろん今のウォンには無理な話だ。
二人は黙ってうなずくしかなかった。
「その上彼女の財産もみんな使い尽くされていてな、今彼女は大変困った状況なんだよ。こういう事情だから生活保護が出ることは出るんだが、それじゃ旅費を貯めるまでにはいかないんでここで働くことになったんだよ」
「旅費?」
イオが訊き返すとミースが答えた。
「ああ。なんでもジェストコーストの、ええと、どこだったっけ?」
「アルガシティーじゃ」
「そうそう。アルガシティー。そこに行くそうだ」
ジェストコーストとは別ドミニオンである。このベレンからは4000光年ほど先だ。従ってさすがにかなりの旅費がかかるのは仕方ない。
「そこに知り合いでも?」
イオが尋ねるとアルマは答えた。
「たぶんおらんじゃろう……でもそういう伝言が残されておったのじゃ。他にどうすればよいというのじゃ?」
そう言って彼女はうつむいてしまった。
「いや、そう言うつもりじゃなくて、ごめん……でもどうしてここで働くことに? 給料安いのに……」
その言葉でミースは明らかに気分を害したようだ。イオはそれに気づいて慌てて手を振った。
「いや、その、そう言うつもりじゃないんですよ。あはは」
それを聞いてアルマが言った。
「これは妾がお頼み申したのじゃ。どうせならば少しでも知っておる仕事の方が良いのでな」
そこで今まで黙っていたスーチが尋ねた。
「それじゃNSEゲームをやったことがあるんですか?」
「一応な。じゃが1500年も前のことじゃ」
アルマの言葉にイオとスーチは顔を見合わせた。そしてイオが尋ねる。
「1500年前って、ほとんど出だしの頃だけど……いったいどんなのをやってたんです?」
イオの問いにアルマは自信なげに答えた。
「ロクス・エテルナとベラトリックスじゃ」
だが彼女がそう答えた途端にイオとスーチ、ギメル、それにぺしゃんこになっていたウォンまでが驚きの声をあげた。それもそのはず。この業界にいてその名前を知らない奴はモグリだ。この二つは現在あるNSE(Neuro-signal Emulation)ゲームの元祖のようなものなのだ。
「すっごーい! 本当?」
スーチが思わず立ち上がって言う。アルマは驚いて半歩下がった。
「嘘は言わぬ。じゃが1500年も前のことじゃ……かような知識が役に立つかどうか……」
「たぶん大丈夫よ。だったらすぐ覚えられるわ」
そう言ってスーチは再びアルマの手を握った。
「本当であろうか?」
アルマはおっかなびっくりという感じでスーチの手を握り返す。
「もちろんよ」
「かたじけない……それではお頼み申す」
そう言ってアルマはスーチに微笑み返した。それを見てミースが言った。
「そういうわけなんで明日から彼女がアシスタントで入るからな。しばらくはみんな彼女をフォローしてやってくれ。いいか?」
「はいっ」
ウォンを除いた一同が一斉に答える。ミースは耳聡くそれに気づいていた。
「ウォン! 返事はどうした!」
「は、はい」
ウォンは今の話を聞いて打ちのめされていた。いくら何でもこれはひどい。ひどすぎる。とにかくまず謝ろう。それしかない。
そう思うとウォンはふらふらとアルマに近づいた。
「あ、あの……」
「なんじゃ?」
アルマは冷ややかな目でウォンを見つめた。
「さっきは、その……ごめん」
「もう気にしておらんわ」
だがその表情を見れば、それが単なる社交儀礼であるのは明らかだった。