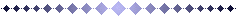第2章 ファイナルブレード
ウォンはまた約束の時間に遅れそうになっていた。そのため階段の上り口から出た途端に、やってきたアルマにぶつかりそうになってしまった。途端にアルマは強烈な前蹴りを繰り出してくる。ウォンは慌てて避けはしたが、勢い余って尻餅をついてしまった。
「てめえ何しやがる!」
「言うたであろうが! 妾に寄るなと!」
「お前が勝手に出てきたんだろうが!」
「妾は普通に歩いておっただけじゃ!」
そう言ってアルマはすたすた行ってしまった。
あれから10日ほど経つが、いまだに万事がこの調子だ。ウォンはアルマに近づく度にこういう目に会っていた。異界の門の建物はそんなに広くはない。近寄るなと言う方が無理である。
だが、ミース達はどうもこの事態を面白がっているようで、ウォンが泣きついても全然取り合ってくれない。仕方なくウォンはなるべくアルマに近寄らないようにと自衛するしかなかった。
だが今回はちょっと問題があった。アルマが歩いていった方向はウォンの行きたい方向だったのだ。当然ウォンはアルマの後からついていく形になる。
「何故おのれは付けてくるのじゃ!」
「こっちに用があるからだよ」
「そんなもの後にせい!」
どうもアルマはウォンの理由を知らないようだ。ウォンはアルマに尋ねた。
「あのさ。これからスーチと潜るんじゃねえの?」
「だったらどうしたというのじゃ!」
「俺も行くんだけど。聞いてないのか?」
「なんじゃと?」
目的の部屋はすぐそこだったので、アルマは中に駆け込んだ。ウォンもその後に続いて部屋に入る。
その部屋はNSEブースにつながるロビーで、中ではゼナとスーチが待ちかまえていた。入ってきたアルマに向かってゼナが言う。
「やっと来たわね。準備はいい?」
「ゼナ殿! イオ殿はいかがなされた?」
それを聞いてゼナは苦笑いした。
「あ、それがやっぱり都合が付かなくなっちゃってね。でも最初に言ったでしょ。場合によったらウォンに頼むって」
「そういうことはなさそうだと言われておったではないか!」
「最近はイオにも固定客がついちゃってね。むげにできないのよ」
それを聞いてアルマはとてつもなく残念そうにため息をついた。
「ううう。何故にこのような男と一緒に潜らねばならぬのじゃ……」
「いやならやめろよ」
「ふざけるでない! 妾の方が先に約束したのじゃ! そうじゃ、おのれイオ殿と代わってくるが良い」
「あのなあ……」
それを聞いてゼナが口を挟んだ。
「二人ともいい加減にしてよ。今回はスーちゃんの練習なのよ。これは業務と思ってほしいんだけど」
ゼナはなりは小娘なのだが実年齢はウォン達より遙かに上で、更にはインストラクター部門のチーフである。ウォンにとっては直接の上司だ。
だがそういった立場を越えて彼女の言葉には魔法のように有無を言わせない力があった。ゼナの一言で二人は黙り込むしかなかったが、ついでにスーチまで緊張して固まってしまった。
「スーちゃんもいい?」
「え? は、はいっ!」
スーチの声は明らかにうわずっている。
「ねえ、そんなに固くならないでいいのよ。本番形式だけど、あくまで練習なんだし」
「は、はい……」
スーチはここのアシスタントをしているが、現在インストラクターになるための訓練中なのだ。インストラクターとは別名ガイドとも呼ばれるが、要するに客と一緒に入ってゲームを楽しくするために様々な手助けをしてやるのが仕事だ。当然アシスタントより高度な技能が要求されるのだが、もちろんその分実入りも良い。
「じゃあいいかしら? スー、始めるわよ。いい?」
「はい」
「それとウォン、今回はあたし達は“素人”だってこと忘れないようにね」
そう言ってゼナがウォンを見る。
「やだなあ、分かってますよ」
「いつもそう言いながら暴走するから、釘を差してるのよ」
「大丈夫ですって!」
横でアルマがくすくす笑っているのを聞いてウォンは少しむかついた。
「アルマもいい?」
それを聞いてアルマはにこにこしながら答えた。
「良いぞ。なんだかわくわくするのう。じゃが、本当に妾は好きにしても良いのかや?」
「今のゲームを実際にするのは初めてでしょ? とにかく見てみないと。でもゲーム中はスーの言うことだけは聞くのよ」
「もちろんじゃ」
「じゃ始めましょう」
そう言ってゼナはスーチに合図をした。スーチがうなずいた。
「それじゃ始めまーす。みなさんいらっしゃい。私が今回ご案内を勤めるスーチ・アインです」
ゼナ、ウォン、アルマの三人は客になったつもりでスーチに自己紹介した。
「これからご案内するNSEゲームは“ファイナルブレード”です。みなさん基本ルールに関してはお読みになって来られましたか?」
三人の代表でゼナが答える。
「ええ。一応」
「でしたら細かいことは中で説明した方がいいですよね。それでは早速入ってみたいと思いますが、その前にみんなの役割だけは決めておきましょう。えっと、何かご希望はございますか?」
それを聞いてアルマがすぐに手を挙げた。
「妾は剣士が良いぞ」
それを聞いて残りは顔を見合わせた。みんなアルマが昔こういうゲームを経験していることは知っていたが、忙しくて具体的な話を聞く暇が全然なかったのだ。
「え? でも剣士って常に敵と接触するんで、初めてだと大変なんですよ。それにこのゲーム、敵が結構強いんで剣士が一番難しいんです」
「さようか? とはいえ妾は剣士以外はほとんどしたことがなくてな」
スーチはいきなりの難問を突きつけられて、困ったようにゼナの顔を見た。彼女もちょっと考え込んでいる。その時ウォンが言った。
「やりたいって言うならいいんじゃねえの?」
ウォンにとってはこれはなかなかのチャンスに思えた。彼がアルマにいいところを見せる絶好の機会ではないか! そういったウォンの下心を知ってか知らずか、ゼナも言った。
「そうね。じゃあウォンとアルマ、二人剣士でどうかしら? ガイドさん、何か困ることある?」
「え? でもシーフの……あ、そうか、はい。大丈夫です。ただちょっと魔導師が難しくなりますんで、私が魔導師になりますが、いいですか?」
「構わないわよ。それじゃ私が僧侶ね?」
それを聞いてアルマが口を挟んだ。
「何? 妾とこ奴が同じ剣士かや?」
そう言ってアルマはウォンを指さす。だがウォンが怒鳴り始める前にゼナが割り込んだ。
「二枚看板の方が戦闘は楽でしょ?」
ゼナはそう言ってしまってから、この言い方では初心者には分からないかもしれないと思い当たった。普通四人パーティーの場合は前面には剣士と盗賊系が入るのが普通だ。危険なところを歩くには盗賊の技能が必要だからだ。だが伝統的に多くの盗賊技能が魔導師の魔法でも代用できる。そのため戦士二人という選択もある。もちろんどちらも一長一短なのだが。
普通ならこういったことを説明しなければならないところなのだが、アルマはそこのところは十分理解できているようだった。
「ふむ。そうじゃな。それに初めての場所じゃ。仕方あるまいな」
それを聞いてゼナ達は、アルマが彼らの想像以上にこういったゲームに慣れているのではないかと思い始めた。
「それじゃ役割も決まったので、こちらにどうぞ」
そう言うとスーチはロビーにつながる部屋の一つに三人を導いた。
その部屋は狭く、真ん中に透明のケースで覆われた細長い装置がある。スーチはそれを指して言った。
「これがNSEブース、すなわち異界への入り口です。そっちの扉はバスルームになっています。ブースに入られる前に用を足される方は足しておいて下さい。それから着ている物を全部脱いで頂いて、そこのロッカーに入れて下さい。ゲームは短くても数時間、長ければ数日に及ぶ場合もございます。ですのでその間本体の方も栄養を取ったり排泄する必要がございます」
それからスーチはブースのカバーを開いた。
「ではブースへの入り方を説明します。まずここの部分にまたがるように乗って下さい。それから右にある赤いスイッチをオンにして下さい。そうしますと股間にこれが自動的に装着されます。ちょっと変な感じがするかも知れませんが、すぐに慣れます。装着が終わると自動的に後ろのシートが倒れます。それから首から背中にかけて神経接続シールが張り付きます。前面パネルのバーが青くなるまでなるべく体を動かさないようにしてください。でないと神経接続が失敗することがあります。それから人によっては接続時にかゆみを感じる場合もありますが、そういう経験をされた方はいらっしゃいますか?」
それを聞いてアルマが言った。
「妾は結構そういうことはあったが……」
「あ、たぶん大丈夫よ。これってマニュアルに書いてあって、言っておかないといけないの。スキン作るときにちょっと入ったんでしょ?」
「ああ。あの時はなんともなかったな」
「スーちゃん。アルマはお客様よ。マニュアルのことなんて言っちゃだめよ。それに馴れ馴れしすぎるわ」
「あ、すみません。えっと、問題はまずございません。ただかゆくなったり痛みを感じたりした場合は掻いたり引っ張ったりしないで、すぐそこの呼び出しスイッチを入れて下さいね」
「分かり申した」
「最終的に接続は5分ぐらいで完了します。前面パネルに接続状態が表示されます。この状態では絶対に背中のシールを引っ張ったりはがしたりしないで下さい。シールから出た大量の微細な繊毛が神経に接続していますので、最悪の場合神経を傷つける恐れがございます。よろしいでしょうか?」
三人は神妙にうなずいた。実際このシステムはこの部分が一番気持ち悪いところではある。だが実際にはシールをはがした所で繊毛がちぎれるだけで滅多に危険はないのだが、事故例がゼロではないので注意するに越したことはない。
「皆様の接続が完了したらこちらから合図を致します。そうしたらまず眠気を感じますが、安心してお眠り下さい。次にお目覚めの時は皆様はタウンの宿屋にいらっしゃるはずです。ゲームのルールに関しては、今回は私が同行しますので私に聞いて下さい。皆様方だけで行かれる場合は、酒場のバーテンがなんでも教えてくれるはずです。えっとそれで、一つだけ忘れてはならない呪文がありますが、おわかりですか?」
そう言ってスーチはアルマを見た。
「システムコマンドのことかや? 確か『我が名はアルマ・マートルなり。ここに真の名を以て異界の扉を開かん』じゃな?」
「はいそうです。その呪文を唱えると『我は汝の望みをかなえよう。汝の望みとは?』という声がします。ゲームから抜けたいときやセーブポイントから再開するときはここで終了したいとか再開したいと言って下さい」
「この呪文は妾の知っておるものと同じじゃな」
それを聞いてゼナが答えた。
「ロクス・エテルナは今のゲームの先祖みたいな物だもの。他にも共通点は多いと思うわよ」
「それは心強いのう。で、そろそろ入って良いのかや?」
アルマは入りたくてうずうずしているのが一目瞭然だ。
「あ、最後にもう一点だけ。戻ってこられたときの注意ですが、場合によっては汗をかいていたりして気持ち悪いこともありますが、接続シールをいきなりはがしたりはしないで下さい。右のスイッチをオフにするとシートが戻り、切断処理が始まります。これも前面パネルに進行状態が表示されます。終わったら自動的にシールが剥がれますので、それからバスルームにどうぞ。これで説明は終わりますが、何かご質問はありませんか」
スーチはそう言って三人を見た。もちろんあるはずがない。
「それでは……本当はチケットに書いてある番号のブースにどうぞ、なんですが、今回はチケットはないので、アルマさんが12番、ゼナさんが14番、ウォン君が15番、私が18番です」
「ふむ。それでは中で会おうぞ」
そう言うとアルマはさっさと自分のブースに入ってしまった。他のメンバーはちょっと顔を見合わせたが、すぐにめいめいのブースに消えていった。
ゲームへのコネクションはスーチの説明通り全く問題なく成功した。
気がつくとアルマは薄汚れた宿屋の一室にいた。そこで横にいきなり見知らぬ女性がいたので彼女は少し驚いた。
「あの、調子はどうですか?」
アルマはその喋り方で彼女がスーチだと分かった。
「おお? 汝がスー殿かや? 見違えておるのう」
「ユディ族のスキンなんてないんで、中だとこうなっちゃうんです」
「ふむ。動きで困ることはないのかや?」
「ないこともないんですが、もう慣れました。そのうちギィにネイティブなデータを加えてもらおうと思うんですが、なかなか忙しくって」
NSEシステムとは要するに神経の信号を途中でフックすることで完全な仮想現実を実現するシステムである。感覚神経に偽の信号を与えてやることで、現実には存在しない世界を完全に実感させることができる。また運動神経への出力を解釈することで、仮想現実内の体を動かすことができる。この仮想現実内の体が“スキン”と呼ばれていた。
このスキンであるが、人の脳というのはやはり自分の体を操作するのに最適にできている。そのためまず各プレーヤー専用のスキンを用意する必要があった。
もちろん同じ人間の物であれば他人のスキンでも使えないことはない。しかし他人のスキンだと同種同性であっても結構な違和感がある。種族までが異なると身体感覚は耐え難いまでに異なっていると言って良い。だがスーチの属するユディ族ここでは少数種族なのでユディ族用のスキンは元々存在していなかった。彼女が今こうしてゲーム内にいられるのは、彼女が多大な苦労と特別な調整を行った結果、何とかヒト族ベースのスキンを扱えるようになっていたからだ。
二人がそういった話をしているところにウォンが現れた。彼の姿はチェインメイルを着込んではいるが、実世界のウォンの姿そのままである。
ウォンは二人に向かって言った。
「おう、調子は?」
「どうもないわ。おのれがおらなんだらもっと良いがの」
「お前じゃなくてスーに訊いてるんだけど」
「なんじゃ? 喧嘩を売る気かえ?」
いきなり雲行きの怪しい二人を見てスーチが慌てて言った。
「あの、二人とも、その、これから一緒に冒険するんだし……」
「分かっておるわ。スー殿には迷惑はかけぬ故、安心するが良い」
「あの、そういう問題では……」
そのときやっとゼナが現れた。ゼナは一瞬で状況を見て取ったようだ。彼女は二人ににこっと微笑みかける。それで十分だった。二人はややひきつり気味に笑い返すしかなかった。
それを見てスーチはほっとため息をついた。それから気を取り直したように言った。
「みなさんお揃いになったようですね。体の調子はどうですか? どこか動きとか感覚がおかしいところはありませんか?」
それを聞いてアルマが答えた。
「うむ。今回はどこも悪くなさそうじゃな。前はよく片腕が動かぬようなことがあったが」
「そ、そうなんですか?」
そう尋ねるようマニュアルには書いてあるものの、スーチはそんなトラブルが実際に起こったという話は聞いたこともなかった。だからアルマがさらっとそう答えたので驚いてしまったのだ。
スーチはゼナに突っつかれて先を進めた。
「あ、それじゃこの部屋の説明をします。ここは宿屋です。ゲームを開始したらまずここに出てきます。またゲーム中に完全に死んでしまった場合もここに現れます」
「ほう? ならばここには冥界はないのかや?」
アルマの問いにスーチが訊き返した。
「冥界?」
「エテルナでは、死んだ場合は冥界に送られてな、そこから連れ出してもらえるか、仲間が全員死ぬまではそこにおらねばならなかったのじゃ。これだとすぐ戻って行けそうじゃな」
「へえ、そうだったんですか?」
それを聞いてゼナがついに口を挟んだ。
「ちょっと! スーちゃん! あなたがいちいち感心してどうするのよ。そういうのってお客様に不安を与えるのよ。相手が悪いとなめられて言うことを聞いてもらえなくなるわ。減点ね」
「あー、そんな……」
「はい。続き続き!」
ゼナの言葉にスーチは慌てて続けた。
「はい。えー、だから、そういうわけで冥界はありません。で、えっとそれじゃゲームを始めてみましょうか。このゲームの場合、最初は目的が定まっていません。そのため初心者の方は途方に暮れてしまう場合もあるんですが、そういう場合はまず誰かと話をしてみるのが基本です。ではまず下におりましょうか」
階下は酒場になっているようでたくさんの人の歓談する声が聞こえてくる。スーチは扉を開けて三人を階下に導いた。
階下は多くの冒険者達でごった返していた。
「結構混んでいますね。とりあえず席をみつけましょうか。それから情報集めの基本を実演して見せますね。えっと席は……」
「あっちで空いたぜ」
ウォンの言う方を見ると丁度四人の客が出て行くところだ。
「じゃあ、あそこに行きます。付いてきて下さい」
そういいながらスーチは人混みをかき分けて空き席に向かった。席を確保するとスーチは振り向いて説明を続けようとした。
「さて、まずこういうゲームで最初にしなければならないことは……って、アルマは?」
ゼナとウォンは付いてきているがアルマの姿がない。
「あら? さっきまで後ろにいたのに……」
ゼナも驚いてあたりを見回した。
その時だった。派手な音と共にテーブルがひっくり返って男が一人床の上を転がっていった。
「ケンカだぞ!」
「ああ、お客さん! 店の中でやめて下さい!」
三人は顔を見合わせる。こういうところでは良くあることだが……
「ははは! NPCの分際で妾に楯突くからじゃ!」
「このアマ! 言っていいことと悪いことがあるぞ!」
「悪かったらどうだというのじゃ?」
あの声は……
三人は顔を見合わせると、慌てて野次馬をかき分けて声のした方に行った。
果たせるかな、そこではアルマが四名の屈強な男に取り囲まれている。男達は手には剣を構えているが、アルマは素手だ。
「ほう? やる気かえ?」
だがアルマは全然動じていない。状況が分かっていないはずがない。だとするとよっぽど自信があるのだろうか?
「あのバカ、何やってるんだ?」
「ど、どうしよう? ウォン君」
「まあ、身から出た錆って奴だね」
「そんなこと言ってないで……」
「ああいう身勝手な奴はちょっと痛い目に遭った方が身のためだぜ。それこそ1500年前の技なんて通用しないって思い知ったら、もちっと大人しくなるんじゃないの?」
「だめよ! そんな!」
スーチは慌てて助けに入ろうとした。だがウォンが余裕たっぷりにそれを引き留める。
「まあ待てよ。俺に任せてなって」
あの程度のチンピラが人を即死させることはあり得ない。またあいつら程度ならウォンであればいかようにも料理できる相手だ。
だからウォンは一番格好良く登場できるタイミングを見計らっていたのだ。
「このアマ!」
男達は一斉にアルマに斬りかかった。
「きゃあああ!」
スーチが顔を覆う。さてそろそろウォンの出番のようだ。
「おいおい、スー。お前今ガイド様だろ? ちゃんと前を見て……」
だがそこまで言ったところで、ウォンはあんぐり口を開けたまま動けなくなってしまった。横では同様に短剣を構えたゼナが目を丸くしている。
アルマの様子を見ればこういう場面の経験が豊富なのは分かるが、ファイナルブレードの敵はザコといえども侮れない。だからウォンの予想ではアルマは最初の一人の攻撃ぐらいはかわすだろうが、すぐに店の隅に追いつめられて動きが取れなくなるはずだった。そこでおもむろに出ていってアルマに恩を着せながらゆっくりと啖呵を切る予定だったのだが……
ところが男達が襲いかかったとき、アルマは身をかわす代わりにそのうちの一人に組み付いていったのだ。アルマはそのまま男の手首を取って剣を防ぐと、顎にパンチをたたき込んだ。男はそう出られるとは思っていなかったのだろう。見事にのけぞってそのまま失神した。
それからアルマは男の剣を奪い取ると、その後ろの男達に襲いかかる。見る間に二人が血を吹き出しながら悶絶する。
人々が息を呑み込み終わったときには、彼女は最後の男の喉元に切っ先を突きつけていた。まさに一瞬の出来事だった。
「なんじゃ? 口ほどにもない! その程度の腕で妾に楯突こうとは、片腹痛いわ! あっはっはっは!」
男は真っ青になっている。誰も唖然として口を開かない。その時アルマがスーチ達に気が付いた。
「おお、スー殿、どうなされたのじゃ?」
名前を呼ばれてスーチは慌てて答えた。
「どうしたのって、あなたこそいきなり」
「ああ? こいつかや? これはな、ここでも昔良くやったガン付けが効くかどうか試してみたのじゃ。変わっとらんのう」
「えっと、あの、その……」
「そうじゃ。こ奴から何か聞き出せぬかな?」
「ええ? いえ、あの……」
パニックになっているスーに代わってゼナが口を挟んだ。
「一体何を聞くって言うの?」
「こうするとな、どうでもよいことまでぺらぺら喋る奴が結構おるではないか」
「ちょっと無理じゃない? 見てごらんなさいな」
アルマが男をみると、男は真っ青になってがくがく震えている。
「ほう? どうしたのじゃ?」
「た、助けて……」
「言うことはそれだけかや? 何か宝物の在処などは知らぬのか?」
そういうとアルマは剣先で男をつつく。
「や、やめてくれ!」
男はへなへなと地面に崩れ落ちた。
「なんじゃ? おのれはそれでも男かや? 恥を知れい!」
そう言ってアルマは男の両足の間に持っていた剣を突き立てた。
「ひぃぃ!」
それを見て男は気絶してしまった。
「ふうむ。なんと軟弱な……まあこんなおもちゃみたいな剣に似合いじゃな。どうしようもないのう」
それを聞きながらゼナとウォンは顔を見合わせた。どうも彼女に自由にやらせておくと、何をしでかすか分からないようだ。
「とにかくこっちにいらっしゃい。喉乾いたでしょ? 何か飲まない?」
スーチが完全にパニックになっているのでゼナが代わりに言った。
「おお、そうじゃな」
四人はとりあえず席についてワインとチーズを注文した。
注文した品が来るまでの間にゼナはスーチにささやいていた。
『ちょっと、しっかりしなさい。あなたがガイドなのよ』
『で、でも……』
『予想外のことってのはいつだってあるわ。ともかく今はどうすればいいの?』
『え? あの、とにかくあまり羽目を外さないようにしてもらうのと……』
『それから?』
『え? ああ、彼女、あんなに強いなんて、その、ちょっとバランスが悪いかなって……いくら何でもあれは……』
『分かってるならいいわ。すべきことをするのよ』
『は、はい。でもどのぐらい上げたらいいんでしょう?』
『それはあなたが判断するの』
『は、はい……』
スーチは小声でゲームのレベルを上げるためにギメルに通信を取り始めた。
その時ウエイターがワインを持ってきた。四人は早速乾杯をした。
「おお、これは美味じゃ。まるで本物のようじゃ」
それを聞いてウォンが答える。
「あたりめえだろ。それとも昔のってそんなにまずかったのか?」
「ああ。味だの臭いだのはかなりいい加減じゃったな。ワインなんぞは砂糖水のような味がしておったぞ」
「へえ。じゃあずいぶん今のって進歩してるんだ」
「そうじゃな。このテーブルの質感なども全然違うのう」
そのときスーチが通信を終えて顔を上げた。
「それはそうとアルマ、あなたとってもすごいのね」
「ええ? そうかや?」
「一人で武器もなしに四人相手なんて、心臓が止まるかと思ったわ」
「いや、あやつら口の割には動きが鈍そうじゃったのでな」
それを聞いてゼナとウォンは顔を見合わせた。アルマはこの短時間に本当にそんなところを見抜いたのだろうか?
「そうよね。たまたまあいつらがザコで良かったわ」
「やはり、そうであったか?」
「そうなのよ。口ばっかりで実力の伴わない奴ってのはどこにでもいるのよね。だからもうあんなに危ないことしないでね」
「ふうむ。すまぬ。ついはしゃいでしもうたようじゃな」
「違うの。これで油断しないでねってことなのよ。今度出会う敵があんなに弱い保証はないから……でね、これからすぐ武器屋に行った方がいいと思うの。こんな騒ぎを起こしたらもうしばらくはトラブルの方からやってきてくれるわ。なのにあなたは武器も防具もぜんぜんないし」
「ふむ。道理じゃ」
彼女は今回が初入りなので、手元には本当に最低限の物しかない。服装といえば普通の村娘のようななりで、武器も小さな短剣があるだけだ。
「他の方もいいですか?」
アルマが同意したのでスーチはゼナとウォンに向かって言った。もちろん二人に異存のあるはずはなかった。この調子だとしばらくは喧嘩の売り買いが頻繁に起こりそうだ。さっさとアルマを武装させておかないと大変である。願わくば武器屋に行くまでの間に襲われないことを祈るのみだ。
世の中たまには祈りが通じることもあるようだ。この街の武器屋は宿屋から少し離れた区画にあるのだが、一行が行きつくまでの間には運良く悶着は起こらなかった。
「着いたわ。ここよ」
スーチは安堵のため息をつきながら一行を中に案内した。中に入ったアルマは感動したようにつぶやく。
「ほう。えらく高そうな物まで揃っておるな」
「あ、このゲームでは武器屋はここだけなんです。ショートシナリオ専門なので」
「ああ、なるほどな。で、妾はいかほど使えるのじゃ?」
「あ、えっと、2000ゴールドあるわ」
それを聞いてアルマは驚いた。
「そんなに使っても良いのかや? かなり良い物が買えそうじゃが……」
「今回は初心者という設定なんで、初期の資金がたくさんあるの。それにあたし達の装備は、この間買ったのがあるし」
「そうか、ではおい。おやじ!」
アルマは店の奥にいた無愛想な親父に話しかけた。
「何だ?」
「そこな武器を手にとって良いかな?」
「ちゃんと戻しとくならな」
それを聞いてアルマはつかつかと迷わずレイピアやエペ等の打突剣のコーナーに向かった。
それを見てウォンは思わず言った。
「ああ。おまえそんなのを使うのか?」
「使ったら悪いかや?」
「いや、それって突くしか脳がないだろ? あっちのソードの方がいいんじゃねえの?」
「最初はこれが軽いから、これが良いのじゃ」
「は?」
ウォンはアルマの言ったことがよく分からなかった。アルマは壁に掛かっている中からすらっとしたレイピアを下ろして手に取った。
「?」
だが彼女はそれを何度か振ってみて不思議そうな顔をした。
「どうしたの? アルマ」
スーチがそれに気づいて尋ねる。
「いや、ちょっと軽すぎるのでな。そんな業物にも見えぬが……」
「どれ?」
アルマはスーチに剣を渡す。スーチは剣を振ってみたが何ら変わったところはない。
「こんなものじゃないの? ねえ、ウォン」
今度はウォンがスーチから剣を受け取ったが、やっぱり同じだ。特に変わったところはない。普通のレイピアだ。
「そんなに軽いか?」
「まるでアルミでできているようじゃ。折れたりはすまいな?」
それを聞いてスーチはやっと思い当たった。
「あ、それ、実物の重さよりはずいぶん軽くなってるのよ」
「なんと? それはまたどうして?」
「どうしてって、重いと扱いにくいからだと思うけど……」
それを聞いてアルマはしばらく考え込んだ。
「ふうむ。あの軟弱者の使っていた剣も、まがい物だから軽かったのではないのじゃな……ならばもう少し大きな剣でも良いのであろうか?」
そういってアルマはレイピアを棚に戻すと隣の壁にかかっていたフラムベルジュを手に取った。巨大な両刃の剣で、歯が鋸のようになっている。だがアルマはそれを片手で振り回した。
「ふむ。これで丁度良いな。価格も手頃じゃし。いきなりパワーアップした気分じゃ」
「ええ? いいの? それ両手剣よ」
「とりあえずこれでやってみたいのじゃ。不都合であれば戻せばよかろう」
「いいんならいいけど……」
それから今度はアルマは防具のコーナーに行ってレザーアーマーを物色し始めた。
「ねえアルマ、残っている金額ならスケールメイルでも買えるわよ」
「あれはかちゃかちゃうるさくてすぐ見つかるので嫌いなのじゃ。火を噴かれたときにも焼け付くしな」
「そう? ならいいけど……」
このあたりの手際はウォンやゼナも口出す隙がなかった。そのころにはみんなもしかしたらアルマはゲームに慣れているというよりは、実は非常に熟達したプレーヤーなのではと思い始めていた。
果たせるかな、それはすぐ証明されることとなった。
一行が買い物を終わり武器屋から出てきた時だった。
「こいつらだ! こいつらだ!」
そういう声と共に多数の男達に取り囲まれてしまった。男達は20名以上はいるだろうか? それを見てアルマは驚くどころか喜びの声をあげた。
「おお、スーチ殿の言った通りじゃな! ついに出てきおったか」
だがスーチの方は肝を潰していた。
「ど、どうしてこんなに出るの?」
そのつぶやきをゼナは聞き逃さなかった。彼女はスーチにささやいた。
『ちょっとスーちゃん。どういう調整したのよ?』
『敵の能力クラスをエキスパートにして、それから出現レベルを4上げてって……』
『4? そりゃいくら何でもやりすぎよ。敵は5割増で増えていくのよ』
『え? 2割増じゃ?』
『それはダークブレード』
「ああ!」
スーチは思わず声を出して叫んでしまった。それを聞いてアルマとウォンがスーチの顔を見る。
「どうしたんだ? スー?」
ウォンの問いにスーチはしどろもどろで答える。
「え? ちょっと、その手違いが……」
「ああ? どんな?」
「その、7~8人ぐらいのつもりが、20人ぐらい出ちゃったの……」
「なんだって?」
ウォンもそれには驚いた。ウォンはスーチがレベル調整していたことには当然気づいている。そうした敵がこんなに出てきたとあれば、相当マジになってやらないとやばいかもしれない。
だがアルマは相変わらず平然としている。
「なんじゃ。そんなことかや? やっつければ良いではないか」
「ええ? でも……」
スーチは目を白黒させている。
「アホ! 簡単に言うけどな」
「何じゃ? おのれは怖いのか?」
「誰が怖いか!」
「ならば良いではないか!」
「あのなあ、こんだけいたらお前をフォローしきれないっての!」
「おお? フォローじゃと? そりゃまたご親切に。だが結構じゃ。おのれの命の心配だけしておれ!」
「寝ぼけるな! こいつらはさっきみたいなザコじゃねえの! 死ぬぞ!」
「それはおもしろいわ。久々に暴れられるというものじゃ!」
スーチとゼナは何とか取りなそうかと考えていたが、もはやこれは処置なしである。
その時男達の中からリーダーとおぼしき男が前に進み出た。他の奴らより一回り大きく、見るからに強そうだ。
「ああ、てめえか? 酒場でうちの子分をシメてくれたアマってのは?」
それを見てまるで当然のようにアルマが進み出る。
「ほう。おのれがあの軟弱者の親玉かえ?」
「何だと?」
「ふうむ。見かけ通りに頭の悪そうな奴じゃ。どうせ話しても通じぬのじゃろう? だったら、さっさと有り金おいて立ち去れい。さすれば命までは取らぬぞ」
なんだかどちらが悪役か分からない。
「な、なんだと? このアマ!」
「せっかく人が友好的に話しておるのに、物の道理の分からぬ奴らじゃ」
はっきり言ってこの場合、道理は相手の方にある。当然ながらそれを聞いて親玉は真っ赤になった。
親玉は剣の柄に手をかけると部下に指令を出そうとした。
「てめえら、このアマをやっち……」
だが親玉はそれ以上のセリフを言うことはできなかった。なぜならその時親玉の開いた口にはアルマのフラムベルジュが突き刺さり、胴体はウォンの大剣でまっぷたつに両断されていたためである。これではちょっと続きは言えないだろう。
そしてアルマとウォンは驚いたような顔で互いに見つめ合っっていた。
これだけ人数差のある戦いでは敵の頭をまず取るしかないが、戦いが始まってからでは困難だ。先手を取るにはあのタイミングしかなかった。こういった瞬間を見切ること、それは剣士に最も必要とされる能力だ。
そして互いにその瞬間を逃さず完璧に行動したことは疑いようもなかった。しかも最初の一撃で倒し損なうと状況は更に悪くなるが、共に十分にその目的を達していたことは明らかである。
この瞬間二人は互いに認め合わざるを得なかった。
それからアルマはウォンににこっと笑いかけた。
「ではそちらの半分、頼むぞよ」
「おう!」
ウォンは何だか知らないが最高の気分だった。
その言葉と共に大乱戦……というより大虐殺が始まった……