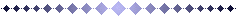第4章 黒水晶
アルマは異界の門のHQ(総司令部)と名付けられた部屋で半球型をした3Dモニターを眺めていた。モニターにはどこかの森の中で重装備のウォンが歩いているのが映っている。彼の後から何人かの客が緊張した様子で続くのが見える。
アルマはコントローラーでウォンをマークすると彼にささやきかけた。
「ほう? なんじゃ? その馬鹿でかい剣は?」
その声を聞いてウォンが目を見開くと、同じく低い声で答える。
『ああ? 何でてめえがモニターしてるんだよ? 仕事はどうしたよ?』
「たわけ! これが今の妾の仕事じゃ」
『はあ? ギィはどうしたんだ?』
「ギメル殿は今休息を取られておる。その間の代わりじゃ」
それを聞いてウォンもふっとため息をつく。彼もここの状況がどうなっているかはよく知っている。
『あーあ。しょうがねえなあ。じゃあちゃんと見とけよ』
「もちろんじゃ。剣聖殿のお手並みをよ~~く拝見させてもらうのじゃ」
アルマの笑い声にウォンはむっとした顔をする。
『けっ! 見てろよ!』
そう言ってウォンは接続を切った。アルマはまたくくっと笑うと、大きくのびをしてから振り返って部屋の中を見渡した。
ここはその名の通り異界の門の中枢部でもある。だが見てくれはほとんどただの機械室だ。部屋の壁はぎっしりと機械で埋められ、部屋の中にもタワー型の装置が林立している。まるで機械の怪物の腹の中に呑み込まれたようなそんな雰囲気だ。
その間を埋めるように半球形の3Dモニタが幾つも並んでいて、それぞれに異なったゲーム画面が映し出されている。
部屋の隅ではギメルが横になってぐっすり眠っている。無理もない。あの晩から今日で4日目になる。ラーンはあの次の朝から今までずっと不眠不休でベラトリックスの調整を行っている。そのため通常なら交代制で行うシステムのモニタリングはギメル一人の役割になっていたのだ。すなわち彼もまた4日間ほとんど寝ていないのだ。彼がカリス族だからといってそういう状況に耐えられるわけではない。
その時ラーンが中央の大モニタをのぞき込みながら叫んだ。
「ゼナちゃん! どう? どう? 大丈夫?」
モニターの中からゼナの声がする。
『ええ。手足はちゃんと正常に動くわ』
「OK! OK! きゃははははは! これでバッチリ! きゃははははは!」
ラーンは徹夜続きと眠気覚まし――要するに覚醒剤だ――のせいで完全にハイになっている。この時代の覚醒剤は昔と違ってそんなに習慣性があったりはしないが、それでも不健康なことに変わりはない。
それはともかく調整作業はうまくいっているようだ。
「ラーン殿。今度は動いたのかや?」
アルマが尋ねるとラーンはVサインを出しながら答えた。
「ええ。今度はもうバッチリ! ゼナちゃん、もうダンスしなくてオッケーみたいよ! きゃははははは」
「そ、それはよかったのう」
アルマは苦笑いした。先ほどまでの馬鹿騒ぎは横にいたアルマも引いてしまっていた。同時にモニターからもゼナの怒った声がする。
『ラーン! 誰のせいだと思ってるのよ! いい加減にしてよね。で、次は?』
ここでの会話は中でテストプレイしているゼナにも筒抜けだ。
「分かった分かった。分かったわよ。じゃあ今度は顔の表情のテストね。まず笑ってみて」
それを聞いてゼナはモニターの中で笑おうとした……が、その顔は歯をむき出して威嚇しているようにしか見えない。それを見てラーンが爆笑した。
「きゃはははははははは! ゼナちゃん、ゼナちゃん、それ、笑顔ちがう、ちがう! きゃはははははははは」
『私だって分かるわよ! あんたわざとやってないでしょうね』
ゼナの口調は怒っているが、その表情はにやけて鼻の下を伸ばしているようだ。それを見て更にラーンが爆笑する。
今日の朝やっとテストプレイができるようになってからずっとこの調子だ。アルマは何だかゼナが可哀想になったが、これは彼女が口を出せる問題でもない。それにゼナの方も口調は怒っているようだが、その実結構楽しんでいるようにも見える。
アルマがしばらくそんな二人を眺めていた所に、スーチが少し慌てた様子で入ってきた。
「あの、ラーンさん。コネクションできないってミースさんが怒ってらして……」
スーチの言葉にラーンは平然と答える。
「ああ? 切ってるんだから当然でしょ」
「切ってるって、それじゃメールとか何も見てないんですか?」
「当たり前でしょ。そんな暇あるわけないじゃない! きゃはははははは」
「え? それじゃ“黒水晶”にシミュレータを発送する件はどうなってるんですか?」
それを聞いてラーンの顔が凍り付いた。
それからたっぷり10秒間ほど沈黙してから、ラーンは答えた。
「忘れた」
「ああ! もう!」
スーチが少しオーバー目に天を仰ぐ。それを見てラーンも慌ててフォローする。
「あ、でもインストールは済んでるのよ。持ってくだけよ。だから取りに来てもらえば?」
「今日の4時って約束なんですよ。今もう3時だし」
それを聞いてラーンがまた少し固まってから答えた。
「じゃあスーちゃん、ごめん。ちょっと持ってってくれない?」
スーチもその答えは予測していたようで、はあっとため息をついてから答えた。
「わかりました。で、どれですか?」
「あれ」
そう言ってラーンは部屋の隅に鎮座している高さ1メートルほどもある装置を指さした。
「これ一人でですか?」
「んー、じゃあアルマにも手伝ってもらって?」
いきなり振られてアルマは少し驚いた。その作業が嫌なわけではなく、彼女は今別な仕事中だったからだ。
「ええ? 妾は構わんが…じゃがそうすれば、このモニターはどうすればよいのじゃ?」
そう言ってアルマはウォン達の映っているモニターを指さした。だがラーンはまた高笑いして答えた。
「そこの大きいのをたたき起こせばいいのよ。きゃははははは! そうそう。たたき起こしちゃいなさいよ!」
アルマとスーチは顔を見合わせた。ギメルも昨晩は徹夜で今やっと仮眠に入れた所なのだ。だがこうなってしまった以上もう仕方がない。
スーチはギメルの横に行って彼の耳を引っ張った。
「ギィ君、ギィ君!」
「んー」
低くうなるような声がする。アルマはその声がまるで怒っているように聞こえてちょっと身を退いた。だがギメルはそのままふっと起きあがるととろんとした目であたりを見回した。
「ああ? スー、寝過ぎたか?」
「違うの。ちょっとアルマとお使いに行かなきゃならなくなって」
ギメルはそれを聞いて時計を見る。今の時間を知ると彼はがっくりと肩を落としたが、文句は言わなかった。
「うー分かった」
それを聞いてスーチが訊ねる。
「大丈夫? あれあげようか?」
「いや、まだいいよ」
そう言って彼は立ち上がるとぶるぶる体を震わせた。彼はどうやら寝起きはいいようだ。彼に向かってスーチが言った。
「それじゃ黒水晶に運ぶシミュレータを屋上に上げてもらえる?」
それを聞いてギメルが目を見開いた。
「え? まだ運んでなかったのか?」
「ええ。だからあたし達が持ってくの」
それを聞いてさすがのギメルも表情が変わった。
「ラーンさん。そのために僕は夕べ寝られなかったんですよ!」
部屋に響くような低音だ。アルマはまたびっくりして身を引いた。だがラーンは涼しい顔だ。
「ごめんごめーん。あたしだって寝てないんだから。終わったら特別手当あげるから。ね」
「もう。いつもこうなんだから」
ギメルはぶつぶつ言いながらシミュレータの結線をはずし始めた。アルマはかなり驚きながら彼らの振る舞いを眺めていた。この時期、特にルフティ・ベイであれば異種族など珍しいわけではないが、彼女は今まで異種族とこれだけ身近に接したことはなかった。だがここの彼らはまるでヒト族と行動パターンが変わらない。そして彼女は今ではなぜかこの二人と一番和んでいたりするのだ。
もちろんそれは彼らがこのベレンの人間社会の中で生まれ育ったからそうなっているのだが、やはりにわかには信じがたいことだ。
そんなことを考えているとスーチがアルマに言った。
「アルマ、カーゴ呼んどいて。あたしファイル取ってくる」
「その黒水晶というのが行き先で良いのかや?」
「ああ、そうなの。同業さんなのよ。うちと同じでファンタジー専門の。それでいろいろお付き合いがあるの。予約が余った時なんかは回してあげたりして」
「なるほど。承知じゃ」
二人がこれだけ一生懸命働いているというのに、彼女だけがぼっとしているわけにはいかない。アルマは左手の甲に意識を集中させると、その上を右指でピアノを弾くように叩き始める。それと共に手の甲の皮膚上に文字が現れてきた。アルマはそれを確認するとまたリズミカルにその上を叩く。これでカーゴの予約は完了で、あと数分もしたら屋上にやってきてくれるはずだ。
これは別に特別なことではなく、アルマの左手に埋め込まれた“チップ”の機能だ。これはちょっとしたバイオコンピュータで、この当時の人間なら誰もが体内のどこかに入れている。こんな風にネットを操作してみたり、クレジットカードや身分証として使ったりなど様々な機能がある。このあたりの仕組みは1500年間変わっていないので全く迷うことはなかった。
予約が終わるとアルマがギメルに言った。
「ギメル殿。手伝いをしようかや?」
「いや、一人で大丈夫ですよ」
「ふーむ。怪力じゃのう」
「それよりそこのコードを持ってきて下さい」
「了解した」
アルマは落ちているコード類を集めると、ギメルの後を付いて異界の門の屋上に向かった。来てみるともう予約したカーゴスライダーは到着している。
「それ開けて下さい」
アルマは言われるままにカーゴの荷台の扉を開ける。ギメルがそれにシミュレータを積み込んでいると下からスーチも上がってきた。
「ありがとう。ギィ君」
「ああ。でも下ろすときは大丈夫か?」
「アルマがいれば大丈夫だと思うの」
それを聞いてアルマも胸を叩いた。
「任せておれ。新しく付けた腕じゃが、前のよりパワーアップしておってな。この程度なら一人でも運べそうなぐらいなのじゃ」
それを聞いてギメルはうなずいた。
「じゃあ気を付けて」
「行ってきます」
スーチとアルマはカーゴに乗り込んだ。このカーゴは荷物用なので二人乗ると結構狭い。アルマは席に着くと安全ベルトを締める。スーチがパネルに触れて目的地を確認する。
「いい?」
「了解じゃ」
それと共にふっと体の重さがなくなって、カーゴスライダーはふわっと斜め上に向かって浮き上がった。窓の外を見ると地上がどんどん遠ざかっていく。
それから周囲の高い建物の間を抜けていくと街の上空に出た。十分な高度に達すると、スライダー上部の翼が開き滑空を始める。それと同時に重力がまた戻ってくる。このあたりも昔と同じだ。
アルマはカーゴスライダーの窓から眼下の景色を眺めた。
この街はルフティ・ベイという。その名の通り入り組んだ湾の奥にある街だ。ここはテラ連邦の第一植民星である“ベレン”の首都だ。現在テラは地球の他にこの“ベレン”、“トリスタン”、“ジェストコースト”という三つの植民星を持っている。このベレンは植民星の中でも最も古く、ヒト族が初めて地球外に移住したのがここだという由緒ある惑星なのだ。
だがそれも3000年以上前の話である。最初の頃は宇宙開拓の前線基地として賑わっていたこの街も、やがてそんな熱気も薄れていって今ではそれとは別な方面で、すなわちこの銀河のなかでも一二を争う“怪しい”都市として名を馳せていた。
アルマは振り返って後ろを見る。異界の門の建物がどんどん小さくなっていく。
「なあ、スー殿。前から訊こうと思っておったのだが」
「なあに?」
「うちの建物はどうしてあんな毒キノコ型をしておるのじゃ?」
アルマの言ったとおり、NSEゲームセンター“異界の門”は街の中に立った巨大なベニテングタケという様子をしている。
それを聞いてスーチは妙な表情をした。アルマももう彼女が困惑している時にそんな顔をするのに気づいていた。
「そう言えばそうねえ。どうしてかしら」
実はスーチがそう言うのも無理なかった。もしこれが普通の建物群の中にぽつんとそんなキノコがあったのならば、彼女もそんな疑問を抱いたことだろう。だがここはルフティ・ベイだったのだ。異界の門などそれが何かと分かるだけまだましな部類で、それ以外の建物はもっとへんてこな物ばかりだったのだ。
まず異界の門キノコの横にあるのは巨大な石像だ。高さは異界の門の3倍はあって時々姿勢を変えるのだが、その度にぎりぎりとうるさい音を立てて迷惑だ。反対側にあるのは銀色の球体が512個ほどつながった大きな四次元立方体だ。ここも同業だが“大いなる西部”という名前でこちらは古代地球のアメリカ開拓物専門だ。
今はその向こうに古代ギリシャのガレー船がゆっくりと飛んでいる。これはレストランでルフティ・ベイ中をよく分からない経路で移動している。別な方を向くとちょっとした広場になっているが、そこには大きな恐竜が何頭か歩き回っているのがここからでもよく見える。
更に別な方に目を向ければ半透明のきらきら光る何だかよく分からない不定型なものがあって、その側面には大きな丸い穴が空いている。その穴を地下5キロメートルほど下るとおいしい喫茶店があるというのだが、アルマは噂を聞いただけでまだ行ったことがない。
これは現在のルフティ・ベイの極めて一部の実にささやかな光景にしか過ぎなかった。だからここを見慣れた者であれば、ベニテングタケなどごく普通だと思うことだろう。
だがアルマが育った頃は、既にそういう傾向は現れてはいたがまだもう少しはましだった。
「うーむ。妾のいた頃はこうではなかったからのう。建物などもアップタウンにあるものとそうは変わらなんだ」
もちろんベレンにある都市がみんなここのようにイカレているわけではなく、まともな所の方が断然多い。
「そうみたいねえ。こんなになり出したのは500年ぐらい前だって話だし」
スーチの答えを聞きながらアルマは1500年という時間を実感していた。彼女にとってはまるで一瞬だったのに、その間に街は全く見慣れぬ姿に変貌してしまっていたのだ。彼女は元々兄との逃亡生活で各地を転々としていたがために、知りあいがいなくなっていたことにはまだ耐えられていた。だがルフティ・ベイがこんなにも変わってしまったことは少し堪えていたのだ。
そんな彼女の気持ちに気づいたのかスーチは話題を変えた。
「そう言えばあたしが来たときラーンさん何をあんなに騒いでたの?」
「ああ、あれかや? 今ゼナ殿が入ってテストをしておるのだが、まだマッチングがうまくいっておらぬようなのじゃ」
「マッチングがだめって、じゃあ体が変に動いたりとか?」
「そうじゃ。最初は右半身と左半身が逆になっておってな」
「ええ? それじゃ」
「そうじゃ。まるでゼナ殿が妙な踊りを踊っているようにも見えて、ラーン殿が大爆笑しておったのじゃ。それが直ったあと、表情のチェックをしておったのだが、これも滅茶苦茶でまるで福笑いのようになっておってな」
それを聞いてスーチは笑い出した。アルマは少し驚いた。
「ちょっと、スーチ殿、あまり笑い事ではないぞよ」
だがスーチは手を振りながら答えた。
「ごめんなさい。ちょっとあたしの時を思い出しちゃって」
「ええ? スーチ殿が?」
アルマは驚いて尋ねた。
「あたしのスキンを調整するときも最初はそんな調子だったのよ。だってユディ族のスキンってないでしょ?」
それを聞いてアルマも納得した。
「おお! 言われてみればそうじゃったな。と言うことはスー殿も手足が動かんとか、前屈みになろうとしたら反り返ってしまったとかされたのかや?」
「ええ? アルマもそんなことあったの?」
「ああ。妾の時はそもそも今のように出来合のスキンなど無かったから、システムごとにそういう目に会っておったわ」
「まあ、そうなんだ。イオ君とかウォン君なんかに話しても全然理解してくれないのよ。この苦労」
こればかりは体験してみないと分からない。
「うむ。あれは慣れるまでが大変じゃからなあ。にしてもウォンのたわけはともかく、イオ殿まで分かってくれぬとは」
アルマの言葉にスーチが首を振る。
「だって今はUNSF標準でメジャーな種族の基本ドライバはあるから、スキンに困ることなんて普通無いのよ。手足が逆さまに動くみたいな苦労ってもうあたしだけかと思ってたわ」
「UNSF標準? そう言えばあの時ラーン殿も言われておったようじゃが、一体それは何なのじゃ?」
「ああ、これね。ユニバーサル神経信号フォーマットって言ってね、ヒト族とかリリア族とかヴィン族っていったメジャーな種族全部の特徴を持った、仮想的なヒューマノイドの神経パターンなの。NSEシステムをこのUNSFベースで作っておいてね、各種族の実際の神経信号パターンをUNSFにコンバートするドライバを作れば、どんな種族でも簡単に同じゲームに入れるようにできるのよ」
スーチの説明にアルマはしばらく宙を見つめていたが、やがてぽんと手を叩くと言った。
「おお、そういう仕組みであれば、ゲームごとにスキンの調整は不要じゃな。1500年も経てばさすがに進歩しておるのう」
「まあ、ね」
二人がそんな話をしているとカーゴスライダーが高度を下げ始めた。
「行き先が近いのかや?」
「ええ。あそこよ」
スライダーは街から離れて海岸線の上を飛んでいる。アルマが前方に注目すると岩でごつごつとした半島が見えてきた。半島は岸から突きだした岩山といった感じで、その先端部はすとんと切り落とされたような断崖になっている。その崖の中途部分に黒光りする大きな六角形の結晶のような物が突きだしているのが見えた。
「ほう。だから黒水晶というのじゃな」
現在の交通機関はこのカーゴスライダーだったから、建物の立地というのは別に平地にこだわることはなかった。なので特にこういった遊興施設だとわざわざこのような変な場所に造ることは良くあった。
カーゴスライダーはその上の平たくなったエアポートに着陸した。そこでは既に男が一人待ちかまえていた。痩せて背が高く、髪はもう真っ白になっている。
二人がカーゴスライダーから降りると男が言った。
「やあ、スーちゃん。元気そうだね」
そう言って男は気さくな笑みを浮かべた。
「あら、ユーゴさん。お久しぶりです。私が来ること分かってたんですか」
「ああ。ギメル君から聞いてね」
どうやらギメルが気を利かして彼女たちが荷物を届けることを知らせておいてくれたようだ。
「お約束のシミュレータです」
そう言ってスーチがカーゴから降りる。ユーゴはスーチの後から続いて出てきたアルマに目を留めると、ちょっと眉をひそめた。
「あれ? そちらは?」
「ああ、彼女が今度うちで働くことになったアルマです」
それを聞いてユーゴが目を見開いた。どうやらミースあたりから彼女のことを聞いていたのだろう。
「アルマって、もしかしてあの?」
彼女が長い眠りから目覚めたという話はちょっとしたニュースになっていたからこういった反応にはもう慣れていたので、アルマは落ち着いて答えた。
「お初にお目にかかり申す。妾はアルマ・マートルじゃ。この度異界の門にて仕事をさせてもらっておりますのじゃ。お見知りおきたもれ」
といってもまだ現代風の言い方はマスターできていない。その喋りを聞いてユーゴは微笑んだ。
「はは、噂には聞いてたけど本当だったんだ。でもヴィジョンで見るのよりずっと可愛いんじゃない? どうだい? ミースの所は。ラーンにいじめられたりしてないか? 何だったらうちに来ないか? うちはみんな優しいぞ」
いきなりの勧誘にアルマは少したじたじとなった。
「い、いや、とりあえずは結構じゃ。ラーン殿にも、直接には被害にあっておらぬし」
それを聞いてスーチが突っ込んだ。
「あー、被害だなんて、そんなこと言って!」
アルマは慌てて手を振る。
「スー殿。今のは秘密じゃ!」
「どうしようかな~?」
そんな様子を見てユーゴがまた笑った。
「ははは。スーちゃんもずいぶんラーンの奴に感化されてるんじゃないの?」
「え? ええ? そんなことありませんよ」
今度はスーチが慌てて手を振る。黒水晶と異界の門のスタッフはかなり親しい間柄らしい。
「冗談だって。さて、それよりさっさとそいつを搬入しなきゃな」
そう言ってユーゴはシミュレータを指さした。
それから三人はシミュレータを抱えて黒水晶の中に運び込んだ。ギメルだと楽々持てていたように見えたのだが、三人でも結構重い。あの時はアルマはああ言った物の、ユーゴが来てくれて感謝していた。
こういった場合このぐらいのサイズの貨物が一番始末に悪い。もっと大きければ反重力カートをレンタルする気にもなるのだが、このぐらいではそれも大げさすぎる。結局こういった太古からの方法になってしまうのだ。
搬入と設置が終わった時アルマはこぼした。
「うーむ。この辺はもっと楽になっておるかと思っておったが、ぜんぜん前と同じじゃな」
それを聞いてスーチが答える。
「無理なんじゃない? シャルムシステムをもっと小型化できたりしたら、それこそ星が買えるわよ」
「そういうものじゃろうか?」
シャルムシステムとは反重力とか空間転移などを行う基本的な機関なのだが、そのテクノロジーはこの数百万年ほど全く進歩していない。だからちょっとでも改良できたりしたらそれは凄いことなのだ。こういった所はスーチの方が遥かによく勉強している。アルマは曖昧にうなずくしかなかった。
そこにユーゴが戻って来ると言った。
「久しぶりだしお茶でも飲んでくかい?」
「ええ? でも仕事中だし」
スーチが一応断るが、ユーゴはそれを遮って言った。
「仕事、忙しいのかい?」
「いえ、そこまでじゃないんですけど……」
「じゃあいいんじゃないか?」
二人も急ぎの用があったわけではなし、ユーゴも気さくで話しやすいので、そのままなし崩しにお茶をごちそうになることになった。
二人が通されたのは水晶の門のロビーだ。壁面にはびっしりと様々な種類の宝石が埋め込まれていて、それが夕陽に反射してきらきら輝いている。アルマはびっくりしてあたりを見回した。目覚めてからこのかたこういうことばっかりだ。
窓際の海のよく見える席に二人を誘うと、ユーゴが尋ねてきた。
「そう言えばウォンの小僧はどうした? 元気してるか?」
「ええ。すごく」
少々苦笑い気味にスーチが答える。それを聞いてアルマは反射的に答えていた。
「ああ? ユーゴ殿はウォンをご存じなのかや?」
それを聞いてユーゴがアルマを見て答える。
「ご存じも何も、前うちで働いてたんだよ」
アルマは驚いて尋ね返した。
「ほう? して何故にお宅を辞めたのじゃ?……と、聞いて良かったかの?」
「おや、何か気になるかい?」
ユーゴはそう言ってにやっと笑った。
「いや、そういうわけでは」
そう言いながらアルマは少し顔が火照ってきたような気がした。
そんな彼女の様子に気づいたかどうかは分からないが、ユーゴはスーチに尋ねた。
「彼女知らないのかい?」
「え? ええ。まあ……」
スーチが曖昧にうなずく。
「みんな知ってることだからね。喋っちゃっていいかな?」
スーチはちらっとアルマの顔を見て、それからうなずいた。
「ええ? まあいいんじゃないでしょうか」
それを聞いてユーゴはアルマの顔を見た。
「ウォンの奴ね、最初はここでアシスタントしてたのさ」
「ほう? 最初から異界の門ではなかったのじゃ?」
アルマは興味津々だった。表向きはウォンをからかうネタが手にはいるのであればそんな嬉しいことはないと言うふりだったが、その実ウォンのことを詳しく知りたい気になっていたのだ。ユーゴも彼女がこの話題に普通以上に興味が持っていることに気づいていて、説明の言葉に力が入る。
「ああ。あいつがこの業界に入ったのはね、フリーダムバケーションの間ずっとここで潜ってたのがきっかけなのさ」
「ええ?」
アルマの驚きの声を聞いてスーチが付け加えた。
「そうなの。ウォン君と実はイオ君もなんだけど、フリーダムバケーションはずっとここに入り浸ってたんだって」
フリーダムバケーションとはこの時代の習慣なのだが、義務教育期間が終了した若者達に与えられる特別なボーナス期間だ。
学校を卒業した少年少女達には1年間という期間が与えられる。この期間は原則として本人が好きに使っていいことになっている。またそれだけでなくこの期間に限っては本人のしたいことをするための費用を連邦が出してくれるのだ。もちろん無制限にとはいかないがそれでもかなりの金額だし、限度額をオーバーしたとしてもその分は無利子で長期返済できるようになっている。
このボーナス期間をどう利用するか、それは完全に本人の自由裁量に任されている。だから多くの者はまずこの時でしかできないことを考える。
一番多いパターンが宇宙旅行だろう。銀河にはたくさんの星があり文明がある。だがそれを巡るとなるとさすがにかなりの費用がかかるから、そこまで気楽にできる物ではなかった。しかしこの期間であれば自由にそれができるのだ。こうやって様々な異星文化に触れることはもちろん極めて大きな意味を持っている。
だがそれが全てではない。当人が何をするかは誰も強制することはできない。だから中にはずっと自分のしたい研究をする者もいるし、ボランティア活動に勤しむ者もいる。中にはひたすら趣味に打ち込む者もいる。
いずれにしても重要な点はその1年間をどう使うかは本人が決定すると言うことだ。それを後の人生に生かすも殺すも本人次第なのだ。
……とまあこういうシステムになっているのだが、要するにウォンとイオはその期間をずっとゲームして過ごしていたとそういうわけなのだった。
アルマは最初にウォンとイオに紹介された時、ラーンが休暇の過ごし方の話をしたら二人が泡を食ったことを思い出して吹き出した。
そんなアルマを見てユーゴが言った。
「全くバカなんだから。あいつら。でもまあ、おかげでこの道で食ってけてるみたいだからな。全く意味なかったわけでもないようだな」
「ハハハ。そ、そうじゃな。で、それはともかくウォンの奴はどうしてここを辞めてしまったのじゃ?」
「うん。それがなんだが、あいつも最初はみんなと同じようにアシスタントをしてたんだ。最初のうちはまあまじめにやってたんだが、そのうち客の一人とえらく懇意になっちまってな。確かエクアとかいう名前の女だったな」
「ふむふむ」
アルマは身を乗り出した。どうやら面白そうな展開になりそうだ。
「その女なんだが平日の昼間っからずっと入り浸ってたりして、まあなんていうかあまり堅気じゃなかったわけよ。でもあいつのことだからそんな女に見境なくのぼせちまってな、予約を優先してやったりしているぐらいなら良かったんだが、そのうちプレイ代の肩代わりまでしてやったりして。なのにその見返りがデートの約束だけってんだから、もうなんて言うか、な、分かるだろ?」
それを聞いてアルマは吹き出した。
「わっははは。あの男がそんな純情少年だったのかや?」
「はははは。そうなんだよ。でな、そのデートなんだが行ってみたらそこで別な男と鉢合わせしたとかで、大喧嘩になった挙げ句結局ボコられて帰ってきてな、泣いてんだよ。そこで」
そう言ってユーゴはロビーの隅の方を指さした。
「ハハハ……そりゃまた哀れな」
「でさ、俺が問いつめたらあいつ、女の代金肩代わりしてて明日からの生活費もないとか言うし。さすがに俺もこのままじゃまずいと思ってね、ともかくさっさとプレイ代を回収して別れちまえって言ったんだな。で次の日あいつが女の家に行ったらな、今度はそこであいつをボコった男が泣いてたそうだ」
「はあ?」
驚いたアルマににやにや笑いかけながらユーゴが続ける。
「聞けばそいつもその女にずいぶん金を貸してたらしくて。ところがその女と来たらさっさと雲隠れしていなくなってたらしくて。それでウォンの奴、それっきりだったんだ」
「それっきりというと? それっきりかや?」
ユーゴはうなずいた。
「ああ。それっきり帰ってこなかった」
「ハハハ……」
「実はな、その女のゲーム代のつけ、あいつの給料じゃ埋め合わせもできなくなってたんだよ。そんなこんなで思い詰めちまったんだろうな」
「あ、ああ……そうじゃな」
アルマはもう少し軽い話を想像していた。だがこれはからかうネタとしてはちょっと可哀想すぎる……アルマの笑いも少しトーンダウンし始めた。
「でもさ、それじゃこっちもやっぱり困るわけよ。せめて理由でも言ってくれればともかく、いきなり一月以上も無断欠勤されるとね。未払い分は結局損失になるし、契約もあったしで、結局クビにするしかなくってね」
そう言ってユーゴはちょっとため息をついた。
「そ、そうじゃったのか……してどうしてあ奴は異界の門に?」
「ああ、アングラでふらふらしてる所を偶然イオと出会ったらしい」
アングラとはアンダーグラウンドの略でルフティ・ベイの一番怪しい界隈の通称だ。
「イオも最初はウォンと一緒にここで雇ってやろうかと思ってたんだけど、その時ちょっと空きがなくってね。で、異界の門に紹介してやってたんだ。ミースには色々貸しがあるからな。で、まあ後からあいつも謝りに来てね。経緯を知っちまったらこれ以上怒るわけにはいかないしね。でもうちはもう別な奴を雇っちまった後だったんで、結局あいつもミースの所に行くことになったのさ」
「ははは。そうじゃったのか。全くバカじゃのう。あの男は」
と言いつつアルマはもうからかい口調ではなくなっていた。
「それはそうと、その女はどうなったのじゃ? 見つかったのかや?」
「ああ。ラーンが調べてやったら、しっかりコールドスリープ中。あと50年は手が出せないって分かって、ウォンの奴怒り狂ってたよ」
それを聞くとアルマが爆笑した。
「あ! あはははは! そうか、そうじゃったか!」
それを見てユーゴが訝って尋ねる。
「ん? 何がおかしいんだ?」
「いやな、初めて紹介されたときのことじゃ。あの男め、スリーパーがどうとか言っていきなり因縁を付けてきおったので、一発かましてやったのじゃ。おかげでその後はおとなしくなったがの。どういうわけかと思えばそんなことじゃったのか!」
それを聞いてユーゴも吹き出した。
「ぶははは。あいつも多難だな。でもまあそういうわけでさ、あいつバカだけど悪い奴じゃないんだ」
「あははは。それは承知じゃ」
とそんなやりとりをスーチは苦笑いしながら見ていたのだが、ふと手がむずむずしたので自分のチップに目をやると慌てて顔を上げて言った。
「あら! ゼナさんが帰ってこいって。どうしたのかしら?」
それを聞いてアルマも長居しすぎたことに気が付いた。
「ああ? 帰りが遅くて怒っておられるのか?」
二人は顔を見合わせると、弾かれるように立ち上がる。
「それじゃユーゴさん。ごちそうさまでした」
「ああ。また来いよ」
二人はユーゴに挨拶すると大急ぎで黒水晶を後にした。
アルマとスーチが戻って来ると、HQではゼナが戻って来ていて彼女たちを待ち構えていた。
「す、すみません。遅くなって」
スーチが慌てて謝る。アルマもその後ろで同様に頭を下げる。二人はてっきり怒られるのだと思っていた。だがゼナは怒っているというよりは何だかうなだれているように見える。
「あ、二人とも戻った? だったらちょっと話があるのよ」
その口調も怒っている風ではない。二人は少し混乱して顔を見合わせた。
「えっと、あの、何でしょう?」
スーチの問いにゼナは答えた。
「実はね、あたしちょっと本番に行けなくなっちゃったのよ」
「本番に行けないって、ベラトリックスにですか?」
「ええ。そうなの」
それは二人とも全く予想だにしていなかった話だった。
「それって一体、どうしてなんですか?」
スーチが驚いて尋ねるとゼナがため息をつきながら言った。
「それが何かね、急に市長が割り込んできたのよ。明後日から」
「ええ? そんな!」
「なんじゃと? 市長じゃと?」
それを聞いてアルマが割り込むと、ゼナが答えた。
「ええ。そうなの。うちのお得意さんで、ちょっとむげにはできないのよ」
「でもゼナさんが一緒に行く必要があるんですか? 市長さんて凄く上手でしょ?」
スーチの問いにゼナは首を振る。
「それが今度は“ハンド・オブ・グローリー”に挑戦したいって言うのよ。それでぜひあたしにガイドして欲しいって……」
「ええ? でも……」
「普段ならこんなおいしい話はないんだけど、どうしてピンポイントにかぶってくるかしら」
そう言ってゼナはまたため息をついた。
「やっぱり抜けられませんよね?」
「市長には色々口聞いてもらってるし……それにあたしが抜けたら市長の相手誰がやる? スーちゃんやってみる?」
スーチは慌てた様子でぶるぶる首を振った。
「そんな! ハンド・オブ・グローリーって、この間一緒に行ってあたし全然だめだったじゃないですか。盗賊物であれより難しいのなんてあるんですか? そんなののガイドなんて無理です。相手は市長さんなんでしょ?」
それを聞いてゼナはうなずいた。彼女も本気でスーチにやらせようとは思っていなかったようだ。
「そうなのよ。で、アルマ、相談なんだけど」
いきなり話を振られてアルマはびくっとしてゼナの方を見た。
「え? 何じゃろう?」
「ローウェルタウンに行くのに、スーちゃんじゃやっぱり難しいと思う?」
「え?」
アルマはちょっと考え込んだ。だが横のスーチがゼナに言う。
「え? あたしが行けるんですか?」
そう言ってスーチがゼナにすり寄った。彼女の目が何か期待で輝いている。それを押しとどめながらゼナが言った。
「それはアルマに聞いてみないと」
「ねえ、どう?」
今度はスーチがアルマににじり寄ってくる。何だかそんな様子は子犬が尻尾を振ってじゃれついてくる所を思わせる。彼女が心底ゲーム好きなことはこの短いつき合いでも明らかだ。
アルマは考えた。ローウェルタウンに行くのは決して簡単なことではないが、スーチもまた素人ではないはずだ。それにベラトリックスであれば彼女の庭のようなものだ。いくらでもフォローのしようはあるだろう。そう思ってアルマは答えた。
「うむ。多分問題ないと思う。あの方面はどちらかと言えば盗賊より戦士の方がきついしの」
それを聞いてスーチの目がきらきら輝いた。
「いいんですか? いいんですか?」
それを見てゼナが言った。
「このゲームを一番知ってるアルマがそう言うんだから大丈夫なんじゃない?」
「余裕は3日もあるし、無理せず行けば大丈夫だと思うのじゃ」
「きゃあ! ありがとう!」
そう言ってスーチはついにアルマに抱きついて頬をすり寄せてきた。彼女は人間と違って体中が柔らかな毛で覆われていてふわふわして心地よい……というのはともかく、アルマはスーチの喜びように少々驚いていた。
「それじゃその前にあなたのスキンを調整しないと。急だけど今から入ってもらえる?」
ゼナの言葉にスーチは元気よく答える。
「もちろんです。分かりました。ブースは何番ですか?」
「六番があたしの使ってた所よ」
「はい!」
そう言ってスーチは駆け出した。だがドアのところまで走ると、急に立ち止まって振り返った。
「あ! それじゃ受付どうしましょう?」
それを聞いてゼナがちょっと考えてから答えた。
「ああ、そうね。じゃあアルマ、ちょっとお願いできる?」
それを聞いてアルマが少し戸惑いながら言った。
「え? 妾でよいのか? まだその、ほら喋り方がこんな調子で」
彼女はここに来てまだ日が浅く、まだ内部の雑用しかしていない。受付に本格的に座るのはこれが初めてになるのだが……だが他に代われる者もいなかった。
「予約はしばらく入ってないし、もう少ししたらイオ君達も出てくると思うから」
ゼナの言葉にアルマはうなずいた。
アルマは彼らと別れると、異界の門の受付フロアに下って、ブースの中に座った。キノコの根元の壺に相当する部分だ。
だが彼女は落ち着かなかった。受付のやり方はこの間教わったから一応理解しているはずだが、彼女はまだ一人で長時間その仕事をこなしたことはなかった。それに彼女は今までこの類の仕事をしたこともなかった。そのことを思い起こすと何だか急に心配になってくる。
《客が来たらどうすれば良かったのじゃ?》
アルマはその場合の手順を頭の中で復習したが、やればやるほど失敗しそうで不安になってくる。
だがゼナの言ったとおり予約はしばらく入ってなかったので、誰もやって来なかった。異界の門は完全予約制なので、受付とは予約客を確認して誘導するのがメインの仕事で、フリーの客の相手をするようなことは意外に少なかったのだ。そのうち彼女は段々退屈になってきた。
「ふうむ」
アルマはブースの中でため息をついた。時計を見るともうそろそろ終わりの時間だ。結局待っている間誰も来なかった。そう思うと緊張していたのが馬鹿らしくなって来る。
《これなら別に妾が待っておらなくとも良いのではないか?》
アルマがそう思った時だった。入り口から誰かが入ってくる気配がする。
《全く! そう思った途端にこれじゃ!》
アルマは慌てて顔を上げる。
そしてそのまま彼女は驚きのあまり凍り付いてしまった。来たのが普通の人だったとしても上手くできたか疑わしいというのに、この客人はとんでもなかった。
最初その姿は背の高い金髪の女性に見えた。だが頭の上に飛び出した大きな耳がそのシルエットに特徴を付けている。その体は上半身は白く、腰から下は黄金色の柔毛で覆われている。そしてヒト族では絶対あり得ない長い尻尾が歩くたびにゆらゆらと揺れている。
アルマは緊張の余り全く声が出せなかった。
「……」
その女性の一挙一動が全て完璧だった。彼女はただ歩いて入ってきただけなのに、その瞬間にこの空間全てを支配したかのようだった。
固まっているアルマにその女性は話しかけた。
「イオはいますか?」
その声にうっとり聞き惚れないようにするには最大限の努力が必要だった。
アルマは慌てて答えた。
「は? イオといえばその、イオ・クロウリーでございましょうか?」
「はい。そうです」
アルマはがくがくとうなずくと、震える手でイオを呼び出そうとする。だが焦って何度もしくじってしまった。
ヴィジョンの先にイオがやっと映ったとき、アルマは心底ほっとした。
「イ、イオ殿、お、お客様なのじゃ」
アルマがしどろもどろなのを見て多分イオは状況を察したのだろう。
『え? ああ、わかった。すぐ行くよ』
イオは軽くうなずいて、すぐに接続が切れる。顔を上げるとその女性がアルマを見つめていた。アルマは完全に上がってしまった。
「す、すぐに来られるとそう言っておるのじゃ」
その様子を見て女性はくすっと笑みを浮かべる。
「もしかしてアルマさんですか?」
いきなり名前を呼ばれてアルマは更に顔に血が上る。
「え? は、はい、でございます」
「あなたのことはイオから聞いてますわ。ウォンさんと同じぐらい強いそうですね」
「え? は、その、どうもかたじけない、でございます」
「スーチさんは今日はどうしたんですか?」
「え? は、はい。ちょっとスキンの調整にて潜っておるでございます。ベラトリックスに共に入ることになったゆえ」
それを聞いて女性がちょっと驚いた表情をした。
「え? 彼女が?」
「は、はいでござりまする。なんと市長が割り込んで来やがって下さいまして」
それを聞いてその女性は声を上げて笑った。アルマはもう目の前がぼうっとしてきた。このままでは脳がオーバーヒートしてしまう、と思ったときやっとイオがやってきた。
「あ、ティルナ、待った?」
イオは全く自然にティルナと呼ばれた女性に話しかける。
「いえ。全然」
彼女も同様に全く自然に答える。
「じゃ行こうか」
「ええ」
それからティルナはもう一度アルマに微笑みかけると、そのままイオと連れだって行ってしまった。
アルマは呆然としてその後ろ姿を見送った。頭の中は真っ白だ。そのせいで後ろからウォンがやってきていたことには全く気が付かなかった。
「おい!」
「うわああああ!」
そのあまりの反応に脅かしたウォンの方がびっくりして飛び下がる。
「な、なんだよ」
振り返ったアルマはたっぷり5秒ほど口をぱくぱくさせてから、やにわに叫びだした。
「ゼノス族じゃ! ゼノス族じゃ! ゼノス族じゃ! ゼノス族じゃ!!」
「いや、だからそのさ」
「ゼノス族じゃ! ゼノス族じゃ! なんとこんな間近でゼノス族を見てしもうた! ほとんど触れそうじゃった! こ、こんなことは生まれて初めてじゃ」
アルマがパニックになってしまったのも無理はない。ゼノス族とは現在の銀河で最も尊敬されている種族だったからだ。
まず彼らは非常に美しい種族だった。だがもちろんそれだけが彼らに対する崇敬の理由ではない。彼らがそうされるのは、彼らが今現在銀河文明で最も古い歴史を誇ることによる。
例えばヒト族は銀河に進出してからまだ3000年ちょっとしか経っていない新参だが、ゼノスは少なくとも15000年以上の歴史を誇る。それだけでなく、地球人がエジプトやメソポタミアなど最初の文明を築けたのは、実は彼らがやってきて指導していたからだったのだ。あの当時の神話に出てくる様々な神は、実はこのゼノス族とかマメン族―――彼らはケンタウロス型をしていた―――の姿を映した物だったのだ。彼らがそういった活動をしてくれていなければ人類はまだ地球の上で原始生活を送っていたのは間違いないとされている。
すなわち地球人にとって彼らはまごうことなき“神”だったのだ。それだけでなく、例えばリリアとかヴィンといった他の銀河文明も同様に皆、文明化の際にはゼノスによる初期教化活動があったことが分かっている。
要するに彼らは現在の銀河における大長老にあたる種族だったのだ。
……と言ったわけでアルマは舞い上がってしまったのだが、ウォンの方はあまりそんな感慨は抱いていないようだった。
「あ、そうかい。そりゃ良かったな。でさ、ちょっと言いたいんだけどさ……」
ウォンが何か言おうとするのをアルマは遮って尋ねる。
「なあ、あの方は一体どなたなのじゃ?」
「彼女はティルナっていって、エボカシオンでダンサーをしてんのさ」
「なに? エボカシオン? それはどこじゃ?」
アルマは真剣な表情でウォンに尋ねる。これも無理もない。なぜならゼノス族は宇宙一の踊り手として知られているのだ。
「こっからちょっと北に行ったとこにあるよ。でさあ……」
「いつ出演なさるのじゃ? ゼノスの舞をナマで見られるのかや?」
ウォンはなかなか言いたいことを言わせてもらえない。
「ああ。見たきゃイオに言えばチケットは手にはいるぜ」
「おお? ほ、本当かや?」
「嘘なんか言わねえって」
それを聞いてアルマが不思議そうな表情になった。
「して、どうしてイオ殿がティルナ殿と行ってしまったのじゃ?」
その問いにウォンはあからさまにむっとした表情をした。
「どうしたのじゃ?」
アルマは無邪気にウォンに尋ねる。ウォンは渋々答えた。
「どうしてって、要するにイオのこれだからさ」
そう言ってウォンは小指を立てた。
「はああ?」
アルマは信じられないといった表情でウォンを見返す。
「だからイオの恋人なんだよ。ティルナさんは」
それを聞いてアルマも大口を開けたまま絶句してしまった。おかげでウォンはやっと彼女に言いたかったことを言うことができた。
「だからここじゃゼノスなんて全然珍しくないんだよ。それよりおい、お前俺のモニターしてたんじゃねえのかよ?」
そう。ウォンはあれからアルマにいい所を見せてやろうと、思いっきり無理をしていたのだ。わざわざ難しいコースを通り、敵のレベルまで調整して最高の見せ場を用意したのだ。ところがもちろんその最高にかっこいい場面で彼に答えてくれたのはアルマではなく眠そうな声をしたギメルだった。
「せっかく俺が必殺のテクを見せてやろうって、おい!」
だがアルマは全然聞いていなかった。
「はあ……美しかったのう」
惚けた表情でアルマがつぶやく。
「おい、聞いてるのかよ?」
「どうすればあんなに綺麗になれるのじゃろう?」
「はあ? 何を世迷い事を。DNAレベルで問題外だろ!」
それを聞いてさすがにアルマもウォンを睨んだ。
「なんじゃと? 言うに事欠いて」
「プ! まさかお前本気でティルナさんに張り合おうってか? 寝言は寝て言えって……うご!」
ウォンの叫びはもちろんアルマに一撃食らったからに他ならない。
「何じゃ! せっかく人がおのれに慰めの言葉でもかけてやろうと思っておったのに」
アルマの言葉にウォンも言い返す。
「何で俺がお前に慰められなきゃならないんだよ!」
「だからユーゴ殿におのれの哀れな過去を聞いたからじゃ」
そう言った瞬間さすがのアルマも手で口を押さえて凍り付いた。
二人は絶句して見つめ合う。
一番痛い心の傷を突かれて、ウォンはかっと怒りがこみ上げてきた。
だがそれよりもアルマの逆ギレの方が早かった。
「なんじゃ! おのれは! 悪かったな! どうせ妾はスッポンじゃ! ティルナ殿のように綺麗になどなれぬのじゃ!」
そう言ってアルマは駆け去っていく。その後ろ姿を見てウォンの怒りは瞬時に消えてしまった。
《え? またやっちまったか?》
ウォンの心の中がなぜか後悔で一杯になる……よく考えてみれば怒るべきなのは彼の方だったのだが。