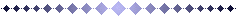第5章 ベラトリックス
それから更に3日が経った。
HQの中央にある大モニターには、相変わらずラーンが張り付いて内部を一心に覗いている。その周囲には様々な機械のコードや部品、それに1週間分の食べ物のかすなどが散らかり、まるで光り物の好きな大鴉の巣のようになっている。
「どう? 調子は」
ラーンの背後からゼナが心配そうに尋ねる。
「もうカンペキよ! ほら、ほら」
モニターの中では緊張した面もちの四人、すなわちアルマ、スーチ、イオ、ウォンが一列になって歩いているのが見える。彼らはちょうど街の門を出ていくところだ。アルマは剣士、スーチが盗賊、イオが魔導師、そしてウォンが僧侶の格好をしている。今回のパーティーはすったもんだの挙げ句こういった構成に収まっていたのだ。
あれからちょうど1週間。ラーンの言葉に偽りはなかった。彼女はほとんど一睡もせずに働いて、ベラトリックスをインストールしてスキンの調整も完璧に終わらせたのだ。その腕前はゼナも再認識せざるを得なかった。
「まったく、こんな時になんで市長が遊んでるのかしら」
ゼナはいまだにぼやいている。
「おーっほっほ! ゼナちゃん人気者だから! お客様は大切にしなきゃだめよ!」
ラーンはあれから更に3日分の徹夜と覚醒剤でハイを通り越して躁状態になっている。部屋の隅のソファの上ではギメルが完全にのびている。
「そのお客様のためにそろそろ行かなきゃならないんだけど、アルマは大丈夫?」
「今のところはね。でもまだ始まったばかりだけど」
ゼナはまた大きくため息をついた。今回のメンバーはやはりどうも不安だ。
「まあアルマちゃん、結構しっかりしてるみたいよ」
「だといいんだけど」
ベラトリックスというゲームはその名前は有名だといっても、さすがに現在稼働している所はない。従って今ベレンにいる者でアルマ以外の経験者は一人もいない。こういう場合最も経験のある者がリーダーになるのは当然なのだが……
「ウォンは?」
「今のところ口げんかを二回ぐらいしただけね。両方ともスーちゃんが仲裁してたけど」
ゼナはまたため息をついた。
「イオとスーで手に負えなくなったら遠慮なく雷落としていいわよ」
「それがね、このモニターシステム、古いからそこまで介入できないのよね」
ゼナはまたまたため息をついた。
「ゼナちゃ~ん、心配しててもしょうがないわよ。あの子達を信じてやりなさ~い! あっははは」
「あなた、今幸せでしょう?」
「だってこんなにおもしろかったこと久しぶりだもの。ゼナちゃんに一番乗りさせてあげたじゃない!」
「分かったわよ。ともかく後をよろしくお願いね」
「OK! OK! きゃはははは!」
意味もなく笑い転げているラーンを残してHQを後にしながらゼナは思った。
《まったくラーン! あなたの方がもっと心配なんだけど》
パーティーの経験が足りないことは想定の範囲内だ。たとえ彼女が付いていった所で、ベラトリックスというシステムでは初心者の一人でしかない。だから問題があったときは外部からの補佐が重要になるのだが、その外部モニターが今のラーンというのも不安要素の一つだった。せめて誰か他の者がモニターできればまだ違うのだろうが。しかしミースもエイドリアンも他に頼れそうな者は今回のどさくさで多忙を極めており、ここにずっと詰めることなど論外だ。
後から考えればこの時市長を放り出してでもゼナが残っておくべきだったのだが……現実世界というシステムはなかなか優れ物なのだが、リロードが効かないという欠点があった。
急造パーティーは最初から前途多難だった。彼らは今戦闘を一つ終わらせたばかりなのだが、ウォンとイオはそれだけで疲れて座り込んでいた。
「こら! ウォン! かようなザコ相手に何じゃ? そのざまは!」
「うるせえな、勝手が違うんだからしょうがねえだろう! なんでこのメイスはこんなに重ってえんだよ!」
「メイスなんじゃから当たり前じゃろうが!」
このベラトリックスという1500年前のシステムは、現在のシステムの基礎になっているだけあって、様々な点でなじみのある仕組みになっていた。だが反面やはり同じぐらい多くの点で現在のシステムと異なっている。
ウォン達にとって最も苦労なのが、このゲーム内の法則が必要以上に“リアル”である点に尽きた。
例えば武器の重さだ。ここの武器を基準に考えれば、アルマが以前武器が軽いと言っていたのは当然のことだ。だが実際の重さにはこちらの方が近いのだ。
「大体な、これでも2割ほどは軽くなっておるのじゃ。贅沢を申すでない!」
「ともかくちょっと休ませろよ。このままじゃ身が持たないぜ」
「そのような物をぶんぶん振り回せば疲れて当然じゃ」
また大きな違いはこのゲームでは疲労度がかなりシビアに設定されていることだった。現在のゲームではテンポ良く進められるように、少々暴れ回ったぐらいでは疲れないようになっている。だがこの世界ではそうではなかった。そのため重たいメイスを思い切り振り回していたウォンはあっという間にへとへとになってしまったのだ。
「それにしても結構これはきついよな。ちょっとやり方考えないとまずいぞ」
同じく息を切らしながらイオが言った。イオの場合は魔導師なので直接戦闘はしなかったが、簡単な魔法をいくつか使っただけで精神力が尽き果ててしまったのだ。
「魔導師はな、精神集中が大事なのじゃ。集中力が高ければ高いほど魔法の効力も上がるのじゃ」
「集中力っていったいどうするんだ?」
「妾はあまり魔導師はしたことがない故詳しいことは言えぬが、カイの言うことには脳波やら何やらをモニターして、雑念のないときに破壊力が上がると言うておった」
それを聞いてイオは天を仰いだ。
「そんな所を見てるのか? それって滅茶苦茶難しくないか?」
「そうかや? じゃが妾と共に潜っておったオブルは上手じゃったぞ。彼が言うには誰でも練習すればうまくなると言うておった」
「そんなものかね?」
「オブルが言うには、まず明かりを灯す魔法で練習するのが良いと言っておったぞ。これならば効果が目に見えて分かるし、それができれば他にも応用はすぐできるとな」
「ふーむ。まずやってみるしかないかな」
まだしばらくウォンがここを発てそうもないので、イオは言われたとおり明かりを灯す練習をしてみる。確かにちょっと慣れてくると前より少し明るくなるようだ。
「ふむ、まだまだじゃが、その調子ならすぐに上達しそうじゃ」
そう言ってアルマはまだ荒い息をしているウォンを見下した。
「それにしてもおのれはだらしのない。スー殿を見てみよ。ぴんぴんしておるではないか。彼女を見習うがよいぞ」
ウォンがわめき出す前にスーチが言う。
「あの、アルマ、あたしあんまり参加しなかったから……」
「そのようなことはないぞ。スー殿も一人倒したではないか。見たところ盗賊が板についておるようじゃが、それが好みなのかや?」
「あたしのって言うより、ゼナさんの好みなのよ。マンツーマンでしっかり訓練されたから……」
「ほう? ゼナ殿が盗賊じゃと?」
「そうなの。女盗賊シャルカ様って言ったら、その筋じゃスターだったのよ」
「シャルカ?」
「ああ、字名ね。メガマルチのゲームでは特別なハンドルネームがあって、選ばれた人しか名乗れないの。これを持ってる人はトップクラスなのよ」
「メガマルチとは?」
「ああ、一度に何万人も入れるゲームのことよ。ネバーランドなんかが有名だけど。それだけ人が入ってると、そこでトップを取るのはとても大変なのよ。だから字名っていうのはそういう人たちのための名誉の証なの。ミースさんは闇のジシュカだし、ラーンさんは暴風魔導師リブシェだし、エイドリアンさんは無抵抗のヴァーツラフなのよ」
「ほう。スー殿は持たぬのかや?」
スーチは慌てて手を振る。
「とんでもない! イオ君やウォン君も持ってないのに」
それを聞いてアルマはウォンの方をちらっと見た。
「ほう? じゃがあの男は剣聖ではなかったかえ?」
「剣聖みたいな称号は条件さえ満たせば誰でももらえるのよ。もちろんそれはそれでとっても難しいけど。でも字名をもらうのはもっともっと難しいの」
「ふーむ。それにしても一時にそれだけ入れるシステムがあるとは、あの頃とはマシンパワーが段違いなのであろうな……」
アルマとスーチがそんなことを話しているうちに、ようやくウォンとイオの体力が回復した。
「アルマ、そろそろ行けるよ」
イオの言葉にアルマがウォンを見ながら言う。
「そちらの男はどうなっておる?」
「ああ? 俺も大丈夫だぜ」
「じゃあ行く?」
そう言ってスーチが立ち上ろうとする。だがアルマはそれを制して言った。
「その前に少し戦い方を指南してやる必要がありそうじゃな」
「え? 本当? アルマが教えてくれるの?」
「スー殿は今のままで十分じゃ。問題なのはおのれじゃ」
そう言ってアルマはウォンを睨んだ。
「なんだと? 俺の戦い方が下手とでも言うのか?」
「どこをどうやったらそんな世迷い言がほざけるのじゃ! おのれがくたばってしもうたら、パーティーがどれほど危険になるか分かっておるのか?」
アルマは胸ぐらを掴まんばかりの剣幕でウォンに詰め寄った。またウォンがわめき出しそうになるところにイオが割って入る。
「まあまあ、ウォンはいつも通りに勢いで言ってるだけだよ。実際こんなに簡単にヘロヘロになっちゃまずいよな」
「……」
その事実を一番感じていたのはウォン自身であったから、それ以上何も言えなかった。むっとしたウォンの顔を見てアルマは言った。
「まあ、おのれは筋は悪くないのでな、ちょっとこつを掴めばすぐ慣れよう」
「そりゃどうも。で、どうするんだよ。精神集中でもするのか?」
「まあそれもあるがな、まずはそれ以前じゃ。そのメイスを貸してみい」
そう言ってアルマはウォンからメイスを受け取ると、大きく上段に構えた。
「このように構えてな」
「ああ」
ウォンはアルマの一挙一動を見逃すまいと目を見開いた。だが彼女はそのままメイスを振り下ろしただけだった。
「こうして一気に打ち下ろすのじゃ。これならば武器の重さも相まって、このあたりのザコであれば一撃で吹っ飛ばせよう」
そのあまりにも当たり前の説明に、ウォンはしばらく言葉が返せなかった。
「そ、それだけかよ?」
「ああ、それだけじゃ」
「そんなんで外したらどうするんだよ」
「その場合は死ぬのじゃ。故に外さぬように打て」
「お前、簡単に言うけどな……」
「ああ? 敵の動きをよく見れば、タイミングなどすぐ分かるはずじゃ。分からぬ時はまずは相手の攻撃をひたすら受け流せ。さすればどう来るかは分かるようになるし、それで突っ込まれるような相手であれば、さっさと逃げた方が身のためじゃ」
それを聞いてスーチが言った。
「あら? それってあたしもよく言われるわ。ゼナさんは口を酸っぱくして、相手の動きを読めって言うのよ。盗賊のような非力なキャラの場合はそうしないと生き残れないって」
「盗賊に限らず接近戦をする者にとっては当然のことではないのかや?」
それを聞いていたウォンが怒ったような声で言う。
「あのなあ、動きを読むなんて当たりめえだろう? 人を馬鹿にしてんのか? 俺がそうしてないとでも言うのかよ!」
「だったらどうしてそんなに下手なのじゃ!」
二人がまた口論になりそうな所でイオが割ってはいる。
「ちょっと待った、なんか分かったような気がするぞ」
三人はイオの方を見た。
「何が分かったんだよ」
「この間お前らがファイナルブレードでバッサバサ斬りまくってたじゃない。外からみてたんだけどな。お前とアルマが同じ戦士でも何か違うよなって思ってたんだよ」
「当然じゃ。このような者と一緒にするでない」
「あんだと?」
それを聞いてわめきだそうとするウォンを押さえながらイオは続けた。
「まあまあ、それはともかく置いといて、ウォン、別にお前が動きを読むのが下手な訳じゃないんだよ。それどころが、何て言うかすごく効率よく戦ってるんだよな。例えば一人やっつけたら返す刀で別な奴がやれるようにって、そういうことまで考えてるだろ?」
「当たり前じゃん」
「でもアルマの場合は一人一人を着実にやっつけてるんだ。だから敵をやっつけるスピードではお前が勝ってたんだけど……でもそれってお前の剣が良く切れるからこそできる芸当だよな」
それを聞いてアルマが付け加える。
「そうじゃ。イオ殿の言う通りじゃ。おのれは良い剣を使いすぎじゃ。あんなに軽くて切れ味の良い剣に慣れておるから、こういった普通の武器で困るのじゃ。ああいう剣であればただ相手の体に当てさえすれば良いのじゃが、このような武器ではそうはいかぬ。特に下から薙ぎ上げてもほとんどダメージは与えられぬわ」
言われてみるとウォンも納得できる話だった。戦闘になるともう自動的に体が動いてしまうので気づいていなかったが、確かにウォンは重いメイスを持ってそのような戦い方をしていたのだ。確かに一見獅子奮迅という様相だったのだが、ザコ相手にやっていたのでは身が持たないのも事実だ。
「じゃあ何か? あんなザコどもを一匹ずつ、ぷちぷちやってけってのか? ダセエぞ!」
「がたがた申すな! あんな戦い方はグラムかエクスカリバーを得た者のみに許されるのじゃ」
それからまた二人の口論が始まってしまったので、出発はもう少し遅らせなければならなかった。
それからしばらくして一行は薄暗い森の中をかき分けながら進んでいた。
「ここ何も出ないのよねえ?」
スーチが心配そうに言う。
「大丈夫じゃ。外を通った方が遙かに剣呑じゃ」
一行がこのようなところを通っている理由の第一は、なるべく敵が少ないルートを採る必要があったからだ。普段なら特にウォンは絶対そんなことは拒否しただろう。だが今回はそうもいかなかった。
先ほどのアルマの指示は結果的にかなり効果的だった。またウォンやイオは一応このタイプのゲームのプロだという意地もある。2回目以降の戦いは1回目に比べて遙かにましになったと言って良い。だがましだとは言ってもそれは比較の問題で、いつもに比べたらど素人レベルだ。敵を蹴散らしていくことなどほぼ不可能と言って良い。
それにそもそも今回プレイしている理由は、アルマがカイからのメッセージを聞くためにローウェルタウンまで行くためである。こんな所のザコ戦で時間の浪費をしているわけにはいかない。
そして理由の第二は森の先に絶対行かなければならない場所があったからだ。
ローウェルタウンに行くためにはかなり強力な怪物達がうろついている場所を通り抜ける必要があった。そういった場合、普通ならゲームのレベルを落としたりすることで対応できたのだろうが、こんな古いシステムにそんな便利な物はついていなかった。いやあったのかも知れないが、少なくともラーンの解析はそこまでは及んでいなかった。
そこで彼らは仕方なく一から始めるしかなかった。そして手っ取り早くそんな怪物達とやり合えるぐらいに強くならなければならなかったのだ。
そのために作戦会議の時にこのようなやりとりがあった―――
「妾はベラトリックの中のことであればよく知っておるが故、ローウェルに行くだけであれば、急げば1日はかからんと思うぞよ」
「そんなに短時間で固有レベルが上げられるの? ここって相当敵のレベルが高い所でしょ?」
それに対してゼナが質問した。この時はまだゼナが行く予定だった。
「効率の良い上げ方があるのじゃ。最初の街の周辺では得られる経験点もたかが知れておる。だからさっさと隣の大陸に渡ってしまうのが良いのじゃ」
「そんなところにいきなり行って大丈夫なの?」
「腕さえ良ければ何とかなる強さじゃ。そこな男はそれしか取り柄がないじゃろう?」
「お前の言い方いちいち引っかかるんだよ」
このキャラクターに固有レベルがあるという考え方も、最近のゲームでは珍しい物だった。NSEの場合レベルとは一般にプレーヤー本人の実際のスキルのことを指す。だがこういう初期のゲームの場合はもっと古いゲームのシステムを引きずっていて、本人のスキルとは別に“固有レベル”という物が設定されている場合もある。
具体的には固有レベルが低いと動きが制限されたり相対的に敵の動きや攻撃力が高くなったりで“弱さ”を演出する仕組みが大半だ。この固有レベルは敵をたくさん倒していけば段々上がっていく。言い換えるとどんな下手な人間でもやっていれば必ず強くなれるわけだ。
だが最近のシステムの場合、ショートシナリオが主流であることもあって、そういうややこしい仕組みは忌避される傾向にあった。そのためウォン達は固有レベルの付いたゲームはほとんどやったことがなかったのだ。
「分かったわ。それじゃアルマ、その短時間でレベルが上げられるってルートについて、もっと詳しく教えて」
「もちろんじゃ。まず最初の街で装備を調えるのじゃが……」
―――今彼らが目指す場所はそのときアルマが説明したルートの最初の鍵となる地点だった。
トップを歩いていたアルマが止まれという合図をした。見ると森が切れてその向こうに堀立て小屋が見える。スーチがそこをじっと観察しながら言う。
「あそこが野党の根城なの?」
「そうじゃ。この時間は手下どもは街道の方に稼ぎに行っておるので根城は手薄じゃ」
「でも見張りが立ってるわよ。こんな開けた所じゃすぐ見つかっちゃうわ。夜まで待つの?」
「そんなことをすれば手下が戻ってきてしまう。しばらく待つだけでよいのじゃ。必ず夕立が降るのでな」
「ええ? 本当に?」
そう言ってスーチは空を見上げる。確かに暑いがいい天気だ。半信半疑ながらも夕立が来たときに襲撃する手順について一行は相談した。
しかししばらく待っていると本当にアルマの言った通り、にわかに空が暗くなって雷鳴が轟いてきた。
「もうすぐ土砂降りになるぞよ。その時には示し合わせた通りに頼むぞよ」
一行はうなずいた。さすがにウォンもこういうときにアルマをからかうほどバカではない。
凄まじい雷鳴と共に、一気に大粒の雨が降り始めた。
「それ、行くぞ!」
それと共にアルマが飛び出した。一行もそれに続く。
見張りは雨に気を取られていて、最後の瞬間まで迫ってくるアルマ達に気がつかなかった。気配にやっと気づいた見張りは、振り返った瞬間にスーチによって喉笛を切り裂かれていた。
一行はそのまま小屋に突っ走る。アルマが小屋にたどり着くと中を窺いながらイオにサインを出す。イオはおもむろに扉を蹴破った。
小屋の中には数名の野党とボスとおぼしき大男がいる。イオは挨拶も抜きに部屋の中にファイヤーボルトを打ち込みまくった。敵を傷つけるためというより、部屋の中の可燃物に火を付けるためだ。
野党達は突然の襲撃に混乱を来し、燃え上がった小屋から脱出できてまともな迎撃体制を取れたのはボスと子分が二人だけだった。作戦は見事に成功したと言って良いだろう。
「よっしゃ! いただき!」
ウォンに限らずみんなそういう気分だった。しかしそれにも関わらず以降は想像もしなかった苦戦となった。
雨の中の戦いは予想以上にやりにくかった。だがさすがにそのぐらいは想定の範囲内だ。最初のミスは、ウォンとスーチが同時に一人の子分を攻撃してしまったことだった。その瞬間フリーになったもう一人の子分が、魔力の切れたイオに襲いかかったのだ。
またイオもここで逃げていれば良かったのだが、ついうっかり応戦してしまった。いつもなら何とかできたかもしれないが、このゲームはそんなに甘いものではなかった。
「うわあ!」
イオは攻撃を避けきれずかなりの深手を負った。それを見て慌ててしまったスーチとウォンは、二人掛かりなのに相手を倒し損なってしまった。
その間アルマはボスにかかりっきりだった。いかなアルマであってもこのレベルで一対一では防戦一方だ。
またそれに輪をかけるようにウォンはイオを助けに走ってしまった。冷静に考えればこの際見殺しにしていた方がまだ良かったのだ。もう一発食らってイオが昏倒しても、そのまま即死するわけではないし、傷を治したからといってこの状況でイオが役に立つわけではない。
「やーん!」
ウォンが離脱したためスーチが今度は手下と一対一になり、一気に押し込まれてしまう。
「何をしておるのじゃ!」
だがアルマは助けに行ける状況ではない。ウォンもやっと状況を把握し、再びスーチを助けに行く。その途端イオを狙っていた子分がウォンに後ろから襲いかかる。
「危ない!」
その子分に対してイオが捨て身のタックルをしたおかげで、ウォンは致命傷を食うことはなかったが、今度はスーチが支えきれなかった。
「きゃあああ!」
「スー殿! うわあああ」
スーチがやられるのを見て焦ったアルマがボスの攻撃を受け損ない……といった調子で、そこから逆転できたこと自体が奇跡に近かったが、ともかく何とか敵を全滅させたときには全員が半死半生の状態だった。
ウォンの治療魔法が効いてくる間、四人は荒い息をしながら呆然と見つめ合っていた。何とか回復してくるとイオがぼそっと言う。
「よく生きてたな……」
「ねえ、これって厳しすぎない?」
スーチの問いにアルマも考え込む。
「ううむ。ここは確かにきついところではあるが、こ奴らにこんな苦労をするようでは……」
「隣の大陸に行ったら敵はもっと強いんだよね?」
「ううむ。物によってはな。ここのボスはここでは相当に強い方じゃが」
確かにゲームを知悉した熟練パーティーであれば、アルマの言っていたルートも可能かもしれない。だが今のメンバーではかなり厳しそうだ。
その時ウォンが言った。
「ま、ともかくそれでそのチケットってのは取ったのかよ?」
「おお、忘れておったわ。ここで忘れては洒落にならぬな」
アルマはそう言ってボスの死体を探ると、銀色に輝く三角形の板を取りだした。
「それがそうなの?」
「ああそうじゃ。これがあれば七つの大陸どこにでも渡ることができるぞよ」
一行がここを襲撃した理由はこれを手に入れるためだった。このチケットは買うこともできるが、かなり高価だ。買えるだけの金を貯めている暇はない。ここのボスは必ずこれを持っているのだ。
「でも片道なんでしょ? 行って戻れなかったら?」
「大丈夫じゃ。あっちに渡ってしまえば、儲かる仕事はたくさんある。チケットぐらいすぐ買えるようになるのじゃ」
「でもなあ、それ以前に生きてられるかって方が問題だよなあ」
イオの言葉に全員考え込んでしまった。
「やっぱり地道にやってた方がよくない? 無理して全滅しちゃったらすごいロスでしょ?」
「確かにスーの言うことも尤もなんだが……だとすると3日でできるのか?」
イオの言葉にみんな顔を見合わせる。今回のプレイのために一応3日間の余裕を見ていた。だがそれを捻出するためにあちこちのスケジュールにしわ寄せがいっているため、これで失敗したら次は早くて数ヶ月先になってしまう。
それを聞いてアルマは考え込む。
「うーむ。ローウェル周辺にいる怪物どもは、こんな奴らの比ではないのじゃ。そいつらと戦えるまで真っ当にやっていては1週間かかるやもしれぬ」
「じゃあどうする?」
イオの問いにアルマはしばらく考え込んだ。それからふっと顔を上げると三人の顔を見回した。
「あれは使えるじゃろうか?」
「あれって?」
イオの問いにアルマが答えた。
「無敵コマンドじゃ。それをかけておけばこのようなザコは蹴散らして行けるわ」
「無敵? どんな奴らでもやっつけられるようになるのかい?」
「いや、やられなくなるだけじゃ。自分の強さは変わらぬので、膠着してしまうこともあるがな。でも今よりはずっとましであろう?」
確かに死なないだけでは相手を倒せることにはならない。だが戦闘ごとに半死半生になるよりはよっぽど良いだろう。
「そんなのがあるんならどうして最初から言わねえんだよ」
ウォンがそういうとアルマは答えた。
「これは本来デバッグ用のものじゃ。どうしようもない場合にのみ使えと言い含められておる。それに無敵になどなってしまったらゲームがつまらぬであろうが」
「まあ、そうだけどな……」
それを聞いてイオが言った。
「でもそんなデバッグコマンドがリリース版に残されてるのか?」
「分からぬ。残されていれば使えるじゃろうし、使えなければ残されていないのじゃろう」
一同は絶句した。なんだかすごく行き当たりばったりな感じがする。だがせっかく苦労してここまで来たのにまた数ヶ月も待つというのも嫌だった。
しばらくしてウォンがアルマに言った。
「まあ、何か怪しいっぽいけど、今は結構どうしようもない状態なんじゃないのか? どうせならやってみたら?」
「ええ? 大丈夫?」
それを聞いてスーチが心配そうに言う。
「やるんだったら、せめてラーンに見ててもらった方が良くないか?」
イオも心配そうにそう付け加える。
「それが道理じゃな。ではしばし待たれよ」
そう言ってアルマはラーンに通信を始めた。
ラーンはこの日まで1週間ほとんど不眠不休で作業していた。作業の成果が出て万事うまく行きだしたとあれば、当然彼女が採る行動は決まっていた。
すなわちアルマがラーンを呼び出したとき、彼女はコンソールに突っ伏して熟睡していたのだ。彼女が目を覚ましたのは数度目のコールがあってからだった。
『ラーン殿、ラーン殿!』
「ふぁーい……」
『おお、やっとつながった、ちょっと見ていて欲しいのじゃ』
「はぁ? ぬぁにを?」
『これから妾は無敵コマンドを使おうと思うのじゃ。妖しげなことが起こらぬように見ていて欲しいのじゃ』
当然ながらラーンの脳細胞は10パーセントも活動していない。
「ふぉーい。OKよぅ」
それを聞いてアルマはなにやらややこしい呪文を唱え出す。それを聞きながらラーンの頭は徐々に稼働し始めていた。そしてとんでもないことにOKを出してしまったことに気づいたのと、派手な効果音と共に3Dモニタがフラッシュしたのとはほぼ同時だった。
「ちょ、ちょっと! アルマ」
『すまぬ。だめであった』
「はあ?」
見るとアルマ達はさっきと全く同じ状態でそこに座っている。
『やはりそのようなコマンドは無効のようじゃ』
「い、今光ったのは何よ!」
『これはデバッグコマンド用の特殊効果じゃ。失敗しても光ることは光るのじゃ』
ラーンは思いっきり安堵の息を吐いた。
「びっくりさせないでちょうだい! それとやっぱり今後そういうのはだめ! 禁止!」
『すまぬ。手間をとらせたの』
そう言ってアルマは通信を切った。それから一行は立ち上がると街に向かって歩き始めた。
《無敵コマンド? まったく、無効で良かったわよ。んなもん動かされたら何が起こるか分かったもんじゃないわ!》
ともかく結果的に何も起きなかったのは幸運だった……そう思った途端にラーンは安心してまた眠ってしまった。
「ラーン殿、ラーン殿!」
『ふぁーい……』
「おお、やっとつながった、ちょっと見ていて欲しいのじゃ」
『はぁ? ぬぁにを?』
「これから妾は無敵コマンドを使おうと思うのじゃ。妖しげなことが起こらぬように見ていて欲しいのじゃ」
『ふぉーい。OKよぅ』
通信は周囲の者にも聞こえていた。
ラーンの返事を聞いてアルマはなにやらややこしい呪文を唱え出した。
「ラーンさん、寝てたみたいね」
スーチがつぶやいた。
「まあ、ずっとやってたからな。あのパワーはどこから出て来るんだろうね」
イオが答える。その時呪文が終わったようだ。派手な音が鳴り響き、目の前が一瞬真っ白になった。
視界はすぐに戻ってきたが、正常な点と言えばほとんどそれだけだった。
《おい、体がうごかねえぞ!》
途端にそこにいたアルマ以外の三人は体が麻痺してしまった、というよりいきなり身体感覚が全く消え失せてしまったのだ。体を動かそうにもその体がどこにあるのかさっぱり分からないのでどうしようもないのだ。
三人はアルマを見つめた。というより彼女を見ていた状態で凍り付いていた。アルマもまたぴくりとも動かないように見えるが、他のメンバーと違って口元が動いている。何か話しているようだ。
それからまたびっくりするようなことが起きた。なんと全員の体から霊体が離脱したのだ! もちろん本当にそうなったのではないが、ともかくそうとしか表現しようのない現象だった。その“霊体”は実物に違わぬほどリアルだった。
《!》
叫びたくとも声は出せない。離脱した霊体は立ち上がると、そのままアルマを先頭に街の方に歩いて行ってしまった。
三人はしばらく呆然とその姿を見送った。それからめいめいに心の中でつぶやき始めた。例えばウォンの場合はこういう感じだ。
《一体何が起きたんだよ?》
ウォンはまず自問自答した。これがアルマの呪文のせいだというのはほぼ間違いないが、それだけでは何の説明にもなっていない。こういう時は状況確認が第一だ。
《我が名はウォン・リンドゥーなり。ここに真の名を以て異界の扉を開かん!》
どのような状況でも、例え言葉を封じられた状況でもこのシステムコールの呪文だけは効く。というか効かなければならない。そういうようにできているのだ。そして聞こえるはずの天の声に対して『状況確認』と言ってやればいいのだ。そうすれば彼らが現在陥っている状況に関して何らかの情報を与えてくれるはずだ。
ところが今回だけはそうはいかなかった。ウォンが何度その呪文を唱えても、全く何の反応もなかったのだ。聞こえるべき天の声は聞こえてこない。
その状況がどれほどまずいことか、いかに楽観的なウォンでも理解できた。すなわち今の彼は本当に何もできないのだ!
それからどのぐらいの時間が経ったか分からない。多分そんなに長い時間だとは思えないが、三人には無限のように長く感じられた。それはアルマの次のような叫びによって唐突に破られた。
「アホンダラァ! さっさと戻さんかい!」
それと共に三人の体の自由が戻った。彼らはしばらく自分の手足を動かしてみて、それが現実だと確認していた。それから声を合わせて言った。
「アルマ! 何だよ? こりゃ!」
「アルマ! 何したんだ?」
「アルマ! なに? これ!」
だがアルマはそれには答えず、その場にへなへなと崩れ落ちてしまった。そしてその横の空間にいきなり男が湧いて出たと思ったら、ぺらぺらと喋りだしたのだ。
「やあ、君たちがマーの友達かい? 僕はカイ・ヴェッセルだ。もし君たちの誰かがマーと結婚したいんだったら、僕のことをお兄さまって呼ぶことになるんだ。分かったかい?」
分かるはずがない。