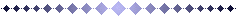第10章 フェニックス
それから30分後、四人は暗闇の中を全力で走り続けていた。
「アルマ! まだなの?」
スーチの疲労はかなりのようだ。
「もうすぐじゃが、薬はもうないのかえ?」
「さっきので使っちゃった!」
「喋れるぐらいなら大丈夫じゃ。もう一息じゃ」
先頭を走るアルマが松明を振り回しながら叫ぶ。今ここで止まるわけには行かない。もちろんそれはみんな分かっている。何しろ後方からはトロールの団体様がやってくるのだ。肩越しに見ると松明が軽く数十個は見える。ちょっと今の状況ではお近づきにはなりたくない。
それからどのぐらい走り続けたのだろうか。スーチだけでなくウォンやイオもそろそろ限界だと思えた頃、先頭のアルマが急に立ち止まった。三人も慌てて走るのを止める。見ると目の前は断崖になっていて、深い谷間が行く手を遮っている。遙か下の方で急流が渦巻いているのが微かに見える。
「ああ! よかった!」
スーチが息を切らせながら歓喜の声を挙げた。だが喜んでばかりはいられない。アルマは対岸を指さして叫んだ。
「よし! 目標はあそこじゃ! ウォン、まずは奴らを!」
「おっしゃ!」
それを聞いたウォンは懐からびっくり玉を取り出す。見かけは大きめの手榴弾というところだ。懐の内部でごろごろして邪魔だったが、これでやっとおさらばだ! そう思いながらウォンはびっくり玉のピンを抜くと、思いっきり後方に向かって投げた。
玉はしばらく弧を描いて飛んでいたが、やがて空中で大爆発を起こした。それを見てウォン達まで腰を抜かしそうになった。
なにしろそのサイズからして彼らは大型の花火程度だと思っていたのだ。ところがどうだ? この爆発の規模は小型の核爆弾並だ!
「うわああ!」
「きゃああああ!」
三人は慌てて体をかばう。だがそれを見てアルマが叫んだ。
「何を呆けておる! イオ殿! 呪文を!」
「お、おお!」
そう言ってイオが何かつぶやき始める。
その時にはウォンやスーチも気づいていた。あれほどの音や光がしたというのに、爆風はやってきていない。これは物理的な実体のある爆発ではないのだ。
しかし後方のトロール達はそれで大混乱を起こしたようだった。
「よし! いいぞ!」
アルマが拳を握りしめながら叫んだ。だがトロールのうちの何人かが混乱にもめげずに突進してくるのが見えた。
《げ! やばい》
それを見てウォンとアルマは目配せしあうと剣の柄を握った。最悪の場合はこれを使う羽目になるかも……そう思った時だった。急に四人の体が軽くなった。イオの魔法が効いたのだ。こうなれば前の峡谷を飛び越えるのは簡単だ。
「このレベルじゃ20秒しか持たないぞ!」
イオが叫ぶ。だがもちろんみんなこの程度のことには慣れている。一人一人落ち着いて谷を飛び越えていった。
対岸に着いてから振り返ると、今まで彼らがいた場所にトロールが何匹か集まって彼らに向かって吼えているのが見えた。
「けっ! バーカ」
もはや手を出せないと思ってウォンは舌を出して挑発した。だが途端にアルマがウォンの襟を掴むと地面に引きずり倒した。
「こら! 馬鹿者!」
「何しやが……」
ウォンはアルマに食ってかかろうとした。だがそれ以上文句は言えなかった。何しろ今までウォンがいた所に、細長く伸びて大口を開けたトロールの首がばっくりと食いついていたのだから。
「ひええええ!」
「逃げるのじゃ!」
ウォンは慌ててアルマの後を追った。その後を追うようにトロールの首が追いかけてきたが、ぎりぎりのところで範囲をはずれたようだ。ウォンの後ろでげふっと嫌な音を立ててトロールの口が閉じる。
だがさすがに今度はウォンもからかう気にはならなかった。
そこからさらにしばらく走って、やっと一行は立ち止まると地面にへたり込んだ。
「なんて首だよ」
「だから言ったであろうが! 気色悪いと」
「あの距離を届くのかよ?」
「そうじゃ! おのれはもう少しで喰われる所だったのじゃ」
そう言われてさすがなウォンも返す言葉がなかった。
それを見ながらスーチが言った。
「ともかくちょっと休ませて」
「ああ、そうじゃな。ここでしばし体力を回復させようぞ」
そう言ってアルマも座り込んだ。
「ああ? 時間は? 急がなくていいのか?」
ウォンの言葉にアルマが行く手を指さしながら答えた。
「これからあそこを登らねばならんのじゃぞ。ヘロヘロでは落ちてしまうじゃろうが」
ウォンはアルマの指した方を見て少しげんなりした。それまでは視界が悪くて見えなかったのだが、今ははっきりと月光の中にフェニックスの住処であるノートス高地を囲む絶壁がそびえ立っているのが見て取れる。
「げえ、あの上かよ」
「そうじゃ。怖じ気づいたか?」
「誰が!」
「それと村からここまで思いっきり走ったせいで、予定より30分は早く来ておるのじゃ。焦ることはないわ」
「なるほどね」
それを聞いてウォンも地面に座った。実際彼もかなり疲れていたのは間違いない。一行はしばらくそうして星空を眺めていた。
その時スーチが息を呑んだ。イオもウォンも同時にそれを見ていた。絶壁の上をすうっときらきら輝く物が飛んでいったのだ。
「あれがそうじゃ」
一行は黙ってうなずいた。
「この先は敵は出ないのか?」
イオが確認する。
「ああ。夜ならば大丈夫じゃ。昼じゃとハーピーがいてうるさいがな。奴らは鳥目なのじゃ」
それを聞いてウォンが言った。
「フェニックスは鳥目じゃないのかよ?」
「さあな。だったとしても自分の光でいつも明るいから関係ないのであろう」
「なるほどね。やな野郎だ」
ここに来て一行はこの“裏技”が修正されずに残された理由を身をもって感じていた。そもそもアルマの案内がなければここに来ること自体が不可能だった。闇の街ペルナタウンの脱出は彼女が裏道や敵の属性を熟知していたからこそ可能だった。今のトロール居住地の突破も同様だ。少々予定外のことはあったとはいえ、そもそもこのポイントで対岸に渡れることを知らなければそんなことをしようとさえ思わなかっただろう。
「さて、そろそろ行くかや?」
アルマの言葉に、残り三人は黙って立ち上がって歩き始めた。絶壁まではかなりあるように見えたのだが、実際に歩いて見ると思いの外早くたどり着いた。
絶壁の下から見上げながらアルマが言った。
「ここは落ち着いて登れば大したことはないのじゃ。登攀道具なども一応買ってはおるが、ほとんど使うこともないじゃろうな。でもイオ殿、重力低下の魔法の準備だけはしていて欲しいのじゃ」
「ああ。まかせとけ」
「それでは行くぞよ」
そう言ってアルマは崖を登り始めた。残りの三人も彼女の後に続く。
こういった崖登りというのはちょっと難しいゲームなら当たり前のように出てくる障害だ。だから登攀その物には全く困難はなかった。それどころかその崖が見かけほど急ではなく手がかりも豊富だったことが分かるに連れて、みんな余裕が出てきたぐらいだ。
「明るければ景色はいいのかしら?」
スーチがアルマに尋ねる。
「ああ。南の大陸が一望にはできるがな。じゃが多分ハーピー共につきまとわれてそんな余裕はないぞよ」
「あはは、そうね」
今は夜だ。眼下は漆黒の闇に閉ざされている。トロールの村と思わしき方向に、かがり火らしき物が見えるだけだ。そんな中を登り続けていたので、その距離は非常に長く感じられた。下からざっと目測した限りでは100メートル前後だったろうか? この程度なら20~30分あれば登れるはずなのだが。
「まだか?」
ウォンがとうとうしびれを切らしてアルマに尋ねた。
「もうすぐそこじゃ。上が見えておる」
ウォンも目を凝らすと、絶壁の上端のシルエットを見て取ることができた。
アルマは最後の部分を器用な身のこなしで上がっていく。彼女は最上端まで行って、ちょっと上に顔を出し、それからすぐ慌てたように頭を引っ込めた。
「おお! 結構近くにおったな」
「見つかったのか?」
「いや、大丈夫じゃ。ぬしらも上がってくるが良い」
ウォンはそこまで来ていたイオとスーチに目配せする。二人は黙ってうなずく。それからスーチが先頭になって登り始めた。
「スー殿、そこが良いぞ。一番飛び出しやすい」
「ありがと」
アルマがスーチとイオに隠れ場所を指示する。まず彼らの行動の成否が全体の成功に大きく関わっているのだ。出だしで文字通りにつまづかれては洒落にならない。
それからウォンも上がってきて、アルマの横に並ぶ。一行は崖の縁から怖々頭を出す。ノートス高地と言うだけあって、絶壁の上はあちこちに小さな尖峰やクレバスなどがあるものの、おおむね平地になっている。
「あ! 右の奥手を飛んでる」
「うひょー。綺麗な奴だね」
夜空を飛ぶフェニックスとはなかなか見られない光景だ。こういうことがあるからゲームはやめられないのだ。たとえそれが人工的な創造物であっても。いやこの時代ではそれが人工物か自然物かという区別その物がほとんど意味を為さなくなっていた。
少なくとも彼らの前を飛翔しているフェニックスが一つの芸術作品であることは間違いない。
「時間は?」
イオの問いにアルマが答える。
「30分は余裕があるぞよ」
そしてアルマは後から付いてきていたカイに向かって尋ねた。
「で、カイ、そっちの方はどうじゃ?」
もちろん彼も今までずっと付いてきていたが、話していると腹が立ってくるだけなので、たまに状況を尋ねる時以外はみんなずっと無視していた。
「こっちも順調だぜ。ほぼ予定通り突入できるさ」
「はあ、そうかい」
それを聞いて一行は複雑な気持ちだった。だがここまで来た以上後はやるしかない。しばらくの間四人は黙って時を待った。その沈黙を破ったのはスーチだった。
「これって何だかまるでいつもと同じね」
それを聞いてウォンが訊き返す。
「いつもって?」
「ほら、例えばこの間のエルガストルムへの突入待ちしてた時と同じよね」
「ああ? まあそうだな。あん時も余裕なかったしな」
「でも結局うまくいったじゃない」
そんな二人の会話を聞きながらイオが言う。
「おい、命がかかってるんだぞ。もっと緊張した方がいいんじゃないか?」
「って言われてもなあ……こう言うのっていつだって命がけじゃん」
ウォンの答えにイオもあまり反論できなかった。彼もまた同じだったのだ。
彼らは皆これから文字通りに“命がけ”の勝負に出ようとしていることを、頭の中では理解していた。だがそう言われても誰も本当の危機感を感じてはいなかったのだ。最初のうちはもっと緊張しようと努力したぐらいなのだ。だがなぜか気づいたらやっぱりいつもの調子になっているのだ。
そもそも“命がけの勝負”などというシチュエーションは彼らの大好きなNSEゲームの中ではいつだって出てくる代物だった。彼らは、最も経験が浅いスーチでさえ既に何十回もそんな勝負をしてきている。もちろんその勝負で本当に命がかかっていたわけではない。それは仮想現実の上の話なのだ。死んだって何度でもやり直せる。だからこそ気楽に命を張っていられたのだ。
しかし今回は違う。死はすなわち真の死を意味し、失敗は破滅を意味する。そのことは皆百も承知だ。なのに彼らはそれを信じることができなかった。死だの破滅だのと言われても、彼らはそれをうんざりするほど経験してきているのだ。まさにオオカミ少年状態だ。今度ばかりはいつもと違うとか言われても、はっきり言って全然ぴんと来ないのだ。
その代わりに彼らが感じていたのはこれが掛け値なしに久々に熱くなれそうなシチュエーションだということだった。
『へえ、おもしろそうじゃん』
それはアルマが“裏技”に関する説明を終えたとき、最初にウォンが発した科白だ。結局彼にとってこれは単に面白そうな状況に過ぎなかった。アルマはそれに対して苦言を呈した。だがそれはイオにとってもスーチにとっても、そして実のところアルマ自身にとっても同様だったのだ。
アルマはウォンとイオに向かって話しかけた。
「そう言えば二人に言っておくことがあったのじゃ」
二人はアルマの顔を見た。ウォンが訊き返す。
「なんだ? いきなりあらたまって?」
「聞けばうぬらはフリーダムバケーションをゲーム三昧で過ごしたそうじゃな?」
それを聞いて二人が赤くなる。フリーダムバケーションとは前にも述べた通り、義務教育を終えた物に連邦から与えられる特別な期間だ。これをゲームなどに費やしてしまうというのは、例えて言えば卒業祝いにもらったお金で駄菓子を部屋一杯買い込んで食べていたのと同じぐらい間抜けな行為と思っていい。
「え? あはは! 何のことかな?」
イオは慌ててごまかそうとする。だがアルマは不思議な笑みを浮かべながら言った。
「この間スー殿から教えてもらったのじゃ」
それは二人をからかっている口調ではなかった。それからアルマはイオとウォンの顔を交互に眺めながら微笑み続ける。ウォンもイオも、それにスーチも彼女の笑顔の真意を図りかねた。
「な、なんだよ。好きなことしてたんだからいいじゃねえかよ。お前には関係ないだろ?」
「いや、違うのじゃ。実はな、妾もそうだったのじゃ」
「ああ?」
三人は驚いてアルマの顔を見た。今度はアルマの方が少し恥ずかしそうに下を向く。
「妾もな、期間中はずっとロクス・エテルナをやっておったのじゃ。じゃから妾は今までベレンを出たことが一度もないのじゃ。で、ぬしらはまあその、あまり他人事とは思えんでな」
アルマがそう言うとスーチが驚いたように言った。
「ええ? じゃあアルマもそうだったの?」
「ん? どうしてじゃ?」
アルマが驚いて顔を上げると、スーチがアルマの手を取って言った。
「だって、あたしもそうだったもの」
「え?」
今度はアルマが驚きの表情でスーチを見やる。だがスーチはいたってまじめな顔だ。それを見てウォン達もにやにやしている。
驚いているアルマにスーチは言った。
「あたしもね、フリーダムバケーションの間ずっとゲームしてたのよ。ユディ族のスキンを作るためって建前はあったけど。でも本当はね、そっちの方が面白かったから」
「なんと! スー殿もかや?」
そして四人は互いに顔を見合わせて吹き出した。
ここに奇妙な四人が集まっている。一人一人の生まれや生い立ちはおろか、種族までもが異なっている。そんな時間も空間も遠く離れた所で生まれた四人が今この不思議な場所で圧倒的な一体感で結ばれているのだから。
これはもう奇跡と呼んでも良いのかもしない。ただその四人を結びつけていた絆が、救いがたいゲームバカという絆だったのは、ちょっと何だったわけだが……
そうこうしているうちに時が満ちた。
「そろそろよ。イオ」
スーチがささやいた。心なしか声が震えている。
「スー殿、大丈夫かや?」
それを察してアルマがスーチにささやいた。
「大丈夫よ。大仕事するときはいつもこうなの。気にしないで」
「ああ。スーの言う通りだぜ。こいつも最近結構修羅場くぐってるからな」
それを聞いたウォンも太鼓判を押す。
「ともかく変なところでこけたりするなよ」
「それはイオもね」
計画の最初の頃は、ある意味スーチが一番気楽な立場だった。このメンバーの中では彼女は一番後輩であったし、自分で言い出そうと言い出すまいと死に役の一人は彼女に決まりのようなものだったからだ。死ぬというのはその瞬間だけは嫌な気分がするだけで、その後はどうということもない。だから彼女もこれを実行するよう強く推したのだ。もちろん彼女が体験したことがあったのはバーチャルな死亡だけだったわけだが。
だが彼女とイオの死に役が意外に重要だということを知って、今では若干後悔をしていたりもしていた。
「それではもう一度確認するぞよ。フェニックスがあのとがった岩の上を通り過ぎたら妾が合図する故、スー殿は飛び出してあの三角の岩に向かって全力で走るのじゃ。それからイオ殿はスー殿の後ろから10メートル程離れて走るのじゃ。岩の手前の足場の良い所を何としても確保するのじゃ」
アルマの言葉にイオとスーチはうなずく。
「大丈夫よ」
「任しとけ」
それを聞いてアルマは二人の手を取って言った。
「二人とも、頼むぞよ」
二人は黙ってうなずいた。それからイオがウォンの方を見て言った。
「じゃあ後頼むぜ」
「おうよ」
ウォンも特に気負いなく答える。こんな風に後を頼まれることは今まで何度もあったことだから、あまり今回が特別という気はしなかった。
「じゃあ始めるぞよ」
そう言ってアルマは岩陰から頭を出してこっそりとフェニックスの様子を窺った。フェニックスは悠々と上空を旋回している。そのルートは複雑なようだが、彼女はそれがどういう軌道になっているのかを理解しているようだ。
「そろそろじゃ。二人とも良いか?」
スーチとイオは息を呑んだ。さすがにこうなると緊張してくる。
フェニックスがゆっくりと周回して近寄って来る。それから旋回して前方のとがった岩の上を通り過ぎた。
「今じゃ!」
アルマの指示と同時にスーチは飛び上がると脱兎のごとく駆けだした。それを追うようにイオも駆け出していく。
その時スーチとイオはフェニックスの姿を始めて間近に見た。
《きれい!》
スーチは思った。
その姿は人の想像力が創り出したものに過ぎないとわかっていても、その毅然とした姿はいかにも世界を支配する王者にふさわしかった。彼女はその姿をずっと見ていたかった。
だがフェニックスは走ってくる二人に気づいたようだ。途端にその輝きが増してくる。これが噂のスーパーノヴァという奴に違いない。
「もうちょっとだ!」
イオが叫ぶ。二人は最後の力を振り絞って走った。
それから目の前が真っ白になったと思った瞬間、それ以上は何も分からなくなった。
「隠れよ!」
アルマが岩陰に身を隠し、なおかつべたっと地面に身を伏せる。ウォンもすぐに彼女の真似をする。
それと同時に目を閉じていても分かるような凄まじい閃光が輝いた。一瞬遅れてからずどーんと激しい音が響きわたる。同時に熱風が二人を包みこむ。
「ぐああ! あちち!」
「我慢せい! 死にやせん!」
思わず呻いたウォンをアルマが小声で制する。今度の爆発はさっきのびっくり玉とはわけが違った。熱風が収まった後も二人はしばらく動く勇気が出なかった。
「ど、どうなった?」
しばらくしてウォンがつぶやくとアルマも恐る恐るといった様子で頭を出す。それからウォンに手招きした。ウォンがその下から顔を出すと、フェニックスは相変わらず悠々と上空を旋回している。その下には真っ黒な消し炭のような塊が二つ転がっているのが見える。
「ひでえ!」
ウォンは思わずつぶやいた。
「でも言うたとおりであろう?」
そう言ってアルマはフェニックスを指さした。
「ああ。本当だ。あの場所でいいのか?」
「十分じゃ」
フェニックスはそれまでの軌道と違って、今は元スーチとイオであった消し炭の上をゆうゆうと周回している。これは簡単に死体を復活させられないようにするためだという。
「ふん。何でか知らないけど、不死の輩のくせにずいぶんせこい奴だな」
「ぐだぐだ抜かすな。妾が合図したら行くのじゃ。良いな?」
「ああ。いいぜ」
それからアルマはじっとフェニックスを睨んだ。フェニックスは相変わらず悠々と夜空を旋回している。
だがアルマはなかなか合図を出さない。ウォンは不思議に思ってアルマの肩に手をかけた。
「おい、どうしたんだよ?」
だがその時ウォンはアルマががたがた震えているのを感じ取った。
「す、すまぬ。さすがに緊張してな、体の震えが止まらぬのじゃ……」
「お前なあ、こんな時に……」
アルマは何度も深呼吸するが、やはり震えは止まらない。それを見てウォンの方が焦ってきた。ここで彼女がパニックになってしまったら全てが水の泡なのではないのか?
《おい、どうするよ?》
ウォンは自分に問いかけた。このまま放っといていいのだろうか? この程度ならそれで問題ないはずだ。アルマだって素人じゃない。そのうち立ち直るだろう……だが今、イオとスーチは文字通りに死んでいるのだ! 30分ぐらいの間なら問題なく蘇生できるとはいえ、それでも一刻一秒を争う状況であることには間違いないのだ。やはりゆっくり待っていては間に合わないかもしれない……ならばどうすればいいのだ?
だが考えてもまともな回答は出てこない。一つだけとんでもなく下らないネタだけは出てきたが……
《バカ野郎! 冗談やってる場合じゃねえぞ?》
ウォンは首を振った。でもこのまま時間を浪費するわけにはいかない。
《大体そんなとこ見られたりしたら……》
そう思った瞬間、ウォンは彼の行動を見ている物など誰もいないことに思い当たった。誰も見てくれていないからこそ彼らはこんな苦労をしているのだ。それに気づいた途端ウォンは気が大きくなった。
そしてアルマの肩に手をかけると言った。
「緊張を解くおまじないしてやるぜ」
「な、何じゃ?」
アルマが驚いて振り返る。ウォンはそれには答えず、彼女の両肩を抱き寄せてキスをしようとしたが……なぜかそれは壮絶な鼻と鼻の激突という結果に終わってしまった。
「な、何をするか! 痛いではないか!」
アルマが鼻を押さえながらウォンに張り手を食らわす。
「い、痛えな! 何しやがる!」
ウォンが頬を押さえながらアルマに食ってかかろうとすると、アルマはウォンを地面に押さえつけながら言った。
「黙れ! 見つかるではないか!」
「お前がやったんだろ!」
反射的に立ち上がりそうになったウォンを、今度はアルマが全身で押さえつけた。その結果アルマはウォンに馬乗りになって押し倒したような格好になってしまった。ウォンの目の前に彼女の胸の谷間が間近に見える。ウォンは目のやり場に困ったが、その時彼女がもう震えていないことに気がついた
そこで彼はその格好のまま言った。
「で、震えは収まったか?」
アルマはたっぷり3秒ほどウォンの顔を見つめて、それから慌てたように彼から離れた。
「どうやら直ったようじゃ」
それから彼女は何事もなかったかのように、再び頭を出してフェニックスに注意を向けた。
「あ奴が背を向けたら行くぞよ」
「おお」
それから5秒後、二人は一気に飛び出した。
フェニックスはすぐに彼らに気づいたようだ。方向を変えると、彼らの方に急降下を始めた。だが明るくはならない。予定通りだ。
それを確認すると二人は剣を抜き放つ。
「そこじゃ! 一直線になるようにな!」
「おお!」
アルマとウォンはスーチとイオの死体を結ぶライン上に立って剣を構える。フェニックスはきっちりとそのライン上を通って彼らに突っ込んできた。
ウォンはアルマの説明を思いだしていた。
『フェニックスの奴はな、攻撃を始めてもまだ死体にこだわるのじゃ。そのため攻撃する経路が決まってくるのじゃ。位置がばらばらの場合は、なんだかややこしいそうじゃが、死体が一直線に並んでおればその直線上を通って攻撃してくるのじゃ』
だからこそスーチとイオの死に方が重要だったのだ。彼らがうまい位置で死んでくれていれば、フェニックスのやってくる経路が制限されて、二人の攻撃が非常にやりやすくなるのだ。
だがこれは“やりやすい”というよりは“できなくはない”という言い方の方が妥当だった。剣を構えたウォンの側をフェニックスがものすごいスピードで通り抜けていく。
「うへえ!」
その瞬間アルマは何とか一太刀食らわしていたが、ウォンは避けるだけで精一杯だった。
「やったか?」
アルマが振り返らずに言う。
「すまん。しくった」
「なんじゃと?」
「最初は練習だよ。な?」
「じゃあ次回からが本番じゃぞ?」
「わかってらって」
だがそう言いつつウォンはちょっと自信がなくなってきていた。あのスピードは半端ではないのでは?
アルマはウォンの不安を感じ取ったのか、こういうこと言いだした。
「うまいこと当てたら、褒美にもっと上手なキスをくれてやるわ」
それを聞いてウォンはずっこけそうになった。
「何をしておるか?」
「あのなあ、こんな時に冗談抜かしてるんじゃねえよ!」
だがアルマは振り返らずに答える。
「ほう? いらぬのか?」
「……もらえる物はもらっとくがな」
そう言いながらウォンはすっかりやる気満々になっているのに気がついた。ウォンは常々自分のことを決して複雑な人間だとは思っていなかった。だがこんなことでこんなにやる気が出るなんてちょっと単純すぎないか? という気もしたが、まあアルマだってさっきのキスもどきで平静を取り戻したりして、単純さという意味では同類かもしれない……などと考えている暇はなかった。
フェニックスは彼らの横を大回りすると、また最初の位置に戻ってさっきと同じ経路で降下を始めた。経路とタイミングが分かっていてさえ当てられるかどうか自信がない速さだ。もし毎回でたらめな方向から突っ込まれたらもはやお手上げだったろう。
《イオ! スー! お前らの死は無駄になってないぜ!》
ウォンはフェニックスに精神を集中した。フェニックスが一気に大きくなってくる。
《今だ!》
ウォンは横に弾け飛びながら剣を振った。手応えがある!
「やったぜ!」
「まことか?」
そしてすぐにアルマが懐から生命力ゲージを取りだした。スーチの特殊能力のせいで買うことができたあれだ。彼女がそれ越しにフェニックスを見ると、嬉しそうに言った。
「確かに減っておるぞよ!」
それを聞いてウォンもほっとした。うまくいきつつあるのだ。
「で、どのぐらい減ってるんだ?」
「これは……1割程か?」
ウォンは天を仰いだ。
「1回で1割? じゃああと9回も当てないといけないのかよ?」
「そういうことじゃな」
「お前確か6回ぐらいって言ってなかったか?」
「あの時はレベルが4じゃったと言ったであろうが!」
ウォンは気が遠くなってきた。これはかなりきわどい勝負だ。決して手が出ないと言うわけでもないが、一歩間違えたら体ごと持って行かれそうだ。これをあと9回も間違えずに繰り返せるのだろうか。
だがくよくよ考えている暇はない。フェニックスは再び飛来しようとしている。
「来るぞよ!」
「おう!」
ウォンはともかくフェニックスに全神経を集中する。そしてすれ違いざま思い切り剣を振ったが、今度は身を引くタイミングが少し遅すぎた。
「うわ!」
ウォンの肩に激痛が走った。フェニックスの尾羽がちょっとかすっただけだったのに。
「大丈夫かや?」
呻き声を聞いて慌ててアルマが振り向く。みるとウォンの肩からかなりの血が噴き出している。
「この程度どうってことないぜ」
ウォンは強がったがこれは決して軽い傷ではない。だが今この程度で治療しているわけにもいかない。
「気を抜くでないぞ。尾羽でこれじゃ。あのくちばしだの爪だのに引っかけられたら、簡単に手足が吹っ飛ばされるぞよ」
アルマの表情は真剣だ。
「わかってらって」
ウォンもうなずいた。これはあらゆる意味で本気でかからねばならない状況だ。
だが彼は焦りは感じていなかった。なぜなら彼はこのぐらいの敵ならば今まで何度も渡り合ったことがあったからだ。今の交錯でウォンは、落ち着いて戦ってさえいれば決して手が出ない相手ではないことを肌で感じ取っていた。もちろんここまでせっぱ詰まった状況だったことはなかったのだが。
「また回ってきたぞよ!」
「おう!」
ウォンは再び剣を構えてフェニックスに集中した。フェニックスが飛来する。アルマがフェニックスを斬り、間髪を入れずにウォンが再度斬りこむ。フェニックスは一瞬で通り過ぎ、またすぐに体勢を立て直してやってくる。二人はまた剣を構え……このようにして二人はひたすらにフェニックスの生命力を削り続けた。
そのうちそれは果てしなく続く作業のような気がしてきた。なにしろ二人が共に攻撃を当てなければならないのだ。どちらかがしくじっただけでその回は無効なのである。なんだかんだで成功する率は5割もいかない感じだ。
ウォンは最初の頃こそ回数を数えていたが、10回を超えたあたりからはもう何回やったか分からなくなってしまった。アルマが生命力ゲージを欲しがったのも当然だ。
「今のはちょっと浅かったか? あと、どのぐらいだ?」
ウォンは喘ぎながら訊いた。アルマが同様に喘ぎながら生命力ゲージでフェニックスの残り体力を調べる。
「あと、3割ほどじゃ」
二人は荒い息をしながら剣を構え直す。残り3割……マラソンなどで言えば最もきついのがこれからだ。
果たして次の攻撃は二人ともしくじってしまった。
「おのれ!」
アルマが毒づく。あれから羽にかすられるようなことはなかったが、二人ともそろそろ緊張の限界に達しつつあった。普通だったらここでちょっと一休みしたりするのが正しい判断なのだが、今そんな時間があるはずない。ウォンは一応ここでは僧侶だったので緊張を解く魔法も使えたりはするのだが、怪我をした時のことを考えると精神力を迂闊に消費するわけにはいかなかった。
「あと三発当てりゃいいんだ! がんばれよ!」
口での応援しかできないのは歯がゆいが、仕方ない物は仕方ない。
後から考えればこの時無理してでも緊張緩和呪文を唱えておけば良かったのかもしれない。もちろん後からなら何とでも言えるわけだが。
フェニックスはまた同じ経路を描いて急降下を開始した。それを見てアルマが身構える。だがその構えを見てウォンは何か不安を感じた。それは彼がインストラクターとして長年やってきた経験から得られる勘だったのだろう。こういうときに得てして大事故が起こるのだが……
果たしてその勘は当たっていた。アルマは疲れてきていた。また捗らぬ作業に少々焦ってもいた。そのため突っ込むのが少々早すぎた。彼女はそこで逃げておけば良かったのだが、また1ラウンド失うのが惜しかった。アルマはバランスを崩しながらもフェニックスに一太刀入れた。
だがフェニックスはそんな状態で相手できるほど甘い敵ではない。彼女が気づいたときはフェニックスの爪が胴体に食い込み、次いで体は宙にはじき飛ばされていた。
その姿はウォンの眼の隅にも入った。
《やべえ!》
そう思った物の、もはや退くことはできないタイミングだ。彼は既にフェニックスの経路に沿って思いっきり剣を振った後だった。そこに爪に引っかけられたアルマが吹っ飛んできたのだ。アルマはウォンの構えた剣にもろにぶち当たり、ウォンの手にざっくりと肉が断たれる感触が伝わってくる。
《やっちまった!》
ウォンは剣を放り出すと慌ててアルマのそばに駆け寄った。見ると彼女は肩口から腹にかけてがばっくりと割れて口から真っ赤な泡を吐いている。かなり危険な状況だ。
「あ、す、すまん」
それはこういうときのセリフとしては最高級に間抜けだったが、もちろんもっと気の利いたセリフを考える余裕などない。
アルマはフェニックスの爪とウォンの剣のダブルパンチを食らって、もう動けそうもない。
「アルマ!」
アルマは弱々しくウォンの顔を見ると、口をぱくぱくさせた。何かいおうとしているらしいが、肺が傷つけられているせいか声にならない。アルマは力無く手を持ち上げようとする。
「しっかりしろよ」
そう言いながらウォンはアルマの手を取った。とにかく彼女の治療をしなければならない。だがウォンの知っている魔法では治療効果は知れている上、時間もかかる。薬の類はここに来るまでに使い果たしている。
その時アルマは口をぱくぱくさせながら、ウォンの手を自分の胸に引き寄せた。
「おい! 何やってるんだよ、そんな場合かよ!」
こんな状況でなければ、ある意味非常に嬉しい行為のような気はするが……
そしてウォンは心を決めた。彼は治療魔法を唱え始めた。この期に及んで役に立つかどうか分からない。だがこのまま滅び去るよりはなんぼかましだろう。
だがそういうウォンをあざ笑うかのようにフェニックスが襲いかかって来る。
《くそ! やられる!》
ウォンはアルマに覆い被さった。
だがその途端アルマがウォンを突き飛ばしたのだ。不意を突かれたウォンはひっくり返って近くの凹みに転がり込んでしまったのだが、そのためフェニックスの攻撃を避けることができた。だが最後の力を使い果たしたアルマはそうではなかった。彼女は再度フェニックスの爪に引っかけられるとまた10メートルばかり吹っ飛ばされて、もはやぴくりとも動かなくなった。
「ええ?」
ウォンは慌ててアルマの元に駆け寄る。
「アルマ!」
だが彼女は何も答えない。
「おい! アルマ! ふざけんじゃねえ!」
だが彼女は何も答えない。その目にはもう輝きは失われている。
それが何を意味するかはもはや明白だった。そう。ゲームオーバーだ。彼らの力は及ばなかったのだ。残された彼一人ではもはや何もできない。イオとスーチはやっぱり無駄死にだったのだ。
ウォンは振り返った。遠くの方にカイが幽霊のように浮かんでいるのが見える。
《あとはあの野郎が成功するのを待つしかないのかよ?》
そう思った途端ウォンの心の底から真っ赤な怒りがわき上がってきた。
《こん畜生が!》
ウォンは立ち上がると剣を構えた。
希望だの何だのといったことはもうどうでもよかった。二人掛かりでなければこの相手にはダメージを与えられないといったこともすっかり忘れ果てていた。ウォンはとにかく相手に一発入れることしか考えていなかった。
そんなウォンの想いとは裏腹に、全く無感動な様子でフェニックスは突入してくる。
「く・た・ば・り・やがれぇぇぇ!」
かすれたようなウォンの声が虚空に響く。ウォンの剣が一閃する。ざっくりとした手応えがある。すごい力で剣が引きずられたがウォンはそれに食らいついた。普通の相手ならただでは済まないはずの手応えだ。
だが相手はフェニックスだ。次の瞬間にはまた元通りぴんぴんしているだろう。
《だったらどうだって? 何度でもぶっ殺してやる!》
ウォンは再び剣を構え直す。もはや理屈もへったくれもなかった。来た奴をぶった斬る、ただそれだけだ。
ウォンは待った。もう少ししたらフェニックスはまたあの岩陰から出てくるはずだ。そいつに対して彼の剣を叩き込んでやるのだ。それが無駄だろうと何だろうともう関係ない。力尽きるまでぶった切りまくってやる! ウォンの頭の中はもうそれだけだった。
「はやく来やがれ!」
ウォンは叫んだ。フェニックスの奴は一体何をしているのだ? いつもならさっさとやってくるはずなのに……だがなぜか次の攻撃はやってこない。ウォンは何かがおかしいことに気が付いた。
《え?》
そのときあたりが急に明るさを増し始めたのだ。ウォンが振り返るとフェニックスが全然違うところをふらふらと飛んでいるのが見えた。そしてその明るさがどんどん増しているのだ。
「なに? スーパーノヴァか?」
ウォンは慌てて隠れるところを探した。だがそれはもはや手遅れだった。彼らは戦いやすいようにと広くて障害物の少ないこの場所を選んだのだ。ここからでは一番近い岩陰でもずっと先だ。だが輝きはもう目も眩むばかりとなっている。ウォンはそのままがっくりと膝をついた。
これでパーティーは全滅である。ベラトリックスのゲームオーバーシーンとはどんな物なのだろう? ウォンはそう考えたがすぐにこれから死ぬのだからそんな物は見られないことに気がついた。
ウォンは吹き出した。終わりとはこんな物なのだ。もちろん彼は数え切れないほどのゲームオーバーを体験している。少なくともやることはやったということで、これはその中ではかなりましな方ではないだろうか?
ウォンはそんなことを想いながら最期の時を待った。だがなかなかそれはやってこない。大体フェニックスの輝きは増すのに、熱さがぜんぜんないのだ。さっきは岩の陰でも熱風に焼かれたというのに。それとも彼はもう死んでしまったのだろうか?
《おい、まだかよ?》
そう思った瞬間だった。今度は急にフェニックスの輝きが薄れていったと思うと、その姿がかき消すように消えてしまったのだ。あとから、一枚の羽がひらひらと落ちてくる。
「なんだ? こりゃ?」
ウォンは呆然とそれを手に取った。その羽は彼の手の中で七色に輝いている。
それこそがベラトリックスをプレイした者なら誰でも喉から手が出るほど欲しがったというレアアイテム“フェニックスの羽”だったのだが、今のウォンにとってはどうでもよいものだった。
彼は未だに何が起こったのか良く理解していなかった。そんな彼が我に返ったのは耳元で聞き慣れた声がしたときだった。
『ありゃ? ウォン君ですか?』
この声はギメルだ! ウォンは慌てて立ち上がってあたりを見回した。だが彼の姿はない。
「どこだ? 見えるのか?」
ウォンは当てずっぽうな方向に叫ぶ。すると返事が返ってきた。
『見えますけど、どこです? そこは? ダンジョンにいたんじゃないんですか?』
ウォンはがっくりと膝を落とした。このままぶっ倒れて眠ってしまいたかった。だが最後にやらなければならないことが残っている。ウォンは最後の力を振り絞って叫んだ。
「ギィ! ゲームをシャットダウンしろ! ブースにいる奴らをみんな出せ! それから外に通じる回線もみんな切れ!」
『はあ? ちょっと待って下さいよ、そんなこと……』
「うるさい! でないと死んじまうんだよ!」
『死ぬって、いったい誰が?』
「お前だ! クラックされてるんだ! でないとカーゴが突っ込んで来るぞ!」
『はあ? あの、もっと詳しい状況を……』
だがウォンはそれ以上は答えなかった。なぜならそこでぶっ倒れて気絶してしまったからだ。