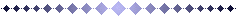第1章 カテドラル
嶺国は貧しい国だ。
その名の通り国土の大部分が山岳地帯で覆われ、作物を育てられる土地は僅かしかない。しかもその場所は大空陸の北端に位置し、冬になると全土が雪と氷に閉ざされる。
嶺国の民はその下でじっと次の春の訪れを待ち望む。
ちょっと寒波が来ただけで人々のそんなささやかな願いさえ叶えられず、多くの人の魂がアニムスの御許へと戻っていくことになる。
嶺国の冬は忍耐と苦難の時だ。
その呪いの象徴である雪と氷……だが少女達にとってはそれさえも天の恵みだった。
「よしっ! いい感じよ! グレイス!」
「いけるよね! 今日は絶対!」
ここは西カテドラルの裏山にある箱橇用の滑降コース。グレイスとブリッサはその中でも最高の難易度を誇る、通称ハヤブサコースに挑戦していた。
斜面に凹んだ道が付けてあって道から外れないように箱橇で滑り降りるのだ。うまくいけばその名の通りにすごいスピードが出る。正直、遊びの中ではあまり安全と言える部類ではない。実際このコースから投げ出されてそのまま天に召されてしまった子もいる。
だが危ないとか危なくないとかそういう問題ではないのだ。
ハヤブサコースを降りる。そのことにこそ何にも替えられない価値があるのだ。なぜだかおおむね理解してはもらえないのだが……十五にもなってそんなことをしているのは子供っぽいとか何とか。
でもブリッサはそれがわかっていて一緒に挑戦までしてくれるという、類い希な親友だ。
だから今日こそは降りてみせる!
斜面を滑降する二人は今までにない手応えと高揚感を感じていた。吹き付ける冷たい風も何のその、これだけ冷えてくれたおかげで雪のコンディションは最高だ。
一人用の橇でなら今まで何度か降りたことがあるが、この二人用の箱橇で成功したことはまだない。あのカナーリとファールケが成功したなどと吹聴しているのだ。ここは絶対引き下がるわけには行かない。
橇は急なカーブをぎりぎりに抜けていった。
「きゃああああ!」
「わあぁぁぁ!」
だが安心はできない。ここから先に一番危険な“逆落としスパイラル”がある。
「ブリッサ! 掴まって!」
「うん」
コースの行く手がすとんと空中に消えているように見える。あそこからだ!
二人は意識を集中すると、一気にその急斜面に突っ込んでいった。
橇がぐっと下を向き、ぐんと速度を増していく。
ここが最初の“逆落とし”だ。
ブリッサの胸がぎゅっとグレイスの背中に押しつけられ腰に回された手に力が入る。
グレイスは歯を食いしばってハンドルを握り、橇の安定を保った。
辺りの景色が矢のように飛び去って行き、それから次いで、名前の残り半分の元となった急カーブが待ち構えている。
普通のスピードなら回れないわけではないだろう。だが彼女達は逆落としで加わった猛スピードでそこに突入しなければならないのだ。
「行っけ~~!」
「うおぉぉぉ!」
思わず喉から叫び声がこぼれる。
次いで箱橇はその“スパイラル”に突っ込んでいって……ほとんど真横になりながらもカーブを曲がりきった。
「やった!」
「だめ、グレイス!」
「え?」
と、思った瞬間だ。
二人はすぽーんと空に跳ね上げられていた。
《うわ、やばっ!》
グレイスはふわっと宙を何回か回りながら飛んでいったかと思うと、ずぼっと深い雪だまりの中に突っ込んだ。
「あたたたた……」
体中雪まみれになって体を起こすと……彼女の姿がない!
「ブリッサ?」
「大丈夫よ……」
少し離れた雪の中から同じく真っ白になったブリッサが顔を出す。グレイスはほっと安堵の息を吐いた。
「怪我しなかった?」
「大丈夫よ。あんたは?」
「こっちも大丈夫。あ、ちょっと擦りむいたかな?」
ブリッサはそれを聞いてはあっと白い息を吐くと、今度は真っ赤になって怒り出した。
「だから一個目で気を抜いたらダメだって言ったじゃない!」
「ごめん。でもずっと一個目で失敗してたから……」
「もう、この下手くそ!」
うう……そう言われても今ばかりは言い返せない……
「じゃ、今度はブリッサがア・リーガーやる?」
「いいわよ。あたしの腕前、見せたげるから!」
ア・リーガーとは二人乗りの箱橇の前に乗って操縦する事を言う。何でかは知らないが巫女の間ではそう言うことになっているのだ。
ちなみに後ろをサ・ジェッターという。二人乗りの場合、後ろの子は掴まっていればいいかというとそうでもなく、カーブなどで重心移動の息が合っていないとあっという間に宙を飛んでいくことになるのだ。
「じゃ、明日ね?」
「ええ!」
これでリトライの予定は決まったが、問題はもう一つあった。
「で、橇は?」
「ええと……あ! あそこ!」
グレイスがブリッサの指した方を見ると……
「嘘でしょ……あんな下に……」
二人は腰まである雪をかき分けながら斜面を降りていった。
運良く橇はどこも壊れていなかった。
もちろんこれはカテドラルみんなの共有物だ。壊したりしたらそれこそ何をさせられるか分かった物ではない。まあその点は良かったのだが……
二人は顔を見合わせるとため息をついた。ここからでは橇を引っ張って歩いて帰るしかない。橇というのは乗っていくのは素晴らしいが引っ張っていくのは全然つまらない物だ。
グレイスとブリッサが橇を引きながらとぼとぼと戻って来ると、向こうから巫女が一人やって来た。ポルフィーだ。
「ちょっと! グレイス! 何よ、その格好」
二人の姿を見つけて彼女が叫んだ。
「あはは。ハヤブサコースでまた飛んじゃって」
「はあ、また? ま、何度飛ぼうと知った事じゃないけど、それより今日のお勤め、どうするつもりなの?」
「え? 今日の?」
そう言ってからグレイスは午後に臨時のミサがあって、そこでこのポルフィーと共に“心臓への祈り”の当番になっていたことを思い出した。
「うわわわわ!」
「そんなことだと思った。早く着替えてきなさいよ!」
「ごめん、ブリッサ!」
グレイスはブリッサに向かって両手を合わせる。
「ええ? これどうするのよ?」
ブリッサは箱橇を指さした。
「だから、ごめん!」
こいつは結構大きくて重いから、二人で引っ張っても結構疲れるのだ。
「あんたねえ……」
ブリッサの目が吊り上がる。グレイスは慌てて手を振った。
「だからほら、始まりの巫女様も言ったじゃない? 憎むよりもたくさん許してやりなさいってね」
もちろんそんなことでごまかされてはくれない。
「もうこんな時ばっかり!」
だが彼女にも分かっていた。グレイスにお勤めがあるのでは仕方がないと。結局一人で橇の片付けをやる羽目になるのだと。ブリッサは地団駄を踏んだ。
「じゃ、本当にごめんなさい!」
グレイスはもう一度ブリッサを拝むと、ポルフィーと一緒に宿舎に走り出した。
これは……晩ご飯のおかずぐらいで我慢してもらえるだろうか?
着替えにポルフィーも手伝ってくれたおかげでミサには何とか間に合った。だが途中のあちらこちらを全力で走っていたせいで息をはあはあ荒げているグレイスを見て、教母のアウロス様がちょっと睨んで頭を指した。ポルフィーが慌ててグレイスの帽子が少し傾いているのを直してくれる。
「ありがと」
「前見て!」
ポルフィーはグレイスより二つ年上で、彼女がこちらに来てからずっと世話をしてもらっているお姉さんみたいな存在だ。だが最近は妙に細かいところにうるさくなってきている。もうすぐ十七歳になって水渡りの儀式をすることになるので、お母さんになる練習をしているのだろう。
それはそうと今日のミサには何でも外国から偉い人が来るらしい。外国の人がどうしてミサに来るのか知らないが、そのために行われる特別なミサなのだそうだ。よっぽどのことがないとそんなことはないのが普通なのだが……
「外国からのお客様ってもう見た?」
グレイスが尋ねるとポルフィーは首を振る。
「ううん。まだ」
「どんな人かな?」
その時教母様がまたじろっと二人の方を見る。二人は慌てて背をしゃんと伸ばした。
ミサの前奏が始まった。
臨時ミサなので会衆席にはカテドラルの関係者しかいないが、と思っていると後ろの扉から数名の男が入ってくるのが見えた。前の三人の服装は見たところ政府のお偉いさんのようだ―――ここは嶺国の三大カテドラルの一つなので、偉い人はそれなりによくやってくるのだ。だがその後ろから付いてくる人は何か変わったコートを着ている。嶺国では見ない型だ。
《それじゃあれがお客様?》
男達は近づいて来ると最前列に座ってじろっとこちらを見た。グレイスとポルフィーは慌てて目を反らした。
《なに? あれ?》
後から来た変わったコートを着た男―――丸い眼鏡をかけて少し背が低くやたらに鋭い目つきをした男が、こちらを見てにたーっと笑ったような気がしたのだ。
いつもならとても誇らしい気持ちになれるこのお勤めだが、今日は何だか凄く不安だった。
おかげで妙に緊張してくるが今はともかくお祈りに集中するしかない。
グレイスは礼拝堂の正面を見上げた。
そこにはアニムスの象徴、四枚羽根の大きなクルスが聳え立っている。彼女達はその神アニムスに仕える巫女なのだ。
前奏が終わると巫女見習いの子供達が一斉にアニムスへの賛歌を歌い始める。子供達の発声はちょっとぎごちない。それもそのはず。彼女達は自分が何を歌っているのかまだよく分かっていないからだ。
アニムスへの礼拝は伝統的に“始まりの巫女の御言葉”という嶺国語とは違う言葉で行われている。その言葉は実は宮国という隣国の古語なのだが、ここでは聖歌の歌詞も祈りの言葉も教主様のお話もみんなその言葉で行われるのだ。
そのため巫女になるためにはまずこの言葉を覚えるところから始めなければならない。
《最初からだったら絶対落ちこぼれてたわよね……》
あの授業を一からやらされていたらと思うと背筋がぞっとしてくる。
グレイスは元々宮国に隣接した国境地帯の出身だったので、最初から文法や単語がある程度分かっていたのがラッキーだった。おかげで両親を失った後もこのカテドラルに巫女見習いとして潜り込むことができたのだ。他の地方出身の子はものすごく苦労していたが……
賛歌が終わると今度は教主様がアニムスの御使い達の事績についての説話を始める。
もちろんこれも始まりの巫女の言葉で話られるのだが、これが長い。時々区切りがあってそこで少し音楽が流れたりはするのだが、子供達はその間じっとしていなければならないのだ。冬の寒い日には結構堪える。
でも少し大きくなって教主様のお話の意味が分かるようになってくると、それが決して退屈なだけの時間ではなくなってくる。特に始まりの巫女様方の話は何だかすごく夢みたいで、彼女達のことを想像しているととても楽しくなってくる。例えばこんなお話がある。
―――始まりの巫女様方が嶺国にいらっしゃったとき、その時もとても寒い冬だった。
慣れない寒さに途方にくれていた巫女達を泊めてくれた親切な村人がいた。村人の家族は巫女達を丁重にもてなした。
だがその夜、巫女達が目を覚ますと家の子供達が泣く声がする。見ると小さな寝床の上に村人の家族全員がぴったりと寄り添っていて、彼らは服を何枚か重ね着しているだけで、子供達は寒さに震えて泣いていたのだ。貧しい家族は自分たちの食べ物や寝床を提供して巫女達をもてなしていたのだった。
その姿を見て驚いた巫女は言った。あなた方は遠くから来た私たちにとても良くして下さいました。でも私たちにはこのような物しか差し上げられる物がありません。
それから巫女は背中の羽を大きく広げると、その羽をむしり取ってふうっと吹き上げた。それはひらひらと舞い散ると子供達の寝床に飛んでいって暖かな布団に変わった。その布団は空気のように軽く春のように暖かかった。
村人は巫女達に感謝しようとして目を見張った。彼女達はそのために自身の翼を失ってしまっていたからだ。村人達は尋ねた。あなた方は翼を失ってどうやって元の世界にお戻りになるのですかと。
すると巫女達は答えた。光に満ちていても心の冷え切った神々の世界より、体は凍えていても心に温もりの満ちた人々と共に歩む方が私たちは幸せなのです、と―――
そんないい話なのだが、最初聞いたときは羽をむしってしまった巫女様の翼ってやっぱり手羽先みたいになっていたのだろうか、とかそんなことが気になって尋ねたら怒られたこととか……普段ならそんな思いに浸って楽しむこともできたのだが……
「げほっ! げほっ!」
今日は全然そういう気分になれなかった。最前列の遠来の客が、ひっきりなしに苦しそうな咳をするのだ。何か病気なのだろうか? だとしたら神殿ではなく病院に行くべきだと思うが……それとも不治の病でもう余命幾ばくもないとか? でもそれなら何で外国の神様の所に来るのだろう? あの人の国に神様はいないのだろうか?
そんなことを考えていると荘厳な音楽が鳴り響き、それまで退屈そうにしていた子供達の目が輝いた。
《よしっ!》
グレイスとポルフィーは目配せすると立ち上がり、礼拝堂の正面に置かれた祭壇の両脇に歩み寄って跪いた。
教主様は大きく両手を挙げるとアニムスを称えて祈る。それが終わると厳かな手つきで祭壇にかけられていた覆いを外した。
グレイスもポルフィーも胸を高鳴らせながら待ち構える。
覆いの下からはきらきらとした美しい宝玉が現れた。その大きさは人の頭よりもう少し大きいくらいで、その中心部がほのかに暗い緑色に輝いている。
いつ見ても美しい。
この宝玉は“アニムスの心臓”と呼ばれる聖遺物で、嶺国に三つしかない。西、東、南の三大カテドラルはこの宝玉を収めるために建立されたのだ。
そのときだ。
「うおぉぉぉぉ!」
会衆席の最前列に座っていた、あの気持ち悪い外国人がおかしな叫び声を挙げたのだ。
それから周囲の視線に気づくと少々気まずそうに咳払いをする。
《なに? あれ……》
再び教主様が祈りを捧げる声が聞こえ始める。
グレイスは慌てて正面の宝玉に意識を戻した。
教主様の祈りは続き、再び彼は両手を広く差し伸べると天に向かって唱える。
「ああ、アニムスよ、我らの祈りを聞きたまえ
我らが道を指し示したまえ
汝の道をゆく者に絶えざる恵みを与えたまえ
我らは信ず。その道こそがいつしか我らを希望の大地へと誘わんことを」
その言葉に合わせて、グレイスとポルフィーは宝玉に口づけをする。
宝玉は石とは違って冷たくはなく何か不思議な感触がする。
と、宝玉の中心に小さな光が幾つも現れて、同時に中心の輝きがみるみる増していった。やがて聖堂内は宝玉から放たれる明るい緑色の輝きで満たされた。
「おおおおお!」
またあの男のうめき声だ。今度は何だ? そう思ってちらっとそちらの方を見ると……
《……!!》
グレイスとポルフィーは蒼くなった。
なんと今度はあの男が、なにやらよく分からないことをぶつぶつ呟きながらふらふらとこちらに近づいて来るではないか!
《うわ! 来るな!》
近くにいた教母が慌てて立ち上がって男の手を取って引き戻す。いくら外国人でもやっていいことと悪いことがある! 何て礼儀知らずな……
だがその時、聖堂内は別のどよめきで包まれた。
「え?」
振り返ると……宝玉の中に不思議なラインが現れているではないか!
《これって……》
グレイスはポルフィーの顔を見る。それから二人は教主様の顔を見た。
教主様は笑顔でうなずくと会衆に向かって告げた。
「アニムスの心臓にイマージュが現れました。アニムスが私たちの祈りをお聞きくださったのです。皆様、感謝いたしましょう」
高らかな音楽が鳴り響く。これは滅多に演奏されることがない、アニムスの天啓が下された時にのみ演奏される音楽で、グレイスも聞いたのはこれで二度目だ。
巫女はたくさんいるが、そのお役目で天啓を見られるのはとても運がよいのだ。
《やったーっ!》
感動のあまり声も出ないが、ともかくまだお勤めは終わっていない。だが、天啓が下された時の巫女の祈りってどうだっただろうか?
ここで間違えたら何もかもぶちこわしだ。
だがグレイスがお祈りの言葉を間違えるようなこともなくミサはつつがなく終わった。
色々おかしなことはあったにしても、終わりよければ全て良しだ!
天啓が下された場合は続けてそれに感謝するための小ミサが行われるので、グレイスとポルフィーは控えの間に残ってお茶を飲んでいた。その小ミサでは彼女達が主役になる。もちろん生まれて初めてのことだ。
「あたし、お祈りが叶ったのって初めて……」
ポルフィーが感動さめやらぬ表情で言う。
「うん。きれいだったねえ」
アニムスの天啓―――イマージュとも言う―――はそもそも見ることさえ滅多にできない。巫女達はほとんど毎日のようにミサを捧げるが、それでも下手をすると一度も見られなかったという子も多いのだ。
だから自分の祈りにアニムスがお答えくださるなどそれこそ夢のような話で、一生語り継いでいけるくらいの宝なのだ。
「でもグレイス。こんな時に何なんだけど……」
「なに?」
「あんた、本当に緊張すると目つき悪くなるわよね」
「ええ? また?」
これはいつもみんなに言われるのだが……おかげで初対面の子とかからには大抵怖がられてしまう。別に全くそんなつもりはないのだが……そんな彼女を見てポルフィーはにこっと笑った。
「あのお客様も、ガン付けられてるって思ったんじゃないの? だからやって来たんだったりして……」
「ええ~? まさか……」
「なんて、嘘だって!」
「ああ? もう……」
などと二人でお喋りをしていたときだ。
控え室に教母様がやってくると二人に向かって手招きした。
《?》
二人が教母様の前に行って胸に手を当てると、彼女は言った。
「あなた方、教主様がお呼びです。お部屋に行ってらっしゃい」
「え?」
「えっと、どうして?」
もうすぐ彼女達の小ミサが始まる事になっているはずなのだが……
「ミサはそのご用事の後になります」
「あ、はい……」
そういうことなら行かざるを得ない。
教主の部屋への道すがら、ポルフィーがグレイスに尋ねる。
「どういうことよ? あんた何したの?」
「知らないって。それだったらポルフィーには関係ないでしょ?」
「ん……そうだけど」
教主様とはこの西カテドラルで一番偉い人だ。
二人とも彼から呼び出しを受けるのは、おおむね怒られる時と相場が決まっていた。だがどうして今? せめてミサが終わった後にしてくれればいいのに……それに最近は一応そういうことには心当たりがないのだが……
二人は首をかしげながら教主の部屋の扉を叩いた。
「お入りなさい」
中から教主様の声がする。二人が扉を開けて中に入ると……
《うげ!》
そこには教主様の他に先ほどの客人達がいた。
教主様のお部屋と言っても、そこは普通の巫女の部屋より少し広くて執務用のデスクと接客用のテーブルがあることを除けば、他と同じように地味で飾り気一つない。
だが今日はそのテーブルの上に大きな銀色のトランクが乗せられていた。
グレイスとポルフィーは顔を見合わせる。
一体何なのだ?
その時、真ん中に座っていた異国の客人が彼女達の顔を見て言った。
「この子達が? まるで少女のようだな?」
今は公式の場ではないので二人の顔は露わになっていた。
《なによ? この人……まるでってどういう事よ?》
それを聞いて教主が諭すように言った。
「ドクター。そのようなことをお話にいらしたのですか?」
男は大仰に頭を掻いた。
「いや、すまん。ついな。未分化型はこちらでは珍しかったから」
未分化型?
教主は訝る少女達に向かって言った。
「この方はドクター・バルヌフ。アルゲントゥム礁国よりいらっしゃいました」
グレイスとポルフィーは再び顔を見合わせる。
アルゲントゥム礁国―――通称礁国とは嶺国の隣国の一つだが、そこでは水渡りの儀式も行わずに、何と生まれた時に男になるか女になるかを決めてしまうのだというが……
「それからこちらは副首領様」
グレイスとポルフィーは目を丸くした。副首領様って、この国で二番目に偉い人ではないか。確かにここには偉い人も来るとは言ったがそれでもせいぜい地方長官クラスで、こんな重要人物はさすがに特別な儀式で何度か遠巻きに見たことがあっただけだ。
ともかくグレイスとポルフィーは型どおりの挨拶を始める。
「私はここ西カテドラルでアニムスにお仕えする巫女、ポルフィーと申します」
「私も同様にここでアニムスにお仕えする巫女、グレイスと申します」
それから二人は息をあわせて言った。
「「皆様方にアニムスのご加護がありますように」
それを聞いて副首領様はにっこりとうなずいた。
異国のドクターはその間も二人をじろじろと眺めていたが、二人の祈りの言葉を聞いてちょっと微笑んだ。
「うむ。バルヌフだ。よろしく頼むよ」
一体何をよろしくなんだろう?
それは教主様も同様だったようだ。
「それでドクター。彼女達を呼ぶようにおっしゃられた理由は?」
彼が二人を呼んだって?
それを聞いてドクター・バルヌフは大きくうなずいた。
「うむ。そうだな。ではまずこれを見てもらいたい」
彼はテーブルの上に置かれた大きな銀色のトランクの鍵を開け始めた。
「これなんだがな……」
「これは……」
グレイスとポルフィーだけでなく、教主様までが驚きの叫び声を挙げる。
なぜならそこから現れたのは紛れもなくアニムスの心臓だったからだ。
「ドクター! あなたは一体どこからこれを?」
驚いて腰を浮かせかけた教主様にドクターは慌てて手を振る。
「いや、もちろん聖堂から取ってきたわけではないよ。だが詳しい話をする前にまず、ちょっと君たち……」
ドクター・バルヌフはグレイスとポルフィーに手招きする。
「これに祈ってはもらえないかな?」
「え?」
「あの……」
二人はどうしていいのか分からないので教主様の方を見る。だが彼も呆然とした様子でその宝玉を見つめているだけだ。
そこに副首領が口を挟んだ。
「レディストフ教主。私からも頼む」
だが教主様が困惑した顔で答える。
「しかし……祈りには順序がございます」
それを聞いてドクターが言った。
「その辺の手順はすっ飛ばしても構わんよ。とりあえず二人でこれに、本物のアニムス様の心臓に祈る時のように口づけしてはもらえないかな?」
「なんですと?」
教主様がドクターを睨む。だがドクターは涼しい顔で言った。
「本物のアニムスの心臓は、あなた方の神殿に安置されている。これは単に“それに似た何か”ですよ。ならば問題はないでしょう?」
教主様は混乱した様子で副首領の顔を見るが、彼は黙ってうなずいた。
そこで教主様はグレイスとポルフィーの方を見ると言った。
「やってみなさい」
「はい……」
二人は恐る恐るそのアニムスの心臓そっくりの宝玉の両脇に立った。
見れば見るほどそっくりだ。多分こっそりと入れ替えても誰も気づかないだろうし、印でも付けておかないとどちらがどちらか分からなくなるだろう。
二人は軽くうなずき合うと、いつものようにその宝玉に口づけをしてみた。
まるで同じ感触だ。先ほど本物に祈ったところだから間違いない。
しかも……
「おおおおお!」
教主様と副首領が同時に声を挙げる。
何とその“宝玉のような物”は本物のアニムスの心臓同様に美しく緑色に輝き始めたのだ!
この輝き! どう見ても本物としか言いようがないのだが……
《これって……どういう事なの?》
ドクター・バルヌフはそれを目を丸くして見ていたが、やがて満足げにソファに身を沈めた。それから、くっくっくと体を揺らして笑いだし、やがてそれは大爆笑へと変わった。
「ドクター……これはどういう事なのです?」
教主様のその声には怒りと共に、恐れの色が混じっていた。
ドクターは首を振りながら答える。
「すまんな。ともかくあなた方に説明せねばな……」
ドクターはちょっと咳き込むと、一同の顔を見回す。
「あなた方の国と我々の国は、とある共通の国と戦闘状態であることはご存じだと思う」
それを聞いてグレイスとポルフィーもうなずいた。もちろんその話は彼女達もよく知っていたからだ。
そう。今彼女達の祖国、プルンブム嶺国は、南にあるシムラークルム宮国―――通称宮国という国と戦争を行っているのだ。
この西カテドラルがある地域は前線ではないので一見は平穏だ。
だがこの地方からも多くの大人達が戦地に出かけているし、軍需物資を供出したり、そのため働き手が減ったりでこの冬はすごく大変なことになっていることも知っている。
宮国というのは巫女にとってはある意味なじみ深い国だ。前にも述べたとおりアニムスへの礼拝で使われる祈りの言葉は、その宮国の古い言葉なのだそうだ。
だが今の宮国は……正直グレイスはあそこが嫌いだった。
彼らは周囲のどこの国とも交わろうとせず、ずっと孤高を貫いていた。
いや、そう言えば聞こえはいいが、そうではない。
彼らは単に無慈悲なのだ。
彼らは嶺国の人々のささやかな―――冬越しの食糧が乏しいから少し分けてはもらえないだろうか、といった願いにでさえ一切耳を貸そうとはしない。別にただでくれと言っているのではない。それ相応の報酬を支払うと言っているのにだ。
彼女はかつてもっと南方の国境地帯に住んでいたのだが……いや、止そう。今こんなことを思い出してどうするのだ?
ドクター・バルヌフは話し続ける。
「先月のことだ。我々は宮国に対して大侵攻を仕掛けた。礁国のほとんど全生産力を動員して準備した、空中戦艦十五隻と、一千機に及ぶ戦闘艇を投入してだ」
空中戦艦? 一千機の戦闘艇?
それはもういろんな意味でグレイスの想像を超えていた。そんな物が行ったら世界が焼け野原になってしまったりしないのだろうか?
「だか、結果はというと……」
ドクターはそう言って首を振った。
「惨敗だったよ。我々はまたあの悪魔にしてやられたのだ。我が軍は結局宮国の国境地帯を越えることはできず、すごすごと引き返さざるを得なかった」
悪魔! 宮国の悪魔、シムーン!
彼らがずっと他の国と交わることもなく、冷ややかに見下ろし続けられた理由。宮国の秘密。それがシムーンだ。
シムーンは鳥よりも自在に空を舞い、その航跡は空に輝く模様を描きだす。リ・マージョンと呼ばれるその模様には恐ろしい力があって、それに近づいた者は全て跡形もなく消し去られてしまうのだという。
「戻ってこられたのは三分の一にも満たなかった。多くの少年達が空に散った」
「少年達?」
教主様の問いにドクターは悲痛な声で答える。
「ああ。それだけの数を飛ばすのだ。通常の兵士だけでは数が足りない。だからかき集めたのだよ。少年も、老人も、な」
「何と……惨いことを……」
「ああ、そうだ。惨いことだ。でも無駄ではなかった」
ドクターは目の前の宝珠をじっと見つめた。
「前が見えなくなるほどの弾幕を張って、多くの兵士達の命を犠牲にして……だが、その結果我々は落とすことができたのだ。あの悪魔を」
「え?」
それにはグレイス達も驚いた。
そう。宮国の悪魔シムーンは神の乗機とも言われている。それゆえ決して落ちることはないのだと。そんな神の使いに向かっていくような不埒な者は、ことごとく地獄へ送られるのだと。
「落とせたのは多分数機だろうがな……」
えっと……さっきドクターは一千機で行って、三分の一しか戻らなかったと言った。
《ということは、その数機を落とすために六百機以上が犠牲に?》
何だか気が遠くなってくる数字だ。でもそれだけの犠牲を出す必要があったのか? たった数機を落とすために……
その思いを察したかのようにドクターは続けた。
「もちろんそれだけでは大した意味はない。でも我々は、そのうち一機の残骸を礁国に持ち帰ることができたのだ」
そう言ってドクターは宝珠をそっと撫でた。
「しかしそれとこの宝玉の話は……」
教主様はそこまで尋ねてから、驚愕した表情となる。
「ということは? まさか?」
ドクターはにたっと笑って答える。
「ああ。そうだ。この宝珠は、そのシムーンの残骸から外して持ってきた物だ」
「えええ?」
「そんな!」
その途轍もない言葉を聞いて、グレイスとポルフィーも声を思わず挙げていた。
アニムスの心臓が、シムーンに? 宮国の悪魔に付いていた?
それからじわじわとその言葉の重い意味がグレイスとポルフィーにも分かってくる。
「まさか……そんな……」
教主様が恐怖に満ちた表情でその宝珠を見つめる。
ドクターは黙って首を振ると、また語り出した。
「この宝珠は今、彼女達の協力によってその見かけやサイズだけでなく、その機能についてもあなた方のアニムスの心臓と区別が付かないことが分かった。これはどういう事だと思いますかな?」
教主様はじっと宝玉を見つめたまま何も答えない。ドクターは話し続けた。
「もしこれが同じ物だとしたら……私は二つの可能性があると思う」
それからドクターは周囲の者達の顔を見た。
「最初の可能性はすなわち、あの宮国の悪魔が文字通り、あなた方の神だと言うことだ。シムーンに逆らうことは、神に逆らうことだ。彼らがあなた方に滅びをもたらそうというのであれば、それを甘んじて受けねばならない。そしてその神に刃を向けた我々の上には……天上の業火が降り注ぐことになるだろう。全ては神の意志だ」
ドクターはにやっと笑う。誰も声を挙げられない。
グレイスは心臓をぎゅっと掴まれたような悪寒を感じた。
「だが、そんなことはない。私はもう一つの可能性の方を信じている!」
グレイス達が思わずドクターの顔を見ると、彼は真剣な表情で続けた。
「それは……シムーンはただの機械だ、ということだ。だから我々は落とすことができた。だから我々はこれを研究することで、やがてはこの大空を自在に飛ぶ翼を得ることができるのだと!」
それからドクターは主教様の顔を真っ直ぐと見る。
「しかしそうなるとあなた方には大変申し訳ないことになる。これが単なる乗り物の部品だったとするならば、あなた方の聖堂に安置されているあの宝珠もそうだったということになる。図らずもここであなた方の信仰が試されてしまうことになるのだが……」
主教様の顔が真っ赤になる。
一体この話をどういう風に聞けばいいのだろうか?
ドクターは続ける。
「だがこれだけは信じて欲しい。我々の望みはあなたを困らせることではない。我々は二度とあんな事を繰り返したくないだけなのだ。少年達の命を空に散らせるようなことはあれで最後にしたいのだ。だからあなた方に協力して欲しいのだ。子供達は子供達らしく過ごせなければならない。それはあなた方も分かっているはず。寒い冬の夜……」
寒い冬の夜!!
その時副首領様が割って入った。
「ええ。分かっています。それ以上は」
「あ、ああ。すまん」
ドクターはそう言ってトランクの蓋を閉じ始めた。光はもう消えていた。
グレイスの平穏な日々はこの日を境に永久に終わりを告げた。
それから数日もしないうちに、特別なお勤めのための巫女が募集された。
聞くところによると今度嶺国と礁国で共同して戦うことになったが、そのためには彼女達の特別な祈りが必要なのだという。ただその祈りを行う場所が大変な所なので体が丈夫な子でなければいけないらしい。
よく分からないが体の丈夫さなら誰にだって負けない自信がある。
グレイスは喜んで募集に応じた。