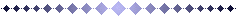第2章 空軍基地
募集に応じた巫女達が連れてこられたのは何と礁国内にある空軍基地だった。
そこで彼女達の目を引いたのは居並ぶ無数の飛行機械群もそうだった、何よりも真冬だというのに雪が全然積もっていないということだ。
それはとても幸せなことだった。
すなわちあの大変な除雪作業や雪下ろしをしなくてもいいということなのだから!
次に行われたのが身体検査と運動会だった―――いや、正式には運動能力テストというものだったらしいが、みんなで走ったり跳んだりロープを上ってみたりと楽しいことこの上ない。
そのうえ出てきた昼食は味はそこそこだが、何とおかわり自由だ!
その後注射で血を抜かれたりしたのだけは少々痛かったが、正直お勤めもせずこんなことばっかりやってていいのだろうかと心配になってしまったくらいだ。
だが楽しいことばかりではなかった。この能力テストの結果によって成績の良い二十四名が選ばれ、残りは故郷に帰ることになってしまったからだ。
もちろんグレイスはその中に入ることができたが、一緒に来た友達と分かれるのはかなり残念だった。
しかし残ることができた西カテドラルの仲間にはブリッサやカナーリ、ファールケ、マリキータ、ラグーナ、それにポルフィーも一緒だ。これだけいれば寂しくはない。それに普段はなかなか行き来のない東や南のカテドラルの子と知り合いになれるチャンスでもある。
その夜、彼女達は初めてここに集められた理由を説明された。
空軍基地のブリーフィングルームに集められた巫女達の前で、中年のがっしりした体格の男が話を続けている。
彼はリフェルドルフといってこの基地の総司令で、今回の作戦の総指揮官なのだそうだ。
その左にはあの日出会ったドクター・バルヌフが座っている。反対の隣には嶺国から来た軍人ベネトラルフ副司令と教母のアウロス、プルミエラ、リエラの三人が並んでいる。彼女達は西、東、南のカテドラルから一人ずつ派遣されていて巫女達の世話役になる―――ということなので、そこまで羽を伸ばすわけにはいかないというのが少々残念だが。
《それにしても……》
どういった感想を述べればいいと言うのだろうか?
色々なことが青天の霹靂すぎて何からコメントしていいのか迷ってしまうのだが……
話によると彼女達の使命とは何と、宮国の奥深くまで潜入して“アンシエンシムーン”というのを取ってくることなのだという。それは何故か巫女が祈らないと動かないらしいので、彼女達自身がそこまで行かなければならないのだと……
《本当にすごく大変な場所でお祈りしなきゃならないんだ……》
何だかもう奇想天外すぎて笑いが込み上げてくる。
リフェルドルフ総司令が話し続けている。
「……以上が今回の作戦のあらましである。正直、このようなことは言いたくないのだが、これは控えめに言って“極めて危険な作戦”と言わざるを得ない。そのような作戦に君たちのような、その、巫女様方を参加させなければならないというのは、我々としても極めて心苦しい物である。だが、先ほど説明をしたように、我々が普通にシムーンに向かって行った場合、そのキルレシオは一対百を遙かに超えている。このような消耗戦をいつまでも続けるわけにはいかない。そして……」
そこまで言って総司令は横のベネトラルフ副司令をちらっと見た。副司令はちょっとため息をついてからうなずいた。それを確認してから司令は続けた。
「先ほど嶺国より連絡が入ったのだが、嶺国の機甲師団が先日、大規模な南進作戦を行った。だが……彼らはほぼ全滅したそうだ」
巫女達の一部から驚きの叫びが上がった。
「あの、それって本当なのですか?」
そう尋ねたのはグレイスの少し前に座っていた、綺麗な長い黒髪のきりりとした顔をした少女だ。
「尋ねる時は挙手してから行いたまえ」
「あ……」
少女は慌てて手を挙げる。それに答えたのは副司令だった。
「それは事実です。本国よりの報告によれば、我が国の第一、第二機甲師団が宮国北部地方を占拠すべく南進を開始しましたが、その行動は国境付近で宮国シムーンに発見され、攻撃を受けてその数の七十パーセント以上を失い、作戦を断念せざるを得ませんでした」
「ええ?」
グレイスのちょっと左に座っていた可愛らしい少女が声を挙げる。
「報告に寄れば、やって来たシムーンは総勢三機」
「三機? たった三機ですか?」
先ほどの黒髪の少女が驚いた声を挙げる。副司令はうなずいた。
「はい。そうです。たった三機のシムーンによって二百台以上の戦車部隊が一瞬にして壊滅したそうです。生存者からの報告に寄れば、最初は二機のシムーンが来たため応戦していたところ、後から更に一機が合流すると、空に美しい模様を描き始めたそうです。それが完成した途端にそこから凄まじい閃光が発して地上を襲い、その光が消えた後には戦車の残骸以外は何も残されていなかったといいます」
巫女達はその話に息を呑んだ。
「それが、リ・マージョンだ」
そう言ったのはドクター・バルヌフだ。彼は礁国ではシムーンに関する最高の権威なのだそうだ。
巫女達の目がドクターに集まる。
「シムーンはその光跡で空にリ・マージョンを描く。それはその形状によって様々な効果を持つ。我々はまだそれについて何も知らないと言って良い。我々の戦っているのはそういう敵なのだ。そんな奴らと戦うにはどうすればいいか? ただ闇雲に突っ込んでいっても命を無駄にするだけだ。だから我々は知らなければならない。シムーンのことを。どうしてシムーンが空を飛べるのか? どうしてリ・マージョンにはあんな破壊力があるのか? それにどうしてシムーンは君たち、まだ性別を得ていない巫女によってのみ、操縦ができるのか?」
ドクターは拳を握りしめた。
「その謎を解くために、せめて一機でもいい。一機でもいいから我々はシムーンを手に入れなければならないのだ」
巫女達は黙ってうなずいた。
続けてリフェルドルフ総司令が話す。
「そしてもし、更に多くのアンシエンシムーンを手に入れることができたなら、我々はそれを使って“もっと直接的に”敵シムーンに対抗できるかもしれない。そうすれば、戦争を早期に終結させることも可能だと考えられる」
巫女達は再びうなずいた。
シムーンに対抗するにはシムーン―――非常に分かりやすい話だ。
総司令はそんな彼女達の顔を見ながら言った。
「この作戦がとても重要なことは分かって頂けたと思う。だが同時にとても危険なことなのも事実だ。だから我々も無理強いはしたくない。なのでまず最初に言っておく。今ならまだ引き返すことはできる。抜けたいと思うのであれば抜けてもらっても構わない。誰もそのことについてとやかく言うことはないだろう」
総司令はその言葉を聞いて彼女達が動揺すると思ったのだろう。だが巫女達は特に変わった様子もなく黙って彼の顔を見つめているだけだ。
「ここで言い出しにくいのであれば、後から私の所に来てもらってもいい」
だが巫女達は何でそんなことを言うのだろう? といった様子で、少し不思議そうに彼を見つめるだけだ。総司令少し困惑した顔になり、それから言った。
「以上だ。何か質問は?」
ちょっとの間を置いて、右の方にいたすらっとした、グレイスから見てもとても凛々しい感じの子が手を挙げて尋ねた。
「あの、これから私たちがしなければならないことですが、それはこういうことでよろしいでしょうか?」
総司令は軽くうなずいてその先を促した。
「私たちはこれから、あの黒カタツムリとシムーンがたくさん待ち構えている国境を突破して、宮国の最も奥深くにある最も神聖な場所にこっそりと忍び込んで、そこにあるかどうか分からないアンシエンシムーンを発見して、動くかどうか分からないそれを、操縦したことのない者が操縦して、敵のシムーンが来ればそれを速やかに撃退しつつここに戻ってくればいい、ということですね?」
それを聞いた巫女達は一斉に吹き出した。見事に的確なまとめだ。
総司令は苦虫を噛みつぶしたような顔になる。
「笑い事ではない! だが……その通りだ」
その答えを聞いて少女が問い返した。
「でもそうすれば、私たちは始まりの巫女様が失ったという翼を取り戻すことができると、そうおっしゃるんですよね?」
「え?」
総司令がちょっと意表を突かれたような顔をする。少女は今度は横にいるドクターを見て言った。
「先ほどドクターは、始まりの巫女がシムーンに乗っていた巫女、シムーン……シビラ? だったとおっしゃいました。そして今回の作戦は彼女達が失った翼を取り返すための物だとおっしゃいました」
ドクターはうなずいた。
「シムーン・シビュラだな。ああ。その可能性が高いと言った」
始まりの巫女とは、この嶺国でアニムスの教えを初めて説いた神官に付き従っていた七人の巫女のことだ。彼女達がグレイス達の大々々々先輩に当たる。巫女だったら誰でも彼女達のことを心から尊敬している。
「それについては私の知り合いの民俗学者がいて、そいつの持論だったがな。そいつの師匠は“アニムスとテンプス・パテューム”という論文を書いたあの高名な先生なんだが……だが、私は半信半疑だったがね。さっきまではな」
ドクターはそう言ってにやっと笑った。
《さっきまで? どういうことなんだろう?》
するとドクターが急にグレイス達を見た。西カテドラルから来たブリッサ、カナーリそしてファールケといった箱橇仲間と一緒に座っていたのだが……
「先ほど私がシムーンについて色々と説明した時、君たちは笑ったな?」
「え? あの……」
「はいっ!」
慌てる四人を見てドクターはにやにやしながら続ける。
「シムーンの乗員のことを宮国ではシムーン・シヴュラと言って、必ず二人でペアを組む。その際に操縦を担当する乗員のことをアウリーガといい、ナビを担当する乗員をサジッタという、というくだりだったと思うが……」
グレイス達は赤くなってうなずいた。
でもそんなの笑わずにはいられないだろう? 四人で一緒に思いっきり吹き出してしまってドクターにみんなの前で吊し上げられてしまったのだ。恥ずかしかったなんて物ではないが、でも何でまた今そんなことを蒸し返すのだ?
ドクターはそこで急に真面目な顔になると続けた。
「ア・リーガーとサ・ジェッターという言い方は巫女の間では良く使われるが、普通の子供はあまり使わないそうだな? だとしたらどうだろう? その始まりの巫女様方が橇で滑っている見習い巫女を見て、それを自分たちのかつての役割になぞらえたのだとしたらどうかな? 彼女達がシムーン・シビュラでなければ果たしてそんなことを言っただろうか?」
巫女達は息を呑んだ。
「そしてもう一つ問おう。もし彼女達がシムーン・シビュラだったとしたならば、彼女達が失った翼とは一体どんな物だったと思うかね?」
ドクターはにたっと笑った。
「もちろんそれはシムーンだ。いや、時代的にはこれから君たちが取ってこようとしているアンシエンシムーンその物かも知れない」
巫女達がどよめいた。
「もちろんこれは、私の想像でしかない。でももしそれが正しければ、君たちがシムーン・シヴュラの末裔なのだとすれば、すなわち……」
ドクターは最初に質問をした少女に向かって答えた。
「先ほどの君の質問への答えはイエスだ。君たちがこの作戦を遂行できたなら、文字通り、君たちの始まりの巫女達が失った翼を再び取り戻すことができるのだ、と答えよう」
それを聞いて少女はにっこりと笑った。
「ありがとうございます」
なんてことだ!
グレイスは隣に座っていたカナーリの顔を見た。いつもは喧嘩ばっかりで意見が合った試しのない彼女だが、この時ばかりは互いに全く同じことを考えていることがすぐ分かった。
《私たちが空を飛べるんだって?》
空を飛ぶ? どんな気持ちだろう? あの箱橇でぶっ飛ばすのも面白いが、何よりもあれはあっという間に終わってしまう。二人でひーひー言いながら三十分以上もかけて橇を裏山の上に引き上げても、下る時は一瞬だ。
でも空の上なら……もしかしてずうっと飛んでいけるのだろうか?
ごんごんと総司令がテーブルを叩く音が、上の空になりかかった巫女達をまた現実に引き戻した。
「他に何か質問は?」
巫女達は何も言わず、ただ総司令の顔を見る。
「それでは解散」
巫女達は歓声を上げながらブリーフィングルームを出て行った。
彼女達が出て行った後のがらんとした部屋の中で、リフェルドルフ総司令は副司令のベネトラルフに尋ねた。
「君の国の巫女様方は、一体どうなっているのだ? 死ぬのが怖くないのか?」
それを聞いてベネトラルフは答えた。
「我が国の巫女は、みなアニムスにその命を捧げておりますから」
リフェルドルフは信じられないと言った表情をしたが、それ以上は何も尋ねなかった。
グレイス達が礁国の空軍基地に来てから一ヶ月以上が経過していた。
故郷ではまだまだ冬のさなかの時期だが、驚くことにここでは既にあちこちに春の息吹が見て取れる。
「うわ……もうちょっと着て来た方がよかった?」
グレイスは手をこすりながらつぶやいた。
日が照って暖かそうだったので喜び勇んでちょっと薄着で出て来たら、やっぱり外はまだ結構寒かった。出てきた理由はアントレーネとの待ち合わせだ。これから二人で山菜採りに行くのだが……
《やっぱちょっと戻って服着てこようかしら?》
でも待ち合わせの時間はもうすぐだ。遅れるわけにはいかないし……
「何とかなる……よね? 多分」
アントレーネはこちらに来てから仲良くなった子で南カテドラル出身だ。最初の頃はみんな出身カテドラルごとに固まっていたのだが今ではもうみんな顔なじみだ。
一ヶ月も一緒に暮らしていると、この殺風景な基地もわが家みたいに思えてくるから不思議だ。
待ち合わせの場所は基地の“目抜き通り”と言われているところだが、無骨なバラックの建ち並ぶ通りに並木がちょっと植えられているだけで、ちょっとその名にはふさわしくない。
グレイスは立っているだけだと寒いので軽く準備運動をするとそのあたりを走り始めた。
少し走ったところで出会ったのはヘリファルテとシュトラーレだ。
グレイスが二人に会釈すると、ヘリファルテが言った。
「や、今日もトレーニングかい?」
「いえ、ちょっと寒いから走ってるだけで」
「頑張ってね」
シュトラーレも微笑んで手を振る。
巫女達の中でも一番目立っているのはやはりこのヘリファルテとシュトラーレ、それにもう一人イーグレッタの三人だろうか。ヘリファルテとシュトラーレは南カテドラル、イーグレッタは東カテドラル出身だ。
あのブリーフィングの時質問をしていたのがヘリファルテだった。すらっとしてつやつやしたチョコレート色の髪が美しいが、何よりもその瞳に魅了されてしまう。ちょっと悪戯っぽいようでいて、でも真っ直ぐに心の底まで射貫いてくるようなその眼差しは、グレイスでもちょっとくらっとしてしまいそうだ。
彼女に並んで歩いていたシュトラーレはそのヘリファルテのライバルとも恋人とも目されている、黒髪のロングで、一見とても女らしく見える。だが性格のきつさはこちらに来ている巫女達の中でも随一かもしれない。だが同時に他の子をいたわる気持ちもあって、今では誰からも尊敬されている。
彼女達は南カテドラルから来ていて、ずっと小さい頃から何かと競い合っているそうだ。
この二人に匹敵できるのが東カテドラルから来たイーグレッタだ。とても綺麗なウェーブのかかった濃い金髪で、一見おっとりしているようだが何をやらせても抜群の成績なのだ。
この三人が訓練の成績も常に上位三位を独占していると、もはや張り合おうという気すら起こらない……などと思っていたら出くわしたのがそのイーグレッタだ。
「あ!」
グレイスが軽く手を振るとイーグレッタも会釈を返す。
その横に誰かがぴったりくっついているが、それは彼女の妹アリエスだ。彼女はグレイスをみてもちょっとうなずいただけですぐ姉に向かって何かを話し始めた。何かこういった空き時間にイーグレッタを見ると絶対に彼女がくっついているように見えるのは偶然だろうか?
彼女達と別れてしばらく走ると射撃場に来る。そこにいたのがショートカットの男っぽい少女だが、それがラテルネだ。
彼女はグレイスが走ってくるのを見て言った。
「何? お前、何か罰でも食らったのか?」
「ちょっと寒いだけよ!」
代わりにいい感じの競争相手となっているのが西からの腐れ縁カナーリと、南のヴォルケ、それにこの東のラテルネだ。
「また撃ちに行くの?」
「ただで練習し放題なんだぞ?」
彼女は大きくなったら猟師になるとかで、射撃が大好きなのだ。
ラテルネと分かれてまたしばらく走っていると、黒髪ツインテールの少女と、赤毛のお下げをした子がやって来る。こいつらが西からの腐れ縁、カナーリとファールケだ。西カテドラルでは主に箱橇とかスキーとかスノーボードとかいったジャンルにおいて、グレイスとブリッサ組の宿命のライバルだった奴らだ。
カナーリがじろっとグレイスを見ると意地の悪そうな声で言う。
「何でこんなとこ走ってるのよ?」
グレイスももちろん相手を見下したような声で答える。
「普段の努力を欠かさないからよ! あんた達はどこに“遊びに”いくのかしら?」
などと挑発したら普通なら乗ってくるはずなのに、ファールケがそばかす顔に満面の笑みを浮かべながら答えた。
「メイフライに乗せてもらおうと思って」
「え? あれに? いいの?」
「頼んだらOKだって」
メイフライというのは礁国機の旧型機で、ふわふわゆっくりとしか飛べない代わりに、比較的落ちにくい。しまった……あれって頼めば乗せてもらえるのか?
グレイスはかなり心が動いたが、さすがに今日はそういうわけにはいかない。
「じゃあゆっくり“遊んで”らっしゃいね!」
「あんたも“トレーニング”、頑張ってね!」
捨て台詞を残しあって二人とは別れる。
《うぬ~……》
これは誰かを誘って乗りに行くべきなのだろうか? 誘うとしたら間違いなくブリッサだが……彼女はこちらの水が合わないのか最近体調を崩し気味だし、ポルフィーは……
《大丈夫かな。やっぱり今日誘ってあげた方が良かったかな?》
だが彼女が山菜採りなどに興味がないのは前々からだし……
《調子治るといいんだけど……》
ここに来た巫女達はそれぞれよりすぐりの体の丈夫な子達だ。だから走ったり跳んだりしている分にはみんなそんなに差があるわけではない。だが飛行訓練となると今まで誰もそんな経験はなかったわけで、そこで初めて向き不向きというのが出てきてしまう。
単に真っ直ぐ飛ぶだけならばいいのだが、これにごちゃごちゃした機動が加わって来るとすぐ自分の向きや進行方向が分からなくなってしまうのだ。でも空の上で方向感覚を失ったら致命的な事になってしまう。グレイスもコツを掴むまでちょっと時間がかかったが、この感覚が掴めない子がまだまだ多いのだ。
そんなわけで西から一緒に来たグレイスの姉貴分に当たるポルフィーだが、彼女がちょっと今スランプ気味だった。グレイスが教えてあげられるのならいくらでも教えてあげるのだが……
《それともアントレーネ誘ったら来てくれるかな?》
でもグレイス達が―――どうやら彼女達は西のスピード狂とか暴走四天王などと言われているらしいが―――暇を見ては箱橇を山の上まで引っ張り上げて“滑り落ちる”のが何よりも楽しかったという話をしたら、さすがに引き気味だったし……
グレイスはあたりを一周してまた待ち合わせ場所まで戻ってきた。
《えっと、まだかな?》
彼女は周囲をきょろきょろと見渡すが、アントレーネの姿はない。約束の時間は過ぎてしまっているようなのだが……代わりに来たのはヴォルケだ。
彼女はアントレーネと同じ南カテドラルの子だが、何かいつも生真面目な顔で本を手にしている。
「あ、ヴォルケ、アントレーネ見なかった?」
ヴォルケは街路樹の下のグレイスをちらっと見たが……
「知らないわ」
そう言うとそのまま行ってしまった。
んー、彼女は何だか苦手だ。
それはそうとどうするべきだろうか? 軽く走ったせいで体は暖まったが、動くの止めたらまたすぐ冷えてくる。
グレイスは仕方なくその場でスクワットを始めた。
《これじゃ何かいつもと同じじゃない……》
今日は週一回の休みの日だというのに。
彼女達の毎日はまず起床して皆で朝のお祈りを行い、その後朝食を取る。
午前の訓練はまず基地一周のランニングから始まる。基地は結構広いのでそれだけで軽く一時間近くはかかるが、山の中を駆け回って育ったグレイスにとっては平たい場所をただ走るなど単に退屈なだけだ。
それが終わると今度は座学だ。まずは礁国の言葉を覚えなければならないのだが、礁国語は嶺国語とほとんど同じで宮国語に比べて遙かに覚えるのは簡単だ。
座学は毎日ではなく、そうでない時は通常の戦闘訓練も行われる。教官の講義を聴いているのは少々眠いが、銃を撃ったり格闘をしたりとかするのはなかなか楽しいものだ。
だがやはり何といっても訓練の華は飛行訓練だ。
礁国にはシムーンによく似た“シミレ”というのが二機あった。ドクターが言うには“シムーンの劣悪なコピー”なのだそうだが。
しかもこれは礁国の人が作ったのではなく、宮国に潜入した部隊が決死の覚悟で分捕ってきたものだという。シムーンの操縦方法は大体これと同じらしいから、これが飛ばせればシムーンも操縦できるはず、なのだそうだ。
だが使えるシミレは二機しかない。しかも複座機と単座機が一機ずつなので、最初は教官が一緒に乗れる複座機しか使えない。要するに訓練は一度に一人しかできず、他の子はずーっと順番待ちをしていなければならない。
そのためシミレは早朝から夕刻まで、みんなが慣れて夜間飛行訓練が行われるようになるとほぼ一日中稼働しっぱなしになる。そのため上記の日課の色々なタイミングにシミレ訓練が挟まることになって、スケジュール表は個人個人で全くバラバラだ。
そんな感じで時々やってくるシミレ訓練だけでは間に合わないので、通常の午後は礁国の練習機で飛行練習を行うことになる。操縦方法はかなり違うが、ナビゲートの訓練ならばこれでも十分だし、飛行感覚を養うのにも役立つし、いざというときに礁国機が操縦できれば何かと便利なのも間違いない。
最初はどちらも同じ空飛ぶ機械なのだからと思っていたのだが、シミレと礁国の飛行機とではまさに月とスッポンの違いがあった。
まず何より操縦のしやすさだ。シミレだとすぐに思った通りに飛ばせるようになるが、礁国機は全然言うことを聞いてくれない。上下に動いたり空中で止まったりきゅっと引き返すようなこともできないし、急に曲がったり上昇や下降をすると体が重くなったり頭がくらくらする。直線速度はまあまあなのだが、これでは真っ直ぐしか走れないイノシシみたいな物だ。
また礁国機には燃料という物が必要だ。これがないと飛び上がることもできず、尽きたらそこで落ちてしまう。その上うっかり高速でぶん回し続けると火を噴いたりすることもあるというから怖い。
だがシミレはその気になればいつまででも飛んでいられるし、爆発したりする心配もない。
そして何よりも―――これが一番肝心なところなのだが―――シミレはかわいい!
このカタツムリの殻みたいな物がくるくる回っているのを見ると、何だかそれだけで和んでしまう。色もきれいな水色とピンクだし。本物のシムーンにはこの回るのが二つ付いているとか。そのせいかどうか知らないが、その性能はこのシミレが足下にも及ばないのだそうだ。と言われてももはや想像も付かないのだが……
だからこれを見た後に礁国機を見てしまうと、悪いけど正直この鉄くずがよく飛んでいる物だと別の意味での感動を覚えてしまう。
だがこの基地にいる礁国の兵士達はそれで出撃していかなければならないのだ。シミレはあのドクター達がずっと研究しているが、未だにそれがどうして飛ぶのかさえ解明されていないらしい。つくづく兵士達が可哀相になってくる……
などと考えていると遠くから声が聞こえてきた。
「グレイス~! 待った~?」
振り返ると青みがかった髪でくりっとした目をした小柄な少女がこちらに向かって走ってくる。
「アントレーネ!」
グレイスは手を振った。
「あは。ごめんね。遅くなっちゃって」
「どうしたの?」
「ちょっとお手紙の仕分けを手伝っててそれで」
「え? じゃあ返事来たの?」
「うん」
アントレーネはうなずくとポーチから封筒を取り出してちらちらさせた。
「あれ? そんな可愛いポーチ持ってたっけ?」
「え? ああこれ、グラナータが作ってくれたの」
グラナータはアントレーネと同じく南カテドラルの出身で、ふわふわした髪の毛の可愛い子だ。
「へえ、彼女って裁縫が得意なんだ」
「うん。そうなの」
アントレーネはにこにこしながら手紙をポーチにしまった。
彼女と仲良くなったのは朝のランニングの時だった。基地の周囲の道は結構凸凹しているのだが、彼女がそこでうっかり転んで膝に大きな擦り傷を作ってしまった時に、グレイスが治療所まで同行したことに始まる。
その際に色々と故郷のことなどを話しているうちに、実は彼女も宮国との国境地帯の、グレイスの生まれた場所の近くで育っていたことが分かったのだ。
それ以来彼女とは何となく親密になっていた。馬が合ったというのだろうか?
実は彼女のことはその前からもちょっと気になっていた。
というのは、この作戦のために集まって来た巫女達は結構大きな子が多くて、十五歳のグレイスでも一番年下の部類になる。そんな中で彼女よりも小さな子というのは貴重なのだ。
そしてこの間の一件だが……
―――アントレーネが膝を擦りむいてから数日後のことだ。その日は休日だったのでグレイスが基地の売店でお菓子を漁っていると、そこでひょっこりとアントレーネを見かけたのだ。
彼女はまだ膝の包帯が取れておらず足を少し引きずっている。グレイスが用事を終えて出ようとした時も彼女はまだ店内をうろうろしていた。
《もしかして調子が悪いのかな?》
そう思ってグレイスは彼女に声をかけた。
「あ、足大丈夫?」
アントレーネはグレイスに気づくと、にこっと笑った。
「まだちょっと痛むけど、随分いいわ」
「今日は何か買い物?」
「ええ。便箋を」
「便箋? そこにあるのは?」
グレイスは文具の置かれた棚を指さした。それを見てアントレーネが首を振る。
「ええ。でも何か可愛くないし」
「ああ、それはそうよね」
彼女の気持ちはとてもよく分かる。当然のことだが基地にある文具は質実剛健すぎる物ばかりで、そういうことはあまり気にしないグレイスでさえもちょっと使うのをためらってしまいそうな物ばかりだ。
「店員さんに聞いてみた?」
「え? でも……」
売店の店員さんは何か怖そうなおじさんだ。だとしたら……ちょっとここはお姉さんが一肌脱いでやるしかないか?
「ちょっと待ってて」
「え? でもグレイス……」
グレイスはつかつかとレジスターの方に向かうと、店員に向かって尋ねた。
「あの、ここに可愛い便箋ってありませんか?」
それを聞いて店員は目を丸くした。
「可愛いだって? そんな物誰が使うってんだ?」
まあそうなのだが……グレイスは後ろのアントレーネを指した。
「彼女が手紙出したいって言うんだけど」
「悪いが入荷してないね」
「そうですよね……」
グレイスが諦めて引き返そうとした時だった。
「でも注文することはできるぞ?」
「え? 本当?」
「ただそれにはまずカタログから取り寄せないとな。今使ってるカタログにはそんな物載ってないからな。それが来てから注文になるから、ま、早くても半月はかかるな」
半月! グレイスは振り返って彼女に尋ねた。
「そうなんだ……ねえ、アントレーネ、やっぱりすぐいるんだよね?」
アントレーネはうなずいた。
その様子を見て店員はちょっと腕を組むと言った。
「あんた、便箋が可愛くなきゃいけないのかい?」
「え?」
そこで店員はごそごそとその辺を探し始めると、やがて一枚のチラシを取り出した。
「あったあった。例えばこんなのはどうなんだ?」
それは何かの懇親会のチラシのようだったが、変わっているのは中央の説明文の周りを取り囲んでいる様々な形の魚の絵だ。手で描いたのとも違うようだが……
「この周りのって、版画?」
「版画っていうか、判子だな。器用にこういうのを彫る奴がいてな、そこの便箋でもこれを押しておけばちっとは可愛くならないか?」
店員はにかっと―――多分本人はにこっとしたつもりなのだろうが―――笑った。
「うわ、どう?」
「うん!」
アントレーネも目を輝かせている。
「ブラトゥフってやつだ。確か四号棟じゃなかったかな? その辺に行って“判子屋ブラトゥフ”って尋ねれば見つかると思うが」
「うわ! おじさん、ありがとう!」
「どういたしまして」
そのまま出て行こうとするグレイスをアントレーネが引き留めた。
「ちょっと待って。じゃあこれ買ってく!」
アントレーネは白地に灰色の筋が入っただけの質実剛健な便箋セットを購入した。
それから二人は四号棟の方に向かった。
だがそこはちょっと少女二人で行くにはかなり無謀と言える場所だった。
その日は休日だったので、兵士の宿舎の区画には大人の兵士達がたむろしているのだ。もちろんみんな怖い顔でグレイス達をじろじろ見つめる。
「グレイス!」
アントレーネが怯えてグレイスの腕にしがみつく。グレイスだって今にも逃げ出したかったが、お姉さんの手前一生懸命自分を抑えている状況だ。
《こうなったらもう……当たって砕けるしかないわよねっ!》
グレイスは腹を決めると近くの兵隊につかつかと近寄っていった。
「ちょっとあなた」
「何だよ?」
兵隊は驚いたような顔でグレイスと、後ろでおろおろしているアントレーネを見る。
「判子屋ブラトゥフって人、知ってますか?」
それを聞いて兵隊は一瞬きょとんとしてから、背後の宿舎を指さした。
「そこの二階にいると思うけど、あいつに何の用だ?」
「便箋が可愛くないんです!」
「は?」
「売店のおじさんに聞きました。ブラトゥフさんに便箋に押す判子を貸して欲しいんです」
兵隊は吹き出した。
「そんな怖い顔で聞くから何かと思ったじゃないか。いいぜ。案内してやる」
え?
振り返るとアントレーネが口を押さえて笑いをこらえている。グレイスは顔が熱くなった。
「あの、別に怒ってるんじゃなくって……」
そう言うグレイスの顔を見て兵士もにやっと笑った。
「いや、もう分かったけど、最初来た時は刺されるかと思ったぞ」
「違いますって!」
くそ! 緊張すると目つきが悪くなるこの癖、どうにかならない物だろうか?
その兵隊に案内されてグレイス達はブラトゥフの部屋までやってきた。
宿舎は六人ずつの小部屋に分かれていたが、彼はその一つの奥で小さな机に向かって何かやっているところだった。
「おい、ブラトゥフ。お客さんだぜ」
「俺に? お客?」
振り返るといきなり自分をぎろっと睨んでいる少女巫女の姿を認めて、ブラトゥフは目を丸くした。
『ちょっと、目! 目!』
そう囁いてアントレーネが突く。グレイスは慌てて顔をこすった。
その様子を見て同行してくれた兵士がにやにやしながら言う。
「彼女はあんたの仇じゃなくって、判子を貸して欲しいそうだ」
「あの~!」
じたばたするグレイスを再び目を丸くしながら眺めると、ブラトゥフは答えた。
「ああ、そりゃ構わんが、あんたがか?」
「いえ、彼女が手紙を書きたいんだけど、可愛い便箋がなかったから」
「あの、お願いします」
グレイスの言葉にアントレーネが頭を下げる。
「ちょっと待ってくれよ」
ブラトゥフは立ち上がると、ベッドの下からトランクを取り出した。それを開くと、中の着替えなどをベッドの上に放り出し、その下から薄い箱を取り出した。箱を空けるとそこには三センチ角くらいの小さな木の板がたくさん入っていた。
「今はこのぐらいしかないがな、気に入ったもんはあるかい?」
グレイスがその一枚を取り上げると、魚の形が浮き彫りされているのが見える。だが何だか墨で真っ黒で今ひとつ形状が分かりづらい。
「あの~、押してみていいですか?」
「ああ」
ブラトゥフはスタンプ台と判子の柄を取り出した。
「それをこの柄の先に填めてこのネジを締める。わかるか?」
「うん!」
そこでグレイスとアントレーネは、彼女が買ってきた便箋を取り出して、ブラトゥフの判子を次々に押し始めた。
「うわー、これ可愛くない?」
「あ、これもいいわね!」
判子には魚だけでなく動物や虫、建物、人の顔とか様々な種類があって、妙にみんな愛嬌がある。
「どうしよう? こんなにあったら迷っちゃう」
などと二人でわいわい悩んでいると、ブラトゥフが木版を二枚差し出した。
「これはどうだ?」
何だか真新しいんだが……と思ってそこの模様を良くみると……
「これってもしかしてあたし達?」
「今ちょっと作ってみたんだが」
「今ですか?」
十五分もなかったのではないだろうか?
ともかく二人がそれを便箋に押してみると、二人の笑顔が白い紙の上に現れた。
「あの……ありがとうございます!」
アントレーネはもう涙目だ。グレイスもこんなのは初めてだし、ブラトゥフさんって、もしかして最高なんじゃないか?
「えっと……いいんですか? あの、お礼とか……」
そう言う二人にブラトゥフはにっこり笑う。
「気にするな。作りたくて作っただけだ。でも、そうだな、だったらクッキーでも焼いてくれるか? 甘い物には目が無くてな」
「クッキーでいいんですか?」
それからグレイスはアントレーネの顔を見る。アントレーネもグレイスの顔を見てうなずいた。
「それじゃ今度持ってきます!」
「おう、楽しみにしてるよ」
という感じでその場は収まったのだが―――
グレイスはクスッと笑った。
「ん? 何がおかしいのよ?」
「いや、ちょっとこの間のこと思い出しちゃって」
実はグレイスは料理は全然ダメだった。だからもしあそこに彼女一人だったら、即座にクッキー以外のお礼に変更してもらったはずだ。
だがその時彼女は一人ではなかった。なおかつグレイスはちょっとした法則を信じていた。
それは“可愛い子は料理も上手い”ということだ。その法則はたまたま西カテドラルではおおむね成立していた。そのため彼女はこんな可愛い子が料理下手なはずがないと、アントレーネを見た瞬間に信じ込んでしまっていたのだが……
「あれ? もう、やめてよ!」
その幻想を打ち破る最初の反例が彼女だった。
そのことに気づいたのは次の週、さあお礼のクッキーを焼こうと二人で勇んで厨房に行った時だ。お互いに「じゃ、お願い。あたし手伝うから」と言い合った瞬間の驚きと気まずさは……
今更仕方ないので二人でどうにか頑張ってクッキーらしき物をでっち上げて持って行ったのだが、逆に苦手なことを無理にさせて済まなかったとか謝られてしまうし……
「あは、ごめん。それじゃ行こっか」
だから西カテドラルにいた時は食事に関してはもっぱら食材調達の方で協力してきた。春夏秋と山の中は見る目さえあれば美味しい食材の宝庫なのだ。その話をしたらアントレーネも同様だったらしく、それでは今日の休み、天気が良ければ一緒に山菜採りに行こうということになっていたのだ。
「あ、ちょっと待って。これ、お部屋に置いてくるわ」
アントレーネはポーチをぽんぽんと叩く。
「あ、そうよね」
それに考えてみれば上着を引っかけた方が寒くないだろうし。これはちょうどいい。
二人は宿舎に戻った。
彼女達が今暮らしているのは六人の大部屋四つで、アントレーネはグレイスの隣の部屋だった。部屋に戻るとアントレーネはグレイスに尋ねる。
「ちょっとこれ、読んでっていい?」
「もちろん」
アントレーネは封を切ってその手紙を読み出した。それからにっこりと笑うと手紙をグレイスに差し出した。
「見る?」
「え? いいの?」
「グレイスのことも書いてあるから」
「え?」
グレイスは手紙を受け取ると読み始めた。
親愛なるアントレ
お手紙ありがとう。とっても元気そうで何よりです。こちらはみんな相変わらずですが、やっぱりヘリファルテとシュトラーレがいなくなるとちょっと寂しくなったかも。私たちは病院からカテドラルに戻ってきて、またお祈りができるようになりました。でも今回は正直、ちょっと辛いです。本当なら病院に来る人が少なくなるのはとっても喜ばしいことのはずなのですが。
でも嬉しこともありました。先週追悼ミサが行われたときに、私とデュエラがお祈りの担当になったのですが、そこで神託が出たんです! とっても綺麗な神託でした。これが少しでもみんなの心の慰めになるといいのですが。
アントレの顔の判子、とっても可愛いですね。隣のグレイスって子のも! できることならまた会いたいです。みんなとまた秋祭りの夜を過ごしたいですね。でもアントレもみんなも大切なお勤めをしてるから無理は言えません。それに私も今度別なお勤めをするために■■■■■■■■行くことになりました。それが終わったらまたみんなと会えるかもしれません。それではそのときまで。
あなたのアングラス
「あ、ほんとだ! へえ、アングラスちゃんっていうんだ。可愛い名前だね」
アントレーネはにっこり笑う。
「ええ。そうでしょ? 本人もすごく可愛いわよ? しかもお料理も上手だし」
「もう、それ無しだって!」
それからもう一度手紙を覗き込む。
「でも……墨塗られちゃったね……どこに行くんだろ? 彼女」
こういった戦時下なので、送られる手紙は全て検閲されることになっている。
「あたし達のいるところも書いちゃいけないって言われてるし」
「危ない所じゃないといいよね」
「うん。彼女、頭いいから多分通訳じゃないかしら。外国との会議とか」
「あ、それなら安心よね」
こういう時勢だ。通訳の必要な秘密の会議、なんていうのもよく行われている。西カテドラルでも時々そんな会議に駆り出されていく子がいたし。それに何よりもそういう所なら間違いなく安全だ。
すなわち、グレイス達さえ頑張って戻ってくれば、また彼女とは会えるということだ!
「でも良かった! ちょっと元気になったみたいで」
「どこか悪かったの?」
「うん。ちょっとね。ほら……南は前線に近いでしょ? だからあたし達よく病院のお手伝いに行ってたの」
「あ、うん」
その件については別な子からも聞いていた。前線の病院は負傷兵がたくさんいて人手が全然足りないので、南カテドラルの巫女達がその手伝いに駆り出されるのだという。今回巫女達がカテドラルに戻れたのは、先の戦いで戻ってくる人がほとんどいなかったために、逆に人手が余ってしまったためらしい。
「で、彼女が担当していた兵隊さんが二人続けて戻ってこなくって……それで彼女落ち込んじゃって」
「え? そうなんだ……」
アントレーネの顔が暗い。
これは……こんな所で辛いことを思い出させても仕方がない。グレイスはにっこり笑うと言った。
「じゃ、いこっか。遅くなると昼ご飯に間に合わなくなるし」
「ええ。そうね」
アントレーネも微笑んでうなずいた。
グレイスは忘れずに上着を引っかけると、アントレーネと連れだって山菜採りに出かけていった。
《アングラスちゃんか。アントレーネの友達ならいい子だよね。きっと! 戻って来られたら紹介してもらえるかな?》
だが……次にその名前を聞いた時、彼女は“救国の英雄”になっていた。
その報告が来た日の夕方、司令室ではリフェルドルフ総司令とベネトラルフ副司令が話していた。
「それにしても無茶なことを……和平会談を装って自爆テロなど……」
総司令が額に皺を寄せながら言った。それに副司令が答える。
「先日の南進作戦の失敗で、嶺国は正面作戦を断念せざるを得なかったのです。そのためそんなやり方にシフトせざるを得なかったのです……しかし、私は反対でした」
総司令はふっと鼻を鳴らした。
「だが、結果論とはいえ、ナイスサポートだったとは言える。宮国シムーンの数はそんなに多くはないと推定されているし、そのうちの十二機を使用不能にしたというのは、大戦果とは言えないかね?」
「しかし……」
「我々が千機近い損害と引き替えに得た以上の戦果を僅か七名で行ったと考えれば、これは素晴らしいことだろう?」
副司令はじろっと総司令の顔を睨んだ。
「いずれにしても、これで彼女達が国境線を突破できる確率はぐんと増したのは間違いないわけだ」
副司令はくっと歯を食いしばる。
「しかし、これでもはや平和裡に戦争終結する道は閉ざされました。宮国は今後二度と和平会談に応じてくることはないでしょう」
総司令はうなずいた。
「ああ。そうだな。次の会談があるとすれば、どちらかの降伏の時以外あり得ないだろうな」
それを聞いて副司令は怒りのあまり声を荒げた。
「どちらかの? 敵はたった二機で機甲師団を壊滅できる化け物なのです! 町一つ消し去ることくらい訳はない! それなのに嶺国には飛行部隊がない。我々は裸同然なんです。どうしてどちらかなどという悠長なことを……」
リフェルドルフは軽く手を振ってベネトラルフを抑えた。
「ああ。だが、実際彼らは今までそうはしてこなかった。私も思っていたよ。その辺の田舎町でもちょっと見せしめに消しさっておけば、正直我々は迂闊には動けなかっただろう。だが彼らはそうしなかった。その気になれば簡単にできたことだ。君はそれはなぜだと思う?」
ベネトラルフはうっと絶句する。
その時、司令室の外を訓練を終えた巫女の一団が通り過ぎ、その一人が話す声が聞こえてきた。
『あー! やっと終わった~! 晩ご飯~! 今日は何かな~!』
リフェルドルフの顔に微笑みが浮かぶ。
「君の国の巫女様方は、本当にいい子達だな。この殺風景な基地に花が咲いたようだ」
総司令はそれから副司令の目をじっと見据えると続けた。
「飛行機械や戦車なら、ただの害虫のようなものだ。ちょっと駆除してこいと言えるだろう。でも君は彼女達に、ちょっとそこの町を焼き払って住人を皆殺しにして来なさいと命ずることができるかな?」
「それは……」
副司令は恐ろしそうに首を振る。
「私は奴らも同じなのかも知れないと思っている。あの宮国のシムーンに乗っているのが彼女達のような少女達だったならば、その子達にそんな恐ろしいことができるとはとても思えないし、正気の大人なら彼女達にそんな命令を下すことなどできない」
「では……」
「ああ。そんな少女達の気持ちが我々を首の皮一枚で生かしておいてくれているのだとしたら……」
ベネトラルフは大きくため息をついた。
「私たちは……どこでこんな迷路に迷い込んでしまったんでしょう?」
「さあな……でも、こうなってはもう後には引けない。我々も、我々にできることをしなければならないのだ」
リフェルドルフもまたそう言って大きくため息をついた。