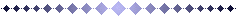第4章 墜ちた雛鳥
空中補給基地シュネルギアの第一甲板上で、作戦総指揮官リフェルドルフは一列に並んだ嶺国巫女少女達の顔をゆっくりと一人一人見つめると、おもむろに口を開いた。
「これよりあなた方プルンブム嶺国と、わがアルゲントゥム礁国の合同作戦、コードネーム“墜ちた雛鳥”の開始を宣言する!」
総司令は再び少女達の顔を見渡した。
「もはや君たちに語るべき言葉はない。我々は誰もが為すべき事は為したと信じている。だから、行って来い! そして我々に翼をもたらしてくれ!」
「はいっ!」
巫女達は一斉に答えると、背後に停まっていた二機の輸送機に整然と分乗していった。
甲板の戦闘機が次々に離陸を始める。それが空を舞う様はまるでイナゴの群れのようだ。
やがて彼女達の輸送機の扉も閉ざされ、咳き込むような音を立てながらプロペラが回り出すと、ゆっくりと青い空の中に滑り込んでいった。
総司令が彼女達に対して黙って敬礼するのが見えた。
中に乗っていた少女達も無言で敬礼を返す。
シュネルギアの姿は段々小さくなってやがて後方の空の中に消えていった。それから輸送機はしばらくまだ朝日に染まった雲とその下に覗く青黒い海の上を飛んでいたが、やがて前方の窓から宮国の大地が見えてきた。
《あそこかあ……》
宮国は初めて見るが、その土地はとても美しかった。空は抜けるように青く、山々は緑に覆われている。
だがどれほど見かけが美しくともそこには悪魔が潜んでいる。
「みんな……大丈夫かな」
アントレーネがぽそっとつぶやいた。グレイスはそっと彼女の手を握る。
心配なのはみんな同じだ。でも今は彼女達を信じるしかない。
この“A機”に乗っているのはヘリファルテ、イーグレッタ、グレイス、アントレーネ、ヴォルケ、アリエスの巫女六人とそして操縦士のコルトーフだ。
彼はこの道のベテランだ。その点では全く安心して良い。
彼女達はしばらくはこうして景色を眺めながらただ運ばれていけばいいのだ。もちろんただ漫然と景色を見ているだけでなく、敵が来ないか注意している必要はあるが……体を動かす必要はないので楽なことこの上ない。
《今はゆっくりしとかないとね……》
ここで疲れてしまっても仕方がない。後でいやというほどのお勤めが待っているはずなのだから。
グレイスはもう一度頭の中で今回の作戦の概要を思い起こした。
この嶺国と礁国の合同作戦“墜ちた雛鳥”は、一口で言えば宮国の悪魔シムーンに対抗するために宮国の奥深くにある聖地から“アンシエンシムーン”を奪取してくる作戦だ。
だがその作戦は正直、素人のグレイス達から見ても、ものすごく無謀としか言いようがなかった。
そもそも、こんな軍事作戦の中核を彼女達のような巫女が担うなど根っこから間違っている。巫女とは神に祈ることがその本分であって、戦争というのはそれこそお勤めではないはずなのだが……
でもそのアンシエンシムーンとやらが巫女の祈りがないと動かないというのであれば仕方がなかった。その場まで彼女達が行かなければ始まらないのだ。
だがそこまで行くということがまずもって大変だった。
アンシエンシムーンがあるその“聖域”は宮国の―――すなわち戦争の真っ最中である敵国のど真ん中、すなわちどこからも一番遠い所に位置していた。彼女達は国境を抜けて宮国深く侵入して、そこからまた戻ってこなければならない訳だ。
作戦の開始場所が“空中補給基地”であったのも偶然ではない。
礁国機には燃料が必要だ。そのため礁国機には航続距離という概念がある。彼女達が何故空中補給基地から出発したかというと、礁国や嶺国本土の基地からでは遠すぎて往復ができないからだ。
しかも今回の出発場所は当初の予定とは異なっていた。
というのは本来ならばもう一月くらい前に作戦は実行されるはずだったのだが、その直前にシュネルギアが敵に発見されてしまったので急遽スタート位置を変更していたためだ。
最初の場所からならばもう少し余裕はあったのだが、今回の場所からだと本当にぎりぎりの距離なのだ。
彼女達の乗っている輸送機には通常の燃料タンク以外に増槽というのが付いていて、可能な限り長く飛べるようになっている。だがそれでも聖地までまっすぐ行って戻るだけでほぼ全ての燃料を使い尽くす計算になる。
『途中で燃料が尽きたらどうなるんですか?』
と、ブリーフィングの時に聞いた子がいたが、その答えはこうだった。
『その場合は歩いてもらうことになる』
なかなか愉快な話だ。しかもそのために実際にどこかの山の中に落とされて徒歩で帰還する訓練まで行ったのだ。訓練と分かっていれば遠足みたいな物だったが、やはり敵国のど真ん中でそんな目に遭うのは願い下げだ。
心配事は燃料だけではない。
グレイスは窓の外を見た。斜め後方に“B機”、すなわちBチームの輸送機が飛んでいるのが見えたが、それ以外の友軍機は近くにはいない。
そうなのだ。彼女達はほぼ丸腰だった。もし敵に発見されたら間違いなく終わりだと言って良い。
だが護衛機を付けたくても付けられない事情があった。その搭載重量の関係で通常の戦闘機は途中までしか付いてこられない。それにもし敵シムーンに発見されたのだとしたら、数機程度の護衛がいたところでほぼ無意味だ。逆に中途半端な護衛機がいれば敵に発見される可能性も高くなる。
だったらいっそ護衛機無しで可能な限りこっそりと飛んでいく方がましだという結論になったのだ。
《で……》
グレイスは貨物室の真ん中にどかんと鎮座した邪魔くさい機銃を眺めた。
一応これが敵に見つかった場合の最後の切り札だが……本当にないよりいくらかマシといった代物だ。
彼女達はそういった状況も想定して訓練はしてきた。ちょうどイーグレッタが発砲騒ぎを起こしたあの日がそうだったのだが、輸送機をシミレで攻撃してみてそれに対応する訓練だ。
だがそれで分かったのは、機銃があると知ったら敵ははわざわざ射角内に入ってこないので落とせないということだった。礁国機の場合後方に大きなプロペラがあるので後ろに付かれたらもうどうしようもないのだ。
従って敵が来た場合どうすればいいかというと、武器などないふりをして敵をぎりぎりまで引きつけて、油断したところを最初の一連射で仕留めれば良いわけだ。何とも心強い限りだ。
こうして国境線を突破して何とか聖地までたどり着いたとする。そこに一番の問題があった。
《本当にアンシエンシムーンなんてあるのかしら?》
苦労して行った挙げ句に荷物がありませんでしたとか言われたら、さすがにちょっと凹んでしまうだろう。まずもって今回の計画はその点にかかっているのだが……それがそこに存在するという根拠がまた笑えた。
あのドクター・バルヌフは礁国のシムーン研究の第一人者なのだが、物理学とか数学だけでなく何故か色々な国の昔話にも妙に詳しかった。それは単なる趣味だったのではなく何と礁国と嶺国に伝わる昔話が、アンシエンシムーンがそこにあるという根拠になっていたためだ。あと一応宮国内の情報源という人がいて、そこからもその可能性はあるというお墨付きを得ているというのもあるらしいが……
その昔話とはこんな感じだ。
―――かつてまだ礁国が美しい海と空を持っていた頃、とある島の浜辺に不思議な少女が流れ着いた。少女は見たこともない服を着ており、誰にも分からない言葉で話した。
少女は村人に介護されて段々元気になった。やがて言葉を少しずつ覚えると、村人達に彼女がどこから来たかを話した。
彼女はテンパス様という神のお側に仕える巫女だった。その巫女達が祈る時には神の翼に乗って空に祈った。神の翼には性別をまだ選んでいない少女二人でないと乗ることができなかった。そのため巫女達は全てそういう少女で、大人になったら巫女を止めなければならなかった。
その中で彼女は“神の右手”と呼ばれるグループに属していた。彼女達の国には神のお膝元である最も聖なる場所があった。その中央に神の泉があり、その周囲には古代より伝えられた神の翼が鎮座している。不思議なことにその神の翼がいくつあるのか誰も知らなかった。行って数える度に数が違っていたからだ。
彼女はそこで祈りの日々を過ごしていたが、ある日彼女の祈り方が悪かったせいか神の怒りに触れて気を失い、気がついたらここで海の上を漂っていたのだと。
彼女はやがて成人し、村の若い男と結婚して子を為し良き母となり、天寿を全うした。
かつて巫女だった女は浜辺で空を舞い踊る海鳥の姿を見ると、決まって彼女がかつて鳥のように大空に羽ばたいていた日々を懐かしそうに語ったという―――
これは礁国に伝わる方の話で、今から数百年ほど前に記録されたお話らしい。
そして嶺国に伝わる話はこんな感じだ。
―――とある嶺国の山奥で怪我をした少女が発見された。その子は不思議な格好をしており、巫女様達の言葉を話したので近くのカテドラルに連れて行かれた。
そこで彼女は神官に、自分は聖なる場所で“右手の一隊”で祈っていた巫女だと言った。彼女達は最も古くからある最も崇高な祈りを再び捧げることができるよう、日々精進していたと。
彼女のいた聖地の最も神聖な場所には泉があり、そこには古から伝わる神の翼が安置されていた。
そこである日彼女達はまた神に祈ろうとしたが、祈りのやり方が悪かったのか神は祈りを聞き届けることなく、気がついたらここにいたのだと。
彼女はそれだけ語ると手当の甲斐なく神に召された。神官達は彼女の亡骸を丁重に葬った―――
こちらの方は今から数十年ほどの前のことらしい。
この時代も場所も異なった二つの伝承には確かに妙な共通点がある。どこかの聖地で祈っていた巫女が、祈りに失敗して? 遠くに飛ばされてしまったということ。その聖地には不思議な場所があって、そこには“古い時代から伝わる翼”が置かれているということ……
ドクター達がアンシエンシムーンと言っているのも、その神の翼こそがシムーンだと彼らが信じているためで、今の宮国のシムーンと区別するため“古代の”という意味の形容詞をつけただけなのだ。
でもそれが本当に背中にくっつける翼みたいな物だったらどうするのだろう? グレイスとしては別にそれはそれで楽しそうだとは思うのだが、その姿で敵シムーンと戦えと言われたらさすがに困ってしまうだろう。
それ以前にたまたま二つの伝説が一致ていたからと言って、昔話を誰かが聞いた可能性だってあると思うし、その聖地が宮国の聖地かどうかさえ不明だし、当てずっぽうも甚だしいのではなかろうか?
ただ宮国内の情報源という人からの話では、かつて宮国には“コール・デクストラ”という巫女の一団がいたのは事実だそうだ。“デクストラ”とは古い言葉で“右手”を意味するので、その謎の巫女はそこから来たと考えることも可能だ、というのだが……
《もうちょっとマシな証拠ってなかったのかしら?》
そして運良くそこにそれがあったとして、この昔話どおりならアンシエンシムーンは数百年前からそこにあったということにならないか? だとしたらそんな物が動くのだろうか? とっくに朽ち果てていたっておかしくないわけで……
更に運良くそれが動く状態だったとしても、それは彼女達に動かせる物なのだろうか?
アンシエンシムーンは巫女の祈りがないと飛ばないらしいが、グレイス達はアニムスにお仕えする巫女だ。宮国の神様はそんな違った国の巫女の祈りを聞いてくれるのだろうか?
その点に関してもドクターは、嶺国の神アニムスと宮国の神テンプス・パテュームは元は同じだったという学説があると、その根拠も含めて色々説明はしてくれたが……元は同じでも喧嘩別れすることだってあるだろうし……
《そのテンプス・パテューム様もアニムス様みたいにお優しいといいんだけど……》
そうして運良く宮国の神様が優しかったとして、操縦方法はシミレと同じだろうか? もちろんそんな確証などないから、そうでなかったとしたらぶっつけ本番だ。
こうして何とか飛び上がることができたなら後は基地に向かって一目散だが、当然アンシエンシムーンには通信機なんてないだろう。誘導なんてしてもらえないし、何か分からなくなっても仲間に尋ねることさえできない。何もかも自力で戻って来なければならないのだ。
そうなったらサジッタは大変だ。彼女が方向を間違えたらえらいことになるからだ―――まあ、この点に関しては散々訓練したから大丈夫だとは思うが。
そして最後に帰る途中、運悪く敵に見つかってしまった場合は?
その問いに対して総司令は答えた。
『その場合は……もはや君たちの勇気に期待するしかない。だがそれは必ずしも戦うこととは限らない。君たちの目的は、アンシエンシムーンを持ち帰ること。それが最優先だ。そのためには……何をしてでも生きて戻ることを念頭に置け。何をしてでもだ……』
全く本当に何をすればいいのだ? 司令達はケースバイケースだとしか言わなかったが……
ともかくこういった“様々な困難”を乗り越えてシュネルギアまで戻ることができれば、ミッション完了でご褒美にきらきらした勲章がもらえるらしい。カラスじゃないんだから小麦粉一年分とかの方が嬉しかったりするのだが……
《でも……シムーンに乗るってどんな気分なのかしら?》
彼女達が気になっているのはひとえにこの点だった。
あの素敵なシミレがシムーンの“質の悪いまがい物”なのだという。だとすれば本物のシムーンに乗るということはどれだけ素晴らしいことなのだろう?
《それを確かめるためだけでも行く価値はあるよね!》
そうなのだ。
それは始まりの巫女様達が失った翼。
それを取り戻すことができたのならば、かつて神に最も近いところでお仕えしていた巫女様方が見ていた光景を彼女達もまた見ることができるのかもしれない! だとしたら……
一目、一目でもいい。そうすればもう何も……
「あっ!」
右前方を監視していたヘリファルテが小さく叫び声を挙げた。
巫女達が一斉にその方を見る。すると遙か彼方でちかちかと光の点が点滅しているのが見えた。
《始まった!》
グレイスは双眼鏡をその方に向けた。
レンズを通して見ると遙か彼方に真っ黒いカタツムリ状の船が浮かんでいる。あれが黒カタツムリこと、宮国の航空母艦アルクス・ニゲルだ。この距離でこのサイズに見えると言うことは、実物はさぞ大きいのだろう。
その黒カタツムリの周囲には、その大きな図体と比べたらそれこそゴミのような、小さい羽虫のような黒点が蠢いている。
そのゴミに混じって時々凄い速度で飛んでいる別な黒点が見えた。
その時、その素早い黒点の軌跡が光りだし不思議な形を描いたと思うと……ぱっとはじけ飛んだ。
途端にちかちかっと星のような輝きが生まれ、消えていく……
《!!》
だが彼女達は知っていた。もちろんそれはゴミなんかではない。如何に小さく儚く見えようとも、それは彼女達がよく知っている礁国機で、その中に彼女達がよく知っている顔があることを。
途端に胃がぎゅっと痛くなってくる。
彼らは戦っている。全く勝ち目のない相手に対して果敢に、と言うより無謀な戦いを挑んでいる。
その目的はただ一つ。巫女達が安全に国境を越えられるよう、敵の目を引きつけるためだ。
そう。彼らの全てが囮だった。
高速の黒点が螺旋型の軌跡を描いたかと思うと急に引き返した……と思った瞬間、今までにない輝きと、多数の“星”が……
グレイスは息を呑んだ。
彼女達は今はそれを黙って見守るしかない。
「おい、花火ばっかり見てないで、他の方向もよろしく頼むぜ」
パイロットのコルトーフが思わず戦いに引き込まれている巫女達に言った。
「あ、すみません」
巫女達は再び四方の監視に戻る。
ここで今彼女達がしくじってしまったら、あの人達の行為が全て無に帰ってしまうのだ。彼女達は為すべき事を為さねばならない。
果たして……
「十一時方向! 敵機!」
アリエスが叫ぶ。艇内に緊張が走る。イーグレッタが後方のB機に通信を送る。
「十一時。敵機です」
『了解』
コルトーフは速度を落とし、それまでも低かった高度を更にぎりぎりまで下げる。巫女達は息を詰めてその動きを見送るが……敵シムーンは彼女達の遙か前方を通り過ぎて、そのまま戦闘空域に向かって行った。
一同が安堵の息をついた。見つかってしまったらそれだけで作戦は終わってしまったような物だ。
もし彼らがあそこで派手にドンパチしてくれていなければ、もちろん彼女達は見つかってしまったことだろう。
とにかくまずは何はともあれ国境線を超えなければならない。宮国のシムーンは数が少ないので全土をカバーできない。そのため大部分が礁国との国境地域に配備されている。飛行して侵入できるのが礁国機だけだから仕方ない。逆にそこさえ超えられれば危険はぐんと少なくなるわけだ。
《とにかくもう来ないで!》
それは巫女達全員の祈りだった。
巫女達の祈りはもう少しで叶ったかと思われた。
だが彼女達が国境を超えて少し宮国内に入り込んだと思われた時だった。
『注意して。九時方向より敵一機』
B機から通信が入る。ブリッサの声だ!
「九時ですって?」
イーグレッタがその方を見る。今の戦闘空域の方向は……大体三時だ。ということは……
《軌道が交差してる?》
いや、彼女達は前進しているから、交差した時にはA機は少し前に行っているが、少し遅れて付いてきているB機は? ほとんどその真上を通っていかないか?
「ちょっとそれって……」
ヴォルケが青ざめた顔で言う。それを聞いてコルトーフが言った。
「向こうは向こうに任せろ。もう素人じゃないんだ」
「はい……」
何と運が悪い……というか、これだけ派手に戦闘してもまだ帰還していなかった機がいたのか。
宮国には無線通信技術がないらしい。あれだけ凄まじい能力を有している宮国のシムーンやシミレだが、僚機と話す時は通信用のワイヤーを相手の機に打ち込まなければならないらしい。
これが礁国なら攻撃を受けた途端に周囲に緊急信号を発信し、それを受けた僚機が即座に戻ってくるのだが、そういうことができないとすると今後もまだ戦いに気づいていなかった機体が戻ってくるのだろうか?
巫女達は迫ってくる黒い宮国シムーンを息を呑んで見守った。
それは後方を通り過ぎ、そのまま行ってしまうかに思われた。だが……
「あっ!」
後方を監視していたアントレーネが叫ぶ。
黒シムーンが急に方向を転換したかと思うと、後ろのB機に機銃を発射したのだ。
「ええっ!」
一同が思わず声を挙げる。
一瞬何事もなかったかと思ったが……輸送機からぱっと煙が上がって尾を引き始める。
「いやっ!」
アントレーネが声を挙げる。グレイスは彼女の手をぎゅっと握った。
《嘘……でしょ?》
あれには西カテドラルから一緒にやってきたブリッサとカナーリが乗っている。南からはシュトラーレとグラナータが、東からはラテルネとモントーネが……この半年間一緒に暮らして家族同様になった子達が……
「コルトーフさん……」
ヘリファルテが上ずった声で言うが、コルトーフは断固とした声で答えた。
「騒ぐな。目立たないように逃げるぞ!」
巫女達は息を呑んだ。彼女達が危険なのに……だが、心に浮かぶ思いは一緒でも、それを言葉にした者はいなかった。
少女達は黙ってうなずくと持ち場に戻る。アントレーネが状況を報告する。
「B機、進行方向を変えました」
「了解」
「敵機……上昇して旋回を始めました」
「なに?」
それって、他の機体がいないか探し始めたということか?
巫女達が一斉にコルトーフの方を見る。
だがコルトーフは振り返ると答えた。
「下手な動きをしたら余計目立つ」
そういう彼の額からも脂汗が流れている。
「機銃、準備しておけ」
「はいっ!」
グレイスは訓練でやったように機銃の発射準備を始める。
《来るな! 来るな! 来るな~~~っ!》
準備しながらも頭の中はこの思いで一杯だ。
しかし敵シムーンはそんな思いをあざ笑うかのように旋回半径を徐々に広げていき、そしてついにグレイス達の機体をも発見した。
「敵機、急降下してきます!」
アントレーネの声が上ずっている。
「ぎりぎりまで引きつけろ!」
一応訓練でやった状況ではある。敵が後ろから迫ってきた時、空気ブレーキというのをかけて急減速して敵が並列した時、一気に撃ちまくるという奴だが……
グレイスが射手担当になっていたが実際に撃つ羽目になるとは……
とにかく、訓練でやったことを思い出せばいい。彼女は合図に合わせて狙いを付けて引き金を引く。それだけだ。
だが……
タタタタタタ!
そんな音とともに機体に衝撃が走る。
先に撃ってきたのは相手だった。コルトーフが慌てて旋回をする。
「あんな遠くから?!」
あんな距離ではなかなか当たらないはず、だったのだが……見るとコクピットのあたりの風防に派手なひび割れが入っているのが見える。コルトーフが大声で叫ぶ。
「大丈夫! かすっただけだ!」
よし。それなら……
「敵機は?」
「一旦離脱していくわ」
ヴォルケが答える。
「また来る気ね?」
イーグレッタがつぶやく。
くそ! 今度来たら……絶対当ててやる!
グレイスは機銃のハンドルを握る手に力を込め、アリエスに向かってうなずく。アリエスは合図に合わせて輸送機の扉を開く係だ。彼女もまたこくっとうなずいた。
だがその時だ。後方から異様な音が聞こえてきた。低くうなるような……
何だろう? これは、確か一度聞いたことのあるような音だが……
その時無線機から声がした。
『こちらB機。動力系をやられて作戦遂行不能です。悪いけどヘリファルテ、こっちもお見送りする側になったわ。イーグレッタとお幸せにね』
この声は……
『何を言ってる! シュトラーレ!』
ヘリファルテが無線機に向かってわめく。
だが返事はなかった。
その次に彼女達が見た物は……火を噴きながらものすごい高速で突入してくるB輸送機だった。それは敵の黒シムーンに向けて全力で突っ込んでいく。
黒シムーンはその姿を見つけてひょいっと回避するが、その途端に輸送機の開いた入り口から突き出した機銃が火を噴いた。その中に巫女服の少女の姿が明らかに認められて……
機銃弾が敵シムーンをかすめて、シムーンがよろめく。
その次の瞬間……B輸送機は大爆発を起こして四散した。
《え?》
何が起こった?
「今だ! 行くぞ。全力で離脱する。オーバーチャージだ。ロック、外せ!」
コルトーフの叫び声だ。
「え、はいっ!」
ヘリファルテが慌てて発動機の制御板に差し込まれている安全ロックのピンを引き抜いた。
途端に輸送機のエンジン音がぐおっと大きくなって……
《そう! この音!》
輸送機はぐんぐん加速していく。
「圧力!」
「まだ、大丈夫です」
「マックスになったらカウントダウン。二十五秒だ。分かったな!」
「はいっ!」
礁国機のエンジンは中で燃料を燃やして推力を得ている。燃料をたくさん食わせてやれば速度も上がるのだが、温度や圧力も高くなって放っておくと爆発してしまう。だから普段はある一定以上の燃料が行かないようにリミッターが仕掛けられている。
しかし非常の際にはそのリミッターを外すことで、ほんの一瞬だけだがものすごい速度を出すことが可能だ。これは一度訓練の時にやってみせられたことがあるが……それは圧力計がマックスになるまでだった。
「マックス! 二十五、二十四……」
ヘリファルテがカウントダウンを始めるが、いつもの彼女の声と違って何だか甲高い。
低空を飛んでいるせいで、地面がものすごい速度で動いているのが分かる。夢みたいなスピードだ!
「十六、十五、十四……」
エンジンの音が何だかおかしくなってきた。これって……そうだ! さっき聞いた音! B機が立てていたエンジン音……
「七、六、五……」
再びコルトーフが叫ぶ。
「敵は?」
後ろを見ていたヴォルケが振り返ると答えた。
「追って……きません」
コルトーフはそれを聞いてスロットルをゆるめた。
エンジン音が低くなっていった。
ぷはーっ!
残った巫女達が同時に息をして、それからみんなで吹き出した。緊張に息をすることさえ忘れていたのだ。
それから巫女達は互いに顔を見合わせた。
あっという間の出来事だった……だがこれはどういうことなのだ?
カナーリとブリッサは? シュトラーレとグラナータは? ラテルネとモントーネは? 彼女達は一体どうなったというのだ?
もちろんその答えは誰もが知っていた。彼女達とはもう、こちらの世界では会うことができないのだと。
だがそう思ってもまるで実感がわかない。今日の朝、みんなで一緒に朝食を取ってシュネルギアからの眺めを楽しんでいたのだ。そんな彼女達ともう二度と会えないなんて……
などという感傷にふける暇もなかった。
「すまん。悪い知らせが二つある」
巫女達は一斉にコルトーフの顔を見た。見ると彼の顔が妙に青ざめているが……
「どうやらさっきの被弾で燃料系がやられた。減りが早すぎる。このままじゃ行って帰るどころか、行き着くことも厳しい。だからまず不要な物は捨てて機体を軽くしてくれ」
「あ、はい」
「それともう一つなんだが……ちょっと気分が優れなくってな、操縦を少しの間、誰か代わってもらえないか?」
「え?」
驚いたヘリファルテがコクピットに行って、叫び声を挙げる。
「さっきかすっただけだって……」
「そのとおりだ。直撃だったらお陀仏だったな」
「アントレーネ、ヴォルケ、来て!」
ヘリファルテの声が完全に裏返っている。
「はいっ!」
二人は慌ててコクピットに向かい、彼女達も同様に声を挙げる。
「そうーっと、そうーっと」
彼女達にイーグレッタが加わってコルトーフを運び出してくる。
「床、寝られるように何か敷いて」
「はいっ!」
グレイスとアリエスが慌てて予備の毛布を取り出して通路に敷いた。
運んで来られたコルトーフを見てグレイスとアリエスも息を呑んだ。
コルトーフの脇腹には先ほどの射撃で吹っ飛んだと見える窓枠の破片がぐっさりと刺さっているのだ。
「これ……抜いてあげないと……」
だがアントレーネが首を振った。
「だめ。抜いたら余計血が出ちゃう」
南カテドラル出身の子は野戦病院のお手伝いをしていたこともあって、こういったことには詳しい。でもそうするとそれって?
「救急セットを」
ヴォルケが持ってきたキットの箱を開け、アントレーネはその中から注射器とアンプルを取り出してコルトーフに見せた。
「今はこれしか……」
パイロットはにやっと笑って答えた。
「ありがとよ」
「それって?」
グレイスがアントレーネに尋ねる。
「痛み止め」
「……」
注射をするとやがてコルトーフの表情が少しずつ安らかになっていった。
そこにイーグレッタが戻ってきて尋ねた。
「コルトーフさん。燃料系以外では?」
「他は何とかなってるみたいだ」
「分かりました」
彼女は戻るとコクピットで操縦をしていたヘリファルテに言った。
「あなたは休んでて」
「え? でも……」
「帰りの操縦は任せなきゃならないから。今は私が」
ヘリファルテはちょっと絶句していたが、それからイーグレッタに操縦席を代わる。
「じゃ、よろしく頼む」
「ええ」
今は行き着けるかどうかの方が問題のような気もするのだが……でもそうだ。彼女の言う通りだ。彼女達の目的は行って戻ってくることなのだから。帰りのパイロットを今休ませておくのは当然のことなのだ。
だとしたらともかく今は何をすれば?
グレイスは貨物室の真ん中に鎮座している機銃を見た。さっきコルトーフさんは機体を軽くしろと言った。だとすればまずはこの邪魔くさい役立たずを捨ててやる!
「アリエス! 手伝って!」
「ええ」
二人は工具箱を取り出して作業を始めた。
……だが巫女達の必死の努力も空しく、輸送機は何とか目的地の遺跡の近くまではたどり着いたが、結局不時着するしかなくなった。
そこは一面荒れ果てた荒野と切り立った山が広がっている。
「あとどのくらいかな?」
グレイスが地図を確認していたヴォルケに尋ねる。
「今ここら辺だと思うから……あと二十キロくらいかしら?」
二十キロか……まあ歩いて行けない距離ではない。だが予定では今晩には帰り着いているはずなのだが、ちょっと遅くなってしまいそうだ。
それより問題なのは機内に寝かされたコルトーフだった。
彼は薬が効いていたのでしばらくは眠っていたが、さっき目を覚ましたらしくアントレーネが介抱をしている。
「ありがとうよ」
「喋ったらダメです」
だがコルトーフは黙って首を振る。
「悪いな。連れてってやるって……約束したのにな」
「いえ、そんなことありません」
「さ!」
そう言ってコルトーフは顎で巫女達の行く先を示した。
「後は俺がやっとくから、お前達は先に行け」
それを聞いて巫女達は顔を見合わせた。それからヘリファルテが彼に向かって言った。
「機体の爆破なら私たちでできます」
コルトーフの目が見開かれた。
「おい!」
ヘリファルテが黙って首を振る。
「私たちも……お約束したと思います」
コルトーフの目が泳いだ。
そう。巫女達は知っていた。彼の目は……冬の夜にやって来た人達の目と同じだ。
自分の人生がここで終わることを知っている、誇り高き人の目。
「いいのかよ? 本当に……」
「それが……お勤めです」
コルトーフはしばらくじっと巫女達の顔を見つめる。やがて目頭から一筋の涙がこぼれ落ちた。
「じゃ……頼もう」
「どうします? 後ろから?」
「いや、お前達の顔を見ていたいさ。当然だろ?」
巫女達は涙をこらえ、普段は決して見せてはならないお役目のための道具―――ミニステリウムを取り出した。黙って慣れた手つきで安全装置を外す。
「で、なんて言うんだっけ?」
イーグレッタが彼の耳元に囁く。
「そっか。いい言葉だな……もっとみんな、顔見せてくれるか? おい……泣くなよ……っても無理か。世話になったな……みんな……綺麗だぜ。それじゃまたな……アー・エル」
「「「「「「 アー・エル! 」
同時に六発の銃弾が発射された。
巫女達はコルトーフの屍に毛布を掛けて水筒の水でお清めの儀式をすると、今度は爆破のための時限装置をセットした。
正式な埋葬もしてやれなかった……だが一人孤独に旅立たせたのでもない。
少女達は振り返らずに歩き始めた。
ここは宮国でかのアルクス・プリーマと並ぶ最大の航空母艦、アルクス・ニゲルの飛行甲板上だ。
そこに被弾したシムーンがまた一機戻ってきた。
今回戻ってきた機体はそれほどの被害は受けていないようだが、アウリーガ席の風防に一発銃弾が貫通したらしく、大きな穴が空いている。
「巫女様、ご無事ですか!」
整備士の言葉に応えるように風防が開くと髪の長い少女が手を振った。
「大丈夫。ちょっとかすっただけです」
少女達がシムーンから降りると、アルクス・ニゲルのデュクス―――シムーン・コール担当の士官のことだ―――が駆けつけてきた。
「大丈夫ですか? お怪我は?」
「ちょっと切っただけです」
実際彼女の怪我は風防の破片で浅い切り傷ができただけだった。
デュクスは胸をなで下ろすと彼女達に尋ねた。
「あなた方は偵察任務だと思いましたが、どこで被弾を?」
それを聞いてアウリーガの少女が答える。
「はい。偵察を終えて帰還中に礁国の小型輸送機を発見して攻撃したのですが、その側面に機銃があるのに気づかなくて、それで……」
「敵機に近づく時にはあれほど注意して下さいと申し上げましたのに……ともかく無事で良かった。それでその輸送機は?」
「爆発しました。あともう一機いたのですがこちらは逃げていきました。でもその前に撃った弾が当たっているので、どこかで墜ちてるかもしれません」
「そうですか。他には」
「いえ、その二機だけです」
デュクスはほっとしたようにうなずいた。そこでサジッタの方の少女が言った。
「あの、一つ気になることがあるんですが」
「なんです?」
「その輸送機なんですが、一瞬だったんですが、その、女の子の姿が見えたんです」
「女の子?」
「灰色のローブみたいなのに、白いマフラーみたいなのをしていました。撃ってきたとき扉が開いていたんでちらっと見えたんですが……」
「灰色? ローブ? マフラー?」
それを横で聞いていた整備士長が言った。
「デュクス……それってまさか嶺国の巫女ではありませんか? 和平会談に来た巫女がそんななりだったと聞きましたが……」
「嶺国の巫女? だとしたらどうして?」
デュクスはちょっと考え込むと、少女達に尋ねる。
「その輸送機はどの方向に向かって飛んでいましたか?」
「えーっと……右から左だから……真っ直ぐ奥地の方に向かってたと思います。逃げた一機も確かそちらの方へ……」
整備士長はデュクスに尋ねる。
「どういう事でしょう? そちらには何もありませんが……」
再びデュクスが考え込んだところに、伝令の兵士が走ってきた。
「デュクス! 五時の方向より敵の第三波が!」
「分かりました。戻ります」
デュクスはそう答えると整備士長に向かって言った。
「ともかく今はこちらが先です。今のことについては後で報告しておきます」
「はい」
整備士長がうなずくと、今度は少女達に向かって言う。
「それからあなた方、疲れているところだとは思いますが、傷の手当てをしたら出ているみんなを手伝って頂けますか?」
「はい。もちろん!」
少女達は元気にうなずいた。
その翌日、遙か離れた宮国の大聖廟の一角にて、軍事担当大臣である司兵院は疲れた表情で書類の束をデスクの上に放り投げた。
司兵院は近くにいた次官に向かって言った。
「昨日の侵攻は随分と派手だったみたいだな?」
「はい。アルクス・ニゲルに対して三回の大規模攻撃が仕掛けられたそうです。しかし報告書にもあるとおり、損害は軽微です。対して礁国機はかなりが撃墜されたようです」
「いくら来ようと同じなのに、何を考えているのだ? 奴らは……」
「いつもどおりの嫌がらせでしょうか? コール・イグニスが健在な以上、確かにいくら来ようと同じでしょうが……でもさすがに巫女様方もお疲れの様子ですし、被害もゼロとはいきません」
「ああ。はやくアルクス・プリーマに復帰してもらわねばな」
「しかし復帰しても、そこに乗るシムーン・コールが……」
「こうなれば遊覧機だろうが小聖廟の守護機だろうがかき集めてくるしかないだろう!」
「分かっておりますが、しかし彼女達には実戦経験が……」
そう言われて司兵院もため息をついた。
「まったく……ルボルとカプトが失われたのは痛かった……司政院のヘタレどもが!」
そんな会話をしていた時だ。事務官がやって来ると言った。
「司兵院様、宮主様がお見えです」
「ああ? 何事だ?」
司兵院の顔にあからさまに不快な表情が浮かんだが、それを押し殺すと答える。
「お通ししろ」
宮主とは宮国の大聖廟の神官長で、テンプス・パテューム教会の実質的な最高実力者だ。実質的なといったのは、真の最高権威は大宮煌オナシアという巫女なのだが、彼女は泉で少女達を見守る役割に徹していて権力沙汰には全く口を出さないからだ。
「これは宮主殿。今日はどういったご用件で?」
司兵院の慇懃な言葉を聞いて、宮主は額に八の字の皺をよせながら言った。
「アルクス・プリーマはどうなっているのです?」
「修理は完了して現在はテスト飛行中ですが?」
「テストなどどうでも良い! 動けるのなら今すぐ、遺跡へ!」
司兵院と横にいた次官の顔に困惑の色が浮かぶ。
「一体何をおっしゃっておられる? どうしてそんな場所に? それに今、アルクス・プリーマにはコールが乗っていません。ご存じの通り先日の……」
その言葉に宮主は割り込んだ。
「使えるコールは?」
「コール・テンペストでしょうか?」
「では彼女達を呼んでください」
「いえ、彼女達は今、前線で哨戒任務中です。呼び戻すにしても数日はかかります」
「ではそこにアルクス・プリーマを向かわせて、彼女達を拾っていけばいい。だから早く!」
司兵院は妙に焦っている宮主を不思議そうな顔で見つめる。
「宮主殿。ご存じの通り我々は今、礁国と大規模な戦闘を繰り返しております。特に最近西の方で奴らの侵攻が激しく、アルクス・ニゲルだけでは追いつかなくなりつつあります。我々はアルクス・プリーマにもそちらの援護に向かって頂こうと考えている所なのですが?」
それを聞いて宮主は目を見開いた。
「あなたは聞いていないのですか? 嶺国の巫女が遺跡に向かったことを!」
「はい?」
司兵院が次官を見ると、次官は書類を取り上げてぱらぱらめくると答えた。
「ああ、これですか? ニゲルより、嶺国巫女が乗っていた輸送機を二機発見して、一機を撃墜してもう一機は取り逃がしたという報告が来ています。逃げた一機は、東に向かったと……」
「だそうですが?」
だからなんだというのだ? 輸送機ごときに! 司兵院も次官もそんな表情だったが、宮主だけは違っていた。
「だから、その先には遺跡があるのです!」
司兵院と次官は眉を顰めた。遺跡は宮国のほぼ中央にあり、従って周辺の国から真っ直ぐ宮国に向かえば、どこからだって遺跡に向かっていると言えるからだ。
「落ち着いて頂けますかな? 宮主殿。あなた方にとって遺跡が最も神聖な場所だということは存じております。そこが嶺国巫女ごときに汚されるというのは、それは確かに我慢のならないことでしょうが……」
だが宮主は司兵院の言葉を遮って叫んだ。
「違うのです! 遺跡には、あそこにはあるのです。あれを奴らに取られたりしたら……」
「ある? 何がですか?」
「シムーンです」
「は?」
「遺跡の中には、古よりの聖遺物、古代のシムーンが安置されているのです。嶺国の巫女が遺跡に向かうのはそのシムーンを得ることが目的に違いありません!」
司兵院は一瞬言葉を失った。それから徐々にその宮主の言わんとすることの重要性が脳裏に染み渡ってくる。
「シムーン、ですと?」
宮主はうなずく。
「古代シムーンは、我々のシムーンの原型になった機体です。今の物はより祈りやすいようにと改良されてはいますが、それほど引けを取るわけではありません」
「ということは……それは動くということですか?」
「もちろんです!」
「リ・マージョンもできると?」
「当然です!」
それを聞いて司兵院の顔が真っ赤になった。
「なんですと? 一体どうしてそんな重要なことを我々に伏せておかれた!」
「神聖なる遺物を戦争などに使わせるわけにはいきません」
「そんなことを言っている場合ではないでしょう! 我々には戦力が足りないのだ。そんな機体を隠していたなど、それで戦いに負けたらどうするのです!」
「シムーンとは神の乗機! それを戦力などという呼び方はお控えなさい!」
司兵院はばんと机を叩くと、立ち上がって宮主を睨んだ。
「この非常時に何を……」
そこに横で見ていた次官が口を挟む。
「あの、ともかく今は、その遺跡に向かっている嶺国巫女の乗った礁国輸送機を……だとしたら護衛に嶺国と礁国の連合軍が潜んでいるかも……」
司兵院は歯を食いしばるとうなずいた。
「わかった。アヌビトゥーフを呼び出せ!」
「承知しました」
そう答えて次官は足早に去って行った。
「ではよろしくお願いします」
次いで宮主もそう言って背を向けると部屋を出て行った。
「シムーン……だと?」
誰もいなくなった部屋で司兵院は呆然とつぶやいた。