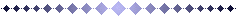第8章 異国の巫女
嵐は突然やってくる。
それはグレイス達が宮国式リ・マージョンのやり方を発見してから僅か数日後のことだった。
巫女達は昼食後でちょっと一休みしていたところだった。その日の午前中も彼女達は新しいリ・マージョンのやり方を試みていた。最初の時に比べたら少しずつコツは飲み込めてきたとはいえ、まだまだ成功率は一番簡単な物でも数回に一回というところだ。
「これって絶対小さい頃から練習してないとだめよね」
アリエスがちょっと疲れた表情でこぼす。それにうなずきながらアントレーネも言った。
「うん。今からだとできるまでに大人になっちゃうかも……」
大人か……そういえばグレイスももうすぐ一六歳だ。この時期は本来なら将来どちらの性別を選ぶかで頭が一杯の頃だが、この騒ぎでそんなことはすっかりどこかに飛んでしまっていた。
グレイスの場合、ずっと男になって立派な密輸業者になるのだと決めていたので元々あまり悩んではいなかったのだが、目の前にシムーンという物が現れてからというもの、急にその思いが揺らいできていた。
「大人になったらシムーンには乗れないのよね?」
グレイスが言うとヴォルケが答える。
「心臓への祈りもできなくなるし、そうなんでしょうね」
そうなのだ。シムーンに付いている心臓とカテドラルにある心臓が同じ物なら、もちろん水渡りの儀式―――嶺国での成人の儀式を終えたら、アニムスの心臓はもう答えてくれなくなるのだ。
「シムーンの神様って、どうして子供のお祈りだけを聞くのかしら?」
「さあ……」
グレイスの問いに当然ヴォルケは首をかしげる。
「大人にならなければずっとシムーンに乗ってられるのかしら?」
それを聞いてヴォルケはじろっとグレイスを睨む。
「そんなこと言うもんじゃないわよ」
「でもヴォルケだってそう思わない? 乗るの好きでしょ?」
「それとこれとは……別よ」
ヴォルケはちょっと目を反らす。彼女はもう一七歳になっている。今はこんな戦いの最中だから儀式をしている余裕がないが、でもこの戦いが終われば……
《戦いが終わったらヴォルケ、乗れなくなるのか……》
何だかそれってすごく寂しい気がする。でももちろん空を飛べなくなるわけではない。シミレがあるし、礁国のリベッラやメイフライでも飛んで楽しいのは間違いない。だがそれだと一つだけできないことがあって……
そんなことを考えていた時だ。いきなり大音響でサイレンが鳴り始めたのだ。
「え? なに?」
「これって敵襲の合図じゃない?」
巫女達は顔を見合わせた。周囲にいた別な兵士達も跳ね上がるように立ち上がると、各自持ち場に走り始める。呆然としている巫女達に兵士の一人が叫ぶ。
「おら! ぼさっとしてるんじゃない!」
「はいっ!」
巫女達は慌てて立ち上がると飛行甲板に走った。
そこには既にウルガヌフが来ていた。
「遅い!」
「すみません」
「敵シムーンが現れた。一時方向に二機だ。お前達も発進しろ」
巫女達はうなずくと各々のシムーンに向かって走った。それから“発進の挨拶”をして各自の席によじ登り、アニムスの心臓に祈りを捧げる。彼女達のアンシエンシムーンは低い唸りをあげると起動した。
もう慣れ親しんだ手順だ。
《でも……》
そうなのだ。今回はテスト飛行でも訓練でもない。本当の戦いなのだ。
戦い……あの遺跡から逃げてきたとき以来だ。それを思い出すとグレイスの胃のあたりがぎゅっと掴まれるような気分になる。するとアントレーネが言った。
「大丈夫よ。あの時とはもう違うから」
「そうよね」
少なくとも何も知らずに操縦桿を握っていたあの時とは、何もかもが違う。
「グレイス=アントレーネ、発進します」
『ヴォルケ=アリエスも発進します』
『よし! 行ってこい!』
二機のシムーンは発進した。
シュネルギアから飛び出したときには既に多数の礁国新型機リベッラが先行していた。
「敵は見える?」
「ええ。二時の方向」
『こちらも確認したわ。行きましょう』
「了解」
考えている余裕はない。巫女達が一気にシムーンを加速させると、軽々と先行したリベッラを追い抜いてしまった。
《うわ!》
グレイスは少し慌てた。
『あまり突出するなよ!』
通信機からウルガヌフの声が聞こえる。
「あ、はい!」
目前に宮国のシムーンが見えてきた。
「あれって遺跡にいた奴ら?」
「多分そうよ」
再び胃のあたりがぎゅっとしてくる。もしあれが本気で攻撃してきたら……彼女達はそれを防ぐことができるのだろうか?
だが敵シムーンは攻撃はしてこなかった。
「あ、逃げるみたい」
「そうだね。こっちは数も多いし……」
グレイスは胸をなで下ろした。これならば戦いにはならないだろう。
だがその時通信機からまたウルガヌフの声がした。
『バカ野郎! 逃がすな』
「え? でも攻撃してこないのなら……」
『帰って大量に仲間を連れてきたらどうするんだよ?』
「あ……」
言われてみれば確かにその通りなのだが……
『追撃して……攻撃しろということですか?』
ヴォルケの問いにウルガヌフが答える。
『そうだ!』
えっと……えっと……
『聞いた? グレイス。行くわよ』
「あ、うん」
考えている余裕はない。
ともかくグレイスとヴォルケの二機のアンシエンシムーンは、逃げ出そうとしている宮国シムーンを追った。
敵機は追いすがるリベッラを振り切ろうとしていたが、礁国の新型機だ。速度だけならシムーンにも匹敵できる。その結果、敵シムーンの後方に雲霞のようにリベッラが固まって追いかけるような形になっていた。
その時だ。急に追われているシムーンの一機から光跡が現れたと思うと、そのまま螺旋を描いて飛び始めたのだ。
「リ・マージョンだ!」
途端に通信機からアリエスの絶叫が聞こえる。
『あれやばいわ! みんな逃げて!』
グレイス達は慌てて側方に離脱した。振り返ると螺旋を描いていた機体がいきなり引き返して、追ってきたリベッラのど真ん中を突破していくのが見えたが……次の瞬間、螺旋型のリ・マージョンから凄まじい閃光が発した。
「うわあぁぁぁ!」
その光と熱がグレイスの背中にも感じられた。
「みんなは? ヴォルケ達は?」
『私たちは大丈夫……でも……』
グレイス達は自分たちの目を疑った。爆発のあったあたりには大量のリベッラが飛んでいたはずなのに……その機影は全くない。リ・マージョンから少し離れて飛んでいた仲間は発動機をやられたらしく、黒煙を上げながら落下していく。
《嘘……でしょ?》
彼女達の仲間が目の前で文字通り、一瞬にして消されていったのだ。こんな至近距離で敵のリ・マージョンを見たのは初めてだったが……だが呆然としている暇さえなかった。
「またやってくるわ!」
先ほどの一機が再びリ・マージョンをしようとしている。今度のはグレイスも見た瞬間に分かった。鮫のリ・マージョン―――来るな! あっち行け、だ。
だが確かに落ち着いてさえいれば離脱するのは難しくない。グレイス達は爆発から再び回避する。
「あいつら……どうやったらいいのよ!」
逃げてばかりでは勝てないのだが……そう思った途端に無性に怒りが沸き上がってきた。
「グレイス! 落ち着いて!」
アントレーネの声と共に、ヴォルケから通信が入る。
『とにかくリ・マージョンさせないようにしましょう』
「させないようにって?」
『後ろについて煽って。得意でしょ』
「あは、了解!」
確かにそうされれば落ち着いてリ・マージョンなどできないはずだ。彼女達はとにかく敵の後ろに回り込もうと努力した。敵シムーンは追跡から逃れようと色々方向を変えてきたが、グレイス達のシムーンも性能に差はない。
《確かに、こうやってればリ・マージョンはできないよね》
敵はこのままでは振り切れないと悟ったらしく、今度は二手に分かれた。
アントレーネが叫ぶ。
「これじゃ逃げられるわ!」
「こうなったら……アントレ! 悪い奴らが妹いじめにやってきた!」
「え、あ……泣き顔なんか見たくない! ああ、アニムスよ、奴らをがつんとやっつけたまえ!」
「「奴らをがつんとやっつけたまえ」
このリ・マージョンは散々練習したので、こういう短縮版でも十分発動できるようになっている。
グレイス達のシムーンがリ・マージョンを始めた。だがどうしたって遅い。リ・マージョンの攻撃エリアは相当に広いとはいえ、逃げた一機を捕らえることはできなかった。
「うわ! 逃げた! 追いかけよう!」
「だめ。深追いはよくないわ!」
確かに今はどさくさ紛れに押しているが、相手が落ち着いて逆襲してきたら負けるのは間違いなくこっちだ。だが敵は逃がすなと言われている。
「でもそれじゃ……」
その時ヴォルケ機から通信が来る。
『あちらの一機に二機で、悪い奴らがやって来た!』
「わかった」
ともかく一機でも確実に仕留めておかなければ……
グレイス達はヴォルケ機に合わせて飛ぶと彼女の声に意識を集中した。
『悪い奴らがやって来た!
妹いじめにやってきた!
妹の泣き顔見たくない!
ああ、アニムスよ。我らの願いを聞きたまえ!
奴らをがつんとやっつけたまえ!』
「「「「やつらをがつんとやっつけたまえ!」
二機のアンシエンシムーンが同期して隼のリ・マージョンを開始した。
二つのリ・マージョンが同時発動すると更に広い壁状にダメージ範囲が広がる。だがそれでも動きの素早いシムーンを捕らえるのは容易ではない。敵シムーンは軽々とその範囲を避けていった。
「あ!」
だが、その方向には味方の弾幕があった。リ・マージョンのダメージエリアを避けて射角内に入ってきた敵シムーンに対して、礁国の僚機が機銃を撃ちまくる。その弾丸が敵シムーンを捉えたのだ。
「当たった……」
敵シムーンは黒煙を挙げながらシュネルギアの方へふらふらと向かって行った。
「ねえグレイス。あのままだとあれ、不時着しない?」
「え? うん。そうだね」
「そんなことになったら……あの人達大丈夫かしら」
アントレーネのその言葉はグレイスをがつんと打ちのめした。
「みんな……滅茶苦茶憎んでるんだよね? あの人達のこと……」
「ええ……絶対……」
その時またヴォルケから通信が入る。
『シュネルギアに落ちるわよ。あれ……そんなことになったら……』
彼女の声もちょっと震えている。
グレイスは通信機に向かって叫んだ。
「だめだよ! 殺されちゃう!」
『でも、それじゃどうすれば……』
「助けるっきゃないよ!」
『どうやって?』
「ともかくみんなより先に行かないと!」
『分かったわ』
何はともあれ、二機のシムーンは全速力で落ちていく宮国シムーンを追った。
それは巫女としての本能のような物だった……彼女達は今まで随分変わったお勤めをしてきたとはいえ、アニムスに仕える巫女であることには違いはないのだ。目の前に今まさに殺されようとしている人がいるのなら、それを助けることができるのが彼女達だけだというのなら、いったいどうすればいい?
礁国兵士達が宮国の悪魔に向ける憎悪は甚だしい物がある。彼らがそれを話す時の目は冷たい怒りに囚われている。それは彼らの間にいれば身をもって感じることができる。その悪魔に消されていったのは礁国の兵士達だけではない。彼女達の大切な仲間も大勢含まれているのだ。その恨み、忘れられるはずがない。
《でも……》
彼女達に命を与えてくれたのは神。ならば命を奪っていくのもまた神の意志なのだ。彼女達は今までそんな神の御業の代行をしてきた。だから恨み言など言ってはならない。彼女達はその命を神に預けているのだから……
《でも……》
そう思っても心は痛い。大切な仲間達と二度と会えなくなることはとても辛い。だから悲しむ。だから祈る。どうして自分なのかと。自分は生き残ってここで何をしなければならないのかと。
ともかく一つだけ言えることは……あの人達を死なせてはならないことだ。なぜなら……
「そんなのダメに決まってる!」
『ええ。そうね』
もしかして思ったことが口に出ていたか?
『不時着するよ!』
アリエスの声に見ると、傷ついた宮国シムーンはそのヘリカル・モートリスを器用に畳みこんで、シュネルギアの飛行甲板上に不時着していた。
グレイス達はその後を追って飛行甲板上に着艦した。幸いなことにまだ兵士達は出てきていない。だが先ほどのリ・マージョンで破壊された僚機はまだ落ちてくる。
「行くわよ!」
『ええ!』
グレイスは風防を開くと、シムーンの外に飛び出した。横を見るとほぼ同時にヴォルケ達も飛び出してくるのが見える。
《これがいるかも……》
グレイスはミニステリウムを取り出した。こんな風に使う物ではないのだが……相手がいきなり暴れそうになったら必要だろう。
巫女達はそのまま甲板上を全速力で突っ走った。
宮国シムーンは甲板の端の、かなり不安定な場所に止まっていた。その上に宮国シムーンのサジッタが出てきて、アウリーガ席を覗き込んで何か話しているのが見えた。
グレイス達はそのまま宮国シムーン上に駆け上がり、手にしたミニステリウムを巫女に向ける。いきなり抵抗されたら困る。それから……
それから?
一体何と言えばいいのだ?
まず思ったことは凄く綺麗な人だということだった。でもいきなりそうは言えないし……
次いで思ったことは、彼女達のコスチュームは何だか巫女らしくないなということだった。でもシムーンを操縦するにはそちらの方が向いてそうだし……何か可愛いデザインだし……などと言ってもしょうがないし……
口火を切ったのは宮国の巫女の方だった。彼女は怖い目つきでグレイス達を睨む。
「あなた方に、私の言葉が分かるのなら聞きなさい。私はどうせこんな所で死んでいく名もないただのシヴュラ。命など惜しくない! しかし……」
それはグレイス達が礼拝の時以外は使わない宮国の言葉だったが、何とか意味を理解することはできた。
「私の後ろにいらっしゃるのはわがシムラークルム宮国最高のシヴュラ、シヴュラ・アウレア・ネヴィリル。絶対ここから助け出し、あなたたちには指一本触れさせない!」
そして分かった。この巫女は傷ついた仲間を守るために命を投げだそうとしている。
そう。彼女は間違いなく誇り高い、真の巫女だ。お仕えする神の名は異なっていたにしても……決して面白半分に呪いの言葉を吐き散らすような悪魔などではないということを。
だが一つ分からないことがあった。彼女は自分のことを名もないただの巫女と言ったが、どうしてなのだろう?
傷ついたアウリーガがシヴュラ・アウレア―――金の巫女なのであれば、そのサジッタは銀の巫女とも呼ばれるべき人なのではないのか? 謙遜しているのだろうか? でもどうして会ったばかりの異国の巫女にそんな謙遜を?
「いえ、後ろの方もあなたも最高のシヴュラです」
思わずグレイスはそう答えていた。
ところが、それを聞いた“銀の巫女”は何故かひどく動揺したのだ。一体どうして? 何かおかしなことを言っただろうか?
ともかくそれで彼女の敵意は随分削がれたようだ。ここぞとヴォルケが彼女に言う。
「あなた方シミュラークルム宮国のシヴュラは、神に最も近いところにいらっしゃる巫女。わがプルングルム嶺国でも最高の敬意の対象です」
更にアントレーネとアリエスも次々に彼女に語りかけた。
「我々もあなた方との戦いを好む者ではありません」
「傷ついたシヴュラを捕まえることは我々の本意ではない」
銀の巫女の表情が少し緩んだ。宮国の言葉は普通は使わないから色々表現が硬いような気がするが……ともかく通じたみたいだ!
「あななたち……」
巫女の言葉にアントレーネとアリエスが答える。
「私たちはプルングルム嶺国の巫女、この船に乗り込む礁国の兵士とは違います」
「先ほどまでの戦いは既に終わりました。戦うべき時は過ぎ去ったのです」
二人の言葉を銀の巫女は俄には信じられないという表情だ。
それは仕方がないことだろう。今の今まで本当に殺し合ってきたのだから……共に行ったリ・マージョンはお互いに巻き込まれていたらその瞬間この世から消え去っていたことだろう。
でもなぜか今は相手が憎いという気がしなかった。それはやはり今、この人の姿を見てしまったからなのだろう。彼女達の大先輩。遙か昔から空に祈りを捧げてきた人達。もしこんな戦いがなかったならば……
《もし戦いがなかったら?》
だとしたら……グレイスとこの銀の巫女との接点は何もなかった。
彼女がシムーンに乗ることになったのは戦争が始まったからだ。戦争がなければシムーンで空に祈ることになるなどとは夢にも思わなかっただろう。
それはともかく……グレイスは言った。
「私たちを信じてください。あなた方を捕まえるつもりなら、こんな手の込んだことをする必要はありません」
銀の巫女はまだ表情を崩さない。そのとき、後ろのアウリーガ席の方から声がした。
「……ーナ」
銀の巫女が驚いて振り返る。
「シヴュラ・アウレア?」
彼女に向かって傷ついた巫女が言った。
「その方達の言葉に偽りはありません……」
銀の巫女は目を見張ると……その表情から疑念が消え去った。
同時に甲板の方から怒声が聞こえてくる。見るとついに兵士達が上部甲板に上がって来ていた。フルフェイスマスクで顔が見えないためより一層恐ろしく見える。
グレイスは巫女に言う。
「お急ぎください」
「うん」
巫女がうなずくとアニムスの心臓―――いや、シムーン球の側にいたアリエスが促した。
「さあ、私と」
先ほどの着陸でシムーンは停止してしまっている。それを再起動しなければならないが、そのためには巫女が二人必要だ。
一抹の不安はあった。果たして奉ずる神の異なる自分達と彼女の間で祈りは通じるのだろうか?
「あ!」
だが心配は無用だった。シムーンの神様は祈りを聞いてくれたのだ! 低い音を立てて宮国のシムーンが起動する。
アリエスと銀の巫女は互いに微笑み合った。
素晴らしい一瞬だった。
だがそれも長くは続かない。甲板上にはもうかなりの兵士が出てきている。このシュネルギアは馬鹿みたいに大きいので、見えていてもここに来るまでにはもう少し時間はかかるが……
シムーンはゆっくりと動き出した。
「一刻も早く」
アリエスが巫女を促す。
できることなら彼女達ともっとゆっくりと語り合いたい。彼女達は普段はどんな祈りを空に捧げているのだろうか? この戦争のことはどう思っているのだろうか? 彼女達も朝が辛かったりパンケーキを焦がしたりすることはあるのだろうか?
《でも、これで……》
一仕事終えたという感じだった。ともかくこれで彼女達は無事に帰ることができるはずだ。生きていればまたどこかで会うこともできるだろう。
巫女達は満足した表情で宮国の巫女を見つめた。
そしてそろそろお別れの時だ、と思った瞬間だ。いきなり銀の巫女がこんなことを言い出したのだ。
「そういうことなのね? ここで私たちを逃がせば、あなたがたの居場所がなくなる」
「は?」
巫女達はびっくりして彼女の顔を見返すが……冗談を言っている顔ではない。本気だ。でも何だ? 居場所?
「いえ、捕まればあなた達は確実に殺される」
グレイスはそう答えたが、その返事は全く予想外の行動だった。
いきなり彼女はグレイス達を四人まとめて突き飛ばしたのだ。そんなことをされるとは思ってもいなかったので、巫女達はもんどり打って甲板上に転落する。
それから彼女はグレイス達に向かって言ったのだ。
「あなた方は私を本当のシヴュラだと認めてくれた。私を逃がせば、あなた方が裏切り者として殺される」
え?
裏切り者って……確かに敵の巫女を逃がすというのは良くないことではあると思うが……そこまでのことだろうか? もの凄く怒られることは覚悟しているが、処刑されたりすることはないと思うのだが……
だが次いで彼女の取った行動は更に驚くべき物だった。
銀の巫女は短刀を取り出すと……何と自分のおさげ髪をばっさりと切り落としたのだ!
《どういうこと?》
古今東西、娘が髪を切るというのは何かから決別する瞬間と決まっている。
一体あの人は何と決別しているのだろうか?
銀の巫女はアウリーガ席の傷ついた巫女に何かをささやくと……飛んだ。
「ああ!」
動き出したシムーンから彼女は、シュネルギアの甲板の一番端にかろうじて飛び移る。グレイス達は慌てて彼女に駆け寄ろうとするが、甲板の端は下方にカーブしていて傾斜がどんどん急になっていく。
「助けなきゃ!」
「ええ!」
グレイスは他の三人に支えてもらって、何とか落ちかけた銀の巫女の手を掴んで引き上げることができたが……
「何ということを!」
一体何を考えているのだ? この巫女は……
確かにこれは重大な命令違反とは言えるかもしれないが……でも逃がすなという命令は受けていない気がするし、いきなり死刑になったりすることなどないと思うのだが……それとも宮国ではそうなのだろうか?
それより問題は、今まさに彼女の命が風前の灯火だということだ。
既に兵士達は間近に迫っている。彼らがこの巫女を捕らえたら……もうお終いだ!
《一体どうすればいいの?》
本当に何を考えてこんな真似を……そう思ってグレイス達は巫女を見て、驚愕した。
銀の巫女の顔は……とても穏やかだった。
こんな表情をする人達をグレイス達はよく知っていた。それは……ここが自分の人生の終焉だと知っていて、そのことに心から納得している人の顔だ。
礁国兵士達が迫ってくる。
考えている暇はない。
「あなたが……あの者達の手にかかって命を落とすくらいなら、いっそ?」
自分たちの手にかかって死にたいと? そういうことなのか?
いや、彼女は宮国の巫女だ。嶺国の血塗られた伝統などを知っているはずが……
だが続いて彼女はこう言ったのだ。
「これでいいのよ。これで。あなたたちの国の言葉、アー・エル」
巫女達は目の前が真っ暗になったような気がした。
そう。彼女ははっきりとその言葉を口にした。
彼女達は命を分け隔てしない。その覚悟と共にその言葉を唱える者を送ってやるのは……彼女達の義務だ。
涙が目から溢れる。だがそれで狙いを外してはならない……
巫女達は銀の巫女にミニステリウムを向けて……
「「「「アー・エル!」
四発の弾丸が発射された。
銀の巫女は前のめりになって甲板上に倒れる……だがまさにその瞬間だった。甲板の下方から聞き覚えのある響きが聞こえてきたのは……
巫女達がその方に目を向けると……下から四機の宮国シムーンがぬーっと現れた。
《ええ? どうして?》
グレイスは呆然とその姿を見つめた。
次の瞬間、シムーンの機銃が火を噴いた。途端に後ろから誰かに引っ張られる。振り返るとフルフェイスのゴーグルを被った大柄の兵士だが……
「馬鹿野郎! 戻れ!」
その声はウルガヌフだ。
「でも……」
グレイスは倒れている銀の巫女を指す。彼女にはこれから清めの儀式をしてやらなければならないのだ。
だがウルガヌフはグレイスの胸ぐらを掴むと、アンシエンシムーンを指して言った。
「シムーンを守れ! あれを失ったら全てが無意味だ」
その言葉の意味だけはよく分かった。
巫女達はまるで人形のようにうなずくと、もうそれ以上は何も考えずにただ彼女達のシムーンに向かって走った。
巫女達が期せずして礁国空軍基地に戻ると即座に総司令達に呼び出された。
リフェルドルフは顔を真っ赤にしてまくし立てている。
「馬鹿者が! 宮国巫女を殺すわけがないだろう! 生かしておいた方がどれだけ役に立つか分からんのか!」
グレイス達は返す言葉もなかった。
「そのうえ、あれに乗っていたのが本物のシビュラ・アウレア・ネヴィリルだったとしたらもう、人質と言うだけでどれほどの価値があるか分かるか? 宮国の副院主の娘だぞ。宮国ナンバー2の娘だ! 下手をすればそれだけで戦争を終わらせられたかもしれないのだぞ?」
「申し訳ありません。でも……兵士達に捕まったら殺されると思ったんです」
そうグレイスは答えたが、リフェルドルフは大声で怒鳴る。
「だから殺したりなどしない! 確かに宮国の悪魔は憎い。でもそれとこれとは別だ! 戦争とは単に憎しみで殺し合っているのではないのだ!」
相手が憎くもないのに殺し合うのはもっとおかしいような気がしたが、グレイスは黙っておいた。確かに憎くなくとも殺さねばならないことはある。そのことは彼女達が一番よく知っていたが、それとこれとは違うように思うのだが……
ともかく今はもう取り返しの付かないことをしてしまったという後悔だけが残っていた。彼女はもう戻っては来ない……
グレイスは歯を食いしばる。
《どうして……もうちょっとだけ早く来てくれれば……》
考えれば考えるほど、あの悲劇は簡単に回避できていたことが明らかになっていく。
総司令の言う通り、冷静に考えれば兵士達がいきなり捕虜を殺すようなことはないはずだった。そんな勝手な行動は軍規という物で禁じられているはずなのだ。それに生かして捕虜にした方が相手の情報をいろいろ聞き出せるかもしれないし、役に立つのは間違いない。
そうなればあの二人は少々不自由な目には遭うだろうが、間違いなく安全で、怪我の治療だってしてもらえたはずだ。
そして宮国ではどんな風に空に祈っているかといった話を聞くことだってできたかもしれないのに……
《それにあの人も勘違いしなければ……》
彼女はこう言った。
『私を逃がせばあなた方が裏切り者として殺される』
でもそんなことはあり得ないのだ。グレイス達は今、両国合わせて唯一の“シムーンパイロット”だ。彼女達がいなくなったらシムーンを飛ばした経験者は誰もいなくなる。それに彼女達はあの墜ちた雛鳥作戦の生還者なのだ。そのことは兵士達もよく知っていて今では大切な仲間として認めてもらっているのだ。だから確かに滅茶苦茶怒られることにはなるだろうが、少なくとも殺されてしまうようなことはないだろう―――彼女がもしそのことに考えが及んでいたのなら、間違いなく傷ついたシヴュラと共に帰って行ったことだろう。
でも彼女はそうは考えなかった。彼女はグレイス達が殺されると考えて……
《そのために彼女が飛んできたとしたのなら……》
だとしたらあの銀の巫女はどれだけ優しい人なのだろう?
彼女にはもっと助けなければならない人がいたはずなのだ。後ろで傷ついていたシヴュラ・アウレア。どうしてあの巫女はその人を置き去りにしてまで自分たちのために飛んで来たのだろうか? あの瞬間初めて会っただけの、しかも敵同士の私たちのために?
《それに……どうして彼女はあんな決意を?》
彼女は自分たち同様、そんなことをすれば殺されると信じていた。だがその顔には一片の恐れも後悔もなかった。決意のできた人の安らかな表情がそこにあった。そして……彼女は間違いなくあの言葉を口にした。
『これでいいのよ。これで。あなたたちの国の言葉、アー・エル』
本当に彼女は知っていたのだろうか? その言葉の真の意味を。辞書には“愛の中の最上の愛”という訳語が乗っている。実際それで間違いはない。でもそれがどこでどのように使われるかは辞書には載っていないのだ。
もし彼女が何か思い違いをしていたのならば……あれはただの人殺しでしかない。
グレイスは沸き上がってくる嗚咽を必死で我慢した。
《だからどうしてもうちょっとだけ早く来てくれなかったの?》
ほんの少しだったのだ。宮国シムーンがやって来たのは、彼女を撃ってしまったほとんど直後だったのだ。
あそこでもう少しだけ迷っていたらどうだっただろう? 兵士達が来ても彼女達が立ちふさがれば時間が稼げたはずだ。そうしていれば間に合ったのだ。
《何ぐずぐずしてたのよ! あんた達がもうちょっとだけ早く来てれば……》
いや、もちろん宮国の巫女達も必死だったのだろう。仲間の危機を知ってあらん限りの速度で駆けつけてきたのだろう。だが本当に、本当にほんの少しだけ遅れてしまったのだ。ほんの少しだけ……
一体……どうしてこんなことになってしまったのだろう?
「それで総司令。どのような処分を?」
ベネトラルフ副司令が言った。リフェルドルフは首を振る。
「こんなことは前代未聞だ。投降してきた敵兵を衆人環視の元で射殺するなど……それは極刑に値する行為だ」
ベネトラルフは珍しく声を荒げる。
「しかし彼女達はお勤めを果たしただけなのです。そのことを罪に問うわけにはいきません」
「彼女達がそう言っているだけだ」
「彼女達は嘘は言いませんよ?」
「もちろん疑ってはいない。だが本国の連中はそうではないだろう」
それを聞いてベネトラルフはリフェルドルフを睨み、低い声で言う。
「でもそうするとシムーンはどうします?」
「わかっておる」
リフェルドルフは鼻を鳴らすとウルガヌフを見た。
「お前はそこにいたな? あの巫女は、何か抵抗する素振りは見せたか?」
ウルガヌフはちょっと目を見開くと少し考えてから答えた。
「はい。怪しい動きを見せましたので、彼女達に危害が加わるとまずいと思い部下に発砲を命令しました」
「なるほど。そうだったか。それでは仕方がないな。彼女達の供述とは少し違うが、少し動転していたのだろう」
いや、そうじゃないから……
「ちょっとお待ちください!」
思わずグレイスは総司令に食ってかかろうとしたが、そこにウルガヌフが立ちふさがって睨み付ける。
「お前らは黙ってろ!」
巫女達はその剣幕に口を閉じた。
その彼女達にリフェルドルフが言った。
「あれは前線ではありがちな、不幸な事故だったということだ。いいな?」
巫女達は不承不承うなずいた。
「だがその前に君たちは宮国の巫女達を逃がそうとしていたのも目撃されているが、そちらの責任は取ってもらわないと困る。これもまたかなりの重罪であるが……」
それを聞いてベネトラルフが口を挟む。
「お待ちください。彼女達は巫女としての本分を全うするためにそうしたまで。それに彼女達は礁国軍に属する兵士ではないことをお忘れなきよう」
リフェルドルフは首を振る。
「わかっておる。だが一応示しという物があるのでな。彼女達には今晩は営倉で過ごしてもらうことになる。それ以外の処分については、君に一任する」
ベネトラルフはちょっと驚いた表情だったが、すぐに敬礼した。
「はい。承知しました」
二人のやりとりを見ていて巫女達は少々混乱していた。
これはどういうことなのだろう? あれだけのことをしでかしてしまった罰が、今晩一晩営倉入りで済むということだろうか? だがどうやら本当にそうらしかった。
総司令は居住まいを正すと全員に向かって言った。
「それからだ。今まで確かに、宮国のシムーンが不時着してくるなどという状況がなかったので、そういう場合の処理が明確に想定されていなかったと思う。今後そういう状況では当然そのシムーンと乗組員の確保を最優先する。乗組員は決して傷つけてはならない。それを徹底させるように」
「了解しました」
その時それまで側で黙って聞いていたドクターが言った。
「あと、壊れたシムーンでも死んだシヴュラでも、可能な限り回収してほしい。研究に使いたいから」
「え? 亡くなったシヴュラを?」
思わずグレイスは問い返していた。
壊れたシムーンはともかく、死者は弔ってやらねばならないのだが?
「ああ。我々は知らなければならないのだ。これほどまでに破壊力のあるシムーンがどうして性分化していない少女のみに反応するのか? それを知るために必要なのだよ」
「でも……巫女の遺体をどうされるのです?」
ヴォルケの声がちょっと震えている。
「死体でも色々調べられるのだ。彼女は残念だった。言わば宮国のエースの一人だったのは間違いない。そういうシヴュラは何か普通の少女と違うところがあるに違いない。例えば脳の構造とか内分泌器官とか。それを調べれば何か手がかりが掴めるかもしれないのだ」
ちょっと待て! 彼は死体を切り刻んで調べるつもりなのか?
「それによって例えば、未分化の動物の脳などを使ってシムーンが飛ばせるようになれば、分かるか? それで大人がシムーンを操作できるようになるわけだ。そうすればもう君たちみたいな子供を戦場に送る必要はなくなる。もう一方通行の船に子供達を乗せて送り出さずに済むのだ」
「ドクター?」
熱くなって話し始めたドクターをリフェルドルフが諫める。ドクターははっと顔を上げると、目を丸くして彼を見つめていた巫女達を見て苦笑いする。
「いや、まあそういうことなんでな。ともかく今度そういうことがあったら、できる限り生きて連れてきて欲しいのだよ」
生きて連れてきたら今度は生体実験でもするつもりなのか?
巫女達は信じられないという面持ちでその話を聞いていたが、一つだけ理解できることがあった。それはドクターもまた彼なりに真剣なのだということだ。そんなやり方は承服しかねるとはいえ、一方通行の船に子供達を乗せずに済むと言ったときの彼の目は、まごう事なき悲しみに満ちていた。
《そんなことして本当に分かるのかしら?》
グレイスはそう思ったが、その思いに何か根拠があるわけでもない。もしかしたらドクターなら何かを見いだせるのかもしれない。
多分ドクターもまた、暗闇の中で手探りしているような状況なのだろう。彼女達と同様に。
その日の晩は初めての営倉泊まりだった。悪いことをした兵隊を閉じ込めておくための、要するに兵隊用の牢屋だ。
薄暗い部屋の中には一カ所に手洗いがあるだけで、後は何もない。寝るときはむき出しのコンクリートの床の上に薄い布団を敷くだけだ。
「うわー。背中痛くなりそうだね……」
グレイスが布団を撫でながらそう言うと、ヴォルケがぼそっと答えた。
「あなたは気楽でいいわね」
それはいつものヴォルケの調子だったのだが、その日は妙に腹が立った。
「どういうことよ?」
食ってかかるグレイスにヴォルケもじろっと睨み返す。
「気楽そうだからそう言ったまでよ」
「なんでよ?」
グレイスはヴォルケににじり寄った。
「ちょっと! 二人ともこんな所で」
その様子を見て慌ててアントレーネが間に入る。
ヴォルケはふうっとため息をつくと、黙って冷たい床の上に座り込んだ。
グレイスも別にそんなつもりではなかったのだが……
他の巫女達もめいめい、壁を背にして座り込む。
やがてぼそっとアントレーネがつぶやく。
「どうしてこんなことになっちゃったのかしら……」
「どうしてだろうね……」
それからまた沈黙が続く。
どうしてなのだろう? あの時どうすれば良かったのだろう?
その時だった。外でがしゃがしゃっと音がして、営倉の扉が開けられた。
「それでは我々は外で待っています」
「ありがとうございます」
この声は……
巫女達が顔を上げると、そこには見知った顔があった。
「教母様!」
入ってきたのは基地に巫女達の付き添いとして一緒にやってきた、アウロス教母、プルミエラ教母、リエラ教母の三人だ。
《そう言えば、総司令は処分はそちらに任せるって言ってたけど……》
巫女達は蒼くなった。総司令やウルガヌフ隊長に怒られるのは何というかあまり怖くないのだが、教母達は別だ。身に染みついた性というのだろうか? 心のどこかで自分は兵士ではないから関係ないという気持ちが働くからだろうか。だがそういった意味ならば、教母達からは逃れられない。
「教母様……」
それ以上言葉が出ない。ただぽろぽろと涙がこぼれてくる。
そんなグレイスをアウロス教母が、アリエスをプルミエラ教母が、ヴォルケとアントレーネをリエラ教母がそれぞれ抱きしめた。
「おかえりなさい。みんな……」
巫女達が彼女達の顔を見ると、その目にも涙が溢れているのが分かった。
「よく帰ってきました」
「教母様!」
巫女達は彼女達の胸に顔を埋めてただ涙をこぼした。
教母はささやくように言った。
「話は聞きました」
グレイスはぴくっと身を震わせる。だがアウロス教母は更にぎゅっとグレイスを抱きしめる。
「それがどこの誰かかは関係ありません。巫女の元にやってきてその言葉を唱えたというのであれば、それはお勤めです」
それを聞いてヴォルケが言った。
「でも……あの方はその言葉の意味をよく知らなかったのかもしれません」
だが教母達は首を振った。
「その方が決意して残り、その言葉を口にした。それは偶然ではありません。そこにアニムスのご意志があったから、だから彼女はあなた方の元に導かれたのです」
本当なのだろうか? 本当にそう信じていいのだろうか?
いや、疑っているわけにはいかない。彼女達はそう信じなければならないのだ。
「さあ、涙をお拭きなさい」
教母はハンカチを差し出した。
「そんな顔で彼女達と再会しますか?」
巫女達が驚いて顔を上げると……営倉の扉から居残りの巫女達が覗き込んでいるのが見えた。
「グレイス?」
その声は……ポルフィーだ!
途端にばらばらと巫女達が房の中になだれこんできた。
「これ! あなた達はまだいいとは言っていませんよ?」
「すみません! でも!」
そのままグレイス達は居残り組にもみくちゃにされて、何がなにやら分からなくなってしまった。