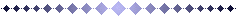第9章 怒り
グレイス達四人が期せずして空軍基地に戻ってから数日が経過していた。
その間、彼女達は目が回るような忙しさだった。
《これって……夢じゃないのよね?》
グレイスは眼前に広がる光景を見ながら何度も目をこする。だが間違いない。彼女達の前にはアンシエンシムーンが六機、朝日に輝いて鎮座している。
なぜそれがここにあるかというと、それは例の追加シムーン奪取作戦が昨日実行されたからだ。
本来なら間違いなく特筆すべき事件だったはずなのだが……何だか上手くいきすぎて、ちょっとお使いに行って帰ってきたようなもので、それ以上何とも語りようがないのだ。
昨日の早朝、アンシエンシムーンに追加の控え巫女達が乗り込めるアタッチメントを付けると、二機のシムーンはそれぞれが六名ずつの巫女を載せて離陸した。彼女達は一度嶺国方面まで迂回して前回とは逆方向から宮国の聖地を目指す。到着すると控え巫女達を下ろして再びあの洞窟を目指した。
唯一の不安事項は本当にまたそこにアンシエンシムーンが存在するかという点だったが、それも問題なかった。先日彼女達がそこにあった四機のうち三機を持ちだして、残りの一機も宮国に輸送されたはずなのに、そこにはまた同じく四機のアンシエンシムーンがあったのだ!
本当に不思議な話だが……ともかく理由などどうでもいい。そこにシムーンがあることが重要だ。シムーンさえあれば後はそれに乗って帰るだけだ。
控えの巫女達もシミレでの訓練は十分受けているし、その前に二日ほどシムーンの現物にも触れている。普通に飛ばすだけならもう全く問題はない。
グレイス達は一応あのオナシア様にだけは挨拶した方がいいかと思って奥の泉にも行ってみたが、昨日はどうも留守のようだった。
そんなわけで、その後は彼女達はずらっと一列に並んで子ガモの行列のように元来たコースを戻っていった。通信機があるのはグレイスとヴォルケの機体だけなので、はぐれたりしたら困ったことにはなるがそんなこともなかったし、最初から最後まで敵の影さえ見えなかった。トラブルらしいトラブルと言えば、アヴェラーナという子がアタッチメントから降りるときに足を滑らせてお尻をしこたま打ってアザができたことくらいだ。
「それじゃもういいですか?」
アントレーネが整備士の人達に言う。
まだ整備士の人達が周りで作業中だ。夕べは徹夜で通信機などを付けてくれていたのだ。
「おう。大体完了だ」
「いいの? もう乗れるの?」
早朝だというのに控えの子達も全員集まってきている。
「じゃ、みんな集まって!」
グレイスの声に控えの巫女達が勢揃いする。
「おう、みんな揃ったか?」
そこにウルガヌフ司令があくびをしながら出てきた。
「はい」
「じゃ、後はよろしくたのむ」
そう言って彼は近くの椅子にどっかりと座り込むとうたた寝を始めた。
「はあ……」
基地に戻って来てからのことなのだが、何故かグレイスが一番機のアウリーガだからリーダーをやれと言われて断りきれなかったのだ。大体彼女はこの中では一番年下の部類だし、そもそもリーダーなんて柄ではないのだが……そんな時の逃げ方はヴォルケには叶わないし……そのうえウルガヌフが何か助けてくれるのかと思ったら、シムーンのことは俺には分からないからお前らよろしくな、とのことだ。
《いいのかしら?》
とはいっても、任せられた以上はやるしかない。そういうわけでグレイスは控え巫女達に向かって言った。
「えーっと、それじゃ今日は最初は各自で、リ・マージョンの練習をしてください。どういうのをやるかはもう考えてるでしょ?」
「はいっ!」
巫女達はにこやかに返事をする。もうはやくシムーンに乗りたくってうずうずしている顔だ。
《数日前の顔とはまったく別人みたい!》
グレイスは笑いを堪えた。
―――営倉で一晩を過ごした次の日、彼女達はすぐに控え巫女達の訓練をすることになった。
控え巫女は西カテドラルからはポルフィー、ファールケ、マリキータ、ラグーナ。南からはラティオーネ、アギーラ、ステラ、ウィオリナ、東からはラリッサ、アヴェラーナ、アリアーテ、クリネーアの計十二名だ。
グレイス達がもたらしたアンシエンシムーンの前に集合した彼女達の表情は……そう。これから獲物に襲いかかろうとしている肉食獣の表情とでも言ったらいいだろうか?
彼女達も墜ちた雛鳥作戦の結果がどうなったかは知っている。それぞれかけがえのなかった仲間が、もう戻ってこないことを知っている。
それを見てアントレーネがささやいた。
「あたし達もあんな顔だったのかしら?」
「多分……ね」
そこにヴォルケがささやく。
「じゃあ、お願いね。リーダー!」
「分かってるわよ」
グレイスは大きく深呼吸をすると、そんなぎらぎらした巫女達の顔を見て言った。
「それではこれから空に祈る方法をみんなに教えます」
それを聞いた巫女達はあからさまに拍子抜けな顔になった。
グレイスは笑い出しそうになるのを堪えると、巫女達の顔を見回して言った。
「えーっと、この中に料理の下手な人、いる?」
控え巫女達は目を丸くして、何を言っているのだこいつは? といった表情でグレイスを見る。
西カテドラルにそういう子がいれば指名もできたのだが、今いる四人はみんな料理上手だ。
そこにヴォルケが口を挟んだ。
「リーダーの言ったこと、聞こえなかった? これってとても大切なことなの」
だが巫女達は相変わらずなのでアリエスがグレイスに囁いた。
「じゃ、ラリッサがいいんじゃない? あなた達と同じくらい彼女も下手だから」
それが聞こえたようでラリッサがぎろっとアリエスを睨む。
グレイスはラリッサの前まで行くと尋ねた。
「アリエスの言ったこと、本当?」
「え? まあ……それが何か?」
ラリッサはむっとした様子でうなずいた。
「よし! じゃ、一緒に来て」
「はい?」
「いいから!」
グレイスはそのままラリッサを引っ張ってアンシエンシムーンの下に行った。
「これから二人でリ・マージョンしてきますから見ててね」
「え?」
巫女達が驚きの声を挙げる。一番驚いているのは当のラリッサだ。
「あの、あたし……」
「いいからいいから。乗って」
ラリッサは首をかしげながらシムーンのサジッタ席に乗ろうとして、またグレイスに止められる。
「違う。アウリーガ席に行って」
「ええ? でもいきなりそんな……」
「大丈夫だって!」
グレイスがラリッサをアウリーガ席に押し込んで自身はサジッタ席に乗ると、シムーンはいきなり凄い速度で上昇していった。
巫女達が心配そうに見上げる。そこでアリエスが笑いながら言った。
「見てらっしゃい」
すると……急に上空のシムーンの後ろから光跡が出始めたと思うと、円く輪を描き始めて、次いでその円周上をくるくる回り始めた。形ができあがるとそれはほわっと光ってかき消えていく。
「えええ?」
巫女達から驚きの声が上がる。それをヴォルケとアリエス、アントレーネがにやにやしながら眺めていると、上空のシムーンが降りてきた。
彼女達が着地するとすぐにグレイスとラリッサが降りてきた。グレイスがラリッサに言った。
「さあ、ラリッサ。あなたからみんなに説明して」
ラリッサは興奮で上気していたが、慌ててうなずくと言った。
「ええ。その、あたしたち、お祈りしてきたの」
「は?」
その説明に巫女達はラリッサにあからさまな不信の眼差しを向ける。ラリッサは慌てた。
「それがね、その、パンケーキを上手に焼けますようにってお祈りなんだけど……」
巫女達はつまらない冗談をいうなという様子で、じとっとした目つきでラリッサを見つめる。
「嘘じゃないの! 本当なの!」
ラリッサは半泣きでグレイスやヴォルケの方を見る。そこでグレイスは言った。
「えーっとね。リ・マージョンのやり方にはどうも二通りあるみたいなの。みんなもマニュアルは読んでると思うけど、あれは難しい方で、今やったのは簡単な方なんだけど、シムーンに乗ってアウリーガとサジッタが二人で心のこもった同じお祈りをすると、ああいう風にリ・マージョンできるのよ」
「ええ?」
巫女達はまた驚きの声を挙げる。
「でもね。お祈りには本当に心がこもってないとだめで、例えばヴォルケとかはお料理が上手だからあのリ・マージョンはできないの」
巫女達は俄には信じられないという表情だ。
「だから、そうね、今度はファールケ」
グレイスは彼女に手招きした。
「なによ?」
不審そうなファールケにグレイスは言った。
「あのハヤブサコース降りようとするときは、やっぱりお祈りしたでしょ? 絶対うまくいきますようにって」
ファールケは西カテドラルでの箱橇仲間だ。相方は違っていたが、その時の気持ちに違いはないはずだ。
「え? そりゃ、そうだろ」
彼女は曖昧にうなずいた。
「じゃあそれやってみましょ。みんなもそれぞれそういうお祈りを思い出してみてね」
それからグレイスはラリッサ同様にファールケをシムーンに押し込んで、今のお祈りを試してみた。これも見事に成功して何だかジグザグの凄くかっこいいリ・マージョンが完成した。
降りてきたファールケが興奮してラリッサと同じような説明を繰り返すのを聞いて、巫女達も段々分かってきた。どうやら本当にリ・マージョンとはお祈りをする行為であり、シムーンとはお祈りをするための装置らしいということを。
こうしてその日のうちに全員がリ・マージョンを体験することができた。ただしできたのはニンジンのリ・マージョン、そばかすのリ・マージョン、雪下ろしのリ・マージョンといった物ではあったが……
その日の晩、巫女達がきらきらした目をしてお祈りの話をしているので、あたりの兵士達が不思議そうな顔をしていた―――
こうして今では彼女達もシムーンの虜だ。彼女達の祈りが空に大きく美しく描かれるのだ。こんな楽しいことはそうある物ではない。
でも楽しんでだけはいられない。彼女達は戦いの場にいた。
「フリーの練習は一時間。それが終わったら攻撃型のタイミング合わせをします」
「は~い」
理屈が分かってしまえばそこまで難しいことではないのだが、やはりみんなで同時に同じ祈りを捧げるというのは上手くいかないことも多い。発動詩を聞いて反射的に気持ちをそちらに持って行ける練習は必要だ。
そして練習となると途端につまらなくなってしまうのも事実で……
《あー……ずっとお祈りだけしてられないかしら》
そうできたなら何と嬉しいことだろうか?
その時だった。遠くから伝令の兵士が走ってきて敬礼した。
「ウルガヌフ司令! それからグレイス軍曹にヴォルケ軍曹!」
うー。何だかいつの間にか彼女達にはそんな肩書きがついていた。
「あんだ?」
「これより戦略会議が開かれるそうなので参加してください」
「ああ? 戦略会議? 昼からじゃなかったのか?」
「急遽時間が繰り上げられました。元帥閣下もいらっしゃっております」
「ああ? 分かった」
「会議にはお二方も」
伝令の兵士はグレイスとヴォルケにも言った。
「えええ? どうして?」
「今回の会議にはどうしても必要ということで」
グレイスとヴォルケは顔を見合わせるが、もちろん拒否できるわけがない。
「えっと、それじゃ、後よろしく」
「ええ……」
二人はアリエスとアントレーネに控え巫女達の訓練を頼むと、急いで会議の場に向かった。
基地の会議室は人で一杯だった。
普段だったらリフェルドルフ総司令、ベネトラルフ副司令、その他各部隊の司令とかがいるだけなのだが、今日はそれ以外に見たことのない、軍人でない偉そうな人まで大勢列席している。
その時ヴォルケがグレイスの肩に触れて言った。
「あれって副首領様じゃないの?」
彼女の指さす方を見ると……確かにそこにいるのは嶺国の副首領だ。いつか西カテドラルに来たときに一度間近で会ったが……その側に嶺国の巫女が一人、付き従っている。
「あら?」
ヴォルケが彼女を見ると、その巫女がこちらに手を振った。
「プリマヴェーラだわ!」
そうつぶやいてヴォルケも手を振り返す。
「え? 誰?」
「南で一緒だったのよ。語学がすごくできたから、ずっと首領様とかに付いて、大切な会議の通訳とかお見届けをしてたのよ」
嶺国では大切な会議をする際には、それを見届けるために巫女が同席する習慣があるが……ということはこの会議はそんな大切な会議なのか?
グレイス達が入ってくるのを見て、司会席に着いていたリフェルドルフが言った。
「これで全員揃いましたか?」
一同が黙ってうなずく。
「まずは紹介しておきましょう。こちらが巣に戻ってきた雛鳥達です。右がグレイス。左がヴォルケ。あと二名アリエスとアントレーネがいますが、彼女達は今、訓練任務中です」
会場がおおっとどよめいた。
「えっと、あの?」
横でウルガヌフが二人に囁く。
「黙って礼をしておけ」
二人は言われたとおりにした。
「我々が入手できたアンシエンシムーンについては後で見て頂くことにしますが、まずはここでこれからの戦略について意見を交換しておきたいと考えております」
リフェルドルフは人々の顔を見渡して、それからベネトラルフに向かって言った。
「さてそれでは現在の状況の説明を頼む」
ベネトラルフはうなずくと話し始めた。
「はい。それではお手元に資料は渡っていると思いますが、現在の我々の状況を再確認しておきたいと思います。まず、我々は現在六機のアンシエンシムーンとそれを操縦できる巫女十六名を保持しています。そのシムーンでは既にリ・マージョンも成功しており……」
彼は現在の嶺国・礁国の現状を説明していく。
「しかし、現在の我が方のシムーン戦力ですが、これは単純比較したら宮国側に対して圧倒的に劣っていると言うべきでしょう。まずその数からしてそうですが、それ以前にシムーンの操縦技術、リ・マージョンの実行技術についても、彼女達は素晴らしい成果を挙げてはおりますが、やはり長い伝統のある宮国に圧倒的なアドバンテージがあるのは間違いありません」
一同はどよめいた。一人の男が彼に尋ねる。
「まともに戦っては勝ち目がないと?」
ベネトラルフはうなずいた。
「正直その通りです。現在彼女達のできる戦闘用リ・マージョンは三種類。しかもそのうち一つは防御用なので攻撃に使えるのは二種類。それも比較的単純な物に過ぎません」
「あの機甲師団を壊滅させたような物は?」
「はい。あのような破壊力を持つ物はまだ再現できておりません。それに報告書にも記されていると思いますが、リ・マージョンの発動方法が宮国と我々では異なっているのです。宮国側がそのような方法でリ・マージョンを行っているとした場合、宮国巫女達のシムーン操縦技術は極めて高いと考えられます。彼らがそれをリ・マージョンを描くためでなく、空戦に応用しようと思った瞬間、我々の優位は全て消し飛んでしまうと考えるべきでしょう」
「我々の方法ではそれ以上のリ・マージョンは困難だと?」
グレイスはぎくりとした。
ベネトラルフはそんな彼女達の方を見ると、再び質問した男の顔を見て答えた。
「あなた方も墜ちた雛鳥作戦の報告書はご覧になっていると思います。我々はこれまでも彼女達に限界ぎりぎりを強いてきました。それに彼女達は見事に答えてくれました。ですからここからは私たちがしなければならないことなのです」
質問した男は黙ってうなずくしかなかった。
それを受けてその横にいた別な男が言った。
「だからここで我々が腹をくくらねばならないと、そういうわけですな?」
ベネトラルフは再びうなずく。
「そうです」
「しかし、和平交渉を宮国側がそう易々とは受け入れるとは思えませんが?」
「それはその通りだと思います」
嶺国は一回和平交渉と見せかけたひどい破壊工作を行っているのだ。また再び同じようなことを言っても、受け入れてくれる可能性はとても低いということはグレイスにも分かる。
その時口を開いたのは嶺国の副首領だった。
「しかし宮国側が動揺している今は、確かに今がチャンスかもしれませんな」
「動揺しているとどうして?」
それに対して副首領は答えた。
「実は私達は昨夜、宮国の密使と会談しておりました」
「なんですと? 一体誰からの密使と?」
「それは言えませんが、宮国の相当な立場の方からの、とだけ申し上げておきましょう。その方からはこれまでも色々重要な情報を頂いたりしていたのですが、今回はもし宮国がこの戦争に負けた場合の自身と一族の安全確保についての打診でした」
「なんと……」
それを聞いてウルガヌフがつぶやいた。
「ネズミは泥船から逃げだそうってか?」
嶺国副首領は続けた。
「我々がシムーンを手に入れたという事実は、それほどまでに彼らを打ちのめしているということです。従って今ならば十分に和平交渉をしても受け入れられる素地はあると考えられます」
そこに礁国の軍服を着た押し出しのよい男が尋ねた。
「うむ……だが、ここで変に下手に出たら、逆に相手に見透かされる事にはならないか?」
「それは……」
嶺国副首領は言葉を濁す。
「そうなるとせっかく手に入れた切り札の価値が下がってしまうことにもなりかねませんな」
「でも元帥閣下。このまま攻勢に出ても押し切れる保証はあるのでしょうか? 確かに我々はアンシエンシムーンを手に入れたわけですが、それでも圧倒的に不利な状態から、かなり不利な状態になっただけだとしか言えないわけです」
「それはそうだが……」
「ならばやはりここで和平交渉を行ってみるのが良いのでは?」
「だが今の状況ではどうかな。何というか、決定的な何かが足りない。私はそう思うのだが」
それを聞いた嶺国副首領は黙り込んだ。その代わりにリフェルドルフが言った。
「だから最初からこれは賭だと申しております。しかし絶望的な賭ではない。十分に勝ち目のある賭です」
会議の参加メンバー達は腕を組んで考え込んだ。
それから、嶺国の副首領がグレイス達の方を見て言った。
「君たち、やはり難しいかな?」
「え? 何がですか?」
「もっと破壊力のあるリ・マージョンをすることだ」
!!
それは……
彼女達が答えないので、ウルガヌフが横から尋ねる。
「おまえら、今までの話、分かってるか?」
「えっと……いえ、あんまり……ヴォルケは?」
ヴォルケも首を振る。
あたりから低い笑い声が上がる。そこでウルガヌフが小声で説明を始めた。
「要するにだ、俺たちは今、宮国を謝らせてやろうとしているんだ。和平交渉っていうのはそういうもんだ。分かるな?」
「あ、はい……」
「でも、今のままだと少々インパクトに欠けるんだよ。相手に謝らせるには、こっちが強いところを見せてからの方がいいだろ?」
グレイスもおぼろげに理由が分かってきた。
「それで強力なリ・マージョンを?」
「まあ、そういうことだ」
グレイスとヴォルケは顔を見合わせる。確かに今のままではちょっと印象が薄いのは確かだ。宮国シムーンがやってきたあの螺旋型の奴とかは見かけも破壊力も凄まじいわけで……こちらにだってそういうことができることを示してやれれば、相手だってうんと言わざるを得ないということらしいが……
「あの、頑張りますけど……その……」
ウルガヌフはそんなグレイスの肩をぽんと叩くと全員に向かって言った。
「ちょっと彼女達も急に聞かれても即答は難しいと思います。もう少し検討させてもらえませんか?」
それを聞いた礁国の軍人が答えた。
「それは仕方あるまい。だが、あまりゆっくりはしていられないぞ」
「もちろんです。閣下」
勝手に話を進められているが……でも、実際ゆっくりできないのは間違いない。
彼らはシムーンを手には入れたがその操縦者は全くのど素人だった。このまま戦ってもやっぱり勝ち目が薄いので、今相手が混乱している隙に和平交渉をしてしまえということらしいが……
《そのためには強力なリ・マージョンが必要?》
もし彼女達がそれを実現できなければ、それは結局グレイス達が前線であの宮国シムーンと戦うということではないだろうか?
グレイスは背筋がぞっとした。
《冗談じゃない!》
だがいくら彼女がそう思おうが、そうなったらもはや避けられない。
それを避けるためには、何としても和平交渉が成立してもらわねばならないわけだが……
結局その会議では最終的な結論は出ずに終わった。
会議の後、グレイス達はやって来た偉い人達にリ・マージョンの実演をして見せた。もちろん危険な物ではなく、全員で心を合わせてできるものとして、春の祈りが選ばれた。ぶっつけ本番だったが見事成功して嶺国や礁国の代表などからもお褒めの言葉を頂けたわけだが、グレイスはあまり嬉しくなかった。
《強力なリ・マージョンか……》
こういう楽しいリ・マージョンならいくらやっても構わないが、人を傷つける物を開発しなければならないと思うと気が重い。
だがそれが戦いを早く終わらせる道なのかもしれないし……
彼女達がやや沈鬱な気分で戻ってくると、そこに今の会議に出ていた巫女が待っていた。
「プリマヴェーラ!」
アントレーネが懐かしそうに彼女の側に駆け寄る。
「お久しぶり! 元気みたいね。アントレ。ヴォルケ」
「ええ」
「えっとそちらは?」
その様子を見てアリエスが尋ねると、アントレーネが答えた。
「彼女はプリマヴェーラ。南カテドラルで一番の才媛だったのよ。今日も代表の通訳で来たんでしょ?」
「ええ」
「へえ……あたしアリエスです」
「私、グレイスです。よろしく」
二人は彼女に手を差し出した。その両手を掴んでプリマヴェーラは言った。
「二人とも名前はよく知ってるわ。もう有名人だから」
「え? そうなの?」
「戻って来た雛鳥四名のことは、もうその筋じゃ知らない人はいないわよ」
「えへ? そうなの?」
にやけてきたグレイスを見てプリマヴェーラは意地悪そうな笑みを浮かべる。
「あなたよね。西の暴走四天王って呼ばれてたの」
「え~? どうしてそんなことを?」
「調査資料がやってくるのよ。偉い人の所には。で、私も見ちゃったの。いろいろ……」
「そんな~!」
そんな彼女を見て笑いながらアントレーネが尋ねた。
「今日は基地に泊まれるの?」
だがプリマヴェーラは少し暗い顔になると首を振った。
「夕方からまた別なところで会議があるから、もう少ししたら発たなきゃならないの」
「そうなんだ……」
アントレーネとヴォルケは残念そうだ。
「それであなた方にこれだけは言っておかないといけないと思って……本当は秘密なんだけど……」
プリマヴェーラは急にひどく真剣な表情になる。
「え?」
「さっき会議でちょっと出たでしょ? 代表達が宮国の密使と会談してたって話」
「ええ」
ヴォルケがうなずく。アリエスがグレイスに尋ねる。
「そうなの?」
「うん。そう言っていた。で?」
プリマヴェーラはうなずく。
「副代表の他に礁国の次官の人とドクター・バルヌフが出てて私が通訳をしたんだけど、実はね、その宮国の偉い人が保身を条件に、シヴュラ・マミーナのご遺体を引き渡すって言ってきたのよ」
「シヴュラ・マミーナって?」
その名前には聞き覚えがなかったが……
「シュネルギアであなた方が……儀式を行った巫女のお名前よ」
「えええええ?」
巫女達は驚愕した。グレイスは声を荒げた。
「ちょっと待ってよ! どうしてそんなことができるの? いくら偉い人だからって……」
だがプリマヴェーラは首を振る。
「分からないわ。でも向こうは、シヴュラ・マミーナの家柄が低いから問題ないって言うのよ」
言っている意味がよく分からない。どうしてこういう事に家柄とかが関わってくるのだ?
「どういうこと?」
グレイスの問いにプリマヴェーラは再び黙って首を振った。
そこにヴォルケが尋ねた。
「でも引き渡すってどうやって?」
「ご遺体はシヴュラの故郷に送って葬儀するらしいんだけど、その故郷はセドロ村という所なんだって」
その名前を聞いてアントレーネが言った。
「そこってあたしの故郷の近くじゃないかしら? 国境のすぐ向こうよ」
「そうなの。それで?」
「ええ。だから行く途中に国境付近で待ち合わせて、そこで遺体を……すり替えるそうなの」
遺体を? すり替える? だと?!
グレイス達は驚愕のあまりしばらく声も出なかった。
それってもはや犯罪行為ではないか! それも人に対するだけではない。神に対する大罪だ!
「それって……」
やっとの事でアリエスが声を挙げるが、プリマヴェーラは顔を伏せながら言った。
「だから……お仕事で知った秘密は……絶対話しちゃいけないんだけど、でも……だから……」
その時ヴォルケがはっと顔を上げて尋ねた。
「あの、葬儀を故郷でするって事は、そのシヴュラ・マミーナはまだお葬式をしてもらってないって事よね?」
「ええ。そうみたい」
巫女達は再び目を見開いて互いの顔を見合わせる。
アントレーネが手をわなわなと震わせながら言った。
「葬儀の前にご遺体をすり替えたりしたら、それって……」
結局シヴュラ・マミーナの葬儀は行われないという事ではないか!
「ちょっと待ってよ!」
思わずグレイスはプリマヴェーラに食ってかかった。
「あの人は凄い人なのよ! 宮国最高のシヴュラなのよ! 間違いないんだから! そんな人にどうしてそんなひどいことができるのよ! 命がけで戦って、みんなを助けようとして、それなのに宮国じゃお葬式もしてもらえないの?」
彼女の胸ぐらを掴む手につい力が入ってしまう。
「きゃあああ!」
プリマヴェーラの悲鳴に思わずグレイスは手を離す。
「あ……ごめんなさい……」
プリマヴェーラの目から涙がこぼれる。
「いいのよ。私もそれを聞いて……よっぽど撃ち殺してやろうかって思ったんだけど」
そこにヴォルケが尋ねる。
「あの、それっていつ?」
「それが、今日の夕方なの」
巫女達はまた驚愕した。
もう昼だ。
「どうやって遺体を運ぶか分かる?」
「宮国の大聖廟からシミレに棺を吊り下げて行くそうよ」
「それだとあまり高く飛べないわね……あ、ちょっと待って」
ヴォルケが走っていって地図を取ってくると、テーブルの上にばさっと広げる。
「セドロ村って?」
アントレーネがその一点を指す。
「ここよ」
「大聖廟からだと……」
ヴォルケが地図をじっと睨む。それからさっと一本の線を引いた。
「こう飛んで、山岳地帯に入ると、多分ここの谷筋を行くことになるわ」
それを見てグレイスが言った。
「この距離だったら……全速力で行ったら間に合うよね?」
「ええ」
その様子を見てプリマヴェーラが驚きの眼差しでグレイスを見る。
「えっと、あなた方……もしかして?」
グレイスはにっこりと笑った。
「うん。ありがとう。プリマヴェーラ」
「でも……」
するとアントレーネが言った。
「あたし達、あの方にお清めもして差し上げられなかったの」
プリマヴェーラは目を見開いて巫女達の顔を見て、それから手を口に当てるとつぶやいた。
「そうだったんだ……」
そんな彼女にヴォルケが言った。
「あなたの親切にはとても感謝するわ」
「ええ……」
そこでグレイスが言った。
「で、どうしよう? アントレの故郷に近いんならあたし達が行った方がいいよね?」
それを聞いてヴォルケが唇を噛む。
「そうね……全員では止した方がいいわね」
「それじゃヴォルケ。いない間よろしく」
「えっと……分かったわ。それじゃ新しいリ・マージョンのアイデアがわいたとか何とか言っておくから」
グレイスとアントレーネはそのまま彼女達と分かれると全力で格納庫に走った。
二人は驚く整備員達を尻目にシムーンを発進させ、一直線に北に向かった。
グレイスの胸の中は怒りでぐつぐつ煮えたぎっていた。
あの事件は四人の巫女達の心に刺さって疼き続ける大きな棘だった。
確かに教母様方は言った。あれはアニムスに導かれた定めだったのだと。彼女達はお勤めを果たしただけなのだと。
だがそれがお勤めだったとしたならば、まだ不完全なのだ。当然のことながら送った人を弔う儀式まで含めてお勤めは完了するのだ。コルトーフさんの時だって彼女達は略式ではあってもお清めと弔いの祈りを捧げたのだ。
だがあの騒ぎのせいで彼女達はシヴュラ・マミーナ―――銀の巫女に対しては何もしてやれていないのだ。
それができなかったことについては、当然宮国の人々が最高の敬意をもって彼女の葬儀を行うだろうからと、それで自分達の心を慰めていた。
なのにこれは一体どういう事なのだ?
「そんなの、だめだろ!」
「ええ。そうよね」
アントレーネの声も怒りで震えている。
確かに自分たちに怒る筋合いはないのかもしれない。だが怒らずにはいられなかった。彼女は文字通りに命を賭けて、傷ついた仲間と、敵である自分たち両方を守ろうとして散っていった。
自分たちがそうされるならともかく、どうしてそんな心優しい巫女が、死んでしまった後までそんな仕打ちを受けなければならないのだ? せめて安らかに眠らせてやろうと誰も思わなかったのか?
シムーンはやがて見慣れた北方の山岳地帯へとやってきた。
こうやって上から見るとここは本当に山ばかりで不毛の地に見える。だが今、この季節は嶺国が一番美しい季節でもある。
グレイスはそこに広がる大きな谷間にシムーンを下ろした。
「ここよね」
「ええ。ここを通るはずだわ」
周囲には高原の夏の花が咲き乱れている。ほとんどが雪と氷で閉ざされるこの地方で、一年の僅かな期間にだけに現れる別天地だ。
二人はただ何も考えずにその光景を見つめていた。
やがてアントレーネが言った。
「来たわ。十一時の方向」
確かにその方向から大きな箱を吊り下げたシミレがやってくるのが見えた。
「護衛機は?」
今になって思い当たったが、護衛機がいたらどうすればいいのだ?
「いないわ。一機だけ」
「一機で?」
逆に怒りがいや増してくる。護衛さえ付けないというのはどういう事なのだ? 本気で彼女などどうなってもいいということなのだろうか?
「じゃ、行くよ」
「ええ」
グレイスはアンシエンシムーンを浮上させた。それから低空から近づいて棺を吊り下げたシミレに一気に襲いかかる。
「今だ!」
それに答えてアントレーネが機銃を発射する。機銃弾は見事に目標を捉え、シミレはそのままお花畑の中に墜落していった。
「終わった?」
「ええ」
「それじゃお弔い、していこう」
「……そうね」
グレイスは小声で囁くように祈りの言葉を唱え始める。
『アニムスよ。我らは今日、此の地より、
汝の御許、古き兄弟達の集う彼の地へと、
我が親愛なる同胞を送りださん。
ああ、アニムスよ。我らの祈りを聞きたまえ。
かの魂が汝の絶えざる輝きの下、
永遠の安らぎを得られんことを』
「「かの魂が汝の絶えざる輝きの下、永遠の安らぎを得られんことを!」
祈りと共に、アンシエンシムーンはリ・マージョンを描き始める。
二人は何度も何度も祈り続けた。
その夜、ドクター・バルヌフは上機嫌だった。
長年の研究が花開きつつあるのだ。
「げほっ! げほっ!」
思わずドクターは咳き込んだ。手にしたハンカチを見ると……血が付いている。ちょっと油断するとすぐこのざまだ。
《だが……》
それでも彼は満足だった。ともかく結果を出せたのだ。今、彼の手元には実際に動くシムーンが六機もあって、それでリ・マージョンも成功した。調査の結果は驚くことばかりだ。そして調べれば調べるほど謎も増えていく。
それでも文献を見て空想していただけの時期に比べたら、どれほど充実していることだろうか。
「一歩一歩だ」
ドクターはつぶやいた。シムーンとあの巫女達さえいれば間違いなく前進していける。
本当に彼女達には驚かされた。
正直最初はあんな子供に何ができると思っていたのだ。
だがどうだ? 大人でも泣きたくなるような訓練を堪え忍び、まさに命がけの危険をくぐり抜けてアンシエンシムーンをもたらし、更にはその操作方法についても大発見の連続だ。文字通りに勝利の女神そのものではないか!
特に彼女達の発見した“嶺国式リ・マージョン”は、宮国の文献では示唆さえされていなかったことを考えると、もう世紀の大発見かもしれないのだ。
実際宮国でもシムーンの用法が知られているだけで、その動作原理などは全く分かっていないことはほぼ間違いない。国内から出土するヘリカル・モートリスを元にあのような機体を作り上げる技術はあるにしても、それを根本的に改良するようなことはできないのだ。
ともかくこうやって一つ一つ階段を上がっていくことができれば、礁国だっていつかはシムーンのような飛行機械を作り出せるに違いない。
美しい海と澄み渡る空。白銀の砂浜。その上空を優雅に飛ぶ、礁国のシムーン……
「げほっ! げほっ!」
自身がそれを見ることは叶わないだろうが……でも彼らの子供達の更に子供達なら多分……
その時ドアをノックする音がした。
「どうぞ」
入ってきたのはグレイスとアントレーネだった。
ドクターは正直驚いた。
「どうした? こんな時間に?」
「お話があります」
グレイスが答える。二人の顔は妙に真剣だ。
「いいが、手短にな。もう遅いし……それとも何か分かったのか? 午後は確か、新しいアイデアを試していたそうだな?」
それに対しては二人は首を振る。
「いえ。それはまだ」
「では何なのだ?」
その問いに対するグレイスの答えは全く予想外の物だった。
「ドクターは、宮国の使節に、シヴュラ・マミーナのご遺体が欲しいとおっしゃいましたか?」
ドクターは目を見開いた。
「どうしてそれを?」
「ドクターがそれを依頼されたのですか?」
「それを聞いて……どうする?」
「亡くなった方の体をそんな風にしてはいけません。神様の御許に送り返してあげなければいけません」
二人の眼差しには冷たい怒りの炎が浮かんでいる。それを見てドクターはちょっとぞっとした。
「いや、それはそうかもしれないのだが……私は知らねばならなかった。そうすることで前にも言ったように、君たちのような少女を戦場に送らずに済むようにできるかもしれない。だから彼らにだめを承知で頼んでみたのだよ。もちろん彼らが同意するなどとは思ってもいなかった。だが彼らは何故か了承してくれたのだ」
そう答えながらドクターは、どうして自分はこんな子供達に一生懸命弁解しているのだと自問した。
巫女達は黙ってドクターの返答を聞き終えると言った。
「申し訳ありませんが、シヴュラのご遺体は手に入りません」
「どういうことだ?」
「私たちが葬って参りました」
「なんだと?」
ドクターは少女達を睨んだが、彼女達は真っ向からドクターの瞳を見つめ返す。
「輸送するシミレを、私たちは撃墜しました。だから国境に遺体は届きません」
さすがにそれを聞いてドクターも血が上った。
「何と言うことを! どうしてそんな勝手なことを……」
だが彼の言葉はそこで途切れた。なぜなら巫女達はローブの下から拳銃を取り出してぴたりとドクターの胸に狙いを定めたからだ。
「どうする……つもりだ?」
ドクターの背筋がぞくりとする。別に死ぬのが怖いわけではない。だが今はまだ……
逃げることは可能だろうか? いや、彼女達はそのための訓練を受けているわけで……
そんな想いが去来する中、彼女達の次の言葉は更に彼を驚かせた。
「死体がご入用なら、私たちにお申し付け下さい」
そう言って彼女達は自分の心臓に拳銃の銃口を当てたのだ。
「私たちはシヴュラ・マミーナほどには上手に飛べませんが、二つあれば十分ですか?」
そう言った彼女達の目は……間違いなく本気だ。本気で死ぬ気だ!
「やめろ!」
ドクターは叫んだ。声が裏返ってかすれている。だがとりあえず彼女達には届いたようだ。
「でも必要なのでしょう?」
「君たちには、生きていてもらわねば困る!」
その言葉を聞いて二人の巫女は困ったように首をかしげる。
「それならばどうしましょうか?」
「どうもしなくていい。ともかく分かった。分かったから戻ってくれ。今すぐ遺体がなければ困るわけではない。あるなら調べてみたかっただけだ。ともかく君たちにはこれから生きてやってもらわねばならないことが山ほどあるんだ。軽々しくそういうことはしないでくれたまえ!」
巫女達はちょっと目を見開いたが無表情にその言葉を聞いた。ドクターが喋り終えても、まだじっと黙って彼を見つめている。
「ともかく今日は引き取ってくれ!」
それを聞いて巫女達はやっと、黙って礼をすると部屋から出て行った。
ドクターはしばらくの間呆然として彼女達が消えていった扉を見つめていたが、やがて力が抜けたようにくったりと椅子に座り込んだ。またしばらくその状態で宙を見上げていたが、次いで立ち上がるとリフェルドルフの部屋に向かった。
そこではちょうど彼とベネトラルフ副司令が何かを話していたところだった。
「どうされたのです?」
総司令はドクターの様子を見て驚いた。ドクターはそこでしばらく咳き込むと、今起こったことを二人に説明し始めた。
「なんと? あの子達が……」
ドクターの話を聞いてリフェルドルフも目を見張った。
「あの子達は何なんだ? 私が迂闊なことを言ったら、ありゃ間違いなく引き金を引いていたぞ! 大体、敵国の巫女にどうしてそこまで肩入れする?」
興奮して話し続けるドクターを遮ったのはベネトラルフ副司令だ。
「いえ、それは当然のことでしょう」
「当然? どこがだ?」
ドクターはベネトラルフを睨むが、彼は黙って首を振り、そして言った。
「かつては私も巫女でした。ですから彼女達がそうした理由はよく分かります。あれがばれたらどうなるかとは思っていましたが……」
そこでドクターとリフェルドルフは思い出した。そうなのだ。ここにいる男はかつては女だったということを―――いや、正確には男にも女にもなり得る未分化の状態だったということだ。礁国ではそれは失われてしまったが、嶺国では今でもそれが当然なのだと。
「いや、確かに死者に対して非常に不敬なことではあるが、だが、そこまですることなのか?」
ベネトラルフはそう言うリフェルドルフの顔を見て答える。
「私でも彼女達の立場だったら、何らかの行動をしたでしょう」
「だが……」
不満げな二人の顔を見て、ベネトラルフは言った。
「違うのです。嶺国の巫女は、少女である前に、人である前に、巫女なのです……巫女でなければならないのです」
「なに?」
総司令とドクターはベネトラルフの顔を見返す。彼はその視線を受け止めると尋ねた。
「あなた方は人を殺したことはありますか?」
「な……」
「私たちは……いや、彼女達はあります。たとえどんなに鈍い者であろうと、自分の撃った弾丸がその人を貫き、その眼から光が消えていくのを目の当たりにすれば、それが殺人だと気づきます。だから私たちは巫女でなければならないのです。そうして自分の魂を神に差し出すことで、初めて普通に……生きていくことができるのです」
二人はしばらく絶句した。それからドクターが低い声で尋ねる。
「それは……魂を人質に取っているような物ではないですか?」
それを聞いていつもは温厚な様子を崩さないベネトラルフの目に冷たい怒りが宿った。彼は二人を睨み付ける。
「我々は、あなた方が自然の摂理をねじ曲げていることについて……あなた方がどちらの性を選ぶかという、神より人に与えられた最大の権利を奪っていることについて、とやかく言いません」
リフェルドルフとドクターもぎろっとベネトラルフを睨む。
まさに一触即発の空気がみなぎった瞬間、ノックの音がした。
「誰だ?」
リフェルドルフの声に応えたのは少女の声だった。
「ヴォルケとアリエスです」
大人達は顔を見合わせる。それから総司令が答える。
「入れ」
入ってきた二人はそこに総司令以外に二人も人がいることに気づいて少し驚いたようだが、すぐに黙って礼をした。
思わずドクターは二人に尋ねていた。
「一体何だ? 君たちまで」
それを聞いてヴォルケが不思議そうな顔をする。
「私たちまで? もしかしてグレイス達が何か?」
「いや、何でもない」
このヴォルケという娘は鋭いのだ。ドクターは慌てて首を振る。それからリフェルドルフが彼女達に尋ねた。
「それで用は?」
ヴォルケはうなずくと答えた。
「はい。私たち、多分できると思うのでお伝えに来ました」
「できる? 何が?」
「リ・マージョンです。今ある物よりも遙かに……破壊力の大きな」
司令達は顔を見合わせる。それからまたリフェルドルフが尋ねる。
「どうしてできると思った?」
それを聞いて二人の巫女はちらっとドクターの方を見て目を伏せる。それからアリエスが答えた。
「あの人達が……許せないからです」
三人の大人達は互いに顔を見合わせる。あの人達? もちろん彼女達も知っているのだ。そこでベネトラルフが言う。
「だが……君たちはアニムスの巫女だ。始まりの巫女は言ったはずだ……」
しかし、巫女達は彼を真っ正面から見据えてうなずいた。
「はい」
ベネトラルフは次の言葉が口に出せなかった。それを見てリフェルドルフが尋ねる。
「本当によいのか?」
二人は黙ってうなずいた。
「それでは頼む」
「はい。承知しました」
二人は礼をすると、総司令の部屋を去って行った。
しばらく三人は無言だった。それから総司令がつぶやく。
「これもそうなのか?」
ベネトラルフが答える。
「だから彼女達には……人の死について語る権利があります。そんな彼女達が出した結論がそれなのだとすれば、そうです。彼女達は嘘はつきません」
「だとしたら本当にそんなリ・マージョンができるということですかな?」
ドクターの言葉にベネトラルフはうなずく。
「はい。でも私たちは、これだけははっきりと認識しておかなければなりません。私たちが何を利用しようとしているのかということを」
総司令もドクターもそれを聞いて息を呑んだ。やがてリフェルドルフが答える。
「ああ。そうだな。そういうことだ」
三人は黙って互いの顔を見る。
それからそのリ・マージョンをどう使うかに関しての作戦を練り始めた。
グレイスとアントレーネは自分たちの部屋で放心状態だった。
こちらに戻ってからは晴れて彼女達は四人部屋になっている。そこにヴォルケ達が戻って来た。
ベッドに寝転がって天井を見つめている二人にヴォルケが尋ねた。
「あなた達、ドクターに何言ってきたの?」
グレイスが寝転がったまま答える。
「え? 死体がいるならあげるって。二つでいいかって言ったら、いらないって」
「そうだったの」
ヴォルケとアリエスはそれを聞いてクスッと笑う。
「ヴォルケ達は?」
「破壊力のあるリ・マージョン、できるだろうって言ってきたの。総司令に」
「あ、そうなんだ……じゃ、一緒にやる?」
「いえ、まずは私たちだけで。そうしたら……二回できるかもしれないし」
「あ、そうだね」
彼女達の怒りはまだ収まらない。
だがこの時はまだその怒りがどれほど致命的な力を持ちうるのか彼女達には―――いや、誰にもよくは分かっていなかったのだ。