赤山禅院は仁和4年、天台座主・安慧大師の遺命によって延暦寺の別院として創建されたのがはじまり。平安京の表鬼門の守護神である赤山大明神を祀る。
本殿屋根に祀られた王城守護の猿は、京都御所の鬼門猿ヶ辻にまつられた猿と向かい合っていると言われている。どの猿も金網の中に入れられているが、これは夜になると道行く人に悪さをしていたので、懲らしめの為だといわれている。
境内には石像の十六羅漢や三十三観音がひっそりと祀られていた。
ひとり一句
秋はもうサラダになっているらしい 赤松ますみ
エレキギターが空に昇っていく紅葉 南野 勝彦
念珠くぐれば水のねじれる音 岩田多佳子
うすむらさきで吸い上げている昨日 森田 律子
もう一度言います水に浮びます 徳永 政二
虹いくつ食べてきたのよ冬もみじ 西田 雅子
池は濁って情けが届かない 前田芙巳代
線香のけむり冬はゆっくり始まった 峯 裕見子
矢印の最後に鬼が待っている 笠嶋恵美子
泣き声を立ててはならぬ蝶番 内田真理子
もう帰る有精卵をころがして 北村 幸子
冬桜めったに来ない寺に雲 墨 作二郎
朽ちかけてじっと昔をものがたる 今井 和子
裏表あってはならぬモミジの葉 北田ただよし
街路樹がひと言ふた言はにかんで 北原 照子
あんぐりと軒にいこうている草履 八木 侑子
青空に腹式呼吸花八つ手 岩根 彰子
横道へ外れるもみじがあたたかい 松田 俊彦
せせらぎに昨日の罪を消してゆく 元永 宣子
もみじ葉の造形 水紋の波形 本多 洋子
キャラメルの箱を転がす赤山禅院 小林満寿夫
云い忘れたことをナナカマドに告げる 平井 玲子



第百五十一回
点鐘散歩会
比叡山延暦寺別院
赤山禅院
蛇行する保津川の渓谷を縫うように走るこのトロッコ列車は四季折々の景色を楽しむことができるが、この時期は、桜さくらサクラ・・・。
満員の盛況で、早くから予約を取っての乗車であった。
亀岡で降りて、菜の花畑をJR馬堀の駅へ徒歩二十分ほどの散策。電車で再び嵐山に戻り、吟行の成果はラボウル京都にて、清記互選の句会。
ひとり一句
いっしょうけんめい遊ばなくっちやこぼれるよ 吉岡とみえ
裁判になったら負ける花筏 小林満寿夫
呼びに来るひっぱりに来る水の音 峯 裕見子
これからを思う菜の花の背すじ 本多 洋子
深々と亡父のさくらを折り畳む たむらあきこ
半券を一枚もっているサクラ 岩田多佳子
面取りをしてから触れる嵐山 内田真理子
公園の桜は支え合っている 墨 作二郎
うつむいて競う相手の無い桜 西村 夕子
トンネルを抜けると鳩は有頂天 平井 玲子
椅子は直角春のひんやりに座る 畑山 美幸
男は無口しゃべる桜をしゃべらせる 前田芙巳代
かと言って桜を見ない訳でない 森田 律子
これ以上桜に聞くと叱られる 徳永 政二
さくらさくらさくらのなかに消えちゃった 八木 侑子
ガッタンと出発 野々宮裏通り 北原 照子
ハイハイと人の掃除をする作務衣 久恒 邦子
きのうのことは忘れて歩くさくら咲く 今井 和子
水の音しきりに犬ふぐりを揺らす 辻 嬉久子
桜にはいいたいことがたんとある 笠嶋恵美子
保津川を上から絶景にひたる 田頭 良子
PRです
「点鐘散歩会」2008年度版が出来ました。
最近4年間の散歩会の集大成です。
力を入れて編集しました。
ご入用の方は 本多洋子までご連絡下さい。HPの
メールででも結構です。
住所と氏名をお書き下さい。
本代は500円です。よろしくお願いします。
トロッコ嵯峨駅前の桜 前庭・機関車の展示


2008年4月 更新
嵯峨野トロッコ列車
「嵯峨野トロッコ列車」はトロッコ嵯峨野駅からトロッコ亀岡駅までの7・3キロを約25分で結ぶ観光列車である。
花見小路 一力の紅い壁 花見小路のマンホール
神前に奉納された鮪(中央) 福笹を売る福娘 花見小路のポスト





第142回 点鐘散歩会
平成20年1月9日
新春穏やかな日差しの京都は南座の前に集合。大和大路通りを南へ。細い通りには出店や屋台が所狭しと立ち並ぶ。酒糟やこぼれうめ・すぐきや漬物店・イカ焼きやりんご飴を潜り抜けて恵比須神社に辿り着く。
恵比須神社は土御門天皇の建仁2年(1202年)に臨済宗総本山「建仁寺」の開祖である栄西禅師によって建立された。禅師は吉備津宮の神官の子であったためか仏門に帰依されてからも日本古来の神を厚く信仰され、建仁寺の建立にあたり、まず守護神として「恵比須神社」を建てられたと言う。
ここに祀られるのは「えびす大神」で大国主神の子の「八代言代主神」。この神は漁獲を好まれ、それを穀物と物々交換されたことから、商売繁盛の神さまとされている。今も神前には大きな鮪が一尾まるごと奉納されていた。
建仁寺から花見小路を経て句会場へ。
ひとり一句
むずかしいところに立っているするめ 峯 裕見子
神さんは若い女の声でした 川田由紀子
もう一つほしいと思う朝がくる 徳永 政二
宵戎今朝は闘牛士がいない 小林満寿夫
招福という部厚いものに陽が当たる 辻 嬉久子
一力の赤い壁から意地になる 前田芙巳代
にんげんの頭ばかりを追っている たむらあきこ
山椒ちりめん京のまつりをかき寄せる 本多 洋子
お目出とうを皆に言えた梅こぼし 畑山 美幸
大根はまだ煮えてません宵戎 墨 作二郎
神さまの住所録からはずされる 内田真理子
笹の福よりも私の勇気 森田 律子
えびすさん笹をひらひら今年をひらひら 今井 和子
日溜りに煙が流れ着く頃だ 笠嶋恵美子
建仁寺の鳩そこはかと京ことば 岩根 彰子
柳の芽尼僧の椀にあおを盛る 八木 侑子
摺り足で近づいてくる同い年 久恒 邦子
黒豆として立つ野晒しの屋台 西村 夕子
建仁寺へ十日戎をこぼれ出る 平井 玲子
恵比須さん酒かすほろり緋寒桜 北原 照子
次回 点鐘散歩会 予告
恒例の一泊旅行 淡路島へ
日 時 平成20年2月6日ー7日
行く先 淡路島人形浄瑠璃会館
2日目は淡路夢舞台ほか
宿 泊 休暇村 南淡路
集 合 2月6日 午前10時30分 JR 高速バスステーション
(大阪駅桜橋出口すぐ)
費 用 宿泊費・雑費ともで一万三千円程度
(交通費は各自持ち)
申し込みは1月末までに
南野 電話 072 278 5039
本多 電話 072 332 9308
または 洋子の部屋 のメールででも結構です。
大阪駅は桜橋バスステーションから高速バス淡路島行きに乗れば約二時間余りで福良うずしおドーム前に到着する。その足で淡路人形浄瑠璃館へ向かった。
淡路人形浄瑠璃は江戸時代には阿波藩主蜂須賀氏の保護のもとに大いに繁栄し、全国に広く巡業したと言われている。人形座も40以上もあったというが、現在は、淡路人形座と市村六之丞の二座だけになっている。
浄瑠璃館では傾城阿波の鳴門の八段目「順礼歌の段」を上演していた。女義太夫のか細い声がドラマをより悲しく歌い上げていた。
ひとり一句
しあわせな男で島になりました 峯 裕見子
ちょっとずらすと春は足先みせている 南野 勝彦
くずかごの中から海を出してくる 徳永 政二
高速バス降りたらみんな玉ねぎ 畑山 美幸
人形が笑う男の手の中で 笠嶋恵美子
カカさんもトトさんも居て孤独です 平井 玲子
巡礼おつる玉葱畑を急がねば 墨 作二郎
抱いた人形に見つめられている 森田 律子
人形の重さ 哀しみの重さ 本多 洋子
あなたからとおいところで明るくなる たむらあきこ
すれ違うことで大きな泡になる 辻 嬉久子
美しく泣いて見せます人形は 前田芙巳代
人形のカシラうわさを三度聞く 北川アキラ
この街の芯のあたりが騒がしい 今井 和子
夕暮れて入江はしばし光の器 八木 侑子
二日目 大塚国際美術館
この美術館は、大塚製薬創立七十五周年記念事業として、徳島県鳴門市に設立した日本最大のスペースを誇る「陶板名画美術館」である。古代壁画からルネッサンス・そして現代絵画に至るまで、西洋名画約1000余点を原寸大にして展示されている。しかも本来の原画がもつ美術的価値を損なうことなく、陶板画として複製したものである。地上二階地下三階の広いスペースはとても三時間ほどの短い時間帯では見切れるものではなかった。
ひとり一句
古事記伝承の地に腹這いの聖教徒 墨 作二郎
裸婦像に終日みつめかえされる 前田芙巳代
キリストの声はいつでも頭上から 南野 勝彦
目を閉じて君はほんとにむずかしい 徳永 政二
玉ねぎを山盛りにしてダヴィンチコード 峯 裕見子
入り口のここから三角形になる 辻 嬉久子
受胎告知のいつかへ女としてかえる たむらあきこ
母さんも聖母も阿波を温くする 笠嶋恵美子
天使のくせしてケータイも持たず 森田 律子
やわらかに冬陽が沈む空間の欠伸 平井 玲子
ヴィーナスのモデルになったのは昔 畑山 美幸
人間も野獣も一つになる雪中の狩人 八木 侑子
大きすぎて崩れてきそうなところ 今井 和子
障壁画の中のひとりになりすます 本多 洋子
人形遣いの説明を聞く 裕見子さんが操る娘 律子さんも兆戦
一行十五名 休暇村南淡路前 人形浄瑠璃館・文楽のカシラ





2008年2月 更新
第百四十三回 点鐘散歩会
淡路島 一泊旅行
淡路人形浄瑠璃館 と 大塚美術館

ノールウェーの画家エドヴァルド・ムンク(1863−1944)はこれまでにも各地で沢山の展覧会を催しているが、今回は人間の魂の叫びを描いた画家ムンクを、装飾プロジェクトという観点から軌道を辿って展示したものである。
愛と死、不安と絶望といった「生命のフリーズ」の諸作品にも壁画装飾性の展開があり、子供部屋のための制作や、劇場や講堂の壁画としての作品構想も解かり易く展示されていた。
ひとり一句
いのちってダンスするものなんですね たむらあきこ
出口のないいのち出口のそばにあるいのち 前田芙巳代
嫉妬する男の耳は立っている 南野 勝彦
手にとってみるとなんだか花である 徳永 政二
届きそうな指 届かずうれしい 八上 桐子
バラの香ですか 屍臭ですか 森田 律子
やさしい人を裏返したときのギョロ目 今井 和子
シーンと絵フーと吐いたら次を見る 西村 夕子
風景の中へ帰ってゆく男 峯 裕見子
ほっとするなあ女の子がいる 吉岡とみえ
お尻ばかり向けて収穫しています 八木 侑子
ゴルゴタに皆集まって皆バンザイ 墨 作二郎
灰になった男を捨てて灰になる 本多 洋子
橋上のシルクハットが重過ぎる 笠嶋恵美子
山を抱き空を抱えているベンチ 北原 照子
マスクを外したら灰になっていた 松田 俊彦
マドンナ ゴルゴダ


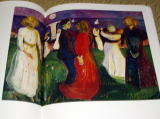
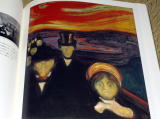
2008年3月 更新
兵庫県立美術館
エドヴァルド・ムンク展
1970年の大阪万国博覧会会場の跡地につくられた広大な記念公園エキスポランド。最近ではエキスポランドの遊具のジェットコースターの人身事故の記憶が新しい。お蔭で遊園地の方は閉鎖のまま。今回は自然文化園と日本庭園を散策。
先ずはパークトレイン「花ぽっぽ」に乗って自然文化園を半周し、あとは自由に若葉の森を散策したり、薔薇園を楽しんだり、日本庭園をそぞろ歩いて思い思いに作句に没頭した。
若葉を背景に現代彫刻の点在する芸術の森もなかなかのものであったし、木道や吊り橋を巧に配したソラードの空中散策も、自然に触れることのできる絶好のチャンスになった。
二時間の散策ではとうていすべてを見回ることは出来なかったが、それぞれの体力に合った楽しみ方は出来たようにおもう。
ひとり一句
公園にぎゅっと抱かれたことがある 南野 勝彦
薔薇であることを小さく声に出す 峯 裕見子
雲からの答えはいつもやわらかい 徳永 政二
遠足の帽子とことん紛れあう 辻 嬉久子
塔の裏の顔は夕日になっている たむらあきこ
きっと来るけやきの丘の風の約束 平井 玲子
ミャンマーが見えるか太陽の目玉 本多 洋子
からだ中植物図鑑になっている 八木 侑子
パスポート持って五月を通過中 赤松ますみ
私のバクハツ小さかったみたい 森田 律子
観覧車の骨がしばらく動かない 墨 作二郎
太陽の塔の手は長いのか短いのか 畑山 美幸
忘れるのにアイリスの名を読んでいる 西村 夕子
すいと来て思わせぶりな黒揚羽 笠嶋恵美子
二人のような一人のような塔の顔 柴本ばっは
別れる君にブルームーンを贈ります 西澤 知子





2008年5月 更新
第百四十五回
点鐘散歩会
大阪 万博記念公園
例年より一週間も早い梅雨の入り。
草津駅からバスで二十分ほど、みずの森水生植物園前で下車。すぐ前が園入り口正面のゲート。しのつく雨の中早速ロータス館(水生植物のテーマ館)へ。
今を盛りと咲き乱れる睡蓮にこころを奪われる。睡蓮は朝8時頃ひらいて、午後3時頃には花を閉じるという。
しばらく館内に寛いでから思い思いに庭に出る。傘やカメラを片手に、花影の池や丘の上の花園をまわる。
木の橋をわたり、あづまやなどを散策する。蓮池のハスはまだ開花をみなかったが7月ともなれば見事な風景であろうと思われた。
トレードマークの大きな白い風力発電の風車は、風もなくて止ったままであった。
ひとり一句
ほしいのは水に映った方の花 吉岡とみえ
夏草や縦一列の変声期 岩根 彰子
雨の日は雨のテンポで振り向くの 岩田多佳子
花の名をみんな知ってる絵の具箱 笠嶋恵美子
水になりスイレンになるボールペン 西村 夕子
右肩の濡れているのはさみしい証拠 内田真理子
透明な時間にへばりつくタニシ 北村 幸子
花びらはもう一声で零れます たむらあきこ
六月の羽は三枚ありました 徳永 政二
のり代に座ったらしい動けない 久恒 邦子
声をあげたのはオオオニバスだった 本多 洋子
戻ってきた青は違った色の青 南野 勝彦
ああしんど朝から咲いているのです 森田 律子
雨はやさしさモネのいろいろ開花する 墨 作二郎
睡蓮の首の長さを競うべし 前田芙巳代
バス降りる水草になる二十人 畑山 美幸
ぽっと灯りになって花の芯に立っている 今井 和子
雨けむるアンスリウムはしゃべりすぎ 北原 照子
色あふれ花あふれ水の宴 八木 侑子



2008年 6月度 更新
第百四十六回
点鐘散歩会
草津市立水生植物園 みずの森

立秋を過ぎて少しは猛暑から解放されたものの、朝から時雨模様の生憎のお天気。曇天の中、伏見稲荷の朱の鳥居を左に見て古い伏見の街並みをそぞろ歩いて、石峰寺に向かう。
百丈山石峰寺は、宝永年間に千呆禅師によって建立された禅道場である。以後、寛政年間に画家伊藤若冲が当寺に草庵を結び、十年余りをかけて裏山に五百羅漢を作った。
この五百羅漢は、若冲が磊落な筆法で下絵を描いたものを、石工に彫らせて裏山に安置したものである。
すぐ近くに若冲の墓と筆塚が祀られていた。
ひとり一句
地下道を抜けると石もあきらめる 徳永 政二
ねむりこけ竹になったり石になったり 岩田多佳子
骨せんべいにされて白状しそこなう 赤松ますみ
それぞれの傘で無口を守りぬく 北村 幸子
さるすべりの空は大きな水のかたまり 吉岡とみえ
蚊にまいって 人間失格 森田 律子
青い柿ゆれて訃報がひとつある 峯 裕見子
たくさんをこぼさぬように立っている 南野 勝彦
少し雨少し寄り添うほとけたち 平井 玲子
躓いたところで笑っている羅漢 笠嶋恵美子
やぶ医者もやぶ蚊も腹を刺したがる たむらあきこ
雨の伏見で人待ち顔のきつね面 墨 作二郎
むずかしい女でした紫式部指す 小林満寿夫
石仏はくずれにくずれ政局不安 西村 夕子
いらっしゃい河原は秋のライブです 八木 侑子
いけずやな狐のせんべいくれはった 北原 照子
若冲は幸せだったと雨の墓 今井 和子
赤門のあたりで蝶をはぐらかす 本多 洋子
石塔には石を積んで 賽の河原の仏 泣くらかん笑う羅漢
藪の中に 釈迦誕生から涅槃までの 若冲・五百羅漢の世界が展かれる





2008年9月度 更新
第百四十九回
点鐘散歩会
石峰寺 若冲の五百羅漢
銀閣寺は俗称。正しくは東山慈照寺、義政公を中心に形成されたいわゆる東山文化の発祥の地である。
この日は生憎国宝の観音殿・銀閣は修理中で足場が組まれ、その全容を見ることはできなかったが、国宝東求堂や銀沙灘、向月台を静かに眺め、雨後の鮮やかな苔の庭を静かに散策した。僅かに紅葉も垣間見られた。
ひとり一句
竹釘でとめる昨日がずれそうで 北村 幸子
真剣にはみ出すための線をひく 峯 裕見子
階段に座っているのは秋の首 内田真理子
あっちで念書こっちで念書 鰯雲 森田 律子
目障りな色があるので迂回する 笠嶋恵美子
銀閣寺逃げないようにして囲む 徳永 政二
水引き草膝を崩して口ごもる 岩根 彰子
すこうしやましいことがある砂目 前田芙巳代
明らかに月の夜がある銀のスジ 辻 嬉久子
砂山のわたしは月を待ちすぎた 岩田多佳子
柿葺一枚一枚 今日明日に 北原 照子
門前で誰を待つのかざくろの実 元永 宣子
辻々で束になってる小学生 八木 侑子
桜みな老いて疎水を見ているか 墨 作二郎
向月台 涙が溢れそうになる 本多 洋子
銀閣を口説く言葉が出てこない 南野 勝彦
解体をされるわたしの銀閣寺 たむらあきこ





2008年10月 更新
第百五十回
点鐘散歩会
銀閣寺から哲学の道
アール・ブリュットーと言うのは「加工されていない生のままの芸術」を意味するらしく、フランスの美術家ジャン・デュビュッフが1945年に提唱した。
精神障害者や幻視者など、正規の美術教育を受けていない人々が、内発的な衝動の趣くままに制作した作品を高く評価したものである。既成の美術概念に毒されていない表現にこそ真の芸術性が宿っていると主張した。
ひとり一句
月曜日ばかりを入れる魔法瓶 たむらあきこ
水分の多いサングラスで転ぶ 岩田多佳子
話すのはいつも汚れてからの口 徳永 政二
どんどん奥に入っていく出口 吉岡とみえ
神様をかき込むための線描画 北村 幸子
銀河鉄道耳から鼻へ通過中 森田 律子
くちびるがもうすぐ薔薇を吐くところ 赤松ますみ
体の中のボタンが一つはずれそう 畑山 美幸
黙っていると口が裂けてきた 八木 侑子
顔のない私が鏡の中にいる 笠嶋恵美子
離れると石 近づくと父 本多 洋子
朽ちてゆくやさしい音を立てながら 峯 裕見子
七色の風で帽子を編んでます 岩根 彰子
やさしいタッチで恐怖の一部始終 平井 玲子
ラビリンスはどこだ窓だらけの窓 山口ろっぱ
やがて雲になる少年の発情期 墨 作二郎
胎内でもっともっとと手を広げ 今井 和子
探さない探さない天井が落ちるから 小林満寿夫
エンピツがピエロになった泣き笑い 北原 照子


2008年11月 更新
第百四十八回
点鐘散歩会
アール・ブリュットー パリコレクション
滋賀県立近代美術館
園内にはあちこちにちいさな館が散らばっていて「世界のさかな館」「森の水槽館」「アマゾン館」「ラッコ館」などめずらしい魚の生態をつぶさ観察できる。
「イルカライブ館」では賑やかにイルカショウが繰り広げられていた。
ひとり一句
歩きたいのか泳ぎたいのかはっきりしない 徳永 政二
骨格が透けてきて八月 吉岡とみえ
「暑い」とあぶく「お腹すいた」とあぶく 畑山 美幸
チョウ鮫のおそ松君が泣いている 本多 洋子
諦めが早くて砂に潜っている 森田 律子
八月の迷彩服で来るヒラメ 峯 裕見子
イルカ君ポニョという子を知ってるか 南野 勝彦
ミズクラゲくるりくるりと夏の旅 墨 作二郎
わたくしの魚の部分を明るくする たむらあきこ
イルカ不意に叛いてオリンピックは近い 前田芙巳代
エラ開きっぱなしでカレー待っている 北村 幸子
ペンギンは僕に同情してくれる 西澤 知子
囚われの魚とさがす青い月 西村 夕子
早よ帰ろシーラカンスが待っている 笠嶋恵美子
タカアシガニ少しとぼけたフラダンス 北原 照子
棲み分けも大変ですね水の檻 八木 侑子
イルカショウのプール
波の大水槽の魚たち




20年8月度 更新
第百四十八回 点鐘散歩会
須磨 海浜水族園

今を咲き誇る桔梗 慮山寺の鐘楼

作二郎氏の挨拶 紫式部顕影碑



2008年7月 更新
第百四十七回
点鐘散歩会
京都御苑から梨木神社を経て
慮山寺
慮山寺は、天台系 圓浄宗の総本山。平安時代に延暦寺中興の祖元三大師良源が開いたといわれている。ここは一説には紫式部の邸宅跡とされ、白砂と桔梗の庭はいかにも清楚なたたずまい。しかしこれは当時のままではなく、「源氏庭」と名付けて、平安朝を再現した現代の作庭である。本堂では源氏物語千年紀にちなんで、写真展が催されていた。
ひとり一句
鯉の口あつめて何の刑だろう 北村 幸子
なにかに縋ろうとして紫はきらい 前田芙巳代
華やかな船を浮かべて静かに眠る 徳永 政二
見る前と見てからがある夏時間 峯 裕見子
紫も集うと私語が多くなる 南野 勝彦
風船のように膨らむ平安期 たむらあきこ
夏萩のほろっと淡い夢を見る 笠嶋恵美子
逃げて逃げて逃げて桔梗の青になる 内田真理子
通り抜けして萩の辺りの水呑み場 墨 作二郎
平安絵巻はとても蒸暑い 畑山 美幸
一筆描きにすると桔梗のような人 本多 洋子
育成中の私踏んではいけません 森田 律子
雀チュンチュン紫式部と遊んだか 松本あや子
ひとときを源氏の庭の雲に乗る 岩根 彰子
御所を横切る 千年を横切る 北原 照子
石橋をそろそろ渡るアフラック 辻 嬉久子
何もかも千年前に置いてきた 中野 六助
年金で花散里に住んでいる 西村 夕子
筆塚のあたりで虫が呼んでいる 平井 玲子
キラキラとみどりの雫 公家の密談 八木 侑子