第一二詞章 天岩屋 後半
[「倭の神話」の星座]
夜明け前の星座
先ほど、「夜明け前の祭事」は「天岩屋神話の星座」の日以外にも行われていた、そう考えていると書いた。それも晴れている日はほぼ毎日行っていたのではないかと思う。冬の寒い日の場合は疑問符が付くが、春・夏・秋の晴天の日に行っていたことは確実である。その理由も明快に説明できる。「天岩屋神話の星座」以外にも別の詞章の内容に対応する「夜明け前の星座」があるからである(具体的には、試論の補助解説で紹介している)。おそらくそれぞれの時季の星座に対応した内容の詞章がその祭事で語られていたのだろう。
そして、それらの星座を統括する位置にある最も重要な星座が、この「天岩屋神話の星座」である。何しろこの星座はそれらの「夜明け前の祭事」の起源になっている星座である。だから、この星座の日に一年のうちでいちばん盛大な祭事が行われていたのではないだろうか。
天岩屋神話が「倭の神話」の原点に位置していると考える理由の一つが、これらの「夜明け前の星座」の存在である。
「倭の神話」の星座の特質
「倭の神話」の星座は西洋の星座とはかなり趣が違う。西洋の星座はそれがどの位置にあっても同じ星座である。例えばカシオペヤ座はMの字に見えるときでもWの字に見えるときでもカシオペヤ座である。ところが、「倭の神話」の星座はこれとはまったく異なる。例えばおおぐま座はある位置では天鈿女になり、別の位置では伊奘冉になり、または伊奘諾になるというように、その時地上からどのように見えるかで星座に意味が与えられている。
また、「天岩屋神話の星座」も前詞章までの星座とは異質である。天岩屋神話は間違いなく星座が先にあって、その星座に合わせて神話が創られている。だから、そこでは星座が決定的に重要な役割を負っている。これに対して、他の詞章の星座はあくまで「見立て」だと思われる。基本的な構想や話の筋は星座とは別に立てられ、その上で星座をそこに登場する神々に見立てて細部の描写に反映させ、神話の内容を充実させているのだろう。星座が構想や筋立てに示唆を与えている場合もあるようだが、その場合でも決定的な重要性を担っているわけではなさそうである。いわば、星座は文字の代わりの備忘録のような役割だったのではないだろうか。
星座の取り扱い
星座は星のつなぎ方次第でどのような形にも作れるので、われわれが「倭の神話」の星座を考える際には、そこに恣意性を排除する工夫は必要だと思われる。本書がこの後紹介する星座はすべて西洋の星座のままである。それは第二、第四、第六、第一一の各詞章のものだが、他にもいくつか推定できるものはある。おそらく「倭の神話」中の半数以上の神話は星座が関わっているのではないだろうか。ひょっとしたら、すべての神話が星座を「見立て」として文字の代用に使っていることも考えられる。だが、仮にそうだとしても、天体と何の関係もない箇所にまでわれわれがそれを穿鑿することにどれほどの意義があるのかは疑問である。
本書では、天体と関係のない神話の解説で星座に言及することはない。以後の詞章で天体が直接関係するのは「国譲り・天孫降臨神話」だが、そこでもできるだけ星座は持ち出さないようにした。星座に論が及ぶのは第二〇詞章「天稚彦」と第二五詞章「天孫降臨」の解説だけである。もちろん、他の詞章でも星座が絡む場合はある。例えば、第一八詞章「国造り」に登場する少彦根のような高皇産霊・神皇産霊系列の神は星座と関係があるのは間違いないが、その場合でもあまり触れないようにした。
星座を前面に出すと安易で皮相な解釈にしかならないだろう。極端な話、星を好き勝手に線でつなげば記紀神話全編を天体神話で説明することさえできる。だが、それでは何も説明しないのと同じである。
この「天岩屋神話の星座」以外の星座はすべて「見立て」でしかないと思われる。だから、詞章の意義、構想、筋立て、前後の詞章との関係などを星座と絡めて論じなければ説得力は出てこないだろう。
[神話と古墳と倭王]
天体観測と古墳
「倭の神話」の中で、天体神話の比重はかなり大きい。また、倭王も含め、各氏族の祖神とは星(星座)の神だということもわかった。もはや、倭人たちの心の中に天体が相当の重きをなしていたことは疑いえないだろう。
しかし、彼らはただ漫然と星を眺め、情緒的な反応をしていたわけではない。むしろ星をかなり詳しく観測し、それに基づいて彼らなりの世界観を構築していたことはこれまでの解説でも明らかである。「かなり詳しく」どころか、第二〇詞章「天稚彦」のように「世界記録」をなんと一〇〇〇年以上更新する発見を基にして創られた神話まである。いったい彼らはどうやって星を観測していたのだろうか。
そんなことを考えたのは他でもない。「天岩屋神話の星座」を星座早見盤で眺めながら、彼らはこの日をどうやって知ったのかと何気なく思ったからである。それまでずっと晴れの日が続いていれば、未明の観測を続けることで翌日にどんな星座が現れるかは予測がつく。だが、この日は梅雨明けの日である。前日の未明に晴れ渡っていたら意味がない。それなら、当日の夜に何か目印のようなものがあるのではないだろうか。
そんなことを考えて星座早見盤を回していたら、その日の暮れにカシオペヤ座が北の地平線すれすれのところで面白い並び方をしているのに気付いた。古墳を横から見た形に似ている、ふと思った。まったくの思いつきだが、それが天体と古墳との関係を考えるきっかけだった。
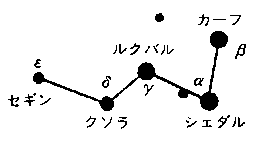 |
「倭の神話」から見た古墳
古墳時代は「倭の神話」が生きていた時代と完全に重なる。古墳時代が終焉したのは乙巳の変(大化の改新)の後で出された西暦六四六年の薄葬令によってだとされているが、なぜその時代に薄葬令が出されたのかを考えるなら、その社会的条件が整っていたからだと言えるだろう。つまり、すでに古墳の意義が忘れられていて、その造営が形骸化していたために薄葬令は出された。
では、なぜ古墳は形骸化したのだろうか。仏教思想が浸透したためだと説明されているが、それを逆に言えば、それまで倭の社会を支配していた思想が衰微したことになる。だから、「倭の神話」が死んだために古墳も形骸化した、そう考えられる。
『紀』第一〇代崇神天皇十年九月条に、最古の巨大古墳と言われる箸墓(はしはか)古墳造営の記事が載っている。
「是の墓は、日は人作り、夜は神作る」。
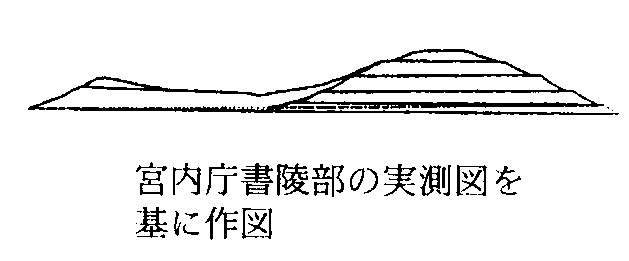 |
おそらくその神は国の神ではないだろう。高天原の神、星(星座)の神ではないだろうか。そして、「夜は神作る」とは、星(星座)の神が自分の形に似せて古墳を作る、という意味ではないだろうか。それならば、それは星座の形に似せて古墳を作ったという意味になる。古墳の築造にあたっては、その稜線に沿って星が並ぶように土を盛ったことになる。
では、箸墓古墳とカシオペヤ座は重なるだろうか。
古墳の全長で考えるなら、重ならないのは簡単な計算から明らかである。カシオペヤ座のルクバル(γ星)は現在では仰角一五度ほどの位置にあるが、当時は歳差のために六、七度ほどの位置にあった。これが後円部の頂上にくるように見える場所で古墳の稜線に沿ってカシオペヤ座の四星が並ぶには、稜線の角度が浅すぎる。古墳をどの位置から眺めてもありえないだろう。
だが、三星が並ぶことはありそうであり、時間の経過に従って五星が稜線のどの位置にくるかも調べる必要があるだろうが、詳しい資料が得られていないので、検証しようがなかった。箸墓古墳はまだ精確に調査されてはいないし、カシオペヤ座の配置も時代によって少しずつ変わっていく。だから、はっきりしたことはわからない。
しかし、古墳は横から眺めるために造られたのではないかとは既に説かれている。それならば、昼間眺めていたとするよりも、夜眺めていた、つまり天体観測に用いていたと考える方が適当ではないだろうか。「夜明け前の星座」は「天岩屋神話の星座」だけではない。それらの星座の日や「夜明け前の祭事」の始まる時刻を知るために、古墳を天文台として造ったと考えることは、「倭の神話」での天体の重要性から言って、それほど突飛な発想ではないだろう。箸墓古墳も、その造営の記事と天岩屋神話とでは時季が異なるので、あるいは別の星座との関連を考えた方がいいのかもしれない。
もちろん古墳が墓であることは間違いない。だが、墓であることが唯一の意義だったのか、あるいは第一義的なものだったのかは考えてみる余地があるのではないだろうか。むしろ天体観測が主たる目的で、墓は二義的なものであった可能性も否定できないのではないだろうか。
もし、古墳が天体と、ひいては「倭の神話」と深い関連を持つものならば、その巨大さは王権の強大さを表すものではない。それは同一の価値観を持ち、同じ神々を奉じる者たちの信仰の強さを表すものである。その者たちの結束の強さと連帯の広がりを表すものである。そして、その時代のその地でその者たちがいかに栄えていたかを事実として証明するものに他ならない。
「倭の神話」から見た倭王
天岩屋神話で倭王の影が薄いのは故ないことではないだろう。そこでは、倭王と倭人たちとの関係は、太陽と太陽の出現を待ち望む者との関係ではない。それは北極星と他の星々との関係のように、あくまでも兄弟である。
そして、北極星は星々の長兄として北天にあり、自らは動かずに他の星々の運行の指針となる。倭王はその北極星のように、民族としての同一性を保証し、同じ道を歩む者の一人として倭人たちの道標となる存在であればよかったのではないか。それならば、倭王が強大な権力者である必要は何もない。彼は権力を揮って人民の上に君臨する専制君主ではなかったことになる。
さらに言えば、倭王の存在感が希薄なのは天岩屋神話だけではない。「倭の神話」全編を通して、倭王だけを特別な存在として扱う意識は微塵も見られない。彼は他の倭人たちと苦楽を共にする同じ仲間として、そして長兄としての相応の敬意の下で倭人たちに遇せられていたのではないか。それが「倭の神話」からうかがえる倭王像である。
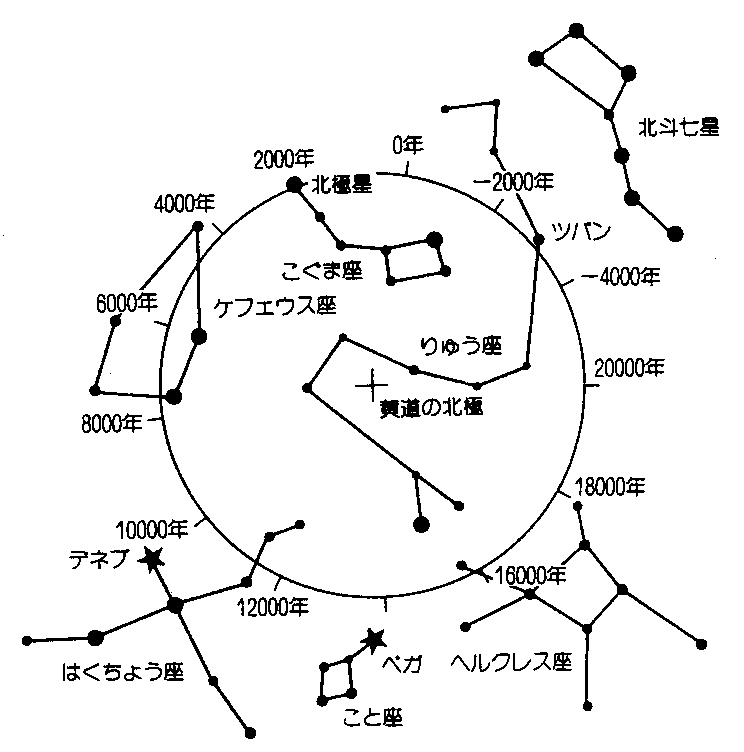 |
ところで、北極星と他の星々との関係はまったく別の意義付けをすることもできる。それは、北極星を星々の世界の中心的存在として解することである。星々は北極星を中心としてその周りを運行する。北極星は自らを同心円の中心に置き、他の星々の運行を支配する。そういう北極星中心主義の考え方も成り立つ。そして、この北極星中心主義は時代が下るとともに強まっていったようにも思える。『隋書倭国伝』の倭王などは、むしろそう解した方がその記事は理解しやすいのかもしれない。
ただし、当然のことではあるが、「倭の神話」から明確な倭王像が描けるはずもない。それは推測でしかない。具体的に倭王は倭人たちの中でいかなる役割を果たしていたのか、それは時代とともにどう変わっていったのか、そして六世紀の倭王はいかにして倭王という存在になったのか、という問題は、「神話」の問題ではなく、「歴史」の問題である。
[基本体系成立時期]
天岩屋神話の成立時期
この詞章解説の最初に、<天岩屋神話の最終型でさえその成立は弥生時代にまで遡れる。‥‥この神話の原型が成立した時期は、さらに百年単位で遡って考える必要がある>と書いた。<この神話こそ「倭の神話」の原点に位置している>とも書いた。それはこの神話の解釈だけから導いてきたものではない。他の神話と比べたとき、この神話が最古−それもかなり飛び抜けて最古−だとしか思えないからであり、また、他の神話の成立時期を考えるなら、この神話は弥生時代にはすでに成立していたとしか考えられないからである。それどころか、「倭の神話」の体系自体が、原型は弥生時代に成立していたようにも思える。もしそうだとしたら、天岩屋神話の原型が創られたのはさらに百年単位で遡らないといけない。
「倭の神話」が成立した時代
神話は「歴史」ではないので、神話の内容から成立の時代を直接知ることはできない。その時代の事物や習俗は叙述に表れているだろうが、それとて時代の変遷に応じて置き換えられたり改められたりしていることは十分考えられるので、その面から成立年代を推測することも難しい。いくつかの神話で下限が絞れるものはありそうだが、神話の体系がいつ頃成立したかを知るには、細部を読んでいたのでは困難である。
だから、本書が「倭の神話」の成立した時代を考えたのは、個々の神話の解釈からではない。「倭の神話」で語られている空間がどの程度の広がりを持っているかがわかったからである。だから、それは高天原神話からではない。天体神話の舞台は天球であり、地上ではないので、原作地の推定はできても、それ以上のことはわからない。これに対して、以後のいわゆる「出雲神話」は地上世界が舞台になっているため、そこに登場する神々がどの程度の空間の広がりの中で存在し、活動しているかを知ることができる。神話では大部分が出雲を舞台としているが、それが現在のどの地に当たるのかを知ることができる−意味がわかりにくい文かもしれないが、この意味は次詞章の解説で詳説している−。
「倭の神話」と銅鐸文化圏
すると、次のような結果が出てきた。
「倭の神話」の神々が活動する舞台は、弥生時代の銅鐸文化圏と重なる。
このことは『風土記』によって傍証される。現存する五篇の『風土記』で記紀神話に登場する神々の記載があるのは常陸・播磨・出雲の三篇であり、豊後・肥前の二篇にはない。また、銅鐸文化圏外(主として九州地方)の『風土記逸文』(筑前・筑後・豊前・豊後・肥前・肥後・日向・大隅・薩摩・壱岐・石見)にも、記紀神話に出てくる神々は天孫・火瓊瓊杵以外の誰も登場しない。その火瓊瓊杵でさえ『日向国風土記逸文』では穀霊として描かれていて、天武・持統朝での誤解の反映があるようなので、それ以後に天孫降臨の地をこの地に探し求めた際、新たに創作されたものではないかと思われる。
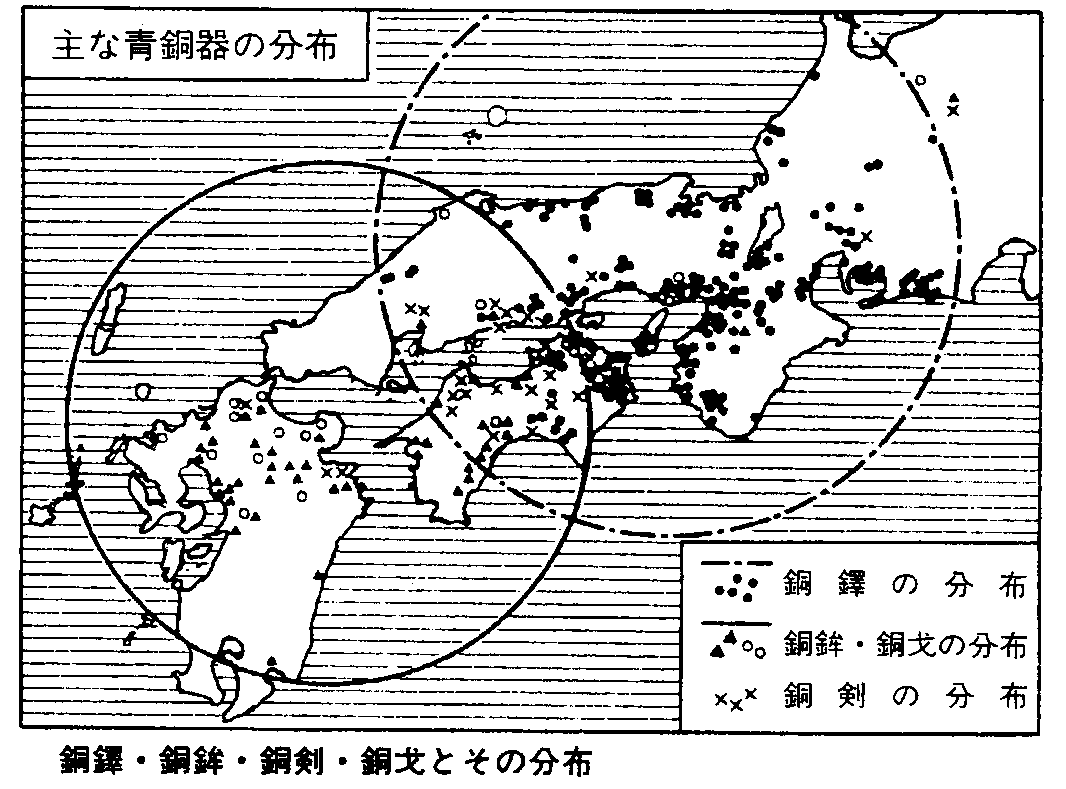 |
『風土記』の成立は奈良時代であり、この頃には伝承もかなり変形していると思われるし、特に九州地方の『風土記』には中央(大宰府)からの強力な規制が加えられているとも言われるので、内容を額面通りには信用できないが、それでもこれだけの明瞭な区別があると何らかの理由は想定せざるをえないだろう。
そこで、本書は、記紀神話解釈の結果から導き出した結論の一つとして、次の命題を提出したい。
「倭の神話」は銅鐸文化圏の神話である。
ただし、この命題には、その基本的な体系が成立した段階では、という条件が付く。体系成立後も新たな神話の創作や入れ替え、訂正、潤色、そして第一〇詞章「二神の誓約」の三女神を祭る「宗像君」のような付加は頻繁にあったと思われる。『紀』の多様な異伝はそのために生じたのだろうが、基本体系は最終型までそのまま受け継がれているようである。
命題と歴史との関係
ところで、この命題は弥生時代に神話の基本体系が成立していたと推測することと同義ではない。その推測は古墳時代が「常識」の通り全国規模の広がりをもっているという前提の下でのみ成り立つ。この点でも「古代史の常識」がひっくり返り、六世紀前半の第二六代継体天皇の時まで弥生時代の二大文化圏−銅剣・銅鉾文化圏と銅鐸文化圏−が温存されていたとしたら話は別である。出雲神話からでは成立の時代を推測できない。
しかし、たとえその「常識」が覆ったとしても、先に述べたように、また試論でも述べるように、古墳と「倭の神話」との関係を考えるなら、古墳時代の始まる前に高天原神話の体系はその原型ができ上がっていたことになる。だから、依然として天岩屋神話の弥生時代以前成立説も、「倭の神話」は銅鐸文化圏の神話である、という命題も揺るがない。
ただし、仮に命題が正しいとしても、そのことと大和朝廷は銅鐸文化圏の発展型だということとは必ずしも結びつかない。基本体系成立後に銅鐸文化圏外の勢力が奈良に入り、神話を自家薬籠中の物とした可能性まで本書は否定するものではない。銅鐸文化圏がその後どう推移し、大和朝廷にまで行き着いたのか、それもまた「歴史」の問題である。
また、『隋書倭国伝』は「倭の神話」と整合するが、五世紀の『宋書倭国伝』は整合しない−むしろ矛盾する−ので、その理由も考える必要はありそうである。
では、三世紀の『魏志倭人伝』は‥‥ということになるが、私は「邪馬台国論争」に参加するつもりがないので、これについての口出しは避けたい。だが、「倭の神話」の基本体系が弥生時代にはすでに成立していたとすれば、時代が重なることになるので、当然照合の対象には入ってくる。「邪馬台国論争」にも何らかの影響は出てくるだろう。
「倭の神話」と縄文時代
以上述べてきたように、「倭の神話」は弥生時代までは遡れると思われる。では、それ以前はどうなのだろうか。
穀物起源神話には縄文時代の農耕文化の反映があるようだとはすでに指摘されている。例えば、『紀』第五段第二の一書に伊奘冉が火神を産んだ後、土神と水神を生むと、その火神が土神と結婚して稚産霊という穀物神が生まれた話が載っている。これが焼畑農業を連想させることは確かである。また、縄文時代の土偶がどれもばらばらになって発掘されることと「殺される女神」(次詞章の大宜都姫=穀物神)とは誰しも関連付けたくなるだろう。
それならば、「倭の神話」の原型は縄文時代にまで遡れることになる。社会を変動させる外部要因も内部要因もなかったとしたら、数千年にわたって神話が受け継がれてきたとしても不思議ではないのかもしれないが、それでは話が飛躍しすぎるようにも思える。
命題について−次詞章以後の解説での取り扱い
ここで、先ほどの命題について付記しておきたい。
命題は出雲神話の解釈結果から導き出したものであり、以後の詞章解説は出雲神話の解釈が主な内容になっている。だから、そこでは命題を未知のこととして、まったく白紙の状態で解説している。
この命題は「歴史」を考える上でも重要ではある。だが同時に、それは「倭の神話」の内容理解にも直接関わっている。命題が誤りだとすると、本書の解釈のどこかに重大な欠陥があるか、あるいは解釈結果に基づく推論に誤りがあることになる。だから、厳密を期すために、あえてその結論に至る過程を明示した。その方が、どこが間違っているのかを発見し易いことにもなる。逆に、もし本書の解釈とその結果からの推論とがともに正しいなら、最後まで読み終えた段階で、読者もこの命題が結論の一つとして導き出せることを確認できるだろう。
[神話が死んだ時代]
「倭の神話」が死んだ時期
ここで話題を転じて、神話が死んだ時代を考えてみたい。
本書は「倭の神話」が死んだ時期を七世紀初頭と推定している。後述するように、それは遣隋使との関連も考慮した上での推定であり、仏教との関係だけを考えるなら、もう少し前の六世紀末とした方が「歴史」とは整合する(この末尾の関係年表参照)。あるいは『隋書倭国伝』の記事は神話が死んだ直後の、まだ神話の記憶も生々しい時代を語っているのかもしれない。
いずれにせよ、それが推古天皇の初期だったことは間違いないだろう。そして、推古天皇の時代が当時としては非常に長く、三七年続いたことが神話を完全に死なせる要因の一つになったと思われる。その間に世代は入れ替わり、時代は新しい色に人々を染め上げていった。
「倭の神話」の死とその後の経緯
七世紀は激動の世紀である。政治的には聖徳太子の国政改革、上宮王家滅亡事件、乙巳の変(大化の改新)、壬申の乱と続いた。文化的には仏教の国教化、遣隋使・遣唐使による中国文化の流入があり、そこに花開いた飛鳥文化、白鳳文化があった。百済の滅亡とそれに続く渡来人の大量移入もあった。人々の意識も大きく変わったことだろう。
そして、「倭の神話」にとって何よりも致命的だったのは、聖徳太子が行った「神話を語る場」の廃止である。そのために、「語り」によって「倭の神話」が受け継がれてゆく道は閉ざされた。
「進歩的知識人」であり、仏教思想によって抽象思考も身につけた聖徳太子にとって、「倭の神話」がどれほど英邁な思考力によって築き上げられた揺るぎない体系であっても、どれほど美しい想像力によって磨き上げられた煌めく珠玉であっても、それはいかにも古くさく、国際化に対応できない代物に映ったことだろう。もう「倭の神話」を真実の話として信じていられる時代ではない。新しい酒は新しい革袋に盛る必要がある。彼はきっとそう考えたのだろう。
その後の歴史の推移を見るなら、それが妥当な判断だったかは評価が分かれるところかもしれない。だが、当時の状況からすれば、彼のその判断はおそらく間違いではなかった。中国大陸の広さを知ったとき、「倭の神話」はもはや「神話」ではなくなっていたのである。だから、「倭の神話」が七世紀初頭に「死んだ」のは、決して仏教思想や中国思想のせいではない。私はそう考えている。
古代の倭人は、彼らと彼らの周囲の世界をきわめて透徹した目で見つめ、当時としてはほとんど完璧と言ってもいいほどの体系立った世界観を創り上げた。「倭の神話」として結実したその世界観は、人生観の細目こそそれほど含んではいないが、それでも現代人を十分瞠目させるだけの深さを持っている。
しかし、残念なことに、神話体系の創出段階では地上世界に対する認識の広がりがなかったために、「国」はほんの狭い範囲に限定され、その狭い範囲の神話として完成してしまった。つまり、「倭の神話」は倭という小世界を語るのにあまりに完璧でありすぎた。だから、神話の世界がそこで閉じてしまい、その外の世界にまで範囲を広げられなかった。広げようとしたら、それだけで体系は無惨に破壊される。
聖徳太子にはそれがよく見えた。よく見えたからこそ、彼は「倭の神話」を安らかに眠らせようとした。その結果、彼の時代に一度「倭の神話」は「死んだ」のである。
だから、彼はその後の天武・持統朝でそれがまったく姿を変えて生まれ変わり、さらに一三〇〇年も後に巨大な亡霊となって再び甦るなどとは夢想だにできなかったことだろう。そんなことのために彼は「倭の神話」を筆録したのではない。
彼は「過去の遺産」をむやみに葬り去ろうとはしなかった。先達の英知の結晶を「記録」としてとどめ、そこに盛られた豊かな財産を後世に遺そうとした。滅亡寸前で倭語の文字化が追いつき、「語られる神話」であった「倭の神話」が『国記』に筆録されたのは、彼の尽力の賜ではなかったか。
「倭の神話」は、その後も亡失の危機に幾度も見舞われながら、『旧辞』『記』『紀』と綱渡りを続けて書き継がれ、奇跡的に現在にまでその姿をとどめている。『紀』などは、自分たちが理解できないからということで、中国史書の通例を破って多くの異伝を載せ、その解釈を後世の者に託した。どの筆録段階でも、これを捨て去ることはできただろう。自分たちのほしいままに改変することもできただろう。彼らがそれをしなかったのは、筆録されていた神話が先人の遺してくれた貴重な遺産だと感じたからである。そこに先人の心が込められていることはわかったからである。その内容を理解できなかったために、多くの過誤は犯したけれども、最大限の努力を払い、何とか後世に伝えようとした彼らの強い意志がなかったなら、われわれは決してこの偉大な作品の内容を知ることはできなかっただろう。筆録者たちの真摯で誠実な筆録態度にむしろわれわれは感謝しなければならない。そして、われわれもまたこれを範としなければならない。
関係年表
| 西 暦 | 天 皇 | 記 事 |
五六〇 五八〇 六〇〇 六二〇 六四〇 六六〇 六八〇 七〇〇 七二〇 |
欽 明 五七二 敏 達 用 明 崇 峻 五九二 推 古 六二八 六二九 舒 明 六四一 六四二 皇 極 六四六 孝 徳 六五四 六五五 斉 明 六六一 天 智 六七二 天 武 六八六 持 統 六九七 文 武 七〇七 元 明 七一五 元 正 |
五五二 仏教公伝(『上宮聖徳法王帝説』などでは五三八年) 五九四 仏教興隆の詔を発布する 五九六 法興寺(飛鳥寺)が完成する 六〇〇 遣隋使(『隋書倭国伝』) 六〇二 百済僧観勒が暦本・天文地理書などを伝える 六〇三 冠位十二階を定める 六〇四 十七条憲法を作る 六〇七 敬神の詔。小野妹子らを隋に派遣する 六〇八 小野妹子を再度隋に派遣する(「天皇」号初見) 六一〇 高句麗僧曇徴が紙・墨の製法を伝える 六二〇 『天皇記』『国記』などを記録する 六二二 聖徳太子が没する 六三〇 第一回遣唐使 六四三 上宮王家滅亡事件 六四五 乙巳の変(大化の改新) 六四六 薄葬令(古墳時代の終焉) 六六〇 百済滅亡 六六三 白村江の敗戦 六七二 壬申の乱 六七三 大嘗祭記事の初見 六八一 帝紀・上古諸事の記定を命じる 六九一 一八氏に祖先の墓記を上進させる(『紀』の資料?) 七一〇 平城京遷都 七一二 『古事記』撰録 七一三 『風土記』撰進を命じる 七二〇 『日本書紀』撰修 |
〈〈 「第一三詞章 大宜都姫」へ 「試論」へ 〉〉