|
�E���ݔ��H�w�̋���͔@���ɂ���ׂ����H�E
�P�D���c��̎�|
�{��89�N�̌����N��̌����W�]�ɂ����ĕM�҂͢���z�ݔ��̕�����Ƒ肵�Ė`���A�A�E�̊����ɐG��Ģ�����Ă݂�ΑI���茩���̔����s��̑吷���A����ł͈���㇗��̐��E�X�L�����_���Ɉ�̉䂪���̂��̖��ނ̌i�C�̊�ՂƂ͉��Ȃ̂��ƁA�悭������悤�Ɋm�ŕs���̊����g�D�����łȂ��A������؍��̂悤�ɔ��R�^�����Ĕ�����ł��Ȃ��Ђ�����y���݂����A�����y���ނ��߂̐�D�̊��ɐ��܂�A�B�X���X�Ƃ���ɓK�����ė�����w�������̏]���Ȑ��i�ɂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���n�߂����̂ł���B�ɂ��S�炸�A�ƌ����ׂ������R�̌��ʂƂ����ׂ����A���z�ݔ��̒�ӂ���Ő�[�܂ł̋Z�p�������I�Ɏx���Ă��錚�z�ݔ��Ƃɐi�H�����邱�Ƃ͍��N���s�\�ł������B���̓��R���Ƃ����A��ɂ͏�q�̔����s��̏��Ţ���������Ƃ�I�Ԃ��Ƃւ̒�R���A����́A�����Ă��ꂪ�����Ƃ��{���I�Ȗ��ł���ƕM�҂͍l���邪�A���z�w�Ȃ̌��z�ݔ��ƊE�ւ̐l�ޕ⋋��n�Ƃ��Ă̌��E�ł��飂ƒQ���A�����Ă��ꂩ��̌��z�ݔ�(�L�`)�̕����Ƃ��Ģ���V�X�e���H�w��̋��猤���̌n�̒�Ă��s�����B
�T�N��̍����A�����ɂ��̔�����������o�ς̏�ŋ���A�A����E�̗͊W����ς��A���Ă̌��z�ݔ��ƊE�ւ̐l�ޗ��o����炩�͍D�]�������̂Ǝv����B������������o�ς̒�͂��̂܂܂ł����Ă͂Ȃ炸�A�l�ވ琬�ׂ̈̍��{�I�ȋZ�p�̌n�����̌n�����P����Ȃ�����A������o�ς����������߂����܂ɂ͌��̖؈���A�ƂȂ邱�Ƃ͖ڂɌ����Ă���B
�@����A���琧�x���v�̗���Ɏ��_�Ă�ƁA�����n�𒆐S�ɑ�w�@�d�_������Y���������Ɍ������Ă���A��w�Ȃ̕������͌��z�w�Ȃ������Ă��Q���������A�֘A�w�ȁA���ɓy�Ƃ̓������_�@�Ɋe��̐V�����A����������킵���A���ɂ͗r������Ƃ��֎v����w�Ȗ����l�Ă���Ă���B�M�҂̏������閼��ł͌��z�w�ȂƓy�؍H�w�ȂƂ̓����̂��Ƃɢ�Љ���H�w�ȣ��V�݂��A���̒��ɢ���z��Ƣ�Љ�{(���y��)��̂Q�R�[�X���݂���ꂽ�B�S���̈�A�̓���������ƁA�D�G�Ȑl�ފm�ۂ�ڎw���y�،n�̏_��A�����͉���I�Ȕ��z���ڗ��B���z�n�͌��z�ƃC���[�W���炭��l�C�Ɏx�����Ģ���z��̖��̂����炵�Ă���Ⴊ�����B
�@���������̂��Ƃ͌��z�G���W�j�A�����O�n�ɂƂ��Ă͕K�������ŗǂ̑I���Ƃ͎v���Ȃ��B����͔N�X�G���W�j�A�����O�n�ւ̎u�]�������ቺ�Ȃ�������Ă��邩��ł���B21���I�̊��ƃG�l���M�[��w���������������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�e�[�}�R�ς̊��n�ɂƂ��Ă͋ɂ߂ďd��Ȗ��ł���B�Ăі���̗���Ƃ�ƁA�]���̢���z�ݔ��T�`�V�����V�X�e���H�w�T�A�U�����Ѣ�ݔ��H�w��Ƃ��A�O�҂͌��z������̃��J�j�Y�����p�b�V�u��A�N�e�B�u�̗��ʂ���V�X�e���H�w�I���_����u�`�A��҂͌��z��s�s��Y�Ƃɂ�����ݔ��G���W�j�A�����O�̊�b����p�H�w�����E�̈�I�ɍu�`����A�Ƃ����B
�@���������̗�ɂ����Ă��ցA�P�Ɍ��z�����ɂ���������ɉ߂����A21���I�Ɏ��̉����锚���I�ȍL��I�����������ƌl���̌���ӗ~�Ƃ̊����ɑΉ����ׂ��A�M�҂̎咣����Ƃ���̖���������H�w�̎��_����̊֘A�����w�Ƃ��Ă̐V�̈�����ł͂Ȃ��B�M�҂̋��߂���̂͂�����̈�ɖړI�ӎ����������w�����W�߂����ł���A���z�ݔ��̗̈���܂�������z�����L�̈��ڎw�������B
�@���āA�䍑�̌��z����̗��j�I���W�ߒ����猩��ƁA��ݔ�������z�v��A���H�w�ɕ�܂Ȃ������������`�œW�J���Ă������A����Ώۂ��K�͓I�ɂ͌��z����X�̐l�ԂցA�����Č��z����n�楓s�s��n���ցA�̈�I�ɂ͌��z�ݔ�����s�s��Րݔ���e��Y�Ɛݔ��ւƊg�債�Ă����B����ɑ��A���ݔ��Ɋւ���Z�p��w��̎傽��S����͋@�B�H�w�n���猚�z�n�ւƐ��ڂ��A���̊g��ɉ����Ĉ�w�n�A��䥓d�C�n�A�G�l���M�[����w�n�ȂǂւƊ֗^�҂̕��������Ɋg�債����B�V�������ݔ��H�w�̗̈����V�X�e���H�w��Ɩ��Â����Ƃ��āA�L�̈扻�̎咣�ƌ��z���炳��ɂ͑�w�@�d�_���Ƃ̒��a�A�w������݂̍肩���A�������x�Ƌc�_�̎�͂��Ȃ��B�{�������c��ł́A�����錤���ҥ�Z�p�ҏW�c�̐��i�Ƌ���̌n�݂̍���ɂ��āA��w�Ǝ����Љ�A���̓��O�̌��͂��܂߂ĕ��L�����n���瓢�_���s���A21���I�Љ�ɔ��������B
�i�ȏ�A���z�G��1994.7�L�ځA�������c���|�����Ɠ����j
�@
�Q�D���z�ݔ��̒S����̕ϑJ
�@���܌��z�ݔ��̒S����́A���Ȃ��Ƃ���w����ɂ����Ă͌��z�哱�A�ƌ������ނ��댚�z�݂̂ƂȂ��Ă���B��C���a�E���r���q���͕ʂƂ��Ă��d�C�ݔ��͂ǂ����ƂȂ�Ɛr�����ڂ��Ȃ����A���Ȃ��Ƃ�����J���L��������͌��z�w���тɂ��̌W�݊w�ȁi�ݔ��H�w�ȂȂǁj�ȊO�Ɍ��z�ݔ��Ȃ����ݔ��H�w���܂܂�邱�Ƃ͖w�ǖ����B
�@�ݔ��H�w�Ƃ����ɍł��ӂ��킵���̂͂ނ��뉻�w�H�w�ł��邩���m��Ȃ��B�����������ł�"���w"�Ƃ������t�ɐ���ĉ��w�v�����g�̘g���o���Ȃ���������������B���ɂ����A�{�C���[�E�Ⓚ�@�����@�B�H�w�̉Ԍ`�ł����������ɂ͂��̉��p�Ƃ��Ă̌��z��C���a�͋@�B�n�o�g�҂���������[�h��������ǂ��A�������O�̂��Ƃł���B�������̍H���͈͂ł��鋋�r���ݔ��Ɏ����ẮA�����������w�n����̌����͂������Ƃ��Ă��A���{�ł͋��炭���z�ݔ����o�ꂷ��܂Ŋw��̌��𗁂тȂ������ɈႢ�Ȃ��B
�@��Q�����E���̑O��ɓ��{�ɖ{�i�I�Ȓg��[�Z�p���n���A�W�J�����y�����B���̖�����S�����͖̂��S�Ɗe�n�̕ČR��n�A�O�҂͒g�[�A��҂͗�[�ɂ����āB���B�ɐi�o�������{���Ɋ��̊��ɐڂ��Ė��S�Z�p�w�����n�Ƃ͎����̈قȂ�g�[�Z�p�̌n��W�J�����B�n��̋C�ۏ������l���ɍł��K�v�ȋZ�p��̌n�����Ă����D��ł���B���ɉ���i���R�W�H����S�������Z�p�w�́A�����E���C���d������A�����J���̖{�i�I�ȋƋ��r���q���̐��_��O��I�ɒ@�����܂ꂽ�B�����A�J��̒|�̎q�̔@�����������ݔ��H����Ђ̑����͂��̉��b�ɗ����Ă���B���̎����A�����Z�p�҂͕��������ɂ���ĐE���D��ꂽ�q��n�Z�p�҂Ȃǂ̌R�����傩���ʂɖ�������ɗ���Ă����B�i�K�͂Ɛ��i���قȂ邯��ǂ��A�ߎ��A�����J�ɂ�����F���Y�Ƃ̏k���A���\���̉����ɂ�閯������ւ̓��]���o��栂����悤�B�j
�@�������Đ��̌��z�ݔ��ƊE�́A�ɂ����Ă͐�O�h�̋@�B�n�A�I��O��̍����Z�p�n���o�c��]�ƋZ�p�W�J�̎���������A���h�̋@�B�n��������x���W�J����ԂɁA���a�R�O�N�����獂������i��w�ȏ�j�o���҂͎���Ɍ��z�n�ɓ���ւ���Ă����\�}��������B�����Ɍo�ς̋}���x�̐����ɂ����܂��āA�@�B�E�d�C���̑��̍H�w�n�͖w�ǂ��ׂĐ��Y��̂ɁA���z�n��������̂ɁA�Ƃ����������S�����m�ɂȂ����B���̒��Ō��z�ݔ��Ƃ����A�������z�ɂ�����@�d�H�w�I�G���W�j�A�����O�Z�p�͂��̏d�v�Ȗ����Ɋւ�炸�A��ɖT������܂˂Ȃ�Ȃ��Ȃ����B���z�t�ѐݔ��Ƃ����A�����̌��z�n�ݔ��Z�p�҂ɂƂ��čł����܂킵���v���N������邱�̕\���̒��ɂ��̂��ׂĂ̌��ۂ��܂܂�Ă���B
�@
�R�D���z�Ƌ���ƌ��z����
�@���{�ȊO�ł͖w�ǂ̍������z����͌��z�Ƌ���Ȃ�Ƃ��Ă���B�Љ�ɔF�m���꓾��悤�Ȍ��z�Ƃ͂S�N�₻����̑�w����A���������{�̂悤��1.5�`�Q�N�̋��{�ے��⑽�ʂ̌��z�G���W�j�A�����O���炪���荞��ł�����w�����͈͓̔��ň�͂����Ȃ��B�����̍��ł͑�w����ȑO�̋�����A���w�Ȃɔ䂵�Ē�����w�����A����ɂ͎Љ���K���o�Ă���̍ċ���A�Ȃǂ�܂荞�����̃J���L��������g�ނ��Ƃɂ���Č��z�Ƃ���Ă�����B���̏ꍇ�A���z�ݔ��͋@�B����Ƃ��鑼�̍H�w�n�A���ɂ͒g�[���C�܂��͋w�Ȃ̏o�g�҂��R���T���e�B���O���������J�݂��Đݔ��v��S������B�ޓ��ɂ͌��z����̊�b�͂��Ƃ��ƂȂ��A�Ɩ��o����ς݂Ȃ���o���Ă����B�������ޓ��͌��z�ƂƂ͑Γ��̊W�ɂ���B�������Ώۂ����z�ł���ȏ�A���z�Ƃ��I�[�K�i�C�U�[�ł��邱�ƂɊԈႢ�͂Ȃ����A���z�Ƃ��܂��\����ݔ��Z�p�̈Ӌ`���\���ɂ킫�܂��A���̈ӌ��d���鋳����Ă���B
�@����A�R���T���e�B���O�G���W�j�A���ɂ��Ă݂�Ό��z�͈�̉��p�Ώۂɉ߂����A�ޓ��̋Z�p�͓s�s�E�Y�Ƃ̊e����ɋy�Ԃł��낤�B���������Ӗ��Ŋ�{�I�ɉ��猚�z�Ƃ��z���K�v�͂Ȃ��̂ł���B��肪����Ƃ���A���z������Ă��Ȃ����߂Ɍ��z�Ɋւ���펯�I�m���E������ۗL���Ȃ����Ƃł��낤�B����͌��z�Ƃ̕��S�ƂȂ�A����ł������z�ƂɃo�����X�̂Ƃꂽ�v�悪�\�Ȃ悤�ɏ\���ȏC�����Ԃ��݂�����̂ł���B
�@����ɑ��ē��{�̌��z����͂ЂƂ茚�z�Ƃ���Ă�݂̂łȂ��\���E�ݔ��̐v�Z�p�҂͂������A���z�s���ƁE�{�H�Z�p�҂̉����ł�����B�]���Č��z�ɂ����閜�ʂ̋�����L��������̂��ړI�ŁA���Z�p�͑�w�@�ے�����юЉ�֑������Ă���̊�Ɠ���������Ɉς˂���B���z�Ɋւ��鏔�Z�p�E���m���𑍍��I�Ƀo�����X�ǂ����炵�悤�Ƃ����킪���̌��z����́A���܂��s���Η��z�I�ł��邱�Ƃɂ͊ԈႢ�Ȃ��B�c�O�Ȃ�����H�w�̊w�╪�삪�L�扻�E�ו��������ƂƂ��ɐݔ��Z�p�����x���E���G������ɂ�A�����͖ڗ����Ȃ������A���邢�͏������̌̂Ɍ��߂����������̋���̌n�̌��_������Ɍ��݉����A������E�ɒB���Ă���A�Ƃ����̂��M�҂̃e�[�[�ł���B
�@
�S�D�ݔ�����ɂ�������{�^���z����̌��E
�@��ɏq�ׂ����_�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ŁA���̂Ɍ��ꂽ�̂����ȉ��ɍl�@����B
(1) ����N���̕s��
�@���z�Ƌ���ɂ����Ă��ւS�N�ȏ��K�v�Ƃ��鋳��N�����킸�������Q�N�ōL�͈͂̋�����o�����X�ǂ����ʓI�ɍs����͂��������B�����Ƃ����̓_�Ɋւ��ẮA��w�@�d�_�̌X���ƎЉ�l�ċ��琧�x�̈�ĕ��@���ɂ���Ă͉����̌��ʂ�������B
(2) �f�U�C�i�[�������ڂ�ӎ�
�@�ǂ̐��ł���A�������̂悤�ȎЉ���ł���A�����h�͑����h�̔��Q����B��w�̌��z�w���炪��q�̂悤�Ȍ��z����ł͂Ȃ����z�Ƌ���ł���Ƃ̌���Ɋ�Â��ē��w���Ă���w���B�ɂƂ��Ă݂�A���z�f�U�C���̓����̂ĂĊ��E�ݔ��ɑ��邱�Ƃ͈��̗������ڂ�A�Ƃ܂ł͂����Ȃ��Ƃ������ł���悤�Ȃ̈�ۂ�^���Ă����Ǝv����B���������ł���ꍇ������A�S�����ɁA�f�U�C���\�̗͂L���ɂ�����炸���E�ݔ��ɐ��������ƈӋ`�����������A���̓��i��ł����w���B�����Ȃ肢�邱�Ƃ͊m���ł���A�����ɉ�X���ݔ��n���t�̖����̐s����Ƃ��낪�������B���������̎��т������Ƃ���A���ϓI�ɂ͂��Ȃ�̏����h�ł���A���Ԃ̗v������x������傫�������B�Ȃ��A�\���Z�p�n�͂��̑ϐk�Z�p�̓��{�ɂ���������I�K�R�I�ȗ��j�I���W�ߒ��Ɋ�Â��A�ނ��둽���h�ƌ����邭�炢�����̋����l���w���ɔz�u���Ă��邩��A����͑S���قȂ��Ă�������ǂ��A�ŋ߂͊��E�ݔ��n�Ɠ��l�̏�ԂɊׂ��Ă���Ƃ�����B
(3) ���̖ړI�ӎ����@
�@1978�N�Ɏ�����w�ɗ��Ă���ŋ߂܂ŁA���Ŏ��������z�w���_�̍u�`�̏I���ɁA���w���Ă����w���Ɏ������A���P�[�g�������Ƃ����x������B�u�`�ɂ����Ċ��E�ݔ��̏d�v�������Ȃ萁����ł����Ă��A������ӎ����Č��z�w�Ȃɗ����ƌ����҂͊F���ɓ������A�u�`���ď��߂ċ�����������Ƃ����҂��P�`�Q���ł��������ƋL�����Ă���B
�@���ǂ��̂悤�Ȉӎ��̂��Ƃɓ��w���̒�����ݔ��Z�p�҂�y�o������ȂǂƂ͓y�䖳���Ȃ̂ł���B����ɂ������ɂ����Ȃ����Ƃ�����ǂ��ł��낤�A�f�U�C���n�����O�ڂƂ��Đݔ��S���_�������オ�邱�Ƃ͖ڂɌ����Ă���B�����Ċm���ɂ����������ƂɂȂ����Ƃ�����A�킪���̌��z�Ƌ��炻�̂��̂͑�ςȂ��ƂɂȂ�ł��낤�B
�@�Ƃ������Ƃ́A���Ƃ̔��[���炵�Ċ��ӎ��E�G�l���M�[���E�����H�w�ɖړI�ӎ����������w�����W�߂�ꂪ�������Ƃ����Ȃ̂ł���B�����Ă��̂��Ƃ͊��E�G�l���M�[���l�ސ����̊ϓ_����ł��d�v�Ȏ��_�̈�ɂȂ��Ă��錻���_�ɂ����āA�����E��������ɂ����鋳����e�ƂƂ��ɁA����̌n��̑���ł���Ǝv���B
(4) �����w�o�p�̐���Ɛl�ޕs��
����ɔ��Ԃ�������̂��ݔ������w�̐l�ޕs���ł���B����ɂ͓�l�̈Ӗ��������āA���̑��͊w�ʂƘ_���Ɛт��d�����߂��邪���߂ɊY���҂����߂��Ȃ��A�ƌ��������ł���B���̂��߂ɏ���E�������Ƃ����ӂ��Ɋw���ŏ��i���Ă����l�ނ͌����Ɛт͂����Ă������o�����������߂Ɏ��̂���ݔ����炪�ł��Ȃ��B���̂��߂Ɏ��i�R�����w�ǂȂ��ɓ��������u�t�ɗ��炴��Ȃ��B���̎��Ԃɂ��Ă͖{���c��ɂ����ĕʓr�����̂ŎQ�Ƃ��ꂽ���B
�@���ɂ́A�z�����ēo�p���ꂽ���u�t�͖���V�ɋ߂��A�܂��w���̌����w�������邱�Ƃ��ł��Ȃ�����A���̊����Ď��Ԃ̒��ł����ɒ��l�I�ȗ͂����ĉ��������Ƃ��Ă��A�撣��Ί撣��قNJw���͗����������Ă����Ƃ������ƂɂȂ�A���̓�������������҂���͓̂y�䖳���Ƃ������̂ł���B�܂��A�����v�ɒ������҂��K��������w�̐ݔ�����ɓK���Ă���Ƃ͌����Ȃ��B�t�ɁA�ݔ��v����Ȃ�D�K�ł���Ǝv���Ă����̂悤�ȏ��݂����J���L�������͐������Ȃ��B
(5) �m���̕�
���E�ݔ��n�R�[�X��I�命���̊w���͑��ƌ�ݔ��H��(�����̓[�l�R����)�Ɍg��邱�ƂɂȂ�B�ޓ��͘_���w���̐搶�̐��ɂ���āA�����鉹�E���E�M�E��C�E�F�����ċ��r���E�E�n��G�l���M�[���̂����ꂩ�ɏڂ�������ǂ��A�M�͊w�E���̗͊w�E��������Ȃǂ̒m����g�ɕt���Č���ōl���鉞�p�͂�g�ɕt���Ă���҂̊����͋ɂ߂ď������B�����̓G�l���M�[�E�M�}�����E���������E��ԕω��ȂǁA�A�N�e�B�u�Ȏ�@����̂Ƃ���e��ݔ��̐���b�H�w�Ƃ��ďd�v�Ȗ����������Ă���B
�@���������z�`�M�A���C�ʕ�����̂Ƃ��錚�z���H�w�̊w��ł͗]��ɂ��p�b�V�u���d�����߂��āA���ɁA�A�N�e�B�u��@�����z�o�g�҂ɂ���܂������@�_�ł���Ƃ��Ďד�����������������ł��Ȃ��B����͂ЂƂɂ͐ݔ��Z�p�҂������܂ŃA�N�e�B�u�ł��������l���Ȃ��A�܂��Č��z�o�g�҂��A�ƌ����X���ɑ��锽���E�����ł��낤�B������ɂ��Ă����݂̌��z���琧�x�̂��Ƃɐ��ɏo�Ă����ݔ��Z�p�҂͂��̏o���_�ɂ����āA�ݔ����Ƃ��Ă͂��܂�ɂ��m���̕�Ƃ����n���f�B�L���b�v���Ă���̂ł���B
�@
�T�D���z���H�w�Ɛݔ�
�@�ȏ�A�M�҂̘_�|��H���Ă���ꂽ�����́A���̋L�q�̒��ɂ����Č��z���H�w�Ɛݔ��Ƃ̊W�������܂��ł��邱�Ƃ��������ꂽ�ɑ��ᖳ���B���ɂ͌�҂�O�҂̑Η��T�O�Ƃ��ėp���A���ɂ͌��s�̊T�O�ݒ�Ɋ�Â��đO�҂ɕ�܂������̂Ƃ��ďq�ׂĂ���B���z�ݔ����܂߂�(���z)���H�w�̊T�O�\�z������A�Ƃ����֓������E���ؑ]�菲�ȗ��̍l�����ɕM�҂͕K������������������̂ł͂Ȃ��B���������̊T�O�ݒ�́A���̊T�O�̌f���闝�z������̏�ɂ����Ă������ł���͂��ł������A�ȃG�l���M�[�ւ̈ӎ��̍��܂�̎�����o�ĂQ�O�N�A�����Ɍ��z����ɉ���̕ω��̒����̔F�߂��Ȃ������A���łɂ��̖������I�����Ǝ咣�������B
�@�����Ȃ��̂́A���Ėk�C����w�ɂ����錚�z�w�Ɛݔ��H�w�̕����A�_�ˑ�w�ɂ����錚�z�w�Ɗ��v��w�Ƃ̕����ƌ������A�M�҂Ɍ��킹��ɂ߂đO�����̂�����A�̓��������̂ɂ���ɑS���I�ɓW�J�����ɓڍ������̂��A�s�����Ƒ�w���ɂ��ꂼ��ŗL�̌��������������̂��A���炩�ɂ���˂Ȃ�Ȃ����낤�B
�@������ɂ��Ă����z���H�w�͌��z�����������ւ���p�b�V�u�̘_���ɍŏd�_��u���Ƃ����̂��A�ǂ������j�I�ɂ����G��I�ɂ��œK���̂悤�Ɏv���Ă���B���z�ӏ��E�v��w����ӏ��v�ցA�\���H�w����\���v�ցA�ƌ����̂Ɠ�������Ō��z���H�w����ݔ��v�i�ƌ������M�҂͌�q����悤�Ɋ��V�X�e���v�Ə��������̂ł��邪�j�ցA�ƌ����̂͂ǂ������̐ڑ����������̂ł͂Ȃ����A�ƍl����Ɏ������B�S��҂ƈ���Ă��̊Ԃ̔�]��ɂ��傫���̂ł���B�\���̊w��ƍ\���v�̊Ԃɂǂ�قǂَ̈��̋Z�p�̌n�����荞�ނ��ƌ����Ζw�lj��������B�������z�̌`�Ԃ���̓I�ɗ^�����邾���ł���B�ݔ��͂ƌ����A�M�͊w������A���̋�Ƃ��Ẵq�[�g�|���v���A�{�C���[���B���̗͊w������A���̋�Ƃ��ăt�@���E�|���v������A�z�ǍH�w�E�����w��������B�����Đ���H�w���A���̋�Ƃ��Ď������䂪�A�r���I�[�g���[�V�������A�\���̗��_���K�v�ƂȂ�B����͂����펯�I�ȈӖ��ł̌��z���H�w�ƈَ��̂��̂ƌ��킸���ĉ��ƌ����悤���B
�@�������A������Ȃ��ł������������B�َ��ł����Ă��߂��e�ʂł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�����ĉ��E���E�M�E��C�E�F�ƌ��������z���H�w������Őݔ��ƌv��E�ӏ��͑ɂ��邢�͎O�p�W�ɂ���B
�@��̗�������悤�B���É���w�ł͊w���E��w�@��ʂ��ċ���E�����ɒ����M�����ݔ��E����E�G�l���M�[�A��{�Y�O���M�E��C�E�s�s��(����)�A�Җ{�����ЁE���X�N�E���A�v��͐����S���E��(��)�E�s�s��(�S��)��S�����Ă���B�K���s�K���ǂ�����Ă������錚�z���H�w���n�Ƃ������F�ʂ������B���̒��ŒҖ{�͔����L�[���[�h�ɂ����Όv��̃O���[�v�ƌ����w�������L���A�v��͊��]�����L�[���[�h�ɂ���܂��v��̃O���[�v�Ƌ����������s���Ă��Ă���B�M�҂̓����ł������v��n�̂x�����́A���Əꍇ�ɂ���āA�v��Ȃǂ͌v��n�݂����Ȃ��̂��ƌ����邱�Ƃ��L�����قǂł���B�����͐ݔ����K��ʂ��ăI�t�B�X���̃v�����j���O�̎w�����s���A�܂��O���[�v�������ɂȂ��ׂ��A��{�Ɩ����p�G�l���M�[���t�˗�[�A�Җ{�ƒ~�M���A�v��Ǝ������w�W��ϓ������̋����������s���Ă����B����ɒҖ{�͖h�Ђ̃L�[���[�h�ɂ���č\���n�̋����Ƌ����̍u�`�ƃ[�~�������A���܂���n�Ƃ������h�Ќn�Ƃ����������ʂ肪�悢���炢�ł���B����͕L��A�M�҂��ݔ��T�C�h�����炵�Ă��邱�Ƃɉ����Ĕޓ��Ɍ��z����̗��_���̓�����Ă��邩��ł��낤�B���݂ɍ�{�������R�l������܂ł̐��̌��z����̌n�̂��ƂŌ��z���H�w�̂��ƂɋƐт�W�J���A�����ł̓I�[�o�[���[�h���o��Ŋ��E�ݔ��n�̌v��E�ӏ��A�\���E�ޗ��n�Ƃ̎O�n�C���������咣�����s���Ă����B
�@�����Ō������������͉̂�X�̂o�q�ł͂Ȃ��A���ꂼ�ꂪ�]���̌��z���H�w�ƈꖡ�Ⴄ�A���܊��V�X�e���H�w�Ɩ��O��ς���Ɏ������悤�ȐV�����x�N�g�������߂Ȃ���A���̒��ł����z����ɕ��L���g����Ă������Ƃ��ł��邱�Ƃ��������������̂ł���B
�@
�U�D���V�X�e���H�w�ƌ��z�w
�@�ݔ����l�C�̖��������̈�ɂ��̃l�[�~���O���L��A�ƌ����̂͑���̍l���̈�v����Ƃ���ł���B�u���z�ݔ��v�ƌ����A�uBuilding
Equipment�v�ƖA�ǂ������������A�Ǝv���Ă���Ƃ���ɁA�C�M���X�ŁuBuilding Services
Engineering�v�ƌ����p��ɑΖʂ��A�����A�Ǝv�������̂́A����ł���������Ȃ��B
�@���B�������Ă�����̂͐l�̂�栂���ΐS���z��n���E�ݒ�������n���E�]�_�o�n���E�C�njċz��n���Ȃǐl�Ԃ������Ƃ��Đ����A�����Đl�Ԃ炵�������邽�߂̌���Ƃ��Ă̐����S���V�X�e���̂��ׂĂȂ̂ł���B�����Ă��̃V�X�e���Z�p�͌��z�݂̂łȂ��A�Y�ƃV�X�e������s�s�V�X�e���ւƓK�p�Ώۂ��L�����Ă䂭�Ƃ��̋��ʂ̌����E��@�ł���B���̂悤�ȓ��e�̂��̂��u�ݔ��v�ł��uBuilding
Services Engineering�v�ł��L�蓾���A�܂��Ă�uBuilding Equipment�v�Ȃǂ͊��S�ɃC���[�W�O��ł���B
�@���̂悤�ȗސ��ߒ�����݂Ă�����͌��z���`�Ƃَ͈��̃R���Z�v�g�ƍL����������̂ł���B����A�l�ނ̒a���Ƃ��̗��j�I�ȓW�J�͂܂��ɂ����鐶���ێ��̏��튯���l�̂ɂ�����ׂ��z�u����A�n��Ŋ����Ɋ��������߂��Ɠ����ɂ��̍����Ȏv�l�ߒ����Y�ݏo����������͂܂��ɐ_�̑��`�ł���l�̍\�����̂��́A�l�̓��̊튯�z�u�v�悻�̂��̂ł��낤�B���̎��_���猩��ƍō��̑��`�����������邽�߂ɂ͈ӏ��v��E�\���E���V�X�e���v��ɂ�����v���W�F�N�g�`�[���̍ō��x�̋�����������Ȃ�Ȃ��̂͌����܂ł��Ȃ��B�����ɕK�v�Ȃ̂͋����ɂ�铝���ł����Ď哱���̒D�������ł͂Ȃ����Ƃ���L���ׂ��ł���B
�@�ȏ�̂悤�Ȋϓ_����M�҂�́u���z�ݔ��v�ɑウ�u���V�X�e���H�w�v��p���邱�ƂƂ��A�܂���̃J���L�����������ɂ������Ė���ł͂�����u�`���Ƃ��i�ʂɂ����I����̂��߂́u�ݔ��H�w�v��݂��Ă���j�B�{���c��̑ō��킹�̏�ŏ��{�������_�ˑ�ł����l�̃l�[�~���O��p���Ă���Ƙb���ꂽ�B�����悤�ȓ��e�ɑ���l�[�~���O�ł��邩�ǂ����͕ʂƂ��Ă��A�l�ԁE���E�G�l���M�[�̃_�C�i�~�b�N�X�𑽗l�ȋK�͒P�ʂƃV�X�e���Ώۂɉ��p�ł���悤�ȃV�X�e���H�w�ƌ����Ӗ��ł���B��X�̊֗^������V�X�e���̓p�b�V�u�ƃA�N�e�B�u�̗��ʂ̋����̂��ƂɌ`������˂Ȃ�Ȃ��B�������Ƃ�������]�Ƃ���Ƃ��������͑������L���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@�]���́u���z���H�w�v���u���V�X�e���H�w�v�ƌĂѕς��Ă��悢�B�������A�O�҂͌�҂ƌ��z�Ƃ̃v���W�F�N�g�S���ƍl���A��Ƃ��ăp�b�V�u�Ȍ��z�����A�l�̐����S���������A�A�N�e�B�u�V�X�e���̂Ƌ��E���A���邢�͋����̂�������e�[�}�Ƃ���A�Ƃ�����������Ȃ悤�Ɏv����B�����v���W�F�N�g�������Ȃ�u�������H�w�v�A�s�s�Ȃ�u�s�s���H�w�v�Ƃ���悢�B�����Ă��̂悤�ȃv���W�F�N�g��g�ނ��߂ɕK�v�Ȋ�b�I�Ȋ������E�G�l���M�[�����ƁA�A�N�e�B�u�V�X�e���̍H�w�A����E�ۑS�̍H�w�Ȃ�тɊe������a�V�X�e���i�ݔ��j�̌�������̕��S�����V�X�e���H�w���S������A�Ƃ��ׂ��ł���B
�@
�V�D�w���w�Ȃ̍ĕ�
�@�M�҂��P�U�N�O�ɑ�w�Ƃ����Ƃ���ɗ��ċ������̂͂��̕ێ琫�Ƒ卑��`�ł������B����͉c�X�Ƃ��ĂȂ���l�ނ̂͂����̊m�ہA�Ȃ�тɑ�w�ԋy�ё�w�ƎЉ�Ƃ̊����Ȑl�ތ𗬂̍���̓�_������ł���B��҂ɂ��Č����A�M�҂̂悤�Ɏ����Љ���w�ɎQ������҂������Ă��A��������̌��𒆂ɑ�w��������Љ�Ɂu���C�i�V���[�n�C�j�v���邱�Ƃ͓��{�ł͊F���ɓ������B����̑��������]�܂Ȃ��Ƃ���A�������S���\���ɋ@�\���Ă��邩�A�����s�\�ɂ��Ă���̎��I���ׂ��A��w�l����Ƒ��̉��ꂩ�ɁA���邢�͗��҂ɂ��邩�̉��ꂩ�ł��낤�B
�@���āA�M�҂͑�w�s���E�����s���ɂ��Ă͑S���s���ŁA����ɂ���ƎЉ�̗v���Ƃ̂Ȃ��肪�ǂ��Ȃ��Ă���̂��ǂ�������Ȃ��B��y�����������B����Ƃ��́A�Љ��̐��i������̂��Ƃ��j���オ���Ă��Ȃ�����Љ�I�v���Ƃ͍l�����Ȃ��A�ƕ����Ȃ������A�ƕ������B����Ƃ��́A���ꂩ��́u���v�ȂǂƂ������̂͒��A���ł��u���v�������Ȃ��ƕ����Ȃ͎���c�ɐU��Ȃ��A�ƕ������B����Ƃ��͍��x�������ɑS���ÁX�Y�X�ɉJ��̒|�̎q�̂��Ƃ����z�w�Ȃ��ݗ�����A���̌��z�w������㉽�\�N�Ԃ͌��z�n�w�Ȃ̑��݂̕K�v�Ȃ��A�ƕ����ȂƖ����̂����z�����̌����炵���A�ƕ������B栂������Ƃ��Ă��A����̕ω������Ă���Ȃ��Ƃ����܂ł������͂��͂Ȃ�����펯�I�ɂ͂܂����Ƃ͎v���B����Ƃ��͕����Ȃ͌��z�w�ȂƓy�؊w�Ȃ��܂Ƃ߂đ�w�Ȃɂ��������Ă���A�����w�ł͂��̂Ƃ���ɂȂ���������A�ꏏ�ɂȂ��������b�g�͔��������A�p���Ď���f�킹��ɗ��܂����A�Ƃ��������B����������ł͖L���Z�ȑ�̂��Ƃ����F���铝�����Ȃ��ꂽ�A�ƌ����b���`���B
�@�����A�����s���Ƌ������Ȃĕ�������̘b�̂ǂ�����A��ʂ̐^���ƈ�ʂ̌֒��E�����ӎ����܂܂�Ă���̂ł��낤�B�������s���ɂ���w�p�ɂ���A���ߕ���ƌ����Ȃ��قǂ̌������ȂēK���K���A����ɑΉ��ł��Ȃ���Ή��̍s������A��w��������ƌ��������B
�@�������s���Ă����̂Ō��_���}�����B����o�҂̊��E�ݔ�����ɑ��鋳��̐��ĕ҂ւ̊��ҁE���]�͈ȉ��̂��Ƃ��ł���B
(1) �V�i���I�P�@���z�w�ȑ����̏ꍇ
�@���z�w�ȂƂ͕ʂɍH�w�����Ɂu���V�X�e���H�w�ȁv�����B���z�ݔ��͓��w�Ȃ��猚�z�w�Ȃɏo�����ču�`������悢�B���w�Ȃł͌��z�w�͊T�_�Ƃ��ču�`����A�������z�ݔ��̃v���W�F�N�g�ɑg�ݍ��܂�Ă���b�I�Ȍ��z�m����K�v���\���ɑ̓����Ă���l�ނ���Ă�B����ɂ���ĂR�ŏq�ׂ��]���̉��ĕ����ɔ������_����菜���B
�@���z�w�Ȃł͏]���́u���E���E�M�E��C�E�F�v�I���z�����E�����S������̓I�ɒS������B������̒��Ɍ��z�ݔ��v���p�[�̋���E�����҂��܂ނ��ǂ��A�]���ʂ茚�z�ݔ��Ȃ������V�X�e���H�w�w���̊w�����y�o����̂����\�ł���B���̈ꕔ�͊��V�X�e���H�w��U�̑�w�@������邱�ƂɂȂ낤�B
(2)
�V�i���I�Q�@���z�w�Ȃ����w�Ȃƕ������ĐV�������n�����ꍇ
�@�Ⴆ�Ζ���ɂ����Ă͌��z�E�y���������ĐV�����Љ���H�w�ȂƂ�����w�Ȃ�����Ă���B���̂悤�ȏꍇ�͂��̌n�͂܂��ɉp��́uCivil
Engineering�v���{��ł́u�s���H�w�v�u�����H�w�v�u�Љ�i���j�H�w�v�ȂǂƌĂԂׂ��s�������̂��߂̍H�w��ΏۂƂ��邱�Ƃ��ł���͂��ł���B
�@���̏ꍇ�A�Ⴆ�Γy�i����ł́A�Љ�{�H�w�Ɖ����������j�A���z�A���V�X�e���H�w�Ƃ������w�ȂȂ����R�[�X���݂�����ׂ��ł���B�i����ł͂����ł͂Ȃ��A�Љ�{�ƌ��z�̃R�[�X�ɕʂ�A�]���ʂ茚�z�̒��Ɋ��E�ݔ��R�[�X������B���̂Ƃ̐�������������܂߂āA����͂܂��ɑ�w�̕ێ琫�̗��܂�Ƃ���ƌ����ׂ��ł��낤�B�j���p�̎d���͂��łɐs�����Ă���̂ł���ȏ�̏��������B
(3) �V�i���I�R�@���z�w�����\�z����ꍇ
�@���{�I�A�J�f�~�b�N���y�̒��Ō��z�w������������y��͊F���ɓ������B����Ƃ���Ζ��O��ς��ĎЉ�H�w�A�Љ���w�A���z�s�s�H�w�A�ȂǂƂ����������I�܂��͐V�K���̂��閼�̂łȂ���Α�w�̕ێ琫�E�卑��`�̗e�F����Ƃ���Ƃ͂Ȃ�܂��B���ɂ��̂悤�Ȍ��z�w�����������A���O�ʂ�̎s���ƒn���̂��߂̍H�w�ł���Ƃ���A���̃q���^�[�����h�ł��镗�y�͊��Ɍ���Ƃ͂��Ȃ�̑̎��ω���B�����Ă���ƍl�����邩��A�u���V�X�e���H�w�v�͂�����̒��̈�w�ȂƂ��Đ������邵�A���������ƈႤ�`���l������B���̂悤�ȋK�͂��̈���g�債�����z�w�̌n�i���Ƃ��l�[�~���O�����z�ł������Ƃ��Ă�����͑Ώۂ����z���݂̂ɗ��܂��Ă��Ă͂Ȃ�Ȃ��A���z�[�A�[�L�e�N�`���A�[���E�s�s�E���܂Ŋg�債���L���Ӗ��ɉ��߂���j�̒��ɂ����Ďn�߂āA���{�^���z���炪�ԊJ���Ƃ��ł��낤�B�������N���͈�w�����݂ɉ��������ł��낤�B���̌`�ɕt���ĐF�X�Ɛ�����痂������邱�Ƃ͉\�ł��邪�A���̂܂����ƂȂ肷����̂ł���ȏ�̌��y������悤�B
�@
�W�D�O���̓���
�@����̋��c��ɂ������āA���R�����E�n�Ӎu�t�����������ďq�ׂ���A���P�[�g�������s��ꂽ���A�M�҂Ƃ��Ă͂��̍ۊC�O���ɕt���Ē��ׂĂ������Ǝv���A���ɃA���P�[�g�����ɂ܂Ŏ��蓾�Ȃ������B�ւ��ɍŋߋC�t�������Ƃ��q�ׂĂ������B�ȉ��́A1989�N���M�҂�IEA(���ۃG�l���M�[�@��)�̌��z�E�Љ�̏ȃG�l���M�[(ECBCS)�����J������̍��ۋ��������AAnnex16(BEMS)�A17(Emulator)�A25(BOFD)�̊e���ȉ�ɓ��{���̌�����\�҂Ƃ��ĎQ���Ȃ����T�����ē����o���ƈ�ۂ���̕ł���B
(1) ���z�w�n�ւ̃G���W�j�A�����O����̎Q��
�@��ɏq�ׂ����z�Ƌ�����|�Ƃ��Ă������Ă̌��z����́A�t�Ɍ��z�Ƃ̊�����������G���W�j�A�̕s�݂Ɍ���Љ�ւ̑Ή�������ɂȂ��Ă������ƂɋC�t���B���̂��Ƃɂ��Ă͈ȑO���牢�ẴG���W�j�A�O���[�v����͂��̌��_���悭��������A���{�͗ǂ��A�Ə�ӂ������猩�ĎƁX�A�܂�����ꂽ�Ƃ���ł���B���}�Ɏ����悤�ɁAMIT(�}�T�c�[�Z�b�c�H�ȑ�w)�ł͌��z�̒��Ɍ��z�Z�p���������ݒu����ƂƂ��ɁA���̋@�d�n�w�Ȃƌ������͂��Ă���B�I�N�X�t�H�[�h��̋Z�p�Ȋw���iDept.
of Engineering Science�j���烉�t�o����ɈڐЂ������鋳���͓y�،��z�H�w�ȁiDept. of Civil & Building
Engineering�j�ɍݐЂ��Ĉ�������Annex�e�[�}�������ۑ�Ƃ��Ă���B���̂悤�Ɉꕔ�Ɍ��z�n�w�ȂɃG���W�j�A�����O���Q�����n�߂Ă���͓̂��M���ׂ��ł��낤�B
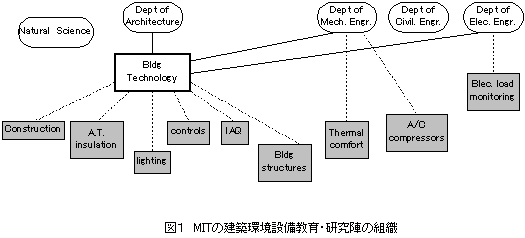
�@
(2) �H�w�̎s����
�@��Ƃ��Ėk���E�����̊����n���ɂ����ẮA�g�[�̗L�����������x�z���邽�߂ɔM�������Ƃ͌��v���������A�܂��A�g�[�E�̂��߂̃G�l���M�[�����̃G�l���M�[�헪�̌��ƂȂ�A�Ƃ������Ƃ������āA�g�[�Z�p�͗��h�Ȏs�����Ă���B�����̍����C���e���W�F���g���̔g�ɂ���ė�[�E�ɑ��ʂ̃G�l���M�[����\�z�����Ƃ��A�����̃V�X�e���̍œK���A�œK�^�c�͍��v��A�܂����ې���Ƃ��Ă��d�v�Ȉʒu���߂邱�ƂɂȂ邱�Ƃ������F���������̂ł���B�����̍��ł͐ݔ��H�w���邢�͊��V�X�e���H�w�i���̂͂��܂��܂ł��낤���j�͌��z�w�ȂƂ͕������A�������Ɨ���������E�����̈���m�����Ă��鍑�������B���̓_�ɂ��ẮA���\�A�E�h�C�c�̉e���̋���������������������ɂ���B
�����t�������Ă��������̂́A���̂悤�ȍ����炵�Ă��Ȃ��A���z�w�ɐݔ��G���W�j�A�����O���܂�����{�^�̌��z����͌`�Ƃ��Ă͗��z�I�ł���ƁA�����ΑA�]�̊�������Č���邱�Ƃ������A�Ƃ������Ƃł���B
(3) �@�d�n�����҂̎Q��
�@BEMS(Building and Energy
Management System)�ABOFD(Building Optimization and Fault
Detection/Diagnosis)��̓��I�V�~�����[�V�����̃��x���ɂȂ��Ă���ƁA���z�̓��I�����ƃV�X�e����������A���̌��ʂƂ��ẴG�l���M�[��������Ǝ����̉��K���]��(�]�������^����ꂽ�Ƃ���)�Ȃǂ́A�@�d�n�i�M�H�w�A����n���܂ށj�̌����҂ɂ͔��ɋ����[���^�V�����e�[�}�̂悤�ł���B�ޓ��̖w�ǂ͌��z����͎Ă͂��炸�A�܂����z�ݔ��̐v�o�����Ȃ��B���z�Ɠ��̂����܂����̐�����Ă͂��Ȃ��Ƃ����_�����_�ł����藘�_�Ƃ��Ȃ�B���@�_�𗝋l�߂œW�J���Ă������ɂ���͗��_�ƂȂ�A���V�X�e���ւ̉��p���̔��f�Ƃ����ǖʂŐ����ɔ��f�ł��Ȃ��Ƃ������_�������B
�@IEA-Annex�������ȉ�ɂ�����ޓ��̌����ԓx�͐^�����̂��̂ŁA��X���o���I�Ɍ��߂����Ă������ۂɖ{�i�I�Ɏ��g��ł���B����ł͉�X���z��������ҁA���邢�͋v�̌��҂Ȃ�Ώ펯�Ƃ��Ēm���Ă��邱�ƂɎ���Ђ˂��Ă���ȂǁA���ɂ͊��m�ȓ_�������ł��������A���̂悤�Ȍ������_�̒����獡�܂ŋC�t���Ȃ������V�������_�A�{���I�ɏd�v�ȉۑ�ɋC�t������A����܂ł̕s���ɑ傢�Ȃ锽�Ȃ����߂���Ƃ����̌����ƁX�ł���B
�@�Ƃ͌����A��c�����Ȃ���A�����̌������ȉ�ɂ����Ď����o���҂̏W�܂�ł�����{�̌����`�[���̖������܂��傫���A�ޓ��̕s���ӂȕ����傢�ɕ₢�L�Ӌ`�ȋ���������W�J���Ă��邱�Ƃ��t�����������Ă��������B
�@
������
�@�M�҂͂���܂łQ�P�N�̎����o���ƂP�U�N���̑�w�̋��猤����̌����A���̊ԏI�n���z�ݔ��̗��ꂩ��̏ȃG�l���M�[�E���Q�h�~�E�œK�Ǘ������Nj����A���̏I�Ղɂ�BEMS/BOFD�A�s�s�̖����p�G�l���M�[�̊��p�Ȃǂ̍��ۓI�E���ƓI�v���W�F�N�g�ɎQ������@����B�S�̂�ʂ��Đݔ��̒��Ԃɂ͌��z�n���A�܂���w���ȏオ�K�����������h�ł͂Ȃ������B����������ɂ���A�e�[�}�Ɍg��钇�ԒB�ƒ��������ɗ�����邽�߂ɂ́A�G�l���M�[�E���E�l�Ԃ̍œK������ړI�Ƃ�����V�X�e�������グ��A�ƌ����ړI�ӎ����K�v�ł������B�܂����̂��߂ɂ͂ǂ����Ă��������������㏬�g�D�ł�����E�ݔ��Ɍ������������Ȃ��B
�@���������M�҂̒��N�̑̌�����Ïk�����e�[�}���u���ݔ��H�w�̋���͔@���ɂ���ׂ����H�v�Ƃ����{���c��̎��ł���A���c��f�[�ԂƂ��č̗p���Ă������������ƂɁA�܂��i��E������������������������X�ɐS���犴�Ӑ\���グ�鎟��ł���܂��B����́A1978�N�́u�ݔ��Z�p�Җ��v�i���H�w�ψ���z�ݔ����ȉ�z�ݔ��Z�p�Җ�菬�ψ����ÃV���|�W�E���j�A1982�N�́u���z���H�w����̌���Ƃ�����v�i�������c��j�A������1991�N�́u���z���H�w�E���z�ݔ�����̌���v�i���C�x�����H�w�ψ���ݔ����ȉ��ÃV���|�W�E���j�i������������W����j���Œ�N�E���_���ꂽ�u���z�ݔ��Z�p�ґ��v�u���H�w���瑜�v�u���z�ݔ����瑜�v�̑��҂ł����W�҂ł�����B����Ƃ��ɂ�����Z�߂��u���V�X�e���H�w�̌n�v����邱�Ƃ͊����Ĕ����A���ɏ�q�̂R��̌������c��⋳�����ł̋c�_�̒��ŁA�ݔ��Z�p�Җ��Ɗ��H�w�E���z�ݔ�����ɂ��ĕM�҂����̓s�x���Ă����C���[�W�}��Z�߂čڂ��Ă��������B����Ƃ͕ʂɖ{��������������Ă��������I�J�����͂��˂Ă�����ݔ��w�̌n�̒�Ă�����Ă���B�������đ�ނƂ��A��낵���{���̓��c��W�J���Ă��������悤���肢����ƂƂ��ɁA���ꂼ��̕��̋Ɩ��̏�ł����������������Ƃ��ē��_�E�v�����d�˂Ă������������Ǝv������ł���B
�@
�}2�@���z�ݔ��Z�p�҂ƌ��z�m���x����
�}3�@���̊�{�v�f�Ɗw��
�}4�@���z�w�̗̈�
�}5�@���H�w�̗̈�ƌ��z�ݔ�
�}6�@���H�w�Ɗ��V�X�e���H�w�̗��̍\��
�}7�@���z�w�Ȃɂ�������ݔ��̋���̌n��i���É���w�E���j
�}8�@���z�w�Ȃɂ�������ݔ��̋���̌n��i���É���w�E�V�A1994�N���݁j
�@
�@
�@
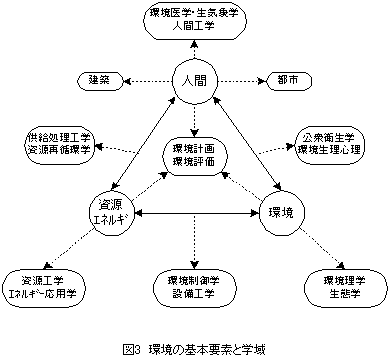
�@
�@
�@
�@
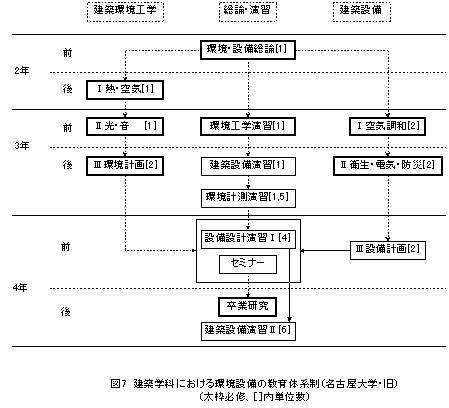
�@
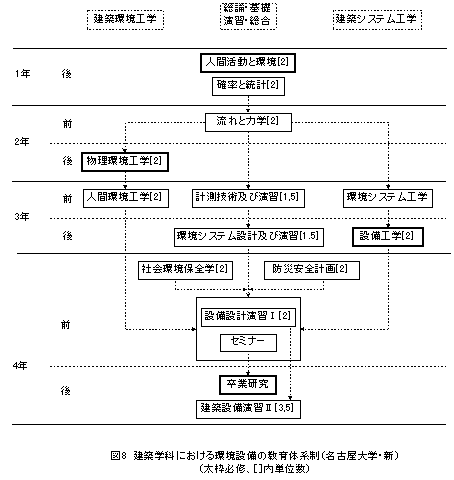
|