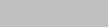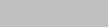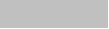2008年11月15日 名古屋市美術館
「ピカソとクレーの生きた時代」を観て
今回、ドイツのヴェストファーレン州立美術館の改修工事にあたって所蔵品
の日本での展示が出来たのだそうです。
印象としては、カンディンスキー、マン・レイ、エンルストなど普段なかなか
目にできない作品を目のあたりにして驚かされた。
画集で目にする作品と本物はまるで異なることが多く、作者の体温が作品
からは伝わってくる。
たとえ数が少なくとも、作品の選択がバラバラで展覧会として何を見せたいか
わからなくても、今回偶然目にできたのはラッキーでした。
中でも、クレーの作品群はクレー好きの僕にはなかなか見ごたえがあった。
暖かい紙色の上に乗せられた水彩絵の具の色調。線が遊ぶ、空間が
浮遊する。クレーの場合、作品の題名も素敵だ。詩的で感覚的で、作品
の中に題目をついついイメージしてしまう。
あと、なんと驚くことにドイツのシュルレアリスト「エルツェ」の作品が1点
入っていた。
以前から画集でしか見たことがなかったエルツェの作品を目の前に
して体が震えた・・・
細部への変質、奇態な形状、悪魔的な浮揚感、意識の喪失。
画集の全体的なイメージしか見ていなかった絵が、細かい線画の集積で
あり2m四方もある全画面のほんの10cm四方の一つ一つが、驚くほど
豊富なイメージの集まりであり手抜きのない心の軌跡であることに、強い
感動と自己への警鐘として本物の芸術を見た喜びを得た。
2008年10月25日
映画「パコと魔法の絵本」を観て
プロデューサのSさんに「いろいろ勉強になるから見たほうがよい」
と言われ、映画「パコと魔法の絵本」を見に行った。
先入感で子供向けの映画と思っていたので、作品の出来に少し驚いた。
窓から降り注ぐ光、明るい庭のきらきらした色、映画でありながらまるで
舞台で演技しているかのような役者たちの切れのよい演技。
それらの玉手箱の中に押し込められた、いっぱいの凝縮したイメージが
一気に爆発する面白さ!
絵本という装置・・・
二次元である絵本を捲る行為の中に、本来、二次元である絵本が時間の
感覚を見る側にあたえる。そして、その行為は毎日、毎日繰り返される。
その巧みな幻惑装置の中にいる心地よさ・・・
中島監督はCGとリアル映像の合成という技術を駆使して、映像の新しい
楽しみを演出してるそうです。観客を惹きつけるために繰り返される試行
錯誤と発見はすばらしい事だと思う。
私の作品作りは1枚の絵の中に、ひたすらイメージを塗り重ねていく行為
の中に見えてくるものがあると信じていく作業なのですが、いろんな手法を
試していく中に表現としての可能性を見つけていくのも必要なのかな・・・・
自己満足に陥らないために、この映画が教えてくれることは多いと感じた。
-日々のこと-
2008年4月29日 JR鶴舞線高架下 K.D.Japon(ケーディーハポン)
「人喰★サーカス」を観て
何が始まるんだろう・・・小さな玉手箱のような劇場には
仕掛けがいっぱい詰まっている臭いがプンプンした。
劇が始まると、信じられないぐらい一杯のイメージと人と音と
映像と曲芸が展開された。面白かった・・・
サーカスの演目で二人の女性が後ろ向きにくっ付いて踊るのが
あった。つるつるの無表情の若い娘がインド風の踊りを回転
しながら踊るシーンを見た時、奈良の寺に置かれた阿修羅の姿
を思い出した。二つの顔4本の手と足、恐らくかつて見たことも
ないイメージが目の前に展開された。
舞台の真ん中に蓋があり、突然奇怪な虫のような生物が這い出して
きた。狭い劇場であるからこそ、その生物の迫ってくる緊迫感で
ドキドキした。その穴の中に落ちていく美女・・・
老ピエロの繊細な演技には魅入られた。高らかと響く言葉で恐ろしい
人食いの過去を告げる姿は人間ではない何かを感じた。
線路下の狭い空間がこんなにも楽しい空間に変えられる演劇の
魅力に驚いた時間だった。
座長であり老ピエロ役で出演されていた原さんに劇後ご挨拶した。
劇の中での迫力のある演技をされている人とは思えない優しい
まなざしに、またお会いしたい気持を抱いて帰途についた。
2008年12月29日
プロデューサSさんとの会話
「福谷さんって、何をしたいの?」年末にプロデューサSさんに言われた。
僕の中には「好きな絵を、じっくり描けたら良い。イメージが思うままに描き出せれば満足」
だという漠然とした思いがあった。しかしその素人感覚、自己満足の水の中に甘んじている
ことの危険性についてSさんに指摘された。
誰に対してメッセージを伝えるのか?何を伝えるのか?どのように伝えるのか?
そして、その結果どうしたいのか?
時間というリスクを背負いながら、なんとなく日々を過ごしている今の自分に
警鐘をくれたSさんに感謝の思いが募った