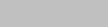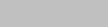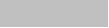2009年3月7日 【名古屋高島屋】
-日々のこと-
「エリック・カール」展を見て
先月末にエリック・カール展を見た。
アメリカの絵本作家エリック・カール展を見た。
会場はとにかく人の多さにびっくり・・・
絵本作家というだけで、こんなに注目を浴びるのかと少し驚いた。
あらかじめペイントしたティシュを動物や魚の形に切り取って
ボードの上に並べていく作風。紙を切り取るから切れのよい形が
できて、多彩な色や模様を並べられるから画面に厚みが出る。
たぶんボードの上で色々並べ直したり、取り換えたりして
見た目より時間をかけて1画面を作っているのだと思う。
彼の魅力の1つは、切り取られた形の面白さと色彩の美しさとだと思う。
絵本は基本、子供が見るもので、子供の視線と想像力がいると思う。
大人の常識や理論を持ち込んでも理解されない。
絵本作家は、そんな垣根を飛び越えた感性を持っているみたいだ。
2009年2月21日 愛知県芸術文化センター
「アンドリュー・ワイエス」展を見て
ワイエスの絵は、光と影を演ずるドラマチックな被写体であふれている。
押さえた色調、筆のタッチ、塗り残しの形状の美しさ。
裸婦でさえも例外ではない。
幻想的な作品が好きな僕にはワイエスは部外の画家と思っていた。
実際に見るワイエスの作品は、絵に塗り込められたイメージと圧倒的な筆力にため息が漏れた。
本物の作品を見るといつも言葉を失い、ため息をついて絵の前を離れる・・・
「冬や秋の風景が好きだ。死に絶えた世界の中に隠されたメッセージを感じる」
ワイエスのコメントがあった。
画面の真ん中にひかれた水平線に向かう一本の道。
真冬の野原には汚れた雪と枯れた草が覆う。どんよりとした空には粉雪が舞う。
ただそれだけの道具立てなのに、画面からは恐ろしいほどの緊張感が漂っていた。
隅々まで描き尽くされた物達は僕を画面の中に引きずり込み、
凍てつく大地の死と生のダイナミックな律動の中に置き去りにする。
ワイエスのメッセージは、間違いなく僕を刺激し、虜にしたようだ。
2009年4月27日 JR鶴舞線高架下 K.D.Japon(ケーディーハポン)
芝居「草枕」を見て
一年ぶりにハポン劇場を訪ねた。今日は雨の中一番乗りで、
二階席の一番良い席(自称)を確保してワクワクしながら開幕を待った。
この芝居「草枕」は、夏目漱石の名作を、
原さん自身の脚本と演出で描く、まったく別の新しい「草枕」だそうだ。
画家が漱石と話すシーンから始まる。
原さん演じる画家は、帽子を冠った全身黒ずくめでもあり無表情。
その陰が極彩色の幻想者たちを引き立てる。
僕は、ポール・デルボウの絵の中に現れる、裸の女性のそばに立つ
黒ずくめの紳士を思い出した。見事な相関図だ。
画家は農家の庭先で老婆と二匹の鶏と出会う。
鶏の演技は実に見事で、全身真白な中に黒い瞳だけが奇妙に強く観客を見返す。
鶏の不思議な踊りを見ているうちにしだいに幻想の世界に引きずり込まれる。
そこに乱入する馬!なんと実物大の馬が狭いハポン劇場に乱入したのだ。
観客を一気に劇に巻き込む心憎い演出だ!
床屋では大きな剃刀をもったヒステリックな女が客の顔を剃刀で切り裂く。
泣き叫ぶ少年。そして現れるキョンシーみたいな服装の4人の少女達。
私はその奇妙な、不思議な踊りにまたもや魅入られてしまった!
なんと4人の少女は同じ顔のマスクをしていた。
その可愛らしくも恐ろしい踊り!人では無く、機械でも無く、霊的な感覚。
前回の「人喰☆サーカス」も、二人の少女が背中合わせに踊るシーンに
魅入られてしまったように、僕は今回も原さんの仕掛けに夢中にさせられた。
心の中で思わず拍手した。またやられたって(笑)
そして温泉の宴会シーンへ。明るく、魅惑的で刺激的なシーンが展開していった.....。
原さんのしなやかな動きが素敵だ。
画家はまるで夢をみているような、水の中を泳いでいるシーンを展開する。
右の壁には水の流れや、花や、鶏や、漢字の羅列による映像が映し出される。
そして響きわたる幻想的な音楽.....。
見ている自分がまるでどこにいるかわからなくなる浮遊感に襲われる。
狭いハポン劇場まるで母の胎内のような空間になる。
終了後、原さんに挨拶をした。よく通る声と、柔らかい笑顔で迎え入れてくれた。
この笑顔に会いたい為に通う人もいると思う。
いつまでも元気で、また不思議な幻想をみせてください!と祈りつつ劇場を後にした。
2009年8月14日 奈良・新薬師寺を訪ねて
国宝「阿修羅像」が全国を巡回していると聞いた。
私が初めて「阿修羅像」に出会ったのは、3年ほど前の奈良旅行である。
もちろんそれ以前にも興福寺には参拝しているのだが、意識に止めたのは
その時が初めてだった。
興福寺の展覧はもちろんガラス張りで、正面からの拝謁であった。
像を見ているうちに「この像を依頼された仏師は、何をイメージし、
どう作意し、何を迷ったのだろうか・・・」の思いに囚われて、30分ほど
像の前に立ち尽くしていた。
顔は無垢な少年というより、眉をひそめる表情は恋に嫉妬する少女の感じがある。
微妙に異なる表情の顔が横に3つ・・・真横ではなく左右が少し上にある。
それによって正面から見た時のまとまり感がある。
少年ような華奢な胸の横には6本の細い腕が生える。腕というよりはまるで光背の
ような、像をつつむ炎のような、軽やかな動きを感じさせる。
なんという巧妙な作意・・・仏師はこの形と位置を決めるためにどれほど迷っただろう
か・・・ため息が出た。
一人の人間の作り出した像が、数百年たった今も見るものを魅了しつづけている。
物づくりをする人間の、はしくれとして羨ましく思った。
2009年8月 2日 「阿修羅展」に添えて
お盆休みを利用して奈良の仏閣を訪ねた。
この暑い時期の参拝は結構好きである。強い日差しの中をバス停から
続く坂道をゆっくり登っていくと、古くてわりと質素なたたずまいの
新薬師寺の門があった。
真っ暗な本堂をくぐると薬師如来の姿を拝する。蝉の声がうるさい
くらい本堂に入ってくるが、僕は薬師如来のリアルな姿に圧倒され
てすべてを忘れてしまう。
特に右腕の柔らかな表情に驚かされた。組み木を彫りあげで作られて
いるそうだが、肘から持ち上げた腕の角度と広げる手の柔らかい傾き
になんともいえないリアルな表情がある。
正面に向かうと薬師如来と目が合う。何か睨まれている気になり思わず
合掌する。30円払って蝋燭を買いバサラ神将に捧げた。
新薬師寺を訪ねたのは初めてである。最近は日本の美しい国宝をもっと
知りたい気持ちになっている。
2009年9月20日 東京を訪ねて
先日、テレビで爆笑問題というタレントグループが東京芸大のキャンパスを訪ねて、
学生と語り合うという番組があった。和気あいあいとした学生たちに、タレントが
芸術大学の存在価値を問う質問をぶつける。しかし学生たちや教授達の答えはあま
りにもあいまいで、軽くて、とても討論というものでなく、見るものに失望を感じ
させる内容だった。
なぜ教授たちは学生に情報武装をさせないのか?自分たちの社会的価値についても
っと教えないのか?
しどろもどろの学生を見てとても可愛そうに思った・・・
先日東京に旅行して、いくつかの美術館や画廊を周った。
最初に訪れた東京オペラシティで開催されていた鴻池朋子の個展は増幅するイメー
ジをオーソドックスな手書きの表現で丹念に描きとめていた。
澁澤龍彦の小説の挿絵も描いているようで、映画的な総合的表現手法が魅力的だっ
た。
次に訪れた青木画廊の「小石サダオ」展では超細密画の世界に引き込まれた。
8号ほどの小作品の中に多くの物達が凝縮されていた。
執拗な表現へこだわりとテクニックには脱帽させられた。
最後に訪れたのは文化村ギャラリーの「ベルギー幻想絵画」展。
幻想絵画の名前に惹かれて訪れたが、作品の量、質ともに中途半端で今一開催者の
熱意を感じない展覧会で少しがっかりした。
街中にいると、さまざまな価値や、考え方に出会います。
何が価値があるとか無いとかわからなくなってしまうけど、その迷いを感じる事と、
迷いの中から自分の表現したい事を見つけていく作業自体が大事なのかと改めて思う。
芸術を行う若い人たちが、周りの声に惑わされず作品作りを続けてもらいたいと思
った。
2009年11月29日 今池ガスホール 「第2回 三匹の芸人」
2009年12月19日 西尾劇場 「ダンス・タンス・ダンス」
今回の原さんの舞台は「西尾劇場」。
駅から見えるトタンに覆われた建物は不思議な存在感を感じ、ドキッとした。
この劇場は昭和15年に建築された建物で、映画のロケ地にもなったとか。
チケットをもぎりされ、少し暗い入口に入ると、そこはまさに昭和初期!
レトロな物がいっぱい並べられた通路は、小さい頃よく行った駄菓子屋のようだ。
今は映画館になっているという劇場に着席し、わくわくしながら開演を待つ。
劇場自体はそれほど広くはないのだが、それがちょうど良い広さなのだと
わかったのは劇が始まってからだった。
演劇者の生声が、劇場のすみずみにまで響きわたるのだ。
やがて暗くなり、劇が始まる。
跡地にひっそりと存在している老婆。
その老婆が、子供たちに語り継ぐ物語の設定。
きらめく踊りと歌と講談が鮮やかに蘇る。
当時の大衆娯楽演芸はこんな風だったのだろうか・・・
インド風の妖艶でアクロバティックなダンスの面白さ、
なんと玉乗りまで登場する!
セクシーな歌声で高らかと歌い上げる歌手!
全般に流れる昭和ノスタルジーの空気がとっても居心地が良かった。
鹿が狭い廃屋に置かれたタンスの中から、ゾロゾロと出てくる不思議な
感覚は、いつもながらドキドキさせられる(笑)
ラインダンスも見ごたえあった。
原さんは、全ての素材を吸収した後、イメージの塊を観客にぶつけてくる。
ゴミでも、宝でも、愛でも、憎しみでも、戦争さえも・・・
あっという間に、西尾劇場さえも取りこんでしまった。
原さんいわく、 今回はダンス中心のヨーロッパ公演以来の冒険したとのこと。
なんと出演者も80名にのぼるとの事。圧巻の迫力でした。
鶴舞の狭い空間で展開される玉手箱のような感覚も好きだけど、
西尾劇場のノスタルジーの中で展開される感覚も大好きです。
こんな素敵な時間をくれた原さんに感謝です。
11月29日にSさんに誘われて「三匹の芸人」を見に行った。
今池ガスホールで開催されたのは、
原智彦さん、六柳庵やそさん、安藤俊子さん、の三人の芸人による独演会。
原さんの「カマキリ」は、狭い劇場で見る
ドキドキした、それでいて面白い舞台とは一味違ったエキセントリックな演出。
二つのアメーバーのようなものが、地面を這いながら登場。
奇妙な動きの中に、何かを暗示させるようなパフォーマンスを展開。
何か現代舞踊のような不思議な感覚を覚えた。
けっして娯楽的な楽しむだけでない表現は、
原さんの中には今の状態に満足しない、
より深い表現を求める精神があるのを感じて、深い感銘を受けた。
やそすけさんは、独特の語り口による長唄が魅力的だった。
ボロンボロンと爪弾く三味線の音は、広い会場を一瞬で違う空間に
変えてしまうような力にあふれていた。
安藤さんは車椅子に乗って登場した。自分の祖母に話かけられている
ような、優しくて、ワクワクするお話に魅入られた。
「綿菓子」とは安藤俊子自身の老人ホームでの体験談として語られる。
強い個性の三人の演目。
「三人」ではなく「三匹」というこだわり。
感覚的・動物的で本能を刺激されるようだった。
とても楽しい時間だった。
2009年12月23日 松坂屋美術館「ベルギー王立美術館展コレクション」展
松坂屋美術館で、「ベルギー王立美術館展コレクション」展を見た。
全般的には、有名、無名を取り混ぜた美術展だった。
しかし、一枚の絵にとても惹きつけられた。
ジェームス・アンソールの「バラの花」である。
アンソールといえば19世紀初頭に活躍した画家で、仮面をつけた
群衆が、街いっぱいに溢れる奇妙な幻想画が有名なベルギーを
代表する画家である。
決して暗い画面ではないが、異様な感覚の絵が多い。
この絵のモチーフは、バラの花と花瓶だけでありながら、
なぜ、こんなに惹きつけられるのだろうか・・・
地のピンク色を塗りかぶすような、白い絵の具の厚みの異常さ。
花弁の少し鮮度を落とした赤い色。
花弁を包む線は、形をたどるラインではなくて、記憶をたどるような
確認作業を感じさせる。
絵を描く行為は、単に形を描くこと意外に画家が体験し、網膜に焼き付け
た光景の表出である。
画家が絵に塗りこめたのは何だったのか・・・
後ろ髪を引かれる思いを残して、絵の前を離れた。