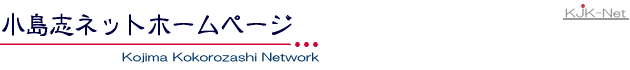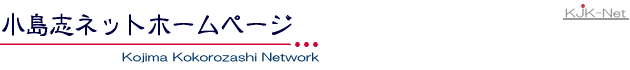■「五感を活かし、手で考える−大学教育再生の道−」 (2008.1)
北海道大学名誉教授 米山 喜久治先生よりの論稿 |
米山 喜久治(北海道大学名誉教授)先生は、大学紛争の盛んだった時期に東京工業大学大学院に在籍された当時同大学教授であった川喜多二郎先生の薫陶を受け、KJ法を学びました。川喜多教授は東京工業大学や文部省大学政策を批判し、あるべき大学を探求して「移動大学」を試みましたが、若き米山先生もこれに参画された経験をお持ちです。その後、博士課程を終えて工学博士として大学で教鞭を執られ、北海道大学経済学部経営学科教授に招聘され、この春、28年お勤めになった北大大学院経済研究科教授を定年退官されました。
国立大学の独立行政法人化や大学全入時代を迎えて、混迷の中にあるわが国の大学はどうしたら再生出来るのか、大学改革のポイントについて、この間の研究・教育の経験を振りかえって、「大学教育再生の道」についての論稿をお願いしました。題して、「五感を活かして、手で考える−大学教育再生の道−」
お読みになったら、ご感想やご意見をお寄せ下さい。(山本 克郎)
大学教育は、偏差値、資格、マニュアル思考で空洞化しています。再生の道は、学生の原体験、原風景を基礎とすること。異質の交流により教室を「現場」に転換して、五感を活かし、手で考えて、作品を創り続けることです。
1. 経済成長と進学率の上昇
敗戦の廃墟から復興して、高度経済成長を達成した日本では家計に教育費支出の余裕が生まれました。高校進学率は、1955年51.2%、1975年91.1%、2005年には97.6%となってほぼ全員が学ぶほどに普及しました。優秀な工業高校の卒業生が、日本の工業製品の「安かろう、悪かろう」から「メイド・イン・ジャパン」は世界最高水準の品質評価とイメージの確立に大きく貢献しました。最近この世代の熟練者の定年退職により、技術・技能の伝承が、日本産業の緊急課題となっています。リストラで熟練者の育成が、二の次にされてシステムとマニュアルの整備ばかりに投資されてきたマイナスの結果なのです。
経済成長とともに産業構造が、第1次(農林水産業)から、第2次(製造業、建設業)へ、さらには第3次(商業、金融、サービス等)へとその比重が大きく変化しました。これは、自営業者の減少と被雇用者の増大、つまりサラリーマン化の進展を意味しています。主として第3次産業化が、誘因となって大学・短大進学率を1960年の17.2%から1995年に45.2%、2006年には51.5%(70万3191人)へと引き上げたのです。高学歴化とは、中卒労働市場に高卒者が進出し、高卒労働市場に大学・短大卒者が進出することです。中卒者に続いて高卒者の就職難が、巻き起ったのです。
こうして今日の大学は、学費の経済的負担に耐えられる平均的な家庭の子弟が、「こんなことを勉強したい」(知的好奇心)を動機とするのではなく、「学歴」、「資格」あるいは単にまだ社会に出たくない「モラトリアム」を理由に集る所になっています。大学から学問をするという雰囲気が、完全に消えてしまい、「就職予備校」「資格試験予備校」へと質的に変化しました。今では誰も「レジャーランド」と揶揄しなくなりました。
2.偏差値思考
日本人は、明治以来の欧米先進国崇拝と敗戦の経験が重なって近代科学の「客観性」=「善」とする信仰にも似た思いを持つようになったのではないでしょうか。こうした思いが、不用意にも学校教育に工業製品の生産管理手法である統計的品質管理を応用する道を、歩ませたのではないでしょうか。従来受験業界がやっていた大学入試の全国模擬試験を文部省が取り上げて、1979年に第1回共通1次試験を実施したのです。生徒の諸能力を、ペーパーテストの成績(偏差値)という単一の評価尺度で判定するシステムが、制度化されたのです。相対評価重視と質的側面の評価を削除した大学受験用のシステムが、社会的に大きな影響を及ぼしたのです。この点については、試験が実施される以前に既に川上正光元東京工業大学学長によって「独創力の養成を強調する立場からいえば、まさに共通一次試験は国を害するもの」として厳しく批判されていたものでありました。(川上正光『科学と独創』(p.154。
1979年朝倉書店刊)官僚機構が、重大な社会制度の設計と運用に関して正確な状況判断と意思決定の主体すなわち責任の所在を明確にしないまま惰性でことを運ぶ通弊が、存在します。無謀な太平洋戦争への突入の例を持ち出すまでもありませんが、再びこの無責任な惰性が、日本の高等教育を、破壊することになったのです。
日本人は人間を評価する軸と尺度を、「試験の成績」と「学歴」に単純化してしまったのです。現場の多様な経験によって磨かれた能力=「現場の知」が、無視されて、現場と直接関係のない「試験の成績」や「学歴」さらには「資格」などの「情報」で能力を評価するようになってしまったのです。また学校で習う一般理論を理解する能力は、単なる情報操作の能力であって、具体的なモノを創る能力ではないという認識を、欠落させてしまったのです。
分業が高度に進んだ現代社会では多様な職業はそれにふさわしい能力を必要とし、「適性」がその能力修得の基礎となっています。これはプロの職業人の誰もが、明白に実感をもって理解していることです。しかしこの認識が、地域に根ざした生活と具体的なものから遊離した断片的「情報」によって攪乱され、希薄になってしまったのです。
大学入試における「偏差値」は将来のサラリーマン的職業生活につながる関門の通行手形となるため、単に試験の成績を示す以上の意味が、付加されるようになりました。この「偏差値」効果は、日本人に試験で測定され、数値化されたものだけが評価して信頼できるという錯覚を、強固に植えつけたのでした。言葉や文字、数値で説明されなくても直接自然やモノに触れるやり取りの中から具体的な作品を、創り出す手と行動力こそが最も重要な能力であることが、忘れられたのです。
有名ブランドの3C(カー、クーラー、カラーテレビ)などの大量生産工業製品の職住分離の都市生活への普及も大きな影響を与えました。地域社会の伝統的な生活スタイルを支えた手作り少量生産品が、公団の集合住宅を先頭にして捨てられると同時にそれが持つ機能や価値も忘れられてしまいました。地域社会において作り手と使い手の顔と顔の関係の中で「技」とその基盤となる「適性」を暗黙のうちに評価したモノと場が消え去ってしまったのです。
「偏差値」中毒ともいうべき〔高い偏差値=万能〕とする錯覚に惑わされて、学生・生徒の能力評価基準から「適性」を外してしまったことが、今日の学校教育の根本的問題の1つだと思われます。適性を見抜くためには、まず両親や家族が、子供に「目をかけ」、「声をかけ」、「手をかける」ことが必要です。家庭教育の外注化である「塾」は、適性を除外した「ペーパーテストの成績」によって子供を評価します。こうして家庭からもその子供を見つめ、適性(何を得意とするか)を評価することが、なくなったのです。
3.大衆化、世俗化、情報化、知識の断片化と大学
日本の高等教育は、2005年度に大学数726校、短大数488校、教員数も17万3650人になるまで量的拡大が進みました。少子化で予想されていた「大学全入」が2007年には現実のものとなりました。大学・短大進学率は、50%を超えたのですが、全体で約3割の私大160校に定員割れが起っています。北海道では、既に学生の確保が出来ない2大学が、撤退しており、2短大も閉校を予告しています。受験者総数の激減に対して大学は、その経営を維持するために定員確保を優先させて、その結果低学力者を入学させることになりました。高校レベルの基礎学力を持たず、進学の目的も定かでないまま入学した学生に高校教師OBや予備校の協力を得て補修授業が、行われています。大学とは名ばかりでその内実は、高校レベルの基礎知識の確実な修得に終始しているのです。やっと少し進んだと思うと大学3年生から開始される就職活動(企業訪問、企業説明会への参加等)が、優先されて、学生の講義やゼミナールへの出席の機会が奪われてしまうのです。こうして大学は、就職予備校、資格試験予備校のような雰囲気に支配される場になってしまいました。
大学院学生数が欧米諸国に比較して、少ないという統計資料に基づき、文部省主導で1990年以降大学院重点化が、進められてきました。しかし大学院修了者の将来の職業生活に関しては、真剣な検討がなされることはなく、全て自己責任に帰されたのでした。大学院定員の大幅拡大で、学部レベルの基礎学力を欠いた者、最も重要な知的好奇心(問題意識)の希薄な者が大量に入学することになりました。大学院には、「学歴病」と「モラトリアム病」の合併症患者が「入院」し、挙句の果てには、「自分は何を研究したいのか分からないが、研究者になりたい」という者まで、「入院」するところに成り果ててしまったのです。
これでは文部省が目標に掲げた「高度専門家の育成」を、達成することは不可能です。
「鉄は赤きうちに打て」の原則に従って成長の各段階で基礎を着実に習得する教育を行って、個人と社会全体の損失を防ぐべきであります。問題を先送りしても、誰もその責任を取ってくれません。最後は全て自分の全人生をかけて支払わざるをえないのです。21世紀に入り地球環境の悪化が進み、過密過疎、少子高齢化、財政赤字の累積等国内、国際的に難問が、山積しております。大学に進んだ若い人々が、適切な指導を受けることなくその才能を、開花させ得ずに朽ち果てていくのは、民族の悲劇です。そればかりでなく、人類にとっても計り知れない損失であると思います。無責任な三流評論を繰り返して、このまま手をこまねいておれば、日本の社会は、衰退から滅亡への道を、転がり落ちていくのは必定であります。
太平洋戦争の敗戦の廃墟の中から立ち上がり、復興をとげ、さらに高度経済成長を達成した日本は、社会が大きく変質したことを、自覚する必要があります。特に1990年代以降の技術革新による情報技術(IT)の進展は、情報ネットワークの構築による企業の生産、流通、販売活動の有機的結合度を高めただけでなく、国民1人1人の生活に広く、深く影響を与えています。
現代の学生はハイテク・情報化時代に生きており、中学、高校時代にTVを超えてゲームやケータイが大きく浸透する情報空間に育ってきたのでした。電子媒体の情報に触れる時間が、圧倒的に長くなり、大学入学までの読書が、「教科書」と「受験参考書」に限られるほど狭いものになっています。自分の知的関心に従って読書する精神的、時間的余裕がなく読書習慣が未形成なのです。このため自分の「知的好奇心」を基に学習活動が出来ないのです。大学の授業で推薦された参考文献はもちろん指定された教科書すら自分から進んで読めない学生が急増しています。瞬時に変化する「仮想現実」に浸る現代学生にとっては、情報の鮮度が大事なのです。書籍は単に古い情報の詰まった「モノ」であり、消耗品に過ぎないのです。その中に人類の知恵が、凝集されているという認識は、極めて希薄であるといえましょう。
他方大学における研究にも問題があります。自然や社会や人間の「全体」に対する関心を失って、特定の部分の「分析」に主力を注ぐ専門化、細分化が進んでいます。「知識の断片化」が、幾何級数的に増大する「情報量」とリンクして進み、異専門間のコミュニケーションが成立せず、相互理解が、困難になっています。
ヨーロッパ中世における発足以来大学は、書籍を手がかりにした対話による「思索」を存立基盤としてきました。しかし現代の大学は、「大衆化」、「情報化」、「世俗化」の波に沈みつつあり、加えて「知識の断片化」が、衝撃波となって「大学の知」の根幹を揺るがしています。このため大学の社会的使命である人類の知的遺産の継承も機能不全になっています。
財政赤字のため教育予算が削減されています。さらに文部科学省によって競争的外部資金の導入政策が、推進されています。貧弱な教育基盤(教室、演習・実習室、実験室、図書館、体育館、食堂等)の改善や基本的教育への予算配分は、顧みられることがありません。大学の知的基盤は、図書館にあると言っても過言ではありませんが、経営難にあって文献、資料の購入予算は、削減されています。国立大学の独立行政法人化を契機として大学の再編成、リストラが進みつつあります。大学教員は
“大学改革”と日常業務、教育、研究業績達成に追われて精神的、身体的に荒廃しつつあります。特に外部からの競争的資金の獲得に多大のエネルギーと時間を、奪われ、地道な日々の教育活動に投入すべき余力を、失っているといえましょう。
独創的な研究を推進するための「アイデアを発想する力と構想力」の劣化、「若い学生諸君の心に響く教育」を行うための「人間性」の貧困化こそが、現代日本の大学の危機の本質であります。
留学生受け入れ10万人の量的目標は、達成しました。しかし留学生は、所属する大学で知的な刺激を受けることが出来ないばかりか、日本人の友人を、作ることも出来ずに失望して帰国して行くのが、現実の姿です。国境を越えて多様な社会的部門間の重層的な交流を進める「国際化」の基盤は、あくまでも豊かな人間性を持った個人なのです。学生時代に留学生との友人関係を、形成できない若い日本人の担う「国際化」は、どのようなものが、可能なのか考えなければなりません。
以上のように現代日本の大学は、何重にも困難な状況にあります。しかし大学には「世界に開かれた公共空間」として異質の交流を通して知的生産を行い新しい価値を創造し、志高き有為の人材の育成を以って社会に貢献すべき使命が与えられています。大学には何らかの形で税金が投入されおり、その実現には社会的責任が、存在しているのです。
4.人間教育を核にした新しい大学教育のモデル
21世紀の日本は、IT技術が深く関与する高度科学技術都市文明の中にあります。環境問題、エネルギー問題、食料問題などに加えて明治以降初めて人口が減少に転じ、急速な少子高齢化、過疎・過密化が進んでいます。また人間性の荒廃など世界最先端というべき問題に直面しています。このような「先端的諸問題」の解決は、人類史的なパイオニアワークへの挑戦です。大学は、問題解決の理念、方法、具体策に関する情報受発信のキーステーションの機能を持つべきであります。情報を発信して世界の関係者間の情報共有化によって、問題解決への取り組みに貢献することが可能となります。それは新しい人類の知的資産の創造を意味しています。
明治維新以来欧米先進諸国に「追いつき追い越せ」を国是とした懸命の努力によるキャッチアップの過程で欧米崇拝後進国型思考が日本人の習い性となってしまいました。まず自分が直面する問題の正確な把握を試みる前にその目的も明確でないまま先進国の理論や事例を調べる思考方法が、染み付いているのです。教育もまたこうした思考様式に縛られております。各自の潜在能力を開発し、その独創性を十全に発揮させるには、先進国模倣優先の思考様式からの脱却が必要なのです。状況(現場)から五感を活かして問題を発見し、その問題の解決に人類の知的遺産を活用し、新しいアイデアを生み出して正攻法で取り組むことが重要です。このような知的能力と勇気と責任倫理を持った人物の養成こそが、大学教育の社会的使命であります。創造性の泉は、外国発の理論ではなく足元にあることを肝に銘じるべきでありましょう
英語のエデュケーション(Education)は、ドイツ語のエアツィーウング(Erziehung)に起源を、持つといわれる。ドイツ語ではもともと、「引き出す」という意味を持っており、これは、その人の持つ潜在能力を引き出す、つまり「育成」を意味しています。
一方中国では、「教」は、「上から下におしえる」ことを意味しており、「教育」とは、「教えて、おこないの正しい人にし、知識を授け、感情を豊かにし、からだを健康にする」ことを、意味しています。(『角川漢和中辞典』 p.461、1959年角川書店刊)
日本は、漢字の受容以来、大宝律令に代表されるように中国の文物の強い影響を受けてきました。長い歴史を経て土着のものとの融合が起こり「日本的な教え、学ぶやりとり」は、江戸時代の寺子屋の「読み、書き、そろばん」に凝集しているように思われます。四書五経等の中国の古典の素読に始まって、師から教示されるその「解釈」を、暗記することが、原型となっています。生徒が素朴な疑問を持つことから始まり、批判に至る思考回路は、遮断されています。「三歩下がって師の影を踏まず」と言われるように生徒にとって師は、批判を超えたものとして、無条件に従うものとされていました。正確な記憶力と礼儀作法だけが、評価されたといえましょう。世俗的価値を重視する「そろばん」に代表される「実技」は、古典解釈の理論からは、全く切り離されていたのでした。
生徒は、師の考えを教え込む対象として位置づけられており、その人間的存在、主体性は、認められておりません。これでは、生徒は師の忠実なコピーになることが、出来ても自らの人生を切り開いていく能力を、開発することは、出来ません。封建的身分制度の中にあって「分をわきまえる」ことが、重視されるばかりでありました。生徒に古典の新しい解釈を、促してそれを実生活で検証し、発展させいくことを、教えるものではありませんでした。明治の文明開化に至るまで日本には、寺子屋や藩校、武士のエリート教育機関であった江戸幕府の昌平坂の学問所で行われた「教育」には、生徒の能力や可能性を、引き出すという基本的な考えは、存在していなかったといえましょう。
幕末大阪で緒方洪庵が主宰した私塾「適塾」には、塾生相互の切磋琢磨によって「能力開発」が、行われました。その結果は多くの人材を輩出したことによって歴史的に証明されています。適塾の集団学習の方法について注目する必要が、あると思われます。(福沢諭吉『福翁自伝』岩波文庫)
こうした社会風土、生活世界を持つ明治初年の日本社会に文明開化によって西洋文物が、奔流となって押し寄せたのでした。富国強兵、殖産興業を実現するためには、それを担う人材を育成するための近代学校制度の創設が、計画されました。“欧米先進諸国”の制度や教科書、教材が、研究されたのですが、もちろんアメリカやイギリスの研究も進められました。日本人は、この時初めて本格的に英語の”Education”という言葉に取り組むことになったのでした。英語の“Education”に対応する日本語を、作らなければなりませんが、既に存在していた「教育」ということばを、対応させたのでした。これは川上正光氏が、指摘するように重大な誤訳というほかは、ありませんでした。(川上正光『独創の精神』p.15
共立出版1978年刊)
明治以来100年以上もこの誤訳に誰も気がつかなかったのです。そこには日本が“欧米先進諸国”を、モデルに「追いつき追い越せ」つまりキャッチアップに邁進する時代の歴史的制約が、ありました。幕末期1850年代に江戸幕府は、フランス政府の協力を得て横須賀造船所を建設しました。この造船所の技術指導の場では、就業規則に「職工ハ業務ヲ執ルニ当リ百事工事課長及頭目ノ指示ニ従ヒ以テ仏工ノ技能ヲ見習ベシ、決シテ自己ノ意見ヲ述べ又ハ他人ノ指示ヲ受クルベカラズ」と定められました。日本人職工は、フランス人技術者、熟練工の指示に対して無条件に従い自分の意見を述べることを、禁じられていたのでした。(『横須賀海軍船廠史』p.7
原本大正4年刊)
ひたすら先進諸国から技術導入を行い、その現場適用により、大きな成果を上げることが、出来ました。1970年代末日本は、先進工業国アメリカ、ドイツ、イギリスと肩を並べるまでに成長したのでした。明治の建国以来の目標が、達成され、鉄鋼業のように量的にも質的にも世界最高水準に到達しえた産業が、登場したのでした。導入すべき技術が、なくなりフロントランナーになって逆風を受けながら走らなければならない段階になって、初めて自らの独創性を、反省する必要に迫られたのでした。
近代日本における先進国からの技術導入の嚆矢となった横須賀造船所において日本人は、自分の意見を述べることを禁じられました。この事は、長く先進国からの技術導入の場面における日本人の思考と行動を縛ることになりました。加えて「三歩下がって師の影を踏まず」という美風が、結合して、日本人は、自らの意見を言葉にして発するのではなく現場でひたすら手を動かして改善工夫を重ね一生懸命働く道をたどったのでした。
高度経済成長の坂を上り詰めた日本を、待っていたのは、国民的な試練でありました。1973年の第1次、1978年の第2次オイルショックと公害による深刻な環境破壊、地域住民の健康破壊が、起こったのでした。これは四大公害裁判として生産力拡大を自己目的にした産業活動のあり方を根底から問うものでありました。多くの犠牲の上にやっと産業界は、重い腰を上げて投資を行いました。こうして科学者、技術者の奮闘により省エネルギー技術、公害防止技術の研究開発が行われて、問題解決が進められたのでした。世界に例を見ない深刻な公害問題の解決は、自らの知恵を出して具体的解決策を開発するしか道がないことに直面して、自らの創造性の欠如を、思い知ることになったといえましょう。1970年代に川上正光氏が、日本人の創造性の欠如に思い至り、その原因として100年にわたり日本人を縛ってきた学校教育の欠陥が、そもそも「教育」という概念にあることを、突き止めたのでした。生徒・学生の潜在能力を、引き出すという英語のエデュケーションに対応する日本語として「啓発教育」つめて「啓育」を、当てるべきであると提案しています。
新しい創造性開発こそ「啓発教育」の中核をなすものといえましょう。
21世紀の困難な地球時代に高き志を持って生きる人材を、育成するためには、まさにこの「啓発教育」=「啓育」を、行うのでなければなりません。
一期一会の場において多様な知的人間的刺激を与えて、知的好奇心を活性化させること。自然や素材、なまのもの(人間の体も自然に直接触れて五感と直観の力を、研ぎ澄まして、問題発見、問題形成、問題解決能力を開発して人間性を解放することが重要です。標準的知識の伝達を目的とする教育(ティーチング、teaching)、さらにスポーツや自動車運転などのように必要とされる一定の技能(スキル)を習得させる「訓練」(トレーニング、training)とも違っていることにもっと注意を払うべきであります。
大学における啓発教育は、第1図に示すように「専門教育」、「教養教育」さらにその存在が明確に認識されていない「探究学(知的生産の技術)教育」によって構成されています。三角形の各頂点に位置づけられる知識の諸領域に関する教育に加えてその中心に位置して「核」となるのが、「人間教育」です。多様な刺激を与えて学生が自らの人生における志を立てること及び人間的な成長を促すことです。これは単なる知識や技術の伝達によっては不可能です。学ぶ者が、自らの五感と直観を働かせて身体感覚をもって感得しうるような場における一期一会の出会いを通して初めて可能となるものです。
「教養」とは、問題の重層的、多面的、多角的な把握に不可欠な基軸となる基礎的知識です。問題の全体像を把握し、解決する構想力を支える知的能力こそ「教養」というべきものです。この4つの領域の統合によって「啓発教育」を、目指すべきであると考えます。
次に「知的好奇心」に従って設定した課題に焦点を合わせながら自ら現場に立って自然やナマのもの、当事者に直接触れることが、現実の問題解決の第一歩です。そこから五感を活かして観察、観測、調査、実験によってデータを作成することが、必要です。そしてオリジナル・データを核にして関連する人類の知識遺産と知恵を組み立て、統合しなければなりません。専門化、細分化、断片化された知識を組み立て、統合して、創造的な一仕事を達成するための方法論が、探究学(知的生産の方法)なのです。モデルを導入し模倣・現場適用するのが技術移転の本質であるとすれば、自主技術開発、新しいモデルの開発と構築能力は創造性そのものであるといえましょう。
現代日本の大学の「教育」は、学生の能力開発には全く不十分であり、標準的知識の記憶のレベルをペーパーテストで評価するに留まっています。これは、習得した技能(スキル)を、実際に使えるレベルまで習得させる「訓練」(トレーニング)にもなっていないことは、明らかであります。
標準的教科書に記載された知識、技術を講義によって伝達し、ペーパーテストで記憶度を評価して「単位」が認定されます。そして所定の単位数を取得すれば「卒業」が認定されます。しかしこのような講義は、1つの問題に唯一の正解が、存在するという「単一正解思考」を助長することになります。混沌の中にある問題には、多様な解き方と複数の解が存在することを、身体感覚を持って体得することが、肝要なのです。
「知識」を「マニュアル」に従って事象に当てはめるだけの思考力では、混迷する21世紀に職業人としてまた一市民として生きてゆくことは、困難です。近年「七・五・三問題」といわれるように新規卒業者が、就職後3年以内に30%も転職する状況が続いています。学生は、3年生になると就職活動を開始するため、講義・ゼミナール等への出席の機会が奪われ、貴重な時間と経費が犠牲となります。莫大なエネルギーと時間とコストをかけた就職活動で得られた就業機会も、「自分の個性に合った仕事=青い鳥」を見つけるためには、簡単に放棄されてしまうのです。もちろん企業の職場環境や労働条件が、期待を外れて劣悪で耐え難い面も多々存在するでありましょう。だがそれは学生時代現場に直接触れて自分の五感を活かして現実の企業と仕事に関するリアルな認識を獲得することが出来なかった結果ではないでしょうか。チャンスを生かして、1つの職務に習熟することから、次のステップへの新しい可能性が開かれるのです。これが職業生活の基本であることに変化は、ありません。リアルな認識の欠如と自己への過信が、不用意な転職に向かわせるのではないでしょうか。企業は、基礎学力もなく社会性に乏しく、他人とコミュニケーションも出来ない人を、大卒の人材とは認めていないのです。
5.教室を「現場」(フィールド)に転換する
学生に多様な刺激を与え「気付き」と「内発的な感動」をもって主体的に学習する契機となりうるような教育は、いかにあるべきか。それを解く鍵の1つは「現場の科学」の理念と方法に基づき「教室を“現場”に転換する」ことです。基本的知識、技術を伝達する一方通行の講義には、学生が現実感と切実感を持てないのは当然でありましょう。工場見学や企業訪問など、仕事の現場に直接触れる機会を持つことが、現場の事実に基づき問題解決思考を訓練する最も有効な方法であることは、言うまでもありません。だがこの方法は、ゼミナールなどの少人数に対して実施可能であります。多人数の学生に対しては実現が、極めて困難な方法なのです。受け入れ先が限定されること、移動時間を加えるとほぼ半日の工程となってしまいます。さらには交通費の問題があります。学生個人レベルでは、近年注目されている企業内短期研修のインターンシップが、有効であることは、参加学生の成長を見れば明らかです。
多人数の学生を対象にする場合には、逆の発想が必要とされます。教室を日常空間から非日常空間に転化して、そこに「現場」を創り出すことが出来れば、移動は必要とされません。決められた時間と教室で教員が、予定されたシラバスによって講義する場は、単純作業を行う日常性の一コマに過ぎないのです。「知的好奇心」の希薄な学生に通常の情報を伝達するだけの講義では「気づき」や「発見」のインパクトを与えることはまず不可能です。それ故「非日常空間」への「場面の転換」を実現するには現実的、現代的テーマを掲げて、それに最も相応しい人物を講師(ゲスト・スピーカー)として教室に招聘することが必要なのです。ゲスト・スピーカーには、社会的各部門の第1線において問題解決に取り組む当事者として自らの仕事の世界と人生を十全に語ってもらうことです。「大学の知」は論理性と体系性を特長としていますが、現場の事実と経験によって問題解決に貢献できるものか否かの、検証が必要とされています。
理論の出発点は、現場であり、その帰着点もまた現場です。大学にある「専門家の知」は、「現場の知」と有機的関連性を持った時初めて「問題」をより広い視野に位置付けることが可能となります。現実から遊離した「大学の知」は、単位を取るための「試験用の知識」に過ぎずません。学生にとっては「現場の知」に生きる人物との一期一会の出会いが、新しい「気づき」の絶好の機会となりうるのです。
実務界にある講師にとっては大学のキャンパスと教室は、非日常的空間であり、学生に語る事は、ある程度の緊張を伴う非日常的な経験となります。他方学生にとっては、講師の講演は、その人間的、知的刺激によって教室が非日常的空間に転化することを意味しています。身体感覚(五感と直観)を働かせて、イメージすることが出来れば教室をインタビュー調査の「現場」、問題発見を行う「現場」として位置づけることが可能となります。自然であれ人間であれ、その理解には論理的思考力以前に共感、共鳴する感性とイメージ力が、重要です。講師の人間性と物語に共感、共鳴することができれば、「現場感覚」修得の第一歩となりえます。提起された問題をわが事として受け止め、その解決に向けて協働する主体的な姿勢を取ることが可能となります。
啓発された内容のノートテーキング(記録作業)は、頭脳への「手による情報の入力」作業なのです。思考のホームポジションで「わが事として考える」ことは、違った現象の底に潜む本質に等価性を発見し「等価変換」を行うことを意味していています。そして思考内容を、情報として出力する「手作業」は学習の身体感覚を回復して現場感覚を修得する実践による訓練(OJT)となるのです。
6.北海道大学経済学部における新しいプログラム
北海道大学経済学部では、1984年の「鉄鋼産業論」以来1989年「公企業経営と地域開発」(池田町助役大石和也氏)、2003年「沖縄の内発的発展」に至る20年間に合計14産業、講師18名の『産業論』集中講義を展開してきました。また1991年には、各産業の横断的研究を目的に12名の講師による連続講義「現代の産業と経営」を展開しました。さらに1996年には、1年生に対する経済・経営入門コースである「現代の経済」において5名のゲスト・スピーカー(内1名外国人の英語)。2003年「企業論」では、民間企業、地方自治体から7名。2004年度「経営学」では民間企業、地方自治体から合計8名(東京、関西から各1名)を招聘しました。2006年の「社会の認識」(1年生)に対しては、1名。「経済経営書購読」(2,3,4年生)には、2名を招聘しました。このような実験的試みの成果は、次のような受講学生のコメントによっても明らかです。
『産業論』へのコメント。「抽象的、理論的な大学の通常の講義に比べてはるかに面白い。」、「大学が、北海道にあるため東京を中心としたビジネスの実態が、よく解からないが、第一線で活躍されている方からお話をうかがい、現実感を持って理解することが出来た。」、「実際に社会人として活躍しておられる人に直接触れることで、社会人として仕事に対する責任感や自分を高めていく努力が、とても重要であるということを強く感じた。」、「自信と誇りを持って仕事に取り組んでおられる。」「自分があらゆる意味で未熟であることを認識した。」「社会に出た時に必要とされる能力の基礎を学生時代に身に付けておきたい。」などが上げられます。現実社会の動向を、直接その当事者から聞くことにより、学生時代の自らの課題を、明確化するきっかけが得られたといえましょう
連続講義『現代の産業と経営』への学生のコメント。「1つの講義科目で多様な産業現場の第1線で活躍されている方の仕事の内容と取り組む姿勢、意欲、生き方に直接触れることが出来た。」、「日本の産業と企業が、抱える問題を多様な業種に即して具体的に理解することが出来た。」、「多様な産業の話を同時に聞いたのでそれらを比較することが出来た。」、「自分がこれから職業を決めるためのヒントをもらった。」などがその代表です。
『現代の経済』(1年生)。受講学生のコメント。「当事者から直接話を聞くことが出来、現場、現状が、よくわかった。全く初めて知ることも多く、大変勉強になった。またやってほしい。」、「ゲストの話は、毎回集中し、メモを取った。これこそ大学なのだと思い、うれしかった。」、「自分の知らないことや将来の展望が、見えた気がする。」等であり、95%の学生が、「よかった」と評価しています。
『企業論』の受講学生のコメント。「多様な現場のナマの話が聞けて企業の実態が、リアルに理解できた。」、「直接現場の方から話を聞くのは、単に自分で想像するよりも刺激が多い。」、「今までぼんやりとしていたものが、自分の中でしっかりと形になった。」、「視野の拡大、自己変革、歴史を見据えることなどを学んだ。」、「コミュニケーション能力の重要性がわかった。」、「学生に圧倒的に足りない“社会感覚”を教えてもらった。」、「仕事だけに秀でている人はいない。人間的にも素晴らしい人が多い。」「ゲスト・スピーカーの方々が投げてくれたボールを私達が、社会に出てどのように投げ返すかを、残りの学生生活の間に考えたい。」、「企業活動は、単に利益追求というだけでなく、自己実現にも似た人の営みである。」などがあります。
『経営学』受講学生のコメント及び評価は実務の第1線で活躍する人の話を直接聞く事のインパクトの大きさを示しています。現代社会は、多様な産業、企業、職場があり、そこに働く人に多様な人生と生き方が、あることを、共感、共鳴と共に理解しているのです。そしてゲストを鏡として自らの職業生活への基本的態度の確立が、必要なことを知り、学生時代に開発すべき能力と目標を明確にして取り組む姿勢を形成することが出来たといえましょう。
7.むすび
現代の大学における啓発教育は、高度に抽象化した理論、専門化、細分化された理論から出発するのではなく、学生の「原体験」、「原風景」を基礎にして五感と直観を働かせるステップを着実に踏むことを重視すべきです。既存の情報を操作するばかりではなく、現場・現実・現物に直接触れることからスタートする必要があります。人の働く(生きる)現場に直接触れて、共感と共鳴をもって理解し、我が事として受け止め自らが働く(生きる)場において協働して問題解決に取り組む志と姿勢を、涵養することが重要です。そのためには大学を「世界に開かれた公共空間」として位置づけた異質の交流(社会的異部門間、異専門間、国際)が不可欠です。交流により「教室」が非日常空間すなわち「現場」(フィールド)に転化されうるのです。学生は自らの五感と直観を働かせ、手を動かして「現場」のデータ(情報)を作成します。そしてこれをフィードバックして、共有化し、累積します。さらに構造化によって問題の全体像を描き、問題解決の見取り図を作成することが可能となります。
事例研究の意義は、マニュアルを使って「専門的知識」を対象に当てはめることではありません。事例(他者の世界)を鏡にして己を映し出して、違った事象の間に共通する本質を見つめて、問題を発見することなのです。さらに問題解決の構想と具体策に至る思考のフルコースを訓練することなのです。
北海道大学経済学部における四半世紀間の実験によって大学教育には、「現場の科学」の方法論を導入した一期一会の場を設営することにより「現実性」と「現代性」の回復が、可能となること。現場に触れて五感と直観を活かして、手で考えることにより「学習の身体感覚」を回復し、問題発見、問題解決能力の開発が可能であることが、実証されたと思います。
なお、本稿は、ブックレツト『うおんつ』(2007年7月 Vol.53)に掲載された同名の論稿を、一部加筆訂正したものです(2007.11.6)。詳しくは、以下の書著、論文を、参照して下さい。
・米山喜久治(1993)『探究学序説』文眞堂
・米山喜久治(2007)「大学教育と現場の科学」『経済学研究』Vol.56 No.4 (北大)
|
|