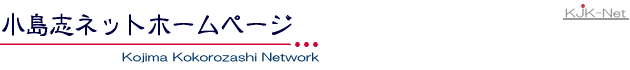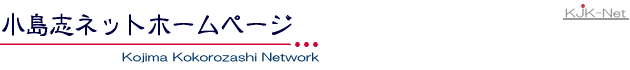| ■このごろ都にはやるもの−58 ヤマニとナーゼルの警告 最首公司 (2007.12) |
石油100ドル時代 なぜ生かされなかったのか、ヤマニとナーゼルの提言
2008年の年頭に当り、拙文読者に新年のご挨拶をおくります。
さて、新年早々、NYの先物市場でWTIが100ドルの大台に乗せました。このことについて、感じたことを書いてみます。
中東戦争と第1次石油危機
1973年10月、エジプト軍はイスラエルの虚を突いてシナイ半島に進撃、占領中のイスラエル軍を追い散らした。第4次中東戦争の勃発である。この戦争はエジプト軍対イスラエル軍という二つの軍隊の戦いだけでなく、もう一つ、石油を武器にした戦争があった。
シナイでの戦争にアラブ側は間髪を入れずOAPEC(アラブ石油油種国機構=本部クウェート)が招集され、“敵性国家”と判定した米国とオランダには石油輸出禁止、その他の国には中東政策をみて判断する、という「石油戦略」を発動したのである。OAPECは同時に毎月5%づつの減産措置をも決定した。
このOAPECの石油戦略に同調してOPEC(石油輸出国機構=本部ウィーン)は原油価格を一挙に4倍に値上げしたのである。これが世に言う「第1次石油危機」の幕開けだった。
このとき、シナイ半島での戦争指揮をとるエジプト・サダト大統領と緊密に連絡をとりながら石油戦略を練り、主導したのがサウジアラビア・ファイサル国王とアフマド・ザキ・ヤマニ石油相の“師弟コンビ”だった。
開戦当初からサダト大統領はどこでイスラエルと手を打つかを、ファイサル国王とヤマニ石油相はどの時点で石油戦略の鉾を収めるか、機をうかがっていた。
「産消対話」を探ったヤマニ
シナイ半島の戦いは、緒戦はエジプト側が圧倒したが、その後、戦さ慣れしたイスラエル軍が反撃に出てこう着状態に陥った。一方、石油戦略の方はなにしろ世界が初めて経験することもあって消費国は大騒ぎ。日本では洗剤やトイレットペーパーの買占めが起こり、私の勤めていた新聞社も普段平身低頭の用紙会社から「重油をもってきたら売ってやる」といった具合だった。
この騒ぎを挟んで日本に二人の要人がやってきた。一人はニクソン大統領の腹心キッシンジャー特別補佐官(のち国務長官)とヤマニ石油相だ。キ補佐官はアラブになびこうとする日本政府を引止めにかかる。「ならばアメリカは日本の石油を保証してくれるのか」という田中角栄首相の問いに対し、キ補佐官は「それはできかねる」と答えた。
そこで田中内閣は二階堂官房長官談話でアラブ支持を表明し、三木武夫副総理を政府特使としてアラブ産油国に派遣した。私もこの三木ミッションに同行記者団として参加したが、ファイサル国王と会談したあとの三木さんの笑顔、そしてサダト大統領から「日本は友好国だ」といわれて、事実上、「禁輸措置」を解かれることを伝えられたあとの日航特別機内の喜びようは忘れられない。
ヤマニ石油相はかねてから産油国と消費国との協調による原油価格と供給の安定化を考えていた。シナイ戦線で停戦協定が成立、戦争が一段落したところで、ヤマニ石油相は「ここで産油国と消費国が話し合う場を設けたらいかがでしょう」ファイサル国王に進言した。国王の賛意を確かめたあと「それを切り出すのはわれわれよりも第3国、たとえばフランスあたりにいってもらうのが良いでしょう」とつけ加えた。ヤマニ氏は消費国には産油国に対する不満が残っていることを危惧したのだ。
ファイサル国王は自らフランス・ディスカールディスタン大統領に連絡してサウジアラビアの意を伝えた。フランスはアンドレー・ジロー・エネルギー工業相を消費国側の根回し役に、サウジはヤマニ石油相が産油国側をまとめとうと動き出した。
翌74年4月、国連特別総会に出席したヤマニ石油相が「南北間でエネルギーを含む全ての問題を話し合う特別会議を開こう」と呼びかけた。フランスは直ちに賛意を表明したが、米国が一顧だにしない。このとき、米国キ補佐官はニクソン大統領の了解のもと、OPECに対抗するための「輸入国機構」を立ち上げようと、密かに英国、西独、日本などに提案していたのだ。
そこでフランスは独自に「国際経済協力会議」(CIEC)を提案したが、これも米国から拒否され、妥協の産物として「国際エネルギー機関」(IEA)が誕生した。日本など西側先進国は軒並み参加したが、フランスだけはサウジアラビアとの約束を重んじて加入を見送り、代わりに本部をパリに誘致することで、IAEを支持する姿勢を示した。したがって、発足当初のIEAは非加盟国の首都に本部を置くという奇妙な組織になったのである。
石器時代は石が無くなって終わったわけでない
70年代後半、原油価格はOPEC主導で値上がりを続けた。結束の方さを誇ったOPECだったが、足並みが乱れ、「穏健派」と呼ばれたサウジアラビアとUAE(アラブ首長国連邦)がOPEC合意価格よりも50セント安で設定したこともあった。演出したのはもちろんヤマニ氏とその追随者UAEオタイバ石油相だった。
79年のイラン・イスラーム革命、80年のイラン・イラク戦争で、原油価格は急騰した。世間はこれを第2次オイルショックと呼んだ。このときも価格引き上げの主導権を握ったのはOPECを中心とする産油国だった。余りに性急な値上げ政策に、ヤマニ石油相は危機感を抱き、「石器時代は石が無くなって終わったわけでない」と産油国を戒めた。石油価格が高騰すると、必ず代替燃料が開発され、石油が存在するのに使われなくなるゾ、と警告したのだ。
同相は 年、ファハド国王に疎まれて退任、総合エネルギー研究所をロンドンに設けて独自の活動(その一つに英字月刊誌「Arabia」の発刊があり、私も編集委員として年2回の編集会議に出席した)を始めたが、80年代後半はヤマニ氏の警告通りに原油価格は低迷し、一時は10ドルを割るほどに低落した。
インビジブル・シェイクハンド
1991年パリで初の「産消対話」となる「第1回エネルギー・フォーラム」が開催された。サウジアラビアから出席したのは、ヤマニ石油相の後を継いだヒシャム・ナーゼル新石油相だった。ナーゼル氏は国家企画相として国王の信任を得た、有能なテクノクラートだった。
この席でナーゼル・サウジアラビア代表は一つの提言を行った。彼はその提言を一言で表現した。それは「インビジブル・シェイクハンド」(見えざる握手)だった。
資本主義のバイブルといわれる「諸国民の富」(富国論)の著者アダム・スミスは、価格の決定を市場に委ねようと説き、その機能を「神の見えざる手(インビジブル・ハンド)」と呼んだ。ナーゼル氏はその「インビジブル・ハンド」をもじって「インビジブル・シェイクハンド」、つまり「見えざる握手」、産油国と消費国の対話と合意によって需給や価格問題を解決しようと呼びかけたのだ。
先物市場で応えた消費国
これに対し、先進国はどうしたか?産消両者の対話や合意を呼びかける「見えざるシェイクハンド」を無視して「見えざる先の先のハンド」ともいえる「石油先物市場」を設けることで応えたのだ。「先物市場」を創設することによって、価格決定の主導権を確保しようとしたわけである。いかにも資本主義らしい「強い者勝ち」「早いもの勝ち」の論理ではないか。
いま、私たちはその先物市場に振り回されている。米国ニューヨークの商品取引所(NYMEX)で取り引きされるWTI(ウェスト・テキサス・インターメディエイト)原油は、世界で生産される原油量の1%にもならない。その原油価格が世界の原油価格を決めてしまうのだ。資本主義は効率を重んじるから、これはこれで尊重されるのだろう。
だが、その結果、世界的に富の移動が津波のように産消双方に襲い掛かる。サウジアラビアを見てみよう。サウジアラビアの08年予算は石油収入を1バレル当り45ドルと設定、日産950万バレルを前提にしている。エコノミストは最低でも通年価格を72ドルと見ている。原油コストは5ドル以下といわれるので、仮に72ドルとしても1日6億3650万ドル、日本円にして700億円の予算外の純益が入ってくるのである。巨額の所得移転が消費国から産油国に起きているのである。
産油国にはドル安インフレ
では、産油国はハッピーか、というと、手放しでは喜んでいられないのだ。アラブ産油国はイランとクゥエートを除くと、自国通貨がドルと連動する「ドル・ペック制」をとっているため、ドル安に伴うインフレに襲われているのだ。UAEは新年から公務員給与を一挙に7割アップした。しかし、この恩恵を受けられるのは国籍がある者に限られ、外国からの出稼ぎ人は対象にならない。民間企業に対しても政府に倣うよう求めているが、できる企業とできない企業がある。インフレはそこに生きる人全てを襲うが、救済されるのは限られた人たちだけだ。
石油の輸入国、消費国はもっと悲惨だ。原油高は石炭、天然ガスからウランまでの燃料価格を引き上げ、食糧、衣類、サービス産業にまで及ぶ。ここでも賃上げされる大企業労働者は救われるが、最低賃金や年金の受給者、フリーターなどは見捨てられる。要するに、ごく一部の石油が投機の対象にされたため、国際的にも国内的にも所得格差を拡大させ、それぞれの国内に社会不安を増大させているのだ。
では、どうすべきか?
第1次石油危機が起きる直前、田中内閣でエネルギー行政を担当していた中曽根康弘通産相はサウジアラビアを訪問した際、リヤドでヤマニ石油相を会談した。そのとき中曽根氏は「いま国際石油情勢は転換期にある。産油国と消費国がパートナーとなって長期契約を求める方向にある」と、産消政府保証による長期安定供給体制づくりを提案した。冒頭のヤマニ構想とほぼ一致した考え方である。
いずれはナーゼル氏がいった「インビジブル・シェイクハンド」が必要になってくるかもしれないが、当面できることは、産油国に移転したオイルマネーを消費国への投資として還元し、産油国経済と消費国経済を一体化させることだ。
その点、昭石シェルにサウジ・アラムコが出資したり、アブダビ政府系ファンドがコスモ石油の筆頭株主になることは歓迎すべきだろう。昭石シェルやコスモ石油が業績を伸ばすことは日本経済が順調でないと期待できないし、原油価格の高騰が投資先企業の首を絞めるようなら、投資資金が回収できなくなる。こうなると、産油国も原油価格のあり方を考えざるを得ない。
産消両サイドの経済を一体化させるには、欧米系のヘッジファンドのように、株価を高くして売り抜ける、ということではまずいので、株式保有期間や株主としての権利行使に条件をつけることも必要になる。そして、なによりもあのNYMEXの先物取引だ。原油で博打をやるならラスベガスかマカオのような隔離されたカジノでやってもらうことにして、原油取り引きは実需に基づくものに限定してもらいたい。例えば、サウジ・アラムコと取り引きする場合、買い手は製油所を所有する法人に限られ、パーパーカンパニーなどは完全に排除される。
産油国も原子力開発
ヤマニ氏が「石器時代の石」に譬えて警告したときの新エネルギーの代表格は原子力だった。原子力が普及すると、石油はエネルギーの主役の座を奪われ、石油収入に依存する産油国経済は破綻することを恐れたのだ。しかし、世の中は変わった。消費国の脱石油を恐れた産油国の筆頭サウジアラビアでさえ、07年2月に訪サしたロシア・プーチン大統領とアブダラ国王の間で「原子力開発協力協定」を結び、リビア、アルジェリア、モロッコはフランスとそれぞれ原子力協力協定、もしくは覚書を交わした。
イランはロシアの支援でブシェール原子力発電所を建設、今春には試験運転を始めるようだし、エルバラダイIAEA事務局長の母国エジプトも原子力発電所建設を計画している。有り余る資金とその余剰資金が生み出す都市化によって急増する電力と水の確保のため、高価な石油を使うよりも原子力を使うべきだという考え方が強くなってきたのだ。今春から動き出す「京都議定書」の実証作業を見据えて、産油国側も「環境重視」「減炭エネルギー国」のイメージ戦略も考慮されているのだろう。
こうした状況下、日本の出番は「原子力技術者養成」「原子力発電所の運転・保守」などいろいろ考えられるだろう。私事になるが、私はアラブ産油国のもう一つのエネルギー資源、太陽光・熱を利用する「集光式太陽炉」で発電、海水淡水化ができないか考えている。2008年1月6日記
|
|