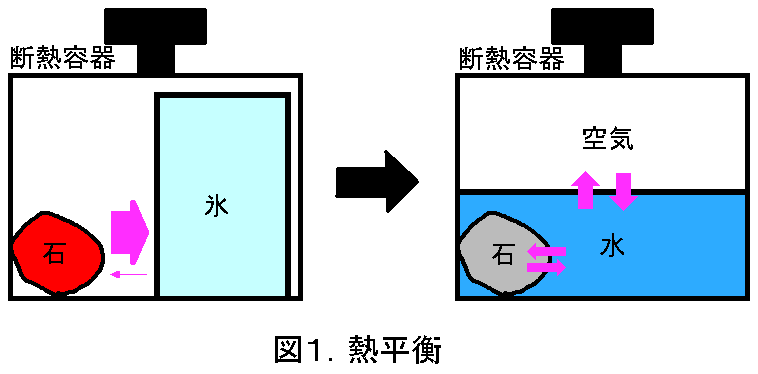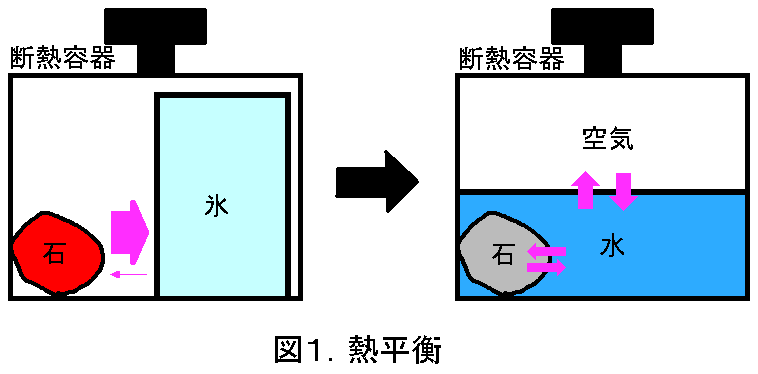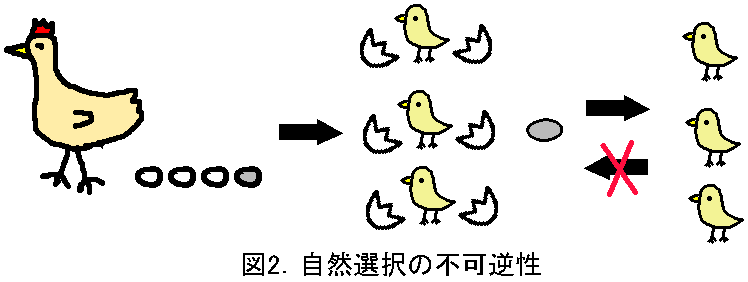遺伝子とエントロピー
最初に熱力学の第二法則について述べます。この法則は熱は熱い物体から冷たい物体に移動し、逆の現象は起こらないということを法則化したものです。熱力学の第二法則の別の表現では、孤立系のエントロピーは常に増加するとなります。エントロピーは分子の無秩序さを表す量です。孤立系というのは、外部と物質とエネルギーのやりとりの無い系を表します。通常は熱と物質を通さない強力な魔法瓶のような断熱容器の内部を近似的に孤立系とみなします。ここで具体的な例を検討します。最初に断熱容器の中を、外部との熱と物質のやりとりのない孤立系とみなします。次に氷の塊と真っ赤に焼けた焼け石を用意し、断熱容器に入れて蓋をします。それを示したのが図1です。
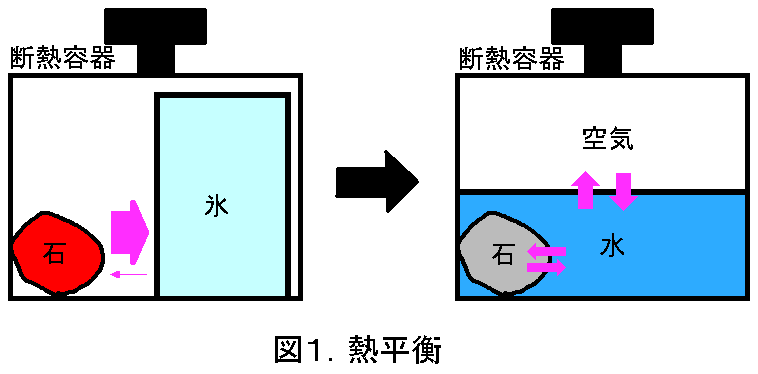
左側には断熱容器に焼け石と氷を入れた状態を表し、ピンクの矢印で熱の動きを示しました。最初は焼け石から氷に熱は移動します。ただし、注意しなくてはならないのは、その時点でもごく少量の熱量は氷から焼け石に移っているということです。時間が経つと、氷は溶けて水になり石の温度は下がって、断熱容器の中は一定の温度で平衡状態となります。その状態を右側に示しました。この状態を熱平衡と呼びます。ただし平衡状態は完全に静止した状態ではありません。石と水の間に関しては石から水に移る熱量と、水から石に移る熱量が釣り合った状態にあります。また空気と水の間でも、お互いにやり取りする熱量は釣り合っています。可逆的に自由に熱がやりとりされるので、温度の高い方から低い方に熱が移動し、断熱容器の中は全体が同じ温度になります。この状態を熱平衡といい、それからは温度は一定となります。熱力学の第二法則では、ここまでの過程は不可逆過程となり逆転できません。この状態から自然に氷が出来、石が焼け石になったという話は聞いたことがありません。
しかし、それは外部との熱と物質のやり取りのない孤立系に限られます。開放系にして人間の手を加えると、話は違ってきます。まず断熱容器を開けて、水を適当な形の容器に移して冷凍し氷の塊を再生します。さらに石は、用意しておいた焚き火の中に放り込み、再び真っ赤に焼いて焼け石を再生します。非生物的な現象は、このように不可逆と思える現象でも、人間がエネルギーを用いて操作すれば逆転可能です。それは熱平衡に至る個々の過程が可逆的だからです。熱平衡に至る個々の過程は、石については焼け石が冷えたのであり、水については氷が熱せられて水になったのです。どちらの過程も単独では逆転可能ですが、断熱容器の中で組み合わせると不可逆になります。つまり熱力学の第二法則における不可逆過程は、可逆的な過程の組み合わせから出来ています。だから石と水を引き離して、それぞれを操作すれば、石は焼け石に、水は氷になります。
それに対して生命の死という現象は絶対的に不可逆です。そして生命と物質で述べたように生命には分割不能な最小単位が存在します。ただ真核細胞では共生という現象が知られており、分割可能な場合もあり得ます。ここでは煩雑な議論を避けるために、出来るだけ単純な細菌について考えます。単純な細菌を考えても、一個の細胞は秩序だって構成されており、人間の作る機械以上に精巧です。細胞を単位とした生命は、多くの高分子が全体として複雑な秩序を構成しており、各高分子の間には構造的にも機能的にも有機的なつながりがあります。これらの高分子が正常に機能するにはホメオスタシスが必要です。ホメオスタシスとは細胞内の環境を一定に保つことで、細菌は細胞内の電解質濃度、浸透圧、pHなどを一定に保とうとします。ホメオスタシスが修復不能なところまで崩れると、生体高分子は正常に機能しなくなり、細胞は死んでしまいます。そのため細胞は全体として一つのまとまりを構成し、細胞は基本的には分割不能です。そして細胞が死んだ場合、高度な秩序が自発的に再構成されるとすれば、熱力学の第二法則に反します。そのため生命の死は不可逆な現象となり、細胞が死ねば分解されます。人間も死ぬと微生物によって分解され、跡形もなく土に帰ります。またこれまでに死んだ生物が生き返ったことはありません。
また生命を構成する有機物などの材料が豊富にあっても、ホメオスタシスを含む生命の高度な秩序は、自然には構成されません。これは人間の作った機械について考てみるとわかります。人間の作ったものの中では、時計はかなり精巧なものです。それでも一匹の細菌と比較すれば、かなり単純です。ところが細胞よりは簡単な時計でも、材料を全て揃えて箱に入れて十億年放置しても、自然に時計が出来上がるとは思えません。ましてや細胞のように柔軟性を備え、時計としての機能もあり、運動能力もあり、化学工場としての能力もあるものが自然に出来るとは思えません。実験的にも生命の自然発生はパスツールによって否定されており、地球が出来てから一度しかなかったとされています。確かに普通に考えると、熱力学の第二法則によれば、生命のような高度な秩序は自然には構成されないと思われます。その意味では生命の死が非可逆的であるのは熱力学の第二法則にかなっています。そうすると最初の生命発生は、本当に驚くべき出来事だったと思われ、色々な学説はありますが、まだ完全に誰もが納得するものはありません。どうして生命が発生したのかは、私には想像もできません。
しかし、生命が発生してからのことはある程度は想像できます。シュレーディンガーは生命の顕著な特徴として、生命は物質が平衡状態に向かう傾向から逃れているように見えると述べています。熱力学の第二法則によれば、孤立系において通常の物質は、速やかに平衡状態に向かいます。ところが生命はこの法則を逃れているように見えます。平衡状態の一種である熱平衡を例にとります。北極犬はアムンゼンが南極探検に用いたので有名ですが、北極犬と同じ温度で同じ組成で同じ質量の物体を南極におけば、短時間で凍ってしまいます。このように通常の物質は、ある程度の時間がたてば熱平衡に達し、周囲と同じ温度になります。ところが北極犬はそれより遙かに長時間体温を保ち、それだけでなく犬ぞりを引っ張ってアムンゼンを南極点に連れて行ったのです。これは北極犬が寒いところでも生きられるように進化したからです。そして進化の原動力は自然選択であり、自然選択の前提条件は以下の二つです。生命が死ぬ場合は一個の生命が全体として死ぬことと、生命の死が絶対的な不可逆過程であることです。
自然選択の対象になるのは遺伝子ですが、遺伝子について予備知識のない方はDNAとデジタル信号を参照して下さい。ここではある程度の知識のある方を対象に、簡単に説明します。遺伝情報はDNAの一本鎖に塩基が一列に並んだ塩基配列として記録されています。塩基にはアデニン、チミン、グアニン、シトシンの4種類しかなく、それぞれA,T,G,Cとアルファベット一文字で略して表されます。二本鎖DNAにおいては、二本鎖は二重らせんを形成しており、塩基はペアを形成しています。各塩基はペアになれる相手が決まっており、必ずAはTと、GはCとペアになります。そしてDNAの塩基配列は三文字で一つのアミノ酸を表し、通常は一つの遺伝子は一つの蛋白質をあらわします。
ここで一個の塩基に注目します。例えばそれがアデニンであったとします。各塩基をプラトンの三原則に当てはめてみます。第一にアデニンはかなり厳密に同じ分子構造のアデニンでなくてはならず、分子構造が少し違っても塩基対形成を妨げ、致死的となる場合があります。これは分割不能と同義です。第二にアデニンはアデニンと全く等しく、塩基配列の中のアデニン同士を入れ替えても全く違いはありません。第三にアデニンは、特に変異が致死的である場合、不変でなくてはなりません。こうしてみると、DNAの各塩基はプラトンの「1」に非常に近い性質を持っています。ただしそれは、デジタル化の意味で述べたようにDNAが自然選択の対象になるからであって、単なる分子としてのDNAがプラトンの「1」としての性質を持っているわけではありません。
DNAは非常に正確にコピーされ、親から子へと遺伝情報を伝えます。しかし希にミスコピーがあり、それを突然変異と呼びます。突然変異は生存に不利な場合がほとんどですが、ごく希に生存に有利な場合があり、進化の原動力になります。自然選択によって生存に不利な突然変異を除去し、有利な突然変異を増加させることで、生物は進化します。第一に重要な点は特に蛋白質をコードするDNAの各塩基が、直接的に自然選択の対象となる点です。仮想的な例について考えてみます。一個の大腸菌のコロニーは、一匹の大腸菌の子孫であり、通常は全く同じ配列のDNAを持っています。その中に突然変異を起こした個体があったとします。特定の一個の塩基がAからTに変化し、それ以外は他の個体と全く同じままだったとします。たまたまそれが耐熱性に関係した蛋白の遺伝子に起こった突然変異で、その個体だけが耐熱性が上がったと仮定します。その時点でコロニーが高温にさらされれば、突然変異した個体だけが生き残ります。結果的には、一個の塩基だけが自然選択された形になります。このように各塩基は独立に選択対象になり、当然一個の遺伝子は独立に 自然選択の対象になります。それは各塩基が「1」としての性質を持つので可能になることであり、デジタル化の意味でも説明したように、DNAは部分的に書き換え可能ということです。この場合は突然変異体の子孫だけが生き残りますので、大腸菌のDNAの特定の一個の塩基がAからTに書き換えられたことになります。
第二に重要な点は、遺伝子が熱力学の第二法則を逃れているように見えるという点です。熱力学の第二法則におけるエントロピーは、統計力学においては分子の無秩序さを表します。例えば閉鎖された部屋で、小さな酸素ボンベの栓を抜いたとします。時間がたてば酸素分子は部屋全体に均一に分布します。ここでボンベ内の一個の酸素分子について考えます。最初は小さいボンベ内に存在していたのに、時間がたてば部屋のどこに存在しているのか分からなくなります。統計力学では、このように分子の状態が分からなくなることをエントロピーが増加したといい、系は無秩序になったといいます。しかし、熱力学の第二法則を適用するには、微細な個々の過程は可逆的でないといけません。そうであれば最終的には一番確率の高い平衡状態となりますが、真に不可逆的な過程を含むとそうなるとは限りません。
これを単純化した例によって説明します。まず自然選択のないコピーを考えます。元のデータを99%の正確さでコピーできたとしても、70回のコピーを繰り返せば、元のデータは半分以上が失われます。このように自然選択が働かなければ、コピーを繰り返すたびに元のデータは失われるはずです。熱力学の第二法則によれば、完全に正確なコピーは出来ません。それを現実に当てはめてみます。細菌のDNAの変異率は、細菌一世代につき約10億塩基あたり1塩基です(2)。そして細菌は実験室での条件では、30分に1回分裂します。この速度で分裂し続ければ、年に約17500回分裂します。仮にそのまま分裂し続けて自然選択が全く働かないとすると、約500年後には1%近くの塩基が変異し、5万年以内に半分以上の塩基が変異します。このように単純にコピーを繰り返せば、最終的にはDNAの塩基配列はランダムになるはずです。またコピーをせずにDNAの塩基配列を長期保存しても、熱力学の第二法則によれば、いつかはDNA全体が変性してしまいます。
ところが現実には細菌の16SリボソームRNAの重要部分は、およそ35億年前から保存されています。これは自然選択によって、生物にとって生存に重要な遺伝子が保存されるからです(3)。これを仮想的な例で考えてみます。全ての変異が致死的となる遺伝子があったとします。この場合は一箇所でも変異があれば、その個体は死んでしまいます。そうするとミスコピーの確率に関係なく、残った個体はすべて100%正確なコピーです。これを何回繰り返しても最終的に100%正確なコピーが残り、半永久的に遺伝子は保存されます。これが自然選択の効果ですが、それを例を用いて説明したのが図2です。
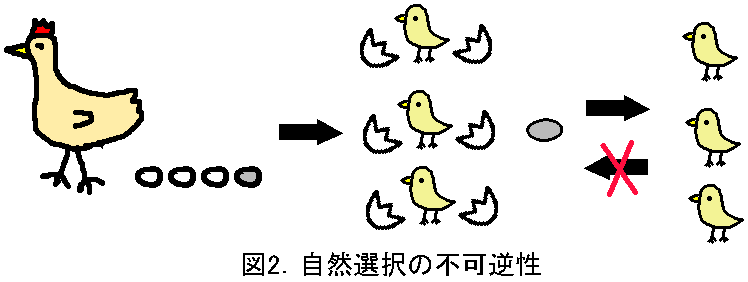
図2には仮想的な例として、鶏が四個の卵を産み、そのうちの一個がヒヨコまで成長できない突然変異を起こした場合を示しました。突然変異を起こした卵はグレーで示しています。三個の卵は孵化してヒヨコになりますが、一個のグレーの卵はかえることが出来ません。一番右側には三羽のヒヨコだけを示しました。その時点では、一個のグレーの卵は死んでしまっています。これは絶対的に不可逆的な過程で、生命は死ねば生き返りません。ここで逆の過程に赤でペケをしたのは、図1の熱平衡の場合と比較して欲しいからです。熱平衡には逆の過程もあったので、人工的に逆転可能です。ところが生物の死は人工的にも逆転不能です。ところがそのおかげで生物は、不可逆的に生存に不利な遺伝子を除去できます。その結果として、熱力学の第二法則に違反することなく、生物は進化できるのです。その意味ではダーウィンによる自然選択の発見は真に偉大な発見だったと考えられます。最初の生命の発生という問題だけは解決できませんが、ダーウィンの進化論(4)によって、生命が情報を蓄積して進化する過程を説明できます。
進化論を補完する分子進化の中立説によると、特に生命にとって重要な遺伝子に対しては、自然選択は遺伝子を保存する方向に働きます。分子進化の中立説については、ここで詳しくは説明しませんが、有名な例を挙げてみます。真核生物の核タンパク質であるヒストンH4は102個のアミノ酸からなるペプチドですが、マメ類とウシのヒストンH4のアミノ酸配列を比較してみると、たった2個の違いしかありません。動物と植物が分かれたのは10億年以上前とされていますが、それからアミノ酸102個中の2個しか変化していません。これは地表にある生命のない物体ではあり得ません。10億年の間には、岩石はもちろんのこと、山脈や平野や大陸も変化しており、原形をとどめていないとされています。自然の地形ですら変化してしまいますから、人間の建造物などは問題になりません。ピラミッドでさえも、一万年もたたないうちに、かなり風化しています。デジタル記録メディアであるCDなどは、百年も保たないとされています。ところが生物にとって重要なタンパク質のアミノ酸配列は長期間保存されます。特にヒストンH4においては、ほとんどのアミノ酸の置換が致死的であるため、突然変異を起こした個体が除去されて、アミノ酸配列が保存されたのです。このように生物は、自然選択を含むコピーを繰り返すことによって、遺伝情報を保存することが可能であり、生存に重要な塩基は自然選択によって不変に保たれます。
「生命とは何か」の中で、シュレーディンガーは生命体が秩序を維持するということが、生命のない物質との決定的な違いであると述べています。それが何故可能であるのか、シュレーディンガーは負のエントロピーという概念を述べています。その正体は当時の科学技術の水準では分かりませんでしたが、それでもシュレーディンガーの考察は本質を見抜いている部分がありました。当時はまだ遺伝子の正体がDNAであるとは知られていなかったので、シュレーディンガーは遺伝情報を担う原子団を非周期性結晶と呼んでおり、それは高度の秩序を備えていると述べ、さらに生物体が環境から秩序を吸い込む能力は非周期性結晶と切り離せないとも述べています。
シュレーディンガーの生命観のその後の発展を見てみます。情報は負のエントロピーとしての性質を持つということは、最初にシラードによって指摘され、ブリルアンによって主張されました(5)。それをファインマンは現代的視点から解説しています(6)。これを遺伝情報に当てはめてみます。自然選択によって生存に有利な遺伝子が選択されますが、生物の死によってエントロピーが増加しますから、生存に有利な遺伝情報はエントロピーの増加を妨げることになります。つまり遺伝情報は負のエントロピーとしての性質を持ち、生命は遺伝情報によって生物体の秩序を維持していることになります。このときに重要なのは、自然選択は不可逆過程を含むので、自然選択が働く遺伝子のコピーには熱力学の第二法則は適用されないということです。
逆に自然選択の働かない現象には必ず熱力学の第二法則が適用されます。そのため非生物学的に情報を蓄積しても、必ず劣化し最終的には失われます。それだけではなく、完全な自然選択の働かない状況では、生物の遺伝子にも熱力学の第二法則が適用されます。熱力学の第二法則が生物の遺伝子に適用されれば、負のエントロピーである情報量は減少することになってしまいます。つまり完全な自然選択が働かない状況においては、生物の遺伝情報は劣化します。これは人間によって飼育されている犬などにもあてはまります。人間に飼育されている環境では自然選択は十分には働かず、人間による選択が働きます。例えばダルメシアンなどは、尿酸が代謝できず尿路結石になりやすく、先天性の聴覚障害も多くあります。ダルメシアンは白地に黒の斑点という見た目が貴族に好まれて、外観によって選別され近親交配されて純血種が作られました。そのため自然選択が正常に働かず、生存に不利な遺伝子を持っているのです。
自然選択の働かない環境として、重要なのは多細胞生物の体内があります。高等な多細胞生物ほど、体内環境を一定に保つホメオスタシスがよく働きます。そうすると体細胞に対する自然選択は働かなくなります。これは多細胞生物に寿命があるということの原因にもなっています。例えば人間の体細胞には、本来の意味での自然選択はありません。そのためミスコピーは徐々に蓄積されてしまい、一部の細胞は癌化したりして個体の寿命を縮めます。さらに劣化した遺伝子を多数持つ個体が生存しないように、人間の寿命には限界が定められているようです(7)。
最後にデジタル記録メディアの優位性について世間では誤解されているように思われるので、デジタル記録メディアの利点と欠点について記載します。デジタル記録メディアは保存性が良いように思われており、劣化しないという先入観があるように思われます。ところがCDやDVDは光、熱、湿気に弱く不安定です。今問題になっているのは、ハリウッド映画の膨大なデータをデジタル記録メディアで保存する場合、耐久性が非常に悪いということです。これはデジタル記録メディアは自然選択の過程を経ないと、優位性を発揮できないということです。例えば誰もが見る名作であれば、見られているということは自然選択を受けているのに近い状態にあるわけで、ヒストンH4の塩基配列が十億年も世代を超えて保存されたのと同じような状態になります。この場合は、デジタル記録メディアの特徴として、正確にコピーが可能で、ミスコピーがあっても検出しやすく修正しやすいという利点が生きます。
ところが同じDNAの塩基配列でも、蛋白質をコードしていない偽遺伝子となると、自然選択を受けずに遙かに速く変化します。これは映画についても似た状況であって、誰も知らない作品であれば、完全に死蔵されることになり、熱力学の第二法則が適用されます。そうなればデジタルとアナログの違いは全く無くなり、メデイアの耐久性が重要となります。今のところは映像を記録するものでは、フィルムが一番長期の耐久性テストは受けており、それなりの信頼性があって数百年から数千年は保つといわれています。それに比べるとDVDなどのデジタル記録メディアの耐久性は劣り、百年も保たないとされています。死蔵される場合、今までに人類が使用したメディアでは、石に刻むのが一番耐久性が良いと思われます。ただデジタル化した映画の情報を石に刻むのは、費用と時間がかかりすぎて非現実的なので、結局はフィルムになります。今後はもっと優れた永久保存の方法が考えられるべきでしょう。
参考文献
(1) シュレーディンガー:生命とは何か,岡小天・鎮目恭夫訳,岩波新書(1951)
(2) Bruce Alberts et al.:細胞の分子生物学,中村桂子・松原謙一監訳,ニュートンプレス(2004)
(3) 木村資生:分子進化の中立説,紀伊國屋書店(1986)
(4) ダーウィン:種の起源,八杉龍一訳,岩波文庫(1990)
(5) L.ブリルアン:科学と情報理論,佐藤洋訳,みすず書房(1969)
(6) A.ヘイ・R.アレン編:ファインマン計算機科学,原康夫・中山健・松田和典訳(1999)
(7) 田沼靖一:死の起源 遺伝子からの問いかけ,朝日新聞社(2001)