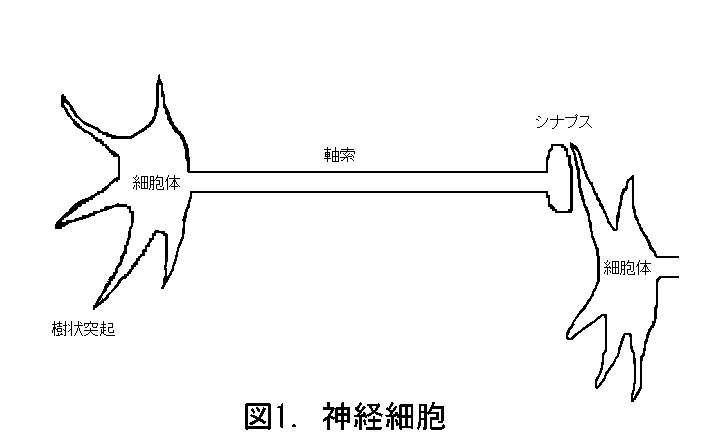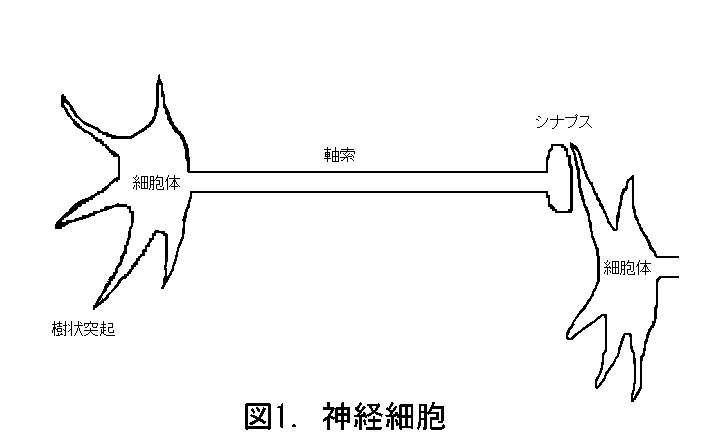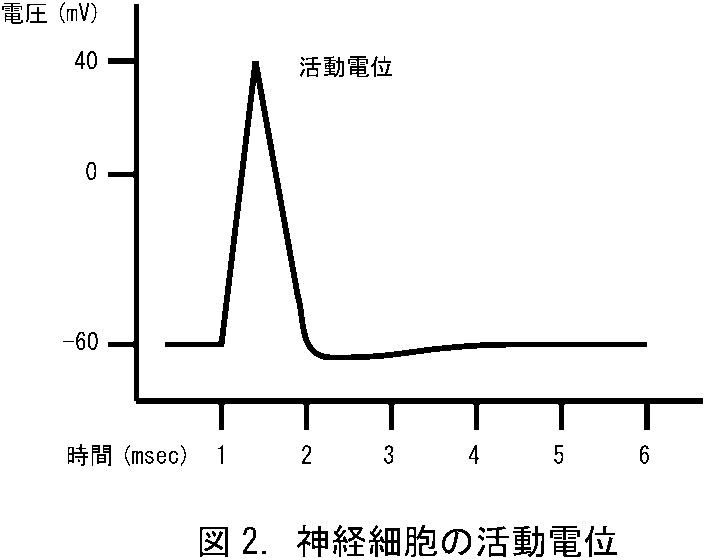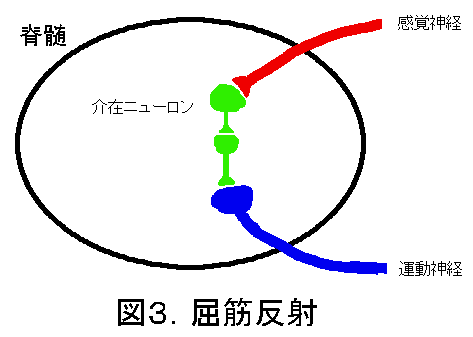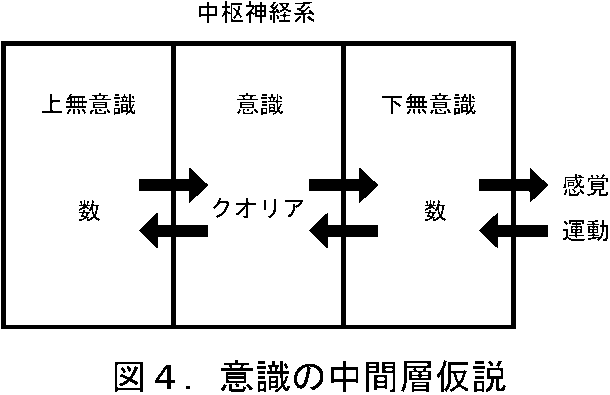感覚と神経細胞の活動電位
自然数「1」と人間で述べたように、神経系の起源は単細胞動物まで遡ります。ゾウリムシが運動する場合は一つの方向にしか進めません。ゾウリムシが進む方向を変えるときには、細胞全体が電気的に興奮します。これは細胞全体を統一的に動かすための方法と考えられます。神経細胞は、そこから進化して情報伝達専門の細胞として特殊化しました。そのため神経細胞は他の細胞と違う特別な形をしていますので、それを図1に示しました。
神経細胞には細胞体がありますが、細胞体には通常の細胞と同じように核、ミトコンドリア、小胞体、ゴルジ体などの細胞内小器官が存在します。神経細胞が特殊なのは多くの突起を持つという点です。図1に示した樹状突起は他の神経細胞からの信号を受け取る場所であって、神経細胞は多くの樹状突起からの信号を受け取りそれを統合します(1)。その結果として細胞体が電気的に興奮すると活動電位が発生します。活動電位は軸索を通じて伝導され、軸索の先端まで伝わります。軸索の先端は次の神経細胞の樹状突起との間にシナプスと呼ばれる接合部を形成し、シナプスを通じて信号は伝達されます。人間の脳のシナプスでは、通常はグルタミン酸やGABAなどが伝達物質として用いられています。
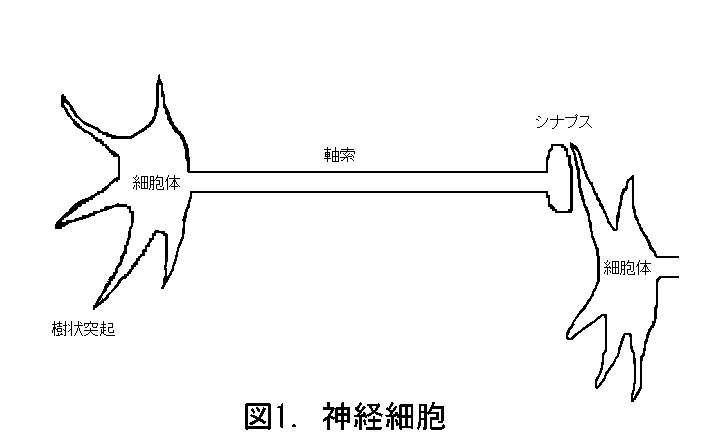
神経系は情報系なので、デジタルかアナログかが興味あるところですが、神経科学から考えるとアナログ-デジタルシステムとなります。詳しい説明は成書に譲るとして、ここでは簡略化して説明します。図2に示したのは、神経細胞内に電極を突っ込んで、神経細胞の電位を記録したのものです。細胞外の電位を0mvとすれば、神経細胞はマイナスに荷電しており、興奮していない状態での電位は約-60mVとなります。神経細胞は細胞外と膜で隔てられており、膜を挟んで電位差が発生するので、これを静止膜電位と呼んでいます。
この状態から活動電位が発生するまでの過程を説明します。最初に樹状突起が他の神経細胞からの信号を受け取ると、樹状突起の一部分が静止膜電位よりもプラスに荷電しますが、この状態では細胞体の膜電位に変化はありません。さらに樹状突起が多数の信号を受け取ると、部分的な膜電位が加算され、ある閾値を超えると細胞全体が一時的に細胞外よりもプラスに荷電します。これを神経細胞の活動電位と呼び、この状態は神経細胞が興奮した状態と考えられています。神経細胞には興奮した状態と興奮していない状態の二つしかなく、中間の状態がありません。その事実を「全か無の法則」と呼びます。神経細胞の活動電位は発生するとほとんど同じ形をしており、図2に示したように静止膜電位との電位差は約100mV、持続時間は約1msecで大体一定しています。
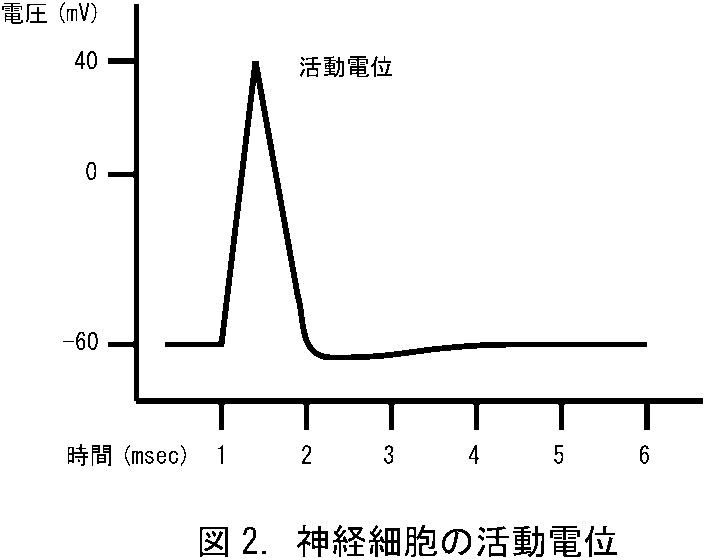
活動電位は自然数「1」と人間で述べたプラトンの三原則を満たします。分割不能ですし、お互いに等しく、一度発生すると減衰することなく軸索を伝わって伝達されます。そこから考えて、数と神経細胞の活動電位で述べたように、神経細胞の活動電位は、生命の「1」としての性質を抽出したものと考えられます。まず活動電位は、どの動物でも同じ信号で、電位と持続時間は全く同じです。昆虫でもミミズでもネズミでも同じであり、人間の活動電位とは区別がつきません(2)。次に活動電位は、神経細胞の種類による違いがありません。運動神経でも感覚神経でも同じであり、さらに感覚の種類による違いもありません。視覚でも聴覚でも味覚でも嗅覚でも、また痛覚でも温度覚でも全く同じです。これはインターネットで世界中を回るコンピューターの信号と似ています。インターネットの信号は、どの信号も全て0か1なのです。
活動電位が発見されるより遙か以前の1868年、ヘルムホルツは神経線維を観察して、電線に類似していると考えました。ちょうど日本で明治維新があった年ですが、大英帝国は七つの海を支配して、世界中に電信を伝える海底ケーブルを張り巡らしており、電線を伝わるモールス信号によって通信を行っていました。モールス信号はトンとツーの二つの信号の組み合わせで成り立っており、アルファベット26文字を表すことが出来ます。例えばタイタニック号が遭難したときに用いられた有名なSOSは、トントントンツーツーツートントントンです。このシステムによって、世界中のどこでも同じ情報を得ることが可能であり、単純なトンとツーの組み合わせで複雑な情報を送ることが可能です。しかも受信する側のシステムによって、音として受信することも可能ですし、紙に記録することも可能です。海底ケーブル網を含む電信システムは大英帝国の世界支配に大いに役立ったと思われます。そして驚くべき事にヘルムホルツは、電信と神経系の共通性を見抜いていたのです。
電信のシステムは現代のインターネットとそっくりですが、一人の人間の神経系はむしろ一台のパソコンと似ています。パソコンの場合、基本的には感覚的性質のある入力を受け付けます。キーボードであればアルファベットなどの文字を入力しますし、マウスであればダイアログボックスのボタンなどをクリックします。さらにマイクを用いれば直接音声を入力できますし、デジカメからは直接画像を入力できます。これらの入力は、全ては0または1を表す電気信号に変換され、コンピューターの内部で処理されます。これは脳が視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚などの感覚器からの入力を、全て活動電位として受け取るのと類似しています。
人間の神経系では、脳での情報処理の結果は活動電位として運動神経に送られ、何らかの運動が行われますが、その中には音声として出力される言語も含まれます。コンピューターの場合は、内部での情報処理の結果は、プリンターやディスプレイ、スピーカーなどの出力装置に送られ、最終的には文字や画像や音声として出力されます。コンピューターに感覚はありませんが、感覚的性質のある信号を受け取り、感覚的性質のある信号を出力します。このように神経細胞の出力である活動電位は、コンピューターの電気信号と類似しており、明らかにデジタルです。
それに対して神経細胞への入力はアナログ的に処理されます。入力として神経細胞は多くの活動電位を受け取ります。それにより樹状突起は部分的に電位変化を起こし、電位変化は細胞体に伝わります。細胞体では部分的な電位がアナログ的に加算されて、閾値を超えた時点で活動電位が発生すると考えられています。このように神経細胞はデジタル信号を受け取り、それをアナログ的に処理し、それを活動電位というデジタル信号として出力します。ただ一部には活動電位に達しない電位を伝達に用いています。よく知られたのは網膜ですが、最近では大脳にもアナログ的な出力があることが知られています。これらは網膜内のようなごく近距離での情報伝達に用いられており、長距離の信号伝達は軸索を伝わる活動電位に限られます。例えば網膜から脳への信号も、視神経を伝わる活動電位です。それ以外の中枢神経への感覚入力も、運動神経を通じての出力も、ほとんど全てが軸索を伝わる活動電位です。
次に神経細胞の活動電位が具体的行動とどう関係するのか、比較的単純な脊髄反射について、なるべく簡単に述べてみます。屈筋反射という多シナプス性の脊髄反射は、痛いときに自動的に手を引っ込める反射です(3)。指先を虫に刺されたとき、熱いものにさわってしまったときなど、手に侵害刺激を受けたとき、人間は自動的に手を引っ込めます。この反射は刺激の強さによって動作の大きさが異なります。例えば少し熱いストーブをさわった場合、ちょっと手を引っ込めるだけです。肘と手首の関節ぐらいしか動きません。ところが、非常に熱いストーブを触った場合、腕全体をすごい勢いで引っ込めます。このように侵害刺激が強くなると、回避運動が大きくなるのです。
この反射において活動電位の役割を考えてみます。まず屈筋反射の第1段階で、侵害刺激は痛覚、温覚、冷覚など、全く物理的性質が異なりますが、それらは全て感覚神経の活動電位に変換されます。次に脊髄の介在ニューロンの受け取る活動電位の数によって、どの範囲の屈筋が収縮するかと、収縮の強さが決定されます。侵害刺激が強いほど活動電位の数は多くなり、侵害刺激が強くなるに従って運動は大きくなります。
このときに介在ニューロンの活動電位の意味を考えてみます。介在ニューロンは、温覚、冷覚、痛覚などの感覚神経からの活動電位を受け取ります。また介在ニューロンからの指令によって運動神経が発火します。こう考えると、介在ニューロンの活動電位は温覚、冷覚、痛覚などの感覚を表しているとも、運動を表しているともいえます。つまり介在ニューロンの活動電位自体には、感覚的性質も運動としての性質も無いことになります。これはコンピューターのデジタル情報と同様であり、抽象的な「1」に非常に近いといえます。
活動電位が抽象的な「1」に近いことを利用して、色々な種類の侵害刺激の強さと回避運動の大きさを比例させることが出来ます。例にあげた熱さであれば、より熱いほど回避運動は大きくなります。これが痛覚であれば、痛みが強いほど回避運動は大きくなります。どちらの場合でも侵害刺激が強いということは、より危険であるということなので、回避運動が大きくなるのは理にかなっています。この例では脊髄で活動電位を用いた計算が行われたと解釈できます。脊髄における屈筋反射の経路を単純化して示したのが図3です。感覚神経を赤で、運動神経を青で、介在ニューロンを緑で示しました。侵害刺激は感覚神経の活動電位として脊髄に入り、介在ニューロンによって処理されて、運動神経の活動電位として出力され、回避運動が行われます。
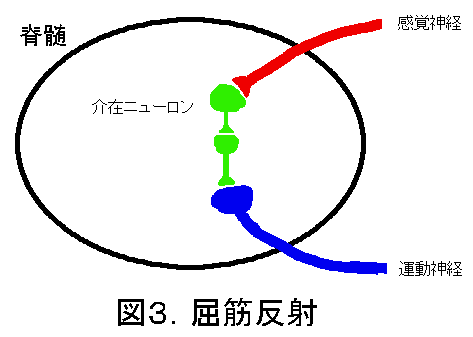
人間の認識の主体である自我が直接認識できる範囲を意識といい、自我が直接認識できない神経細胞の活動を無意識といいます。数と感覚で述べたように、意識は、視覚、聴覚、触覚、味覚などの感覚を通じてしか世界を認識できず、直接的に活動電位を認識できません。先程のストーブを触って手を引っ込める反射でも、意識は自分で熱さを感じて手を引っ込めたと解釈します。活動電位を用いた計算は無視され、熱さの感覚と手を動かしたことだけが認識され、意識によって解釈されます。人間の自我が感覚的性質を持たない活動電位を、直接認識出来ないからです。
そのため屈筋反射における脊髄での計算だけでなく、複雑な運動をするときの脳での計算も意識できません。例えばプロ野球の外野手の場合、バッターが外野フライを打ち上げた場合、素早くフライの落下点に到達し、ボールをキャッチします。そのためには風の影響も入れて、ボールの軌道を計算しなくてはいけません。これは非常に複雑な計算ですが、その内容は全く意識されません。外野手に訊いても、どうして落下点に到達したかは説明できません。バッティングの名人の場合でも同様です。この場合はピッチャーの投球フォームをよく観察し、ボールが手から離れて間もなく、ボールの軌道を予測してバットスイングを開始しなくてはいけません。それには複雑な微分方程式を解く必要があります。ところが計算の内容は全く意識化されません。
このような無意識の高速な計算システムを、クリストフ・コッホは著書「意識の探求」(4)の中で、ゾンビ・エージェントと呼んでいます。ゾンビは外見は全く人間と同じで魂が存在しないので、クリストフ・コッホは意識にのぼらない中枢神経系のシステムの意味に用いています。
それに対して意識は世界を感覚を通じて認識します。その感覚の中心となるのがクオリアです。クオリアは赤い色を見たときに感じる、あの「赤い」という感じであって、それを直接他人に伝えることは出来ません。言葉にするしかありませんが、ニュアンスは失われてしまいます。分かり易い視覚ですらそうなので、これが味覚ともなると余計に伝えにくくなります。例えば辛さなどは、辛い物好きな人とそうでない人で全く感じ方が違っていて、私が辛くて食べられないラーメンに唐辛子を入れる人もいます。また関西人と関東人では味の感じ方が違いますが、それをお互いに話し合っても、言葉だけでは伝えられません。つまり同じ物を食べても、他人がどんな味を感じているのかは、知ることは出来ないのです。そのため職人が味を伝授する場合、例えば旨味という言葉だけでは何のことか分からず、真の旨味を知るには長年の修行が必要となります。このようにクオリアは他人に伝えることが出来ません。
次に意識の内容には必ずクオリアを伴います。脳で思考をする場合でも、多くの人は音声言語を用いて思考するか、視覚的イメージを用いて思考する場合が多いと思われます。他の感覚を用いる場合はあっても、感覚的性質を持たないものは意識化できません。そうすると意識とゾンビ・エージェントの関係はどうなっているのでしょうか。この問題を考える場合、非常に魅力的な仮説をクリストフ・コッホは紹介しています。それが図4に示したジャッケンドフの意識の中間層仮説です(5)。
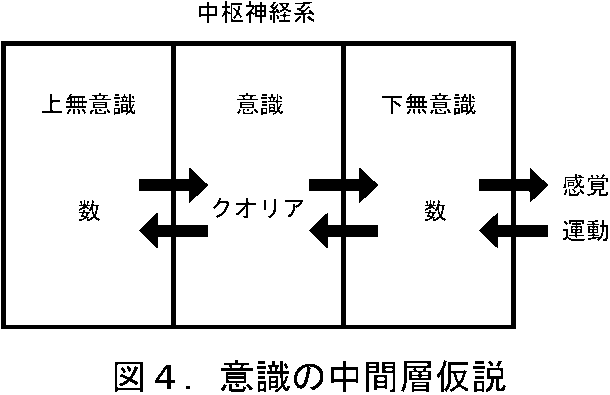
ジャッケンドフの仮説によると、屈筋反射のように脊髄で無意識に行われる反射は下無意識に属することになります。これには多くの動作が含まれます。野球のバッティングなどは大脳も用いますが、ほぼ感覚から運動への直結であって、意識の関与する割合は少なくなります。このような場合は、むしろ意識が関与すると、運動が上手に出来ません。オリンピックの体操競技などを見ると、それを強く実感します。いつもは簡単に演技を行う選手が、メダルがかかってくると途端に緊張して失敗してしまうのを、私は何回もテレビで見ました。自分でも経験がありますが、意識するまいと思うほど意識してしまい、動作はぎこちなくなってしまいます。このような動作は、感覚を受け取って無意識に運動を行うゾンビ・エージェントに、任せるのが良いのです。
例えば屈筋反射を考えると、屈筋反射は脊髄反射なので、意識が関係出来るのは屈筋反射が終わった後の解釈だけで、屈筋反射そのものには意識は関与できません。そのおかげで屈筋反射の一番少ない反射弓ではシナプスはたったの3個です。そして介在ニューロンの活動電位には感覚的性質がなく、純粋な「1」に近い活動電位を用いているので、意識には認識できません。その代わり余分な神経細胞の興奮がないので、それだけ速度が速くエネルギー効率も良いのです。これは図4では、右側の感覚入力を下無意識が受け取って数に変換して計算し、その結果を運動出力するということになります。
今度は高次の思考について考えてみます。ジャッケンドフの仮説では、高次の思考を担当するのが上無意識です。クリストフ・コッホによると、上無意識は前頭葉にあって、脳の後方から大量の感覚入力を受け取り、判断を行って、それを運動に関連した部位に送り出しています。この中枢をクリストフ・コッホは小人にたとえて非意識ホムンクルスと呼んでいます。
上無意識の働く例を考えてみます。私は囲碁と将棋が趣味ですが、囲碁にしても将棋にしても、手が勝手に浮かんでくるのであって、どのように考えて手が浮かぶのかは意識化できません。それは何日もかかるような、数学の難しい問題を考える場合でも同じです。ある時に解き方が浮かんでくるのであって、その過程は意識化できません。つまり高次の思考は上無意識が行っているのであって、意識はその結果を利用していることになります。ところが上無意識は簡単には仕事をしてくれません。例えば将棋であれば必死で意識的に手を考えるという行為が必要です。そうして考えているうちにフッと手が浮かぶのです。さらにそれまでに練習が必要です。何回も意識的に詰め将棋を考える等の訓練を行い、無意識に手が浮かぶ段階まで、熟練しなくてはいけません。事前に訓練しておいて、さらに将棋の対局中にも意識を用いて必死で考えます。そうすれば上無意識が良く働くようになり、手が見えるようになります。この例から考えると、上無意識を上手く働かせるには意識が必要だということが分かります。そこで上無意識がどう情報を処理しているかですが、これは脊髄反射ほどよく分かっているわけではありません。ただ感覚によって把握できないことから考えると、やはり純粋な数に近いものを用いているのではと考えられます。
さらに意識の役割を考えるために、自動車の運転を例にとってみます。最初に運転免許を取るまでの間は、全ての動作を意識的にしなくてはなりません。まずブレーキとアクセルの位置、踏み込み方、さらにハンドル操作など、全てを意識しても上手く運転は出来ません。なかなか上達はしませんが、失敗を繰り返すうちに上手くなります。経験が蓄積されて慣れてくると、全く意識せずに運転できるようになります。さらに慣れた道であれば、完全に道順も覚えてしまい、ほとんど何も考えずに目的地に到達できます。それどころか渋滞状況によって道順を変えることすら、ほとんど無意識に出来てしまいます。こうなるとかなり高次の機能までが自動化され、ゾンビ・エージェントに任されます。その時には意識を素通りして上意識も関与していると思われます。
それほどのベテランでも、初めての道を運転する場合は、意識的に道順を考えて運転する必要が生じます。ここで理解されるのは、意識は新しい状況に出会ったときに、ゾンビ・エージェントを訓練するのに必要であるということです。結論として意識は、ゾンビ・エージェントを導く司令官の役割をしていると考えられます。ただ中枢神経系に入る情報は膨大なので、情報を要約してから判断しなくてはなりません。情報の要約をクリストフ・コッホはエグゼクティブサマリーと名付けています。アメリカではエグゼクティブとは大統領という意味がありますので、レーガン大統領が側近に、大統領が判断しなければならないことを1ページのレポートに要約させたという話から、この名前が付けられました。
次に問題になるのは、エグゼクティブサマリーは何故クオリアによって構成されているのかです。これは難問で、クオリアが不利な点は多く上げることが出来ますが、クオリアの必要性を説明するのは困難です。ゾンビ・エージェントが高速であるのに、意識は低速です。意識がクオリアを必要とするのも、大きな速度低下の一因となります。クオリアを引き起こすには、多くの神経細胞の興奮が必要だからです。さらにクオリアによって世界を認識するため、意識による世界認識は不正確になりやすいのです。その点については、プラトンの対話編においてソクラテスが何回も指摘しています(6)。それに対して、ゾンビ・エージェントによる世界認識は、コンピューターと同様に数学的で正確です。それは活動電位の「1」としての性質を用いているからです。さらにクオリアを必要としないので、高速でもあります。
身近な例を挙げてみましょう。人間は坂道の下に立つと、坂道が実際よりも急角度に見える傾向があります。この事実に関して、コッホはデニス・プロフィットの実験(7)を紹介しています。プロフィットは丘のふもとで、通りがかかった学生に、口頭、視覚、手の三種類の方法で丘の角度を見積もってもらったのです。その結果は、口頭と視覚では被験者は丘の角度を非常に過大に見積もりました。これは富士山に近づいてみても分かることで、北斎の秘密で触れたように冨嶽三十六景における富士山の傾斜は近づくほどに急になります。これは坂道を上から下に見た場合も同様で、急な坂を下る場合、ものすごく急角度に見えて恐怖を感じます。これは人間の認識の一般的傾向のように思われ、人間は坂道の角度を正確には認識していないという結論が、正しいように思われます。ところが手で見積もってもらったときに、驚くべき結果が得られました。最初に被験者を自分の手が見えない状態にして、視覚の影響を除きます。その状態で被験者に手で坂の角度を示してもらうと、ほぼ正確に丘の角度を見積もったのです。これはゾンビ・エージェントの仕業です。ゾンビ・エージェントは正確に体を動かす必要があるので、正確に世界を認識しています。この場合は坂を登ることに備えています。その状態で手を見えなくして意識の影響を除いたので、手はゾンビ・エージェントに従ったのです。ゾンビ・エージェントは計算に活動電位を用いており、世界を数学的に正確に認識していると考えられます。
現実世界においてゾンビに近い存在は、意識やクオリアを全く持たず動作するコンピューターです。人間の中枢神経のゾンビエージェントは、デジタルーアナログシステムですが、コンピューターは純粋なデジタルマシンです。ここでコンピューターと人間を比較することによってクオリアについて考えて見ます。コンピューターと人間の違いを明確に示したのは、チェスの名人であるカスパロフと、IBMのコンピューターであるディープブルーの戦いですが、最終的にはディープブルーの勝ちとなりました。これは私にとっては大変なショックとなった出来事です。私は将棋が大好きなので将棋には思い入れがあり、人間対コンピューターのチェスの勝負にも関心がありました。私自身は将棋にも常にクオリアを感じています。優れた手順には美を感じますし、それぞれの駒も何となく生き物のように感じます。カスパロフもやはりチェスの手にクオリアを感じていたようで、それが敗因になったように思われます。コンピューターはクオリアを持たず、意識も感情も無いのですが、カスパロフの方が勝手に相手の手にクオリアを感じ、相手に人格を感じてしまったのです。それが最終的にはカスパロフを心理的に追いつめ、カスパロフの心理的な憔悴が敗因となりました。
ここまでの話では、クオリアは全く無駄な上に感情を動揺させるので、チェスの対戦には邪魔なもののように思われ、チェスではゾンビの方が有利となります。それではあまりに悲しすぎるではありませんか、何とかクオリアの利点を探してみます。この対戦に敗れたとはいえ、カスパロフにはディープブルーに勝っている点があります。ディープブルーは1秒間に2億手を読みますが10手先ぐらいまでしか読めません。それはシラミつぶしに読めば、手数が長くなるにつれて読む手が天文学的に増えるからです。それがカスパロフは20手以上先を読むことも出来ます。カスパロフには直感的に正しい手が見えるので、読む範囲を絞ることが出来るからです。これはおそらく一種の美意識によるので、クオリアが関与しているのではと考えます。これがクオリアの利点の一つである可能性があります。
それでもディープ・ブルーよりもはるかに優れたコンピューターが出来て、初手から終局までチェスの全ての手をシラミつぶしで読めるようになったとしたら、人間がそのコンピューターと対戦すれば必ず負けます。そのときにはチェスに関するクオリアは完全に無意味となります。それこそ悲しむべき出来事ですが、いつかは現実にそうなる可能性はあります。このように考えてみて、私は次のような結論に到達しました。クオリアの存在意義を知るには、合目的的に考えるよりも、より深く神経細胞の特性を研究すべきでしょう。
参考文献
(1) 宮川博義・井上雅司:ニューロンの生物物理,丸善(2003)
(2) J. G. Nicholls et al.: From Neuron to Brain 4th ed., Sinauer Associates,Inc.(2001)
(3) E. Kandel et al.: Principles of Neural Science 4th ed., McGraw-Hill(2000)
(4) C.コッホ:意識の探求,土谷尚嗣・金井良太訳,岩波書店(2006)
(5) R.Jackendoff:Consciousness and the Computational Mind, MIT Press(1987)
(6) プラトン:国家, 藤沢令夫訳,岩波文庫(1979)
(7) D. R. Proffitt, M. Bhalla, R. Gossweiler, J. Midgett: Perceiving geographical slant, Psychonomic Bulletin & Rev., 2, 409(1995)