MUSIC ARRANGE
作・編曲講座 Vol.
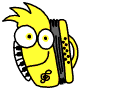
さてさて、C藩のお殿様のC大名をはじめとして、G筆頭家老・F次席家老他のご家来衆の話。
ここで大切ですので、C藩の名簿をもう一度おさらいしておきましょう。
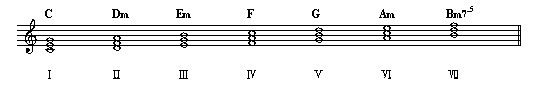
このお話は、主要三和音(Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ)と副三和音(Ⅱ・Ⅲ・Ⅵ)、それと元服前の(Ⅶ)の和音が主人公のC藩のお方たちです。
このお方たち・・・・かっこよく言えば、Cメジャーの「固有和音」です。
(それぞれの和音の機能説明はVol.2に書いています)

「借用和音」
もう一度確認しますが・・・・C藩はお殿様と筆頭家老と次席家老(主要三和音)とご家来衆(副三和音)と筆頭家老のG大老おあずけの元服前の(Ⅶ)和音のお方たちで成り立ってすが、この人数だけですと少人数すぎて、いざ戦いが始まったりしたら軍の人数が足りません。たちまち敵の軍勢に蹴散らされてしまうでしょう。
おえええええええっ・・・やべっ!
そこで、平時はご家中の家来だけでいいが、イザと言う時に頼りになる助っ人が欲しい・・・・
つまり、よその藩から助っ人を頼んだり浪人を雇い入れたりしたい・・・・・が。
が~、せっかく助っ人で雇っても反乱を起こされてお家をのっとられたり(転調)、ご家中でのよけいなもめごとを招かないようにしなければなりません。
また、助っ人の必要がなくなったらさっさと藩から出て行ってもらうことも大切です。
「安全有利な助っ人の頼み方」
しかし、助っ人が欲しいとは言え縁もゆかりもない所から借りてくるわけにはいきません。
しかるべき所から、しかるべき手続きをふんで借りて来る必要があります。
もちろん身元引き受け人も確かなお方が必要です。でないと・・・・・・・・・・
ここで・・・・LESSON 1でのドミナント・モーションを思い出してみましょう。
属和音(Ⅴ7)→主和音(Ⅰ)が和声進行の元祖で、強い説得力を持つ和音進行と言いましたが、ならばこれを利用して借用手続きをしましょう!!ご家来衆の親戚筋だと身元もはっきりしてるし。。。
ん、ん、それがいい、それがいい。
Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵを主人として、このお方たちの知り合いがさらに家来として仕えるというのはどうでしょう・・・・
まっ、例えばⅡのご家来衆の家に仕える下働きの家来?みたいな。。。。ねっ、ねっ。
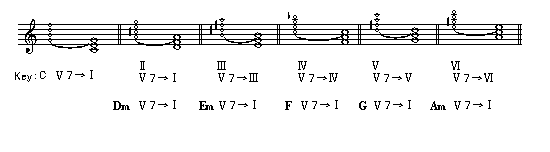
Ⅱの和音で例えて言えば: Ⅱの和音(Dm)を二短調のⅠと考え(Ⅱの和音はC調の副次調といいます)
これにドミナント・モーションするⅤ7の(A7)は副次調に仕える副Ⅴの和音といいます。
Ⅱ
つまり、A7はⅡの武士宅に居てⅡの和音に仕えるのでⅤ7と表します・・・・・
(Ⅱに行くためのⅤ7です)
Ⅴ
ちなみに大老のⅤ7(G7)に仕える家来はD7で Ⅴ7と表します。
(Ⅴはもともとドミナントですが、そのまたドミナントなのでダブル・ドミナント(ドッペル・ドミナント)と呼ばれます。)
だんだんと話が込み入ってきました・・・・・??
しかし、まだまだ、江戸時代の話は続きま~~~~すっ。。
次回はC藩以外の、お隣の藩やその他の藩の話をしましょう。。。。。。
あっ、この時代 ・・・・・・なんと30ものお藩がありましたとさっ。。。
そう、長調と短調を合わせると30の調(藩)が存在する話は次回。