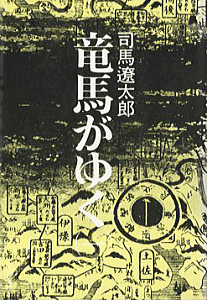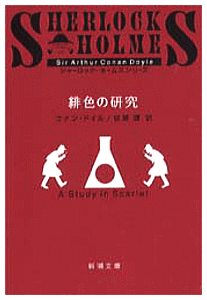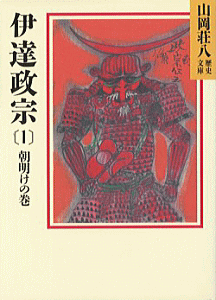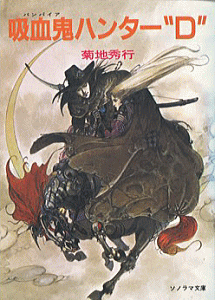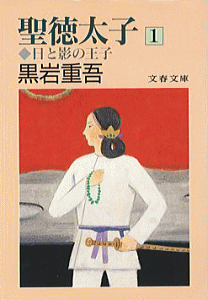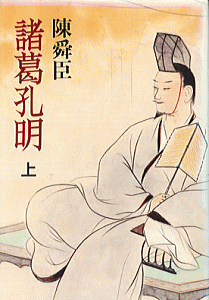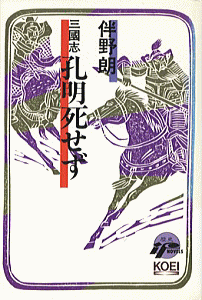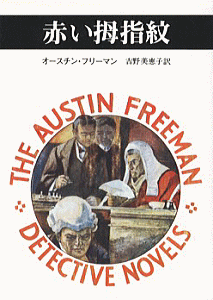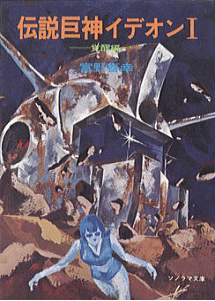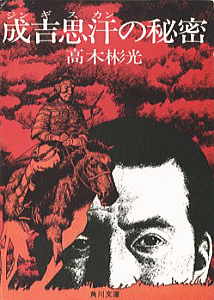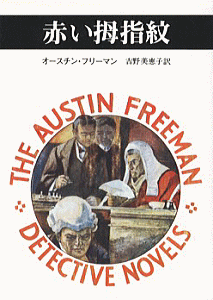 |
| 赤い拇指紋 |
| 原 題/The Red Thumb Mark |
|
| 著 者 |
リチャード・オースチン・フリーマン〈略 歴〉 |
| 訳/吉野 美恵子 〈略 歴〉 |
| 種 類 |
Mystery |
| 初 出 |
1907年 |
| 巻 数 |
全 壱 巻 |
| 出 版 |
東京創元社 |
| 創元推理文庫 |
| ── Story ── |
| ロンドンの貴金属会社で、金庫からダイヤモンド盗まれるという事件が起こった。現場に落ちていた紙には、見紛う事の無い血染めの指紋が残されていたが、この指紋が一人の青年ルーベンの左手の親指とピッタリ一致したのだ。彼は経営者の甥で、いずれもう一人の甥と共に共同経営者になるはずだった。警察に突きつけられた動かぬ証拠。しかし、無実を主張するルーベンは法医学の権威であり、弁護士の科学者探偵ソーンダイク博士へ事件の調査を依頼した。彼は、旧友ジャーヴィス、助手ポルトンと共に調査を始める。果たしてソーンダイクは完璧な証拠を打ち破り、ルーベンを救う事が出きるのだろうか? |
|
疑問があるときはソーンダイク博士に忠実であれ
── アメリカの作家 クリストファー・モーリー ── |
リチャード・オースチン・フリーマンが創造した探偵「ジョン・イヴリン・ソーンダイク博士(Dr.
John Evelyn Thorndyke)」が活躍する探偵譚は、推理小説の中に本格的な科学捜査を取り入れたことから「科学探偵小説の祖」と言われています。
この『赤い拇指紋』はソーンダイク博士が始めて登場した作品です。
タイトルの通り、事件は指紋を巡る犯人とソーンダイクと警察のせめぎあいなのですが、フリーマンがこの作品を書いたキッカケは、イギリスの人類学者であり優生学者であるサー・フランシス・ゴールトンが唱える指紋の〝終生不変〟〝万人不同〟を重要視しすぎ、他の可能性を低く見ることの危険性を世に問うためだったそうです。現場に指紋があっても、その指紋の持ち主が必ず犯人であるとは限らないのですから。因みに、ゴールトンは進化論で有名なチャールズ・ダーウィンの従兄弟。
ソーンダイク博士が登場した時代。それはシャーロック・ホームズが名探偵の名を欲しいままにしていた頃。同時代、数多く登場したホームズのライバルの中で、ソーンダイク博士は最も有名な探偵でしょう。
調査には顕微鏡や指紋採取用具等が詰め込まれた緑色の実験箱を携帯し、現場に臨むと証拠を収集・分析し、医学的・科学的知識に基づき推理を組み立て事件を解決する
─── ソーンダイク譚が「科学探偵小説」と言われる所以です。小説ではこのような捜査方法や知識を多用しているにも関わらず、そのような知識を殆ど持たない読者を納得させられるのは、思いついた数々のトリックを、著者フリーマン自身が友人とともに実験し、その結果を読者に判りやすく描いているためでしょう。だからこそ説得力が感じられるのです。
また、物語にはジャーヴィスという医師の友人が登場しますが、彼が事件を記録する形を取っている所はホームズに似ています。ジャーヴィスはこの事件がキッカケで結婚しますが、これもホームズの『四つの書名』を思い出させます。尤も、主人公の活躍とそれを記録する平凡な人間のコンビという「ホームズとワトスン」のパターンは、ホームズ登場以降、現在まで続く「推理小説の王道」になりましたが(笑)。
ソーンダイク博士が登場する小説は著者が八十歳を過ぎるまで書き続けられ、全部で21の長編と40の短編がありますが、その多くが未邦訳です。是非、全部読んでみたいので、どこかの出版社さん!完全翻訳出してくれませんかねぇ・・・ |
| 2004.12.12 sun 改 |
|