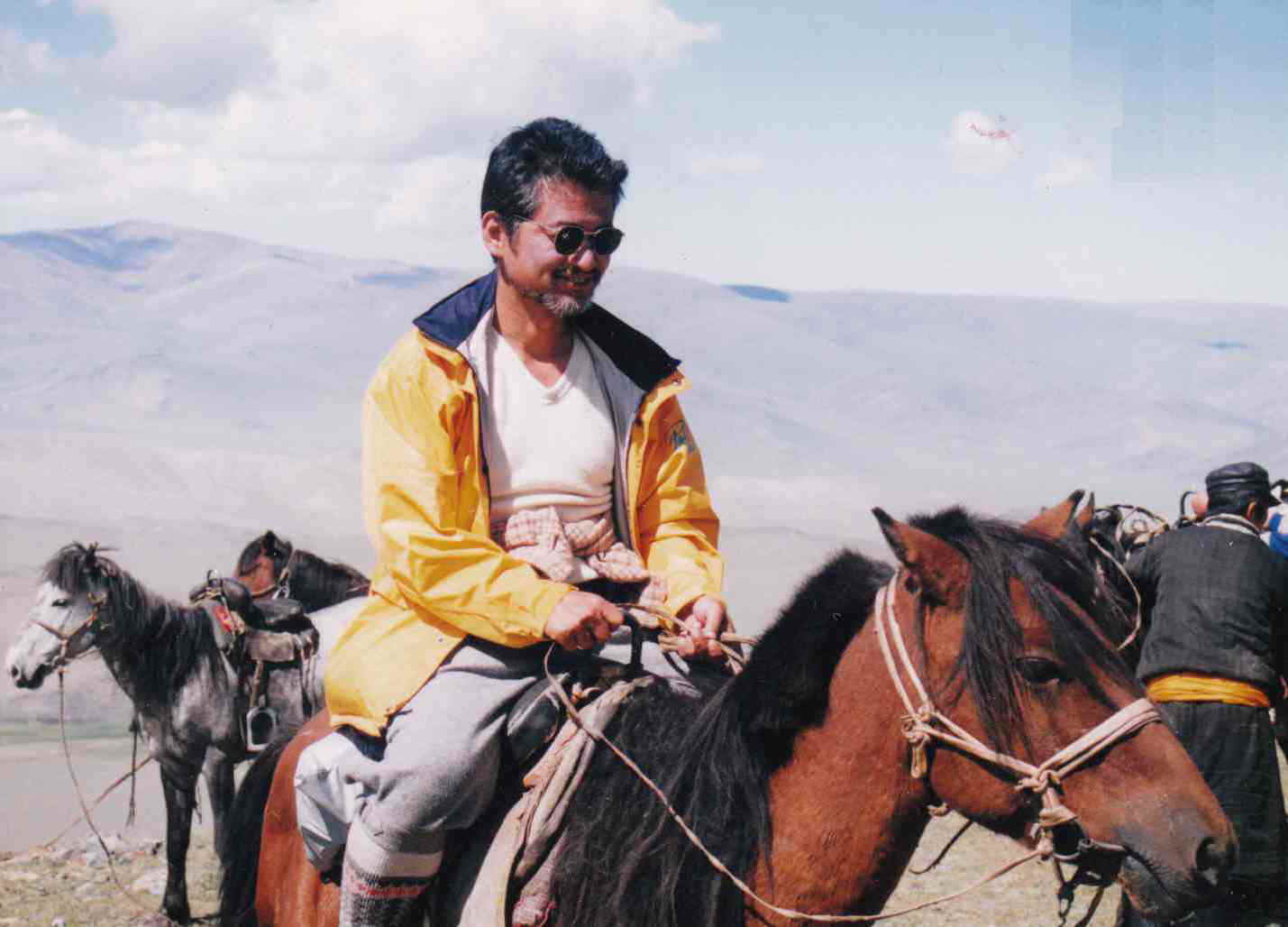鹿島神宮 香取神宮の三つ穴灯篭と六芒星
六芒星とは
六芒星は△と▽を組合わせたものですが、ダビンチコードでは▽が陰、女性を表し、△が陽、男性を表すという説を紹介しています。![]() ダヴィンチコード キリストの子孫 六芒星
ダヴィンチコード キリストの子孫 六芒星
![]() ユダヤの六芒星と日本の六芒星
ユダヤの六芒星と日本の六芒星
伊勢神宮の六芒星

 六芒星が伊勢神宮の参道の灯篭に彫られています。五十鈴川駅から伊勢神宮までの参道の全てに写真の六芒星が刻まれています。
六芒星が伊勢神宮の参道の灯篭に彫られています。五十鈴川駅から伊勢神宮までの参道の全てに写真の六芒星が刻まれています。
![]() 伊勢神宮の六芒星
伊勢神宮の六芒星
日本では伊勢神宮と六芒星について論ずるのはタブーのような気がします。
香取神宮


香取神宮は、千葉県香取市にあり、全国にある香取神社の総本社です。香取神宮には∴三つ穴灯篭があります。三郷市の香取神社の多くにも∴三つ穴灯篭があります。
鹿島神宮


鹿島神宮には∵の三つ穴灯篭と∴の三つ穴灯篭がありますが、別々に配置されています。
∴と∵がセットで対になっている三つ穴灯篭
三郷市の丹後神社にも∵の三つ穴灯篭と∴の三つ穴灯篭がありますが、∴と∵がセットで対になっています。私の知っている限りでは、∴と∵がセットで対になっている三つ穴灯篭があるのは三郷市の丹後神社だけです。このセットの配置の意味は不明です。

神宮がつく神社
平安時代に「神宮」がつく神社は、伊勢神宮、香取神宮、鹿島神宮の3つでした。この三つの神宮の灯篭には、六芒星に関係するような紋様が刻まれています。これは偶然でしょうか。
鹿島神宮と香取神宮は辺境の地です。辺境の地の神社に神宮の名前を許して、さらに六芒星に関係するような紋様が刻まれている灯篭があります。灯篭に謎めいた彫刻をした人たちの意図は何だったのでしょうか。
鹿島神宮と香取神宮
10世紀はじめの平安時代に作られたという法典、延喜式によると、当時から「神宮」と呼ばれていたのは伊勢神宮、鹿島神宮、それに香取神宮の三つの神宮だけであるという。伊勢神宮は当時のヤマト政権に比較的近い地理にあるが、鹿島と香取は当時の感覚では、まさに辺境の地である。
明治以降の神宮がつく神社
- 熱田神宮。明治元年に熱田神社から熱田神宮に名前を改めました。
- 平安神宮。平安神宮は明治28年に創建されました。
- 明治神宮。1912年(明治45年)に明治天皇が崩御し、1915年(大正4年)5月1日、明治神宮を創建することが内務省告示で発表されました。
麻賀多神社の三つ穴灯篭
鹿島神宮、香取神宮から、そう遠くない成田の麻賀多神社(まかたじんじゃ)に三つ穴灯篭があるようなので、調査します。
最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。