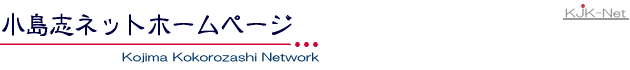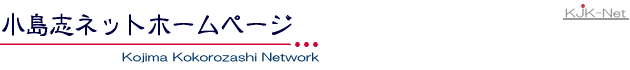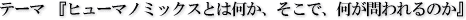
□話し手 後藤 隆一先生 『人間主義経済学序説』著者
□聞き手 山本 克郎 「小島志ネットワーク」代表幹事 |

ロエブルのヒューマノミックス−その2
−ロエブルのパラダイム論と社会システム論−

前回はロエブルの人生と思想形成の背景について伺いましたが、今回は理論の内面に入って、その体系の二つのテーマであるパラダイム論と社会システム論についてお願いいたします。
この問題に入る前にいくつかの質問をお許し頂きたいと思います。現在、私達日本人にとって、一番大事な課題は、パラダイム論だと思います。パラダイムとはものの見方、考え方ですが、私達の意識は予め思想的な枠組みを前提にしている場合が多いと思います。それも時代とともに変わっていきます。
戦前は、教育勅語というものが価値観の枠組みとして小学校の段階からインプットされました。それは、日本的な儒教道徳でした。しかし、大学教育を始めとし、学問の世界を支配して来たものは、近代ヨーロッパの哲学であり、社会科学でした。敗戦後、それが、一挙にアメリカナイズされ、そのパラダイムが、一度も問われることがありませんでした。
21世紀に入り、小泉政権が出現して改革を叫び、グローバル化の中で規制緩和が進みました。それは、日米同盟を基軸とした金融自由化、米国産軍複合体という体制に深くコミットすることになりました。これは、時代の逆行ではないのか。ソ連型社会主義が10年前に消滅したが、次は、アメリカ型ケインズ主義の破綻する番ではないのか。というのが、ヒューマノミックスの立場からの予感でした。
改革の必要性は万人の認めるところですが、誰のための、何のための改革か。その内容が問題なのです。改革のパラダイムの問題だと思いますが、如何でしょう。
次の問題は、後藤先生の人間主義経済学序説の第二部「マルクスとウェーバー」で学んだことですが、パラダイムと社会システムという概念は、近代ヨーロッパの自己認識である社会科学の二つの流派、つまり、ドイツ観念論とイギリス経験論という二つの哲学を原点とする流れであり、それは、キーワードとして対立するものとされてきました。
パラダイムとは、マックス・ウェーバーの主体の論理であるエートスにあたり、シューマッハーの価値観、人間観にあたり、ともに認識や思考方法の枠組みでした。それに対して、システムとは、マルクスの客体の論理にあたり、客観的な法則の世界の論理であると考えられてきました。前者は、ドイツ観念論、または認識論をベースにし、後者は、イギリス経験論を基礎とした理論になっています。これは、対立概念にほかなりません。
それをロエブルは、同一の社会の主体の論理と客体の論理として統合していますが、この変化の意味するものは何かという問題です。
三つ目の質問は、シューマッハーは「価値観は、形而上学の問題で、科学の教えるものではない。それは、宗教や哲学の問題である。したがって、価値論や意味論を対象とする文化科学の使命は大きい。それ故、人間観のない文化科学は存在意義がない」と言っています。ここで、社会科学や教育の根本に、価値観、人間観の問題として、宗教や思想が登場してきます。しかし、天皇制神話を信じて突入した戦争に負けた日本人は、宗教に対して強いアレルギーを持っています。戦争後の日本には、教育や社会科学から、宗教を排除しようとする傾向がありました。
私の考えでは、「人間とは何か」、「人は何処から来て、何処へ行くのか」、「命とは何か」、「生と死」という一番大事な問題を探求して来たのは、宗教と哲学だと思います。それらの教えや論理、形而上学、哲学が求めてきた世界観、人間観もパラダイムの構築には不可欠の知的資産と思います。
同時に私は、20世紀の生命科学の研究が齎した「人間とは何か」、「命とは何か」についての成果に注目しています。それは、生命が地球上に如何にして誕生したか、生命の誕生から人間の誕生まで、人間誕生から現在に至る生命進化のプロセスとその法則は、生命とは何か、人間とは何か、の実証的な解明に貢献する成果と考えています。
少し長くなりましたが、先生のご見解を伺いたいと思います。

ご質問に対するお答えからはじめましょう。第一のパラダイム論が大事だというご意見について、まったく同感です。一言付け加えるなら、パラダイムとは、自然法則ではなく、人間の作ったもので、社会の共有する仮説です。それ故、最高を求めて努力すべきものですが、代案に対して開かれたものでなければなりません。第三者に対しても、明確なパラダイムを提示することは、文化社会の責任なのです。
第二のパラダイム論と社会システム論は、近代ヨーロッパ社会が自己認識の学としての社会科学の方法論を求めるに際して、一方でドイツ観念論哲学から、他方でイギリス経験論哲学から求めました。前者から生まれたのが、マックス・ウェーバーの主体論的社会学、文化論的社会学であり、そのキー概念が、エートスと呼ばれたパラダイム論でした。後者から生まれたのが、カール・マルクスの客体論的唯物弁証法であり、そのキー概念が、社会システム論です。したがって、パラダイムと社会システムという概念は、対立する哲学の中で、対立する役割を果たしてきた概念でした。
それが、ロエブルや私のヒューマノミックスにおいては、同一存在の二面性として統一されています。それを基礎づけるドイツ観念論とイギリス経験論以外の哲学があるのか。という質問になると思いますが、私の場合、法華経の生命哲学なのです。不思議ですが、ロエブルの11年間の獄中の思索から生まれた近代ヨーロッパの行き詰まりを超える思想は、法華経の空、仮、中の三つの真理観と一致しているように思います。
これから論ずるロエブルのパラダイム論は、ドイツ観念論でもイギリス経験論でもありません。この二つを統合する生命哲学です。そして、その意味的体系の根本は、西洋哲学ではなく、東洋哲学に見出されるものです。つまり、ヒューマノミックスの理論体系は、ロエブルを媒介として生命哲学によって基礎づけられるのですが、詳しくは後論に譲ります。哲学的最重要問題だということだけは申し上げておきたいと思います。
三つ目のご質問は、「社会科学は、宗教や思想にどう対応すべきか」という問題ですが、日本人にとって弱いところだと思います。エコノミック・アニマルと言われ、宗教音痴、哲学音痴と言われてきたのは、戦後の異常な状態に影響されているのでしょう。セクショナリズムとかファンダメンタリズムと言われるものは別として、宗教を差別してはならないと思います。
私の場合、法華経の研究や実践は、学問や生活と別のものではありませんでした。私は、戦争と戦後のあらゆる行き詰まりを法華経の英知と慈悲と勇気で切り開いてきたという感じを持つものです。人間の精神性と宗教性は通じるものがあり、自然に対する愛情も宗教性につながるように思います。それが、人間にとって健全なことだと思うのです。
最後のご質問ですが、最近の生命科学の進歩によって、宗教や形而上学の問題とされてきたことも、実証可能な科学的問題となりつつあるという提起ですが、私は概ね賛成ですが、しかし、全面的には賛成はできません。私達に役に立つ知識の大半は、経験論的知識であります。多様で無常な経験論的事象に秩序を与え、システムに意味を与えるのが認識論ですが、経験論は認識論を作り出すことはできません。その力は、生命に内在する主体的性能だからです。認識論は、カントの純粋理性批判、実践理性批判、判断力批判に始まって、ウェーバーの社会科学の主体論的方法としてのエートス論に繋がるのですが、パラダイム論は認識論の流れなのです。
生命科学が進歩すれば、古代宗教が神話的表現を用いていたことが、科学的認識になることがあることも否定できませんが、人間の主体性に根拠を持つ認識論は、経験論的認識からは出てこないのです。生命科学は、法華経の英知を助けるものですが、それに代わるものではありません。それが、ロエブルの理解の難しいところであると思うのです。
このくらいにして、本論に入ってお話しましょう。
1、ロエブルのパラダイム論
ロエブルのパラダイム論は、二つのテーマから成っています。
その一つは、伝統的経済学の基本的テーマであった経済法則という概念の否定でした。経済法則という概念は、自然科学のモデルによるもので、社会科学の概念ではない。人間という主体的で、創造的な存在によって作られる経済社会は、多様性、特殊性を特徴とし、自然科学のような抽象的、一般的法則概念で把握されるべきものではないとするウェーバーの方法論を継承するものでした。そして、パラダイム論はウェーバーの主体の論理にあたるものでした。
もう一つのテーマは、伝統的経済学の基本概念であった労働価値説の否定です。
経済法則批判の第一は、需要と供給の均衡の法則の否定です。それは、スミスやリカルドの古典派の理論の否定になります。
第二は、効用逓減の法則の否定です。これは、新古典派の理論の前提の否定になります。
第三は、収穫逓減の法則の否定です。これは、ケインズ経済学の理論の前提の否定になります。
第四は、このパラダイム論のもう一つの大テーマである労働価値説の否定です。これは、自由主義経済学のみならず社会主義経済学を含む経済学という建物の基礎である所有権の否定になります。
所有権とは何か。この世に存在するものは総て人間の所有するものであるという思想です。ユダヤキリスト教の旧約聖書では、すべてのものは神のものであるとされ、神はそれを人間に託したというのですが、二人の経済学の始祖、つまりフランス人の宮廷医ケネーとイギリス人の大学教授スミスが、労働が富の源泉であるという概念を創出しました。富の生産者に所有権が属することが経済社会の大前提になるのです。この説が、リカルドやマルクスによって、理論的概念として洗練されていきました。
そして、実際社会では、企業の所有権、つまり支配権は、株の所有者とか、代表権者にあるとされ、アメリカの株主資本主義とか経営者資本主義といわれるものの基礎になり、極端な差別社会の合法化に利用されてきたのです。
この所有権の根拠である労働価値説に対して、ロエブルは、次のように主張しました。「今日の応用科学による生産の時代では、労働価値説ほど非現実な学説はない。今日、富の源泉は、私的な労働にあるのではなく、社会の知的水準と総合システムにある。」そして、社会の総合システムとは、無数のサブシステムの相互依存的関係によって成り立つ有機的統一体であって、個々の構成要素に分析しても無意味なものである。サブシステムは、輸送や金融機関のみでなく、教育や政治も含まれるのである。この言葉の意味するものは、伝統的経済学のパラダイムの全面的否定であり、経済社会の基礎をなしている所有権という概念の根拠を破壊するものでした。したがって、所有の蓄積である富という概念も妥当性を失います。
そこで、生産とは、自然のエネルギーと財を人間に役立つエネルギーと財に転換することだ、ということになります。そして、生産に投入されたインプットと生産されたアウトプットの差額が、社会的ゲインであるというのです。そして、生産物は、社会の知的水準と無数のサブシステムの相互依存的協業から生まれたもの故、ソーシャルゲインと呼ぶべきものと主張したのです。
それは物質的なものだけではなく、知的で機能的なものも含み、物より生活の質の向上に役立つことが重要になってきたことを意味します。このような全体性、関係性に視点をおき、個体の実体性を否定する思想は、あらゆるものは、他に依存し、変化して行くものだから、固有不変の実体ではなく、空であるという思想にほかなりません。これは、排他的エゴイズムと物を実体視することの否定で、私的所有権の否定と論理的には同じであることに気がつくと思います。これは、仏法の空観であり、相互依存的関係主義である縁起観の一つです。
これは、哲学的には、功利主義的な欲望の支配と外的な法則による束縛からの自己解放の思想であります。これに目覚めることは、同時に、この世のルールや価値の問題は、自然法則のような客観的法則ではなく、人間の心が創造すべきことだという自覚となります。それが、言葉や文字や貨幣というシンボルによって、人間が作り出す意味の世界であり、文化価値の世界であります。これは、仏法の仮観であり、人間の主観のつくり出す仮の世界ですが、同時に日常的現実の世界でもあります。これが第二の真理観です。此処で、人間は平和と幸福を目的に、文化と価値を創造していく主体的存在になります。
この転化が、仏になることで、これを中道といいます。縁起観から生まれた第三の真理観です。この空、仮、中の真理観は、人間の仏性という主体性によって統合されるのです。
ロエブルは、「均衡は自然の法則ではない。価格を決めるのも、市場の法則ではない。人間の作った社会システムとそれを運用する人間の英知以外に平和と幸福を実現する方法はないと宣言するのです。そのための理論が、パラダイム論という主体の論理から始まり、手段論としての貨幣論と社会システム論という客体の論理に終わるものです。
ロエブルの道具としての貨幣論は、法華経の仮観という哲学に他ならないのです。もう一度仮観という哲学を簡単に説明しておきましょう。自分を含めてこの世が空であることは否定できません。すべてが死すべき存在であり独立不変の実体ではありません。しかし、同時に、それは私たちの意識との関係において、言葉や文字のようなシンボルで表現される現象であり、意味の世界であります。それを仮の世界と呼ぶのは、人間によって作られた条件づきの真理であり、実体は空の世界と違うものではないからです。しかし、私たちの実生活を支配し、私たちが変革し操作できるのは、この仮の世界なのです。
ロエブルは、ケインズ以後の貨幣は、労働価値説に基づく商品貨幣ではなく、シンボルであり、制度に過ぎないことを知っていました。したがって、そこにある矛盾を改革するのは、人間の当然の義務でした。その矛盾の最大のものは、社会的必要によって供給される貨幣の存在そのものが、債権者と債務者という対立関係の拡大によって作り出されてゆくことです。
また、企業は、投資額以上の売り上げを予想できなければ、つまり利潤が予想できなければ、投資できないということです。これは社会全体では、成り立たないことです。需要の総計は供給の総計以上のものになりえないからです。これが、ケインズが、古典派的経済法則を前提とする限り避けられなかった実体論の限界であり、矛盾です。
これに対し、ロエブルは、貨幣の機能を触媒機能にのみ見出し、社会の自己制御の手段としたのでした。貨幣や所有権を実体とは見ず、人間によって仮設された手段であり、シンボルに過ぎない。したがって、貨幣は、社会的必要性と人間の価値観によって創造され、変革と操作のできるものだと考えるのです。
そこで、貨幣は、経済社会に内在する可能性を活性化し、交換や分配や循環を媒介する触媒であるとし、触媒機能を貨幣の本質とする定義が生まれます。触媒とは、化学反応を促進する第三の物質ですが、貨幣が市場経済の景気をよくしたり、環境問題の改善を可能としたり、社会福祉を充実する手段となり、いろいろな政策を実現する手段となるのは、この触媒機能によるのです。したがって、ロエブルの手段としての貨幣は、シンボルとしての貨幣であり、触媒としての貨幣であったのです。そして、何の実体性もないシンボルであり、触媒であるものが、出口のない暗黒の牢獄である経済社会に、意味と価値の秩序を与え、自覚的自己制御の主体である人間の登場を待つことになりました。
これが、ロエブルの貨幣論と社会システム論の意味であり、そこから、自覚的自己制御の主体である共同体システムの建設に向かう道を開くのです。
ロエブルの理論が問題解決学としての要であるというのは、この手段としての貨幣論を創造することによってミクロの世界である市場システムが生み出す矛盾に対応して、マクロ機関としての共同体システムの理論が開拓されたことであります。
それでは、社会システム論の構造について付け加えましょう。
その一は、ロエブルは、ケインズに習って、経済社会のシステムを個人乃至私的企業を主体とする分業と交換のシステムであるミクロ経済と、社会全体を相互依存的な統合システムとするマクロ経済とを二大サブシステムとする統合的システムと見ます。
その二は、ミクロ経済は、マクロの次元の矛盾を生み出すが、その解決の能力はありません。例えば、必要な貨幣の供給、不況や失業の克服、自然環境の悪化の防止や改善、健康や老齢などの社会福祉に対応する責任は、政府などのマクロ機関に負わせます。
その三は、この責任を負うマクロ機関には、それを果たすための能力、財源として貨幣の創造と支出と回収の権限を与えます。ここでの重要な点は、支出の目的と対象が、社会の必要不可欠なことで、企業などのミクロ機関には本来解決能力がないものであること。さらには、この支出の財源は、ミクロ経済から税金として回収される収入ではないこと。すなわち、共同体原理の担い手であるマクロ機関の公的権利と義務の遂行のためのものとして新設された制度であること。したがって、ここに生まれた貨幣量の増加は、インフレを起こさないように、流通課税に似た掬い取り課金によって回収すること。国家財政は、私的所有権から離れているから、収支の均衡という概念にも関係ないこと。
このようなロエブルの貨幣は、マクロ機関のための手段として、ケインズ的貨幣システムの矛盾部分を補正するものですから、これまでの全貨幣をこのようなシステムに変える必要はないと考えます。マクロ経済における企業家が投資できるような予想利潤が確保されればよいのですから、その分は全体の10%ぐらいから始めてテストしてみればよいと思います。
次は高齢者手当や医療保険等々があります。これらは、今日の年金制度が抱える問題を引き継いで検討し、必要額を求めます。それらは、概論的にいって、社会の目的は、幸福と平和であり、共存と循環のシステムの実現にありますから、そのための必要経費ということになります。最後に最も重要な問題となるのは、環境問題と平和の問題です。ロエブル的貨幣論が必要不可欠なのは、この分野です。
ロエブル的貨幣の回収と循環について、
次の問題は、このような貨幣の供給は経済社会の矛盾と問題解決のためであり、そこから過剰貨幣とインフレーションという矛盾が生まれてくることです。それに対しては、合理的な回収方法が考えられねばなりません。それは既に述べたような流通課税に似た掬い取り課金でした。しかし、それは、私的個人や企業が所有するものを税金として取り上げることではなく、共存と循環のシステムを円滑に回転させるための手段としてなされるものです。
貨幣は目的ではなく、手段であり、触媒なのです。触媒とは役目が済めば、回収され廃棄されるだけのものです。政府のような公的機関が貨幣を作って、必要なところに支出し、眠っている労働と技術と資源を結びつけ、必要な生産と所得を作り出せばよいのです。これが、まるで、偽札作りのように聞こえるのは何故でしょうか。それは、これまでのパラダイムとの違いです。
それでは、ロエブルの貨幣と労働価値説時代の貨幣との違いは何か。労働価値説時代の貨幣とは、既に生産し終わった過去の労働価値を表すものでした。これに対して、ロエブルの貨幣は、この貨幣の触媒機能によって、これから生産される社会的ゲインに対応する価値なのです。今日のような豊かなストック社会では、その違いは何の問題にもならないでしょう。
ヒューマノミックスの社会は、人間の主体性を中心に、そこから派生し、そこへ収斂するべきものです。その社会システム論としては、マクロ経済における政策主体である共同体システムの形成という問題になります。それを、私は、社会の自覚的自己制御の主体と名づけてきました。
それは、知的な存在であり、道徳的存在であります。目的の選択と手段の使用と操作がその任務です。そこで現れる真理とは何かという問題は、試行錯誤的なものです。何故なら現象の世界は、人間の意識から生まれ出る仮説の世界だからです。したがって、これは形而上学的独断ですが、必要にして最善の仮説にならねばならないのです。それ故、民主的国民の理解と支持を得ることが望まれます。しかし私たちは、利害の対立を前提に多数決原理で決める議会制民主主義の欠陥を余りに多く知っています。私としては、本来、生命に内在する英知と慈悲を信じて、自覚的な自己実現としての政治経済の主体が形成されるよう念じています。
以上、少し長くなりましたが、今日の対談は、この辺で終わります。
次回は、小島先生の提起されたものは何か、今日、その意味を私達はどう受け止めるべきかを考えてみたいと思います。
(第八回対談に続く) |
| ■この対談内容のPDFファイルをダウンロードできます→こちらから |
| ※この対談のご感想、ご意見をメールまたは会員掲示板へお寄せ下さい |