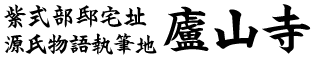沿 革
略 史
比叡山天台18世座主元三大師良源によって天慶年中(938年~947年)に船岡山の南に創建されました。寛元3年(1245年)に法然の弟子である覚瑜が船岡山の南麓に再興、中国の廬山にならって蓮社を結び道俗貴賎が群集し、廬山天台講寺と号しました。
室町時代に応仁の乱で焼失した後、元亀2年(1571年)、織田信長の比叡山焼き討ちは正親町天皇の女房奉書により免れましたが、天正年間(1573~1593)に現在地に移転してまいりました。度々の火事のため、現在の御仏殿(通称本堂)と御黒戸(通称尊牌殿)は寛政6年(1794年)、光格天皇が仙洞御所の一部を移築し、女院、閑院宮の御下賜でもって造営された。明治維新までは御黒戸四箇院と云って、宮中の仏事を司る寺院が四ケ寺ありその中の一つでありました。けれども、廃仏毀釈により宮中より天台宗にお預けになり、明治天皇の勅命により当山のみが復興され現在は天台圓淨宗として今日に至っております。
本 尊
木造 阿弥陀如来及両脇侍坐像 3体 平安末~鎌倉時代(国指定重要文化財)
13世紀初めの製作と推定される作例で,来迎阿弥陀像と称される,臨終を迎える者の許に出現した阿弥陀如来と観音・勢至菩薩をあらわした彫像である。両菩薩は膝を揃えた坐り方で,衣が後方に強くなびく様子を表すことで,来迎のスピード感を強調しているのが注目される。また勢至菩薩は元来,両手で往生者に差し掛ける天蓋を執っていたとみられ,彫像では珍しい図像である。当代の来迎と彫像の優品として注目される。

勢至菩薩

阿弥陀如来

観音菩薩
年間行事
毎月3日は月例の護摩供を元三大師堂にて行っております。
1月3日 初元三會 2月3日 節分会 鬼法楽 春分の日 春彼岸 8月1日~8月16日 盂蘭盆会 9月3日 元三大師 生誕會 秋分の日 秋彼岸
どなた様でもお参り・御祈祷の申込みが出来ますのでご参拝下さい。
主要文化財
他多数ありますが一部のみ掲載しております。
慈慧大師御遺告 【国宝】 東京国立博物館に寄託 絹本著色普賢十羅刹女像【重要文化財】 京都国立博物館に寄託 木造如意輪観音半跏像【重要文化財】 京都国立博物館に寄託 阿弥陀三尊像 【重要文化財】 本堂に安置
トップ > 略史