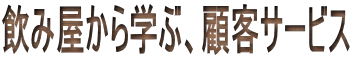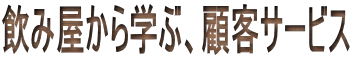|
|
| 利益率の向上 |
| 経営者は売上額や客数を気にするが、利益率は忘れがち |
商業・サービス業の場合、要するに利益率=客単価×回転率である。
したがって、①どうすれば客単価を上げられるか、②どうすれば回転率を上げられるか、が利益を増やす上でのポイントになる。 |
とはいっても、簡単に客単価を増やせるわけではない。
私たちはごくごく一般的な酒飲みであり、豪遊するほどお金持ちではない。それでいて、できれば毎日飲み屋に寄りたい。
そんな私たちにとって、割り勘にしたときの千の位が3か4かは、心理的に大きな違いだ。
「割り勘で一人4千円ね」という店だと、月2回行くところ1回にしておこうかという気持ちになる。
店としては3人×3千円×2回=18,000円の売上げになるところが、3人×4千円×1回=12,000円にしかならない。粗利が5割にしても、△3,000円になる。店全体では、大きな収益減になる。
客足が遠のいた分、新規の顧客で埋められればいいのだが、こういう場合は、どこの店も値引き合戦をしていて、一気にお客が少なくなる。
かといって、英断をふるって値上げしたのだから、すぐに元の値段に戻すことも躊躇される。
客がわんさか来ているのなら、多少の値上げは冒険してみる価値があるが、単なる収支改善から客単価を上げるのは、たいへん危険だ。 |
来店頻度を上げれば収益は良くなる
商業・サービス業の経営者は、えてしてこれを忘れがちだ。
客単価が同じでも、回転率が上がれば利益は増える。
たまに来て長居をする客を減らし、短時間で回転する客を増やす。飲み屋なら、学生客を減らし、帰宅サラリーマン客を増やすことになる。
前に述べたように、帰宅サラリーマン客には①職場→会社最寄駅組と、②自宅最寄駅→自宅組がいる。仮に前者を“終業後流れ組”、後者を“帰宅前立寄り組”と呼称する。
終業後流れ組に対しては、徹底したリピーター化戦略が効果的である。その店を選ぶことによって何らかのメリットがあるという刷り込みをする。例えば、割引券の発行だ。
帰宅前立寄り組の繋ぎ止めには、「あなただけは特別よ」戦略が有効になる。例えば、注文になかったつまみ(高級品)を出してみたりする。
こうした戦略は、後述の「集客の安定化」にも連動していく。 |
売上額と利益とは違う。
商店の場合、経営者は日々の販売額や、商品の販売個数に興味を奪われがちだ。
しかし、販売額・販売個数と利益とは、必ずしも繋がらない。
仮に、A、B、2種類の商品があったとする。
商品A:単価300円、粗利100円は、1日に100個売れる。従って粗利は10,000円だ。
商品B:単価2,000円、粗利1,000円で1日に10個売れる。従って粗利は10,000円だ。
AとBが商店に与える利益は同じだ。しかし、売るための従業員の手間やレジ袋の出を考えると、明らかに商品Bの方が商店の経営には貢献している。
ところが、ひっきりなしに購買者が来る商品Aの方が、見た目には人気商品である。経営者はこの様子を見て、商品Aの品揃えを増やそうと指示する。従業員がばたばた働いていると、店が繁盛しているように見えるからだ。
経営者ならば、売上額よりも商品ごとの収益貢献度を再検討すべきだ。 |
商業・サービス業であろうと、製造業であろうと「定番メニュー」は必要だ。
しかし、それに頼りすぎるのは危険。
例えば、貴社が仮に「鍋」のメーカーだったとする。その鍋の売れ行きがここのところ思わしくない。
この場合、打つ手は2つ。一つは、その鍋を別の市場で売ること。しかし、それは簡単にできることではない。新しい市場には、すでに別のメーカーがいるだろうし、そこでも鍋の需要は頭打ちになっている可能性は大きい。
そこで第二の手段は、今までの販売ルートを活用して、顧客に別のもの、例えば「フライパン」とか「たこ焼き器」とかを売ることだ。
ところが、これまで売ってきた自社の鍋に自信を持っている経営者は、別の種類の鍋―「ホーロー鍋」とか「土鍋」とか―を製造販売しようとする。
しかし、大概の消費者にとっては、鍋は一種類あれば、それで十分なのだ。
そのうえ、自社の新しく開発した鍋が、結果として自社の主力製品である既存の鍋のシェアを食っていく。
新しく売り出した鍋がそこそこ売れているので、経営者はその実態に気づかない。
結果、その企業は、たくさんの在庫を抱えることになり、経営が危うくなる。
笑い話のようだが、こういう例は実際にはたくさんある。 |
ここで大切なのは、既存の主力商品の売れ行きがいいうちに、新商品のプランを練ることである。
どんな商品にも寿命がある。
思うように収益が得られなくなってから、「さてどうしよう」と考え始めたのでは、間に合わない。
さらに、ここで大事なのは、方向性を誤らないこと。思いつきで、やたらとあちこち手を出さないこと。
鍋を作っていたメーカーは、自社の鍋が消費者から好評を得ているとすれば、まずはその理由を探るべきである。
「軽い」「コンパクトで戸棚にしまいやすい」「耐久性がある」「デザインがいい」「贈り物でもらった」――何か理由があるはずだ。ひょっとしたら、電子調理器に乗せたときに、他社の鍋より熱効率が良いのかもしれない。
それが“売り”になるなら、次は「熱効率の良いフライパン」を目玉商品にすべきだ。 |
話は変わるが、昨今の成長産業に「アニメ」が挙げられることが多い。
たしかに、日本生まれのアニメーションが世界を席巻しているのは事実だ。
しかし、関係者に言わせると、「アニメの監督は、良い作品を生み出すことについては大変熱心なんだが、売れる作品を作ることについては、興味を示さない」という。
押井守氏は有名なクリエーターだが、あるとき鳴り物入りで作った作品が不評で、数年間仕事を干された時期があったという(本人もそう言っている)。
その作品は、私も映画館で見た。クオリティーの高い作品だとは思ったが、正直なところ面白い作品ではなかった。
芸術家で賞をもらった人の中には、「好きなことをずっとやってきただけで、別に賞を取ろうとしてやってきたのではない」と言う人物が多い。日々の売上金額に一喜一憂している商店主からみれば、とんでもなく贅沢な発言だ。
個人事業主という言葉と、個人経営者という言葉があるが、個人という文字がつくと、事業主の方がしっくり来る。事業を行う、つまり、自らが仕事をするということは、実はその中に“楽しみ”が隠されている。
売れない作品でも、作るのが楽しければ作るという理屈が、そこには成り立つ。
しかし、経営者と称すれば、そこには、“会社組織”の運営との関係が問われる。企業の経営を行うというのは、自らが仕事をするのに比べると、さほど面白いことではない。
例えば、「事業として成り立つ創作物を作る」ということになれば、
(1)構想を練る
(2)資金調達をする
(3)プロモーション計画を作る
(3)販路を確保する
(4)(1)~(3)を考慮して、当初の構想を修正する(=“売る”ための要素を加える)
(5)実際に宣伝活動を行う
(6)作品を公開する
というような、段取りを取る。正直いって、かなりつまらない。
企業を経営するためには、商品の販路開拓をどうするかとか、商標登録をどうするかとか、顧客の苦情にどう応えるかとか、従業員のモチベーションをどうやって上げるかとか、資金調達をどうやるかとか、めんどくさい仕事をこなさなければならない。
クリエーターは、そこまでやりたくない。
マエストロと呼ばれる宮崎駿氏には、鈴木敏夫氏という名伯楽がいて、七面倒くさいプロモーションなどは、この人が一手に引き受けている。だから“宮崎マエストロ”は、作品に専念できる。
宮崎氏のスタジオジブリには従業員もいるだろうし、配給会社などとの交渉ごとも必要になってくる。
しかし、“事業主”がそんなことに奔走していては、とてもいい仕事はできないのだ。
だが、ごく普通の中小企業“経営者”となると、そうはいかない。
有能な補佐役がいない経営者は、自らが七面倒くさい業務をこなさなければならないのだ。
当然、販路、利益率、原価などといったことも、経営者だと、考えなければならない。
いい仕事をすれば事業主としては賞賛される、しかし、会社を潰せば「経営者失格」と批判される。 |
次のページへ→
|
|