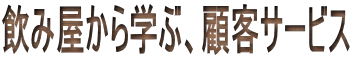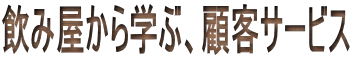従業員教育に悩む経営者は少ないないようだ。
人件費の負担は企業にとって大きい。では、どの程度が適正なのかと聞かれても、スタンダードは作りづらい。
ここに、東京都産業労働局がまとめた「輝く技術、光る企業」(2009年度)がある。
この冊子で紹介された企業(製造業)は、人の生かし方に優れた点が認められる会社であるから、おそらくは、経営状態も比較的に良い企業が掲載されているものと、想像できる。
この冊子には、各企業の売上高と従業員数が記載されている。乱暴なやり方だが、売上高を合計し、それを従業員の合計で割ると、従業員一人あたりの売上高は2千8百万円。全体を二分し、売上高の低い企業だけで平均を出しても、1千5百万円となる。
今日、中小企業の従業員の平均年収は、5〜6百万円程度。ここから推定すると、中小企業の従業員は、自分の年収の2倍程度の貢献を企業に与えなければ、よい従業員と呼ばれないことになる。
この額はかなり大きい。
しかし、それを自覚している従業員は、おそらく少数だろう。
「年収500万円の営業マンをモデルにして、1回あたりの訪問コストを算出してみると、仮に営業マンが1日平均4件を訪問するならば、訪問1件につき1万円もかかる。1日平均8件の訪問でも、1訪問コストは5000円になる。」
との指摘もある(出典:営業力が高まる!「見える」しくみ 吉岡行雄 すばる舎) |