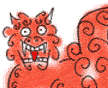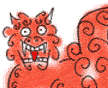4
《編集長!もう描きたくありませ〜ん(大泣)》
絵の評価がきました。
グットな仕上がり。クマノミもかわいいし、ウツボも登場させていい感じ。ただ、
親クマノミは、もじゃもじゃしてるから、なんとかならないか?(参考資料2)
という評価。そして、今度は、キャラクターを一匹づつ描いてほしい。という依頼。
「え゛〜〜〜〜っ!!!もう、あれで終わりとちゃうんかいっ!!」
私は、前回の絵で、全精力を使い切っていました。しかも、同じ絵を何度も描くなどという芸当が、
この飽き性の私にできましょうか?
一気にやる気ダウン・・・。
もう、だいたいオッケーなんやし、なんべんも同じ絵なんか描きたくないな〜。と思い、
ちょうど琉球フェスティバルも重なって、遊び気分バリバリの状態で、何日かほっておきました。
「絵のほうは、どうですか〜?」携帯に電話がありました。
「うん、描くよ。土日に描くから、大丈夫!」と元気に答え、やる気が出ないので、
その日も遊びほうけてしまったのでした。
だけど、夜になり、ちょっと罪悪感が沸いてきて、編集長(この頃から、私と谷川くんの関係は、
駆け出しの漫画家と、編集者のような関係になりつつあったので、冗談半分に編集長と言っていた)
に土日は遊びほうけてしまった旨謝罪し、許してもらったのでした。
編集長の注文は、もうひとつあって、ペンが揺れてるから、一筆書きでざくっと描いてほしい。
というものでした。私の使っていた水性ペンは、にじみやすく、ざくっと描くと、線にムラがでる。
ということを訴えたら、いろいろ何本か試して。と言われたので、東急ハンズへ行き、違う水性ペンや、
油性と水性の中間のやつや3本購入し、試して結局、PILOT PERMABALL太字という
ペンを使用し、やる気を振り絞って、仕上げたのでした。
ペンを買いに行ったり、同じ絵を何度も描いたり、
も〜う、超めんどくさいっ!!絵、描きたいとかなんで言うたんやろ・・・。
もう、当分絵なんか描きたくないっ!!
仕上げた絵を入れた封筒を横目で見ながら、
もう、絶対描くもんか。(怒) これは、宣言しとかな、ここで限界や。
と思い、編集長へ宛ててメールを打ったのでした。
「もう嫌や〜。疲れた〜。やる気残ってませーん。もう描かない。」
結果的には、イラストはOKが出て、完了で、あとは色を入れたものを
最終チェックすればいいだけとなり、やれやれ一安心。
編集長からは、私の弱音に対して、
厳しく感じるのは、期待してるからですよ。
3巻を作るのは、三度目の正直といって、気合を試されている時です。
と愛と熱意を感じるお言葉が・・・。(しかも、谷川くんは7つも年下やのに、
言うことがめちゃ大人やし・・・どっちが年上かわからへん・・・グスン。)
はい、わかってるんです・・・。
初対面で、私の絵すら見ていないときに、私の気まぐれな一言を信じ、ゆだねてくれた編集長、
それって、すごいことやな〜と思うわけです。(だって、どんな絵描いてくるかわからないわけだから・・・。)
弱音吐いてごめんなさい。
|