「あるべきようは−私の十年を振り返って」
[平成9年(97)2月記]
最近になって「どうして坊さんになったんですか」という質問をよく受ける。僧侶になったのは既に十年ほど前のことになるが、当時はいろいろと考えを重ねて決断したように思い出される。
が、今では、その問いに対してそう簡単には答えることが出来なくなってしまった。当時考えていたことの根底にあった深層の意識が本当は私の身の振りを決めていたと思えてきたからでもある。しかし、ともあれ、この十年を振り返ってみると、自分にとってとても自然な歩みであったと思える。
<僧侶に>
「お寺の息子だったんですか」、これが、当時、僧侶になると会社の同僚に私が言ったときの返事であった。
「いやいや、出家は家庭を持たないものなのですから、もとはお寺に息子なんていなかったんですよ」とでも答え、寺の生まれでもないものが僧侶を志す正当性を主張したのを記憶している。
サラリーマン九年目にして僧侶になると決めてからの私は、まことにすがすがしく、頭の中に、もやもやと漠然と抱いていた将来に対する不安や焦燥を一瞬にして吹き飛ばしてくれた。周りと比べられ、競走し、世間の体裁を気にする生き方、常に何かと張り合い、精一杯走っていなければいけないといった強迫観念からも解放させてくれた。
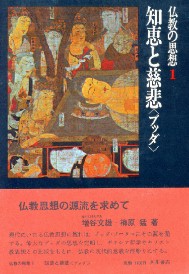
<仏教との出会い>
そもそも私が仏教と出会い、こうして今日あるのは、大学二年目に再会した高校時代の友人たちに感じた反発からであろうか。彼らが語る西洋の哲学に、何か私たちがそもそも身に備えたものとの隔たりを感じていたのかもしれない。
そしてそれが、その後間もなく、その時まで宗教書など手にすることもなかった私が仏教書と出会うきっかけとなった。その最初の本は増谷文雄先生の「仏教の思想・知恵と慈悲<ブッダ>角川書店刊」であった。
パーリ経典にもとづく、ありし日のお釈迦様のお姿を彷彿とさせるその文体に惹かれ、それから次から次にと仏教書を紐解く日が続いた。いつの間にか僧侶を志し、自然と高野山への道が開かれた。
そしてこのはじめて手にした本によって得られた、お釈迦様をはじめとする仏弟子たちのお姿を慕う思いが、高野山の真言僧侶修養の道場・専修学院を経て、なお、インドの地へと私を急き立てることになった。
<インドへ>
灼熱のブッダガヤ。ヒンドゥー教の聖地リシケシの雨期。そこで私は、生命の源・ガンジス河の滔々と流れる雪解け水に体を冷やしつつ、現代インドの信仰をつぶさに垣間見ながら過ごした。
宿泊したシバナンダ・アシュラム(道場)を後にする日、荷物をまとめドネーション(寄付)を払いに行くと、そのお金を受け取るスワミジ(ヒンドゥー教の僧)は「あなたは日本で何をしていますか」と聞かれた。日本の仏教僧であることを告げると、インド服を着ていた私に、「なぜあなたは仏教徒のドレスを着ないのですか」といわれた。
私はそのとき、誤魔化しを許さないインドの宗教者の厳しさを教えられた。いついかなる時でも衣を纏い自らの姿勢を明らかにし、世間に染まらず心を浄らかに保つ。そんな簡単なことにさえ抵抗があった自分にとても恥ずかしい思いがしたものだった。
<四国遍路へ>
そして私は日本に戻り、それまで世話になっていたお寺の役僧を辞し、一人住まい托鉢をし、四国八十八カ所の徒歩遍路に出ることになる。そもそも出家とは、定住することなく、樹下を住まいとするものであった。
儀礼や祭祀によって生活するのが僧侶なのではなく、瞑想にふさわしい場所を求め、また聖地をめざし歩く遊行者が出家の理想である。今日の日本でその理想を少しでも味あわせてくれるのが四国巡礼ではないかと、私は思っている。
一人錫杖を突きつつ、網代笠の下、地面を見つめ、ひたすら歩く。遍路道で出会う見ず知らずの人たちから受ける情け、ご飯や飲み物などを施されるお接待のありがたさ。出会いの妙。それまでの自分を振り返り、そんな至らぬ自分に施しをされるお気持ちに涙することもあった。
四国遍路は、正に心を見つめつつ歩く瞑想の道場とも言えまいか。
(四国遍路を終えて小松島港にて)
<インド僧へ>
しばらくそうした生活を続けつつも、はたして僧として自らのなすべきことは、と考え始めたとき、再度インドを訪れる機会を得た。
そしてそのときの縁で、後にカルカッタに本部を置くインドの伝統的仏教教団・ベンガル仏教会で南方上座部の僧侶として、三年あまりの間黄衣を纏い過ごすことが出来た。
カルカッタのフーグリー河に十五人の黄衣姿のインド僧を乗せた小船の上で私の具足戒式(ウパサンパタ゛ー・正式な僧侶になるための授戒式)は行われた。そして、本部僧院で他のベンガル人のお坊さんたちと共に生活し、様々な儀式にも参加させていただいた。
彼らの生活は今日でも非常に質素である。持つものが少ない身軽さ、心もまことに軽快である。生涯独身の僧院生活を送る彼らの持ち物はといえば、衣類と僅かな書籍、それに鞄やひげ剃り、傘など必要最小限の生活必需品と多少の現金くらいなもの。
昼は、仏教徒の家に招かれ、食事の供養を受けることが多い。在家の信者にそうして布施の功徳を積ませる存在であり、それだけ日頃の生活に清貧さと供養を受けるに値するものとしての気概が求められる。 (カルカッタの僧院にて) (カルカッタの僧院にて)
<南方仏教僧の生活>
この間私は、インドから一時日本に戻った際にも当然のことではあるが茶褐色の袈裟衣を常に身につけて過ごした。そのときはじめて実感されたことは、一つには、日本の僧侶に比べとても身軽であるということ。
衣が何種類もある日本の僧侶とは違い、出家されて五十年になる大長老から十代の見習い僧まで皆同系色の腰に巻く下衣と身に纏う上衣、普段はこの二枚の袈裟だけ。寒いときにはもう一枚袈裟を纏うか、同じ色のシャツや靴下を身につける。
足袋も白衣も数珠もいらない。白いものを身につけない手軽さ。外出時にあれこれと身支度する必要もなく、寝る際にも上衣を外すだけ。まことに簡便な合理的生活が送れるものだと実感することが出来た。
そして食事も朝と昼のみ、午後からは固形物を口にすることが出来ない。一日二食と考えるとどうも栄養が足りないのではと考えられる向きもあろうが、過食気味の食生活を送る現代人には却って適度な健康的な食習慣ではないかと思えた。
そしてこの二食のお蔭で、夕方から夜の時間がまことに有効に生かすことができた。夜外出することもなく、余裕ある意義ある時間を毎日のように作り出すことになった。日々のなすべきことに追われる生活の中に、次元を変えた充実した時間を作り出す秘策とでも言えるものだと思えた。
住まいは、インドではもちろんベンガル仏教会の僧院に逗留したが、日本では知人の寺に居候をさせてもらっていた。そのお蔭もあるが、この間日本にあっても、金銭について全くといってよいほど気遣うことなく過ごすことができた。
それは、何もせずとも常に袈裟を身につけている安心感、充実感があったればこそなのだと思える。お釈迦様の教えを学び、実践しつつ、縁あった人々と語り合う。これ以外のことから解放された存在なのだといえる。
逆に言えば常に身につけている袈裟が余計なものに心が向かうことを防いでくれるとも言えようか。インドにいる間、暑いため僧院内では上衣を外して過ごしたいところであったが、師匠からは常に身につけていなければいけないと、ことある毎に教えられたことを思い出す。
<捨戒し帰国>
九六年八月、カルカッタの僧院で上座部の僧侶の戒を捨戒し黄衣を脱いだ。インドで経験した簡素な生活は、世事に煩わされることなく、時間と活力を無駄なく僧としてなすべきことへ身を任せる礎であると思えた。袈裟そのものが普段着の仏教。お釈迦様の教えとは本来こうしたものであったのだと知ることができた。
誰しも生きている一瞬一瞬の営みがその人を作るのであって、私たち僧侶もあらためて袈裟を纏う特別な時間はその発露であるにすぎない。常に原点を忘れず、お釈迦様や宗祖の時代を慕い、自らを律する真摯な姿勢が必要ではないかと思う。
かつて明恵上人がインドの地にあこがれ、お釈迦様の時代に生まれ得なかったことを嘆かれたように、今の時代にあっても“あるべきようは”と自らに問う営みが必要ではないか。自らの生活習慣によって、自分も、周りの人々も自然と心浄らかなものとなるよう心がけることが、僧侶にとって肝要なことではないかと思う。
アジアの仏教国を旅した人なら、それらの国々では颯爽と街を行く僧侶の姿をしばしば眼にしたであろう。多くの僧侶がいるはずの日本で、街にそうした姿を見かけることは誠に稀ではないだろうか。
心が問われている現代社会にあって、今仏教という心の教えを日々の生活や様々な問題の解決に生かしていくことが、切実に求められているのではないかと思う。仏教を今の社会の中にいかに浸透させていくか、私たち一人一人がその使命を担っていることも忘れてはなるまい。(大法輪・平成9年4月号掲載)
|
 インドとの出会い
インドとの出会い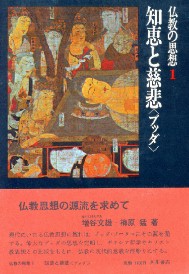

 (カルカッタの僧院にて)
(カルカッタの僧院にて)