 ダゲレオ・タイプ
ダゲレオ・タイプ日本に「写真術」が伝わったのは1848年。ダゲレオ・タイプがオランダから輸入され、
薩摩藩の島津斉彬が入手。藩士たちに扱い方や撮影技術を研究させたのが始まりとされる。
―――――◇―――――
| トップ | はじめに | 中古写 | 新写 | 特写 | 外写 | 彩写 | 写界小話 | 写界生活 | 写界裏話 | 写リン | AI写真 |
「写界現象」
★写真技法の誕生★
|
|
 ダゲレオ・タイプ
ダゲレオ・タイプ
日本に「写真術」が伝わったのは1848年。ダゲレオ・タイプがオランダから輸入され、
薩摩藩の島津斉彬が入手。藩士たちに扱い方や撮影技術を研究させたのが始まりとされる。
―――――◇―――――
殿様が撮った写真――幕末に島津斉彬と交流し、写真技術も学んだとされる尾張徳川家
十四代の殿様・慶勝が自ら撮影した貴重な写真の数々と、その現像処理などを記した書面などが、
2006/9/9~10/1、名古屋市東区にある徳川美術館(カット写真)で特別公開された。

「幕末の残像―尾張の殿様が撮った写真―」(主催・徳川美術館、朝日新聞社)と
題された写真展で、写真愛好家をはじめ、一般客、とくに若い人たちも多く来場して、
はるか昔の写真を熱心に見入ったり、興味深そうに眺め、メモしたりしていた。
そのパンフレットに紹介された説明と写真の一部をここに紹介します。
|
|---|
また当時、長崎県生まれの上野彦馬もダゲレオ・タイプにヒントを得て、
自分で写真機を作り、苦心の末に撮影に成功した、と伝えられている。
江戸時代後期に入って、国産の「堆朱カメラ」も誕生。
 堆朱カメラの模型
堆朱カメラの模型
当時の感光材料は、銀メッキした銅板に露光して撮影する「銀板写真」。その後に、
コロジオン液剤を塗ったガラス板に光をあてる「湿板写真」(ガラス写真)が生まれた。

明治15年撮影のガラス写真
*注 ガラス写真は、「陽画」でガラスの裏側に白い紙などを当てて眺めるものだったが、
後にプリントもできる「陰画」が通常となり、さらにはフィルムの登場で姿を消した。
いずれも I SO感度が低いうえに、レンズの研磨技術もまだまだ未熟で、1枚撮影するのに
銀板写真の場合で露光時間が20分以上、湿板写真の場合も相当長い露光時間が必要だった。
そのため、人物撮影の場合は露光時間中にモデルが動いてブレないよう、イスの後方や壁などに
顔や体を固定する道具が装備され、身動きできないようにして撮影されたと言われる。
それほどに難しい写真撮影の技法は、「写真術」とも言われ、
その技法をマスターした人たちは「写真師」と呼ばれ、尊敬されたそうだ。
―――――◆―――――
★35ミリカメラの誕生★
小型「35mmカメラ」の原型が生まれたのは、1913年。
当時、映画用カメラを開発に携わっていたドイツ人のオスカー・バルナックさんが、
映画用フィルムを転用して私物の小型カメラを造り出したのが始まりと言われる。
そのカメラは、後にメーカー「エルンスト・ライツ社」で「LEICA」と命名され商品化・発売へ。
改良後継機もぞくぞく誕生し、手軽に携行できるカメラとして、世界中のプロカメラマンに愛され、
高価ながらアマカメラマンからも憧れの品となり、カメラの最高級品としてしばし君臨した。
しかし、デジタルカメラの登場で、今日ではマニアのコレクション品になってしまった。
その一方で、ライツ社はデジタルの波に乗り遅れまいと、日本のパナソニック等の
デジタル技術を取り込み、今日、デジタル機能搭載のLEICAを売り出した。
 LEICA・スタンダード
LEICA・スタンダード
| 「消えたカメラ」 カメラの歴史の中で、一時期一世を風靡したが、今日、その姿を消したカメラが多くある。1930―70年代に大流行した「二眼レフ・カメラ」と「スプリング・カメラ」は、その代表的なものと言える。  「二眼レフ・カメラ」は、カメラ本体の前面にレンズ二個が上下についており、上のレンズで被写体を見て、下のレンズでその画像を写す仕組みになっている。35ミリカメラに比べて大きく携帯向きではないが、ブローニー判フィルムを使用して、画面が縦横6センチになる6×6判カメラと、少し小ぶりでベスト判フィルム使用する4×4判カメラの二種類があり、どちらもフィルムの大きさから35ミリ判に比してきめ細やかなプリントが得られるということで、精密な写真を好む人たちから愛用された。  また「スプリング・カメラ」は、レンズと本体の間が折りたたみ自在な蛇腹状の幕で造られ、使用しないときは蛇腹をたたんで本体に格納できるようになっている。 使用するフィルムも二眼レフ同様ブローニー判、ベスト判用があり、二眼レフに比べて軽く携帯にも便利なことから、風景写真や山岳写真などを撮る人たちから重宝された。 上記のカメラにとどまらず、デジタルカメラ時代になった今日、フィルムを使用するカメラは生産がストップされ、姿を消すことになってしまった。 その一方でこうしたフィルムカメラはコレクター商品となり、新品に近いものは貴重品扱い。高い値段で取引されたり、また壊れかけたカメラでも部屋を飾るインテリアの一つとして第二の人生を送ることにーー。 |
★デジタル・カメラの出現★
| 1970年代になって、アメリカで光の濃淡をデジタル信号に変換する「CCD」、「CMOS」が開発され、それらをカメラに利用できないものか――と研究開発がはじまった。 その先陣をきったのはカメラ業界でなく、ソニー、カシオなど家電関連業界で、一部のマスコミなどと提携して開発・試作・試し撮りなどを繰り返しながら、10年程の後に「デジタルカメラ」を完成させた。 未来型カメラとして市販も始まったが、当初のデジカメはミカン箱の半分ほどもある大きさ。画素数も低く、色調も悪く、その上に開発コストの関係で、値段が今日のコンパクト・デジカメの約50倍以上。そのために一般化せず、ただ、画像がデジタル信号に変換され、簡単に編集者の元に送信出来ることから新聞社、出版社、通信社などで使用されるぐらいだった。 その後、研究開発が進み、カメラ内部が小さくコンピュータ化されて量産も可能となり、値段も手ごろとなって一般でも使用する人たちも増えた。これにはカメラ業界も見過ごしてはおられないと開発に参入。電気関連業界、カメラ業界がこぞって次々に新製品を開発し、発売されるようになった。  今日のデジカメは、画素数も3000万画素を越える製品も登場し、色調もフィルムと同等になり、値段も格段に安くなった。 今日のデジカメは、画素数も3000万画素を越える製品も登場し、色調もフィルムと同等になり、値段も格段に安くなった。フィルムの役割をする記録メモリーは何度でも使えることや、液晶モニターで即時に撮影画面が確認でき、撮り直しも即座にできる、画像をパソコンに取り込んで編集処理したあと簡単に送信やプリントできることなど、利点が多いことから、大ブームに。 いまや一家に1台から2台の時代になった。 |
スマホ・カメラの誕生
スマホ・カメラの誕生以前に、まずはケータイ電話のカメラ付きが誕生した。
1999年9月、DDIポケットより発売された、京セラが開発した「VP-210」が
世界初のカメラ付き携帯電話 (PHS) と言われる。
その後、色々な企業がカメラ付きのケータイ電話を開発して発売。
各社ますます研究開発に当たり、携帯電話はカメラだけでなく、
インターネット通信もできるなど、ミニパソコンのような機能を持つ
現在のスマートフォン(スマホ)に進化していった。
スマホは2010年代には、大人から子供までが使用する大ブームとなり、
今やスマホは一人一台から二台--と必需品。
搭載されているカメラの画素数も小型デジタルカメラと変わらない製品まで登場。
その上、全自動機能システムにより自分を撮影(自撮り)することも簡単。
人物や風景などは当然のこと、草花などの接写も可能。
そうした撮影画像を親しい仲間と送信しあったり、
さらにはツイッター、フェースブック、インスタグラム、blogなどにUPして、
多くの人に見せることが流行となった。
スマホで上手く映った写真は、「インスタ映え」との造語も誕生。
インスタ映えする風景や建造物などをウリにする観光地や店舗業者なども続々登場した。
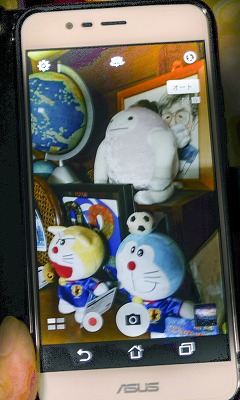
スマホカメラの撮影は誰でも簡単に出来るので大変便利だが、観光地などで
撮影に夢中になって危険な足元のことを忘れ川や崖から転落――などの事件も。
◆
スマホでの撮影に限らず、通常カメラでも写真撮影時には
身の安全も――それが一番大切であること心したいものである。
―--------------------------------――