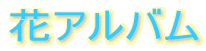 |
気の向くままに撮した花の写真を 50音順に並べてみました 振り返れば随分と撮した物です |
| 2007/08/00 Up |
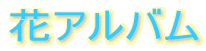 |
気の向くままに撮した花の写真を 50音順に並べてみました 振り返れば随分と撮した物です |
| 2007/08/00 Up |
 |
バーベナ(ビジョザクラ) Verbena hortensis hort クマツヅラ科バーベナ属 花の形がサクラに似ていて、花色が豊富(赤、ピンク、白、紫)で華やかな咲き方です。花径10ミリほどで5〜6月に咲きます。 |
 |
バイカカラマツ Anemonella thalicetroides キンポウゲ科バイカカラマツ属 北アメリカ西部原産の多年草です。 草丈10センチほどで、春〜夏にかけて一重〜八重の10〜20ミリの花を咲かせます。品種は多数あるようです。 |
 |
ハイビスカス Hibiscus rosa-sinensis アオイ科フヨウ属 中国南部原産で江戸時代初期に渡来した花木です。3000種以上もの品種があると言われています。 樹高2〜3メートルになり、7〜9月に約10センチほどの花を咲かせます。花色は赤、橙、黄色ですが品種により異なります。 |
 |
ハギ Lespedeza bicolor マメ科ハギ属 日本、朝鮮半島、中国が原産の多年草または落葉低木です。樹高1〜3メートルの物が多く、種類によって分布や高さが異なります。 花は6〜10月に長さ10ミリの紅紫の唇弁花を多数付けます。 ヤマハギ、ミタギノハギ、シロバナハギなどの品種があります。 |
 |
ハキダメギク Compositae Galinsoga ciliata キク科コゴメギク属 熱帯アメリカ原産の1年草です。大正時代に東京で見つかり、今では関東地方以西の各地で見られるようです。 草丈15〜60センチになり、2分枝を繰り返した枝先に、5ミリほどの頭花を6〜11月につけます。周りの舌状花は白、内側の筒状花は黄色をしています。 |
 |
ハコベ(ミドリハコベ、ヒヨコグサ、スズメグサ) Caryophyllaceae Stellaria neglecta ナデジコ科ハコベ属 日本の至る所に見られる1〜2年草です。良く枝分かれして高さ10〜30センチになります。3〜9月に6〜7ミリの白い花を咲かせます。花弁は5枚ですが、基部近くまで2裂しているので10枚のように見えます。 |
 |
ハゴロモジャスミン Jasminum polyanthum モクセイ科ジャスミン属 中国原産ですが明治末期に渡来したツル性常緑低木です。2〜4月に3〜4センチの白い芳香のある花を咲かせます。 |
 |
ハス Nelumbo nucifera スイレン科ハス属 日本、中国、インドなどに分布します。根は蓮根として知られるもので、鑑賞用の花ハスと食用ハスが栽培されています。花ハスは70種近い品種があるようです。 水面から1〜2メートルの高さになり、7〜8月に15〜25センチの桃、紅、白色などの花を咲かせます。 |
 |
ハツユキカズラ |
 |
ハナカイドウ バラ科リンゴ属 中国原産の高さ5〜8メートルの落葉小高木です。 葉は先が尖ったタマゴ形で長さ3〜8センチ、幅2〜5センチで縁にギザギザがあり、固く光沢があります。 花期は4月頃で枝先に花経3〜4センチの鮮やかな淡紅色の花を4〜6個集めて咲かせます。 |
 |
ハナカンザシ Ryodanthe chlorocephala rosea キク科ローダンテ属 オーストラリア原産の1年草です。基部から多数の枝を出し、草丈は40〜60センチになり、枝先に3センチほどの花を咲かせます。 花色は桃、白色があります。 |
 |
ハナキリン Euphorbia milii トウダイグサ科ユーフォルビア属 マダガスカル原産の低木状の多肉植物で、大正初期に渡来して植物園の温室で見られましたが、今では鉢植えとして売られるようになりました。 樹高1メートルほどになり、冬から春頃に1センチほどの花を咲かせます。花色はピンク、白色、黄色があります。 |
 |
ハナショウブ Iris ensata アヤメ科アヤメ属 日本、朝鮮半島、中国西部、シベリアが原産地です。 野生のノハナショウブから改良され、江戸系、肥後系、伊勢系、アメリカ系などの品種が作出されています。 草丈は60〜120センチほどになり、6月頃に12〜30センチの花を咲かせます。花色は紅紫、白、青、桃と品種により異なります。 |
 |
ハナズオウ Cercis chinensis マメ科ハナズオウ属 中国原産の高さ3〜5メートルになる落葉低木です。江戸時代に渡来して、日本各地の庭園や公園に見られるようになりました。 4月頃に枝の節々に2センチほどの紅紫の花を多数付けます。 |
 |
ハナニラ(セイヨウアマナ) Ipheion unifiorum ユリ科イフェイオン属 アルゼンチン、ペルー、ウルグアイ平地原産で明治半ば頃に渡来した球根多年草です。 草丈10〜15センチほどで、3〜4月頃に3〜4センチの淡青紫の花を咲かせます。 |
 |
ハナミズキ(アメリカヤマボウシ) Comus florida ミズキ科ミズキ属 北米原産の落葉高木で大正初期に渡来した花木で、日本では5〜8メートルになります。 4月頃に花径6ミリほどの半球形の花を咲かせます。花びらのように見える物は総苞で、長さ4〜6センチの総苞片が4枚つきます。 |
 |
ハナモモ(モモ) バラ科サクラ属 果実の収穫を主にするモモに対して、花を観賞する品種の総称で、基本的にはモモと変わりません。 花期は4月で、葉の出る前に花径25〜35ミリ、白色、淡紅色、紅色の花を咲かせます。 八重咲き、菊咲き、じだれ咲きなどの品種があります。 |
 |
ハハコズサ(ホオコグサ、オギョウ) Compositae Gnaphalium affine キク科ハハコグザ属 道端や畑などに普通に見られる高さ15〜40センチの多年草です。全体に綿毛に覆われて白っぽく見えます。 4〜6月頃に、枝先に黄色い小さな頭花を多数付けます。 |
 |
ハブランサス Habranthus robustus ヒガンバナ科ハブランサス属 中南米の原産です。 アマリリスを小さくしたような花形の小球根多年草です。草丈は15〜25センチほどになり、6〜7月に6〜8センチの桃、白色の花をやや上向きに咲かせます。 |
 |
ハボタン |
 |
パポニア |
 |
ハマナス(ハマナシ) Rosa rugosa バラ科バラ属 茨城県以北、島根県以北の海岸に分布して株立ちになる落葉低木で、高さは100〜150センチほどになり、地下茎を伸ばして広がります。 5〜8月に桃色、紅紫色、まれに白色の6〜8センチの花を、枝先に1〜3個咲かせます。 8〜9月に平たい丸形の果実を赤く熟します。中には5ミリほどの種子が入っていて果実は食用になります。 |
 |
バラ Rosa spp. バラ科バラ属 北半球に100〜200種、日本には10数種が自生しています。 世界に15000種、日本に5000種の品種があると言われていて、観賞用に栽培される多くは、複雑な種間、品種間交雑により作られてきた株立ち性とツル性に分けられます。 |
 |
ハルジオン(ハルジョオン) Compositae Erigeron philadelphicus キク科ムカシヨモギ属 北アメリカ原産の多年草で、大正時代に園芸植物として渡来しましたが、各地に雑草化しています。 5〜7月に20〜25ミリの淡白紅色の頭花を咲かせます。蕾の時は花序全体がうなだれていて、花は舌状花は糸状で多数あります。 |
 |
バルレリア |
 |
パンジー(サンシキスミレ) Viola × wittrockiana スミレ科スミレ属 北欧原産で日本には江戸時代末期に渡来して、沢山の品種が作り出されています。 草丈は10〜15センチほどで、3〜5月頃に3〜5センチの花を咲かせます。花径や花色は品種によって異なりますが、黄、紫、白、ピンク、橙と豊富です。 |
 |
パンジーゼラニウム |
 |
ヒガンバナ(マンジュシャゲ) Lycoris radiata ヒガンバナ科ヒガンバナ属 日本全土に分布していて、土手や田の畦道などに普通に生える球根多年草です。 9月頃に高さ30〜50センチの花茎を伸ばし、15〜20センチの赤い花を咲かせます。品種改良されて紅桃色、黄色、白色などの花も見られるようです。 |
 |
ビナンカズラ(サネカズラ) Kadsura japonica モクレン科サネカズラ属 東北南部以南、四国、九州、沖縄、中国、台湾に分布するツル性の常緑低木です。雄雌異株です。 花期は8〜9月頃で黄白色、10〜11月頃に3センチほどの丸形の実が赤く熟します。園芸品種には葉に斑が入る物や果実が白色になるスイショウカズラなどがあります。 |
 |
ヒポエステス |
 |
ヒマラヤユキノシタ(オオイワウチワ) Bergenia stracheyl ユキノシタ科ベルゲニア属 ヒマラヤ原産の耐寒性が強い宿根多年草です。 草丈は30〜40センチになり、3〜4月に花茎を伸ばしピンクの1センチほどの花を密生させます。 |
 |
ヒマワリ(ヒグルマ、ニチリンソウ) Helianths annuus キク科ヒマワリ属 アメリカ中西部原産で江戸時代に渡来した1年草でうす。 高さが1.5〜3メートルになり10〜30センチの黄色い花を7〜8月に咲かせます。 品種が幾つかありオレンジ、黒赤色の物もあります。 |
 |
ヒメアリアケカズラ(アラマンダ) Allamanda neriifolia キョウチクトウ科アラマンダ属 中南米原産で明治末期に渡来した花木です。 高さは1〜2メートルになり、温室で張るから秋に3〜5センチの黄色い花を咲かせます。 |
 |
ヒメイワダレソウ |
 |
ヒメウズ(姫烏頭) Ranunculaceae Aquilegia aboxoides キンポウゲ科オダマキ属 山麓の草地や道ばたなどに生える10〜30センチの多年草です。花はかすかに紅色を帯び、相対的には白っぽく見えます。 花期は3〜5月で、花径は4〜5ミリと小さく俯き加減に咲き、関東地方以西、四国、九州に分布しています。 |
 |
ヒメオドリコソウ Labiatae Lamium purputeum シソ科オドリコソウ属 ヨーロッパ原産の2年草で、明治中期に渡来して東京周辺に多く見られます。 高さ10〜25センチで上部の葉は密生し赤紫色を帯び、4〜5月に長さ1センチほどの淡紅色の唇形花を密に付けます。 |
 |
ヒメコブシ |
 |
ヒメジョオン Compositae Erigeron annuus キク科ムカシヨモギ属 北アメリカ原産の1〜2年草で、明治初期に渡来しました。現在では日本中に広がり亜高山地でも見られるようになりました。 高さは30〜130センチになり、頭花は2センチと小さく、上部の枝先に多数つきます。舌状花は白色またはわずかに淡紫色を帯びます。 |
 |
ヒメツルソバ Polygonum capitatum タデ科タデ属 インド北部、ヒマラヤ原産で明治中期に渡来した宿根草です。 草丈は30センチほどになり、8〜10月に花径1センチほど、半球形の淡紅色の花を咲かせます。 |
 |
ヒメビシ |
 |
ヒメフウロ |
 |
ヒメフヨウ |
 |
ヒヨドリジョウゴ Solanum lyratum ナス科ナス属 日本全土に分布するツル性多年草です。 8〜9月に10〜15ミリの白い花弁の花を咲かせ、秋には6〜8ミリの丸い果実が紅色に熟します。 |
 |
ヒヨドリバナ Compositae Eupatorium chinense キク科フジバカマ属 ヒヨドリが鳴く頃に花が咲く所から、この名があるそうです。 高さ1〜2メートルになる多年草です。8〜10月頃につく頭花は散房状で、少数の長さ5〜6ミリの筒状花から成り立っています。 |
 |
ヒルガオ Convolvulaceae Calystegia ヒルガオ科ヒルガオ属 日当たりの良い野原や道端などに生えるツル性多年草です。地中に白色の地下茎を伸ばして増えます。 6〜8月に葉脈から永い花柄をだし、日中に5〜8センチの淡紅色の花を咲かせます。 |
 |
ピラカンサ(トキワサンザシ) Pyracanths coccinsa バラ科トキワサンザシ属 西アジア、南ヨーロッパ原産の高さ2〜6メートルの常緑低木です。 5〜6月に枝先に7〜8ミリの白い花を半球形状に多数付け、10〜11月になると房状に密集した実が熟すと、鮮紅色あるいは黄色くなります。 |
 |
ビワ Eriobotrya japonoca バラ科ビワ属 東海地方以西に分布し、暖地では果樹として栽培される、常緑高木で高さは6〜10メートルになります。 11〜1月に長さ10〜20センチほどの花房をつけます。花は白色で花径1センチほどが多数纏まって咲きます。 果実は3〜4センチの卵形をして、5〜6月に熟すと黄橙色になります。 |
 |
フウセントウワタ Gomphocarpus fruticosus ガガイモ科フウセントウワタ属 南アフリカ原産の高さ1〜2メートルになる1〜2年草です。 花果実期は8〜11月で、花は白色で15ミリほど、フウセンのような果実は5〜6センチで緑色をしています。 |
 |
フウリンブッソウゲ |
 |
フウロケマン Corydalis.pallida ケシ科キケマン属 山地や低地の日当たりの良いところに生える越年草です。草丈15〜45センチになり。長さ2〜5センチの総状花序に長さ2センチの黄色花を沢山つけます。霶果はややくびれた線形で長さ2センチほどになります。 |
 |
フキノトウ(フキ) Petasites japonicus 本州、四国、九州の山野に生える多年草で、地下茎を伸ばして増えます。 フキの若い花茎がフキノトウで早春の山菜として知られ食用にされます。雌雄異株で、雄株は10〜25センチになり期白色の頭花を多数付けます。雌株ははじめ密に頭花を付けますが、花後に45センチほどになります。 |
 |
フクロナデシコ(マンテマ、シレネ) Silene pendula ナデシコ科シレネ(マンテマ)属 地中海沿岸原産の1年草です。草丈は20〜40センチになり、5〜6月に2センチほどのピンクの花を多数咲かせます。花の基部がプックラとふくらんでこの名がついたようです。 |
 |
フサスグリ Ribes rubrum ユキノシタ科スグリ属 ヨーロッパ西部、アジア北西部原産で明治年間に渡来した小果樹で、高さ1〜1,5メートルになります。 4月に葉脈から房状に花芽をつけ、花形5〜10ミリの黄緑色の花を多数つけます。 7〜8月に8ミリほどの果樹を赤く熟させます。果樹は生食したりジャムや果実酒に利用されます。 |
 |
フジバカマ Compositae Eupatorium fortunei キク科フジバカマ属 本州の関東地方以西、四国、九州の川の土手などに野生する高さ1〜1.5メートルの多年草です。奈良時代に中国から渡来したそうです。 花期は8〜9月頃で頭花は淡紅紫色で散房状に多数付けます。 |
 |
フヨウ(モクフヨウ) Hibiscus mutabilia アオイ科フヨウ属 日本の南部に分布する高さ1〜4メートルの低木です。寒地では冬に地上部が枯れ、地下部だけで越冬し春に再生します。 花期は7〜10月で上部の葉脇に白または淡紅色の花径10〜14センチの大輪の花を咲かせます。 |
 |
ブライダルベール |
 |
プラタナス(スズカケノキ) Platanus orientalis スズカケノキ科スズカケノキ属 西アジアからヒマラヤにかけて広く分布し明治初期に渡来しました。高さは30メートル以上になる落葉高木です。 花期は4〜5月で丸形、花径3〜4センチの赤い集合花を垂れ下がるように咲かせます。果実はそのままの形の集合果です。 アメリカスズカケノキ、モミジバスズカケノキなどの種があります。 |
 |
プリムラ・オブコニカ(トキワザクラ) Primura obconica サクラソウ科サクラソウ属 中国西部原産の草丈20〜30センチになる多年草です。 プリムラ類のなかでは暑さに強く上部ですが、寒さには弱いようです。 花期は1〜4月、1〜2センチの桃、白、橙色の花を5〜10センチの半球形状に沢山咲かせます。 |
 |
プリムラシネンシス |
 |
ブルークローバー Parocetus communis マメ科パロケツス属 ヒマラヤ、熱帯アフリカ原産の草丈10〜15センチの多年草です。葉がシロツメクサ(クローバー)に似ています。 花期は5〜6月で花の大きさは15ミリほどで青色の花を咲かせます。 |
 |
ブルースター |
 |
ブルーファンフラワー |
 |
ヘクソカズラ(ヤイトバナ、サオトメカズラ) Rubiaceae Paederia scandens アカネ科ヘクソカズラ属 何とも可愛そうな名前ですが、花や葉、果実を揉んだりしたときの匂いを嗅いだらなるほどと納得ができるでしょう。 日当たりの良いやぶや草地、土手などで普通にみられます。 |
 |
ヘチマ |
 |
ヘトロケントロン |
 |
ベニゴウカン(ヒネム) マメ科ベニゴウカン属 南アメリカ北部原産の常緑低木で高さ1〜1,5メートルになります。 花期は5〜10月と長く枝先に赤紫色の花を咲かせます。花弁に見えるのは雄しべで、基部で合着し先が永く突き出ています。 |
 |
ベニヒモノキ(アカリファ) Acalypha hispida トウダイグサ科エノキグサ属 マレー半島原産で温室などで栽培され、温室地植えで2〜3メートルになります。 花期は通常夏頃で(温室では冬でも見られます)、花序は20〜50センチの紐状をして垂れ下がります。花色は赤、白色があります。 |
 |
ベニマツリ |
 |
ベニモンヨウショウ |
 |
ヘメロカリス(デイリリー) Hemerocallis ユリ科ワスレグサ属 日本、中国が原産地で野生のノカンゾウ、ユウスゲ、ニッコウキスゲなどから19世紀末にヨーロッパで改良され、アメリカで品種が作られたそうです。 草丈60〜120センチになる球根植物で、6〜7月頃に5〜20センチの花を咲かせます。花色は黄、橙色が主ですが品種により違います。 |
 |
ヘリコニア |
 |
ホオズキ Physalis alkekengi ナス科ホオズキ属 熱帯〜温帯アメリカ原産で草丈30〜50センチの1年草です。古くから日本に帰化しています。 花期は7〜8月で1〜2センチの白い花を咲かせます。花後に3〜5センチの袋状の鞘に包まれた果実を付け、熟すと橙色になります。 |
 |
ポーチュラカ |
 |
ボケ(カラボケ、クサボケ、ノボケ、シドミ、コボケ) Chaenomeles speciosa バラ科ボケ属 中国原産で平安時代に日本に渡来し各地に広がった樹高1〜2メートルの落葉低木です。 江戸時代からさかんに栽培され多くの品種が作出されてきました。 花期は4月で赤、白、ピンクの花色がありますが、品種により異なります。 |
 |
ホシアサガオ Convolvulaceae Ipomoea triloba ヒルガオ科サツマイモ属 北アメリカ原産と言われるツル性1年草で主に西日本に帰化しています。 花期は7〜9月で、花は淡紅色で中心部が紅紫色を帯びる物が多いようです。花径は1〜2センチで漏斗形をしています。果実はやや縦長の球形をしています。 |
 |
ホソバテッポウユリ |
 |
ホタルカズラ Buglossoides zollingeri ムラサキ科イヌムラサキ属 日本全国に分布し、日当たりの良い山野の乾いたところに野生する草丈15〜20センチの宿根多年草です。 花期は4〜5月で花径15〜20ミリの青紫色の花を咲かせます。 |
 |
ホタルブクロ(チョウチンバナ、ツリガネソウ、トックリバナ他) Campanulaceae Campanula punctata キキョウ科ホタルブクロ属 日本全土に分布して山野や丘陵に生える高さ40〜80センチの多年草です。 花期は6〜7月で茎の上部に長さ4〜5センチの釣鐘形の花を咲かせます。花冠は淡紅紫色または白色で濃い色の斑点があります。 ヤマホタルブクロ、シマホタルブクロなどの種もあります。 |
 |
ボックセージ |
 |
ホトケノザ Lamium amplexicaule シソ科オドリコソウ属 本州、四国、九州、沖縄で見られる草丈10〜30センチの1年草です。 花期は3〜6月で15〜20ミリの筒状の花を咲かせます。花色は紅紫色をしています。 |
 |
ホトトギス Tricyrtis hirta ユリ科ホトトギス属 関東以西の本州、四国、九州に分布して、山地の湿った崖などに生える多年草です。 花にある斑点がホトトギスに似ているところから付いた名前のようです。 花期は9〜10月で草丈50〜100センチになり、葉の付け根に25〜40ミリの花を咲かせます。花色は淡紫色、白色などがあります。 |
 |
ポポー(ポーポー) Asimina trioba バンレイシ科ポポー属 北アメリカ東部原産の果樹で、明治の中頃に日本に導入されました。高さ6〜15メートルの落葉小高木で関東以南では戸外で栽培されています。 花期は4〜5月で、花色ははじめは緑色をしていますが暗紫色にかわり、 花径3〜4センチの鐘形で中心は黄色をしています。 果実はアケビに似た形をして10月頃に熟すと、果肉は粘りけのある黄色になり甘く特有の香りがします。 |
 |
ボリジ(ルリチシャ) Borago officinalis ムラサキ科ボラゴ属 ヨーロッパ原産の草丈40〜60センチになる食草です。 開花期は6〜9月で、花は星形の5弁花で花径2〜3センチ、初めはピンクをしていて次第に青色に変わっていきます。 若葉はキュウリに似た風味があり生食します。 |