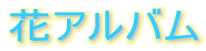 |
気の向くままに撮した花の写真を 50音順に並べてみました 振り返れば随分と撮した物です |
| 2007/08/11 Up |
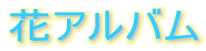 |
気の向くままに撮した花の写真を 50音順に並べてみました 振り返れば随分と撮した物です |
| 2007/08/11 Up |
 |
アオキ(青木)Aucuba japonica ミズキ科アオキ属 暖帯の林に生えます。果実は楕円形で赤く熟します。 庭木として植えられています。 |
 |
アオコケ |
 |
アカギツツジ ツツジ科ツツジ属 ツツジは北半球の温帯を中心に約800種以上があり、日本にも数十種が分布しています。 この種は赤城山に多く見られる1種です。 |
 |
アカザ Chenopodium album var. centrorubrum アカザ科アカザ属 若葉が紅紫色の粉状物に覆われています。ホウレンソウの仲間で食用になります。乾燥地やアルカリ性の土地に生え日本全土に分布します。 |
 |
アカツメクサ(ムラサキツメクサ) Leguminosae Trifolium pratense マメ科シャジクソウ属 牧草として明治初期に渡来して、全国に野生化している多年草です。 花は球状に集まって咲き、赤紫色で13〜15ミリほどあります。 |
 |
アカバナユウゲショウ Onagraceae Oenothera rosea アカバナ科マツヨイグサ属 南アメリカ原産の多年草で、明治時代から栽培され始めたそうです。現在は関東地方以西に野生化しています。 淡紅色の1センチほどの花を夕方に開くところから付けられた名前のようです。 白い花のシロバナユウゲショウもあります。 |
 |
アガパンサス Agapanthus ユリ科アガパンサス属 アガパンサス属には約20種があり、日本には2種があるそうです。栽培が容易なので花壇に植えられたりしています。 花色は青紫と白があります。 |
 |
アカミサンザシ バラ科サンザシ属 中国南部原産の落葉低木です。枝は良く分枝して横に広がり刺があります。 花は約2センチの白い花です。果実は15ミリの丸形で熟すと赤くなります。 |
 |
アカリファ レブタンス Acalypha reptans Sw トウダイグサ科エノキグサ属 インドに分布しています。ベニヒモノキに似て小形、葡萄性で花は赤色をして花序は5〜7センチあります。 |
 |
アキノキリンソウ Compositae solidago virga aurea ssp.asiatica キク科アキノキリンソウ属 日当たりの良い山野に生える30〜80センチの多年草です。枝の上部に約13ミリの黄色い花を多数つけます。 花期は8〜11月で日本全土で見られます。 |
 |
アキノタムラソウ Labiatae Salvia japonica シソ科アキギリ属 山野の道端などに見られる高さ20〜50センチの多年草です。7〜11月に茎の上部に長さ10〜25センチの花穂をだし、長さ10〜15ミリの青紫の唇形花を数段輪生させます。 |
 |
アキノノゲシ Compositae Lactuca indica キク科アキノノゲシ属 日当たりの良い荒れ地や草地に生える高さ60〜200せんちの1〜2年草です。 頭花は2センチほどで淡黄色、まれに白色、淡紫色も見られ昼咲き、夕方には萎んでしまいます。 |
 |
アケビ Akebia quinata アケビ科アケビ属 つるを長く伸ばして樹木などにからみついて生育し,春先に淡い紫色の花が葉の脇に数個まとまってつきます。果実は長楕円形で秋に熟すと縦に割れて甘い果肉が覗きます。 普通種の他にミツバアケビ、シロバナアケビなど数種があります。 |
 |
アサガオ Pharbitis nil choisy ヒルガオ科アサガオ属 奈良時代に薬用として種子が中国から渡来したと言われます。江戸時代に観賞用として改良され一般に広まるようになりました。 花色は赤、白、青、紫、茶などがあります。 |
 |
アサザ Gentianaceae Nymphoides peltata リンドウ科アサザ属 池や沼などに生える多年生の水草です。地下茎は水底の泥の中を長く這い、葉には長い葉柄があって水面に浮かびます。6〜8月頃に3〜4センチの黄色い花を咲かせます。花弁は5つで縁は糸状に細かく裂けています。 |
 |
アザミ Compositae Cirsium japonicum ets キク科アザミ属 北半球に約250種有ると言われ、日本にも60種ほどあるそうです。 葉には刺があり頭花はすべて両性の筒状花が集まった物です。 花期は5〜10月で品種によって異なります。 |
 |
アサリナ・グラリオ ゴマノハグサ科アサリナ属 メキシコ原産で非耐寒性の蔓性1年草または多年草です。 蔓は3〜4メートルになり3〜4センチの赤い花を6〜11月頃まで次々と咲かせ続けます。 |
 |
アジサイ Hydrangea macrophylla ユキノシタ科アジサイ属 本州と四国の一部に分布するガクアジサイの変種と考えられているそうで、自生種か園芸種かがはっきりとしないようです。 花期は6〜7月で花色は青紫、淡紅、白などがあります。 |
 |
アセビ ツツジ科アセビ属 高さ1〜5メートルの常緑低木です。春に壺形の花がまとまって、下向きに垂れ下がるように咲きます。 花期は3〜4月で淡紅と白の花色があります。 |
 |
アベリア Abelia grandiflora スイカズラ科ツクバネウツギ属 中国原産のシナツクバネウツギとユニフローラの交配種で大正末期に移入されたそうです。 1〜2メートルの低木で垣根などに植えられています。 花期は6〜10月で花色は白、淡い桃色を含んだ物もあります。 |
 |
アマチャ Hydrangea macrophylla ユキノシタ科アジサイ属 本州の山地に自生しています。乾燥した葉が甘いので甘味料として利用されています。 花期は7月で淡紫から淡紅に変化します。 |
 |
アマドコロ Liliaceae Polygonatum odoratum var.pluriflorum ユリ科アマドコロ属 山野の草地などに生える高さ30〜60センチの多年草です。葉腋に白い筒状の花を1〜2個ずつ垂れ下がるようにつけます。花は長さ15〜20ミリで、先の方は緑色をしています。 |
 |
アメリカフウロ Geraniaceae Geranium carolinianum フウロソウ科フウロソウ属 北アメリカ原産の1年草で、昭和初期に渡来して本州、四国、九州に帰化しています。花は淡紅白色をして5〜9月に咲きます。 |
 |
アメリカン・ブルー(エボルブルス) Evolvuls pilosus ヒルガオ科エボルブルス属 北アメリカ原産の多年草です。草丈20〜50センチ、花径10〜20ミリで鮮やかな青色の花を6〜11月頃にかけ多数付けます。非耐寒性のため冬は室内で育てます。 |
 |
アラビス |
 |
アリアケカズラ |
 |
アルストロメリア Alstromeria psittasina ヒガンバナ科ユリズイセン属 花色は黄、オレンジ、桃色とカラフルで切り花としても人気がある多年草です。草丈30〜70センチ、花径5〜7センチで、品種改良がされています。 |
 |
アルピニア プルプラタ Alpinia purpurata ショウガ科 |
 |
アルペンブルー |
 |
アロエ Aloe arborescens ユリ科アロエ属 アロエ属は不耐寒性の多肉植物で約300種ほどあります。医者いらず、薬用アロエと呼ばれ火傷や切り傷などに使われています。1〜2メートルの高さになります。 |
 |
イタドリ Polygonum cuspidatum タデ科タデ属 山野の日当たりの良いところや川の縁などに群生する、高さ30〜150センチの多年草です。 中部以北の山地に生えるオオイタドリもあります。 |
 |
イチョウ Ginkgo biloba イチョウ科イチョウ属 実は球形で秋に完熟すると自然に落ち、悪臭を放ちます。種はギンナンとして市販されています。 |
 |
イヌウメモドキ |
 |
イヌコウジュ Labiatae Mosla punctulata シソ科イヌコウジュ属 山野の道端などに生える高さ20〜60センチの1年草です。枝先に花穂をだし淡紫色の3〜5ミリの唇形花を多数付けます。花期は9〜10月で日本全土に分布します。 |
 |
イヌタデ(アカマンマ) Polygonaceae Polygonum longisetum タデ科タデ属 道端や畑、荒れ地などに生える高さ20〜50センチの1年草です。 *タデ属は種が多く判別が難しいです。 |
 |
イヌホウズキ(バカナス) Solanaceae solanum nigrum ナス科ナス属 ホオズキやナスに似ているが役に立たない。畑や道端に生え高さ30〜60センチの1年草です。7〜10ミリの白い花を付け、7〜8ミリの球形の実は熟すと黒くなります。花期は8〜10月で日本全土に分布します。 |
 |
ウグイスカグラ(ウグイスノキ 鶯神楽) スイカズラ科スイカズラ属 本州以南に分布する落葉低木で、高さ1〜3メートルあります。4〜5月に枝先に細長いラッパ状のピンクの花が下向きに垂れ下がります。6月に1センチほどの楕円形の甘味がある果実が紅熟します。 |
 |
ウチワサボテン(オプンチア・ロブスタ) Opuntia robusta サボテン科アプンチア属 熱帯の海岸から高山に分布して、かなりの耐寒性があり暖地では戸外でも越冬します。円形扁平の緑色の葉のような茎に花径5センチほどの黄色い花を夏期に咲かせます。 |
 |
ウノハナ(ウツギ) Deutzia crenata ユキノシタ科ウツギ属 幹が中空になることから空木の名があるそうです。樹高150〜200センチ、花径10〜15ミリの白い花を5月頃咲かせます。 本州(長野県南部、静岡県西北部)、四国に分布しています。 |
 |
ウメ Prunus mume バラ科サクラ属 高さ5〜10メートルになる落葉高木で中国原産ですが古来から日本各地で栽培され親しまれています。 園芸上では野梅性、紅梅性、豊後性、杏性の4系統に分類されて、品種改良され200〜300品種あると言われています。 果実は梅酒や梅干しなどに使われています。 |
 |
ウメモドキ Llex serrata モチノキ科モチノキ属 山地に生え赤い実が沢山付くので鑑賞用に公園や庭園などに植えられています。 樹高は2〜3メートルになり、11〜12月頃に5ミリの実を赤く熟します。 |
 |
ウラシマソウ Araceae Arisaema urashima サトウモ科テンナンショウ属 山野の木陰に生える多年草です。地中の球茎は多くの子球をつくって繁殖します。葉は1個だけ根生し11〜17に深裂して、高さは40〜50センチになるものもあります 3〜5月頃葉柄の基部から花茎をだし紫褐色の仏炎苞に包まれた肉穂花序をつけます。花序の付属体は紫黒色で長さ60センチほどになるものもあります。 |
 |
エアープランツ(エアプランツ) Tillandsis * *は品種名になります パイナップル科 土のいらない植物として人気が有ります。パイナップルの仲間でアメリカ大陸の熱帯、亜熱帯に原産し、木の幹や岩場に着床している植物です。湿度の差が激しい地域や多湿の地域に自生していますが、乾燥にも耐える構造を持っています。 |
 |
エクボソウ |
 |
エゴノキ(チシャノキ) Styrax japonica エゴノキ科エゴノキ属 全国に分布する落葉高木で6〜7メートルになります。5〜6月頃に新緑の枝先に花径15ミリほどの白い花を多数付けます。秋には丸形の果実が多数垂れ下がるようにつきます。 花が淡い紅色のベニバナエゴノキや枝先が垂れ下がるシダレエゴノキがあります。 |
 |
エゾギク(アスター) Callistephus chinensis キク科エゾギク属 中国北部の原産で江戸中期に渡来したそうです。草丈30〜50センチ、花径3〜4センチ、花色は豊富で赤、紫、藤、桃、白などがあり8〜9月に花をつけます。 |
 |
エノコログサ(ネコジャラシ) Setaria viridis イネ科エノコログサ属 日本全土の道端や畑などに生えています。花穂が子犬の尾に似ているところから付けられた名前だそうです。 開花期は8〜11月で草丈40〜70センチ、花色は淡緑をして黄茶変します。 |
 |
オオイヌノフグリ Veronica persica ゴマノハグサ科クワガタソウ属 ユーラシア、アフリカ原産の2年草で、明治中頃に渡来し全国で見られるようになりました。3〜5月頃に茎上部の葉腋から1〜2センチの花柄を伸ばし、10〜15ミリのルリ色の花を1つ付けます。茎は良く分枝して横に広がります。 近似種にタチイヌノフグリがあります。 |
 |
オオフトモモ |
 |
オカタツナミソウ Scutellaria brachyspica シソ科タツナミソウ属 丘陵の林縁などに生える高さ10〜50センチの多年草です。5〜6月頃に茎の先に短い花穂をだし淡紫色の花を密につけます。花冠は長さ2センチで筒部は長く、基部で急に曲がって直立します。 |
 |
オキザリス Oxalis カタバミ科カタバミ属 南アフリカ、中南米原産の球根植物です。草丈は種類によって異なり、花径も種類によって異なります。開花期は色々ですが冬から春にかけて咲き、日中だけ開いて夜には閉じてしまいます。 |
 |
オキナグサ Pulsatilla cermua キンポウゲ科オキナグサ属 本州、四国、九州に分布しています。和名は花後の白い冠毛を老人の白いひげに見立てて付けられたようです。 草丈は10センチ位になり、花径3センチ位の暗赤紫の花を4〜5月に咲かせます。 栽培されている西洋オキナグサには色々な花色があります。 |
 |
オシロイバナ(ユウゲショウ) Mirabilis jalapa オシロイバナ科オシロイバナ属 熱帯アメリカ原産で江戸時代初期に渡来した多年草です。夕方頃から咲き出し明け方には閉じてしまいます。 草丈は60〜100センチほどになり、7〜9月に3センチほどの花を咲かせます。花色は黄、赤、白、桃などがあり混色も見かけられます。 |
 |
オダマキ(セイヨウオダマキ) Aguilegia tlabellata キンポウゲ科オダマキ属 中央ヨーロッパ、北米、アジア北半球、日本が原産地で、日本原産にはミヤマオダマキ、ヤマオダマキが知られています。高さは30センチほどになり、5〜6月頃に5センチほどの花を咲かせます。 花色は白、黄、紫、淡赤などがあります。 |
 |
オトコエシ(男郎花) Patrinia villosa オミナエシ科オミナエシ属 オミナエシより強く丈夫そうに見えるところから付いた名前だそうです。日当たりの良い山野に良く見ることが出来る60〜100センチの多年草です。8〜10月頃に白い花を散房状に多数付けます。日本全土に分布しています。 |
 |
オニタビラコ Compositae youngia japonica キク科オニタビラコ属 道端や公園、庭の隅などに生える高さ20〜100センチの1〜2年草で、鬼は大きいことの意味だそうです。 茎の先に径7〜8ミリの黄色い花を散房状に付け、花期は5〜10月ですが、南の地方では1年中咲いているところもあるようです。 |
 |
オニノゲシ Compositae sonchus asper キク科ノゲシ属 ヨーロッパ原産の2年草です。明治時代に渡来して、現在では各地の道端や荒れ地で見られます。 高さ50〜100センチほどになり、枝先に黄色い径2センチほどの花を4〜10月に付けます。 |
 |
オニブキ |
 |
オニユリ Liliaceae lilium lancifolium ユリ科ユリ属 古くから栽培され、人里近くには野生化している物も見られる球根多年草です。 高さ1〜2メートルになり、茎には暗紫色の斑点があります。茎の上部に径10〜12センチの花を4〜20個付け、横向きあるいは下向きに咲きます。花色は橙赤色で濃い色の斑点があります。 |
 |
オミナエシ(女郎花) Patrinia scabiosaefolia オミナエシ科オミナエシ属 日当たりの良い山野の草地に生える高さ60〜100センチの多年草です。茎の上部は良く分枝して、8〜10月頃に黄色い花を散房状に多数付けます。日本全土に分布しています。 |
 |
オランダカイウ |
 |
オリヅルラン Chlorophytum comosum ユリ科オリヅルラン属 南アフリカ原産の多年草です、明治初期に渡来して観葉植物として人気が続いています。 ランナーを伸ばして、その先に折り鶴のように見える子苗を付けます。強健で育てやすい種です。 |