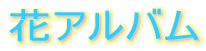 |
�C�̌����܂܂ɎB�����Ԃ̎ʐ^�� �T�O�����ɕ��ׂĂ݂܂��� �U��Ԃ�ΐ����ƎB�������ł� |
| 2007/08/11 Up |
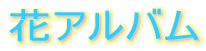 |
�C�̌����܂܂ɎB�����Ԃ̎ʐ^�� �T�O�����ɕ��ׂĂ݂܂��� �U��Ԃ�ΐ����ƎB�������ł� |
| 2007/08/11 Up |
 |
�}�[�K���b�g�i���N�V�����M�N�j Chrysanthemum frutescens �L�N�ȃL�N�� �J�i���[�������Y�̏h�����N���ł��B ����R�O�`�S�O�Z���`�ŁA�Ԋ��͂Q�`�S���A�Ԍa�T�`�U�Z���`�̔��A���A�s���N�̉Ԃ��炩���܂��B���|�i�킪�����o����Ă��܂��B |
 |
�}�c�o�E�������@Linaria canadensis �S�}�m�n�O�T�ȃE�������� �k�A�����J���Y�̂P�N���A����P�O�`�U�O�Z���`�ł��B�t�����t�̂悤�ɍׂ��A�Ԃ��E�������Ɏ��Ă���Ƃ��납��t����ꂽ���O�������ł��B �Ԃ͂P�O�~���قǂŐ��̐O�`�Ԃł��B �֓��A�ߋE�A�l���A��B�ɕ��z���Ă��邻���ł��B |
 |
�}�c�o�M�N Mesembryanthemum spectabilis �c���i�ȃ}�c�o�M�N�� ��A�t���J���Y�ő���P�O�`�Q�O�Z���`�̑��N���ł��B �Ԋ��͂T�`�U���ł����g�n�ł͂P�N���Ԃ�t���Ă���悤�ł��B�Ԍa�T�Z���`�قǂŁA�s���N�A��A���A�ԐF�Ȃǂ̉ԐF������܂��B |
 |
�}�c���C�O�U Onagraceae Oenothera stricta �A�J�o�i�ȃ}�c���C�O�T�� �`�����Y�̂Q�N���ŁA���݂ł͊e�n�̊C�݂�͌��ɖ쐶�����Ă��܂��B ����͂R�O�`�P�O�O�Z���`�ɂȂ�A�T�`�W���ɉԌa�R�`�T�Z���`�̉��F���Ԃ�[�����璩���ɂ����č炩���܂��B �������A���ґ��̕�������܂�Ă��܂��B |
 |
�}���J�~�c�� Compositae Cotula australis �L�N�ȃ}���J�~�c���� �I�[�X�g�����A���Y�̂P�N���ł��B���݂ł͒g�n�𒆐S�ɋA�����Ă��܂��B �s�̊��͒n���㕔�͎Ώサ�ĂT�`�Q�T�Z���`�ɂȂ�܂��B���Ԃ͂T�`�W�~���ŁA���S���ɉ����F�̓���Ԃ���R����܂��B |
 |
�}���n�P�I���g�i�n�G�}���T�X�j Haemanthus albiflos �q�K���o�i�ȃn�}�G���T�X�� ��A�t���J���Y�Ŗ��������ɓn�����܂����B �t�͏�Œ����P�T�`�Q�O�Z���`�A�W�`�X���ɔ����т̂悤�Ɍ����锒���Ԃ��炩���܂��B |
 |
�}���~ Euonymus sieboldianus �j�V�L�M�ȃj�V�L�M�� ���{�S���̎R��ɕ��z���闎�t��ō����͂R�`�T���[�g���ɂȂ�܂��B �T�`�U���ɍ��N�}�̓r������Ԍa�P�O�~���قǂ̗Δ����F�̉Ԃ��炩���A�ʎ��͂P�O�`�P�P���ɍg�F�ɏn���S�āA��ԐF�̉����ɕ�܂ꂽ��q��`�����܂��B |
 |
�}���o�f�B�R�i�A�����J�f�B�R�j Erythrina criste-galli �}���ȃf�B�R�� �u���W�����Y�ō]�ˎ���ɓn���������t�����Ŏ����͂Q�`�T���[�g���قǂɂȂ�܂��B �Ԋ��͂U�`�X���ŁA�}��ɑN�₩�Ȏ�ԐF�̂T�`�U�Z���`�̉Ԃ��炩���܂��B ��r�I�ϊ���������A�g�n�ł͒�Ƃ��ĐA�����Ă���悤�ł��B |
 |
�}���o���R�E Convolvulaceae Ouamoclit coccinea �q���K�I�ȃ��R�E�\�E�� �M�уA�����J���Y�̃c�����P�N���ŁA��ɒ����n���Ȑ��ɖ쐶�����Ă��܂��B �W�`�P�O���ɁA�Ԍa�P�T�`�Q�O�~���̂T�p�`�Ɍ������ԐF�Œ��S�������F���Ԃ��炩���܂��B |
 |
�}���e�} Caryophyllaceae Silene gallica.var.quinquevulnera �i�f�V�R�ȃ}���e�}�� ���[���b�p���Y�̂P�`�Q�N���ŁA�]�ˎ��㖖���ɓn�����܂����B���݂ł͖쐶�����Ė{�B�A�l���A��B�̊C�݂ȂǂɌQ�����Ă��܂��B ����Q�O�`�R�O�Z���`�ɂȂ�A�Ԋ��T�`�U���Ɍs�̏㕔�ɉԌa�V�~���قǂ̉Ԃ��炩���܂��B�ԕق͔��F�ʼnԕق̒��S���ɍg���F�̔ǂ�����܂��B |
 |
�}�������E Ardisia crenata ���u�R�E�W�ȃ��u�R�E�W�� �֓��n���ȓ�ɕ��z������g�n���̏�Β�ŁA�����͂P���[�g���قǂɂȂ�܂��B �Ԋ��͂V�`�W���ɉԌa�W�~���قǂ̔��F�̉Ԃ��P�O���܂Ƃ܂��ĉԖ[������܂��B �ʎ��͂T�`�P�O�~���̊ی`�ł܂Ƃ܂��ĕt���A�P�P�����ɂ͐Ԃ��n���ĂR�����܂Ŏc��܂��B |
 |
�~�Y�L�i�N���}�~�Y�L�j Cornus controversa �~�Y�L�ȃ~�Y�L�� ���{�S���̎R�n�␅�ӂɑ������z���闎�t���ŁB�����P�O�`�Q�O���[�g���ɂȂ�܂��B �Ԋ��͂T�`�U���Ŏ}��ɉԌa�T�~���̏����Ȕ��F�̉Ԃ𑽐����l�[������܂��B �ʎ��͂T�`�P�O�~���̊ی`�ŁA�P�O�`�P�P���ɂ͐ԐF�`�����F�ɏn���܂��B |
 |
�~�Y�q�L Polygonaceae Polygonum filiforme �^�f�ȃ^�f�� ���{�S�y�̗т��M�̂ӂ��Ȃǂɕ��ʂɐ����鍂���T�O�`�W�O�Z���`�̑��N���ł��B �Ԋ��W�`�P�O���Ɍs�̏㕔�ɒ����R�O�Z���`�ׂ̍�����ԏ����o���A�������Ԃ��܂�ɉ������ɂ��܂��B�Ԕ�Ђ͂S�A�㑤�̂R�͐Ԃ����̂P�͔��F�����Ă��܂��B |
 |
�~�]�\�o�i�E�V�m�q�^�C�j Polygonaceae Polygonum thunbergii �^�f�ȃ^�f�� ���{�S�y�̓c�̌l�␅�ӂȂǂ̎������Ƃ���ɌQ�����鍂���R�O�`�P�O�O�Z���`�̂P�N���ł��B�s�ɂ͉������̎h������܂��B �Ԋ��͂V�`�P�O���Ŏ}��ɂP�O���W�܂��č炫�܂��B�ԕق͂T�Œ����S�`�V�~���A�㕔�͍g���F�ʼn����͔��F���Ă��܂��B |
 |
�~�c�}�^�V���c�c�W |
 |
�~���}�L�P�}�� Corydalis var.tenuis �P�V�ȃL�P�}���� �t�E���P�}���̕ώ�ŎR��ɍL�����z���܂��B�������傫����v�ő���Q�T�`�S�T�Z���`�ɂȂ�A�����S�`�P�O�Z���`�̉ԏ��ɉ��F�Ԃ𑽐����܂��B���ʂ͂Q�`�S�Z���`�̐��`�����Ă��܂� �Ԋ��F�S�`�U���@�@���z�F�{�B�ߋE�n���ȓ� |
 |
�~���}�r���N�V�� |
 |
�~���}�z�^���J�Y�� |
 |
���X�J�� Muscari �����ȃ��X�J���� �n���C���݁A���B�A����A�W�A���Y�̋������N���Ŗ�T�O�킪����܂��B ����P�T�`�Q�O�Z���`�قǂɂȂ�A�Ԋ��͂S�`�T���Ŏ��A���F�̉Ԃ��炩���܂��B |
 |
�����T�L�T�M�S�P Scrophulariaceae Mazus miquelii �S�}�m�n�O�T�ȃT�M�S�P�� �{�B�A�l���A��B�̓c�̌l�Ȃǂ̂������������Ƃ���Ɍ����鑽�N���ł��B �S�`�T���ɍ����̗t�̊Ԃ��獂���P�O�`�P�T�Z���`�̉Ԍs��L���A�W���F�`�g���F�̂T�`�P�O�~���̐O�ىԂ��܂�ɍ炩���܂��B ���Ԏ���T�M�S�P�ƌ����܂��B |
 |
�����T�L�V�L�u�i�~�����T�L�A�R���S���j Callicarpa japonica �N�}�c�d���ȃ����T�L�V�L�u�� ���{�A���N�����A�����̌��Y�œ��{�S���̎R��ɕ��z���闎�t��ō����Q�`�R���[�g���ɂȂ�܂��B �Ԋ��͂U�`�W���ŗt�̘e�ɂR�`�S�~���̒W�g���F�̉Ԃ𐔌܂��܂��č炩���܂��B �ʎ��͂T�~����̊ی`�ŏn���ƐԎ��F�ɂȂ�܂��B |
 |
�����T�L�c���N�T Tradescantis reflexa �c���N�T�ȃ����T�L�c���N�T�� �k�A�����J���Y�Ŗ��������ɓn�������h�����ł��B ����R�O�`�T�O�Z���`�ɂȂ�A�U�`�W���ɉԌa�Q�O�`�Q�T�~���̎��A�Ԏ��A���F�̉Ԃ��炩���܂��B |
 |
�����T�L�n�i�i�i�I�I�A���Z�C�g�E�A�V���J�b�T�C�A�n�i�_�C�R���j Orychophragmus violaceus �A�u���i�ȃI�I�A���Z�C�g�E�� �������Y�̂P�N���ŁA�ʖ��̃V���J�b�T�C�A�n�i�_�C�R���͕ʐA���ɂ��g���Ă��܂��B ����R�O�`�S�O�Z���`�ɂȂ�A�Ԋ��͂R�`�S���łQ�O�`�Q�T�~���̎��A���F�̉Ԃ��炩���܂��B |
 |
�����`�R�[�� |
 |
���L�V�R�n�i���i�M |
 |
���h�[�Z�[�W |
 |
���N�����i�V���N�����A���N�����Q�j Magnolia liliflora ���N�����ȃ��N������ �������Y�̗��t��`�����ō����S���U���[�g���ɂȂ�A�}���������番���ꊔ������ɂȂ�܂��B �Ԋ��͂R�`�S���ŗt�Ɠ����ɂ��܂��B�Ԍa��P�O�Z���`�ŁA�g���F�ŊO���͔Z�������͒W������ł��B |
 |
���~�W�A�I�C Hibiscus coccineus �A�I�C�ȃn�C�r�X�J�X�� �k�ẴW���[�W�A�B�A�t�����_�B���Y�Ŗ��������ɓn�������h�����ł��B �����͂Q�`�R���[�g���ɂȂ�A�W�`�X���ɂP�Q�`�Q�O�Z���`�̍g�F�̍炩���܂��B |
 |
���� |
 |
�����C���^���|�| |
 |
�����C���q���U�L�c�L�~�\�E�i�G�m�e���j Onagraceae Oenothera speciosa var.childsii �A�J�o�i�ȃ}�c���C�O�T�� �k�A�����J�A��A�����J���Y�œ��{�ɂ͏��a�����ɓn���������N���ł��B ���݂ł͒����Ȑ��ɖ쐶�����Ă��āA����͂R�O�`�T�O�Z���`�قǂɂȂ�A�Ԋ��͂U�`�V���ŁA�Ԍa�T�`�V�Z���`�̒W�g�F�̉Ԃ𒋂ɍ炩���܂��B �Q�̎��͉��������Ă��܂����Ԃ��J���Ə�����ɂȂ�܂��B |