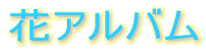 |
気の向くままに撮した花の写真を 50音順に並べてみました 振り返れば随分と撮した物です |
| 2007/08/11 Up |
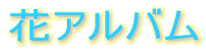 |
気の向くままに撮した花の写真を 50音順に並べてみました 振り返れば随分と撮した物です |
| 2007/08/11 Up |
 |
ガーベラ Gerbera hibrida キク科センボンヤリ属 南アフリカ原産で大正初期に渡来したそうです。草丈30〜50センチ、花径5〜15センチ、温室栽培で1年中出回っています。花色が豊富で赤、黄、桃、白、橙があり一重咲き、二重咲き、八重咲き、丁字咲きなどがあります。 |
 |
カイドウ(ハナカイドウ、ナンキンカイドウ) Malus halliana バラ科リンゴ属 中国原産の落葉小高木で5〜8メートルになります。花期は4月頃で鮮やかな淡紅色の花は3〜4センチ有り、枝先に4〜6花が垂れ下がるように付きます。 |
 |
ガガイモ Asclepiadaceae Metaplexis japonica ガガイモ科ガガイモ属 日当たりの良いやや乾いた原野に生える蔓性の多年草です。長卵形の葉は先が尖り基部は心形をして対生します。 8月に葉腋から花序を出し花経1センチ、淡紫色の花を数個付けます。 |
 |
ガガブタ Gentianaceae Nymphoides indica リンドウ科アサザ属 池や沼に生える多年生の水草です。花期は7〜9月で中心部が黄色の白い花を水面に咲かせます。花径は15〜20ミリで5つの花弁には白く長い毛が生えています。 |
 |
カキツバタ(カオヨバナ) Iris laevigata アヤメ科アヤメ属 日本原産、高さ70〜90センチあり水辺に育ちます。花期は5〜6月で花径6センチほどの紫色の花を付けます。園芸品種もあります。 |
 |
カクトラノオ(ハナトラノオ) Physostegia virginiana シソ科ハナトラノオ属 大正時代に渡来しました。草丈80〜100センチ、10〜30センチの花穂に淡紅紫の花が8〜9月頃に咲く花期の長いはなです。茎が角張っているところからカクトラノオの名があるようです。 |
 |
ガザニア(クンショウギク) Gazania gaertn キク科ガザニア属 南アフリカ原産で大正末期に渡来し広く栽培されるようになったそうです。草丈20〜40センチ、6〜8月頃に6〜8センチの花をつけます。園芸改良されて品種も多く花色は白、黄、褐色、桃色などがあります。 |
 |
カネノナルキ(シンカゲツ) Crassula portulacea f. ベンケイソウ科クラッスラ属 葉は鮮緑色の楕円へら形で、樹高30センチほどになります。晩秋から冬に桃白色、花径8ミリほどの花を咲かせます。通常戸外栽培をし冬は室内に取り込みます。 枝または葉を差して増やせます。 |
 |
カノコユリ Lilium speciosum ユリ科ユリ属 四国、九州、台湾、中国が原産で、花びらの奥にかのこ絞りのような乳頭状突起があるところからこの名があるそうです。草丈100〜150センチ、花径10センチほどの花を7〜8月頃つけます。自生には花形、花色に変異が多いそうです。 |
 |
ガマズミ スイカズラ科ガマズミ属 関東以南に分布する落葉低木で高さ2〜3メートルの株立ちです。5〜6月頃に白く小さい花を枝先にまとまって多数つけます。秋にみのる果実は小さく丸形で、熟すと赤くなります。 |
 |
カライトソウ |
 |
カラスウリ(タマズサ) Cucurbitaceae Trichosanthes cucumeroides ウリ科カラスウリ属 薮などに生える蔓性の多年草です。8〜9月頃、日が暮れてからレースのように細かく裂けた白い花を開きますが夜明け前には萎んでしまいます。果実は5〜7センチで楕円球形をして、熟すと赤くなります。本州、四国、九州に分布しています。 |
 |
カラスノエンドウ(ヤハズエンドウ) Leguminosae Vicia angustifolia var.segetalis マメ科ソラマメ属 豆果が黒く熟すところからカラスにたとえたそうです。 道端や畑、野原などの日当たりの良い所に生える2年草です。葉は8〜16個の小葉が連なり、3〜6月頃に葉腋に1〜3個の紅紫色をした花をつけます。豆果の長さは3〜5センチほどです。本州から南の沖縄まで分布しています。 |
 |
カラマツソウ Ranunculaceae thalictrum aquilegifolium var.intermedium キンポウゲ科カラマツソウ属 北海道、本州、四国、九州に分布し、山地から亜高山の草原に生える多年草です。高さ70〜120センチになります。 7〜9月頃に、茎の先に散房状の花序を出し、径1センチの白色〜淡紅色の花を多数つけます。花弁はありません。 |
 |
カランコエ Kalanchoe ベンケイソウ科カランコエ属 マダガスカル原産の多肉植物で沢山の品種があります。花の時期は冬が多いのですが、1年中見られるようになりました。 花色も多様で桃、赤、黄、橙などがあります。 |
 |
カリアンドラ |
 |
カルミナ(アメリカシャクナゲ、ハナガサシャクナゲ) Kalmia latifolia ツツジ科カルミア属 北アメリカ原産で大正時代に導入されました。原産地では高さ10メートルほどになり、5月に径15ミリの白または赤いコンペイトウ状の花を咲かせます。 |
 |
カンナ(ハナカンナ) Canna generalis カンナ科カンナ属 熱帯、亜熱帯地方原産の球根多年草です。50種ほどが野生しているそうです。 鷹は1メートルほどになり、8月頃に10センチ前後の赤、黄、桃色の花を茎頂に付けます。園芸改良されて品種の多い花です。 |
 |
カンパニュラ(フウリンソウ) Campanula medium キキョウ科ホタルブクロ属 南ヨーロッパ原産で明治初期に渡来しました。高さは1メートル前後になりますが、矮性の物は40〜50センチほどです。6〜7月に花径3〜4センチの花を咲かせます。花色は紫、桃、白などがあります。 多くの種類があります。 |
 |
カンパニュラバツラ |
 |
キイチゴ(モミジイチゴ) Rubus palmatus バラ科キイチゴ属 本州中部地方以北に分布しています。東日本の山野に自生する高さ2メートル位の低木で、葉はモミジも葉ににています。 4月頃に白い3センチほどの花を咲かせ、果実は6月頃に黄色く熟して食用になります。 |
 |
キカラスウリ Cucurbitaceae Trichosanthes kiritowil var.japonica ウリ科カラスウリ属 薮などに生える蔓性の多年草です。7〜9月頃に咲く花はカラスウリに似ていますが花冠の裂片の先が広いようです。果実は10センチほどの長楕円球形をして熟すと黄色くなります。日本全土に分布して根や種子は薬用にされます。あせもなどに使われる天花粉は根の澱粉から作られるそうです。 |
 |
ギガンテア |
 |
キキョウ Platycodon grandiflorum キキョウ科キキョウ属 シベリア、中国、朝鮮半島、日本の原産です。 高さは80〜120センチほどになり、9〜10月頃に4〜5センチの青紫の花を咲かせます。園芸品種には白、ピンク、2重咲きなどがあります。 |
 |
キキョウソウ Campanulaceae Specularia Perfoliata キキョウ科キキョウソウ属 北アメリカ原産の一年草で各地に帰化しているようです。 日当たりの良い乾いたところ生え30〜80センチ程になります。茎の下部から咲き上がり最初は閉鎖花で上部に紫色をした15ミリほどの花をつけます。 |
 |
キク Chrysanthemum morifolium キク科キク属 中国が原産地です。古くから愛好家によって品種改良されてきました。 大輪、中輪、小輪、一重、八重、丁字咲きなど種類は多く、鉢や花壇に植えられています。 |
 |
キチジョウソウ Liliaceae Reineckea carnea ユリ科キチジョウソウ属 吉事があると開化すると言う伝説から付けられたそうです。 暖地の林内に生える常緑の多年草で、葉は根生し、長さ10〜30センチ、幅1〜2センチほどの線形をしています。8〜10月頃に8〜12センチの花茎を立ち上げ淡紅紫色の花を穂状につけます。本州、四国、九州に分布しています。 |
 |
キツリフネ Balsaminaseae Impafiens noli tangere ツリフネソウ科ツリフネソウ属 山地の渓流沿いや湿った林内に生える1年草です。草丈40〜80センチです。淡黄色で長さ3〜4センチの花を細い花柄でつり下げます 花期:6〜9月 分布:北海道、本州、四国、九州 |
 |
キッコウハグマ Compositae Ainsliaea apiculata キク科モミジハグマ属 山地のやや乾いた木陰に生える小さな多年草です。 花茎は高さ10〜30センチになりますが、葉は茎の下部に5〜10個集まってつき長い柄の先に1〜3センチの心形をしています。 頭花は3個の小花からなり花冠は白色ですが、閉鎖花を結ぶことが多いようです。 |
 |
キバナアキギリ(黄花秋桐) Salvia nipponica シソ科アキギリ属 山地の木陰に生える多年草です。草丈20〜40センチになり、葉は5〜10センチの三角状鉾形をします。8〜10月ごろ茎先に25〜35ミリほどの黄色い唇形花を多数付けます |
 |
ギボウシ(ギボシ、ギボウシュ、シガク) Hosta tratt ユリ科ギボウシ属 東アジアの亜熱帯から温帯に分布しています。日本では全国各地に自生して種類が多く、古くから庭の植え込みに使われてきました。 高さも種類によって30〜100センチまであり、花径も5〜6センチ、花色は淡紫、白があります。 |
 |
キミノバンジロウ |
 |
キュウリグサ(タビラコ) Boraginaceae Trigonotis peduncularis ムラサキ科キュウリグサ属 葉を揉むとキュウリの匂いがするところからつけられたようです。道端や庭に見られる高さ10〜30センチの2年草です。3〜5月に花径2ミリほどの淡青紫色の花を咲かせます。日本全土に分布しています。 |
 |
キョウチクトウ Nerium indicum キョウチクトウ科キョウチクトウ属 インド原産で日本には江戸中期に渡来しました。樹高は3〜4メートルになり、庭木、街路樹として用いられています。6〜9月頃に4〜5センチの淡紅、白、紅色の花を咲かせます。 |
 |
キランソウ(ジゴクノカマノフタ) Labiatae Ajuga decumbens シソ科キランソウ属 道端や庭、山麓などに生える多年草です。地をはって広がり葉は長さ4〜6センチ、幅1〜2センチで粗い鋸歯があり紫色を帯びることもあります。3〜5月頃に葉腋に1センチほどの濃紫色の唇形花を数個つけます。本州、四国、九州に分布しています。 |
 |
キリ Paulownia tomentosa ノウゼンカズラ科キリ属 本州、九州に分布する柔らかく軽い材として、家具や下駄、器具、彫刻材、建築などに使われてきました。古くから植栽されています。 樹高は8〜15メートルになり、5月に5〜8センチの青紫の花を付けます。 |
 |
キリシマリンドウ |
 |
キンカン |
 |
ギンコウボク(ギンバイカ、イワイノキ) フトモモ科ギンバイカ属 地中海地域原産の常緑低木で、高さは1〜2メートルです。葉はユーカリに似た強い香りがします。 5月頃に白い径20ミリほどの花を咲かせます。白梅に似ることから銀梅花の文字を当てて和名にしたそうです。 イワイノキの由来は、祝い事や宴席で、この葉を酒に浸して香りを付けたことによると言われます。 |
 |
キンモクセイ Osmanthus aurantiacus モクセイ科モクセイ属 中国原産で江戸時代に渡来した芳香のある花木です。 樹高3〜4メートルで、10月頃に5ミリほどの黄色い花を枝幹に密に付けて、強い香りを漂わせます。 |
 |
キンレンカ(スイレンボク) シナノキ科グルーイア属 南アフリカ原産の高さ1〜3メートルになる常緑ツル性の低木です。 花径は3〜4センチで花弁が5枚、発達した萼片が5枚で、10弁の花の用に見えます。花色は桃から紫色をしています。 |
 |
クサギ Clerodendron trichotomum クマツヅラ科クサギ属 日本、朝鮮半島、中国が原産地で、日本では全国に分布する落葉低木です。 山野の林縁や川岸の日当たりの良いところに生えます。葉に悪臭があるところから付けられた名前です。8〜9月ごろ枝先に25ミリほどの白い花を数花まとめて咲かせます。秋になる実は花後の萼に包まれて、羽根突きの羽のようにみえます。 |
 |
クサノオウ Chelidonium majus ケシ科クサノオウ属 日当たりのよい道ばたや草地、林縁などに生える草丈30〜80センチの2年草です。 全体に縮れた毛が多く白っぽく見え、4〜7月に鮮黄色の2センチほどの花をつけます。 |
 |
クサハナビ |
 |
クジャクソウ(クジャクアスター) Aster hybridus キク科アスター属 北アメリカ原産です。高さは80〜100センチほどになり、8〜10月頃に15〜30ミリの花を沢山咲かせます。 花色は淡紫、白があります。 |
 |
クズ Leguminosae Pueraria lobata マメ科クズ属 根からとった澱粉が葛粉、根を乾燥した物を風邪薬の葛根湯にもちいます。山野に普通に見られる多年草です。 7〜9月頃に紅紫色の半を総状に多数つけます。 日本全土で見られます。 |
 |
クチナシ(センプク) Gardenia jasminoides アカネ科クチナシ属 日本、中国、台湾、インドシナ原産の低木です。花に芳香があるので庭木として用いられています。 樹高は150〜300センチほど、6〜7月に6〜8センチの白い花を咲かせます。八重咲きの物は大型の花を咲かせます。 |
 |
クフェア(ベニチョウジ) Cuphea ignea ミソハギ科クフェア属 メキシコ、ジャマイカ原産で目宇治中期に渡来しました。この属には250種ほどがあります。 高さは30センチほどで8〜10月頃に長さ2センチの紅色の花を咲かせます。 |
 |
クモマグサ |
 |
クリサンセマム Chrysanthemum spp. キク科キク属 地中海沿岸が原産地です。クリサンセマムとはキク属を総称する言葉です。 草丈は20センチほどで、4〜5月頃に2センチ位の白、黄色の花を咲かせます。品種は幾つかあるようです。 |
 |
クリスマスローズ(ヘレボラス) Helleborus キンポウゲ科ヘレボラス属 地中海沿岸原産の常緑多年草です。クリスマスの頃に咲くのでこの名が付いたそうです。 草丈は15〜30センチほどになり、1〜2月に白、ピンクの5〜6センチほどの花を咲かせます。 園芸改良されて多くの品種があります。 |
 |
クレマチス(テッセン、キアザグルマ) Clematis hybrida キンポウゲ科クレマチス属 中国、日本、南欧〜南西アジア原産のつる性多年草で、園芸上のクレマチスは明治末頃から輸入されるようになりました。園芸改良が進み様々な品種があります。 5月頃に5〜10センチほどの花を咲かせます。花色は白、紫、青、紅、桃色などがあります。 |
 |
クローバー(シロツメクサ) Leguminosae Trifolium repens マメ科シャジクソウ属 ヨーロッパ原産の多年草で牧草として世界中に広がりました。茎は地を這って長く伸び、5〜8月頃に長さ1センチほどの白い花を球状に咲かせます。 |
 |
クロガネモチ Ilex rotunda モチノキ科モチノキ属 本州の関東以西、四国、九州、沖縄の暖地に生える樹高20メートルにもなる常緑高木です。 5〜6月に4ミリほどの淡紫白色の花を葉の付け根に密に付け、11月頃には実が赤く熟します。 |
 |
クロッカス Crocus vernus アヤメ科サフラン属 地中海沿岸の原産で、ヨーロッパでは昔から春をつげる花として人気があり「幸福の使者」とも呼ばれているようです。 細長い葉と3〜4月に咲くふわっとふくらんだ花は3〜5センチほどです。 花は日中だけ開き夕方には閉じてしまいます。 花期は3〜4月で自然分球で増えます。 |
 |
ゲッカビジン Epiphyllum oxypetalum サボテン科エビフィルム属 メキシコ、中央アメリカ原産で昭和初期に渡来した多肉多年草です。高さは2メートルいじょうにもなり、6〜9月に白い15センチほどの花を咲かせます。 花は夜に咲き翌朝には萎んでしまいます。強い香りがあります。 |
 |
ケトラステリア |
 |
ゲラニウム・モナセンス |
 |
ゲンノショウコ(ミコシグサ) Geraniaceae Geranium thunbargii フウロウソウ科フウロソウ属 下痢止めの民間薬として有名で、飲むとすぐに薬効があると言うところからつけられた。山野に普通に見られる高さ30〜60センチの多年草です。7〜10月頃に紅紫色、淡紅色、白色の花径10〜15ミリの花を咲かせます。実は熟すと5裂して裂片が御輿の屋根のように巻上がります。日本全土に分布しています。 |
 |
コウゾ(ヒメコウゾ) Broussonetia kazinoki クワ科コウゾ属 和紙製造のための品種が全国で栽培されているので、日本全土に分布しています。 樹高は2〜5メートルほど、4〜5月に10〜15ミリの雌花は赤、雄花は白の花を咲かせ、花後に10ミリほどの果実を付けます。 |
 |
コウホネ Nymphaeaceae Nuphar japonicum スイレン科コウホネ属 浅い池や沼、小川に生える多年生の水草で、観賞用に栽培もされています。 花は長い花柄の先に1つだけ咲き、黄色い椀状をして花径4〜5センチほど、花弁状にみえるのは萼で、花弁は外側に反って輪状に並んでいます。 |
 |
ゴエテア |
 |
コエビソウ(ベロペロネ) Beloperone guttata キツネノマゴ科コエビソウ属 メキシコ原産の常緑多年草です。鑑賞温室などで見られ、花の形がエビのように見えるので、この名があります。 高さ50〜100センチで、3〜5月に長さ3〜4センチの花を付けます。 |
 |
コスモス Cosmos bipinnatus キク科コスモス属 メキシコ原産の1年草です。明治初期に渡来しました。 高さ2〜3メートルになり、8〜11月に4〜5センチの花を咲かせます。花色にはピンク、赤、白、黄色などがあります。 |
 |
コセンダングサ Compositae Bidens pilosa キク科センダングサ属 世界の熱帯から温帯に分布する50〜100センチの1年草です。茎上部の枝先に黄色い頭花を9〜11月頃に咲かせます。 |
 |
コデマリ(テマリバナ) Spiraea cantoniensis バラ科シモツケ属 中国原産の常緑低木です。庭や公園、植物園に古くから観賞用に植えられています。 4〜5月に10ミリほどの白い花を枝先に多数まとまって付けます。 |
 |
コバンソウ(タワラムギ) Briza maxima イネ科コバンソウ属 地中海沿岸地方原産で日本には掲示初期に渡来し、各地に野生化している帰化植物です。 高さ30〜60センチで、5〜6月に花を付けます。ドライフラワーとして利用されるようです。 |
 |
コブシ(ヤマアララギ、コブシハジカミ) Magnolia kobus モクレン科モクレン属 日本と済州島に自生する落葉高木で10〜18メートルほどになります。 花は葉よりも早く、3月に花径10センチほどで枝全体を覆うように咲きます。 花色は白ですが淡紅色をしたベニコブシ、花弁が細いシデコブシなどもあります。 |
 |
コマツナギ Indigofera pseudotinctoria マメ科コマツナギ属 本州以南の野原に分布する落葉低木で高さは50〜100センチほどになります。 花期は7〜8月で、淡紫の5ミリほどの花が数十花集合して花房を作ります。 茎が丈夫なので馬を繋ぐことが出来るろ言う意味でこの和名が付いたようです。 |
 |
コメツブツメクサ Trifolium dubium マメ科シャジクソウ属 日本全土に分布しています。明治後期に渡来した帰化植物で、道端や荒れ地で見ることが出来ます。 5〜9月に3〜4ミリの黄色い花を咲かせます。 |
 |
コリセウムアイビー |