DDRメモリとDDR2メモリの違い
ここでは、DDRとDDR2の違いに関してお話します。
双方の大きな違いは、ハード面とソフト面の両方に見られます。
ここではどのような所が違い、その為にどのような差が出るのかをお話します
見た目の違い
ピン数の増加と今後の高速化に対応する為に、配線距離を短く設計できる形状に変更してあります。
メモリモジュールの外形には余り大きな差はありません。
正確に寸法を測定すると2mmほど高さが違う程度です。
しかし、ソケットへ差し込むコネクタ端子の凹みの位置やメモリチップの形状が違います。
まず、メモリチップの形状を簡略化した物を見てみましょう。
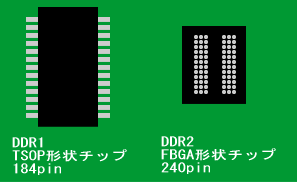
上図ではスペースやサイズの問題からピン数を省略していますので、御注意ください。
DDR1のピンがパッケージから左右に出ているのに対して、DDR2では中央付近に配列されています。
このピンの位置が意味する事は、中にあるダイから外へ出ているピンへの距離が、DDR2はDDR1より短くて済むと言う事です。
またピン数が増加すると必然的に距離が伸びてしまうので、それに対応する為と言うのも、理由の一つでしょう。
メモリからのデータ通信は、どのピンからも同じ距離もしくは規定の距離で繋がっていなければ、タイミングがずれて動かなかったりデータにエラーが起こってしまいます。
その為、メモリの配線距離は極力短い方が良いとされます。
DDR2は高速化を更に推し進める為に、配線の距離を極力短くしたわけです。
中身の違い
DDR2はDDR1の半分のDDR動作周波数で同じデータ量を送信でき、安定して高速に動作させる為の機能を備えています。
DDR-400とDDR2-400のデータ転送量やメモリクロック数は同じです。
しかし、DDR2はDDR1の半分のクロック数で動作しています。
例えば、DDR-400が400MB/sでデータ送信する場合、2bitのデータを200MHz毎に送信します。
これに対してDDR2-400は、一挙に4bitのデータを送信できる為、100MHzで4bit送信すれば、400MB/sになってしまいます。
このままでは分りにくいので、データ送信を下図に示します。
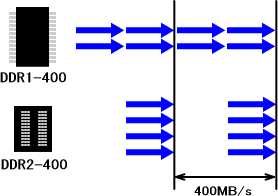
400MB/sでのデータ転送を実現させる為には、DDR2はDDR1の半分の仕事量で良い事になります。
これにより何が良いのかと言うと、メモリにかかる負担が少なくて済むので、電力の消費と発熱を抑えることが出来ます。
また、実際に使用する上では無関係ですが、今後の更なる高速化にも耐えうる設計になっています 。
次に安定して高速に動作させる機能を説明します。
ODT(On Die Termination)
DRAM内部に終端抵抗を設置する事で信号が反射してしまうのを防ぎ、誤動作の低減や通信の高速化が図れます。
DDR-400を販売し始めた時に出た諸問題は、この終端に問題があったと聞いたことがあります。
OCD(Off-Chip Driver)
出力信号のタイミングのズレを減少させます。
出力ドライバの抵抗値を調整する事で、出力信号の立上がりと立下りの抵抗が等しくなるように電圧を調整します。
Posted CAS & AL(Additive Latency)
Posted CAS機能によるコマンドの先読みをして、処理の効率化を図ります。
ALはこの機能のパラメータです。
発行されたコマンドがその前のコマンドに被ってしまった場合、前のコマンドが優先され発行されたコマンドは後回しにされます。
その分処理が遅れてしまうわけですが、それを防ぐのがこの機能です。
大まかにではありますが、以上がDDRとDDR2の違いです。
