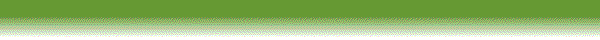
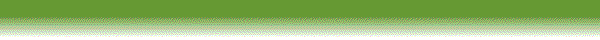
平成20年12月 ☆一般質問 平成20年9月 ☆一般質問 ☆決算質問 平成20年6月 ☆一般質問 平成20年3月 ☆一般質問 ☆事項別質問 |
| 平成20年12月度一般質問 |
木野山 牧野町長におかれましては、この度の、無投票当選、誠におめでとう御座います。心よりお慶び申し上げます。 無投票ということで「責任」の重さを感じている。 一期目は乱雑だったが、二期目は、品格のある町長、責任ある町長、成果を出す町政、との自覚をもって取り組みたい。との事ですが以下4点についてお伺いいたします。 ①新年度構想について また、地方紙に、農業と観光を関連付けたいとの記事も見受けましたが、具体的な構想をお伺いします。 観光についての町長答弁(9月度一般質問)では、 「観光事業は、景気の波に左右される。日本の観光立国が言われるが、観光資源と担当者のやる気がカギ。収益が上がらねば事業効果は見込めない。観光事業は予想がつきにくい。 景気、社会背景を見極めなければ事業の成果は見込めない。リスクの大きい事業と思う。」 といわれましたが。 町長 「抱負」については、述べたとおりだが、 ①財政健全化に努める。 木野山 50%という具体的な数字が出ましたので以下お伺いします。 項目4のケーブルテレビについての質問9にて「3取り組む必要は無い、4わからない。」がともに⇒質問12へと質問が飛び「地域情報化サービスを利用しない理由は何か」と問われている。4わからない。は×なのか。 |
| 平成20年9月度一般質問 |
|
木野山 住民の意見を参考にするのが前提だ。統合については賛成でも時期が早いのでは、ということではないか。学校と地域が一緒になって体験学習や地域の歴史を学びそういうことをつうじて子供を育て教育について頑張っている地域は、もう少し地域で頑張りたいと思われているのではないか。どう思うか。 教育長 統合はやむを得ないのであれば、学校教育の方針、通学の関係、道路の安全性、など示せとの意見もある。高小は生徒数の減少が激しい。どう捉えるかだが教育効果の面で出来るだけ早いほうが良いのではと言うのが教育委員会の方針です。保護者の理解を頂き、安心できる方向性を出して行きたい。 2)ブロードバンド環境について 3)農業対策について |
| 平成20年9月度決算質問 |
|
③企画課「自然公園管理運営経費」
⑤教育委員会「歴史民俗資料館管理運営経費」
|
| 平成20年6月度一般質問 |
(1)町の将来の発展に繋がる事業について 新年度の予算は、財政改革と町の将来の発展に繋がるものの2本建てで行きたい。 厳しい財政状況の中で、緊縮予算と言われながらも、過去の負の清算をしながら町の将来に繋がる事業の新たな展開・拡大を行う。との事でしたが、以下について、町長のお考えをお伺いいたします。 ①CATV事業について 昨日からの先ほどまでの同僚議員の質問によりすべてが言いつくされた感じがいたしますし、交通・運輸網、上下水道整備、電気、環境整備など町のインフラ整備については、CATV事業は町の下水道施設と同じように社会資本整備と考えている。政策としては利用効果があると考えていると答弁されています。 特に情報網メディアの面では、先の答弁においても4点のメリットを挙げられ、課題の解決に有効な手段とも言われましたが、もうひとつ踏み込みまして、CATV事業は、町の将来の発展に繋がる重要な事業のうちの一つと思うがどうか。町長のお考えをお伺いいたします。また 地デジ対応のための事業開始(GOサイン)のタイムリミットはいつ頃とおもわれるか。あわせてお伺いいたします。 ②県立神石三和病院の移管について 町長は、苦渋の選択と表現されましたが、県から具体的な支援策が提示され、この度、公設民営方式での移管を決断されました。 すなわち、民間の病院に町の病院の運営を委託する訳ですが、町内にある私立病院、診療所との連携はどうするのか。 これは町内の医療・福祉の体制の確保に繋がります。介護施設との連携を含め、町内医療体制の全体像をどう考えておられるのか、お伺いします。 また、その中で高蓋の直営の診療所はどうされるのか。当面、存続すべきと考えますが、どうでしょうか。 ③学校統合について 教育委員会の方針では、三和地区は平成23年度三和小学校新校舎建設に伴い高蓋小・来見小を三和小に対等統合となっており、現在地元説明会を行われていますが、情報がからり錯綜しています。 地元意見の集約はされたのか。結果として、統合の方針は変わりないのか。お伺いいたします。 (2)事務事業の簡素化について 3月議会にて、上山副町長は「モノによっては耳に入るので是正はしているが、まだ不十分な点もあるので、キチンと指導する。問題点を整理する。」と答弁されました。 何度も要望をしていますが、ふれあい補助金など補助金の支払いについて簡素化できないか。 子育てありがとう補助金も手続きが面倒との声もあり、制度がいかにもお上的だ。と思います。 もう少し住民の目線を大事にして、事務を簡素化すべきと思いますがどうか。 以上お伺いいたします。 ①CATV事業について 町長 CATV事業は、情報通信面から利用効果のある特に重要な事業だと思う。今後の神石高原町を担う子ども孫の世代まで有効に活用できる町の財産となる整備だと思う。 しかしながら町の財政状況を考慮すると、この事業を推進すれば大きな影響を及ぼすことになる。まだ私の腹は決まっていない。タイムリミットがあるようだが、もう少し時間を頂きたい。地デジの関係で、アナログの終了時には、国の新しい施策が講じられておりこれはこれで出来ると思う。 CATV事業は、国の農水省、総務省からの補助が有り、アナログの終了があるので早急な決断が必要と思っている。議会の特別委員会の動向を見ながら十分な検討をしたい。 夕張では炭鉱から観光へと国が力を入れたが、後は面倒を見なかった。CATVも同じようではダメだと思う。 木野山 町長はこの事業は「格差の解消に有効な手法である」、「下水と同じように社会資本整備と考えており政策としては利用効果はあると考えている」諸々の施設と同じレベルと考えておられる。あとは財政問題とのことだが、重要な「決断」とは前向きか、後ろ向きか判断しかねます。町長が言われるように「後世に残る財産となる」にひとつのキーワードがある。 合併以来4年が経ったが統一できるところは統一しようとの姿勢である。「町内の統一は、情報の統一から」と思う。情報の格差は田舎と都会だけではない。田舎どうし・町内各地区どうしにも情報の格差が生じている。そういう意味からも、CATV整備は道路などのインフラ整備よりも重要になって来ている。このことを前提に、財政問題を考えないとこの事業は前に進まない。平行線で考えては前に進まないと思うが、どう思われるか。 町長 CATVに賭ける意欲を感じる。この問題は加入者にある。加入者率イクオール住民のニーズである。財政と比べたらこの事業は前に進まない。財政は後からついて来る。政策は後からでなく前に進まなくてはならない。就任いらい言っている3つの考え方。「選択と集中」「創造と改革」「信頼と合意」のうち、この事業は「選択と集中」が問題となる。この点を注意してすすめたい。特別委員会の動向も見極めながら行きたい。 木野山 議会特別委員会も設立されたので、あとはこの事業は「将来に繋がる重要な事業であるというより必要な事業の認識」の下に進める必要があると思う。加入率という点から言えば、CATV事業は、高齢者のためにこそ必要とおもう。まず「安否確認」から、それから遠隔医療サービスへと拡充が出来る大きな事業と考えられる。その点をおさえて加入率を上げる努力をして行きたい。 副町長 総務省、国交賞の事業は眉唾ものが多い。光を導入して困っている市町もある。良いところばかりでは無いので、その点にも注目しながらすすめる必要がある。 企画課長 CATV事業を取組んでいる3つの地域を現状調査した。導入は大変である。ランニングコストの面では、直営だけでなく、公設民営の方式も有るので検討をしている。 木野山 町の将来の発展に繋がるに重要な事業であるとの認識の下、前向きに進めて欲しい。 ②県立神石三和病院の移管について 町長 町では平成19年3月に長期総合計画を策定した。この中で「保健・医療・福祉が充実した、安心して暮らせるまちづくり」を推進する。この中の医療の充実したまちづくりの中で①救急医療の充実と緊急医療機関との連携、緊急医療体制の整備、②医療サービスの充実を図るため地域医療機関との連携した取組みの推進、③高齢者の在宅福祉を支援するため地域医療機関と連携して、訪問診療、訪問介護などのサービスの提供体制の推進、に取組む。病院機能あり方委員会の最終報告の意見に基づき、保健・医療・福祉の拠点とし充実したまちづくりを推進し、町内の医療機関・介護施設・町(行政)の三者が連携しそれぞれの機能を分担し医療の情報を共有した町民一人一人に合った一体的な医療サービスの提供を推進する。 高蓋の直営の診療所は、僻地診療所である。特別行政措置交付金によって賄われており財政面では財源の圧迫に繋がっていないので、町立病院の医師の確保を含め、地元の意向を考慮しながら協議を進めていく必要があります。当面は現状確保を視野に入れていきたい。 木野山 指定管理の公募において、郡内の福祉の拠点作りが大きな課題である。ひとつの病院をどうするかという話ではない。病院の経営だけを考えると民間の事業者にとっては、魅力のある病院であり医師、看護師の確保をどうするかにかかっている。資本を持たない若い医師にとってもグループを組めば新病院の経営に夢が繋がる。病院を単体で考えるのではなく、地域の医療の確保をどうするか、町の福祉・医療の体制をどうするか。病院と診療所との連携をどうするかが問題である。 「病院のあるへさ将来像に関する意見書」には、病院機能の目標とのなかに(カ)病診連携(病院と地元開業医との連携による患者への適切な診療及び支援)(地域医療の確保)、(キ) 医療機関・介護施設・町(行政)の連携(三者が連携のもと,医療・介護・福祉・健康の一体的なサービスの提供が行われるシステム)とありますが、具体的にどういうイメージで捉えればいいのか。説明を求める。 副町長 例えば豊松、油木、神石の患者さんが県病院に意外と紹介されていない、連携が出来てない。新病院には入院施設があるのでそれを解消する。町は新病院を公共施設として運営する。民は経営を合理的に行う。新病院と診療所の先生とが連絡を取り合って患者さんの診療を行う。町立病院は入院が出来るので診療所との連携を深める。委員会を作るのはは民が勝手に経営を行うのではなく町民の病院であることと、不採算部分の医療を担うことを議論していくシステムを作る。今のシステムをつくり変えていく。 木野山 病院同士がお互いに独立をするのではなく、患者さんの情報を共有しながら医療を担っていく。住民の病状・状態を把握し病院・診療所・介護施設が連携体制をとりあう医療システムを構築することはどうか。これには中心となる情報センターのような施設も必要と成るがどうか。 副町長 おっしゃる通りでイメージは全く一緒だ。 木野山 期間が無いので、公募の段階で条件を示し、優秀な指定管理者を選定し、すばらしい病院が出来ることを期待します。 ③学校統合について 教育長 策定した方針は住民の理解を前提としている。このことを踏まえ、PTA、学校区の保護者、住民の方へ、今日まで13回の説明会を実施してきている。 説明の途中であるが今日までの住民の意見の集約したものを、中間的なものとなるが、報告書を町長、議会に報告する。 住民説明を行っていく中で色々な意見が出され、方針どおり実施することが厳しい状況になってきた。 児童生徒の減少傾向が著しく緊急性を要する自体が発生した。 二幸、高蓋、三和、来見、神石小学校、を優先して対応する。来見小は児童の減少傾向が横ばいで住宅団地推進計画もあるので変更をという住民意見が強い。一方的な推進は出来ないので状況をみて判断する必要が出てきた。 早い時期に一定の方向性が出るように努める。継続して検討協議する。 木野山 どうするのか、はっきりとしたらどうか。 教育長 住民理解が大前提である。その段階で方向転換もあるかもしれない。早急な報告に努める。 木野山 住民説明の段階であるが、情報が錯綜している。正確に誤解を与えないような説明をして欲しい。 (2)事務事業の簡素化について 町長 交付決定した事業は請求があれば40%以内の支払いを行い、事業完了後に実績及び収支決算の分かる資料を提出して頂きそれに基づき金額をお支払いする事になっている。 公費であり事業の内容が確認できない場合は支払いが出来ないのは当然であると認識している。 提出書類の簡素化は今まで以上に進めていますが、あいまいな形での実績報告を認めて支払いをすることは行政としては行ってはいけない行為であり、この点は申請者の方に納得していただけるよう誠意を持って説明していきます。 住民の目線に立った仕事の出来ない職員がいたら責任を持って指導していきます。 子育てありがとう補助金も手続きの簡素化については、本年7月1日から自治振興会長の証明については省略することを決定した。 町民と町職員との信頼関係が無くなったら折角の事業が台無しと成る。
木野山 ふれあい予算の支払いでの前払い40%の基準の理由は。 総務課長 工事など事業の前払い基準に沿っている。 木野山 工事などの事業と、ふれあい予算の事業との前払いに関する整合性がどこにあるのか分からない。事務局も公から民へと代わっている。事務処理が実行委員会で受け持つ方向性が実行に移され、会計処理も当然委員会となれば、40%の前払いでは60%部分の立替が必要となり事業規模が大きいと負担が大きくなり苦労している。どうにか成らないか。事業は民に丸投げか、とも思われる。住民不信に繋がるが、どう思うか。 総務課長 |
| 平成20年一般質問 |
|
木野山 平成20年度「予算大綱」に、合併して4年目を迎え、任期最後となる平成20年度予算です。新町長として就任して3年が経過し「新町の基盤づくり」が初代町長としての使命であると「財政健全化」を最優先に町政を進めて来たと、あります。 3つの過剰の解消に向けてはかなりの成果が上がっていますがそれを上回る国県からの交付税・補助金の減額により効果は相殺され、更なる歳出の抑制と自主財源の確保が必要とのことで、まさに20年度の予算規模は一般会計で繰上げ償還経費を考慮すると5.4%弱の緊縮予算と成っております。 しかしながら、厳しい財政のなかですが、4年目にしてやっと、新町の「夢」を託した新規の事業が本格化するスタートの年度になったなと思っています。 町民は、合併によってどのような町に生まれ変わるのか、多くの合併の効果を期待しましたが思うように行っていないなと言うのが実感であります。 しかし厳しいからこそ、緊迫感とやる気、新たなアイデアが生まれてきたと感じています。 任期最後となる平成20年度予算を、広い視野をもって「泰然自若」の精神で全うしたいとの事ですが、私としましては、あえて初心に帰り「猪突猛進」の精神で「勇気」をもって「住みよい、住んでみたい」神石高原町を目指して頂きたいと思います。 新年度予算の目玉は何ですか。合わせて新年度に臨む長町の決意をお伺いします。 町長 目玉としては、財政改革と町の将来の発展に繋がるものの2本建てで行きたい。 新年度の財政改革では、繰上償還が主である。本年度28~29億の返済を行う。予算全体では28%を占める。 限られた一般財源を、財政再建と町の将来の発展に繋がるような事業の両面に節約をしながら有効に活用する。義務的経費の5,1%の増は繰上償還など公債費の増が要因である。投資的経費の減は1%程度である。またその他の経費も10,5%の減に抑えている。平成17~20年の間に町債いわゆる借金総額は42億7,900万円で、公債費いわゆる総支払額は104億2,600万円であり差引61億4,700万円の返済を行った。3~5年先には実質公債費比率は18%以下になる予定である。 任期もあと8ヶ月なのでオーバーランしてもいけない。「泰然自若」の精神で行きたい。 木野山 夢の大きい部分が見えない。新年度に臨み、将来の展望に繋がる事業について、もう少し具体的に聞きたい。 町長 本町の基幹産業である農林業については、広島牛改良センターの無償移管を受けての「和牛の里再構築プロジェクト」を将来に繋がる大きな事業にしたい。 農業経営について規模を拡大する。法人化へ向けての畜産、米、ブドウ、トマトの振興。林業は広島の森づくりで、など産業の振興をはかる。 昨年から少雨の傾向でボーリングの要望も多く、生活に密着した予算はカットしない。 福祉に関する予算も前年度ベースである。 緊縮予算と言われながらも、過去の負の清算をしながら新たな展開・拡大を行う。 平成20年度予算は、選択と集中で次年度へ繋がる予算である。 木野山 ①予算大綱に、「交付税のマイナス・不本意な権限委譲・「道州制」に向けた事業の地域集中・「県病院問題」などの情勢の変化に対応できる町財政基盤を構築するために、制度・事業内容の根本的な見直し~」とありますが、具体的にはどうされるのか。 また、「スムーズな行政運営が図れるような組織の見直し~」とありますが、具体的にはどうされるのか。新年度で大幅な組織の見直しをされるのか、お伺いします。 町長 制度の見直しは、以前からの制度・要綱・要件を情勢の変化に対応できる時代に合ったものに再度見直して制度の自立を図って行く事が必要と思われる。 例えば、予算大綱でふれているように農産物の一大産地作りを加速させるための助成のあり方では財政事情をふまえ、補助制度を縮小・廃止するものもでてくる。長年の経過で不透明なものもあり、洗い直し最小の経費で最大の効果が現れるようにする。 スムーズな行政運営が図れるような組織の見直しとは、「3つの過剰」の課題を克服。 これは現在、公債費負担適正化計画、集中改革プラン、などで取組んでいる。 スリムで効率的な体制作りを目指す。現状に即した体制作りが求められています。 大幅ではないが、職員数の減少による組織の見直し。町長部局では支所2課4係体制の見直し。教育委員会部局での課の統廃合と公民館体制のあり方の検討を行っている。 新規の事業としては、「教養立町」への取組を行う。 木野山 不本意な権限委譲・「道州制」に向けた事業の地域集中とはどういう認識か。 町長 権限委譲は200件以上来ている。権限委譲は車の両輪のように権限に財源が伴わねばならない。小規模町では財源が対応しない。これが課題だ。 道州制は、おそらく福山圏となるので福山から見て魅力のある町づくりが必要。例えば福山50万都市の安心で安全な食料供給ができる町づくり、そういった農業振興の確立を図りたい。 県病院問題は、結論を出す時期となった。住民の皆さんの理解を得ながら判断をする必要があるが、地域の足を引っ張る病院にしてはダメである。「あり方委員会」から公設民営化が望ましいとの意見書が提出されたが、その相手先について間違いのない選択をしたい。
峠本総務課長 職員は7名減で1名の採用。条例改正しない。若干の見直しとなる。 権限委譲の県の考えは、県に於いてトータルで計算した事業費用を事業別に割振りを行い町に移譲するので、単町では、基礎固定費部分を単独で賄う事となりどうしても高くつく計算となる。 道州制での事業は、大事な事業は都市部に集中させる。あおりを食うのは本町のような周辺弱小市町となる。いろいろ想定し、あるべき制度・事業内容の検討が必要。 木野山 大まかに言えば、財政力を付け本町が力をつけて、あまり左右されない町づくりをすると言うこと。一つ一つの積み上げが必要と思います。 スムーズな行政運用のところで、事業を行ったが清算が遅くて、事務局が個人的に立替える事例など、住民サイドからスムーズでないと思われることが多すぎる。お役所仕事の域をまだ出ていないのではないか。事務事業の中身の見直しが必要ではないか。どう思うか。 上山副町長 モノによっては耳に入るので是正はしているが、まだ不十分な点もあるので、キチンと指導する。問題点を整理する。 木野山 省ける所は省いた事務事業の執行も大事だ。 木野山 ②公民館を中学校区に1ヶ所の設置との事ですが、従来の小学校区に1ヶ所でなぜいけないのか。このことで、これまでの公民館活動が保障できるのか。お伺いします。 合わせて、「教養立町神石高原」への対策は、具体的にどう計画されているのか。お伺いします。 佐竹教育長 公民館設置基準の改正によりに小学校、中学校の通学基準はなくなった。また指定管理者制度の運営が可能となった。 本町の公民館の設置状況は各地区で大きく異なる。平準化することが求められた。平成18年度から公民館の再編について小学校区の公民館設置を含めて協議し4地区公民館の方向性を出した。これに伴い各自治振興会長、公民館自治体部の皆さんに説明を頂き各地域で主体的な公民館活動を行って頂いている。高蓋地域も各種活動が主体的に運営されている。今まで一番大きい行事である三和地区で実施されている公民館祭りも、各地域で取組む方向性が出ている。これに伴い平成20年度からは、地区公民館が支援を行うため運営体制を充実し、地域の要望に応えて行く体制作りに努める。 高蓋には小学校があるので、放課後子供プランは、今までどおり継続して実施する。 教養立町についての対応は、本町での読書週間を定め、実施についてのポスターなど啓発に努める。子供の読書推進については、平成20年度アンケート調査を行い、子ども読書推進計画の策定を行う。大人の読書については、家庭、地域、職場の分野に分かれるが、まず行政職員から率先して始め、教育委員会から輪を広げて行きたい。関係者、関係団体と協議を行い確実に実施する。 木野山 現在の中央公民館館長は、教育長か、生涯学習課長か。 新しく就任される中央公民館町の役割は。 三和地区以外の分館も多くの公民館的事業を行っているが、分館廃止でこの事業が保障されるのか。 来見ふれあいプラザについても、各種の活動が保証されるのか。現在の3日体制はどうなるか。高蓋も同様で1日減か。今までの公民館活動は保証されるのか。
教育長 現在の中央公民館長の役割は、公民館運営審議会の召集、方針・諮問、県内各公民館連絡会議への出席などで、現在は教育長が兼務している。 4つの地区公民館の運営を横に繋ぐ機能を高める。また公民館自体の機能を高めるために専任の中央公民館長を配置する。 他の分館についての現在の活動の保障については、各分館の事業は、自治振興会との協力事業が多く含まれている。また自治振興会そのもの事業も含まれている。例えば、高蓋公民館については、子供放課後活動など子供を対象としたものが多い。公民館自体のものである公民館祭り、高蓋クラブ活動、写真パネル展示もある。高蓋は、「さんわ総合センター」として町内全体の文化芸術の拠点としてある。広域な活動で具体的にどれがどの分野と分けるのは難しい。即ち、取組みの方向性が分かれば地域の中で地域の公民館との連携を図りながら地域の自治体活動を行って頂く。地域の公民館活動に於いては今までも分館として予算化していたので、地区館となっても今までの公民館活動であればその中で予算化し支援して行く。 中央公民館長を配置して、地区公民館には、公民館評議委員会を設置する。地域の自治振興会の各部会の中の「ひとづくり部長」と地区公民館とで組織を作り各自治振興会の活動の把握を行い、それに対する地区館の支援の体制作りを図る。 現在、各公民館に配置している職員については、地区公民館機能と自治振興会とを合わせた体制整備が必要となるので、各支所へ移動し双方の意思の疎通を図って行ける組織作りを行う。 分館の廃止による管理形態は、各自治振興会での自治公民館として検討していましたが一度に指定管理とはいかないので、平成20年度は行政が管理する。教育委員会の管理体制でなくなる。設置管理条例に関係する課で管理を行う。分館で行っていた業務について、公民館としての活動は、地区公民館と連携を図りながら重点的に実施できる体制を作る。 木野山 来見ふれあいプラザの館長はどうなるのか。 管理は企画課となるが、管理経費358万円に公民館活動費が含まれるのか。
近藤生涯学習課長 企画課の管理となり設置条例に定めてあるような形の建物の管理となる。今までの公民館活動は、それぞれ個別に予算化する。 木野山 来見ふれあいプラザは公民館でなくなるので、公民館活動は三和公民館が統括して実施するのか。地区館としての三和公民館の職員が担当し、現在の嘱託の館長は不在となるのか。 生涯学習課長 基本的には地区公民館が地域の活動をカバーする事になる。公民館の役割は戦後まもなくは戦後復興だったが、最近は産業活動、学習の場の提供などに取組まれてきた。合併で町は大きくなったが今までの小さな単位での自治活動を如何にまとめるかが重要な役割となっている。そういう意味で自治振興会と連携した地域づくりにも役割がある。自治振興会と連携した活動をどうするかに取組む。サークル活動についても自治振興会と連携して推進し取組みます。 木野山 連携ということは自治振興会が公民館活動を行うという意味だと思う。 出来るか心配ですが、充実した取組みが出来ることを期待します。 木野山 ③地域を守るために「自主防災組織」の組織化が提唱され各振興会で取組まれていますが、今後どう取組むのか。方針をお伺いします。 町長 23振興会で自主防災組織が出来ている。81%の組織率である。来年3月からの組織化をお願いしている。「自らの町は自らの手で守る」という崇高な精神とその重要性を多くの住民が理解され推進されている事に感謝している。 独自での地域防災訓練、防災関連設備の点検、自主防災計画策定であり基本的には自主防災であり地域で行うもので、行政は各種情報の提供、消防団・消防後援会との連絡調整、研修会の開催など行い行政面から対応・支援する。 木野山 自主防災組織結成の手引きパンフレットなどの活用で自主防災組織の組織化を各自治振興会に呼び掛けられていますが、全町での組織化が必要と思う。 特に一朝有事のときに、一人暮らしの高齢者世帯など生活弱者の方への対応などには、自治振興会、班単位での自主防災組織の救助活動が一番有効であり、地域を守ることに繋がる。組織の立上げは急務である。早急に取組んで欲しい。予算化は出来ないか。 全町での組織化が出来たら、町をあげての防災訓練など実施したらよいと思うが。 総務課長 思いは同じである。昨年の3月から自主防災組織の立上げを自治振興会に呼び掛けた。 組織化が進まないのは反対とか資金がないからではなく、規約の作成など手続き上手間取っていると思われる。お金を出して組織を作っていただくものでもない。 防災訓練などへの対応は、防災連絡協議会など立上げ統一してやりたい。 財源は、ふれあい事業補助金や建設課の草刈り補助金など活用して欲しい。 木野山 自主防災活動で、事故が発生したときの保障はどう考えているか。 総務課長 基本的には町の消防賠償保険での対応となるが、ケースバイケースである。 良く研究し対応する。 木野山 ④多くの効果をもたらす「CATV事業」に新たに取組む「気持ち」はありませんか。 町長 財源や加入率の問題があるが、期限が迫っており早急に検討し間違いのない選択をしたい。 木野山 町としては、CATVの総事業費は20~30億円と見積もられていますが、財源につきましては、本町よりも財政状態が悪いと思われる「北広島町」は財源不足解消、財政再建のために、若者が定住し、企業誘致を可能にするCATV事業にあえて取組んでいます。 町長の政策判断の範疇である。新たにもうひとつ踏み込んだ、決意をお願いしたい。 町長 単純な事ではないので、あらゆる事を研究して間違いのない判断をしたい。 木野山 地デジ対策もあり、鍋谷山に基地局の出来る平成21年の10月までには結論が欲しい。 事業費についても13億円程度で出来るという見積もあると聞いているので、よろしくお願いしたい。 |
| 平成20年事項別質問 |
木野山 ①情報センターシステム管理経費 10,200→14,700千円 *パソコンサポート期限切れに伴う機器の更新 職員用50台/4,500千円)との事ですが、具体的に説明を。単価は安いのか。個人の物は無いのか。セキュリティーは。どこの職員でどのパソコンか。初期投資はいくらか。 *パソコンの価格が高いように感じるがどうか。 峠本総務課長 ウィンドウズ98、MEのサービス切れファイアーウオール設定などシステムの改修を行う。職員用パソコンは羅針盤メールサービス使用のため旧町で使用していたパソコンを全職員に配布したが、内50数台は旧式のためインターネットなど対応が出来ないので機種の更新をする。単価については入札で決定する。5年リースである。 予算の内容は、122,850円/1台×50台で5年リースの1年分、それと情報センターのインターネットルーターにファイアーウオールとウイルスサーバーがあるがそれがME、98なので設定を変更するための単価を含んでいる。 パソコンは個人所有のものは無い。 セキュリティは情報センターを中心としたウイルスのチェック、ウイニーによる情報の流出についても年に1~2回の情報セキュリティポリシーで管理を促している。万全を期していきたい。
木野山 *情報センター経費で住民情報システム管理費が半額となっている。何か理由があるのか。 16,810→8,500千円 平井企画課長 情報システム管理で、光ケーブル(45k)を単独で福山から引いていたものを、ADSLの太線に切り替えたため。 個人情報の確保については、戸籍・住民・税など行政系の情報は財務会計システムで管理しているので、個人のパソコンと系統が違う。従って情報が外に漏れることはない。 個人パソコンもそれぞれウイルスソフトで守っているがこれから煮詰める。 木野山 ②*町内一体化イベント委員会補助 2,260千円の積算根拠は。 3,000千円だったのでは。
企画課長 住民の参加状況など考慮し経費を抑える方針。YMCMラジオのCM放送を一般の番組提供を止めてCM放送のみにする。 226万円については、今回は豊松の順番で、豊松の実行委員会と協議しているが、イベントの巡回バスに120万円、4地区のイベント紹介のポスター、ラジオ・新聞・テレビなどのPRに80万円、スタンプラリーのような景品代に16万円、消耗品に10万円を見積もっている。 まちづくり実行委員会と地元の委員会が一緒になって中身を煮詰めて頂いている。
木野山 ③*各コミュニティ施設管理経費が、一律10%程度の減額となっているが積算根拠は。 地域のコミュニティ施設は、指定管理者制度になじむのか。地元の自治会は法人格は無いが自治会のメリットは何があるのか。使用料は条例で決まっている。経費の切り詰めで地元に負担ばかり押し付けるのでは。 *小畠交流会館/指定管理委託料 1,270→800千円(福祉協議会)地元の利用は。 企画課長 電気、掃除など節減してもらう。 地元の使用は、一年間検討する。 自治振興会地区にあるコミュニティ施設は、地域へ特化された使い方を想定すると、地元の自治振興会に指定管理をお願いするのがベターである。使用料は使用者負担の原則で他の指定はなじまない。 木野山 地域のコミュニティ施設を指定管理制度で地元の自治会に指定管理者に選んだ場合、自治会にはどんなメリットがあるのか。 企画課長 一定の制約は有るが、地元の皆さんに自由に使っていただける。これがメリットである。 木野山 ④福祉タクシーの本格試行。H19年6月の事項別質問で 「<福祉タクシー試行運転について> 福祉タクシーは7月から本格運行と聞いていたが、なぜ試行運行となったのか。 <企画課長> 福祉タクシーは、乗合タクシーでは時間的ロスがあり、身体的には狭くて苦しいなど問題があり、福祉の専門家とも相談し、単独の利用を考えたものです。利用者は、身体的・精神的な障害を持った方や、突発的に体に異状を訴えた方を対象とするものです。 7月から本格運行しようとしたら、一般の障害者は500名おられ、その中から利用者を選択・決定することは難しい事。障害者対策としては、この程度のことは既に実施しており効果が無いのではという意見もあり、専門家サイドからはもう少し検討する必要があるのでは、となった。おでかけタクシーについては運行時間、予約方法など形がほぼ決まってきたにも拘らず、特別な運行をする福祉タクシーの必要性について福祉関係担当課から疑問符が付けられたので、総合的に判断して、7月から試行運行とした。 どういう形で皆さんのニーズに最大限答えるのか、運行形態を、予約にするか予約無しにするか、対象者はどうするか、人数はどうなるか。担当課と協議の結果しばらく考える事になったので、データー収集に徹底するため9ヵ月間の試行運行としました。 という事でしたが、本格運行と成りました。 問題はどう解決されたのか。」 企画課長 利用者の数、利用方法など定まってきた。 台数を増やす必要はなく現状で対応できることが判明したので福祉課で本格運営とした。 木野山 ⑤老人会開催経費 5,940千円 なぜふれあい基金から経費を負担するのか。 町の主催に統一して一般予算化しないのか。早急に平準化をすべきだ。
総務課長 平成20年度は、4地区敬老会対象者に1,000円をふれあい予算に上乗せする。 過去、油木町は各地域支部ごとの実行委員会方式、他の3地区は町の直接方式。 実行委員会方式で各地区まとめて出来ないかお願いしたが、現実的に出来ないということで統一できなかったので「ふるさとふれあい予算」方式として違うやり方も認める事とした。町が主体でまとめて行う方式に統一出来れば一般財源で対応する。 木野山 油木地域の敬老会の実行委員会方式を改めて町の主催に切替え統一した敬老会にすべきだ。サービスの平準化に繋がる。 総務課長 敬老会のあり方の統一が出来たら、一般財源化する。 西本福祉課長 旧町村の伝統文化があり統一できていない。府中市は、それぞれの地域で行い内容は違っても一定の補助金を出している。できれば直営方式ではなくいわゆる油木方式で統一を考えている。 木野山 敬老会は、お年寄りの方の長寿のお祝いの式典が主となるもので、長年一生懸命町のために尽くされ頑張ってこられたことに対して町を挙げて感謝の意を表し式典を行う事が重要で、意義付けをした敬老会が望ましい。 地域方式(油木方式)は、担い手も少なくなり、高齢化など敬老会をするには限界のある地域もあり長続きしないと思う。 統一し平準化のほうが、敬老会としての意義付けも大きいのではないかと思うのでその方向で検討されるよう提案いたします。 福祉課長 良い方向で調整する。 木野山 ⑥保育所運営経費のうち需用費・賄い材料費15,394千円ですが、 *食材の調達はどうされているか。中国野菜・冷凍食品はないか。 福祉課長 以前から地産地消で、安全安心な食事、地元商工会や地元産品を利用し冷凍食品を直接仕入れ使用することはない。 どの保育所も今回の事故に該当する中国冷凍食品は使用していなかった。 木野山 ⑦非常備消防費 71,680千円 *消防団員 総員800名→760名に見直し(実質742名)との事ですが、消防団員は地域防災の要であり、町のあらゆる分野での実動隊でもあり活性化・元気の基である。 団員数についての町の考えは。800名を確保すべきだ。 総務課長 少子高齢化により、団員の確保が困難となってきた。800名で満というのが望ましいが現実的には実働人員が742名となっている。将来的には、経費面から団員定数で支出をするものもあるので経費節減の意味からも消防団員定数を760名にする。定数を満にしたいしその様に努力をしているが現実的には難しい。 木野山 消防団員であることは崇高な誇りの持てる職業である。町を挙げて意識の高揚に勤め、団員の減少に歯止めをかけ、800名を確保すべきだ。 総務課長 |