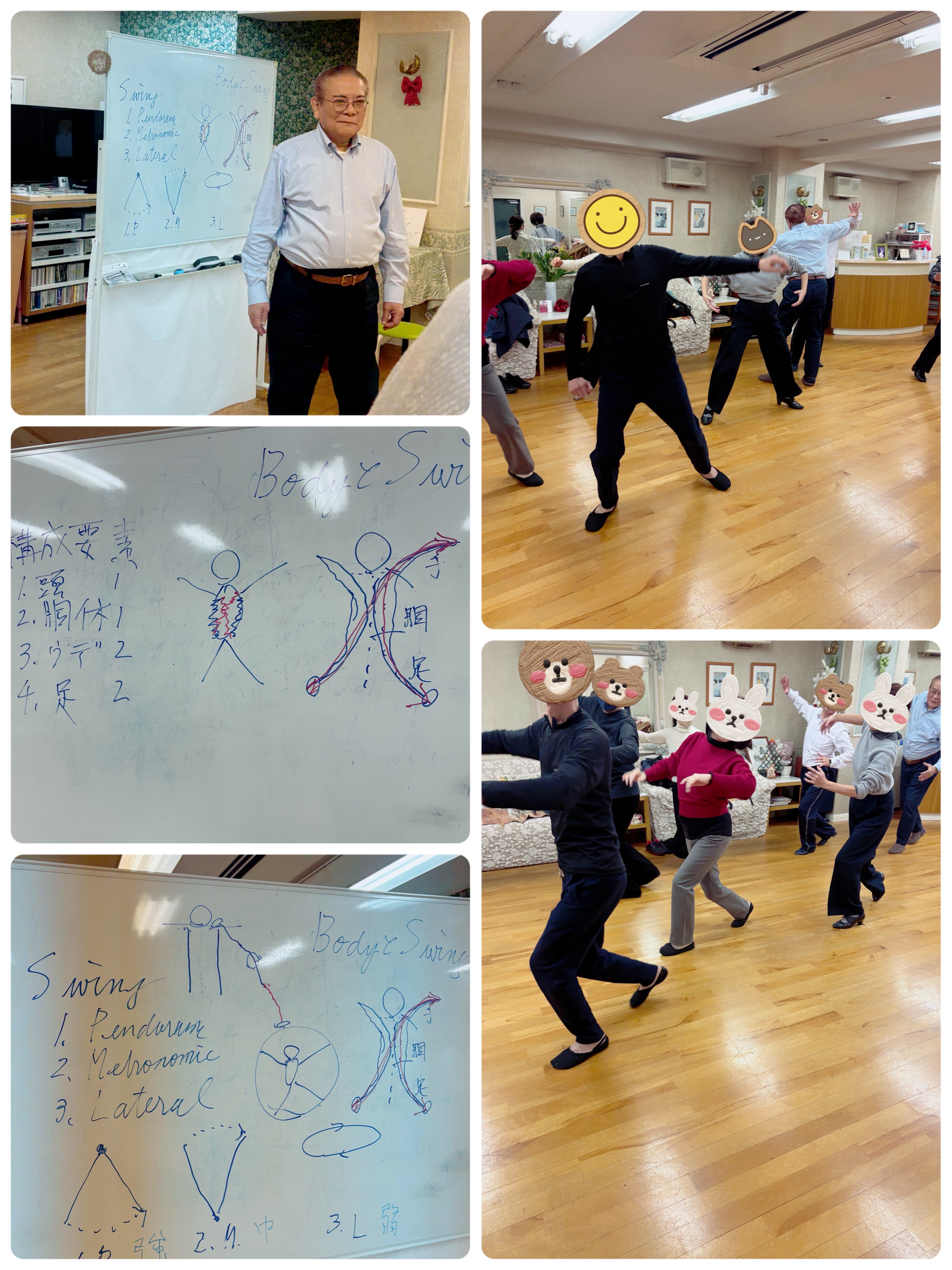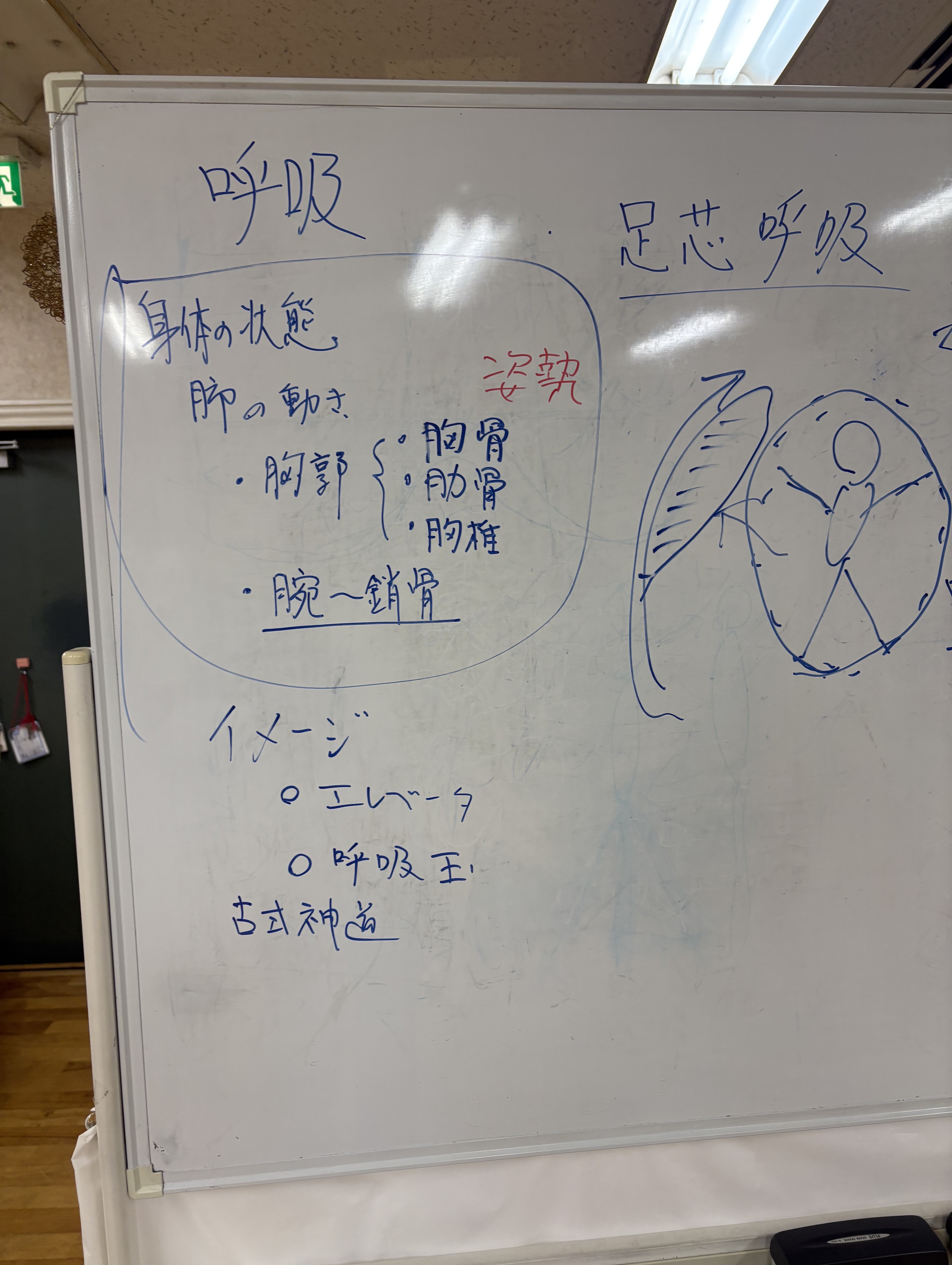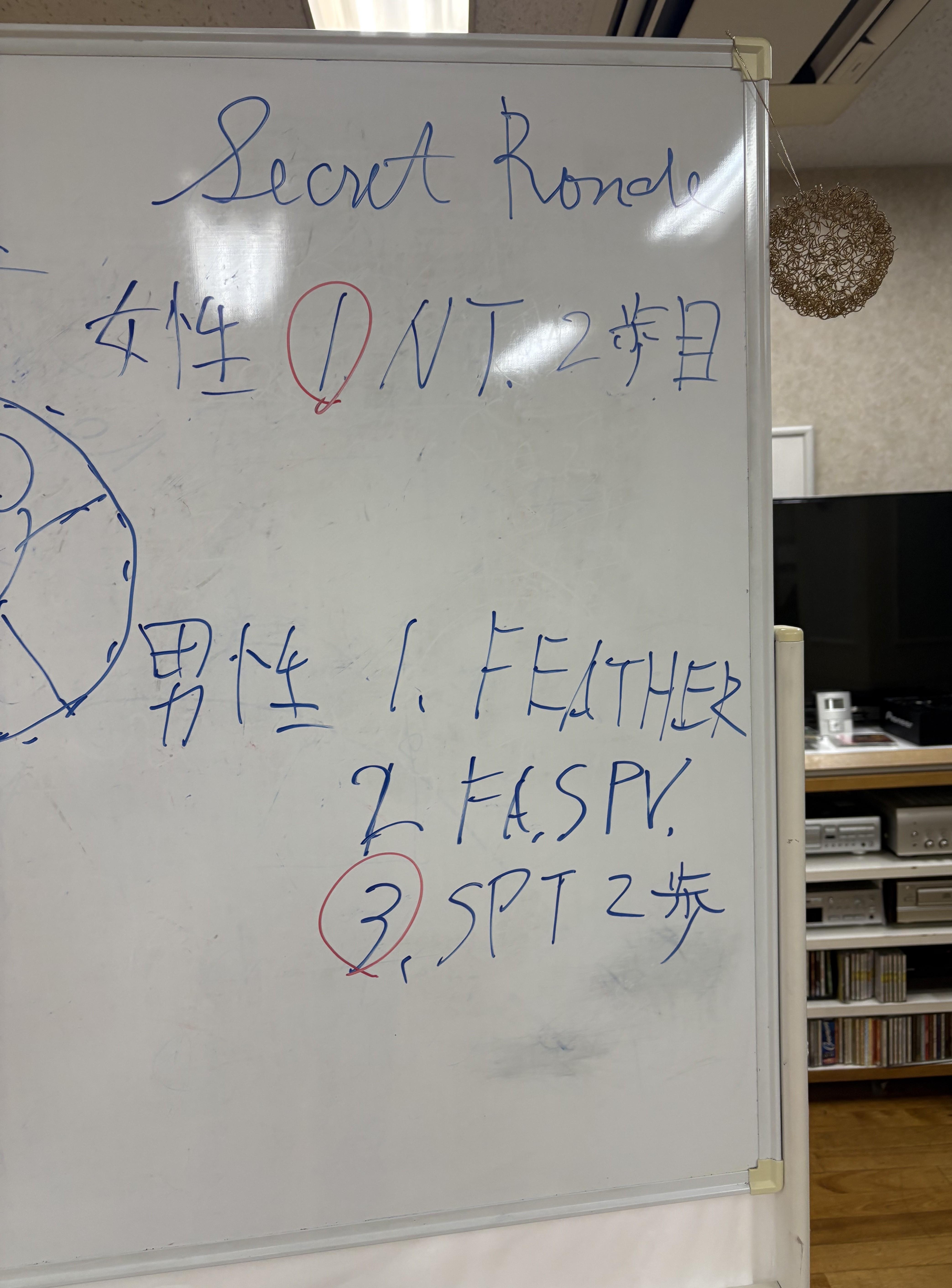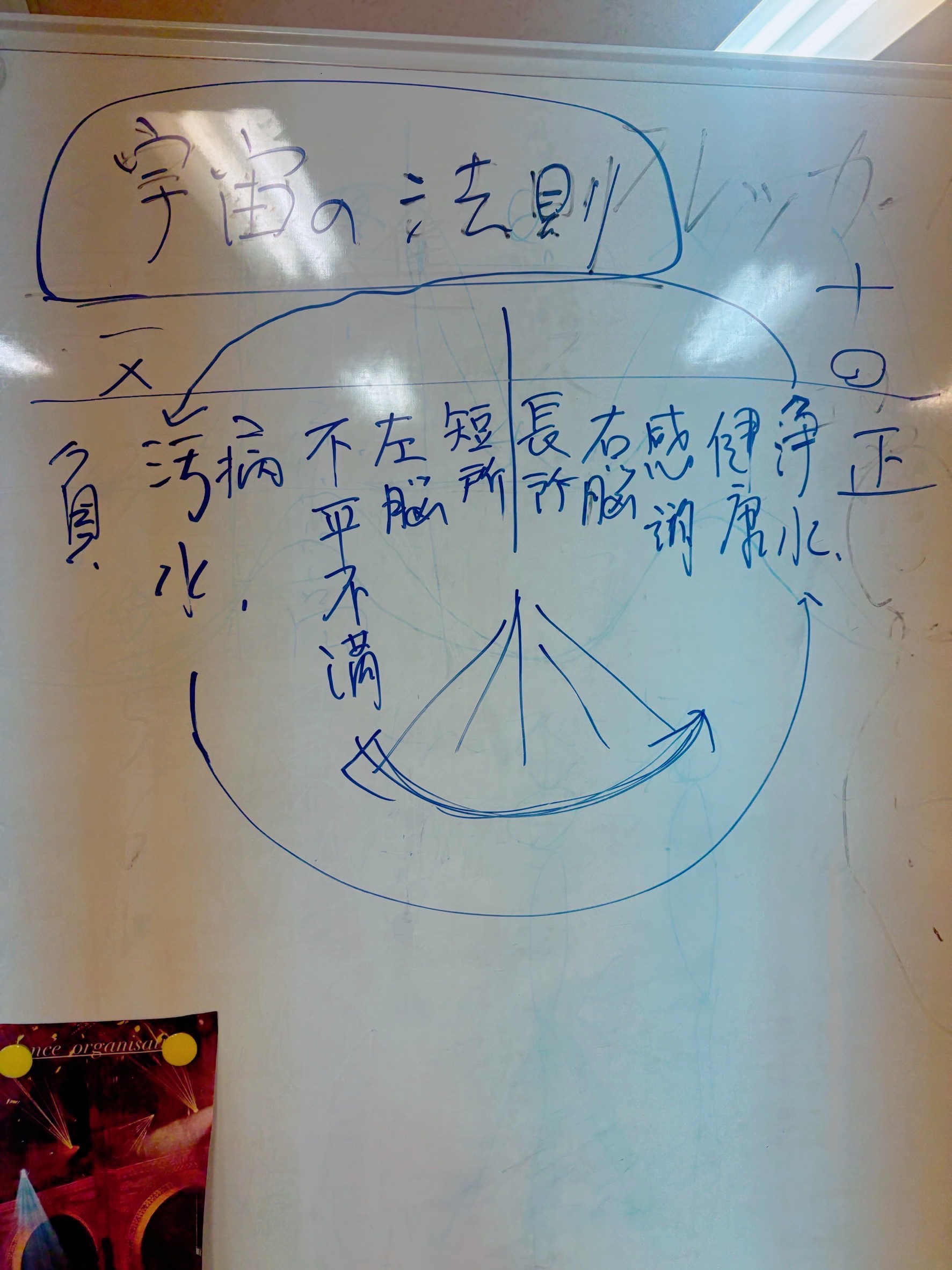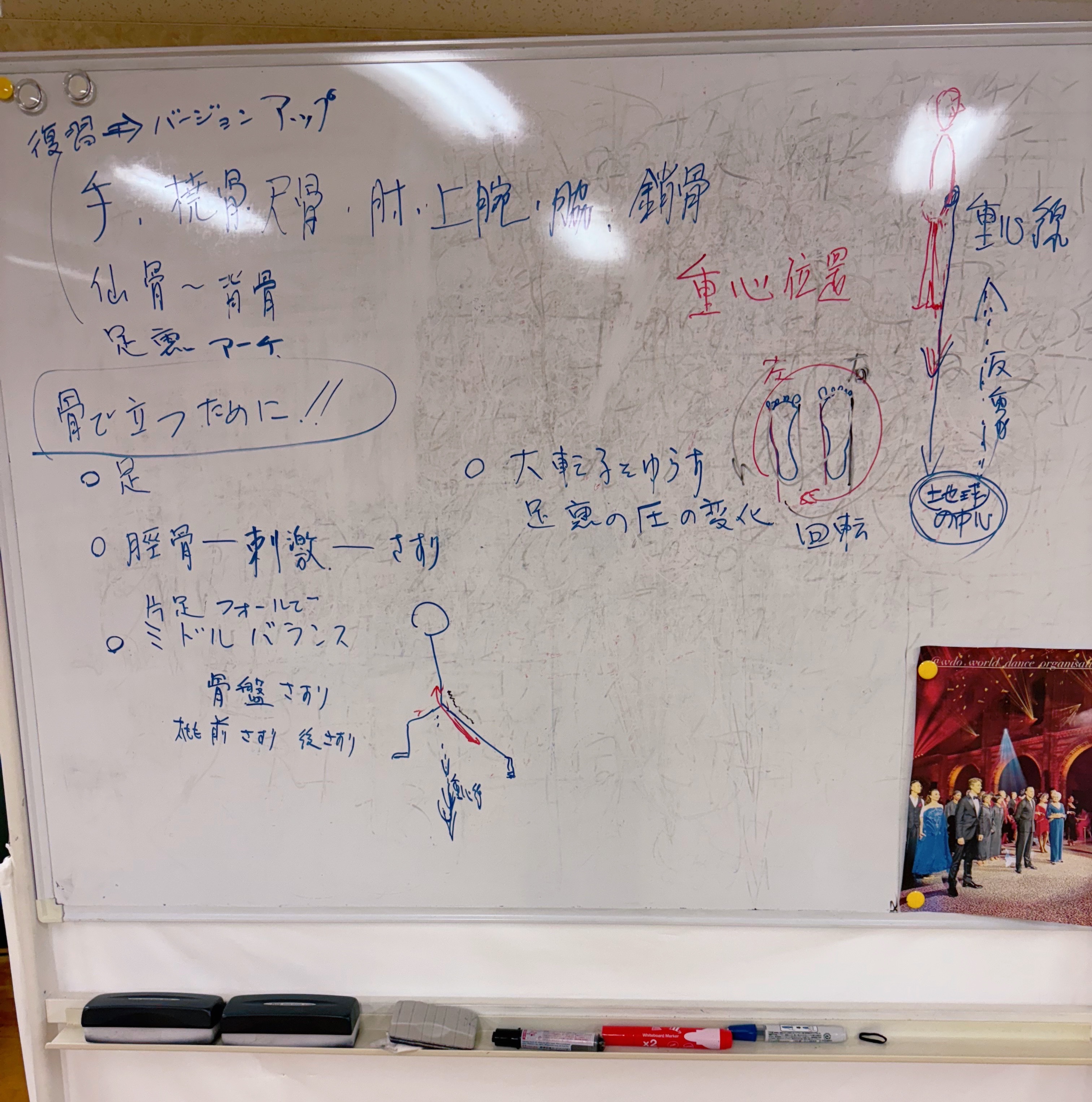骨格バランストレーニング(中井理恵)
前回の復習
・エネルギーと呼吸 オープン&クローズの法則
・身体の見えない部分を知ることで身体の動きを知ろう
天才の動きをまねるなら、
動きの連動とエネルギーの流れに注目!
動きの連動とは?
ある部分が動くと次の部分が連鎖的に動く事、しなやかで無理のない動きができる状態
1)腕を上げる、横に開く
筋肉を使っていきなり腕を動かす?身体の中心から順番に連動して動かす?
違いを体感してみよう。
トレーニングの前に、連動を妨げる力みや滞りをケアしよう
足、足首、脛骨、太もも、股関節、仙骨、骨盤、頸椎、鎖骨、肋骨、胸骨
①体幹から胸骨、肋骨、鎖骨、アーム、指先まで動きを連動させると?
②その連動にエネルギーの流れ(呼吸のオープン&クローズの法則)を加えるとどう変わるか?
*呼吸のオープン&クローズの法則
息を吸う=エネルギー IN
息を吐く=エネルギー OUT
エネルギーは身体の外からINし、身体の外へOUTする
③ダンスでは、重心移動に従って、身体のバランスを取りながら、重力を地球の中心にOUTし、地球の中心から足裏を通して体の中へINし、全身へ連動させる。
⇒足芯呼吸でパワーアップさせている
2)ラテンのベイシックアクション「クカラチャ」を例に研究してみよう。
・フリーアームの動きは、どこから・どの方向に・どのように連動させる?
・アームを開いて行く時、吐きながら指先からエネルギーをOUT
この時呼吸を吸ってしまう場合は⇒足に力みが有る
足の力みを抜くと⇒息を吐きながらエネルギーを放出できる
アームを戻すとき、息を吸って、空中からエネルギーを取り込む
・ラテンで慣れたら、スタンダードでも同じ事が体の中で起こす。
3)音楽との関わり
・8小節毎のフレージングがなぜ必要か?身体が音楽の波動を感じているから。
・呼吸のオープン&クローズの法則をヒントに、エネルギーの流れやパワーの出し方を検討してみよう。
スタンダード ベーシックフィガーから学ぶ(2)中井信一
前回の復習 ピボットの種類
SLIP PV、TOE PV、HEEL PV、OP PV、OP PV PVAC、PV AC
《フットワーク》
フットワークがH=ヒールに乗っているか?
*スピンターンの後退THTのヒールはフロアに触れるだけで乗らない!
*タンゴ シンプルリンクとプログレッシブリンクにおけるフットワークを例に
・ノーウェイトの瞬間がある(ポイント)
・右足で体重を受けるときフラットになるタイミングは?
・フラットであっても体重の圧は移動している