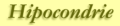ゼレンカの生涯
- 以下は主に Oxford University Press より出ている Jan Dismas Zelenka (1679-1745) [Janice.B.Stockigt] の解読結果を元に記した物です。ゼレンカ研究はまだまだ現在進行中のようで、ちょっと古めのCDのライナーノートなどとは記述が違っていることもあります。
出生と若年時代
ヤン・ディスマス・ゼレンカは1679年10月16日、現在のチェコのプラハ近郊のロウノヴィツェ(Louñovice)で、8人兄妹の長男として生まれました。父親の名前はイジー(Jiřík Zelenka (1648-49 or 1655 -1724)) 母親はマリア・マグダレーナ(Maria Magdalena)といいました。父は職業音楽家で、この地で教師兼オルガニストをしており、後にその地の教会のカントールともなります。
この当時の音楽家とは芸術家ではなく世襲の職業でした(その最たる例がバッハ一族)従ってゼレンカは父親から最初の音楽教育を受けたと思われます。また彼の弟ヤン・キリアン (Jan Kilian (1694-1740以降)) もプロの楽師となったことが知られています。
ゼレンカはおそらくプラハのクレメンティヌム(Clementinum)というイエズス会系の学校で教育を受けたと思われます。彼はその後もこの学校に音楽を献呈していることから、こことはかなり深いつながりがあったようです。
ゼレンカの最初の作品の記録は、1704年にこの学校プラハの下町にあったイエズス会の学校で演奏されたセルニン伯爵 (Count Cernin) の先祖の武勲Supreme Burgrave(城伯:神聖ローマ帝国における爵位の1つ)への叙勲を記念した学校劇 School Drama: Via Laureata ZWV245 のための音楽です。セルニン伯爵はプラハの大物貴族で、音楽家のパトロンとしても有名だったようです。
しかしこの作品は現在失われてしまい、どのような物だったかは不明です。
ゼレンカの子供時代・青年時代に関しては、この程度しか分かっていません。ここで一つ注目すべき事は、ゼレンカの洗礼名はルカス (Lucás) とつけられましたが、後の自著では常にディスマス (Dismas) となっていることです。ルカスとはルカによる福音書のルカのことですが、ディスマスというのは、キリストの横で一緒に磔になっていた良い方の犯罪者の名前です。
ゼレンカが本格的に音楽史上に現れるのは、1709年、プラハのハルティッヒ男爵 (Baron Josef Ludvík Hartig (後伯爵となる)) の宮廷楽団のコントラバス奏者としてでした。ハルティッヒ男爵の弟であるヤン・ヒューバート (Jan Hubart Hartig) がゼレンカのパトロンだったようで、ゼレンカは晩年になっても彼に作品を献呈しています。
その次の年1710年(1711年の説もあり)ゼレンカは300ターラーの報酬でザクセンの首都ドレスデンの宮廷楽団(ここは現在のシュターツカペレ・ドレスデンの前身)のヴィオローネ奏者となりました。
この当時のザクセン選帝候は、アウグスト強王と呼ばれたフリードリッヒ・アウグストI世 (Friedrich Augustus I) でした。宮廷は10年ほど前の1696年にカトリックに改宗したばかりで、カトリック教会音楽がたくさん必要になっていました。
このことにより、その当時既にゼレンカは演奏家として十分に認められるだけの実績があったことが分かります。というのはドレスデン宮廷楽団はその当時のヨーロッパで最も伝統のある、最高レベルの楽団だったからです。
1711年、ゼレンカは "Missa Sanctae Caeciliae" ZWV1 を作曲しました。この曲がゼレンカのドレスデンでの最初の作品です(この曲で既にゼレンカの音楽の基本的な特徴が顕れているようです)
ただ、ゼレンカの使命はイタリア行きではなく、ウィーンで教会音楽を筆写してくることと、皇室宮廷作曲家ヨハン・ヨーゼフ・フックス (Johann Joseph Fux (1660-1741)) に師事して作曲の勉強をしてくることが目的だったようです。フックスはその当時対位法の最高の権威としてヨーロッパ中に知られていました。
いくつかのライナーノートには1716年頃ゼレンカがフックス推薦によってヴェニスに行ってロッティ (Antonio Lotti(1667-1740)) に師事したという話が載っていますが、これは19世紀の二次資料に初めて現れる話で確証はないようです。
ちなみに皇太子のこの旅行はドレスデン宮廷楽団には大きな影響を与えました。当時著名だったロッティがこの縁でドレスデンに行くことになります。またイタリア遊学中だったヨハン・ダビッド・ハイニヒェン (Johann David Heinichen (1683-1729)) が次の宮廷楽長になったのもここで皇太子と知り合ったことがきっかけです。
ゼレンカがドレスデンに戻ったのは1719年頃だったようです。
ここで初めてゼレンカはコントラバス奏者として登録されています。この年ゼレンカは "Missa Corporis Domini" ZWV3 を作曲していますが、まだ「作曲もできる楽団員の一人」ぐらいの認知だったようです。
1723年はゼレンカの生涯で最も華々しかった年かも知れません。
1724年以降は一見華々しい出来事はなくなりますが、その実ゼレンカは非常に多忙な日々を送っていました。
もちろん同じ曲をそう簡単に使い回せるわけがなく、ミサ曲や、晩課に使う詩編・アンティフォナ・賛歌などが大量に必要になるわけです。
またこの時期よりゼレンカはドレスデンの楽譜の管理もしていたようです。1726年から39年にかけて作成された彼自筆の「教会音楽目録」“Inventarium rerum Musicarum Ecclesiae servientium"が残されています。ZWVリストには現在散逸してしまった作品がかなり含まれていますが、その作品がかつて存在していたという証拠がこの目録です。
1724年にはまたゼレンカの個人的に重要な出来事がありました。ロウノヴィツェで父親のイジーが死去したのです。
ところで当時の宮廷楽長であるハイニヒェンという人はかなり病弱だったようで、1729年に46歳で亡くなってしまいます。
ゼレンカの期待に反し宮廷楽長の座はしばらくは空位でした。そして1730年、ある重要な出来事が起こります。この年イタリアから歌手の一団がやってきました。彼らはヨハン・アドルフ・ハッセ (Johann Adolf Hasse(1699-1783))ゆかりの歌手達で、さらに1731年にはハッセ本人と彼の妻で当時ヨーロッパで大人気の歌手であるファウスティーナ・ボルドーニ (Faustina Bordoni) がやってきて、ドレスデンオペラを再興したのです。
この当時アウグストI世は大抵ポーランドの方にいたため、ドレスデンの内政は皇太子であるアウグストII世が代行していました。彼がイタリアで流行しはじめていたいわゆる「ギャラント風」の音楽を好んでいたことは疑いようもありません。それに対してゼレンカの音楽のスタイルは当時としてはもはや「古くさい」物でした。
そのことを暗示する出来事が既に1722年の時点で起こっています。この年ゼレンカがある晩課の音楽を作ったとき、出席していた皇太子はそれが長いのに業を煮やして、曲目の一部をカットさせたという記録が残っています。
そんなとき、1733年2月、ドレスデンに大変な事件が勃発しました。アウグスト強王が突如逝去したのです。この年はてんやわんやの騒ぎだったでしょう。ゼレンカは“レクイエム ニ長調 ZWV46” や“死者のための聖務曲集 ZWV47”を大急ぎで作ることになります( やむにやまれぬ事情の元に、偉大なる国王陛下の御前に身を捧げ、陛下の最も従順な僕が嘆願申し上げます。
これまでは陛下は国内外の様々な事件に深く関わらなければならなかったことを存じておりましたので、申し上げるのことを差し控えておりました。
私は24年もの間陛下の宮廷にて、光栄なるお役目を仰せつかって参りました。とりわけ今は神の御許におられます、陛下の父君であらせられます先代の王の命で、私の音楽によるささやかな見返りさえ求められずに、ウィーンの王宮の高貴な方々に一年半の間お仕えできたのは大変おそれ多いことです。しかしながら、同時期にここより送られた音楽家は、全て彼らの必要に応じた豊富な報酬を得ております。このことは寛大なる陛下にはご承知頂けることと存じます。
私はウィーンからの帰還に続いて、長年の間王宮の教会音楽を供し、宮廷楽長のハイニヒェン殿を援助して参りました。また彼亡き後には私がほとんどの音楽の作曲と指導をして参りました。何処かより必要な音楽を入手するため、私の音楽を筆写させるため、私は多額の出費を強いられました。それは私の報酬の半分にも達します。
それ故に私は伏してお願い申しあげます。どうか私にハイニヒェン殿亡き後空席となっており、その役目をずっと私が代行して参りました宮廷楽長の地位をお与え下さるようお願い申しあげます。
そして彼が最後に得ていた報酬の一部でも私の報酬に加えて頂ければ、大変光栄に存じます。
ヤン・ディスマス・ゼレンカ 1733年11月18日 ドレスデンにて
それにしてもゼレンカはこのことに全く気づいていなかったのでしょうか? どうも実際そうだった可能性が高いようです。
この作品はゼレンカがこれ以降では多用する
もちろんそういう付け焼き刃の対応では、もはやどうしようもない状況になっていました。
こうしてゼレンカは宮廷楽長の座を得ることはできませんでした。そしてその後誰からも忘れられて孤高の晩年を迎える―――とよくライナーノートに書かれていたりします。
宮廷楽長の座を逃してからしばらくして1735年、ゼレンカは「教会作曲家」という称号をもらいます。
しかし実際にはゼレンカの待遇は、少なくとも1737年ぐらいまでは現状維持か、実質はそれ以上だったようです。当然のことですが、ハッセはまだ新参の立場です。特に教会音楽関係のことではゼレンカのサポートがしばらくは必須だったでしょう。
これはどういったことでしょうか? 単なる誤記でしょうか? 想像するしかありませんが、少なくともゼレンカは名目上はともかく、実質上は宮廷楽長並の扱いを受けていたのではないでしょうか。
1736年にゼレンカは再び請願書を出していますが、このときは昇給してくれという願いだけで、宮廷楽長云々には言及されていません。これはゼレンカが既に諦めていたともとれますが、十分満足していたととることも不可能ではありません。
少なくともゼレンカは1736年一杯ぐらいまではかなり忙しい日々を送っていたようです。
1737年以降、ゼレンカが演奏を行ったという記録はめっきり減ります。多分ハッセも環境に慣れてきてゼレンカのサポートが不要になってきたためでしょう。それだけでなくこの頃からゼレンカの健康状態が悪化してきた事も考えられます。
この時期特に重要なことは、ゼレンカの作風が大きく変わってくることでしょう。
この時期のミサに出てくるアリアは
ゼレンカのこの時期の音楽を聴くと、世捨て人の音楽とはとても思えない気がします。どちらかというと意欲満々で新しいことにチャレンジしているような、そんな感じさえします(もちろん一部にはかなりメランコリックな部分があったりしますが、元々ゼレンカはレクイエムが大得意なので、単に地のような気がします)
そして1740年から41年にかけて、ゼレンカは「最後のミサ曲」(Missa Ultimae)という全6曲の連作ミサ曲を作ります。
その第一曲の「父なる神のミサ曲」(Missa Dei Patris)には以下のような前書きがあります。 L:J:C:Missa Dei Patris と呼ばれる「最後のミサ曲」の最初の曲。ヤン・ディスマス・ゼレンカによる最もささやかな取るに足りない作品ではあるが、全ての物の創造者、最高にして至高の父に、最大の謙虚さと尊敬の念を持って、与うる限りの敬愛の念と共に捧げる。
これを見ればこの作品は、もはやこの世のしがらみに囚われず、ゼレンカ本人と彼の信仰する神のためだけに書かれた作品であることが明らかでしょう。
しかしながらゼレンカは、この連作ミサを完成させることはできませんでした。現在残されているのは第1曲 "Missa Dei Patris" ZWV19 第2曲 "Missa dei Filii" ZWV20 第6曲 "Missa omnium Sanctorum" ZWV21 の3曲で、第2曲はクレド以降がなく未完成と思われるので、実質2曲半でしかありません。
ゼレンカはなぜこれを完成させることができなかったのでしょうか? 単純に時間が足りなかったのでしょうか? 少なくとも彼の健康が損なわれていたことは事実で、そのために書けなかったことは十分考えられます。ただこの後ゼレンカの最後の作で、作品の規模ではミサ曲並の「聖母マリアのためのリタニア」ZWV151ZWV152 が書かれているため、その後ずっと不健康のため書けなかったというのはやや不自然です。
また残されている最後のミサ曲はかなり短期間に仕上げられています。"Missa Dei Patris" 作曲期間は不明ですが、仕上がったのは1940年9月21日のようです。"Missa omnium Sanctorum" は1741年2月3日にできています。その間に "Missa dei Filii" が書かれています。すなわち、dei Filli と omnium sanctorum は順番に書いたとすれば、5ヶ月前後で書き上げられているわけです。
最後のミサ曲を聴いてみて筆者が思うには、ゼレンカは燃え尽きてしまったのかも知れません。やはり音楽家にとって自分の作品が実際に音になったときが一番喜びを感じられる瞬間でしょう。演奏される宛がまったくない作品を書き続けるということは、相当のエネルギーが必要となるでしょう。
そのためゼレンカが若い頃なにか致命的な過ちをやらかしたと考える向きもありますが「ディスマス」という名前は当時のチェコでは結構ありふれた名前だったようで、必ずしもそう言い切れるほどのものでもないようです。
もちろん彼の改名は何らかの決意の結果だったのは間違いないでしょうが……
音楽史への登場
この年 "Immisit Dominus pestilentiam" ZWV58 という名のオラトリオがクレメンティヌムのために作曲されていますが、これが現在スコアの残されたゼレンカの最初の曲です。
ザクセンは北のポーランドと南のオーストリアに挟まれた小国で、アウグストI世はポーランドの国王も兼任していましたが、これは政略的な意味合いが強く、ザクセンがカトリックに改宗したのも政治的取引でした。このことは国内に大きな波紋を投げかけていました。元々この地方はルター派の信仰が根強く、アウグストI世の妃クリスティアーネ・エバーハルディーネも最後までプロテスタントで通したと言われています。
ちなみに大バッハがカントールをしていたライプツィヒはドレスデンから100Kmちょっとぐらいの距離にあります。
例えばバロック中期の最も有名な作曲家であるハインリッヒ・シュッツ は長い間ドレスデンの宮廷楽長を務めていました。後に大バッハもドレスデンに憧れて、ロ短調ミサ曲のキリエとグローリアをドレスデン宮廷に献呈したことはよく知られていますし、更に後にはウェーバーやワーグナーが宮廷楽長になっています。
ウィーン留学
この曲によってゼレンカは作曲家として使えそうだと認定されたのでしょう。1714年、報酬は400ターラーにアップします。更に1715年11月、旅費300ターラーが支給されて皇太子(後のフリードリッヒ・アウグストII世)のイタリア旅行に随行することになります。随行員にはヨハン・ゲオルグ・ピセンデル (Johann Georg Pisendel (1687-1755)) も含まれていました。
ゼレンカは1716年から約3年、ウィーンに留まります。この間にカプリッチョの最初の4曲が作られました。またこの頃同じくフックスの元に留学してきたヨハン・ヨアキム・クヴァンツ (Johann Joachim Quantz (1697-1773)) に作曲を教えたとも推定されています。
またピセンデルがヴィヴァルディやアルビノーニなどと親交を結んだのはこのときです。
ドレスデン宮廷でのゼレンカ
この年の最大のイベントは、皇太子の結婚でした。結婚相手はウィーンのマリア・ヨゼファ (Maria Josepha) 王女でした(彼女はマリア・テレジアの従姉妹にあたります)マリア・ヨゼファはドレスデンの宮廷楽団の重要なパトロンとなります。
このイベントは華々しく行われ(更新履歴のトップにある画像です)ヨーロッパ各地から著名な音楽家がドレスデンにやってきています。その中にはテレマンやヘンデルもいました。従ってここでゼレンカは彼らと会っていた可能性はあります。
しかしこのときから1723年ぐらいまでに、現在最も人気がある六つのトリオソナタ ZWV181、エレミアの哀歌 ZWV53、聖週間のための27のレスポンソリウム ZWV55 などが作曲されており、これらがゼレンカのその後の地位に大きく影響したことは間違いないでしょう。
この年の秋、プラハでオーストリア皇帝カール6世の即位のための式典が催されました。その際には近隣の王侯が招かれ、当然アウグストI世も宮廷楽団を随行して参列しました。ゼレンカはそこで演奏される音楽のかなりの数を作曲することになります。
このページのタイトルになっている "Hipocondrie" ZWV187 を含む、ゼレンカのオーケストラ曲の大半はこの時のために書かれたものです。
また同時にクレメンティヌムの依頼で「聖ヴァーツラフの音楽劇」"Sub olea pacis: Melodrama de Sancto Wenceslao" ZWV175 も作られました。これは成功裡に終わり、ゼレンカの知名度は大幅にアップしたと思われます。
ゼレンカの中期作品はほとんどが1724年以降の日付になっています。すなわちこの成功によってゼレンカはドレスデン宮廷楽団の実質上のNo2を手にしたと思われます。
カトリック教会ではミサと晩課が重要なセレモニーでした。これは日曜だけでなく「祝日」にも行われます。この祝日というは主に聖人の功績にちなんだもので、ともかくやたらに数が多く、年の三分の二以上が何らかの祝日でした。しかも重要な祝日はその日から1週間祝うことになっていました。
この時期ドレスデンではそのために宮廷楽長ハイニヒェン、ゼレンカ、リストーリ (Giovanni Alberto Ristori(1692-1753))、ブッツ (Tobias Butz(c.1692-1760)) の4人体制で音楽を作りまくっていたようです。
例えば復活祭などの最も重要な祝日の音楽はハイニヒェンが担当しており、ゼレンカはその次に重要な祝日の音楽を担当していました。
このためにゼレンカは "De profundis"「深き淵より」ZWV50 とレクイエム(消失)を作曲してドレスデンの聖堂で演奏しています。楽団員やその縁者の追悼のためにカテドラルでミサを上げることは普通のことだったようです。またゼレンカはその際にレクイエムを依頼されることも多かったようです(そのかなりが散逸してしまったのは残念と言うほかありません)
宮廷楽長の座を逃す
このためゼレンカはハイニヒェンの死の少し前から死後しばらくは、実質上の宮廷楽長の職務をこなしていたと考えられます。
当然ゼレンカは次の宮廷楽長になれると思っていたことでしょう。しかしその希望はかなえられませんでした。
再興というのは、前述の通りドレスデンのオペラは1720年にハイニヒェンとイタリアの歌手の喧嘩をきっかけに、閉鎖されていたためです。
当初はハッセはオペラだけを作っていたようなのでゼレンカは自分には関係ないと思っていたのかもしれません。しかし彼の知らないところでハッセを次の宮廷楽長にしようという動きは着々と進行していたのです。
この時期ヨーロッパ音楽の流れはバロックから古典派にという大変革期にありました。すなわち皇太子はゼレンカの音楽を古めかしくてごちゃごちゃしている音楽としか評価していなかったわけです。
バッハの音楽が弟子のシャイベにボロクソにけなされたという話も、ちょうどこの頃のことです。
ゼレンカが世渡りに長けた人物であったら、このときすぐに気づいて、作曲のスタイルを皇太子好みに変えていったことでしょう。しかしゼレンカはそういうことはしませんでした。その後の記録にもよく「ゼレンカ氏の作曲による非常に長い**が演奏された」といった記事が見られます。これはゼレンカが自分の信じる音楽表現を最優先して、曲を作っていたことを窺わせます。
レクイエムは10日で作ったらしいです10日で作ったのはMissa Purificationis BVM in D major. ZWV16でした)
これが何を意味したかというと、今後ドレスデンの宮廷音楽は100%新選帝候、すなわちアウグストII世の意のままになるということです。多分葬儀のどさくさが終わった後、ハッセが次の宮廷楽長になることが名実共に明らかになってきたのでしょう(更にバッハがロ短調ミサ曲のキリエとグローリアを献呈したのも影響しているかも知れません)
それがゼレンカにとってショックだったのは容易に想像できます。
そして11月にゼレンカは新選帝候に以下のような請願書を出しています。
というのは上記の請願書を書く前にゼレンカがマリア・ヨゼファ妃に宛てて出そうとした請願書の下書きが残されており、それと共に8つのイタリア風アリア ZWV176 が残されていたからです。
イタリアオペラ風アリアギャラント風アリアですが、これ以前にはこのタイプの作品を彼が書いた記録はありません。ある意味非常にエポックメイキングな作品です。
ゼレンカがそれを書いた理由は、彼もまたハッセのような作品を作れることを示したかったと考えるのが最も妥当でしょう。
要するにゼレンカは、ハッセが宮廷楽長になることを知って、この期に及んで慌てていたことが窺えるのです。もし彼がそれを知っていて前から準備していたのなら、もっと前の時期からそういう作風に転換しようとしているでしょう。この時期になって急にそのような物を作ったということは、やはり彼は知らなかったのではないでしょうか。
しかしながらこれは失敗作だったようです。聴いたことがないので駄作かどうかは分かりませんが、少なくともイタリア風ギャラント風音楽という意味では「違って」いたようです。
1734年早々にハッセは正式な宮廷楽長に任命されます。見事に手遅れだったわけです。
晩年
しかしはっきり言ってこれは肩書きだけでほとんど内容を伴うものではありませんでした。
というのは同じ称号を次の年(1736年)ドレスデン宮廷とはあまり関係のないライプツィッヒのカントールであるバッハももらっているし、ゼレンカの同僚の、あまり大したことのなかったブッツも同時に同じ称号を得ています。この時もう一人の同僚リストーリはドレスデンを離れていたためこのときはその称号は受けていませんが、後にやはり同じ肩書きを得ることになります(この時期リストーリはロシアに行っており、ロシアにオペラを最初に紹介した人になります)
このことは新選帝候のゼレンカに対する「仕打ち」であって、ここからゼレンカの「晩年の悲劇」が始まる―――というのですが……
ハッセ就任後の1734年はゼレンカとハッセが半々ぐらいの感じで仕事をしています。1735年には昇給も行われています。
その上、名簿上は明らかにゼレンカは「コントラバス奏者兼作曲家」でしかないのですが、この頃のドレスデンの記録には「宮廷楽長ゼレンカが……云々」といった記述も何カ所かあるのです。
この時期政治的には「ポーランド継承戦争」が始まって、新選帝候はほとんどドレスデンにはおらず、そんな細かいことに関わり合っている暇はなかったでしょう。
更に選帝候不在のおり、ハッセも1735~6年の間ドレスデンを離れています。この時期はゼレンカがドレスデンの音楽の全責任を引き受けていたのは明らかです。
しかしゼレンカはこのときはもう宮廷楽長という地位にはもはや興味がなくなっていたのかもしれません。この時期以降のゼレンカの作品の変化がそれを示唆しているように思うのですが……
最後のミサ曲
しかしそのころやっとポーランドの動乱も収まり、ハッセも復帰します。そしてこのあたりからやっと明らかにゼレンカは第一線を退き始めます。
1739年の後期ミサの傑作の一つ "Missa Votiva" ZWV18 はゼレンカが病気から回復したことを神に感謝するために作曲されたことが知られています。実際この年ゼレンカは60歳です。この当時ならいつ逝ってもおかしくない年齢です。
ハッセが来て以来ゼレンカはハッセ風の音楽を自作に取り入れるようになります。これはハッセが宮廷楽長になった後も続きます。そしてこの頃にはゼレンカはそれを自分なりに消化して自在に扱えるようになっています。
例外なくイタリア風の物で、場合によっては独唱者のカデンツァが出てきたりします。ギャラント風をゼレンカ独自に消化したスタイルになっています(と、筆者は思います)
またその長さも急に長大な物になってきます。ドレスデンの慣習ではミサ曲の長さは最大でも45分前後でしたが、1736年の "Missa Sanctissimae Trinitatis" ZWV17 は60分以上、前述の "Missa Votiva" は75分もあります。
またミサの各曲の構成も従来の「番号付き」構成から脱却しようしている様が見られます。リズムも複雑になり、また最新の音楽だけでなく、100年も前の古楽を取り入れるなど、まるでゼレンカの知っている古今東西の音楽を統合しようとしているかのようです。
確かに外面的にはかなり孤独で人々から忘れられていっているようですが、ゼレンカの内面では、やっと様々な束縛から逃れられて、自由に音楽を作れることを喜んでいたのではないかとさえ感じてしまいます。
このミサ曲は明らかに演奏することが目的なのではなく、彼の「書きたい」音楽でした。これらの「最後のミサ曲」には演奏用のパート譜が残されておらず、生前には演奏された形跡はありません。この曲はつい10~15年前までは、ゼレンカの頭の中だけに響いていた作品です。
そういう意味でこれはバッハの「ロ短調ミサ曲」や「フーガの技法」に相当する作品でもあります。
また前述の通り彼は、選帝候崩御の際のレクイエムMissa Purificationis BVM in D major. ZWV16を10日で仕上げたりもしています。
ゼレンカにとってミサ曲1曲を仕上げる期間はそんなに必要はなかったわけです。
ゼレンカは dei Filli のグローリアを書いた時点で、自分の中の気力が急速に枯渇していることに気づいたのかも知れません。そのため彼はそれを中断して最後の力を振り絞って、最終曲を作ったのではないでしょうか。
もしくはその音楽が彼が理想としていた物とは全然かけ離れていたのかもしれません。そのために彼はこれ以上書けなくなってしまったのかも知れません。
最終曲である omnium sanctorum は、一種鬼気迫る音楽ですが、曲の規模はかなり小振りになっています。これもまたゼレンカが意図していた最終形態とは異なっているような気がしてなりません。
ゼレンカの晩年の悲劇があるとすれば、単に人々から忘れ去られたといったことでなく、日が暮れてもまだ道は遙か遠いことに気づいてしまった彼自身の中にあるのかも知れません。
もちろんこれは筆者の想像です。真相は多分誰も知ることはできないでしょう。