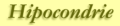ゼレンカの音楽
- ここではゼレンカの音楽に関して、私が思っていること書いてみます。言い換えれば1ファンの意見ということなので、あまり深く突っ込んではいけません(^^;
作品のカテゴリー
ゼレンカの曲は約250曲あります(実際に残されているのは150曲ぐらい)
今でも最も有名なゼレンカの作品はやはり「6つのトリオソナタ」でしょうか。しかしこのような器楽曲はゼレンカの作品のうち1割程度しかなく、残り9割以上が「カトリックの宗教音楽」です。
以下おおざっぱな表にしてみましょう。
| ミサ曲やレクイエム | 最も根幹をなすレパートリー。レクイエムは“死者のためのミサ曲”です。 |
| 聖務日課の音楽 | 詩編や哀歌などの聖書朗読につけられた音楽、及びそれに伴うレスポンソリウム、アンティフォナ、賛歌などが細々と多数あります。 |
| 各種行事のための音楽 | テ・デウムやリタニアなど。 |
| オラトリオ | 宗教的オラトリオやセレナータなど。 |
| 器楽曲 | トリオソナタ、カプリッチョ、シンフォニアなど。 |
- 詳細はゼレンカ作品リストやカトリック音楽豆知識を参照してください。
この当時の作曲家は注文されて音楽を作る職人でした。すなわち注文のない音楽を作っていても食べていけませんでした。バッハの作品がワイマール時代、ケーテン時代、ライプチヒ時代で大きく違っているのもそれが理由です。ただそのせいで広い範囲の音楽を作ったために後に評価されやすかったのも確かでしょう。
ゼレンカは後期バロックの作曲家ですが、その作品の特徴を表すキーワードを羅列してみると混合様式、半音階や変わった和声進行、そしてチェコ風味などがあげられるでしょうか。
まず最初に特筆すべき点はやはり、ゼレンカがドイツバロックの対位法音楽のエキスパートだったという点です。
ゼレンカの時代17~18世紀は情報伝達の仕組みがまだまだ未発達でした。そのため様々な文化は各地で独自に発展し、その「地域差」というのが歴然としていました。
しかし時代と共に各地域の交流も行われ始めます。そうすると文化の融合が発生して、各地の様式が混在した音楽が作られることになります。こういった様式を混合様式もしくは混合趣味と称します。
このような混合様式の作品を作った作曲家が他に誰がいるかといえば、それはまさにバッハやヘンデルです。
これはゼレンカの音楽を一度でも聴いたらまず気づく点ではないでしょうか。
ゼレンカとバッハ、そしてテレマンあたりを聴き比べてみると、バッハとテレマンは曲の雰囲気が何となく似ているのに対して、ゼレンカはやや違った雰囲気があります。
バッハやテレマンの音楽を聴いていると、当時の宮廷にぴったりという雰囲気ですが、ゼレンカの音楽はどちらかというと田舎の風景にマッチしそうな気がします。
さて、ゼレンカの音楽はドイツバロックとイタリアバロックの両者の性格を持つ混合様式(混合趣味)だということなのですが、両者がどう混じりあっているかということを説明する前に、ドイツバロックとイタリアバロックがどんなものだったかについて軽く説明しておきましょう。
まずドイツバロック音楽の特徴ですが、それはなんといってもポリフォニー(対位法音楽)だということでしょう。
それに対してイタリアバロックとは何かといえばそれはオペラでした。
まず一番簡単なやり方として考えられるのが音楽を時系列的なブロックに分けることです。すなわち音楽を小さな独立した音楽の集合体として構成して、あるブロックはドイツ式、あるブロックはイタリア式、と作るわけです。
ゼレンカの場合も同様に、ミサなどのテキストを適当に区分けしてある部分にはポリフォニックな合唱曲、別な部分にはイタリア風のアリアをつけるといった構成がほとんど全てです。
さて、こういう構成をした場合の欠点は、各曲の独自性が高くなりがちなことで、下手に作るといわゆる「ぶつ切り」になってしまいます。実際他の作曲家なども色々聴いてみると、各曲は結構いいのだけど全体を見てみると何だか構成が散漫、のような物も見受けられます。
ドイツとイタリアの融合は、曲を単に並べるだけでなく、各楽曲の内部でも行われています。
問題はこれをどうポリフォニックに処理するかです。こう考えれば結局、アリアには歌と伴奏しかないわけだから、歌のパートと伴奏のパートがポリフォニックに絡み合っていくような作りにすることになるでしょう。さらに伴奏を複数パートを持つポリフォニックな楽曲にして、歌も含めた多声部の音楽にしてもいいでしょう。
ゼレンカの場合職務として宗教曲を作らなければなりませんでした。この宗教曲の大部分をなしていたのが、典礼文や聖書などの長い文章の朗読につけられた音楽です。
この場合には短いテキストを歌い上げるアリアと違った構成が必要なのはいうまでもないと思います。イタリアオペラの場合はこの部分がレチタティーボという一種の朗唱に落ち着いていました。それはイタリアオペラがひたすらアリアを聴かせる方向に発展していって、物語を伝えるところはわりとどうでも良くなっていたからでしょう。
朗読に音楽をつける場合、ごく自然に一節単位に区切りの入ったような音楽になります。すなわち器楽パートは歌手がある一節を歌っている間は伴奏に専念して、区切りになったところで自己主張する、といった構成になるのがほぼ必然です。
そしてゼレンカのミサ曲などでは、独唱者数名に四部合唱、それに規模の大きなオーケストラがついていたりという大構成になっています。彼はその構成を全力で生かした音楽を作りました。
ちなみにゼレンカがこのような音楽を作れた背景には、彼がドレスデンの宗教音楽担当だったからだということが大きいでしょう。
以前だとここまでのような説明をしても読んでいる人はふーん? といって終わってしまいましたが、最近はYoutubeという便利な物ができてそこに優れた演奏がいくつも登録されています。その中からMissa votiva in E minor. ZWV18を紹介しましょう。
ゼレンカの場合はドレスデンの宮廷のための教会音楽を作るのが使命だったため、作品がこのような狭いカテゴリに集中する結果になっています。もし彼がケーテンの宮廷とかに雇われていたとしたら、間違いなく大量の器楽曲を作っていたに違いありません。
作品の特徴
対位法音楽のエキスパート
ゼレンカはかつてはよく「ボヘミアのバッハ」と呼ばれていました。実際その名に違わず、彼はバッハ同様に対位法に対する深い造詣があります。実際にゼレンカの作品を聴けばすぐに、どれもが高密度なポリフォニーとして構築されていることが分かります。
そしてそれだけでなく、それを心から愛していたのではないかというべき点でもバッハと共通しています。このポリフォニーへのこだわりというところがゼレンカの(そしてバッハの)音楽の魅力の根底をなすところでしょう。
イタリアバロックの影響
音楽に関してもそれは同様で、その当時の特に重要な音楽的な中心地はイタリア・ドイツ・フランスでしたが、同じ後期バロック音楽といってもこの三地域では全然性格が異なる音楽になっています。
ゼレンカは基本的にドイツの作曲家ですが、活躍したのがドレスデンの宮廷で、そこはイタリアとも交流が深く、その結果ドイツバロックとイタリアバロックの音楽様式が混在した音楽を作ることになりました。
ヘンデルはご存じの通りドイツ生まれですが、イタリアオペラの作曲家として名を上げますし、バッハもヴィヴァルディなどの楽譜を研究していたことはよく知られています。
ちなみにドイツ/イタリア混合比ですが、バッハが80%/20%、ヘンデルが30%/70%、くらいだとしたらゼレンカは60%/40%くらいなんじゃないかと思います。
特殊な和声進行や半音階の利用
CDのライナーノートなどを見ると、非慣用的な和声進行、特異なフレーズ感覚、半音階進行の多用などといったことがよく書かれていると思います。
実際に聞いてみたら、例えばこういう和声進行だから次はこうかなと思ったら全然違う和声が来たとか、フレーズがこう来たなら一段落しそうなのにまだ続いたりとか、その逆とか。さらにフーガでは大抵半音階の対旋律が出てきたりとかいったことはすぐに分かります。
そのせいもあって常に意表をつかれる音楽展開になってくるところが、ゼレンカの音楽の大きな特徴と言えるでしょう。
チェコ民族音楽の影響
そう思わせるのはその音楽の持つ、例えばタンタカタンタンタンとかいったリズム感や節回しのせいでしょうか。ゼレンカの音楽には常に「溌剌とした」雰囲気がありますが、そのルーツは出身地チェコの音楽なのではないかと思われます。
ゼレンカにはゼレンカ節とでもいいますか、知らない曲を聴いても「あ、これってゼレンカだよね?」と分かってしまうような個性がありますが、その源がこのチェコ民族音楽の要素なんじゃないかとという気がします。
特に器楽曲ではその傾向は大きく「6つのトリオソナタ」を聴けば、リズムだけでなく旋律線も民族音楽風だということは一目瞭然です。
中期・後期の作品には露骨な民族風の旋律というのはあまり出てきませんが、そのリズム感は最後までゼレンカの音楽の骨格になっています。
混合様式(混合趣味)
ドイツバロック - 対位法
ポリフォニーとは対位法を使って作曲された音楽です。すなわち複数の異なった旋律が重ね合わされてできた音楽といえます。そして旋律を重ねるのですから、各パートは基本的に対等に扱われます。
この当時の対位法には大きく分けて2種類あります。古典的対位法とバロック的対位法で、古典的対位法とはパレストリーナやジョスカン・デ・プレに代表されるような、いわゆるルネッサンス音楽のことを指します。それに対してバロック的対位法とは、バッハに代表されるものであって、両者は一目瞭然の違いがあります。
イタリアバロック - オペラ
17世紀から18世紀にかけてのイタリア音楽はオペラを中心に回っていたのです。ただここでのオペラはバロックオペラというもので、現在の19世紀のイタリアオペラとは相当に違ったものです(細かいことはバロックと古典派の章に詳しく書いてありますのでそちらを参照してください)
レチタティーボとアリア、特にダ・カーポ・アリアといわれる音楽形式は、バッハのカンタータや受難曲にも使われていますが、これは元々オペラ発祥のものだということです。
そしてオペラである以上は当然ですが歌がすべての基本になります。そこから必然的にオペラ音楽は歌とその伴奏という構造を持つということです。絶対的に優位な歌のパートとそれに付随する伴奏のパートというのが厳然と区別されるということです。
もちろんそのこと自身はモノがオペラである以上、誰も文句のつけられないところだとは思いますが。
ドイツとイタリアの音楽がこのような構造を持っているとするならば、それを統合するのは結構大変なことだということがわかります。なぜならドイツの音楽は各パートがみんな平等なのに対して、イタリア音楽ではパートの主従が完全に分かれているのです。
このジレンマをゼレンカをはじめとする当時の作曲家達はどう統合していったのでしょうか。
番号付き構成
実際これはごく普通に行われていて、例えばマタイ受難曲などを思い浮かべてもらえば、派手なポリフォニックな導入合唱、そのあとレチタティーボとかアリアが出てきて、今度はコラールが現れる、などという構成になっていますが、まさにこれがそうです。
これは当時非常に普遍的に行われていた方法で、楽曲が小さな曲の集合体みたいになることから番号つき構成などと言われています。
これがゼレンカの場合には、各ブロックでは完全終止せずに次に移行したり、短い経過句を挟んだり、同じ動機をあちらこちらで使ったり、曲の最後に冒頭の旋律を持ってきたりなど、全体的な楽曲としてバランスが取れるようにかなり気をつかっていることがうかがえます。
ポリフォニックなアリア
バロックオペラの華といえるのがアリア、すなわちソロ歌手が器楽伴奏の上で美しい歌を歌いあげるというものです。
このアリアの旋律にもいわゆるイタリア的な独特の世界があるようなのですが、これを取り入れるだけでは単にイタリアバロックのアリアを書いたことになってしまいます。
そしてこの際に注意しなければならないのが、伴奏で歌が聞こえなくなってしまわないようにすることです。すなわちポリフォニックではあるけど歌のパートが他よりは優先して作られた音楽になるわけです。
しかしそうではあってもあくまでそれはポリフォニーであって、歌だけを切り離すことはできず、各声部が調和をなすことによって初めて音楽が完成する―――こんな考え方で作られているアリアがまさにゼレンカの、そしてヘンデルやバッハのアリアといってよいでしょう。
協奏曲的声楽曲
しかし宗教曲の場合は聖書の言葉を聞いてもらうのが目的なわけですから、そこを手抜きするわけにはいきません。そのため聖書朗読を劇的に、ドラマティックに音楽化していくことになるわけです。
そこにドイツバロック的な技法を適用したとしたら、やはり歌っているときに伴奏声部と歌の声部が絡んで、器楽声部と歌の声部がどちらか一方だけでは意味をなさない渾然一体となった音楽になることになります。
ポリフォニックな管弦楽に合唱と独唱が出たり入ったり重なったり掛けあったりソロで歌ったり、もう縦横無尽に絡み合い、曲想はテキストの変化ごとに次々にめまぐるしく変わります。
こういう音楽は実はバロック器楽ではよくある合奏協奏曲(コンチェルト・グロッソ)そのままです。ゼレンカはそれを声楽つきで大規模にやってしまっているといえるでしょう。
このスタイルがある意味ゼレンカの真骨頂なのではないかと思います。
まず宗教曲の場合、特にミサ曲などのテキストは千年以上前から決まっている完全な定型文章です。すなわち聴いている人は誰でも知っているわけで、だとすると少々テキストが音楽の中に埋まってしまっても問題なかったと思われるわけです。
そして彼はドレスデンのオーケストラ、歌手、合唱団を自由に使える立場にありました。そういうわけで当時はゼレンカ以外には作りたくても作れない音楽だったのではないかと思います。多分一番近かったのが晩年のヘンデルのオラトリオ群でしょうか。
作品例:ZWV18 Missa votiva
この作品は1739年、ゼレンカの晩年に彼の病気からの回復を神に感謝するために作られたミサ曲で、彼の最高傑作の一つです。長さ一時間以上ある大曲ですが、彼の特に後期の特徴をよく表しています。
演奏しているのは Collegium1704 というチェコの古楽団体で、近年ゼレンカを精力的に紹介していて、現代風のメリハリのついた非常に水準の高い演奏をしてくれています。
この Missa votiva も番号付き構成になっていて、下の表はそれがどういった構成になっているかを示したものです。コメントには各曲が前項で説明したどういったジャンルの音楽に属するかを簡単に記しています。
| KIRIE | |
|---|---|
| Kyrie eleison I | 協奏的合唱曲 |
| Christe eleison | アリア |
| Kyrie eleison II | モノフォニックな合唱曲:Kyrie III への経過句的性格が強い。 |
| Kyrie eleison III | 協奏的合唱曲:Kyrie I の短縮版。 |
| GROLIA | |
| Gloria in excelsis deo | 協奏的合唱曲:ゼレンカの作品の中でもトップクラスの派手さを持つ作品。 |
| Graitias agimus tibi | 協奏的合唱曲:モノフォニックな合唱とソロが交替する。 |
| Qui tollis peccate mundi | アリア:ゼレンカのアリアの中でもトップクラスの美しさだと思います。 |
| Qui sedes ad dexteram patris | モノフォニックな合唱曲:次のアリアへの経過句的性格が強い。 |
| Quonism tu solus sanctus | アリア |
| Cum sancto spiritu I | モノフォニックな合唱曲:次のフーガへの経過句。 |
| Cum sancto spiritu II | フーガ:楽章の締めはほぼ大規模なフーガになっています。 |
| CREDO | |
| Credo in unum deum | 協奏的合唱曲 |
| Et incarnatus | アリア:処女懐胎のくだりにつけられた美しいアリア。 |
| Crucifixus | フーガ:受難のくだりにつけられた十字架音型に半音階進行の絡み合うフーガ。 |
| Et resurrexit | 協奏的合唱曲:復活以下のくだりにつけられた明るい曲。ところどころでふっと暗くなるのはテキスト中の死者(mortuos,mortuorum)という単語に対応したもの。 |
| et vitam ventui saeculi. Amen | フーガ。Et resurrexitのコーダといった方がいいかもしれません。 |
| SANCTUS | |
| Sanctus | モノフォニックな合唱が一転協奏的に変化します。 |
| Benedictus | アリア |
| Hosanna in excelsis | フーガ |
| AGNUS DEI | |
| Agnus dei | モノフォニックな合唱曲 |
| Dona nobis pacem | 協奏的合唱曲。Kyrie I のパロディ。ゼレンカのミサ曲の場合最後のDona nobis pacemは大抵が前にあった曲のパロディになっています。 |
その他
以下は筆者が感じているゼレンカの音楽についての印象です。
ゼレンカ作品のエンターテインメント性
ゼレンカの音楽を聞いているとめまぐるしく曲想が変わったり急にふっと転調したりと、聴き手の意表が突かれることがよくあります。彼の音楽が非常に個性的で、現代人にも受けるのは、こういった部分に負うところが大なのではないでしょうか。
言い換えるとゼレンカの音楽には、それがミサ曲などの宗教音楽であっても、聴き手を飽きさせないためのエンターテインメント性が多大に含まれていると言えるかもしれません。
ところでなぜゼレンカはそういう作風にこだわったのでしょうか?
本人に聞いてみないと分からないと言えばそれまでですが、推測ならば可能です。以下は本当に私の勝手な推測ですが……
私はこれは単にゼレンカ個人の趣味というよりは、彼の信仰及びクレメンティヌムの教育によるものではないかと思うのです。
プロテスタントの教会では会衆が賛美歌を歌いますが、カトリックのミサの場合は会衆は「聖歌隊」が歌うのを聴いているだけ、というのが通常でした。
ルターの宗教改革で賛美歌を歌うようになったのは、そういうことに対するアンチテーゼでした。しかしカトリック側もそれを傍観していたわけではなく、彼らなりに内部改革を加えていきます。クレメンティヌムを創設したのはイエズス会(ジェスイット派)で、ここはそういった「反宗教改革」の旗頭でした。
イエズス会では布教のために音楽を有効利用しています。従ってミサ曲などの音楽に対しても、新しい物が求められていたと思われます。
そこで重要になったのは「いかに聴衆を引きこむか」という点でしょう。
多分それまでのミサは、眠くなりそうな音楽をバックに、司祭様がなんだか有り難そうなことを、訳の分からない言葉で唱えているのを我慢して聞いている―――といった場所でした。
それに大胆な改革を加えて、わかりやすい言葉を使い、礼拝の形式まで変えてしまったのがルターです。これに対抗してカトリックの枠内で改革したいわけですが、カトリックである以上ミサの式次第は譲れないところでしょう。
そうしたときにミサ曲の位置づけは重要になります。ラテン語は勉強しないと分かりませんが、音楽は万国共通です。人々にミサという場で一体感を与えるためには、どういったミサ曲を作ればよいのか、ということは当時の宗教音楽作曲家の間の大きなテーマになっていたのではないでしょうか。
ゼレンカはまず間違いなく敬虔なカトリック信者でした。そのため彼にとっては、神を賛美する喜び、憐れみを乞い願う気持ち、信仰の宣言などをいかに音楽で表現すかは、仕事と言うより「使命」であったはずです。
彼の音楽に聴衆を退屈させないための様々な仕掛けが凝らされているのは、決して奇をてらっているからではなく、非常にまじめに考え抜かれた結果なのではと思います。
心に訴えかける音楽
最後に、ゼレンカの音楽は非常に感性が豊かだという、極めて当然のことを挙げておきます。
それが音楽である以上理屈ではなく、人の心を打つ何かがなければなりません。それが作曲家の感性というものです。
古今東西の「巨匠」と呼ばれる作曲家でこれのなってない人はいません。逆にこれがなければ、その時代にいくらもてはやされても、その作曲家はやがて忘れ去られる運命にあります。
ゼレンカのミサ曲を聴いてまず面食らうのは、そこに今の私たちが宗教音楽に期待するような「厳粛さ」「荘厳さ」が非常に希薄なことでしょう。代わってあるのは非常に人間くさい歌です。
これは多分ゼレンカには当然のことだったでしょう。なぜならミサのテキストを読んでみれば、それは有り難いお説教でもなんでもなく、単に「神様。私はあなたに出会えて大変嬉しいです」といった内容なのです。
この気持ちをいかに表現するか、ということがゼレンカの第一目標だったに違いありません。
そのためゼレンカのミサでは喜びを表すグローリアなどでは目一杯に盛り上げてくれますし、敬虔な祈りの部分では美しいハーモニーになりますし、キリストが十字架に付けられるような所では悲しみが炸裂します。
そしてそれが「天上の音楽」なのではなく「人間の音楽」であるところにゼレンカの真価があるように思います。