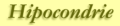バロックと古典派
えー、前回のまともな更新からずいぶんと間が空いてるようですが…もちろんその間私が惰眠を貪っていたんですが、そうなってしまったのも決して故なきことではなくて…とぐだぐだ書いても仕方ないですね。
事の起こりは、後期ミサの解説の続きを書こうかとしていたときなんですが、そうするとゼレンカの書いたアリアとかについてある程度ウンチクを垂れなければならなくてですね、ところがそのとき、お前がどれほどバロックアリアのことを知っているのかと小一時間問いつめられてしまったどうしようかと背筋が寒くなってきたわけで………
ではとりあえず他の作曲家も本気で聴いてみようとヘンデルのオペラとかを買ってきたんですよ。ちょうどアルチーナとかタメルラーノのDVDが出てたりしてですね、それに結構はまっていたりして、なにしろアルチーナおばちゃんが舞台の上ですっぽんぽん…じゃなくて、ともかくその後あちこちバロック期の他の作曲家を求めて放浪していたりして、その間ゼレンカの新録は出ないし、それで結局そのままずるずるとって感じだったわけですが、いや、どうでもいいでしょうが。
ただそういうことをしていたおかげで、前よりももっとバロック音楽の事がわからなくなってしまったので、こういう文章が書けるようになってしまったのが少々の収穫かと…
なんだかわからない方は続きを読んでみてください。
さて、そもそもの疑問は、ゼレンカというこれほどの才能を持った人がどうしてこんなに長い間忘れられていたのか? ということでした。
その理由ですが、これには以下の2つの要因があると思います。
まず重要なのはこの点です。このことはすでに本でもウェブサイトでもあちこちで言及されていますのでご存じの方も多いでしょう。18世紀にはいわゆるバロック→古典派という大きな嗜好の変化があって、バロック音楽家はほとんど全てが一旦忘れられてしまったということです。
音楽家の場合一度忘れられると復権は極めて難しい、という事実があります。
例えばバッハのフーガの技法の初演は20世紀に入ってから、ということは結構有名ですが、これはいったいどういうことでしょう?
と、古人をいじめてみてもしょうがないですね。要するに音楽の世界では百聞は一見に如かず…ではなくて百見は一聴に如かず、というのが真理だと言うことでしょう。
ゼレンカにはそれだけでなくもう少し事情がありました。彼はそもそも、その時代既にそれほどメジャーな存在ではありませんでした。
まず彼はオペラを書いていません。このことが既にマイナーの証です。
また彼の活躍したドレスデンですが、実はここはプロテスタント勢力圏でした。ザクセンがカトリックに改宗したのは1698年、アウグストI世がカトリック国であるポーランドの王を兼任する際の政治的取引のためです。すなわちカトリックとしての歴史はほとんどないと思ってもいいでしょう。ザクセンの国民はみんな相変わらずプロテスタントの教会に行っていました。カトリック教会はある意味王室のほんの一部の人たちだけのものだったのです。
また彼は弟子をほとんど取った形跡がありません。バッハが再発見された最大の理由は、実は息子達や弟子達が彼の音楽を継承していった所にあります。弟子達が実際に生きた音楽を伝承してくれたからこそ、バッハは生き残れたと言っても過言ではないでしょう。
また楽譜だけでも流布すれば違ったことがあったかもしれません。
そして最後のとどめが、彼が作ったのがカトリックの宗教音楽だったことです。
これでは覚えておけという方が無理でしょう。
…という感じでこの章は軽く締めようと思っていました。ところがそこで、ちょっとした問題が発生したのです。
というのは1の「バロック→古典派の嗜好の変化」なんですが、本当はそこでさらっとポリフォニックモノフォニック云々と説明しようと思っていたのです。ところが書く前までは「歴史的事実です、以上終わり!」って感じで気にもとめていなかったんですが、書いて行くうちに、果たしてこれで本当に良いのだろうかと急に心配になってきたのです。
さてゼレンカだけでなく、バッハやヴィヴァルディなどバロック期の音楽家全てに降りかかることになった「バロック→古典派への嗜好の変化」による忘却事件なんですが、その理由は一般的には次のようにアードルフ・シャイベ(1708~76)のバッハに対する批判が引き合いに出されることが多いようです。 この偉大な人物は、もし彼がもっと快さを身につけていて、ごてごてした入り組んだものによって曲から自然さを奪うのでなければ、また技巧の過剰によって曲の美を曇らせるのでなければ、すべての国民の感嘆の的となることだろう。
シャイベ:批判的な音楽家(1737)
またもうちょっと後のフランスのブフォン論争時にはジャン=ジャック・ルソーがこんな事を書いています。 BAROQUE: バロックな [形容詞]
バロックな音楽は旋律が複雑で、転調や不協和音を多く持つ音楽である。そして歌は堅く、自然さに欠け、抑揚はむづかしく、テンポは不自然である。この用語が論理学用語の Baroco(三段論法の変則形の一つ)から来たというのはもっともらしい。
ルソー『音楽辞典』(1767)
これらの引用は、この時代バッハやゼレンカが得意としていたポリフォニック(対位法的)な音楽が時代遅れになり、ナポリ派オペラに代表されるモノフォニック(和声的)な音楽に取って代わられつつあったことの証言だと説明されています。 なぜ、ある時代の人たちは、寄せては返す波のようなポリフォニーの音楽を好み、別の時代の人たちは快い旋律に比較的単純なハーモニーを加えた音楽を好んだのか。それは「音楽聴」が変化したからにはかならない。(中略)シャイベの批判は、そうした観点から見るなら、新しい「音楽聴」の到来を告げるものだったのである。音楽は壮麗で重厚なバロックから、規範的なものに束縛されない、より個性的な感情の流露に向かって、大きくカーヴを描きはじめる。
服部幸三:西洋音楽史「バロック」p177
実際この時代、モノフォニックなスタイルが広まっていったことは間違いありません。そしてこのモノフォニックなスタイルは新時代の音楽の大きな特徴の一つでもあります。そのためこの事実はバロックから前古典派への時代の推移を表していると考えられています。
でもちょっと待ってください。本当にそうなんでしょうか?
これが何を意味するかというと、上記の議論が正しければ少なくとも1750~1800年頃のほとんどの聴衆はポリフォニック音楽を聴くことを全く望んでいなかったのだ、ということになってしまいますが…果たして本当にそうなのでしょうか? なんだか恐ろしい極論に聞こえるんですが…
しかしこの最もポリフォニーが「嫌われた」はず時期ですが、実はポリフォニックな音楽は全然滅びていないようです。
教会音楽には相変わらずポリフォニックな楽想は頻出します。まあ教会は化石の巣窟だったから却下だと言えるかもしれません。
しかしこの時期を代表するハイドンの交響曲や弦楽四重奏などはどうでしょう。フーガ楽章が結構含まれています。
そして1829年マタイ受難曲が蘇演されると、今度はあっという間にバッハは神になってしまいました。これはどう解釈すべきなのでしょうか? マタイ受難曲を聴いたが故に人々がポリフォニーのすばらしさに目覚めたとか言うのはさすがにあり得ないでしょう。その頃既に人々はポリフォニーを受け入れる下地があったと考える方が素直です。ということは19世紀初頭ぐらいに、それまではみんなが嫌いだったポリフォニーが再び受け入れられるようになった「嗜好の変化」があったのでしょうか?
このことを無理なく説明しようと思えば結局、当時の人々が決してポリフォニックな音楽を嫌っていたわけではない、とするしかないのではないでしょうか?
もちろん当然ですが、そうすればこの時期ポリフォニックな音楽が作られていたことにも矛盾はないし、マタイ受難曲復活蘇演でバッハが一気にメジャー入りしたのも、全く不思議ではありません。
ついでにいえば、ポリフォニック音楽はモノフォニックな音楽よりより作るためには熟練が必要で、下手が作ったら実際にシャイベやルソーが言ったような結果に陥りやすいとも言えます。そのため多くの作曲家がモノフォニックな音楽の方を優先して作ったのはごく自然でもあります。
こう考えていけば、18世紀後半の人々の趣味に関しての疑問はなくなります。
もしこの議論が正しいのならば、バロック音楽家忘却事件の要因は別になければならないことになります。
さてここで、バロック音楽及びバロック音楽家がなぜ忘れ去られたのかということを議論するに当たっては、バロック音楽とは何かということをもうちょっと明らかにしておく必要があるでしょう。
まず現在バロック音楽といえば、おおざっぱに言えば大体1600~1750年ぐらいの期間に作られたヨーロッパの音楽のことを指します。
この時期の音楽は上演場所を元に分類すると、基本的に劇場音楽、室内楽、教会音楽、の3カテゴリーに分けることができます。
まず劇場音楽とは基本的にオペラやオラトリオのことだと思っていていいでしょう。オペラ劇場はベネツィアに発祥してから、数十年のうちに一挙にヨーロッパ中に広まって、どこにでもあるようになりました。
次に室内楽とは現在では小編成の器楽作品のことを指しますが、この当時はまずは室内カンタータのことで、それに加えて小編成器楽、といった感じでした。要するに貴族の屋敷で演じられる音楽や小コンサートの曲目と言うことです。
そして教会音楽は礼拝に使用される音楽です。カトリックとプロテスタントでは当然内容が異なっており、プロテスタントではバッハの作品に見られるような宗教カンタータ、受難曲、コラールなどから構成されており、カトリックではミサ曲や聖務日課用の音楽からなります。
ここでまず重要なポイントは、当時はまず音楽といえば声楽が主だったということです。上記の3分類は演奏会場による分類ですが、まず劇場ではオペラやオラトリオなどは演じられても、器楽コンサートは行われませんでした。もちろんオペラの序曲などは器楽だけで演奏されましたが、これは開演ベルの代わりでした。
室内楽の分野でのみ、17世紀後半ごろから純粋な器楽が演奏されるようになっていきますが、これも多くはBGM扱いで、本気で耳が傾けられたのは室内カンタータの方でしょう。
古典派は器楽の時代、バロックは声楽の時代とよく言いますが、当時は間違いなく音楽といえば声楽のことだったのです。
さて、バロック時代は声楽が非常に重視された時期でしたが、その中でも最も人々に愛されて影響力の大きかったジャンルと言えばオペラに他なりません。
そういう意味でバロック音楽を最も良く代表するジャンルはオペラということになるのです。
さて、通常の音楽ジャンルについては、いつ誕生したかということはほとんど分からないのが普通です。しかしことオペラに関してはそのジャンルが生まれたのがいつかはかなりはっきりしています。
このオペラを発明した人たちがフィレンツェのジョバンニ・デ・バルディ伯爵(1534-1612)をリーダーとするカメラータ・フィオレンティアーナという名のグループでした。
このカメラータでは古代ギリシャ悲劇の復興を目指して研究していました。彼らはそこで古代ギリシャの演劇はすべて歌われることで演じられたと考えました。それは実は誤解だったのですがそれはともかく、彼らはそれを「再現」したと考えた「音楽劇」を創り出しました。これが後に言うオペラになるのです。
記録に残る最初の作品は1598年頃ヤーコポ・ペーリ(1561-1633)によって作曲された「ダフネ」ですが、これは一部しか残されていません。全体が残された作品は1600年に同じペーリによって創られた「エウリディーチェ」です。
この作品は当時の人に相当のインパクトを与えたようです。この上演を見たと言われている人の中にマントヴァの公爵ゴンザーガI世がいました。彼はマントヴァに戻ると自分の宮廷音楽家に自分の所でもそういう作品を作るように命じました。
この音楽劇において重要な点は、結果的に言うと彼らがレシタティーヴォという音楽形式を編み出したと言うことでしょう。
これは多声音楽で対位法を使うからこその制限です。従って単声で歌えばその限りではありません。そのためにこの当時、モノディ形式というスタイルができあがりつつありました。すなわち、後に通奏低音と呼ばれるようになった低声の伴奏の上に、単声の旋律を重ねる方法です。
そういったわけで、まさに彼らにとっては歌詞の表現こそがその目的であり、最優先事項でした。 音楽とはまず言葉とリズムであり、楽音自体は最後にある物、その逆ではあり得ない
とあります。
さてこうして生まれたオペラですが、最初の数十年はそこまで一気に広まることはありませんでした。オペラが本当にメジャーな存在になったのは、1637年ヴェネツィアに新サン・カッシアーノ劇場ができたことによります。更に1639年にはサンティ・ジョバンニ・エ・パオロ劇場、1640年にはサン・モイゼ劇場ができます。
これ以降ヴェネツィアはオペラの中心地となり、ヴェネツィアでオペラを作った音楽家をヴェネツィア派と呼びます。
初期の作曲家で最も重要なのはモンテヴェルディです。彼はもう70歳を過ぎていましたが、ここで傑作「ウリッセの帰還」「ポッペアの戴冠」を作りました。
モンテヴェルディの後継者として重要なのがピエートロ・フランチェスコ・カヴァッリ(1602-76)で、「ジャゾーネ」「セルセ」「カリスト」といった作品を残しました。また、ピエートロ・アントーニオ・チェスティ(1623-69)も重要な作曲家で「オロンテーア」やウィーンで上演された「金のリンゴ」などが有名です。
その他ヴェネツィア派として有名な作曲家はピエトロ・アンドレーア・ジアーニ(1616-84)、甥のマルカントーニオ・ジアーニ(1653c-1715)、アントーニオ・サルトーリオ(1630-80)、ジョバンニ・レグレンツィ(1626-90)、カルロ・パッラヴィツィーノ(1640c-88)、カルロ・フランチェスコ・ポッラローロ(1653c-1723)、トマーゾ・アルビノーニ(1671-1751)、アントーニオ・ヴィヴァルディ(1678-1741)などが挙げられます。
ヴェネツィア派と一括りにしていても、作風は当然時代と共に変わります。
現在でも良く演奏されるいわゆる「イタリアオペラ」では、当然のように物語はレシタティーヴォによって進行し、ここぞというところでアリアが始まる、いわゆる番号付き構成になっています。それに対してワグナーが楽劇という概念を出して云々というのはよく知られている話です。
ここでカヴァッリの作品を聴いてみると、最初から最後まで一貫して音楽が流れていて、その構成から見ると実はワグナーの楽劇の方に似ていたりします。カヴァッリの作品でも感が極まったところではかなり音楽的になりますが、また完全に分離されているわけではありません。
しかしこのスタイルはやがて廃れていって、レシタティーヴォとアリアが明確に分かれていく方向に変化していきます。
こうしてヴェネツィア派によってオペラの基礎が築かれました。しかしヴェネツィアは18世紀に入るとやや凋落します。
元々ナポリには優れた音楽学校があり、音楽の盛んなところでした。そこではフランチェスコ・プロヴェンツァーレ(1626c-1704)などが活躍していました。
スカルラッティはバロックオペラのスタイルを集大成した人として重要です。後にオペラ・セリアと呼ばれるジャンルの確立に非常に重要な役割を果たしました。
ナポリ派の頃になるとその影響力はヨーロッパ全域に及びます。そしてイタリア以外の地域でもナポリ派の影響を受けた作曲家が多数現れます。
このナポリ派の人たちの音楽の特徴として真っ先に上げられるのが、ホモフォニックでシンプルなスタイルでしょう。
このホモフォニックなスタイルが生み出された背景には、当時は作曲家よりも歌手のほうが遙かに力が上であったということが大いに関わっていると思われます。
ここで歌手がアリアを即興変奏する場合、もし伴奏が対位法的に作られていたら、瞬時に伴奏の動きとマッチする変奏を作らなければならないわけで、非常にやりにくいことになります。失敗したら変な不協和音になってしまうかもしれません。しかしこれが単なる和音連打であれば、和声が違っていなければ不協和になることはありません。
ナポリ派でホモフォニックな音楽が作られていったのは、こんな経緯ではないかと思うのですが…という理由はともかく、この音楽スタイルが新しいスタイルとして当時の人たちに受け入れられいったのは事実です。
音楽に限らずどういった分野でも、あるスタイルが生まれて発展したら、次にはマンネリ化して形骸化するのは世の常です。
オペラの誕生時には、オペラはあくまで音楽劇で、最初から最後までレシタティーヴォによって物語と音楽が進行しました。しかし音楽性の強いところが人気があったので、説明的な部分はレシタティーヴォ、登場人物がその感情を吐露する場面ではアリア、といったように音楽的な分業が進行していきます。
以下の引用は1732年、後の有名な劇作家カルロ・ゴルドーニ(1707-93)が駆け出しの頃に自作のオペラ・セリアの台本を見せたときに受けた「忠告」の一部です。 …オペラの三人の主役には、それぞれに五曲ずつのアリアを歌わせねばなりません。第一幕に二曲、第二幕に二曲、第三幕に一曲です。第二女性歌手や第二カストラートは三曲だけ歌わせてもらえるけれど、それ以外の歌手は一曲かせいぜい二曲で我慢せねばなりません。台本作者は作曲家に、音楽の明暗をなす三つの異なる声部を提供しなければなりません。荘重なアリアが二曲続かないように気を配ることも必要です。同様に注意を払って台本作者は、ブラヴーラ・アリア、劇的アリア、半ば荘重なアリア、メヌエット、ロンドを適切に配分せねばなりません。なによりも大事なのは、脇役たちの口に、たとえば情熱的なアリアやロンドなどが行かないようにすることです…
フーベルト・オルトンケンバー「心ならずも天使にされ」より
これを読めばどういったことになっていたかは明白でしょう。当時のオペラもはやカメラータの人たちが理想とした「音楽劇」なのではなく、文字通りに「仮装衣装付コンサート」と化していたのです。そういった意味では、当初の姿からほとんど180度反対側に来てしまっていたと言ってもいいかもしれません。
これはこれで現在の我々にとっては見物だとは思いますが、当時の人たちにとってはもううんざりだったようです。
これまでのオペラは主に神話劇や歴史上の人物を扱った堅い話が主流でした。しかし18世紀に入ると当世の登場人物による軽妙な物語を題材にした物が増えてきます。そしてやがて前者のいわゆる伝統的なオペラ・セリアに対して、オペラ・ブッファと呼ばれるようになります。
喜歌劇そのものは17世紀からありましたが、これが流行りだしたのはペルゴレーシの奥様女中のヒットからでしょうか。これはオペラ・セリアの幕間に挟まれたインテルメッゾという40分ぐらいの小話ですが、これがヨーロッパ中を巻き込んだ大ヒットになります。
それから喜歌劇がたくさんられ始めますが、その中でも有名なのが前述の台本家ゴルドーニとバルダッサーレ・ガルッピ(1706-85)のコンビです。
当時の作曲家は大抵オペラ・ブッファもセリアも両方書きました。そのため前述のナポリ派の音楽家は多かれ少なかれ、オペラ・ブッファを書いています。特にパイジエッロ、チマローザはこっちの方で有名です。
これまでは主にイタリアのことについて書いてきましたが、もちろんそれ以外の地域でもオペラは発展していきました。特に地方の場合は現地の音楽とイタリアの影響が融合して独特な物になっていると言います。
しかしその辺まで突っ込んでいるといつまでたっても終わらないし、そもそもここで音楽史を延々書くつもりもないので今回はカットします。
さて、現在バロック音楽というと、バッハとかヴィヴァルディの協奏曲や器楽作品に作品に代表されるような、さわやかな感じの室内楽っていうイメージが結構あります。
もちろんルネッサンス以前の時期から器楽曲は存在していましたが、まずはオルガンやリュートなどの独奏曲が主で、本格的な器楽合奏が始まったのは17世紀も後半になってからでした。
ルネッサンス期にも器楽合奏が行われなかった訳ではないようです。しかしこの時期は声楽で使われる譜面を楽器で弾いてみました、といった感じで、器楽と声楽の区別はあまりありませんでした。
現在の器楽合奏、すなわち「オーケストラ」の基礎を固めた、イタリアのボローニャにいた人々でした。
そのころドイツではいわゆるバロック組曲形式が形成されつつありました。
この二つの伝統を融合して、金字塔とも言える作品を創ったのが、アルカンジェロ・コレッリ(1653-1713)でした。
さて、合奏音楽とは別に、オルガンやチェンバロなどのいわゆる鍵盤音楽も、この時期に大きな発展を遂げました。
フレスコバルディと同時期に、フランドル地方で著名だったのがジャン・ピーターソン・スウェーリンク(1562-1621)です。彼はファンタジアといった形式の元祖で、多くの後継者に恵まれました。
そしてこの北ドイツと南ドイツのラインの交点に、バッハやヘンデルがいます。
さて、バロック音楽の第3のジャンルになる宗教音楽ですが、これは他のジャンルと違ってまず第一に礼拝という儀式で使用されることを前提に書かれた物です。そのため宗派によって書かれる音楽ががらっと変わります。
まずローマカトリックにおいては、ミサではミサ曲、晩課に使用される音楽としては各種詩編、マニフィカト、テ・デウム、リタニアなどの曲種が生まれました。
しかしバロック期になって、その音楽の内容はがらりと変わります。
ただ基本的に宗教音楽は保守的でした。モンテヴェルディ本人も、ミサ曲に関しては第一作法すなわち伝統的なパレストリーナのスタイルで作っています。
この辺の所から、バロック期のミサ曲は旧態依然としたパレストリーナの亜流音楽が作られ続けていた、とまでいう人もいますが、これはとんでもない間違いです。
確かに教皇のお膝元であるローマでは音楽に関して比較的保守的だったのは事実です。
それ以外の都市ではもっとそれは顕著になります。
またナポリ派が活躍する時代のナポリではまずアレッサンドロ・スカルラッティがオペラの他にたくさんの宗教曲を書いています。またレオナルド・レオ(1694-1744)、フランチェスコ・ドゥランテ(1684-1755)なども活動しています。特にドゥランテはオペラは書かずほとんど宗教曲と器楽曲だけ書いていましたが、注目すべき人でしょう。
そしてもっと離れたウィーンではヨハン・ヨーゼフ・フックス(1660-1741)やアントニオ・カルダーラがいました。フックスはオペラも書きましたが、やはり宗教音楽の権威として名を馳せていました。
この辺の作曲家の作品になると、混合様式として知られるように、古風な合唱曲や新式のオペラアリア風歌曲、協奏曲様式など当時知られていたあらゆるスタイルを自由自在に駆使した作品になります。
カトリックでもプロテスタントでもイースター前の受難節には、まあ当然ですが、オペラのような派手な見せ物は禁止されていました。しかしオペラというのは当時の人々にとっては人生最大の娯楽でした。当然受難週でも何かそういった物は見たいわけです。そしてその代わりとなる物として受難オラトリオが発展していきます。
このオラトリオという音楽形式そのものは、ほとんどオペラと同じような物です。ストーリーのある台本があって、それにオペラのように音楽を付けていった物です。
この形式は最初ジョバンニ・フランチェスコ・アネーリオ(1567c-1630)によって開拓されましたが、それを完成させたのはなんといってもローマのジャコモ・カリッシミ(1605-74)でしょう。
というわけで、バロック期のミサ曲に代表されるカトリック宗教音楽も、みんなバロック的な当時における「最新」の作品であり、パレストリーナの亜流ではありません。
実際驚くべきことに、これらの曲は紹介されていないというよりは、そもそも研究さえされていないのでどんな曲があるか、どんな作曲家がいるのかさえよく分からない、というのが現実のようです。
その理由はいろいろあるでしょうが…まあ音楽学者などになろうという酔狂な人は滅多にいないので間違いなく人手が足りない上、金とも縁がないので、だとしたら少しでも金になりそうなバッハ研究などに走るのは仕方なく、そうすればプロテスタントだし、大体カトリックだとラテン語とかを勉強しなきゃならないのでますます人気薄…といった感じで後回しにされてるってところでしょうか。
ともかくイタリアに限らず各地の大聖堂には17~18世紀の音楽の手稿譜が大量に未整理のままに眠っているそうです。
プロテスタントの場合、バッハ研究の関連でカトリックより遙かに研究は進んでいます。
プロテスタントの場合、これがまた宗派によって異なりますが、音楽を積極的に振興したのはルター派でした。
これらの音楽は前述の北ドイツオルガン系の人々は大抵手がけていると思っていいでしょう。こういった音楽にオルガン伴奏を付けるのが彼らの最大の職務であったからです。
プロテスタントでは受難週には受難曲が演奏されていました。これは最初は聖書の受難に関する部分を朗唱する物でした。
しかし時がたつにつれて受難曲ももっとドラマチックな要素を高めていき、後には宗教オラトリオと変わらない物になっていきます。
さてここまで延々とバロック音楽史を書いてきたりしたわけですが、どうでしょう?
さて、音楽の教科書などをを見てみると、ルネッサンス期にはジョスカン・デ・プレ、バード、ラッスス、タリス、パレストリーナ…といったかなり知名度の高い作曲家がかなりの数います。ところがそれよりも後世の17世紀には、なぜかその数が落ち込んでいるように見えないでしょうか?
もちろん17世紀に作曲家の数が落ち込んでいるわけではなく、その大多数がオペラや宗教音楽を手がけていて、そのジャンルの紹介が致命的に遅れているために、17世紀の作曲家が少ないように見えるというのが真相です。
そして注目すべきことは、器楽的な作品はかなり紹介が進んでいることです。このあたりは器楽も声楽も書いた作曲家、例えばヴィヴァルディなどを思い浮かべれば、明白でしょう。
それにしてもどうしてこんなにバロック時代の声楽は紹介が遅れているのでしょうか?
オペラであればある程度言い訳は思いつきます。例えばバロックオペラはド派手な演出が必要なので上演に金と手間暇がかかるとか、カストラートの声部をどうするかとか、歌唱法がよく分からないとかです。
しかしオペラがだめでもカンタータがあります。これは音楽的にはオペラとほぼ同様な物です。それに多くは歌手一人とチェンバロ1台あれば演奏可能で、長さも比較的短くバロック声楽の紹介用とすればある意味最適でしょう。
そう考えると本当に困るのは歌唱法だけのようです。この時代の音楽は楽譜はほとんど骨格だけで、音楽的な肉付けは歌手に大幅に依存していました。その当時の歌唱法の伝統は、バロック音楽忘却の過程で大部分が失われてしまいました。
また前述のオペラにしても、実は現代の普通のオペラに比べれて上演は楽なのです。
というわけで実はバロック声楽作品を演奏できない技術的な理由は全くないのです。
技術的な障害がないとすればあとは作品がつまらないから、という理由しかありえませんが…
しかしバロックオペラやカンタータはすさまじい数が残されています。例えばアレッサンドロ・スカルラッティ一人で100曲近いオペラと数百曲以上のカンタータを残したと言われています。その他の作曲家も含めればもう膨大な数でしょう。
すなわちバロックオペラやカンタータの全てが駄作だと言うことはあり得ないわけで、それにも関わらずどうしてここまで紹介されてこなかったのかが、重大な問題となるわけです。
それを明らかにするためには、実物を検討してみるのが早道です。
さて、バロック声楽で最も特徴的なのがレシタティーヴォとそれに続くアリアです。合唱曲はルネッサンスの遺産を引きずっているのでここではふさわしくありません。
で、そのサンプルですがここではヘンデルのメサイアから38aのアリアの前半部を引用しました。[→譜例を開く]
このアリアは以下の2節の歌詞のみからなる小さなアリアで、この直後からあのハレルヤコーラスが始まります。
さてこの曲ですがどうでしょうか。聴いてみると小ぶりですがなかなか良い曲です。しかし聴き終わった後に簡単に口ずさめるでしょうか? 多分かなり慣れた方でないと結構難しいのではないでしょうか?
実は他のバロックアリアでもいろいろと聴いてみると、結構こういう状況に出会います。聴いてみたら結構いいんだが、後から思い出してみようとするとどうもうまくいかない。で、印象が薄かったのかと思ってもう一度聴いてみると、やっぱりいいけどまた後からだと…というループにはまるのです(少なくとも私はですが)
その理由の一つは譜面を見て頂くと分かります。
また今度は旋律そのものをよく見てみます。普通私たちがよく聴く音楽では、旋律というのは2小節程度の動機があって、それの模倣パターンになっていることが多いのですが、このアリアではそういうパターンを抽出するのはかなり困難です。
それにしてもどうしてこんな曲の作り方をしているのでしょうか?
その理由は別段難しいことではありません。
このアリアはの歌詞は二つの節よりなりますが、見れば詩句の長さが異なっています。従ってそれにそのまま曲を付ければ、曲のフレーズの長さも必然的に変わってくるわけです。
またこの理念では、音楽は歌詞のイントネーション、アクセント、リズムによって規定されることになります。従って歌詞が変われば旋律も変わるのが当然です。
もしこれだけだと音楽的には非常に散漫な物になってしまいそうですが、伴奏部を見てもらえば、どうやってここに音楽的統一感が与えられているかがよく分かります。
と、こうやって見てみると、バロック声楽を評価する際に旋律だけを分析したのでははっきり言って片手落ちになってしまうことが分かるでしょう。
だから上記の例の場合は英語をネイティブに理解できる人であれば、それほど困らないに違いありません。歌詞を聞いていればどこで切れるかは明白だからです。そして優れた作品であればあるほど、歌詞の響きや意味、情感などが実に自然に表現されている物になっているはずです。
しかし英語が分からない人は音楽的構造を頼りに聴くしかなく、そういった構造が元々ない以上、その音楽は散漫で印象の薄い物になってしまうわけです。
このようにバロック時代は、音楽よりも言葉の方が優先される時代でした。
例えばモーツァルトでも誰でもいいですが、適当に知っている独唱物の声楽作品を思い浮かべてください。大抵の場合何を歌っているか分からなくても、それなりに楽しめるはずです。
その理由は古典派以降の声楽ではその音楽そのものに「構造」があるためです。
しかしこのように音楽に構造があるということは、実は歌詞の表現はそれだけ制限されていることも意味します。なぜなら歌詞には意味があり、各単語にもそれに付随する情感があります。また単語の読みには個々にイントネーションやアクセントがあり、その結果歌詞にはそれなりの響きという物が生まれてきます。
バロック時代はこの響きこそが音楽を作る上の基礎でした。しかしこれを厳密に守れば前述のバロック声楽になってしまって、音楽の構造は損なわれます。
例えて言えば、バロック声楽では歌詞が骨で音楽が肉と言うぐらいに一体化しているのに対し、古典派声楽ではは歌詞は着ている服で体が音楽ぐらいの関係だと言えるでしょうか。そして中には余計な服などいらん! と言うような人さえいたりします。
ここまで読んでもらえば、バロック声楽は現在の私たちが一般的にイメージしている声楽とは相当かけ離れた物で、多分吟詠の方に近い物だと言うことがわかるでしょう。
だとすれば、今まで漠然と言ってきた「バロック的なるもの」と「古典的なるもの」の最大の相違点とはこの「声楽における歌詞の扱い」と考えることができるのではないでしょうか。すなわちこう言えるのではないでしょうか? 声楽で「言葉>音楽」とするか「音楽>言葉」とするかの意識の違いこそが、バロックと古典派の違いの本質である。
もちろんこれは今のところ仮定ですが、現在この点以上に両者を区別するポイントは見あたりません。そこでこれからこういう仮定をおいた場合、様々な問題がどう解釈できるかを見ていきましょう。
ますこう仮定すれば、元々の問題であったバロック音楽家忘却事件が解決できます。
バロックの時代のオペラはほとんどイタリアの都市でのみ作られていました。またオペラの聴衆は現地でこそ一般市民も入っていましたが、それ以外の地域では基本的には王侯貴族の娯楽でした。またオペラを愛するような王侯貴族は当然高い教養も持っていました。
しかし18世紀も後半になると、聴衆として非イタリアの一般市民達が台頭してきます。音楽の中心はイタリアからドイツに移り、聴衆はヨーロッパ全土、さらには世界中に広まっていきます。当然彼らは普通イタリア語など理解できません。それどころか自国語の読み書きでさえ怪しい人も多かったでしょう。そういった人達は当然高尚な詩などにも興味はないわけです。
このことよりバロック音楽家忘却事件、すなわちバロックから古典派への趣味の移行という現象は以下のようなプロセスだったと説明できます。
18世紀初頭に器楽音楽が発展した時代に最初の端を発します。この時期はまだ声楽中心で、器楽もまだ声楽の影響を強く受けています。これが世紀中頃になると器楽が更に発展し、器楽の影響を受けた声楽、すなわち古典派風の声楽も増えてきますが、まだ従来の声楽もオペラ・セリアとして勢力を持っていました。しかし18世紀末にはついに器楽が声楽を完全に浸食して移行が完了します。
というわけで、これに関しては片が付いたわけですが、当然従来の説とは異なった前提に立っているため、新たな問題がいくつか発生します。
まず器楽の問題です。もしバロックと古典派の違いが歌詞の扱いだとすると、そもそも歌詞のない器楽はいったいどう考えればいいのでしょうか?
結論から言えば、今回の仮定の上では器楽とは本質的に非バロック的な存在だと言うことです。なぜなら歌詞が存在しない以上、音楽的な構造を元に楽曲を構築せざるを得ないからです。
もちろん時代による音楽スタイルの違いは十分にあります。楽曲形式の変遷やポリフォニックとモノフォニック、通奏低音の使用、楽器の進歩、などといった今までバロックと古典派を分けていた要素は厳然と存在します。しかしこの違いは、バロックと古典派の声楽における相違点に比べて遙かに小さいし、厳密な線引きも難しいということが言えます。
初期の器楽の場合、バロックオペラとかなり密接な関係がありました。最初にできた形式の一つに協奏曲形式がありますが、これは前述の通りにオペラアリアの構造から派生したと言われています。
当時の文献を見ると、例えばマッテゾンの旋律論では最初に「歌う旋律」と「弾く旋律」が明確に区別されています。これは当然声楽の旋律と器楽の旋律のことですが、ここから当時の人はこの両者をはっきりと区別して考えていたことが分かります。また「声楽旋律はいわば母であり、器楽旋律はその娘である」とあるように、まず基本は声楽の旋律であったと考えられていたことが分かります。
次にこの仮定を導入すると、そもそも今までのバロック/前古典派/古典派といった区分を変える必要が出てきます。というのは従来バロックと古典派を区分していた最大の指標は通奏低音の使用ですが、ここではもうそれは「細かい」話だからです。
まず第一次的に注目しなければならない点が「バロック声楽」と「器楽」の区分です。
この視点を導入すると、17~18世紀の音楽スタイルは以下の4つに分類ができることになります。
ここで作品としたのは、同じ作曲家が声楽と器楽を書くこともあるからです。そのいい例がヘンデルやヴィヴァルディです。
(1) バロック声楽+旧式技法 --- バロックスタイル
この分類では元祖バロック派に関しては、従来の前期・中期バロックが対応していると考えていいです。
2番目の「古典的バロックスタイル」は、これは私が入手できた比較的少ないCDからの結論ですが、それほど間違っていないと思います。
第3の「バロック的古典スタイル」は逆に作曲スタイルは古いやり方ですが、音楽性の面から見ると逆に古典派に近いグループになります。
第4の古典スタイルはいわゆる古典派です。ウィーン古典派はもちろんですが、ここでは前古典派で器楽をメインに書いた人も同様に含まれます。
そしてこの分類において、バロック声楽に分類される作曲家がすべて現在では忘れ去られているとこういうわけなのです。
ところで当サイトのメイン作曲家ゼレンカはどこに含まれるかというと、バッハと同じバロック的古典スタイルに入るでしょう。彼の後期ミサのグローリアなどに見られるあのド派手な協奏的合唱曲は声楽的ではあり得ないですし、また作品全体の音楽的な構成に注意して作っているところなどは考え方が古典的だと言えます。
こういう視点に立った場合、例のシャイベのバッハ批判の解釈はずいぶんと変わることになります。
それから後のフランスのブフォン論争でも同様です。
今までバロック音楽と呼ばれていたジャンルの紹介が非常に偏っていることは明らかです。しかしとりあえずその代表者と考えられていたバッハに関しては、十分に紹介されてきました。大抵の作品に関してはより取り見取りで、何を買っていいのか迷うほどです。
このことを如実に示すのは、同様に知名度の高いヘンデルやヴィヴァルディの扱いです。
この扱いの違いはいったいどういうことでしょうか? ヴィヴァルディのオペラは全て箸にも棒にもかからない駄作で、演奏する価値もないのでしょうか?
その答えは現在の価値観で判断する限りはその通りなのです。ヴィヴァルディのオペラは現在の価値観から見ればほとんど無価値な存在なのです。もし評価したとすれば、旋律的には評価できる部分もあるが、音楽的構成力が全く無く散漫で退屈、といった感じになるでしょうか。
結局、本当のバロック音楽家は未だに忘却されたままなのです。
それではバロック声楽の復権の可能性はどの程度あるでしょうか?
しかし同時に、歌詞の対訳を付けてもらわないと話になりません。対訳首っ引きというのは結構疲れるので、可能なことならばDVDの字幕付がよりベターでしょうか。
また対訳の際には個々の単語の意味が分かるようにしてほしい物です。というのはバロック声楽では歌詞に音楽が依存するので、各単語ごとに曲想が変わることなどごく当たり前だからです。そのとき単語の意味が分からないとなぜ音楽がこんな変化をしたか理解できません。
このあたりさえしっかりしておけば、決してバロック声楽が復権できないわけではないと思います。ただどの作曲家が本当に復権できるかは、本人の実力次第でしょうが…
元はといえばゼレンカのアリアが当時の基準ではどの程度の物だったのかを調べようとしたのが発端でした。それからいろいろ調べていくうちに本末転倒してこういった大げさなことになってしまったわけですが、いかがだったでしょうか。
この議論に関しては当然非常に粗っぽい物です。本当はもっとたくさんの資料を基に検証すべき問題です。そこは私が学者でも何でもなく1音楽ファンだからと逃げておきますが…もちろんご意見・ご感想があればメールとかでどうぞ。
ゼレンカはなぜ忘れられたか?
世の中には嚢中の錐ということわざもあります。もし本当に実力があるのであれば、こんなに何百年もお蔵入りにはならずに、もっと早く知られていたのでは? とも言えるわけで、そうならなかったことに関しては、やはりある程度納得いく説明が欲しいところです。
1 18世紀に起こった嗜好の変化
これはゼレンカだけの話ではなく、当時の作曲家全てに関係したことでした。ヘンデルのメサイアのような僅かな例外を除いて、バロック期の音楽は一時ほとんど聴かれない時代が続いたというのです。
あの大バッハでさえそれは免れ得ず、1829年のメンデルスゾーンのマタイ受難曲蘇演で復活した、というのは有名な話です。今ではバッハ以上の人気を誇るかもしれないヴィヴァルディなどは20世紀になってからの発掘です。
音楽とは音の芸術です。それをそのまま記録できるようになったのは20世紀からです。それ以前の音楽は楽譜だけがその頼りになります。
しかしちゃんとした楽譜があっても、それを見ただけで「ああ、これはすばらしい音楽だ!」と判断できる人は、やっぱりほとんどいないでしょう。特にゼレンカの場合その特質は複雑な対位法にありますから、ますます困難なことになるでしょう。
この作品は4つの声部しかなく、構造は簡単な部類です。また楽譜その物もずっと前に出版されていましたので、バッハを研究したり演奏したりしていた人は間違いなく目を通していたはずでしょう。
しかし19世紀の人々はこれを演奏する必要がないと判断したわけです。これはいったいどうしてでしょうか?
2 ゼレンカがドレスデンのカトリック教会専属の音楽家であったこと
この当時は人々に認められる作曲家=オペラ作曲家でした。バッハもライプツィヒのカントール職を得る際に、まさにそれが理由で二流呼ばわりされています。
すなわち彼の作品を聴いた人は実はほとんどいなかったのです。
しかしゼレンカにはそういった人々がいませんでした。
彼の死後ピセンデルがテレマンに打診して、レスポンソリウムを出版しようとしました。もしこれが実現していたら、もう少し違った展開があったかもしれません。しかしこれは結局楽譜の貸し出しができなかったため没になりました。
ゼレンカの時代に彼の作品で出版された物は、多分テレマンの「忠実なる音楽の師」に収録された「14の転回を持つカノン」だけのようです。
カトリック豆知識の方でも触れましたが、19世紀にはカトリック内部でセシリア運動という運動が起こりました。これは華美な宗教音楽の使用を戒めて、パレストリーナスタイルやグレゴリオ聖歌のスタイルにまで戻そうという運動でした。その運動の是非はともかくとして、ゼレンカの音楽はカトリックの宗教音楽が最も派手だった時期の物です。
ゼレンカの音楽は実際の使用という方面からも復活する目がなくなってしまったのです。
だからゼレンカがバッハやヴィヴァルディよりもずいぶん遅れたとは言っても、こうしてかなりの作品がリバイバルしているということ自体が、錐が袋を突き破っていることの証明とも言えるでしょう。
いったい何が心配になったかというと、詳しくは次章以降になりますが、ともかくここから「そもそもバロック音楽とは何か」みたいな話になっていってしまうのです…
バロック音楽家忘却事件
つまりその当時人々の嗜好がポリフォニックなスタイルからモノフォニックなスタイルへと変わっていったため、旧世代のバロック音楽家は忘れ去られていったと言うことになります。
ちょっと突っ込んで考えてみると、実はこれが結構大変なことだということが分かります。なぜならここで一世を風靡した一つの音楽ジャンルが消滅したことを意味しているからです。
音楽ジャンルが存在するということは、それが好きな人がいるということです。好きな人がいればそれを供給する人もいるでしょう。逆に言えば、ある音楽ジャンルが滅びるということは、それを望む聴衆が誰一人いなくなったということを意味します。
モーツァルトの音楽にもポリフォニックな部分はたくさんあります。モツレクのキリエのフーガなんかは、歴史上の全フーガの中でもトップクラスでしょう。モーツァルトの手紙の中にはバッハ(親子共々)のフーガに夢中だとか、コンスタンツェがフーガを作ってくれとおねだりしたとかいった記述もあります。
モーツァルトだけなら真の音楽家であるが故に云々と言えますが、コンスタンツェまでフーガ好きとなると、これはどういうことでしょう? 彼女の趣味はよっぽど偏っていたのでしょうか?
またベートーベンがバッハの平均率にハマっていたことも有名で、バッハは小川ではなく大河だと言ってみたり、作品の中にもちょっと探せばポリフォニックな楽想はいくらでも見つけられます。
大体考えてみれば、モノフォニックなスタイルとポリフォニックなスタイルは対立概念でもなんでもなく、表現手段がちょっと異なっているいるだけです。
そして音楽に限らずあらゆる分野で新しいスタイルが出て受け入れられる場合、一時的に古いスタイルを覆い隠す勢いで広まることがよくあります。しかしその熱が冷めたら古いスタイルと新しいスタイルは共存していたり融合していたりとか言う話は枚挙にいとまがないでしょう。
しかしこれで終わりというわけにはいきません。なぜならここではそもそも「バロック音楽家忘却事件」の原因を探っていました。その理由としてポリフォニック・モノフォニック云々を検討していたわけですが、いまここでそれを全く否定してしまったわけです。
今出た結論は、バロック音楽家はポリフォニー音楽を作っていたから忘れられたわけではない、ということなのですから。
それではいったいそれは何だったのでしょうか?
ということでこれから簡単に音楽史の復習をしてみましょう。
バロック音楽のジャンル
1600年と言えば、初めてのオペラが上演された年で、1750年と言えばバッハの没した年です、なんてことがよく言われますが、理由はともかくそういうことにしておきます。
室内カンタータとは出張してきたオペラ歌手がパトロンのところで歌った小規模のオペラみたいな音楽と思えばいいでしょうか。
それに対して器楽は基本的には例えばテレマンの「食卓の音楽」というタイトルでも分かるように、BGM的な扱いをされていたようです。器楽が重要なレパートリーになるのは、おおむね18世紀以降のことになります。
また教会ではもともと音楽は礼拝に付随する物なので、全部器楽ということはあり得ません。ただ「教会ソナタ」の名があるように、礼拝の所々に器楽だけの音楽が挿入されることはありましたが、普通は声楽曲が演奏されていました。
さてこの後は、各音楽ジャンルに関してもう少し詳しくまとめてみましょう。
バロックオペラ
またこの時期のオペラは、他のジャンルに対する影響も非常に大きな物があります。後でもう少し詳述しますが、オラトリオや教会カンタータ、バッハの受難曲にしても基本的な音楽形式はオペラから派生しています。また協奏曲のリトルネロ形式はオペラのアリアから、交響曲はオペラの序曲からと、器楽曲に対しても大きな影響を与えています。
オペラの誕生
これはオペラというのが自然発生した音楽ジャンルではなく、ある特定の人たちによって発明されたジャンルだからです。
このグループのメンバーには、ガリレオ・ガリレイの父親ヴィンチェンツォ・ガリレーイ(1520年代後半-1591)も含まれていました。
この時そこで働いていたのがクラウディオ・モンテヴェルディ(1567-1643)で、1606年ににできあがった作品があの「オルフェオ」です。
この当時の音楽はパレストリーナなどのミサ曲などに代表されるように、多声部の合唱曲が主流でした。しかしこのスタイルは歌詞のダイナミズムを表現するには今ひとつ不向きだと考えられていました。また音楽の技巧に走りすぎて、歌詞をないがしろにしているとの批判にもさらされていました。
それはある意味正しい指摘でした。実際に多声音楽を作ろうと思った場合、この当時は当然古典対位法によるしかなかったわけですが、それ故にいろいろなところで歌詞の流れを犠牲にせざるを得ませんでした。
そしてこのモノディ形式で物語を歌うように語っていく音楽劇というのが、カメラータの面々が新しく創り出した形式でした。
ペーリのエウリディーチェの出版譜の序文には
この考えこそがバロック期のオペラ及びその影響を受けた音楽を理解する上でのキーとなる概念だと言えます。
ヴェネツィア派
初期の頃はカメラータの提唱した理想通り「音楽劇」という形で幕は進行していきました。しかし時と共にいわゆるレシタティーヴォとアリアの分離が発生してくるのです。
逆にレシタティーヴォの部分でも後のように枯れておらず、非常に音楽的表情豊かです。
次世代のチェスティの頃にはその分離はかなり明確になっていたといいます。そして更にその次の世代では、番号付構成がほぼできあがっているようです。またアリアでもダ・カーポ形式が現れてきます。
代わってオペラの中心地となったのがナポリです。
ナポリ派
しかしナポリがその重要度を増したのは何と言っても1684年アレッサンドロ・スカルラッティ(1660-1725)が王室礼拝堂楽長になって以降でしょう。彼は鍵盤楽器で有名なドメニコ・スカルラッティの父親です。
そしてここから後にナポリ派と呼ばれる次のような人々が現れてきます。
ニコーラ・アントーニオ・ポルポラ(1686-1768)、レオナルド・ヴィンチ(1696c-1730)、ジョバンニ・バッティスタ・ペルゴレーシ(1710-36)、ニッコロ・ヨンメッリ(1714-74)、トンマーゾ・トラエッタ(1727-79)、ヨハン・アードルフ・ハッセ(1699-1783)、アントーニオ・マリーア・サッキーニ(1730-86)、ニッコロ・ピッチンニ(1728c-1800)、ジョバンニ・パイジエッロ(1740-1816)、ドメーニコ・チマローザ(1749-1801)。
ジュゼッペ・サルティ(1729-1801)、ヨハン・クリスチャン・バッハ(1735-82)、フランチェスコ・ガスパリーニ(1661-1727)、ジョバンニ・ポルタ(1675c-1755)、アントーニオ・カルダーラ(1670c-1736)、フランチェスコ・バルトロメーオ・コンティ(1681-1732)、ジョバンニ・バッティスタ・ペシェッティ(1704c-66)、ジョバンニ・ボノンチーニ(1670-1747)、アッティーリオ・アリオスティ(1666-1729)、ゲオルグ・フリードリッヒ・ヘンデル(1685-1759)。
例えばバッハの何かの曲のアリアを思い浮かべてみてください。その伴奏部の動きは大抵旋律と対位法的に動いているのが分かると思います。しかしナポリ派の作品のアリアの場合、いわゆる和音連打の和声的な伴奏が目に付きます。
シャイベがバッハを批判した際に頭にあったのは、こういったナポリ派のシンプルさでしょう。
当時の一流オペラ歌手は、その人気においても報酬においても作曲家より遙かに上を行っていました。また当時アリアを歌う際には、歌手が独自に即興変奏を加えることが当然でした。そもそもなぜダ・カーポアリアなどという物が生まれたかというと、歌手に好き勝手やらせるために他なりません。
もし当時の歌手が舞台で「与えられた楽譜に忠実に」歌ったとしたら、それはもう作曲者に対する悪質な嫌がらせだったに違いありません。
歌手は当然歌いやすい音楽を要求するでしょう。その際に作曲家がより凝った伴奏を付けたくとも、歌手の要求の方が勝ってしまうわけです。その上シンプルな伴奏はそれはそれなりの美しさを持っています。
バロックオペラの形骸化
それはバロックオペラも例外ではありませんでした。
ナポリ派の時代にはそのスタイルが完成します。と同時にそのころにはそういった作り方をするのが「規則」になっていきます。
そしてその流れの中から生まれてきたのがグルックのオペラ改革だったのですが…その辺のことを詳しく書いてると本論からはずれてしまうので(正確には面倒なんで…)今回は省略します(^^;
喜歌劇
そしてこれらの喜歌劇の伝統はそのままモーツァルトにつながっていきます。
その他の地域
ということでリュリやラモーのフランスオペラ、ハンブルグのカイザーやテレマン、ベルリンのグラウン、ロンドンのヘンデル…といった興味深い人々がいっぱいいますが、いつかまた別な機会でということで。
器楽の発展
しかし前章にも書いたとおり、バロック期(1600-1750)においては、純粋な器楽作品というのはどちらかというと日陰の存在でした。
しかし18世紀に入ると器楽曲の地位は向上し、大きな進歩を遂げていくことになります。
ここでは器楽合奏及びオルガン音楽に関して簡単に解説します。
合奏音楽
器楽がある程度声楽と独立した存在として認められたのはバロック期になってからで、バロック初期のジョバンニ・ガブリエリのカンツォーナはそのハシリのようです。しかしこれもまだまだ未分化で、器楽編成も適当なものでした。
ここにいたマウリッツィオ・カッツァーティ(1620c-77)、ジョバンニ・バティスタ・ヴィターリ(1632-92)、ジョバンニ・レグレンツィ(1626-90)などが、現在いうところのトリオソナタや教会ソナタの形式を創り出しました。
ボローニャでは更にドメニコ・ガブリエリ(1651-91)、ジュゼッペ・トレッリ(1658-1709)、 ジャコモ・アントニオ・ペルティ(1661-1756)といった人達が続き、ボローニャ楽派と呼ばれることになります。
これはバッハの管弦楽組曲などに見られる、プレリュードの後に舞曲が何曲か続く形式です。これを創り出した人達は、パウル・ポイエル(1570-1625以降)、ヨハン・ヘルマン・シャイン(1587-1630)、そしてヨハン・ローゼンミュラー(1619c-84)といった人達でした。
彼の作品は出版され、ヨーロッパ中に強い影響を与えました。その作品op.1~6が現在でもしばしば演奏されています。
彼の影響を受けた人にピエトロ・アントニオ・ロカテッリ(1695-1764)やフランチェスコ・ジェミニアーニ(1687-1762)やアルビノーニがいますが、なんといっても有名なのはアントニオ・ヴィヴァルディ(1678-1741)でしょう。
そしてさらにその後にバッハ、ヘンデル、テレマンといった人達が続くわけですが、このあたりに関してこれ以上説明する必要はないでしょう
鍵盤音楽
鍵盤音楽に関しては、イタリアよりもドイツの方が重要な働きをしています。
イタリアでも初期には、ジローラモ・フレスコバルディ(1583-1643)がいました。彼はトッカータとフーガというオルガン音楽の形式の原型を作り、一つの伝統となります。
しかし彼の後を継いだのは、ミケランジェロ・ロッシ(1601/2-56)、ヨハン・ヤーコプ・フローベルガー(1616-67)、ヨハン・カスパー・ケルル(1627-93)といった南ドイツの音楽家達でした。
ヤーコプ・プレトリウス(1586-1651)を始め、中部ドイツ地方ではサミュエル・シャイト(1587-1654)、ハインリッヒ・バッハ(1615-92)、ヨハン・クリストフ・バッハ(1642-1703)、ヨハン・ミヒャエル・バッハ(1648-94)、ヨハン・パッヘルベル(1653-1706)、ヨハン・クーナウ(1660-1722)などがいます。
また北ドイツ地方ではハインリッヒ・シャイデマン(1595c-1663)、フランツ・トゥンダー(1614-67)、マティアス・ヴェックマン(1619c-74)、ヨハン・アダム・ラインケン(1623-1722)、ディートリッヒ・ブクステフーデ(1637-1707)、ヴィンセント・リューベック(1654-1740)、ゲオルグ・ベーム(1661-1733)、ニコラウス・ブルーンス(1665-97)など、そうそうたるメンバーがいます。
バッハはよくバロックを集大成したといわれますが、実際に彼は今まで出てきた合奏音楽の伝統とオルガン音楽の伝統を共に受け継いで、それらを完成させた人でもあります。
宗教音楽
カトリック宗教音楽
このあたりはルネッサンス以前からの伝統と特に変わるわけではありません。
そのエポックメイキングとなったのが、モンテヴェルディの聖母マリアの晩課でしょう。これは当時最新の形式、すなわち本人のいうところの第二作法で書かれた作品です。
しかし既にグレゴリオ・アレーグリ(1582-1652)やオラツィオ・ヴェネーヴォリ(1605-72)の作品を聴けば、それをパレストリーナスタイルと言うわけにはいかないのは明白です。
アレーグリやヴェネーボリは、派手な器楽伴奏などはそれほどつきませんが、大聖堂の空間的特性を利用した、元祖5.1chステレオとでも言うべき、コンチェルタート様式の使い手でした。
例えばヴェネツィア派のオペラ作曲家は、たいていの場合同時に宗教音楽も作っていました。そのため宗教音楽といえどもオペラなどの音楽の影響を免れることはできませんでした。
例えばオペラ作曲家カヴァッリの作ったミサ・コンチェルタータ(1757)などは、きわめて雄弁なバロック的傑作です。
そして後のアントニオ・ロッティ(1667-1740c)などもヴェネツィアの人です。彼は間違いなくゼレンカに大きな影響を与えていますが、そのオーケストラによるきらびやかな響きは、まごうことなくバロック音楽そのものでしょう。
ヴィヴァルディもまたかなりの数の宗教曲を作っています。それは真摯でありながら、同時に彼独特の旋律美に満ちた、すばらしい音楽となっています。
もちろんその他のオペラ作曲家も、多かれ少なかれ宗教曲を書いているようです。
そしてここでは説明するまでもなく、ドレスデンにはゼレンカやハイニヒェンがいました。
ゼレンカの後期作品はまさにこの究極のバロック音楽とも言うべき作品でしょう。同時にバッハのロ短調ミサ曲はこのような伝統なくしては決して生まれることはなかったでしょう。
オラトリオ
ただ舞台で演技をしないこと、その代わりに合唱がもっと重要な役割を果たしているところが違います。合唱が演技や舞台装置の代わりになっていたと考えてもいいでしょう。
彼に完成されたオラトリオは、アレッサンドロ・ストラデッラ(1644-82)、アントニオ・ドラーギ(1634/35-1700)、マルク・アントニエ・シャルパンティエ(1645/50-1704)などの手によってヨーロッパ各地に広がっていきます。
そしてバッハやヘンデルなどが作ったレシタティーヴォとアリア、それから合唱からなる教会カンタータや受難曲は、形式的にはオラトリオそのものと言えます。
知られざる教会音楽作品
しかしそういった誤解が生まれる背景には、実はこの時期の音楽の紹介がとてつもなく遅れているという事実があるでしょう。
このため、ゼレンカのようにちょっと田舎で宗教音楽専門でやっていた人は、ほとんど陽の目が当たっていない可能性は極めて大でしょう。
ともかく今後は本気でがんばってほしいところです。
プロテスタント教会音楽
ルター派では礼拝の形式はかなりカトリックに近い物があって、ミサ曲のキリエとグローリア部分はそのまま使用されます。しかしルター派では会衆が礼拝に直接参加するところがカトリックとは異なっており、そのために誰でも簡単に歌えるようにした聖歌である「コラール」が発展しました。
同様にドイツ語の宗教カンタータも礼拝に導入されます。これの形式はほとんど宗教オラトリオの形式そのままです。
ハインリッヒ・シュッツ(1585-1672)の受難曲はそういった形式の傑作です。
そういった受難曲を作った人にハンブルグオペラの総帥であったラインハルト・カイザー(1674-1739)がいて、彼の作品がバッハやヘンデルに大きく影響を与えています。
こうやって記録に残っている作曲家はかなりたくさんいるのに、なぜかその紹介はさっぱり進んでいないことに気づかれるのではないでしょうか? また、紹介されている物もジャンルにかなり偏りがあることも分かるのではないでしょうか?
このあたり前々から疑問には思っていたのですが、今回調べてみてそれに対する自分なりの結論が出てきたんで、こういった長文を書いていたりするわけです。
それがこの章となります。
忘れられたバロック声楽
器楽系の作品であれば日本でもかなりCDなどを入手できます。それに対してオペラやカンタータの紹介は、ほとんど壊滅的といっていいでしょう。本来ならばバロック音楽史上極めて重要な役割を果たしているはずなのにです。
またカストラート用がだめでも、普通のソプラノ用も大量にあります。それにカストラートだからといって全員がファリネッリのように3オクターブの声域があったわけではなく、ちょっとがんばれば普通のソプラノやカウンターテナーで歌える物が大部分だと言います。
しかし文献が全くないわけではなく、それに100%再現できなくてもやってみることに意義はあるでしょう。それに作曲家は歌手に音楽を半分委任しているわけですから、歌手がどう歌おうと自由でもあるのです。従ってある程度現代風なやり方で再構築してしまっても、それが完全な間違いだとはいえません。
なぜならバロックオペラには合唱はほとんど使われず、歌手も4名程度です。オーケストラの規模も現在の室内楽程度です。演出に関しては完全な再現にこだわらなければいいだけで、そもそも現在のオペラファンは変な演出には慣れてますから、誰も文句は言わないでしょう…実際ヘンデルのアルチーナの演出なんかは相当キてます。
それにもかかわらずこれらの音楽は今に至るまで、なぜか演奏されてきませんでした。
某所でよく言われる経験則にスタージョンの法則というのがあります。これは元々「SF小説の90%クズである」という物でしたが、一般化して「あらゆる物の90%はクズである」ということになります。これは裏を返すと10%ぐらいはまともな物があるという意味にもなります。
要するに膨大な数の作品があれば、その中には必ず優れた作品も混じっていると言うことです。
声楽と器楽
レシタティーヴォに関しては後期になればなるほど形骸化していきますので、ここではアリアが最も良い対象になるでしょう。
Thou shalt break them with a rod of iron; 汝は鉄の杖で彼らを打ち、 thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. 陶工が器を壊すように砕くであろう。
これはいったいどうしてでしょうか?
まずこの曲は前奏が9小節です。次に "Thou shalt ... with a rod of iron" のフレーズは6小節(休符まで入れれば7小節)、"thou shalt ... like a potter's vessel." のフレーズは5小節、それから同じ節が別旋律でカデンツァ風のフレーズを経て9小節…となっています。
これを見てすぐ気付くように、各フレーズの長さがまちまちです。これがまずわかりにくさの原因の一つとなっています。
そしてそれが原因で旋律の流れのパターンが非常に掴みにくく、結果として曲が覚えにくいということにつながっていきます。
前章のオペラの歴史の所に書きましたが、バロック音楽では「音楽とはまず言葉とリズムであり、楽音自体は最後にある物」なのです。そしてヘンデルはこの理念そのままに音楽を作っているからです。
この曲の旋律パターンが掴みにくかった理由は、元々そういうパターンを意識して作られた旋律ではなかったからです。
譜を見てみると似た旋律が使われているところは、"Thou shalt *** them" といった同じような歌詞の場所で、それ以外ではないことが分かるでしょう。
伴奏はある意味「音楽的」に特定のフレーズの模倣が繰り返されます。また前奏にあった2種類の音型を対位法的に絡めたり、曲の切れ目ごとに前奏風の伴奏を再現してフレーズの切れ目をよく強調しています。
曲の切れ目ごとに再現される特徴的な伴奏部をリトルネルロといいますが、協奏曲形式=リトルネルロ形式はこういったアリアの作り方から派生したとも言われています。
バロック声楽は基本前提として、聴衆が歌詞を聞いて理解できるという前提の元に成り立っています。従ってバロック声楽を鑑賞する際に最も注目すべき点はその歌詞と音楽の関係であって、音楽そのものの流れや構造は二の次なのです。
その上、音楽の流れが原語に依存しているため、別な言語に翻訳してしまうと、意味をなさなくなってしまいます。例えばイタリア語の「あも~れ♪」という旋律を英語で「ら~~ぶ♪」と歌ってしまったら、相当に間が抜けて聞こえるはずです。これが日本語だったら文法からして違うので全く意味不明な代物になってしまうでしょう。
それに対して古典派以降になるとそれが逆転しています。
音楽的な構造とは、まず通常4小節単位の規則的なフレージングです。そして例えば複合二部形式は A A' B A' という言い方をするように、異なったフレーズの間に反復や模倣などといった関連性があることです。
古典派以降はソナタ形式などに代表される「**形式」というのが大量に増えますが、これらはすべて音楽を内在する構造で分類した物です。この構造は言葉とは無関係に、音の連なりによってのみ構築される秩序です。
それ故に、古典派以降の声楽ではその音楽を理解する上で歌詞の意味を理解することは必ずしも必須ではなく、音楽的な感性さえあれば世界中の誰もが同じようにその音楽を鑑賞できるわけです。
バロック期の作曲家でも彼らの書いた器楽を同時に見てみれば、彼らが音楽の構造を知らなかった訳ではないことはよく分かります。
しかしバロック的な作曲家は、歌詞の流れと音楽の流れの不一致が発生した場合は、歌詞を優先して音楽の構造を犠牲にします。逆に古典派以降の作曲家は歌詞の方を犠牲にして、音楽の構造の方を優先しているわけです。
バロックと古典派の違いの本質
音楽を作る上で言葉が先か音楽が先かというのはもはや180度異なったアプローチです。すなわち声楽曲に関してはバロック時代と古典派時代ではもはや本質的に異なっているのです。
バロック音楽家忘却事件円満解決
従ってバロックオペラの聴衆はみな全てイタリア語を十分理解することができたわけで、その作品の鑑賞に何の障害もなかったわけです。
その結果彼らは当然の行動として、彼らにもよく分かる音楽を選択しました。そうやって選択されたのが器楽を基礎とする古典派風の音楽なのです。これならば別に難しい歌詞を理解せずとも、誰でもが聴いて楽しめる音楽だったからです。
このあたりはロンドンでヘンデルのイタリアオペラが乞食オペラにしてやられた現象を思い起こせば明らかでしょう。
バロック器楽など存在しない?
従って器楽においてはバロックと古典派で、最も本質的な所に違いはないということが言えます。
そこでこれらの相違点をここでは「旧式技法」と「新式技法」と呼ぶことにします。
しかしこれはある意味見せかけだけの類似と言っていいでしょう。なぜならバロック時代にはまだ歌詞抜きで長い音楽を聴かせられるだけの構成法が知られていませんでした。だから手近に良い手本がなかったからそれを使ったわけです。
その後器楽はどんどん発展を遂げて、もはや歌詞に依存しなくても十分に長い楽曲を構築できるようになります。音楽の構成もオペラなどから離れて最終的にはソナタ形式のような形式を生み出していきます。
予備知識無しでこれを見たら多分ぴんとは来ないでしょう。しかしこうやってバロック声楽の検討をした後では、彼らがこれを区別したことはほとんど自明にも思えます。
新しい作品区分
そして従来の区分、すなわち対位法や通奏低音を利用する「旧式技法」と和声的な作法を特徴とする「新式技法」による区分は、副次的な物となります。
今まではバロック→古典派という変遷に関しては、この作曲技法の変遷こそ最も重要な役割を占めていると説明されていたわけですが、ここではそれはあまり重要な点ではないことになるわけです。
ヴェネツィア派などのオペラ作曲家、ヘンデル
(2) バロック声楽+新式技法 --- 古典的バロックスタイル
ナポリ派などのオペラ作曲家
(3) 器楽+旧式技法 --- バロック的古典スタイル
バッハ、ラモー、ゼレンカ、その他バロック時代の器楽
(4) 器楽+新式技法 --- 古典スタイル
いわゆる古典派、マンハイム楽派とか
しかしそれ以外はかなり変わっています。
例えばハッセの晩年の作品では、オペラアリアの伴奏はモーツァルトと聞き間違えるか、というぐらいスタイルが似ていますが、アリアの歌詞の扱い方は紛れもなくヘンデルと同様の歌詞主体の作法を示しています。
このグループは通常前古典派として扱われることが多いのですが、実は古典派とは本質的に異なるグループと考えた方がいいということになります。また彼らは器楽を書くこともありますが、その際にはどうしても声楽を書くときの癖が抜けず、わかりにくいフレーズ書く傾向があるようです。現在の聴衆に彼らが受け入れられにくい理由はその辺にあるのかもしれません。
ここの代表選手がバッハと言えます。バッハの音楽の作り方が声楽であっても器楽的だということは、今までの説明を見てもらえば分かると思います。また彼の最後の作品がフーガの技法という究極の純粋音楽であるというのも印象的です。
バッハはあの当時としてはある意味異端の存在であったとも言えます。
ただバッハほどは徹底しておらず、そのアリアに関してはかなりバロックスタイルの影響を受けていて、フレージングなどを見れば前述のヘンデルのアリア同様の特徴があります。しかしメロディーラインはかなり器楽的な特徴を備えているようです。
シャイベの批判の評価
一般的には進歩派のシャイベが時代遅れのバッハを批判したという解釈が為されているわけですが、シャイベが擁護した音楽はナポリ派の音楽でした。彼らの音楽は技法こそ新式でしたが、音楽に対する考え方そのものは、非常に保守的だったと言えます。
それに対してバッハの音楽は技法こそ旧式でしたが、音楽に対する考え方は非常に新しかったわけです。特にバッハは声楽に対しても「器楽的な旋律」で作曲しています。バッハの時代にはそれで声楽を作るのは珍妙なことだった訳ですが、それから100年後にはあらゆる旋律が「器楽的な旋律」になってしまったのです。結果としてバッハは時代をうんと先取りしていた作曲家と言えることになります。
この点に注目すればシャイベの批判は、実は遙かに新しかったバッハの音楽を理解できなかった古い評論家による批判であったと解釈できるわけです。
ここで著名な哲学者のルソーとラモーが論争しますが、ここの争点も実は同様で、古い声楽の理想にこだわっているルソーが和声学の基礎をまとめたラモーを理解できずに食ってかかっているという構図になっています。
バロック復権未だ来たらず
しかしこの論の仮定を認めれば、もはやバッハをバロック音楽の代表者と考えるのには無理があることになります。バッハはその音楽が非バロック的であったからこそ、後世の人々に簡単に受け入れられたとも言えるでしょう
彼らの器楽作品は十分に紹介されています。しかしそれ以外のオラトリオやオペラはどうでしょうか? ヘンデルのメサイアを唯一の例外とすれば、最近はCDだけなら何とか入手はできますが、演奏を選ぶようなことはまず無理です。1種類だけでも手に入ればラッキーといった状況です。
そしてヴィヴァルディに至っては、彼も何十曲ものオペラを書いたはずですが、CDさえほとんど手に入らない状況です。
これを再評価するには、現在の音楽にとは異なった価値観で評価する必要がありますが、まだそれは全然普及していません。
まずバロック声楽はこういう物だから、歌詞と音楽をちゃんと聞き比べてくれ、という啓蒙が必要になります。まあこれは一言書いておけば問題はないでしょう。
逆にそのあたりが見え出すと、当時の人達が実は極めて緻密な作業をしていることが分かり始めて来ます。
おわりに
参考文献