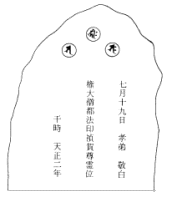国見山(霜野山)の麓の山岳密教寺院 文字サイズ:
この石碑は、「干時(時に)天正二年甲戌」とあるので、1574年7月19日、弟子が建てた、康平寺の院主であった禎賀(ていが)法印のための墓石であることがわかる。
|
|
この霜野地区では、この石碑を「ミースさん」と言って、「歯の神さま」と敬ってきた。
「ミースさん」とは、農作業に使う箕(み)のような形から、そう呼んだものである。 大正元年(1912)生まれの私の父も、子どもの頃、虫歯が痛むと、祖母に連れられお参りしたという。 その際、年の数だけ大豆を煎ってお供えし、「後で戴いて噛むと痛みがとれる」と祖母は語っていたそうだ。 心なしか、父は痛みがとれた気がしたそうである。 ところで、この石碑は、「鍋田石」のとても大きなもので、これだけの扁平な大きな石を、山鹿市鍋田から霜野まで運ぶのは、大変なことである。 |