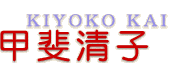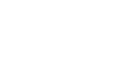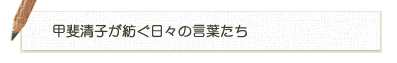2014.9.26 晴れた秋の日に・・・
※ 写真をクリックすると大きな画像をご覧いただけます。 5月に更新して以来、実に4か月ぶりのコラム。キーボード操作が、腰に及ぼす負担はことのほか大きく、何をするにも文字通り腰が肉体の要であることを痛感させられている。季節は夏を飛び越えて、9月も終わろうとしていた。 5月に更新して以来、実に4か月ぶりのコラム。キーボード操作が、腰に及ぼす負担はことのほか大きく、何をするにも文字通り腰が肉体の要であることを痛感させられている。季節は夏を飛び越えて、9月も終わろうとしていた。私は9月生まれ。あろうことか時の内閣総理大臣と同じ誕生日と知って愕然とし、ムンクの「叫び」の図、ヤレヤレ。 嬉しいのは、昔のバンド仲間Y君(宮崎市でピアノバーを経営している)が歳も誕生日も同じで、幾つになっても誕生日となると必ず思い出してくれるようで、たいていあちらからおめでとうメールが入り、「お互いじじばばになったなあ」「いやーまだまだ、我々にはアートがあるから大丈夫」などと空元気で励まし合っている。 そんな9月も押し迫った。 10年くらい前までは9月の声をきくと、空気や風などに秋の気配がそこはかとなく漂い、どこかメランコリックな寂しさをたたえたこの月が好きだった。しかし最近では、残暑がいつまでも続き、夏から秋への季節の移ろいを味わうどころではない。昨年などは10月の体育の日、秋川渓谷での芋煮会に参加したとき、まるで真夏の焼けつくような炎天下で汗だくになって芋煮を食べたことを忘れない。 今年気象情報で頻繁に聞かれるようになった「猛烈な」という言葉は特に耳に残っている。「猛暑」、「豪雨」では間に合わない気象の表現手段として「猛烈な」という形容詞が出現し、これが新しい気象用語となったのか、それとも「猛烈な」という気象表現は昔からあったのか、、、ワンセンテンスの中で何度も何度も「猛烈な・・・」が繰り返されていた。 しかし今年の秋は様子が違っていて、「猛烈な暑さ」や「猛烈な雨」が日本列島に膨大な災害をもたらしながら9月に入ると、早々に本格的な秋が訪れた。「四季の国」といわれる日本なのに、「春」と「秋」が不在となってしまって久しいここ数年だが、今年はあのころのような本格的な「秋」が戻ってきている。  さて昨年大晦日に激しいぎっくり腰に見舞われた後、今年の3月には骨粗鬆症による圧迫骨折を発症し、長期治療を余儀なくされた私のその後の経過です。 さて昨年大晦日に激しいぎっくり腰に見舞われた後、今年の3月には骨粗鬆症による圧迫骨折を発症し、長期治療を余儀なくされた私のその後の経過です。整形外科であつらえたオリジナルのロングハードコルセット装着開始から、そして週に一度の骨生成注射「テリボン」がスタートしてから6か月が経とうとしている。 「薄皮を剥ぐように」快復へ向かう、ということを口にしていた。あのころは快復への希望的観測を漠然と抱いていた。しかし「薄皮を剥ぐように」とは実はどういうことをいうのだろうと最近思う。わずかずつでも、一ミリでも快方へ向かうことを意味するのだろうが、その速度が問題で、あくまでもこれは個人差によることだ。 確かに現在では、腰の痛みを和らげる麻酔注射と、痛み止めの投薬はなくなったし、週に1度の骨生成のための皮下注射「テリボン」が、来年10月まで延々と続くだけにはなった。コルセットはロングから短めのものを入手した。6か月も装着が続けばそろそろ外してもよさそうな時期だと思うけれど、私の場合コルセットとステッキは外出時にはいまだに外せそうもない。これも個人差である。まあ、長い目で振り返ると、これも「薄皮を剥いで」いるといえるのかもしれないとは思う。しかし問題は、なかなか解消されない腰の「だる重い痛み」だ。長きにわたる闘病で擦り減ってしまった腰の筋力が、上半身を充分に支えるだけの力として取り戻せていないのだ。体力、筋力が疲弊してしまっていることを痛感する。やはりこれは長丁場になりそうだな・・・と実はこの頃覚悟を新たにしている。 私の病状はこのような具合だが、10月には恒例の「デッサン教室展」が28回目を迎え、またその2週間前には、町田「新芽会」のデッサン展・第6回が目前に迫ってきた。(2つの展覧会の詳細はイベントの予告をごご覧ください) 闘病が始まってしばらくの間、当然教室へ出かけられない私だったが、神楽坂のクラスは生徒全員の熱意により実習はただの一度も休むことなく指導者不在のまま自主的に行われた。特に1時間前に教室を開錠するという作業を毎回続けてくれたOさん、Mさん、そして事務局のTさんには只々感謝である。また、指導者のいない実習の現場にもかかわらず、いつもと変わりなく通い続け、モデルのポーズ決めやタイマー操作などを全員の協力により継続することができた。現在でも、私は少し遅れて教室に入る。夜まで続く長丁場のため、できるだけぎりぎりで教室に入らせてもらっている。 また、町田も、長距離の電車移動のため数か月は指導者不在のまま、会員だけの自主制作となった。ここへきて、町田へはなんとか付き添いつきで出かけているが、こちらもスタッフの皆さんの尽力により、無事展覧会開催にこぎつけることができて胸をなでおろしている。 そんなわけで、今年の秋の二つの展覧会は、おそらく一味も二味も違う感慨深いイベントになることだろう。 |
||
|
2014.3.31 春来れども
※ 写真をクリックすると大きな画像をご覧いただけます。 3月に入り、長引いている腰痛にぶり返しの痛みが発症し、再レントゲンとMRI検査で、圧迫骨折が判明。初めのレントゲンにはなかった症状だった。圧迫骨折は3月に入ってからのものらしい。骨密度も低くなっているので、新たな治療が始まった。ハードコルセットは新たに採寸して4月初旬から装着が始まる。加えて週に1度の注射は1年半に及ぶ「テリボン治療」。なんとも気の長い話である。まさか途中から骨折が発症とは思いもせず、ただの腰痛にしては長引くなと思っていたが、検査結果をみて、ようやく納得した次第。
 この間、「谷口モミエ展 第1回」が無事終了した。(イベント報告参照)
この間、「谷口モミエ展 第1回」が無事終了した。(イベント報告参照)季節は急に桜の季節となり、世の中はにわかに春めいてきたが、私の日常はご覧のとおり、気の長い治療のスタートである。 桜はマンションのベランダで、日光浴をしながら満開を眺める。私にとって今年はこの程度のささやかな桜である。 そんな中、見事な「フリージア」が届いた。次々に新しいつぼみを開いてくれるこんな立派なフリージアも珍しく毎日花に元気づけられている春です。 |
||
2014.2月 大雪の洗礼
※ 写真をクリックすると大きな画像をご覧いただけます。
|
|||||
|
2014.2.4 年頭報告、ああ、ぎっくり腰!! ※ 写真をクリックすると大きな画像をご覧いただけます。 暮れも押し迫り田舎へ帰郷中の出来事。
母の隠居に家族が集合して食事をしながらにぎやかに年を越すというのが我が家の年中行事となっている。普段は母一人の住まいのところへ本宅から弟の一家が押し掛けてくるわけで、大きな食卓を仏間から茶の間に運び込むのもいつもの作業だが、昨年秋から左肩を痛めて体調万全でないにも関わらず、その大テーブルを移動しようとして、弟嫁と二人で持ち上げた途端、ギクッと音まで聞こえるほどの衝撃が腰に走った。これが悲劇の始まりである。途端にその場で動けなくなったが、家族みんなの手前もあり、湿布を貼りなんとかその場を凌いだ。 除夜の鐘が聞こえ「ゆく年くる年」の時間になるころから激痛が増し、翌元旦は一日寝たきり。悲劇は帰りの飛行機が2日ということ。もし延期しても7日まで満席の状態。これは這ってでもなんとか帰京しなければならないと意を決した。弟の見送りのおかげで熊本空港までたどり着き、痛みをこらえながら1時間半のフライトに耐え、2日夜帰京を果たした。今思えばあれはただただ気力だけの信じられないパワーだった。 その後ぎっくり腰を体験した人にしかわからない独特の痛みが続き、4日にようやく砂町診療所に行く。レントゲンでは圧迫骨折は免れたものの症状は重く、未だに通院、ブロック注射、投薬が続いている。 この間、神楽坂教室を休み自主制作にしたり、新百合ヶ丘のデッサン指導をお断りしたりと、散々な年明けとなり、教室の皆さんにも大変な迷惑と心配をかけてしまった。 あの日からもうひと月が経ち、いまだに冷湿布、温め、杖歩行、コルセット装着・・・と、あらゆる処方で努力しているが、低温やけどを発症して治療が中断するハプニングがあったりして、症状は一進一退を繰り返しながら、わずかずつ薄皮を剥ぐように快方に向かっているのか、今回だけは敵もしつこくなかなか楽にしてくれない。 安静が一番の薬とは誰も言う最短の治療法だが、ここまで時間が経つと寝てばかりではかえって筋肉の衰えに拍車をかける。コルセットも適当にはずして、体の調子をうかがいながらの毎日が続いている。 さて、そんなわけで新年の報告をもう一つ。昨年から不具合ばかり続いたパソコンをリニューアルするのに年を越してしまいました。このコラムが新しくなったPCからの第一信です。 イベントで今年の主な展覧会のお知らせを記載しましたが、3月の谷口モミエ展が迫っています。その準備はすでに始動しておりこれからいよいよあわただしくなります。 |
||