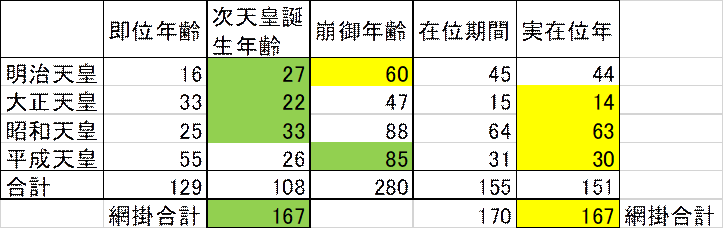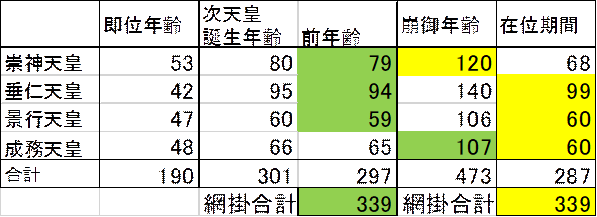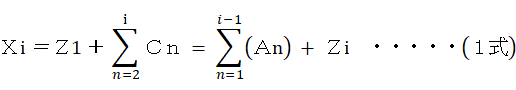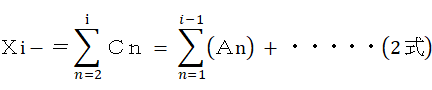|
天武天皇の年齢研究 -目次- -拡大編- -メモ(資料編)- -本の紹介-詳細はクリック 2018年に第三段 「神武天皇の年齢研究」 2015年専門誌に投稿 『歴史研究』4月号 2013年に第二段 「継体大王の年齢研究」 2010年に初の書籍化 「天武天皇の年齢研究」 |
First update 2019/08/01 Last update 2019/08/03 年齢からも在位年を導くことができます。在位が人の営みの累計である以上、人から人へ次世代に引き継がれる年齢差の合計は同じなのです。日本の天皇系譜は同じ血縁の親子や兄弟相続なので、さらにわかりやすいはずです。このことは、明治時代に久米邦武が明らかにしており、同胞の那珂通世も知っていたはずです。 一般に言われる例えとして、日本書記における後半期天皇の平均在位年は大凡12年ですが、12歳で天皇が次の天皇生むことが出来ません。これは親子相続だけでなく、多くの兄弟相続が混在すると断定できるのです。 現在の天皇で確認します。 現在の紀年は、日本書紀の越年称元法と異なり現在は当年称元法ですので、天皇崩御年が次天皇元年となり重複します。西暦2019年は平成31年から5月1日より令和1年と引き継がれました。 一方、現在年齢は満年齢です。生まれた歳が0歳ですが、日本書紀は数え歳では1歳から始まります。 さらに特異な例外事項として、平成天皇は昭和8年降誕ですが、昭和27年に立太子になり、皇室典範により立太子は18歳でなければならないとされ、これ以降19歳ではなく、18歳にされていることです。 これを考慮しての在位合計と年齢との関係式は 黄色(明治天皇の崩御年齢)と(大正・昭和・平成)在位の合計は 緑色(明治・大正・昭和が太子を生む年齢の合計)は(平成天皇が退位した年齢)と等しいのです。 【近現代天皇の年齢推移】
【明治~平成までの在位と年齢の関係】
このように、年齢研究上一番に問題になるのは、天皇と次の天皇との年齢差ということです。 年齢は在位年に直結しているのです。 日本書紀の記述と比較 そこで、日本書紀の記述から検証します。日本書紀の第10代崇神天皇の誕生から、第13代成務天皇の崩御までの合計年数を確認します。下記表の次天皇が生まれた時の年齢は日本書紀の崩御年齢から推算したものです。例えば、崇神天皇は開化9年に生まれ、54歳で即位、80歳で次天皇になる垂仁を出産、在位68年120歳で崩御、これが日本書紀の記述です。同様に垂仁、景行と成務を計算すると、崇神誕生から成務崩御まで在位期間は 120歳+99年+60年+60年=339年間(翌年称元法なので在位年の調整は不要です) 一方、年齢だけを積算しますが、当時は誕生が0歳ではなく1歳の「数え」なので1年の誤差が生じます。1年の補正が必要です。例えば、30歳即位40歳崩御の場合、在位年は11年です。これを次天皇出産年齢からみても同じ結果が得られます。 (80-1)歳+(95-1)年+(60-1)年+107歳=339年間 【日本書紀が描く崇神から成務天皇4代の年齢推移】
【表日本書紀 崇神~成務親子の年齢表】
一般式 まず、基本的な在位年と年齢の関係をはっきりさせます。 An=n代の天皇が生まれ、世継ぎ(n+1)が生まれるまでの期間 Bn=世継ぎ(n+1)が生まれ、天皇(n)即位までの期間 Cn=n代天皇の在位年数(即位から崩御までの期間) Zn=n代天皇の誕生から崩御まで年数(崩御年齢) Xn=1代天皇誕生から第n代天皇崩御まで年数 一般式 Xi=Z1+(C2+C3+・・・+Cn) =(A1+A2+・・・+An)+Zn
この公式の意味を、下の図を用いて説明します。 Z1第1代誕生からZ3第3代崩御までの期間を求めます。 Z1天皇の誕生からZ3天皇崩御までの年数X3を求める方法一つ目は 1代目の崩御年齢Z1と2代と3代の在位年の合計(C2+C3)です。 二つ目の方法X3は、1代と2代が次天皇を生む年齢(A1+A2)と3代目の崩御年齢Z3の合計に等しい、ということです。 以上を公式化すると上記の(1式)が求められます。以下に図式にすると、 【4代天皇の年齢と在位年の関係】
このように、初代の崩御年齢とそれ以降の在位年の合計は、初代から次世代の年齢差の合計と最後の崩御年齢の合計は等しいのです。 年齢に基づく上代天皇の在位モデル 日本書紀に描かれた異常な高年齢をこのままには出来ません。 日本書紀の在位年に普通の年齢を加えた紀年で考えます。当時の編纂者たちにとって、情報がないなかで上代の在位年を推定するのは難しかったでしょう。しかし、系譜は一部に欠損があったとしても残されていました。上代は親子関係の連鎖の合計なら、素直に合計を求めることはできます。年齢なら当時の第1子の平均出産年齢は21歳とする統計もあります。さらに第2子、第3子などの情報を集めれば、より精度が上がります。人の営みの連鎖のなかでは、親子相続の連続ならば、ある天皇在位が短いとか、長いいとかは関係ありません。容易に時代推定がしやすくなるのです。 現在と違い、古代は20歳までには第一子は生みたいと考えていたようで、人体の成長に素直な行動パターンが見られます。具体的事例として日本書紀や続日本紀の確かな古い出産年齢を挙げます。草壁皇子19歳と阿閇皇女20歳の夫婦により、第一子、後の元正天皇降誕、3年後、第二子、文武が降誕しています また、具体的な数値は示されていませんが、持統天皇は草壁皇子を18歳で生んでいます。 中国「緯書に、男は二八十六にて陽道通じ、八八六十四にて陽道絶へ、女は二七十四にて陰道通じ、七七四十九にて陰道絶へる」とあります。昔の人は、人の体を良く観察した面白い言葉を残しています。現在と違い、讖緯思想の中でも、陽(男)は16歳、陰(女)は14歳に始まると言っているくらいです。 まず、簡単な親子モデルを作りました。一つの平均的モデルA天皇として、次天皇B誕生を21歳のとき、A即位31歳、在位20年として50歳崩御を想定します。 【紀年標準モデル】
日本書紀1代から15代の同じ平均的な親子相続を概観します。これは神武天皇から応神天皇までをイメージしています。途中、「成務-仲哀」は異母兄弟ですが、天皇系譜「-景行-成務-仲哀-応神-」を「-景行-日本武尊-仲哀-応神」の連続した親子系譜として考えます。 まず、1代誕生から15代崩御まで、在位に基づく年数を計算します。1代天皇の崩御年齢は50歳で2代から15代が在位20年なので330年は要することになります。 50+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20=330(年) 同様に、年齢で計算すると、1代から14代21歳で次天皇を生み15代が50歳崩御で同じです。 20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+50=330(歳) この厳しい条件でも第1代神武天皇誕生から第15代応神天皇崩御まで330年は必ず必要なのです。 日本書紀の応神天皇崩御はAD310年です。この数字は同時に引用された百済記などから、現実とは120年ずれており、実年代はAD430年だとする定説があります。すると神武降誕は最短でAD100年前後でなければならないのです。 AD310年+120年-330歳=AD100年 歪な日本書紀の紀年 もう少し詳しく記紀旧辞に合わせて見ます。 神武天皇は大和に来てから第2代綏靖を生んでいますが、日向で生まれた長男はそのときすでに成人に達していたような記述なので、2代綏靖出産を20歳ずらし41歳とします。 【モデル2神武天皇】
また、4代懿徳と6代孝安天皇は実兄の娘を娶り、太子を生んでいます。娘が成人するまで太子は生まれない異世代婚の形です。皇后が成人するまで子供は生まれません。すなわち、「4代懿徳-5代孝昭」は「4代懿徳-渟名底仲媛-5代孝昭」という3世代系譜と同じなのです。在位期間が必然的に伸びます。2代40年の在位追加が必要なのです。 【モデル3懿徳・孝昭】
また、垂仁15年に11代垂仁天皇の皇后が殺され、後の日葉酢媛が生んだ2番目が景行、垂仁の第3子になります。時間差が生じています。記紀旧辞は次期景行の生まれが遅れています。無視できません。正確な年数はわかりませんが、平均より10年遅れた31歳出産と仮定します。 さらに、14代仲哀天皇は崩御後に応神が降誕しています。その年齢を日本書紀の記述は50歳ですが、仲哀天皇の項でも解説しますが40歳崩御とします。
すると大まかですが、神武誕生から応神崩御までの間は430年と仮定できます。 40+20+20+40+20+40+20+20+20+20+30+20+20+40+60=430(年) 実はこれ、先ほどの応神AD430年崩御説を念頭にはじき出した少し強引な計算ですが、日本書紀の神武天皇誕生年もちょうど、BC1年生まれと推測も出来るのです。よって、日本書紀には系譜が示されていることから紀年は大凡見当が付くのです。 以上の様に、日本書紀の記述には、年齢の長寿命化だけでなく、異世代婚の多さ、末子相続の多さ、応神のような父親死後の誕生談、皆、少ない即位天皇系譜に年齢を引き延ばす稚拙な裏技に見えてしまいます。 ©2006- Masayuki Kamiya All right reserved. |