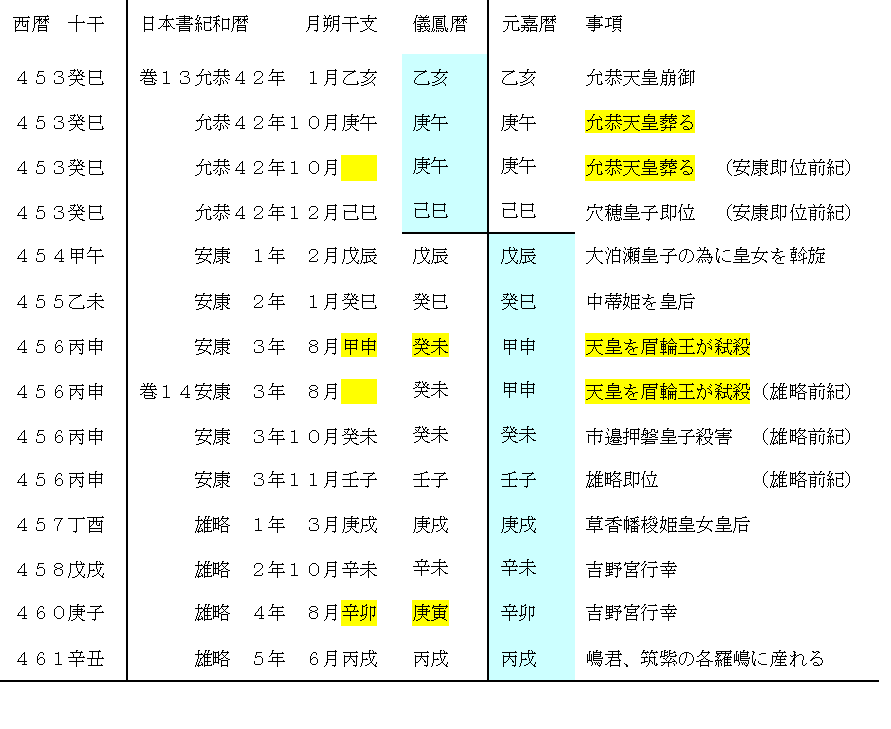|
天武天皇の年齢研究 -目次- -拡大編- -メモ(資料編)- -本の紹介-詳細はクリック 2018年に第三段 「神武天皇の年齢研究」 2015年専門誌に投稿 『歴史研究』4月号 2013年に第二段 「継体大王の年齢研究」 2010年に初の書籍化 「天武天皇の年齢研究」 |
First update 2014/07/23
Last update 2018/11/17 朔日付の数え方 日本書紀には、例えば「庚申欽明天皇元年一月庚戌朔甲子」などと日付が書かれています。 この意味は、最初の「庚申」が年を示します。干支年は古代中国に古くからありました。中国後漢朝の四分暦で理論づけられたと言われています。それ以前の古王朝で定められ暦法では、暦法が変わるたびに干支が変更されていましたが、後漢朝から王朝が変わっても干支は規則通り、毎年60個の干支が順にくり返されるようになりました。 ある基準年を「00甲子」とし、60個の干支を何度もくり返した後、「56庚申」年はその57番目です。西暦と照らせば西暦540年に当たります。 ここで問題にしたい月朔干支、欽明1年1月の月の初日(朔)は「庚戌」と書かれています。その「甲子」日は月初め庚戌から数えて15番ですから15日となります。 よって、「庚申欽明天皇元年一月庚戌朔甲子」は旧暦で西暦540欽明1年1月15日となります。 干支表 00甲子01乙丑02丙寅03丁卯04戊辰05己巳06庚午07辛未08壬申09癸酉 10甲戌11乙亥12丙子13丁丑14戊寅15己卯16庚辰17辛巳18壬午19癸未 20甲申21乙酉22丙戌23丁亥24戊子25己丑26庚寅27辛卯28壬辰29癸巳 30甲午31乙未32丙申33丁酉34戊戌35己亥36庚子37辛丑38壬寅39癸卯 40甲辰41乙巳42丙午43丁未44戊申45己酉46庚戌47辛亥48壬子49癸丑 50甲寅51乙卯52丙辰53丁巳54戊午55己未56庚申57辛酉58壬戌59癸亥 実際の計算方法 最近のニュースで騒がせた再現実験は重要です。この問題はいろいろな場面で遭遇します。例えば、神武即位日BC660神武元年1月1日は現在の暦では2月11日だそうですが、この計算根拠が示されないままの謎の日付です。身近な体験でも、古代史の学術論文を読むなかでの引用記事を鵜呑みすると、思わぬ失敗をします。引用した原文を調べ直すと、その学術論文が言いたいこととニュアンスが異なることに度々遭遇します。この元嘉暦、儀鳳暦レベルになるとその検算は大変でした。どうしても腑に落ちないことがあり、自分で計算しようと悪戦苦闘しました。 教則本は内田正男編「日本暦日原典第四版」暦法編第2章暦の計算法を軸に検討しました。以下一部、式を簡素化しました。素人計算ですが、以下に事例を示します。間違い等ご教授頂ければ幸いです。 元嘉暦 基本となる数字は天文観測から得た時間と次の理論基準です。 1太陽年=365+75/304=111035/304=365.24671日。これは、111035を304で割った商365と余 75 1朔望月=29+ 399/752= 22207/752=29.530585日。これは、 22207を752で割った商 29と余399 19年=(12×19+7)=235ヶ月 これは、上記の太陽年と朔望月を結びつけています(参照:中国の暦法) 元嘉暦の基準年は443元嘉20年から数えて、上元(積年)5703年前の1月1日(朔)甲子日であり,午前0時が「雨水」になります。雨水は二十四節気の1つで,正月中気で1月を指します。
例として、問題の一つ、日本書紀の697持統11年8月1日の月朔干支「八月乙丑朔」の正当性です。持統天皇は、皇太子に譲位しました。この697年8月「乙丑朔」を検証します。 続日本紀では同日を文武天皇即位日として「甲子朔」とあります。1日違いです。 まず、元嘉暦は南宋の443元嘉20年より、積年5703年前が基準になり、求める年697持統11年までの積年は 積年=5703+(697-443)=5957年 よって、697持統11年正月朔(1日)は、 1式 5957×(235÷19)=73678・・・13余り 2式 73678×(22207÷752)=2175754・・・338余り(朔の小余) 3式 2175754÷60=36262・・・34余り(1月朔の大余34=戊戌) (上記干支表により、割り切れる時=甲子、余り1の時=乙丑、余り2の時=丙寅・・・) なお、その1月の小余= 338÷752=0.4495 よって、その年8月は(2式の商)2175754+(8-1)×(22207÷752)=36262・・・余り 36262÷60=36266・・・1余り(1月朔の大余01=乙丑) なお、その8月小余は、338÷752+(399÷752)×(8-1)=4.1636 小数点以下の部分0.1636が8月の小余となります。 よって、元嘉暦による697持統11年8月1日の月朔干支は「乙丑」で日本書紀の記述と確かに一致します。 儀鳳暦 内田正男編「日本暦日原典(第四版)」では儀鳳暦に計算方法は細かく表示されていません。説明文にあるように、その後の宣明暦と同様とあることから、計算式はこれに準拠しました。 1太陽年=489428/1340 =365.24477日。これは、489428を1340で割った商365と余 328 1朔望月= 39571/1340 =29.530597日。これは、 39571を1340で割った商
29と余 711 儀鳳暦の基準年は664麟徳1年の前年11月1日(朔)甲子日から数えて、上元(積年)269880年前の11月1日(朔)甲子日であり,午前0時が「冬至」になります。冬至は二十四節気の1つで,00冬至11月中気を指します。 同じ例として、日本書紀の記述では、697持統11年8月1日「八月乙丑朔」を計算します。 続日本紀では同日、文武天皇即位日として「八月甲子朔」とあります。 まず、儀鳳暦は中国では麟徳暦とよばれ、唐の664麟徳1年より、積年269880年11月が基準になり、よって697持統11年までの積年は 積年=269880+(697-664)=269913年 よって、目的の前年696持統11年11月朔(1日)は、 1式 269913×80400=3・・・28713余り (269913を26966は間違いとご指摘いただき、 2式 28713×(7028÷80400)=2509・・・71364余り 有難う御座いました。)2018/11/17追記 3式 71364÷1340=53・・・344余り(11月朔の小余344) 章閏法=489428-(39571×12)=14576 4式 269913÷39571=6・・・32487 5式 32487×14576÷39571=11966・・・23926 6式 23926÷1340=17・・・1146 よって、696年11月朔は各々余りと商を引く3式-6式 小余=344-1146+60=538(小川解 538÷1340=0.402) 引くとマイナスになるため60を加えた。 大余=53-17-1=35己亥 小余に60を加えたので1を引いた。 696年12月朔は前月11月朔に1朔望月の余りと商を加える。 小余=538+711=1249(小川解1249÷1340=0.932) 1340を超えた場合には、1340を引き、大余に1を足す。 大余=35+29+0-60=4戊辰 59を超えたら60を引く。 これをくり返した翌670年8月朔干支は、 小余=1249+(711×8)-1340×5=237(小川解 237÷1340=0.177) 大余=4+(29×8)+5-60×4=1(01乙丑) よって、儀鳳暦(平朔)による、697持統11年8月1日の干支も「乙丑」になり、日本書紀の記述と確かに一致しますが、続日本紀とは一致しません。これは、内田正男編「日本暦日原典(第四版)」では定朔による小余計算を加味しているため、大余にも影響を与え、小余も一致しません。つまり、続日本紀は儀鳳暦(定朔)を用いて書かれていることが確認できました。 本稿の結果は、小川清彦氏(上記の小川解)の論文と一致する結果になります。小川氏の論文の式は正確に理解出来ませんでしたが、元嘉暦と同じ平朔法で計算したものです。 平朔法と定朔法 唐の時代の中国の暦法には、定朔法が導入されるようになりました。 麟徳暦は定朔法を用いました。残念ながら太陽をまわる地球の楕円軌道の遅速をどのように計算したかの資料は現存しません。幸い換算表が残されています。 古い平朔法では、日月の運行の遅速は考慮に入れられていません。このため、真の朔を含む日が29日、30日や2日になることがあります。定朔法の暦では日食は必ず朔一日に起きるのです。 日本書紀における元嘉暦と儀鳳暦の大きな違い 暦名 太陽年 1朔望月 元嘉暦 365+ 75/304 =365.24671 日 29+
399/752 =29.530585日 麟徳暦 365+ 328/1340 =365.24477 日 29+ 711/1340 =29.530597日 現在 365.24220 日/月 29.530589日/月 元嘉暦の基準年は443元嘉20年から数えて、上元(積年)5703年前の1月1日(朔)甲子日であり,午前0時が「雨水」になります。 儀鳳暦の基準年は664麟徳1年の甲子日から数えて、上元(積年)269880年前の前年11月1日(朔)甲子日であり,午前0時が「冬至」になります。 小川氏の学説の論点 この論文は天文学者小川清彦氏によって、1940昭和15年8月に明らかにされました。 1.儀鳳暦は本来「定朔法」をとる暦法だが、日本書紀では「平朔法」を採用した。 2.「日本書紀の暦日は神武以降5世紀に至るまでの分が儀鳳暦により推算され、その後の分は元嘉暦によって推算されたものと考えられる。」 3.その境は「たぶん454安康元年以降が元嘉暦による推算になったとすべきであろう。」 3.について、神武から始まる儀鳳暦による記述が、安康3年8月の月朔干支の記述以降から齟齬をきたすことから、暦法の変更は安康天皇即位元年から変わったとしました。天文学者らしく、厳格なものです。この安康天皇即位から暦法が変わる説を採用する学者はまだ多くいます。 【小川清彦氏が発見した日本書紀上の儀鳳暦、元嘉暦の使い分け】
上記のようにそれまで儀鳳暦(平朔)で記述された月朔干支が安康3年8月では「甲申」で、これは元嘉暦で計算された結果と同一でした。この後も、儀鳳暦(平朔)では一致しなくなります。 そこで、安康1,2年の記述は元嘉暦と儀鳳暦(平朔)が計算上同じであるため、安康1年から元嘉暦で記述されていると小川氏は推測されたのです。 一方、元嘉暦と儀鳳暦(平朔)による計算結果の違いは全体の中でそれほど多くはなく、元嘉暦と儀鳳暦(平朔)の結果が類似していることもわかります。小川清彦氏の計算では日本書紀月朔干支899例の中で36例が元嘉暦と儀鳳暦(平朔)の計算結果が異なり、これを、日本書紀の記述と比較したものです。 小川氏学説の反響とその問題点 1.岸俊男氏は、小川清彦氏の『書紀』の暦日研究結果から、神武紀~仁徳紀の終りまで、唐代の暦である儀鳳暦、安康紀3年8月条から以降は宋の暦で、445年から施行された元嘉暦が使用されていることから、雄略朝には元嘉暦が日本に伝わっていた、と決めつけてしまいました。 2.山中鹿次氏は、仁徳以降履中からは天皇の寿命や在位年数は、後世の儀鳳暦による架空の造作が見られなくなるため、現実味を帯びた年数となり、元嘉暦が採用される雄略以降は確実性を増すといえ、仁徳以前については、信用度の高い記事は伝えられていない、と決めつけました。「前期大和王権に関する二、三の考察1998山中鹿次」日本書紀研究22 ところが、有坂隆道氏は、あくまで、日本書紀の記述として、その編纂者がどう書こうとしていたかを問題と考えました。日本書紀は巻14雄略紀から編纂者が異なるような書き方など内容に変化が見られるので、暦法も第14巻冒頭(雄略天皇即位前紀安康3年の記述)から元嘉暦で書かれたと推測しました。上表参照 問題の安康3年8月の安康天皇崩御の記述は、巻14雄略即位前紀の冒頭記事にも出てきます。この14巻から元嘉暦で書かれたと考えると、雄略前紀ですが、安康3年8月「甲申」と元嘉暦で書かれたのです。後から安康以前の記述に月朔干支を書き加える際、この8月甲申が生かされ、他の即位前紀の記述例に則して、実際の巻14雄略紀冒頭の安康天皇崩御記事の干支表記は落とされたと考えました。 元嘉、儀鳳暦併用期間にについて 小川清彦氏は元嘉暦と儀鳳暦(平朔)において、667天智6年閏11月丁亥6年以降、相違はないとしました。確かに元嘉暦と儀鳳暦(平朔)は同じだったのですが、内田正男氏は元嘉暦と同じ月月朔干支を示した儀鳳暦(平朔)が持統6年から最後11年までの間に3カ所に違いがあり、日本書紀は、むしろ儀鳳暦(定朔)で表現されていることを示しました。 日本書紀 持統4年11月11日に、勅を奉りて、始めて元嘉暦と儀鳳暦とを行ふ。 この持統4年の記事、元嘉暦と儀鳳暦を同時に始めたと解釈し、違いが生じた持統6年から併用されたと考えました。6年11月、10年12月、11年4月に儀鳳暦(定朔)が使われたからです。記入ミスではないことになります。 【持統6年以降、紀の記述が元嘉暦、儀鳳暦(平朔、定朔)で合わない月朔干支】
注 *は続日本紀 持統紀1年から5年まで、日本書紀の記述と儀鳳暦(定朔)が同じ場合には、元嘉暦と儀鳳暦(平朔)の3つの計算値もすべて同一になる。 そこで、日本書紀記述と儀鳳暦(定朔)計算値が一致する3つの文章を抽出しました。 持統6年「十一月辛卯朔戊戌、新羅遣級飡朴億徳・金深薩等進調。賜擬遣新羅使直廣肆息長眞人老・務大貳川内忌寸連等祿、各有差。」 持統10年「十二月己巳朔、勅旨、縁讀金光明經、毎年十二月晦日、度淨行者一十人。」 持統11年「夏四月丙寅朔己巳、授滿選者、淨位至直位、各有差。」 官位等の授与、天皇の勅といった、公式記録です。特に「各有差」は身分等によって、分配に差があったという意味で、特徴的です。 持統紀では「各有差」の使用例は26回ありますが、そのなかで、月朔干支に絡む事例は次の3例もあります。 持統2年「九月丙辰朔戊寅、饗耽羅佐平加羅等於筑紫館賜物、各有差」 「十二月乙酉朔丙申、饗蝦夷男女二百一十三人於飛鳥寺西槻下仍授冠位賜物、各有差」 持統4年「十一月甲戌朔庚辰、賞賜送使金高訓等、各有差」 これは日本書紀、計算値(元嘉暦、儀鳳暦(平朔、定朔))がすべて一致しています。逆に言えば、ここでも公式文書を暦法の修正ではなく、丸写し引用した可能性もあるのです。 さらに、日本書紀全体で「各有差」の記述は66カ所ありました。 日本書紀巻15清寧 2カ所、 巻19欽明 2カ所、 巻22推古 2カ所 巻24皇極 2カ所、 巻25孝徳 4カ所、 巻27天智 1カ所 巻28天武上 2カ所、 巻29天武下25カ所、 巻30持統 26カ所 続日本紀 巻1文武 11カ所、 巻 2大宝 8カ所、 ~ 天武、持統紀で集中的に現れる単語だったことがわかります。この言葉は続日本紀でも引き続き166カ所に使用される常套句です。当時の書記官の記録記事と思われます。持統6年から元嘉暦と儀鳳暦(定朔)が併用されたのではなく、日本書紀編纂者が後に持統時代の記録をそのまま、引用したものだと思います。 「併用」という、行き過ぎた解釈の横行 その後、併用自体は曖昧模糊として拡大解釈されていきます。 儀鳳暦は神武東征から~仁徳崩御まで、元嘉暦は雄略即位~持統4年までとし、さらに履中即位~安康崩御、また持統即位年(4年説、5年説6年説がある)~持統譲位までは両暦併用していたとする折衷案が登場し、いろいろな本で紹介されるようになります。 これは現代の研究者が現実と日本書紀の記述を混同しているのが原因です。よって、このままでは、どちらの意見も取り込み、実際、現実の世界でも当時、こうであったと考えた説まで出てしまいます。 こうした曖昧さは、儀鳳暦(平朔)と元嘉暦の結果が同じ結果になりやすいからです。 相違はたまに1日程度しか違わないものです。 儀鳳暦(平朔)と元嘉暦は399仁徳87年10月癸未(甲申)で違った以降は456安康3年8月癸未(甲申)まで157年間同じ月朔干支です。667天智6年閏12(11)月丁亥以降はこれも日本書紀最後の持統譲位の記述まで同じです。 まとめ 本稿では、現実は別として、日本書紀の記述は、巻3神武紀~巻13安康紀までは、儀鳳暦(平朔法)で書かれ、巻14雄略紀~巻30持統紀最後まで元嘉暦で表記されたと考えます。 また、現実の当時の暦法は、554欽明15年に暦法が伝わりますが、百済の暦博士が来たという程度です。604推古12年から一部の人間によって元嘉暦が使われはじめ、記録され出したと思われます。 儀鳳暦は676天武6年から天武8年が唐の儀鳳年間ですから、麟徳暦がその頃、新羅経由で入って来たと思われます、681天武10年に国史編纂事業がスタートする切掛けになったことでしょう。しかし、実際に実践されるのは持統4年11月の記事からで、691持統5年からとしていいと思います。 結局、日本書紀は事象の記述の正確さは別として、記述の表現方法に関しては、その書物の中だけで通用するものでした。 持統から雄略までは、元嘉暦で書かれ、それ以前は儀鳳暦(平朔)で書かれました。 元嘉暦使用はそれまでにも使用されていたからでしょう。全体を元嘉暦で統一しなかった理由は、古代中国南宋の元嘉暦成立が443年であり、それ以前の使用が許されないからです。実際に元嘉暦法が日本に入ってきたからではありません。 そこで、それ以前を儀鳳暦に平朔法を用いて表現しました。いわゆる何処にも存在しない暦法といえます。この方は計算が容易で、元嘉暦との誤差が少ないことも理由の一つです。 むろん、続日本紀は儀鳳暦に定朔法を用い、正式に中国の暦法、麟徳暦で表現したのです。唯一進朔だけは用いなかったと言われていますが、正確な結論はでていません。 現実の世界は、推古天皇の御代で古い元嘉暦が百済経由で入ったことから、スタートしました。麟徳暦が新羅経由で天武天皇の御代に入ってきました。ここで、暦法が一つではないことを学びました。天武天皇はそのまま元嘉暦で記録を残し続けさせました。国史編纂に自分の記録を残す意思はありませんが、記録として元嘉暦を用いて書記官に記録するよう命じていたと思います。 持統4年、持統天皇は元嘉暦から、儀鳳暦の採用を決定します。現実問題として併用などできません。官僚機関などの公文書は儀鳳暦(定朔法)に統一されたはずです。元嘉暦は強い天武天皇の意思に基づき、史書編纂事業のなかだけで息づいていたのです。 後に元明天皇の御代、日本書紀編纂に際し、持統紀をまとめる際、公文書は儀鳳暦のまま採用されました。幸い丸写しした月朔干支は同じだったのですが、3カ所だけ、元嘉暦と儀鳳暦(定朔)と異なるカ所があり、そのまま記述されてしまいました。 天文学者、内田氏の表現は元嘉暦と儀鳳暦が併用した時期と表現しています。確かに、日本書紀の持統紀6年から3カ所儀鳳暦(定朔)の干支が使われていますが、これは、日本書紀の表現を当時の現実も同じとして考えてしまった結果だと思います。 こうして、日本書紀は続日本紀に引き継がれます。 【文武天皇即位記事】
720養老4年、日本書紀が完成後、すぐ、聖武天皇が即位しますが、これはもっとすごい。 724甲子年と年を甲子年に合わせています。年号も前年養老7年から神亀1年に改められました。ただ、実施日は2月辛卯朔甲午(4日)でした。当初は甲子神亀元年春正月壬戌朔1月1日の計画であったはずです。 「朝を廃む。雨ふればなり」とあります。聖武天皇即位式は延期されていたのです。 参考文献 小川清彦「日本書紀の暦日に就いて」『小川清彦作品集』皓星社1997 内田正男編「日本暦日原典第四版」雄山閣出版H4 内田正男「日本で使われた古暦法1」17-1 S49 内田正男「元嘉暦法について」16-2 1973 有坂隆道「古代の歴史」『図解検証現像日本④』旺文社1988 有坂隆道「古代史を解く鍵」講談社学術文庫1999 飯島忠夫「天文暦法と陰陽五行説」『飯島忠夫著作集4』第一書房S55 山中鹿次「前期大和王権に関する二、三の考察1998」『日本書紀研究22』横田健一編 塙書房H11 ©2006- Masayuki Kamiya All right reserved. |