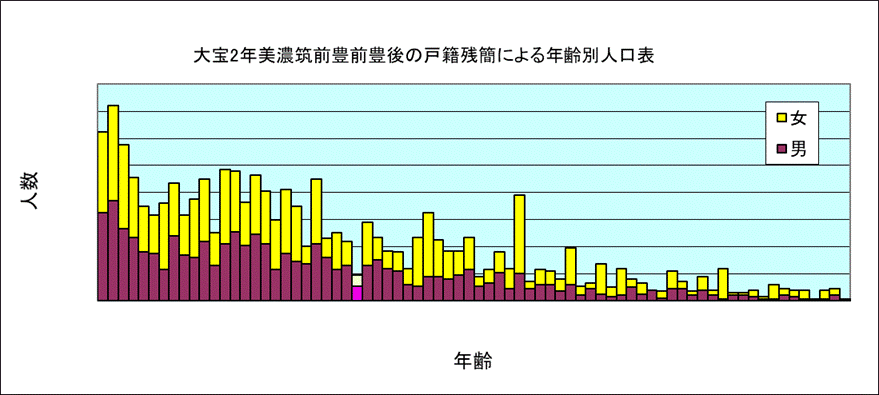|
天武天皇の年齢研究 -目次- -拡大編- -メモ(資料編)- -本の紹介-詳細はクリック 2018年に第三段 「神武天皇の年齢研究」 2015年専門誌に投稿 『歴史研究』4月号 2013年に第二段 「継体大王の年齢研究」 2010年に初の書籍化 「天武天皇の年齢研究」 |
First update 2009/02/15
Last update 2012/10/04 660斉明6年生 ~ 678天武7年没 19歳 本稿主張 653白雉4年生 ~ 678天武7年没 26歳 折口信夫 648大化4年生 ~ 678天武7年没 31歳 伊藤博氏 647大化3年生 ~ 678天武7年没 32歳 梅原猛氏 父 天武天皇 686朱鳥1年崩御 日本書紀 母 額田王 生没不詳 夫 高市皇子 696持統10年7月薨去 日本書紀 胸形徳善――尼子娘 ├―――高市皇子 天武天皇 | 某氏 ├―――十市皇女 ├――――鏡王――額田王 ├――――鏡王女 | 妻 | | 天智天皇 注:本稿では鏡女王を額田王の姉ではなく叔母と考える。 660斉明6年 1歳 十市皇女生まれる。(本稿) 665天智4年 6歳 葛野王生まれる。懐風藻に十市皇女の子と書かれる。 672天武1年 13歳 壬申の乱。大友皇子没。懐風藻に十市皇女の夫と書かれる。 674天武3年 15歳 阿閉皇女14歳らと伊勢神宮に詣で大伯皇女14歳と会う。 677天武6年 18歳 大地震。 678天武7年 19歳 宮中で突然薨去。 600年 4455555555556666666666777777777 年 8901234567890123456789012345678 齢 額田女王 ⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳―――――――――30―――――――73 十市皇女 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ 高市皇子 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱―35 大友皇子 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳――――25 葛野王 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭―37 天武天皇こと大海人皇子に嫁いだ額田王が生んだ娘が十市皇女です。 天武天皇にとってはじめての子です。 懐風藻にのる葛野王小伝の冒頭記事
この記事はすこぶる重要で、その後、現在に至るまで大きな影響力をもつ一文です。 この短文を信じるかぎり、いろいろなことがわかります。 1.大友皇子は天智天皇の子である。 日本書紀の記述と一致する。 2.十市皇女は天武天皇の子である。 日本書紀の記述と一致する。 3.葛野王は大友皇子の長子である。 4.十市皇女は天武天皇の長女である。 5.十市皇女は大友皇子の室である。 6.十市皇女が葛野王を産んだ。 この一文が後世に扶桑略記、水鏡、宇治拾遺物語、愚管抄などにより物語を産むことになります。 十市皇女の物語 壬申の乱において、十市皇女が近江にいながら敵となった父の大海人皇子に近江側の内情を知らせる文を認めたとされるものです。 まず、平安末期に表された扶桑略記がこのことに触れます。 扶桑略記 天武天皇元年壬申五月
これに忠実な当時のベストセラー水鏡が脚色を加えます。 水鏡 四十一代 天武天皇
愚管抄 第三 (漢字は本稿の当て字)
宇治拾遺物語 巻第十五 (漢字は本稿の当て字)
意訳すれば、「大友皇子の妻に一人に天武天皇の娘が居りました。夫の策謀を知り、父が殺されるのではと悲しみ、何とかこのことを知らせねばと思いましたがどうしようもありません。考えた末、文を小さく書いて、フナの包み焼きのお腹に忍ばせ、父のもとに届けさせたのでした。」 このような物語が誕生するくらい十市皇女は特別な存在として扱われています。 愚管抄、水鏡にもこの話が大なり小なり出てきます。時代が下るにつれ細部描写に磨きがかかります。しかし、不思議なことにどれも名指しで十市皇女のことだとは言っていません。天武天皇の娘で大友皇子に嫁いだ娘とは懐風藻に従えば、十市皇女のことでしかないのですがはっきり言わないのも妙な話です。信頼ある歴史書、本朝皇胤紹運録も、葛野王を大友皇子の子としていますが、母は誰なのかを記述していません。まさに、懐風藻だけが、葛野王の母を十市皇女と言っているに過ぎないのです。 懐風藻から大友皇子の室として子をなしたとすれば、亡くなったのは30歳程度といわれますがどうでしょうか。彼女は自殺と思われます。30歳の一児を持つ母がそう簡単に一人死ぬとは考えにくいのです。反対勢力のなかに母子が取り残され、もし思いあまった末の自殺なら、母親の心理としては子供を道連れにしそうな気がします。 また、卑近な例で恐縮ですが、連れ合いに、自分の父親と夫が争ったとしたら、一般的に女はどちらに味方するものか尋ねたことがあります。彼女は迷うことなく夫と答えました。 これらの物語には儒教的なにおいと不自然さを感じるのです。 十市皇女の年齢を探る手がかり まず、懐風藻の記述を無視して、本編を進めます。 実は十市皇女の年齢は万葉歌から推測できると考えています。
「川中の神聖な岩々に草も生えないように、いつも不変であることができたらなあ。そうしたら常処女でいられように。」伊藤博氏訳 「この河のほとりにある、沢山かたまり合うた巌の上には、一本の草も生えていない。何時迄も古めかず、新しう見える。その様に、我が皇女も、齋宮になってお下りだから、いつまでも年とらず、処女で入らせられることであいりたいものだ。」折口信夫訳 いずれも難しい解釈になっています。 天武4年2月、十市皇女は阿閉皇女らと伊勢神宮に詣でるとき、同行した吹芡刀自(「刀自」とは40歳程度の女性といわれる一般的表現)が十市皇女に成り代わり代作したものです。 清らかな山中を流れる岩肌の風景です。十市皇女の姿と重ねています。この清らかな乙女を褒め称える歌だと思います。同行した吹芡刀自の十市皇女への穏やかな眼差しを感じます。 万葉集は注記として十市皇女を14歳の阿閇皇女と同等に並べて書いています。阿閇皇女は天智天皇の娘で後に草壁皇子と結ばれ、元明天皇となる女性です。 この伊勢に詣でる大きな役目の一つは、その伊勢に5ヶ月前に赴任した同じ14歳の大伯皇女を尋ねることだったはずです。 よって、年齢の知れるこの二人の娘に挟まれた十市皇女も同様の年齢の女の子ではなかったかと考えたいのです。十市皇女と大伯皇女は母が違うけれど、二人とも天武天皇の若い時に生まれた娘です。そんな同年代の三人娘が再会したのです。 大伯皇女は前年13歳で伊勢斎王になりましたが、その幼さで一人伊勢での慣れない5ヶ月間の生活はさぞ厳しく寂しかったことでしょう。そこへ2人の同年齢の女の子がこの斎王を見舞っているのです。励ましているように思えるのです。たぶんその年齢の女の子は他にも付き添いが多数いたのかもしれません。結構和やかで騒がしい女の子集団です。 そうだとすると、父、天武天皇の粋な計らい、細やかな心遣いが見えてきます。 また、もし懐風藻に伴う通説に従いこのとき29歳の一児の母十市皇女なら、この歌を人任せにせず、天才額田王の娘として自分で堂々歌ったことでしょう。本書の予測する15歳では歌うにはすこし若すぎます。上記の歌が吹黄刀自の代作となったのは当然です。 ましてや、山の清水を題材にした清らかな歌です。「常処女」などの表現もあり、29歳の一児の母を表現する歌とは考えにくいものです。 川崎庸之氏もこのことには不思議がっておられます。 「高市皇子にしてもそうであったが、(十市)皇女はこの深刻な(壬申の乱の)経験を自ら歌にうたうことはしなかった。天武天皇を父に、額田女王を母にもち、自らもまたこの深刻な経験を経てきた人がという一般的な環境論からいえば、或いは不思議といわれるかもしれない」 「天武天皇の諸皇子・諸皇女」より。 本稿では壬申の乱のとき、十市皇女はまだ13歳です。歌わないのは当然です。 十市皇女の死の原因 十市皇女はその3年後、678天武7年に突然亡くなります。 なぜ死ななくてはならなったのでしょうか。 亡くなる前年、677天武6年6月14日に大地震がありました。前後の推移をみると火山の大爆発があったのではないかと思われます。この年はひどい旱魃で、京や畿内では雨乞いであふれていたときでもあります。各地で必死の思いで神々が祭られ、飛鳥寺では斎会がもうけられ、政府側でも浮浪人対策、全国の大赦令、免税処置等、矢継ぎ早に対策が打たれています。 のちの大宝2年の人口調査でこの677年に生まれた人口が極端に減少していることでもその被害の大きさがわかります。正倉院文書による大宝2年美濃筑前豊前豊後の戸籍残簡によれば、大宝2年26歳になる、すなわち677天武6年大飢饉のとき生まれの男女は、19人で前後の年の人口の半分しか生存していなかったことがわかります。
注)本資料は澤田伍一氏「復刻 奈良朝時代民政経済の数的研究1972柏書房」の正倉院文書解析のよる資料を抽出したものです。精度としては多くの問題があることは承知していますが、傾向はつかめると思います。 その厳しい年の翌年678天武7年になった春、天武天皇は倉梯の河上に斎宮を建てられました。天皇自身が神事を行うためのものです。この時代の天皇は天災にも責任を持たなければならないのです。祭礼の日時は4月1日の占いにより7日と決定されました。行幸の当日、午前4時に先払いが出発、百寮が列をなしたといいます。天皇の御輿に蓋を召して出られようとするその時、十市皇女が急に薨じられたのです。「十市皇女、卒然病発、薨於宮中。」このため、天皇の行列は停止し行幸はできず、神々への祈りもなくなったのです。 4月13日、雷がこの新宮に落ちています。 4月14日、十市皇女は赤穂に葬られました。天皇は心のこもった言葉をかけられ、声を出して泣かれたとあります。 そして同年12月今度は九州筑紫でまた大地震が起こっています。 【万葉集 高市皇子】
十市皇女は亡くなったとき高市皇子が詠んだ歌です。挽歌です。 同じ天武天皇を父にもつ、母が違う二人です。 高市皇子は死んだ十市皇女を深く愛していたことがわかる歌です。契りを結んだばかりだったようです。 十市皇女の美しさを、山間を流れる清水にたとえています。 この歌だけをみるかぎり、純粋な若者の十市皇女を偲ぶ挽歌だと思えるのです。 難解な歌に数えられるものですが、これは一般通説により25歳の高市皇子が贈る30歳になる子持ちの十市皇女への挽歌と考えるから歌の解釈が難しくなるのです。幼い子を残しての母親としての死、また行幸を止めることになる慌ただしい身勝手な行為は不自然です。 二人ともまだ18、19歳で、契りを結んだばかりだったのではないでしょうか。 天才的万葉歌人を母にもつ繊細で生真面目な十市皇女です。あの日、巫女として天武天皇と同行する予定だったはずです。巫女として神々に祈り日本のこの飢饉を救済したい。少しでも役に立ちたい。ところがこの頃、処女でなければならぬ巫女が男性と関係を結んでしまった。多感な年頃です。また迷信が信じられた時代です。 一方、高市皇子は九州宗像氏を母にもつ九州男児です。高松塚古墳の被葬者が高市皇子だとすると「筋骨発育良好な163cmの男性」となります。当時としては上背のあるがっしりとした男臭い男性像が浮かび上がります。周囲も将来はと本人達には了解との約束がなされていたのかもしれません。その彼が京育ちの十市皇女を求めたのも自然なことです。 その結果、十市皇女はこの世情における大きな役目を担った大切な巫女としての責任を全うできないと一人思い詰め、せっぱ詰まった末の覚悟の自死だと思います。 十市皇女 660斉明6年生まれ~678天武7年没 19歳 ここに描かれた十市皇女の姿はある意味で誰もが考えた当たり前の結論でした。 それを一児のいる30歳くらいの女とする懐風藻などの横やりが入るから話が歪んでいろいろな解釈がでてくるのです。 後日談としての高市皇子ですが、これ以降、年長者の皇子であり壬申の乱の功績者であるはずの彼の業績は天武天皇在位期間中、認められることはありませんでした。 それどころか、翌年春1月7日の詔で、卑母に拝礼してはいけない、その氏神を祭ってはいけないなど、まるで宗像氏への戒めに聞こえます。 日本の長い歴史に於いて、力あるものに対し卑しい身分として力を封じ込める方法は常套手段です。 そして、5月5日に吉野会盟です。この意味についてもいろいろな解釈があるところですが、私は草壁皇子を第一番目に指名し誓約宣言させることで皇子たちの序列を明らかにした、意味をもつ一族会合と考えています。正式に高市皇子は排除されたのです。ちなみに誓盟の順は草壁・大津・高市・河嶋・忍壁・芝基の順です。吉野からもどると、20歳になった草壁皇子を正式に太子に任命、さらに、翌々年21歳になった大津皇子に朝廷会議に列席させ、歴史編纂事業には忍壁皇子を参加させていくのです。 高市皇子にはなにもありません。 天武14年正月の叙位により吉野会盟のときと同じ序列が公表されます。 天武天皇の厳しい一面を見る思いです。 十市皇女の年齢推定ですが、661斉明7年に額田王は斉明天皇に従い、夫、大海人皇子らと九州に向け出航しています。よって、その直前に十市皇女を幾内の十市の地で生んだと設定しました。日本書紀に「十市皇女、阿閇皇女」と書かれるところから、阿閇皇女よりすぐの年上と考えられます。 よって、懐風藻がいう十市皇女の生んだ子が葛野王である可能性はないと思います。葛野王は年齢から逆算して、669天智8年の生まれです。そのとき十市皇女は10歳でしかないのです。葛野王への権威付けのために十市皇女が利用された気がしています。懐風藻の分析は「考察」で詳細に論じます。 この懐風藻の十市皇女の記事により額田王の年齢も同時に天武天皇の年齢も高く設定されてきたと思っています。娘十市皇女は天武天皇の初めての子供ですが、 上記で検証したように年若い多感な巫女十市皇女は男性と関係したため、一人悩み亡くなったと思われます。 昔から、額田王の年齢を推測するために、この懐風藻が唯一の手段として多用されてきました。 葛野王が天智天皇の長子、大友皇子と天武天皇の長女、十市皇女の子供だと書かれてあるからです。 このことは次のことを連想させます。 1.十市皇女と大友皇子の年齢が同等である。 2.天武天皇と額田王 の年齢が同等である。 そして、当の懐風藻には、次のことも書かれています。 大友皇子 648大化4年生まれ ~ 672天武1年没 25歳(懐風藻) 葛野王 669天智8年生まれ ~ 705慶雲2年没 37歳(懐風藻) なお、日本書紀の記述から大友皇子の没年が、続日本紀の記述から葛野王の没年がわかります。懐風藻にはそれぞれの享年が記載されており、そこから生年を逆算したのが上記の生没年齢で、これは定説として人名辞典にも記述されています。本稿もこれを採用しています。 問題なのはこの先です。 本稿では十市皇女が通説と異なり若くして亡くなったとしました。ですから、懐風藻に書かれたように十市皇女が大友皇子の妻であるはずがなく、その結果、葛野王が十市皇女の子供であるはずがないのです。 過去いろいろな学者が、この懐風藻の記述に基づき、額田王と十市皇女の年齢を推定しようと試みています。しかし、どれもかなり無理のある推理であることは以下のとおりすぐにわかります。 【折口信夫氏の説】 600年 4455555555556666666666777777777 年 8901234567890123456789012345678 齢 大友皇子 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳―22――25 葛野王 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩-37 十市皇女 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳―――――26 額田女王 ⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳―――――――――30―――――――――40―――79 大友皇子とその息子、葛野王の年齢はわかっています。 折口説を簡単にまとめると、女性として子を最短の年齢で産んだとして計算したものです。葛野王の生年から母の十市皇女が17歳で葛野王を出産し、さらに額田王が十市皇女を17歳で出産したものとして額田王の年齢を推定されています。 なぜ、最短の出産にしなければいけないかというと、額田王の項でも述べましたが、少なくとも716和銅8年までは額田王が生きていた証拠があるからです。一般的な年齢設定だと化け物のような長寿者に額田王がなってしまうのです。この計算でも額田王は716年には79歳にもなります。 【梅原猛氏の説】 600年 4455555555556666666666777777777 年 8901234567890123456789012345678 齢 大友皇子 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳――――25 葛野王 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱-45 十市皇女①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳―――――――――30―32 額田女王⑮⑯⑰⑱⑲⑳―――――――――30―――――――――40―――――――83 梅原説も考え方は折口説と同じです。女性の最短の出産年齢を15歳とされました。 ただ、葛野王の享年を45歳としておられます。これは懐風藻に記述された持統10年の葛野王の記録「時年三十七」からこの持統10年を35歳と解釈されたことによるものです。これだと、大友皇子は14歳のときに15歳の十市皇女に葛野王を産ませたことになります。 その結果、出産期を若く設定したわりには、額田王の年齢は716年には83歳にもなってしまいます。 同様の試算は向井毬夫氏「額田王の実像」にも採用されています。 【伊藤博氏の説】 600年 4455555555556666666666777777777 年 8901234567890123456789012345678 齢 大友皇子 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳――――25 葛野王 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭-41 十市皇女 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳――――――――――31 額田女王 ⑳―――――――――30―――――――――40―――――――――50― 天武天皇 ⑳―――――――――30―――――――――40―――――――――50―56 それに比べれば、伊藤博氏の考え方は極めてオーソドックスなものです。女性の出産年齢に無理を強いていません。夫婦の年齢を同じとして設定しております。天武天皇と額田王の年齢が同じとし、大友皇子と十市皇女の年齢も同じとしたものです。 しかし、このことから額田王の年齢が716年には85歳にもなってしまうため、この716年の額田王生存記録である鑪盤を無視されているようです。額田王の没年は不明とされています。 なお、葛野王の年齢がなぜ41歳なのかよくわかりません。 これは伊藤博「萬葉集釋十一別巻『万葉歌人の年齢』」より抽出しました。 すべて懐風藻の記録に基づき、すべての間違いが始まったのです。 しかし、懐風藻の歌の評価について、江口孝夫氏は葛野王の歌を「少々ポースをとるところがあり、大げさで中国の教養を得意げに振りまわす」と厳しいものです。また、林古溪は、「論ずるに足りぬ」とこれまた厳しい批判をされています。 日本書紀の時代の年齢記載の書物がほとんどないなかでの、懐風藻の記述は昔から希少価値がありました。しかし、これを私たちは今まで信用し尊重しすぎてはいないでしょうか。 再度、本稿の結論を示し、この項を終わります。 【本稿の説】 600年 4455555555556666666666777777777 年 8901234567890123456789012345678 齢 天武天皇 ⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳―――――――――30――――――43 額田女王 ⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳―――――――――30―――――――73 十市皇女 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲ 19 天智天皇 23――――――30―――――――――40―――――46 46 大友皇子 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳―22――25 25 葛野王 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩-37 十市皇女の死に際し、母である額田王は史書には登場しません。よって後世の史家もこのことには触れていません。憶測にすぎなくなるからです。あえてこのことに触れます。 本稿では額田王は非常に負けず嫌いな厳格な性格の女性だったと考えています。 どの史書も子供の死に直面した母、額田王の動向に触れないのは、傍目に見ても芳しからぬ彼女の葬式での様子だったからではないでしょうか。 葬式の場にはいたはずなのです。天智天皇の室だったなどと遠慮などしていられないはずです。自分の娘が死んだのですから。 しかし、日本書紀は父親である天武天皇が人目もはばからず声を出して泣かれたとあるのに、一方の母親は黙々と自分の娘の葬式を事務的にこなしていたようで、泣き崩れる姿はどこにもありません。万葉集の常套句である「悲傷流涕」「泣血哀慟」といった姿はいっさいなかったのです。 十市皇女に対する挽歌は高市皇子が歌に詠んだように、他の多くの人達も詠んだと思いますが、万葉集最大の歌姫、額田王の歌はこの娘に対しては一首も残していません。 彼女は娘への気持ちを飲み込んでしまい、死ぬまで外にその思いを見せることはありませんでした。 何も示さないことが、額田王らしい母として娘への深い愛情の表現方法だったのだと思います。 ©2006- Masayuki Kamiya All right reserved. |