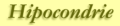後期ミサ曲
さてさて、なんだかずいぶん間が空いてますが…今回から何度かに渡って後期ミサ曲を特集していこうかと思います。
ここで言う後期ミサ曲とは1736年以降の作品、“聖三位一体ミサ イ短調 ZWV17”,“奉納ミサ ホ短調 ZWV18”,“父なる神のミサ ハ長調 ZWV19”,“神の御子のミサ ハ長調 ZWV20”,“全ての聖人のミサ イ短調 ZWV21” を指しています。ゼレンカの作品の中核をなすのがミサ曲なので、従ってこの5曲こそがゼレンカの作品の神髄を為すと言っても過言ではありません。
生涯の所でも述べたように、ゼレンカはこの頃を境に一線を引退していったようです。作品の数はぐっと減り、彼の作品が演奏されたという記録もほとんどなくなります。
しかし間違いなくこれ以降がゼレンカの最も円熟した時期でした。またそれまでは業務として様々なしがらみの中で作曲しなければならなかったのが、ここからは何にも縛られることなく作曲に専念できたわけです。言い換えるとこれ以降の音楽こそがゼレンカが本当に作りたかった音楽なのだと言えるでしょう。
その結果できあがった作品は、バッハの受難曲やロ短調ミサに匹敵する、バロック音楽の集大成というべき作品群でした。
この時期にゼレンカのスタイルは最終的に完成しますが、それを簡単にまとめてみると大体以下のようになるでしょうか?
- 古典的なモテット風の楽曲…和声は相当変
- 古典的なフーガ…名人芸的
- 最新の協奏曲形式楽曲…あくまで対位法的で独自拡張あり
- オペラアリア風歌曲…あくまで対位法的
一般によく言われるのは上記ですが、それに加えて筆者は音楽全体の構成法にもずいぶん特徴があるように感じます。
ゼレンカの時代の声楽曲は「番号付き構成」と呼ばれる形式になっていました。これは長い歌詞は細かく寸断してそれぞれに短い音楽を付けるものでした。
例えばバッハのマニフィカトなどを思いだして頂ければ分かりますが、ほとんど各節ごとに独立した音楽が付けられており、各音楽はそれごとに完全に終止してから次の節に入ります。
そうなっていた理由は、この時期はまだソナタ形式などの長い楽曲を構成する原理がまだ存在しなかったためです。かろうじてあったのが協奏曲形式(リトルネルロ形式)だけです。
このような構成にすると、得てして個々の曲そのものは良いのに、全体を聴くと何だか支離滅裂だったり、何となくだらだら続いている印象を与えたりと、いわば木を見て森を見ず状態になってしまうことがよくあります。
ゼレンカの作品を聴くと、このようにならないように作曲者がいろいろ腐心している点が窺えるのです。
といってもゼレンカがいきなり時代を突き抜けてしまえたわけではなく、彼の構成も基本的には番号付き構成といっていいでしょう。
しかし、まず分割数が比較的少なく代わりに各曲の構造が協奏曲形式を導入するなどして複雑になっていること、曲がいわゆる完全終止で終わらず半終止で次の曲に行くことがよくあること、曲間に短い経過句が挟まることが多いこと、更には別と思われる曲にも同じリトルネルロがでてきたりするなど、複数の曲間の連続性や統一性が遙かに考えられています。
これは当時としてはかなり先進的な構成だったのではないでしょうか?
これはゼレンカがカトリックの宗教音楽作曲家だったことが幸いしたのかも知れません。 編成:solo SATB; ch SATB; 2 fl; 2 ob; chalumeau; 2 vn; va; b.c.;
ミサ曲というと700年以上の歴史があって、それこそ無数の曲が存在するわけですが、私の場合その中で「最高にかっこいいミサ曲」といえばこの作品なんでないか、とか思ってたりするわけです。
しかしこの作品、どういう機会のために書かれたのかが意外に分かっていません。演奏されたという記録もないようですし、そもそも通常のミサに使用するには既に規模が大きすぎると思われます。
このように作曲の理由は今一つ不明ですが、この曲で興味深いところは、ゼレンカとバッハの関連を暗示する点でしょうか。
こうやってみればリズムは一緒ですが、反転にもなってないことは明白です。しかし聴いてみると何となく似ているのも事実です。
ゼレンカはドレスデンの副楽長をしていました。従ってバッハが以前に宮廷に贈呈したロ短調ミサの前半部を見たことはまず間違いないでしょう。もちろんそれを見て「こいつただ者じゃないぜ!」と思ったのもほぼ間違いないでしょう。
ということを考え合わせれば、この曲はゼレンカがバッハを意識して作った作品と考えることもできるかもしれません。その意識がバッハに対する敬意なのか、それとも「コルァ!そこのルター派の若造!ミサ曲っちゅうのはこうやって作るんじゃい!」という意識なのかは不明ですが…
グローリアはかなり長いテクストなので一般の番号付きミサ形式ではかなり細かく分断されることになりますが、この作品の場合音楽的に分ければ3つにしかなりません。
この最初の部分ですがこれまたゼレンカの協奏曲的声楽曲の代表作と言えるかも知れません。まずは意表をついた強烈な出だしで始まり、独唱と伴奏と合唱が渾然一体となりながら対位法的に絡み合って、怒濤のごとくに進行していきます。
次に Quonism tu solus sanctus (8) でゼレンカアリアがはさまり、最後の cum Sancto Spiritu (8) の部分がフーガになっています。
次ぐクレドは5つの部分に分かれます。
サンクトゥスは打ち沈んだ感じですが非常に真摯な合唱で始まります。しかしそれはすぐノーテンキな調子になり、Benedictus (19) ではAがフルートとかけ合うなかなか心にしみるアリアになります。
この部分はシャリュモーとフルートがかけあうこれまた心にしみいるTとBによる重唱です。それが終わると総合唱による経過句の後に、Dona nobis pacem (23) が第二キリエのパロディとして現れます。
この作品はどこからどこまで聞き逃せない、高いレベルでバランスが取れている傑作中の傑作といえるでしょう。
聴衆が歌われている言葉を理解できる場合は、音楽が少々統一されていなくとも意味は伝わるでしょう。しかしゼレンカが使用していたラテン語は、当時ですらほぼ死語でした。意味が分からなければ歌詞があっても声という楽器を使った器楽曲のようなものです。
そういう条件で聴衆を飽きさせないために、しっかりした全体構成をする必要があったわけです。
“聖三位一体ミサ イ短調 ZWV17”
一応 1736/11/1 の諸聖人の祝日用なのではと考えられているようですが、確証があるわけではないようです。他にもこの年に Franciscus Retz という人物がイエズス会の聖人にまつわる聖遺物を教会にもたらしたらしく、それに対する感謝として作られたという話もあります。
実はこの曲の第二キリエですが、ここの主題が実はバッハのロ短調ミサの第一キリエの主題に何となく似ているのです。

そして1736年というと、バッハがドレスデンの「教会作曲家」称号をもらい、12月にはドレスデンを訪問しています。これはゼレンカが前年に得た称号と同じもので、いわばバッハがこの時「同僚」となったわけです。
キリエの部分は、付点音符が特徴の緊張感溢れる合唱で始まります。一発目からこんなテンションで大丈夫かと心配になりますが、だいじょうぶです。このあたりはまだ準備運動です。
続いてクリステの部分はゼレンカアリアで、派手なカデンツァ付きです。
その後に続く第二キリエが多分これからもいろいろ問題になるでしょうが、極めてドラマチックなフーガ合唱です。多分ゼレンカの作ったフーガの中でも一二を争う名曲と言えるかも知れません。
Gloria in excelsis Deo (4) から Qui sedes ad (7) までが統一したリトルネルロが使用されていて一つの音楽と言っていいです。
更に各部分は短い経過句でつながれており、ゼレンカが全体を通して1曲というイメージでつくっていたことはまず間違いないでしょう。
クレドは Credo 以下 (9) ~ (11) がまたゼレンカの協奏曲形式声楽曲傑作です。それに続く Et incarnatus (12) ~ Crucifixus (13) はモテット長の穏やかな合唱となります。
次の Et resurrexit (14) は復活の喜びを表現した華やかな協奏曲的楽曲となり、Et unam Sanctam (16) では数名の独唱者だけによる、極めて美しい重唱となります。
最後の et vitam ventui saeculi. Amen (16) はもちろんフーガで締められますが、対位法の名人にかかったらドレミファソラという主題でもかくも素晴らしい音楽になるのかという見本でしょうか。
その後 Hosanna (20) でまたノーテンキな雰囲気が再現したあと、アニュスデイが始まります。