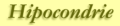“聖週間のための6つの哀歌 ZWV53”
1722年、ゼレンカは“聖週間のための6つの哀歌 ZWV53”を作曲しました。これがドレスデンでの彼の地位を固めると同時に、現在彼の作品の中でも最もポピュラーな物の一つでもある「エレミアの哀歌」です。
この作品は旧約聖書中で最も悲しみに満ちた詩である「哀歌」に由来します。
紀元前587年、新バビロニア王国のカルデア人の軍勢はエルサレムを破壊し、多くのユダヤ人は奴隷となってバビロンに連行されます。この事件が名高い「バビロン捕囚」で、この時代の有名な預言者がエレミアでした。
「哀歌」はこのエレミアが作ったと伝えられるため、エレミアの哀歌とも呼ばれます(が、実際にはエレミアが作ったものではありません)
哀歌は、カトリック典礼においては聖木曜日、聖金曜日、聖土曜日の朝課(テネブレ)で朗読されることになっています。聖週間とはキリストの受難を思い起こす週間なので、ある意味非常にふさわしい内容なわけです。
聖週間という非常に重要な時期に歌われることと、その悲痛な内容からこのエレミアの哀歌は単旋律の時代から特別扱いされて、独特の朗唱形式を持っていたといいます。そしてルネッサンス期からバロック初期にかけてたくさんの作品が作られました。
しかしバロック後期になると、人々の趣味が明るい音楽の方に向かったためか、作曲は下火になっていきます。ゼレンカの時代ほとんどその最終期に属し、彼の作品はエレミアの哀歌というジャンルの最後を飾る傑作となりました。
ところで朝課を正式に行ったとすると、夜中の2時ぐらいから始めて翌朝までずっとやっていることになります。はっきり言って、滅茶苦茶眠たそうです。さすがに信心深かった当時の人もこれはやっとられんと思ったのでしょうか。ゼレンカの時代にはこれが前日の晩に行われる習慣になっていました。
ゼレンカの哀歌のタイトルが聖水曜日、聖木曜日、聖金曜日と一日前にずれているのはそのためです。
また正式には哀歌の朗読は1日3つずつ、計9個の朗読が行われるのが決まりでしたが、ゼレンカのセットには2個ずつ計6個しか入っていません。この理由はよく分かっていません。もしかしたら1723年版(ZWV54)の3つの哀歌がその残りかもしれませんが、迂闊なことは言わない方がいいでしょう。
この作品はアリアとレチタティーボで構成される一人カンタータのような形式を持っています。もともとこの哀歌は朝課における「聖書朗読」の一部でしたので、一人で歌われることには意味があるわけです。
「哀歌」は元から詩の各節にヘブライ語のアルファベットがついていて、このアルファベットの部分を歌うときはメリスマティックに、長く引き延ばしてアリア風に歌われます。各節の詩の部分に入ると、レチタティーボで歌われます。
ところでこの作品の名前は「哀」歌ですが、実際に聴いてみたら結構明るい曲もあって「じと~っと沈みたいから聴いたのにぃ!」と拍子抜けされる人がいるかも知れません。
これはこの作品がキリストの「受難」週に歌われるということが大きく影響していると思われます。
受難という出来事を思い返した場合、もちろん主を失う悲しみが最も大きな感情になりますが、その他にも主を見捨てて逃げ去った弱さへの怒りや、これが最も重要ですが来るべき復活への希望などの様々な想いが複雑に絡み合ってきます。決して単に悲しんでいるだけではないわけです。
ゼレンカはそのあたりを当然よく理解していたでしょう。彼の音楽が単に悲哀一辺倒ではなく、いろいろな想いがいろいろな形で曲の中に反映されているのはまさにその現れだと思います。
ちなみに、実際の朝課では哀歌が歌われるごとにそれに対するレスポンソリウムが歌われます。当然ゼレンカもそれを前提にして作曲していると思われます。 編成:solo B; 2 ob; 2 vn; va; b.c.;
さてそれでは各曲ごとのコメントを行ってみたいと思いますが、まずこの作品は聖水曜日用2曲、聖木曜日用2曲、聖金曜日用2曲とまず大きく分けられます。
聖水曜日(典礼上では木曜日)のための2曲はこれから起こるであろうキリストの受難を予期しているのでしょうか、悲しみを基調とした音楽になっています。
6曲の哀歌のトップを飾るこの曲は、同時にゼレンカの最高傑作の一つでもあるでしょう。器楽編成は上述のように地味ですが、その音楽の持つ破壊力はとてつもない物があります。
本編の歌詞は以下のような物です。
1で「預言者エレミアの嘆きが始まる」と歌われた後、2の神を忘れたがために滅びたエルサレムを嘆く部分が続きます。それは3の部分で一度クライマックスに達し、一度間奏が挟まると押さえた、しかし内面はかなり悲痛な調子で「今は慰めを与えない。彼女を愛した人のだれもが」と歌われます。
4の部分は少し明るい曲調になりますがそれもすぐ終わって、5の部分からまたひたすら悲痛にエルサレムの惨状が歌われていきます。
そして最後の締めの部分「エルサレムよ、エルサレムよ。主の道に立ち返れ」という部分(これは元の哀歌にある歌詞ではなく、ホセア書よりの引用)で、ポリフォニックな極めて印象的なコーダに突入します。
とにもかくにもこの曲はゼレンカのとかバロックのというレベルを超えて、全音楽史上での屈指の名曲の一つであると私が保証します!…「私」がですけどね 編成:solo A; 2 ob; 2 vn; va; b.c.;
第2曲はヘ長調という調性もあって、始まりは比較的明るい雰囲気で始まります。
1の部分はまだ冒頭の雰囲気を引きずって明るめの感じです。ここは「シオンの乙女」という言葉のイメージを現しているためとも言われます。
しかし2そして3の部分になってくるとどんどんまた悲痛な雰囲気になっていきます。
最後の「エルサレムよ主の道に立ち返れ」になるとまた冒頭の雰囲気が戻って、音楽的なバランスがとられています。
ちなみにバロックオペラでのソプラノとかアルトはカストラートが歌うのが普通でしたが、教会音楽でもカストラートが起用されました。聖堂内で女性が歌うのはやはり何かと問題だったようです。これはドレスデンでも同様で、ゼレンカもソプラノとかアルトはカストラート前提で曲を作っています。
そういう理由でバロックの声楽曲では少なくともアルトはカウンターテナーが歌うのがもはや当然という感じになっています。 編成:solo T; 2 ob; 2 vn; va; b.c.;
聖木曜日の哀歌(典礼的には金曜日用)以降は、音楽の構成が少し異なってきます。
聖水曜日用の2曲は、全体がアリア・アリオーソ的で非常に「音楽的」な構成になっていました。ヘブライ文字部分はメリスマティックに、本文はシラビックにという違いはあっても、曲の流れは連続していて、各節の途中でいったん間奏が入って残りの節を歌う、といった部分もありました。
しかし聖木曜日・聖金曜日用の4曲では、ヘブライ文字部分だけがアリア風な音楽で、詩の本文の部分は完全なレチタティーボとなります。この部分では伴奏は場合によったらチェンバロだけといったシンプルな物になり、歌唱も朗唱的でこの二つの部分の対比が非常にはっきりとしています。
このためある意味音楽が更に地味になっています。
聖木(金)曜日用の第1曲目は、まずフーガ風に始まります。
1~3の部分は淡々と歌い進められる印象があります。
エルサレムのリフレインは希望に満ちた音楽といえるでしょう。 編成:solo B; 2 ob; 2 vn; va; b.c.;
聖金曜日は、キリストが十字架につけられる日です。そのためキリスト教徒にとってはある意味最も悲しい日であるわけです。
この第2の哀歌は水曜日第1曲と並んで最もそういった気分が出た曲です。
1でいきなり悲痛なオープニングに始まります。実際この節は全哀歌中でも最も哀れといえる内容を持っています。この部分はもうじっくりと聴いて下さいとしか言いようがありません。
2も同様に悲しく歌われます。しかし3そして4の部分に入ると、エセ預言者やあざけられるエルサレムに対して、悲しみは怒りへと変わってきます。ヘブライ文字部分がやや明るいのは、それに続く怒りをためているといった感じでしょうか?
最後の「エルサレムよ立ち返れ」の部分は、この曲集を代表する名曲と言っていいでしょう。 編成:solo T; 2 fl; 2 vc; b.c.;
前にもちょこっと書いたように、哀歌だからといってずっと悲しみっぱなしではありません。
楽器編成が今までの物とは変わって、フルートとチェロになっているのもその現れでしょうか。
哀歌の第3章は1節1節がおおむね非常に短いので、曲はヘブライ文字部分が結構あって、その合間に本文が挿入されるような感じになっています。
2の部分は美しいフルート2重奏で始まります。
最後のエルサレムの部分では再び冒頭のような喜びに満ちた牧歌的な音楽になります。「エルサレムよ、主の道に立ち返れ」と歌いつつ、既に救いを確信しているかのようです。 編成:solo A; chalumeau; fg; vn; b.c.;
哀歌最後の曲は、悲しみ、怒り、あきらめ、そして希望と、このエレミアの哀歌全6曲の総まとめとも言える音楽になっています。
特徴的なのは使用楽器にシャリュモーが使われていることです。これはクラリネットの前身となった楽器で、クラリネットに似た甘い音を出します。
オープニングの雰囲気は前の曲からの続きという感じの明るい雰囲気の曲です。シャリュモーとバイオリンとファゴットの絡み合う美しい音楽です。特にファゴットの動きはあのトリオソナタ(ZWV181)を彷彿とさせる物があります(たぬきさんに頂いた自筆譜)
しかし2の部分になってくると、音楽は段々暗くなっていきます。詩がそういう詩なのでしょうがありません。
3の部分では山犬以下の我が民の娘に対する、やり場のない怒りを感じさせます。
しかし5、6節ではそれも収まり、因果応報を受け入れ悔悟の念に沈むといった感になります。
最後のエルサレムでは再び、曲冒頭のように来るべき復活と赦しを待ち望む歌で、全曲が閉じられます。
そのためもし持っているのであれば、哀歌とレスポンソリウムを交互に聴いてみるのも一興です。レスポンソリウムだけ、哀歌だけを連続して聴くと似たような物が続くのでちょっと飽きがくる可能性がありますが、こうするとバランスよくなります。一度試してみてはいかがでしょうか?
“聖水曜日第Iの哀歌 ハ短調 ZWV53-1”
また詩の朗唱部もレチタティーボというよりアリオーソに近く、伴奏もかなり凝った物が付いているため、全体が非常に音楽的です。そのためこの2曲は特に個々の歌詞の意味を知らなくとも、その悲痛な感情がありありと伝わってきます。
聴いたことのある方なら、冒頭でバスが“Incipit Lamentatio"と歌い出すあたりで、いきなり捕まってしまった人も多いのではないでしょうか。
Lamentatio I 第Iの哀歌
(1) Incipit Lamentatio Ieremieae Prophetae 預言者エレミアの嘆きが始まる。
(2) ALEPH アレフ quomodo sedit sola なにゆえ、独りで座っているのか civitas plena populo 人に溢れていたこの都が。 facta est quasi vidua やもめとなってしまったのか domina gentium 多くの民の女王であったこの都が。 princeps provinciarum 国々の姫君であったこの都は、 facta est sub tributo 奴隷となってしまったのか。 BETH ベース plorans ploravit in nocte 夜もすがら泣き、 et lacrimae eius in maxillis eius 頬に涙が流れる。
(3) non est qui consoletur eam 今は慰めを与えない。 ex omnibus caris eius 彼女を愛した人のだれもが。
(4) omnes amici eius 友は皆、 spreverunt eam 彼女を欺き、 et facti sunt ei inimici ことごとく敵となった。
(5) GIMEL ギメル migravit Iuda propter adflictionem ユダは捕囚となって行き et multitudinem servitutis 貧苦と重い苦役の末に habitavit inter gentes 異国の民の中に座り、 nec invenit requiem 憩いは得られず omnes persecutores eius 苦難のはざまに adprehenderunt eam inter angustias 追い詰められてしまった。
(6) DELETH ダーレス viae Sion lugent eo quod シオンに上る道は嘆く non sint qui veniant ad sollemnitatem 祭りに集う人がもはやいないのを。 omnes portae eius destructae シオンの城門はすべて荒廃し、 sacerdotes eius gementes 祭司らは呻く。 virgines eius squalidae おとめらは悲しむ et ipsa oppressa amaritudine シオンの苦しみを。
(7) HE ヘー facti sunt hostes eius in capite 苦しめる者らを頭とされ、 inimici eius locupletati sunt 敵がはびこることを許すよう、 quia Dominus locutus est super eam 主は定められた。 in multitudinem iniquitatum eius シオンの背きは甚だしかったがゆえに。 parvuli eius ducti sunt in captivitatem 彼女の子らはとりことなり ante faciem tribulantis 苦しめる者らの前を引かれて行った。
(8) Ierusalem, Ierusalem, エルサレムよ、エルサレムよ。 convetere ad Dominum, Deum toom. 主の道に立ち返れ。
“聖水曜日第IIの哀歌 ヘ長調 ZWV53-2”
といってもゼレンカの音楽はたいていの場合長調と短調の間を行きつ戻りつしながら展開していきますので、出だしが明るいからずっと明るいという保証はありません。実際この曲も途中からどんどん「哀歌」になっていきます。
Lamentatio II 第IIの哀歌
(1) VAV ヴァーヴ et egressus est a filia Sion おとめシオンより omnis decor eius 栄光はことごとく去り facti sunt principes eius その君侯らは野の鹿となり velut arietes non invenientes pascua 青草を求めても得られず et abierunt absque fortitudine 疲れ果ててなお、 ante faciem subsequentis 追い立てられてゆく。
(2) ZAI ザイン recordata est Ierusalem エルサレムは心に留める dierum adflictionis suae 貧しく放浪の旅に出た日を et omnium desiderabilium suorum 宝物のすべては、 quae habuerat in diebus antiquis いにしえから彼女のものであったのに。 cum caderet populus eius in manu hostili 苦しめる者らの手に落ちた彼女の民を et non esset auxiliator 助ける者はない。 viderunt eam hostes 絶えゆくさまを見て、 et deriserunt sabbata eius 彼らは笑っている。
(3) HETH ヘース peccatum peccavit Ierusalem エルサレムは罪に罪を重ね propterea instabilis facta est 笑いものになった。 omnes qui glorificabant eam 恥があばかれたので spreverunt illam quia viderunt 重んじてくれた者にも ignominiam eius 軽んじられる。
(4) ipsa autem gemens et conversa retrorsum 彼女は呻きつつ身を引く。
(5) TETH テース sordes eius in pedibus eius 衣の裾には汚れが付いている。 nec recordata est finis sui 彼女は行く末を心に留めなかったのだ。 deposita est vehementer 落ちぶれたさまは驚くばかり。 non habens consolatorem 慰める者はない。
(6) vide Domine adflictionem meam 御覧ください、主よ quoniam erectus est inimicus わたしの惨めさを、敵の驕りを
(7) Ierusalem, Ierusalem, エルサレムよ、エルサレムよ。 convetere ad Dominum, Deum toom. 主の道に立ち返れ。
そして最後の6の「御覧ください、主よ。わたしの惨めさを、敵の驕りを」という部分は非常に真に迫った音楽になっています。
このことの是非はまあいろいろ議論があるようですが、まあ歌がうまければ許すという立場なんで私は気にしてませんが…最初ルネ・ヤーコプスを女と信じてて、ライナーノート裏のおっさんはいったい誰? とか思っていたことはひみつ
“聖木曜日第Iの哀歌 変ロ長調 ZWV53-3”
また第1曲に見られたような複数の節にまたがって同じ流れの音楽が付けられたり、節の途中で区切られたりということはなく、1つの節に対して1つの音楽という構成になっています。
しかし、このレチタティーボ部がなかなかの優れ物で、歌詞の意味をよくかみしめながら聴くと、大変情感がよく現されていてバッハ受難曲のレチタティーボにも劣らぬ出来映えだと感じます。
Lamentatio I 第Iの哀歌
(1) HETH ヘース cogitavit Dominus 主は定めた dissipare murum filiae Sion 乙女シオンの城壁を滅ぼそうと。 tetendit funiculum suum 打ち倒すべき所を測り縄ではかり et non avertit manum suam a perditione 御手をひるがえされない。 luxitque antemurale 城壁も砦も共に嘆き、 et murus pariter dissipatus est 共に喪に服す。
(2) TETH テース defixae sunt in terra portae eius 城門はことごとく地に倒れ、 perdidit et contrivit vectes eius かんぬきは砕けた。 regem eius et principes eius in gentibus 王と君侯は異国の民の中にあり non est lex 律法を教える者は失われ et prophetae eius 預言者はもはや見いだすことができない。 non invenerunt visionem a Domino 主からの幻による託宣を。
(3) IOTH ヨーズ sederunt in terra 地に座して黙する conticuerunt senes filiae Sion おとめシオンの長老は皆。 consperserunt cinere capita sua 頭に灰をかぶり、 accincti sunt ciliciis 粗布を身にまとう。 abiecerunt in terra capita sua 頭を地につけている。 virgines Ierusalem エルサレムのおとめらは。
(4) CAPH カフ defecerunt prae lacrimis oculi mei わたしの目は涙にかすみ、 conturbata sunt viscera mea 胸は裂ける。 effusum est in terra iecur meum わたしのはらわたは溶けて地に流れる。 super contritione filiae populi mei わたしの民の娘が打ち砕かれたので。 cum deficeret parvulus 幼子も乳飲み子も et lactans in plateis oppidi 町の広場で衰えてゆく。
(5) Ierusalem convetere エルサレムよ、立ち返れ ad Dominum, Deum toom. 主の道に。
しかし4の部分になると詩の内容もあって「幼子も乳飲み子も町の広場で衰えてゆく」というあたりでは身につまされる音楽になります。
“聖木曜日第IIの哀歌 ト短調 ZWV53-4”
Lamentatio II 第IIの哀歌
(1) LAMED ラーメズ matribus suis dixerunt 幼子は母に言う ubi est triticum et vinum パンはどこ、ぶどう酒はどこ、と。 cum deficerent quasi vulnerati 傷つき、衰えて in plateis civitatis 都の広場で cum exhalarent animas suas 息絶えてゆく。 in sinu matrum suarum 母のふところに抱かれながら
(2) MEM メーム cui conparabo te あなたを何にたとえ、 vel cui adsimilabo te 何の証しとしよう。 filia Ierusalem * おとめエルサレムよ。 magna est enim velut mare contritio tua 海のように深い痛手を負ったあなたを quis medebitur tui 誰が癒せよう。
(3) NUN ヌーン prophetae tui viderunt tibi 預言者はあなたに託宣を与えたが falsa et stulta むなしい、偽りの言葉ばかりであった。 nec aperiebant iniquitatem tuam あなたを立ち直らせるには ut te ad paenitentiam provocarent 一度、罪をあばくべきなのに viderunt autem tibi adsumptiones あなたに向かって告げるるのは、 falsas et eiectiones むなしく迷わすことばかりであった
(4) SAMECH サーメク plauserunt super te 手をたたいてあなたを嘲る。 manibus omnes transeuntes per viam 道行く人はだれもかれも。 sibilaverunt et moverunt caput suum 口笛を吹き、頭を振ってはやしたてる super filiam Ierusalem おとめエルサレムよ、あなたに向かって haecine est urbs dicentes perfecti decoris これが麗しさの極みと称えられた都なのか? gaudium universae terrae 全地の喜びと称えられた都なのかと
(5) Ierusalem, Ierusalem, エルサレムよ、エルサレムよ。 convetere ad Dominum, Deum toom. 主の道に立ち返れ。
この木曜日第2曲は水曜日第1曲に比べると表現は地味ですが、内に秘められた感情は遙かに勝っていると言っていいかも知れません。
“聖金曜日第Iの哀歌 イ長調 ZWV53-5”
聖土曜日は死んだキリストを悼むことよりも、来るべき復活を待ち望んでいるという気分の方が重要です。
もちろんこの時点ではまだキリストは死んだままなので、浮かれ騒ぐわけにはいきませんが、ともかくそのためにこの聖金曜日(土曜日)の哀歌は、全体が穏やかななおかつ希望に満ちた音楽になっています。
Lamentatio I 第Iの哀歌
(1) HETH ヘース misericordiae Domini 主の慈しみは quia non sumus consumpti 決して絶えない。 quia non defecerunt miserationes eius 主の憐れみは決して尽きない。 HETH ヘース novae diluculo それは朝ごとに新たになる。 multa est fides tua あなたの真実はそれほど深い。 HETH ヘース pars mea Dominus dixit anima mea 主こそわたしの受ける分とわたしの魂は言い propterea expectabo eum わたしは主を待ち望む。
(2) TETH テース bonus est Dominus sperantibus in eum 主は幸いをお与えになる。 animae quaerenti illum 主に望みをおき尋ね求める魂に TETH テース bonum est praestolari 幸いを得るだろう。 cum silentio salutare Domini 主の救いを黙して待てば。 TETH テース bonum est viro 幸いを得るだろう。 cum portaverit iugum ab adulescentia sua 若いときにくびきを負った人は。
(3) IOTH ヨーズ sedebit solitarius et tacebit 黙して、独り座っているがよい。 quia levavit super se くびきを負わされたなら。 IOTH ヨーズ ponet in pulvere os suum 塵に口をつけよ、 si forte sit spes 望みが見いだせるかもしれない。 IOTH ヨーズ dabit percutienti se maxillam 打つ者に頬を向けよ saturabitur obprobriis 十分に懲らしめを味わえ。
(4) Ierusalem, Ierusalem, エルサレムよ、エルサレムよ。 convetere ad Dominum, Deum toom. 主の道に立ち返れ。
1の部分はまずその希望に満ちた雰囲気で始まります。本文はやや哀歌の雰囲気になりますが、今までの物ほど悲痛ではありません。
3の部分はこの曲のハイライトでしょう。ほとんどチェロだけの渋い音楽ながら、歌とかけ合いながら盛り上がっていく非常に印象的な楽曲です。
“聖金曜日第IIの哀歌 ヘ長調 ZWV53-6”
Lamentatio II 第IIの哀歌
(1) ALEPH アレフ quomodo obscuratum est aurum なにゆえ、黄金は光を失い mutatus est color optimus 純金はさげすまれているのか。 dispersi sunt lapides sanctuarii 聖所の石が打ち捨てられているのか。 in capite omnium platearum どの街角にも。
(2) BETH ベース filii Sion incliti et amicti auro primo 貴いシオンの子ら、金にも比べられた人々が quomodo reputati sunt in vasa testea なにゆえ、土の器とみなされ opus manuum figuli 陶工の手になるものとみなされるのか。
(3) GIMEL ギメル sed et lamiae nudaverunt mammam 乳を与えて子を養うのは lactaverunt catulos suos 山犬ですらすること filia populi mei crudelis だのにわが民の娘は残酷になり quasi strutio in deserto 荒れ野の喚鳥のようにふるまう。
(4) DELETH ダーレス adhesit lingua lactantis 乳飲み子の舌は渇いて ad palatum eius in siti 上顎に付き parvuli petierunt panem 幼子はパンを求めるが、 et non erat qui frangeret eis 分け与える者もいない。
(5) HE ヘー qui vescebantur voluptuose 美食に馴れた者も interierunt in viis 街にあえぎ qui nutriebantur in croceis 紫の衣に包まれて育った者も amplexati sunt stercora 塵にまみれている。
(6) VAV ヴァーヴ et maior effecta est iniquitas filiae populi わたしの民の娘は重い罪を犯したのだ。 mei peccato Sodomorum あの罪深いソドムよりも。 quae subversa est in momento ゆえにその町は一瞬にして滅んだのだ。 et non ceperunt in ea manus 人の手によらずに。
(7) Ierusalem, Ierusalem, エルサレムよ、エルサレムよ。 convetere ad Dominum, Deum toom. 主の道に立ち返れ。
そして4の乳飲み子が飢え乾いている部分ではまた、第1曲や第4曲に見せたような悲しみの音楽になります。